お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説



捨てられた者同士の絆
O.K
SF
捨てられたホームレスの男性、ジェイクがゴミ捨て場で廃棄されたロボット、チャーリーを見つけ、家族のように大切にし始める。彼らは共に孤独と闘いながら絆を深め、技術の可能性を追求する。ある日、若い女性エミリーに出会い、彼女の協力でチャーリーは感情を取り戻し、新たなAIの道を歩むことができるようになる。ジェイク、エミリー、そしてチャーリーは、互いに支え合い、愛し合いながら社会の偏見に立ち向かい、新たな家族として未来を切り開いていく。彼らの物語は、捨てられた者同士が絆を深めていく姿を通じて、希望と勇気を与える感動的な物語となった。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。


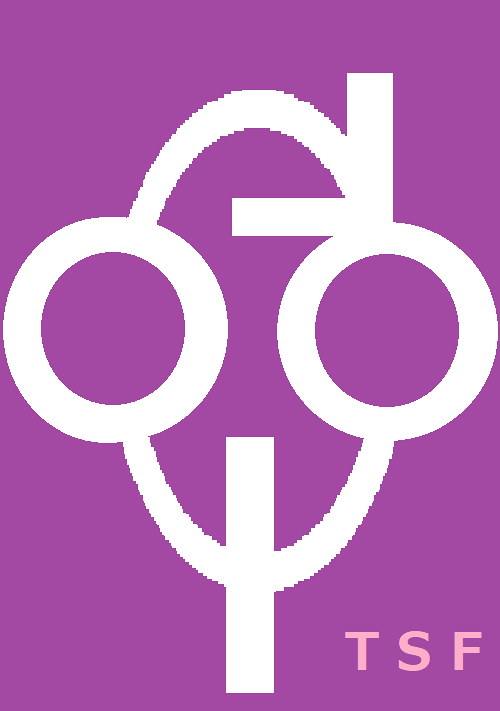
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















