33 / 149
33
しおりを挟む
「……これけっこう美味しくない?」
自分で作ったものが自分の口に合ったらしく、良は期待を抑えているような声でそう訊いてきた。
コシの残ったパスタに柔らかいトマトの色味が乗って、品のいい穏やかな味がした。
「美味いな。何かレシピ見たのか?」
裕司も良も、日頃はあまりレシピ通りに作るということをしなかった。とりあえず家にあるもので適当に作るのが当たり前で、特段に食べたいメニューがあるときだけレシピを調べたり材料を買いに行ったりする。それでもレシピを遵守しないことが多くて、結果的に美味しければ何でもいいという点だけは二人とも最初から合致していた。
「こないだテレビでやってたの真似してみたけど、量とかは適当」
「上出来だろ」
いつの間にそんな番組を観ていたのだろう、と思ったが、裕司がつけっぱなしにしたテレビを良だけが観ていることも多いのを思い出す。裕司は良の行動を見ているようで存外見ていなかったし、同じ家の中でも互いに何をしているのか知らない時間も長かった。
「いいねこれ、また作ろ」
「おう、期待してる」
裕司の応えに、良は楽しそうにくすりと笑った。
良が明らかに疲れている様子のときは、食事はもっぱら──出来合いのものを含め──裕司が用意するのが習いだったが、そうでないとき良は手間を惜しまずに温かい手料理を並べてくれた。
それは最初からそうだったわけではなく、裕司が美味しいと言って食べてくれるのが楽しくなってきたのだと言ってくれたのを覚えている。
料理をする理由はもっぱら節約のためだと思っていたけれど、喜んでくれる人がいて、一緒に食べるとより美味しく感じる相手がいると、作るのも楽しいのだと気付いたと言っていた。
レパートリーも増えてきて、失敗する頻度も減ってきて、もしかしたら料理は彼の趣味のひとつになるのかもしれない、と裕司は思う。
良には趣味らしい趣味がなくて、せっかく好奇心旺盛な心を持っているのに、それを遊ばせているだけなのはもったいないと感じていた。
「飯が美味かったら、人生の最低限の幸せは保証されるって言ってた人がいたなぁ」
「へえ。なに、偉い人?」
「さあ、忘れたけど……飯を美味いと感じるのは幸せって意味かもな」
ああ、と良は頷いた。
「それはわかる。仕方なしに食べるご飯って味はするのに美味しいって思えなくてやだよね」
良の台詞に裕司は少し苦笑する。裕司の前での良はいつも食欲旺盛で、仕方なく食べているような姿はほとんど記憶になかった。
「お前がいるおかげで、最近また太りそうだよ」
良は黒い目を丸くして、しげしげと裕司を眺めながら言った。
「え? あんた太ってたことあんの?」
「……何想像してんのか知らねえけど、そんな見るからに太ってたわけじゃねえからな。デスクワークと飲み歩きばっかしてた時期がちょっとヤバかったんだよ」
「あー、あんたの仕事って太りやすそう」
「まあ……そうだよ。そのときはジムも行ってなくてな」
「でもそれがなんで今俺のせいなの」
じい、と真っ直ぐな目に見つめられて、裕司は何やら照れくさくなる。良の瞳は本人よりはるかに多弁で、その視線には力があった。
「お前と食う飯は美味いってだけの話だよ」
恥ずかしさを誤魔化したくて平気な声を繕って言うと、良はぱちぱちと瞬きをして、柔らかに笑んだ。
「それなら幸せでいいじゃん」
そう言って良はまたパスタの残りを食べ始める。その様子を裕司は思わず眺めて、はたと我に返って目を逸らした。
つまらないことで恥ずかしがった自分が愚かに思えるほど、良の反応は穏やかで自然だった。裕司が良のそばにいることにどこまでも肯定的な言葉をもらった気がして、反芻していくらか顔が熱くなる。
良がいてくれて、良が食事の支度をしてくれて、それを二人で一緒に食べる。それが今ではもう特別なことではなくなっていた。
──最低限どころじゃなく幸せだろ。
口には出せずにそんなことを思って、口をつけたスープはやけに甘く感じた。
「──で、訊きたいことっていうのは?」
昼食の片付けも済ませて、もう何も拒む言い訳はないだろうと思われるタイミングで再び問うてみると、良はしょっぱい顔をしてみせた。
「……俺が訊いてみたいって言ったのに、なんであんたが聞きたがる感じになってんの……」
「お前が何を訊きたいのか気になるに決まってんだろ」
ここまですれば逃げないだろう、という気持ちで淹れてやったアイスティーのグラスの中で、氷が揺れて音を立てた。
「……そんな気にされたらすごい訊きにくいんだけど……」
「それはまあ、諦めろ」
良はうらめしそうな目で裕司を見て、少しの間テーブルの上に視線をさまよわせていたが、やがて控えめな声音で言った。
「……言っとくけど、そんな大事な話じゃないからね?」
「お前が何を訊きたいのか知りたいだけだって」
良はそれでもまだ躊躇う顔をして、自分の膝を抱き寄せると、ようやく本題を口にした。
「……あんたって何で今の仕事しようと思ったの?」
「え?」
「なんか、あの、パソコンで色々作ったりするの、大学出てからずっとやってるんでしょ? ……なんでそれ仕事に選んだの?」
自分で作ったものが自分の口に合ったらしく、良は期待を抑えているような声でそう訊いてきた。
コシの残ったパスタに柔らかいトマトの色味が乗って、品のいい穏やかな味がした。
「美味いな。何かレシピ見たのか?」
裕司も良も、日頃はあまりレシピ通りに作るということをしなかった。とりあえず家にあるもので適当に作るのが当たり前で、特段に食べたいメニューがあるときだけレシピを調べたり材料を買いに行ったりする。それでもレシピを遵守しないことが多くて、結果的に美味しければ何でもいいという点だけは二人とも最初から合致していた。
「こないだテレビでやってたの真似してみたけど、量とかは適当」
「上出来だろ」
いつの間にそんな番組を観ていたのだろう、と思ったが、裕司がつけっぱなしにしたテレビを良だけが観ていることも多いのを思い出す。裕司は良の行動を見ているようで存外見ていなかったし、同じ家の中でも互いに何をしているのか知らない時間も長かった。
「いいねこれ、また作ろ」
「おう、期待してる」
裕司の応えに、良は楽しそうにくすりと笑った。
良が明らかに疲れている様子のときは、食事はもっぱら──出来合いのものを含め──裕司が用意するのが習いだったが、そうでないとき良は手間を惜しまずに温かい手料理を並べてくれた。
それは最初からそうだったわけではなく、裕司が美味しいと言って食べてくれるのが楽しくなってきたのだと言ってくれたのを覚えている。
料理をする理由はもっぱら節約のためだと思っていたけれど、喜んでくれる人がいて、一緒に食べるとより美味しく感じる相手がいると、作るのも楽しいのだと気付いたと言っていた。
レパートリーも増えてきて、失敗する頻度も減ってきて、もしかしたら料理は彼の趣味のひとつになるのかもしれない、と裕司は思う。
良には趣味らしい趣味がなくて、せっかく好奇心旺盛な心を持っているのに、それを遊ばせているだけなのはもったいないと感じていた。
「飯が美味かったら、人生の最低限の幸せは保証されるって言ってた人がいたなぁ」
「へえ。なに、偉い人?」
「さあ、忘れたけど……飯を美味いと感じるのは幸せって意味かもな」
ああ、と良は頷いた。
「それはわかる。仕方なしに食べるご飯って味はするのに美味しいって思えなくてやだよね」
良の台詞に裕司は少し苦笑する。裕司の前での良はいつも食欲旺盛で、仕方なく食べているような姿はほとんど記憶になかった。
「お前がいるおかげで、最近また太りそうだよ」
良は黒い目を丸くして、しげしげと裕司を眺めながら言った。
「え? あんた太ってたことあんの?」
「……何想像してんのか知らねえけど、そんな見るからに太ってたわけじゃねえからな。デスクワークと飲み歩きばっかしてた時期がちょっとヤバかったんだよ」
「あー、あんたの仕事って太りやすそう」
「まあ……そうだよ。そのときはジムも行ってなくてな」
「でもそれがなんで今俺のせいなの」
じい、と真っ直ぐな目に見つめられて、裕司は何やら照れくさくなる。良の瞳は本人よりはるかに多弁で、その視線には力があった。
「お前と食う飯は美味いってだけの話だよ」
恥ずかしさを誤魔化したくて平気な声を繕って言うと、良はぱちぱちと瞬きをして、柔らかに笑んだ。
「それなら幸せでいいじゃん」
そう言って良はまたパスタの残りを食べ始める。その様子を裕司は思わず眺めて、はたと我に返って目を逸らした。
つまらないことで恥ずかしがった自分が愚かに思えるほど、良の反応は穏やかで自然だった。裕司が良のそばにいることにどこまでも肯定的な言葉をもらった気がして、反芻していくらか顔が熱くなる。
良がいてくれて、良が食事の支度をしてくれて、それを二人で一緒に食べる。それが今ではもう特別なことではなくなっていた。
──最低限どころじゃなく幸せだろ。
口には出せずにそんなことを思って、口をつけたスープはやけに甘く感じた。
「──で、訊きたいことっていうのは?」
昼食の片付けも済ませて、もう何も拒む言い訳はないだろうと思われるタイミングで再び問うてみると、良はしょっぱい顔をしてみせた。
「……俺が訊いてみたいって言ったのに、なんであんたが聞きたがる感じになってんの……」
「お前が何を訊きたいのか気になるに決まってんだろ」
ここまですれば逃げないだろう、という気持ちで淹れてやったアイスティーのグラスの中で、氷が揺れて音を立てた。
「……そんな気にされたらすごい訊きにくいんだけど……」
「それはまあ、諦めろ」
良はうらめしそうな目で裕司を見て、少しの間テーブルの上に視線をさまよわせていたが、やがて控えめな声音で言った。
「……言っとくけど、そんな大事な話じゃないからね?」
「お前が何を訊きたいのか知りたいだけだって」
良はそれでもまだ躊躇う顔をして、自分の膝を抱き寄せると、ようやく本題を口にした。
「……あんたって何で今の仕事しようと思ったの?」
「え?」
「なんか、あの、パソコンで色々作ったりするの、大学出てからずっとやってるんでしょ? ……なんでそれ仕事に選んだの?」
0
お気に入りに追加
24
あなたにおすすめの小説
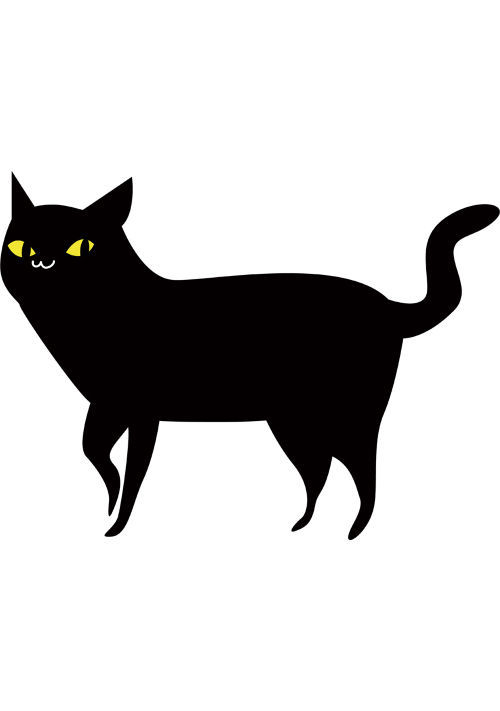
俺、猫になっちゃいました?!
空色蜻蛉
BL
ちょっと美青年なだけの普通の高校生の俺は、ある日突然、猫に変身する体質になってしまった。混乱する俺を助けたのは、俺と真逆のクール系で普段から気に入らないと思っていた天敵の遠藤。
初めてまともに話した遠藤は「自分も猫族だ」とか訳わかんねえことを言ってきて……。
プライドの高い猫×猫(受け同士という意味ではない)のコメディー風味BL。
段々仲良くなっていくと尻尾を絡ませ合ったり毛繕いしたりする……予定。
※が付く話は、軽微な性描写もしくはがっつりそういうシーンが入ります
◇空色蜻蛉の作品一覧はhttps://kakuyomu.jp/users/25tonbo/news/1177354054882823862をご覧ください。

【完結】離縁したいのなら、もっと穏便な方法もありましたのに。では、徹底的にやらせて頂きますね
との
恋愛
離婚したいのですか? 喜んでお受けします。
でも、本当に大丈夫なんでしょうか?
伯爵様・・自滅の道を行ってません?
まあ、徹底的にやらせて頂くだけですが。
収納スキル持ちの主人公と、錬金術師と異名をとる父親が爆走します。
(父さんの今の顔を見たらフリーカンパニーの団長も怯えるわ。ちっちゃい頃の私だったら確実に泣いてる)
ーーーーーー
ゆるふわの中世ヨーロッパ、幻の国の設定です。
32話、完結迄予約投稿済みです。
R15は念の為・・

【完結】遍く、歪んだ花たちに。
古都まとい
BL
職場の部下 和泉周(いずみしゅう)は、はっきり言って根暗でオタクっぽい。目にかかる長い前髪に、覇気のない視線を隠す黒縁眼鏡。仕事ぶりは可もなく不可もなく。そう、凡人の中の凡人である。
和泉の直属の上司である村谷(むらや)はある日、ひょんなことから繁華街のホストクラブへと連れて行かれてしまう。そこで出会ったNo.1ホスト天音(あまね)には、どこか和泉の面影があって――。
「先輩、僕のこと何も知っちゃいないくせに」
No.1ホスト部下×堅物上司の現代BL。


組長様のお嫁さん
ヨモギ丸
BL
いい所出身の外に憧れを抱くオメガのお坊ちゃん 雨宮 優 は家出をする。
持ち物に強めの薬を持っていたのだが、うっかりバックごと全ロスしてしまった。
公園のベンチで死にかけていた優を助けたのはたまたまお散歩していた世界規模の組を締め上げる組長 一ノ瀬 拓真
猫を飼う感覚で優を飼うことにした拓真だったが、だんだんその感情が恋愛感情に変化していく。
『へ?拓真さん俺でいいの?』


貧乏大学生がエリート商社マンに叶わぬ恋をしていたら、玉砕どころか溺愛された話
タタミ
BL
貧乏苦学生の巡は、同じシェアハウスに住むエリート商社マンの千明に片想いをしている。
叶わぬ恋だと思っていたが、千明にデートに誘われたことで、関係性が一変して……?
エリート商社マンに溺愛される初心な大学生の物語。

総長の彼氏が俺にだけ優しい
桜子あんこ
BL
ビビりな俺が付き合っている彼氏は、
関東で最強の暴走族の総長。
みんなからは恐れられ冷酷で悪魔と噂されるそんな俺の彼氏は何故か俺にだけ甘々で優しい。
そんな日常を描いた話である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















