121 / 154
第四章 試練と成長【ダンジョン探索編】
外伝 三人の旅立――イルマが望むもの
しおりを挟む
夜がほのぼのと明けるころ。サーデン帝国、帝都サダラーンの南門には、開門を待ちわびる冒険者や商人たち数百人が既に集まっていた。
いつものことなのだろう。無秩序に門の周りに集まっているのではなく、行儀よく整列している。
イルマは、辺りを観察してから言った。
「コウヘイ、ここからは一言もしゃべるでないぞ」
カタギリ・コウヘイ――サーデン帝国から依頼されたイルマが他の魔法士と協力して勇者召喚の魔法で呼び出した人物。ただそれも、彼は勇者ではなかった。しかも、魔力がゼロという稀有な存在。
そんな彼は、黙したまま頷いて隣にいるエルサの手を握った。
エルサは、コウヘイの奴隷であり魔力ゼロの彼にとって必要不可欠な存在。それは、逆もまた然りで互いに互いを必要としているのだ。
イルマは、あくまでおまけに過ぎない。コウヘイに対する罪滅ぼしとしての同行であり、請われてのことではなく自己満足に近い。コウヘイから信頼めいた感情を寄せられていることをイルマは気付いている。けれども、彼らの間に割って入れるほど親しくもない。
イルマもかつては、ヒューマンや獣人族たちと冒険者をしていたことがある。それは、一〇〇年近くも前の話だ。懐かしい感情の波が押し寄せてきたが、イルマには許されないことかもしれない。
コウヘイとエルサが手を繋いだまま、門へ向かって歩き出した。結束が固い二人の様子を羨望の眼差しを向けて眺めていると、イルマは異変に気付いて視線を行列の方へと向ける。
静かに並んでいた人々は、痺れを切らしたのか列からはみ出すように首を伸ばして前方を確認したり、グループから代表者を出して門の方へ様子を窺いに行かせたりと次第にざわつきはじめる。
とうに開門の時間を過ぎている。けれども、門は開かない。
人相書きを持った兵士四人組が、整列している人物の顔を検めるように、手に持った羊皮紙と列に並ぶ人々の顔との間で視線を往復させていた。
通り過ぎる間際、チラッと見えた羊皮紙にコウヘイに似た少年が描かれていることにイルマは気が付いた。どうやらコウヘイを探しているようだ。
そんな兵士たちを気にも留めず、目深にフードを被った黒いローブ姿の三人は、列を追い越して門へと向かう。かなり体格差があり人目を惹く風貌にもかかわらず、三人の存在にまったく気付いていない様子の兵士たちは、目当ての人物がいなとわかると次の集団を確認するために後方へ移動する。
あまりにも怪しい三人が門の前で立ち止まると、開門が遅れている理由が判明した。
「いやあ、勇者パーティーにいた人物がそんなことをするかね」
「いやいや、だからだろ。そんなことをするから追放されたんだよ」
「なるほど、そう考えればそうだな」
「まあ、もう少しで勇者様たちも来る。そうしたら開門だ」
商人と門番がそんな会話をしていた。
それを聞いたコウヘイは、俯いて拳を指が白くなるほど固く握っていた。濡れ衣を着せられて悔しいのだろう。彼は悔しさに耐えるように下唇を嚙んでいた。
そんなコウヘイの様子にいたたまれなくなったイルマが、空いている片方の手に自分の両手を添える。すると、ハッとなってから恥ずかしそうに微笑んだコウヘイが握った拳を開いてイルマの左手をギュッと握り返した。
握り返された手の感触から、「大丈夫、ありがとう」と言われた気がしてイルマも微笑んだのだった。
三人が纏っている黒いローブは、身隠しのローブという視認障害の効果が施されたマジックアイテムである。人前で声を出さない限りバレることはない。
暫くすると、ようやく勇者パーティーの一人が十数人の騎士を連れて南門に到着した。門が開かれるなり三人は、門を抜けて身体強化魔法の脚力でひたすら南に向けて走り出すのだった。
休憩がてら数時間おきにマジックポーションで魔力の補充をしつつ、南下し続けると辺りはすっかり夜の帳が落ちていた。
夏が近付き昼間は暑いくらいなのだが、夜ともなればまだまだ肌寒い。暖を取るために焚火用の小枝などを森から拾ってきたコウヘイが野営地に戻って来るなり尋ねた。
「大分走ったけど、どの辺りまで来たんだろう」
「ふむ、ここがレーマン侯爵領だと言えばわかるじゃろう?」
「え! じゃ、じゃあ、さっき遠くに見えたのは、もしかして城塞都市レーマン?」
レーマン侯爵領と聞き、現在地を理解したコウヘイが驚いたように声を上げた。突然の大声にイルマが顔を僅かに顰め、頷いてからコウヘイが抱えている小枝を受け取る。
驚くのも仕方のないことだろう。城塞都市レーマンは、帝都に一番近い都市とはいえ、馬車で二日掛かる距離である。それを己が身だけで一二時間程度、つまりは四分の一の時間で到達したのだ。
「イグニション……むむ、火がつかんの」
イルマが生活魔法である着火を唱えたが、なかなか火が付かない。数日前に雨が降ったせいか、小枝が湿っているようなのだ。
「どれどれ、ちょっと僕にやらせてよ」
「いらん。そのうちつくじゃろうて……」
イルマが何度か試すうちに火が付いたものの、直ぐに消えてしまった。
「ほら、言ったじゃないか。魔法はイメージ力なんだって」
結果、コウヘイにやらせてみたら成功した。
イルマとしては釈然としない。つい先日まで魔法が使えなったコウヘイに出来て、エルフの賢者とまで呼ばれている自分が失敗してしまいイルマは納得がいかなかったのだ。
イルマは、焚火で暖を取りながら無言でオークの干し肉をガシガシと齧る。
「あ、あのー、イルマさん? もしかして、怒ってらっしゃる……」
「ふんっ、怒っとらん。しかも、イルマさんとは何じゃ? バカにしておるじゃろ」
大人げないと思いながらも、イルマは子供っぽくぷいっとそっぽを向く。すると、エルサが苦笑いしていた。
「まあまあ、コウヘイだって悪気がある訳じゃないと思うよ。ねーコウヘイ」
「そうそう、エルサの言う通り。何て言ったらいいのかわからないけど、魔法が使えるようになったのが嬉しくて」
そんなのは理解している。イルマは、面白くないだけなのである。コウヘイの魔法をはじめてみたときイルマは相当驚いた。コウヘイの魔法は、イルマが六四八年という長い年月信じてきた魔法の常識を全て覆すものだったのだ。
だがしかし、イルマはそのことを面白いとも思った。コウヘイから聞かされる魔法の話は、全てが新鮮でよく考えてみれば理解できるものばかりだった。
イメージ次第で効果が変わると言われれば、色々な可能性を感じて興奮したものである。
ただ単に、イルマには出来ないのが面白くないのだ。むしろ、才能が無いと言われているような気がして打ちのめされたのである。
「まあ、よかろう。そのうち、わしもできるようになるじゃろ」
「え?」
「なんじゃ?」
「ううん、何でもない」
イルマが漏らした言葉から、コウヘイは察したのだろう。間の抜けた声を出したコウヘイを睨むと、勢いよく首を左右に振っていた。
イルマだってわかっている。たかが一六歳の青年に嫉妬している自分が恥ずかしい。
食後のハーブティーを飲み終えてイルマがティーセットを水洗いしていると、視界の端でコウヘイが立ち上がった。
「それじゃあ、今夜は僕が見張りをするから、エルサとイルマは先に寝ていいよ」
「その必要はない」
ティーセットを洗い終えたイルマがそれを魔法袋にしまいながらそう告げた。それには、コウヘイとエルサの二人が説明してほしそうに首を傾げている。
「これから移動を再開するからじゃよ」
「いやいや、無理でしょ。夜になると魔獣が活発化するし、盗賊だって出る危険性が高いんだよ。って、イルマ!」
コウヘイの指摘は百も承知だ。が、イルマは焚火をウォーターで消して踏み散らす。辺りが真っ暗になったからかコウヘイが非難の声を上げる。
「トーチボール」
イルマが気にせず魔法を唱えると、光の玉が出現して辺りを照らす。
「見張りをしてくれるのはありがたい。じゃが、コウヘイが眠れんじゃろう」
「大丈夫だよ。勇者パーティーのときだって騎士団がいないと僕が担当していたし」
どうやら、コウヘイにはイルマの意図がまったく伝わっていないようだ。それならば、「いいからついて来るのじゃ」と言うにとどめて街道の方へとイルマが歩き出す。
途端、エルサが気付いたように手の平を打ち鳴らした。
「あ、もしかして、明日の移動に支障が出るってこと?」
「うむ、その通りじゃな」
「……いや、そうだけど、数時間寝れば大丈夫だと思う、よ?」
「何で疑問形なんじゃ。まったくお主は……」
自信なさげなコウヘイの言い分に、イルマが呆れたようにはぁーと吐き出すように息をする。けれども、夜通し進んでもいつか休憩する必要が出てくるのは事実だ。
「まあよい。種明かしをするとこれで移動するんじゃよ」
街道まで来たところでイルマが魔法袋から幌付きの大きな荷馬車を取り出した。
「え、馬車? 魔法袋でも生き物は収納できないハズじゃ……」
「そりゃ当たり前じゃ。馬ではなくこれじゃな。これはわしの傑作でな。自律型魔導ゴーレムが引く魔導馬車じゃよ」
馬型のゴーレムを出したところでイルマが、「どうじゃ? 驚いたじゃろ」と無い胸を張る。
今後も今日のように移動しても良いが、身体への負担が大きい。立証されている訳ではないが、ポーション類の過剰使用は人体に悪影響を及ぼすという説がある。
指名手配されているなか、帝都付近でのんびりするのはさすがに危険である。故に、今日は無理を押して急いだに過ぎない。手配されたのは昨日のことであり、馬車で二日掛かるレーマン侯爵領まで来てしまえば十分だろうとの判断である。
イルマが諸々の説明をすると、コウヘイとエルサの二人は、すぐに理解を示して魔導馬車に乗り込んだのであった。
魔導馬車で移動すること十数分。見張りをすると言っていたコウヘイは、既に夢の世界へ旅立ってしまった。
「しかし、なんともまあと言う感じじゃのう」
「いいじゃない。コウヘイにとって長時間の魔法行使は不慣れなことだし、疲れちゃったんだと思うよ」
エルサがコウヘイを庇うような発言をする。彼女が言ったことをイルマも理解できるが、目の前の光景にはさすがに呆れて脱力してしまう。
「じゃが、あれは何じゃったんじゃ? 偉そうに言っていた割には気持ちよさそうに眠っておる。いつもこんな様子じゃあるまいな?」
「うーん、どうだろう。コウヘイは、自分にできることとできないことを理解している感じだよ。むしろ、慎重すぎるくらい。それに、わたしのことも凄い気に掛けてくれるんだよー」
「ふむ、大事にされているようで何よりじゃ」
「そうだねー。奴隷になったことに気付いたときはショックだったけど、コウヘイといると自分が奴隷であることを忘れちゃうんだよね」
自嘲気味に笑うエルサから悲壮感は感じられない。むしろ、コウヘイの奴隷であることが嬉しいようだ。
イルマは思わずエルサに尋ねた。
「それにしても、じゃ。夜も凄いのか?」
エルサが装備を外し、恥じらいもなく胸をはだけさせ身体を拭き始めたのだ。ダークエルフの褐色の肌が魔導ランプの灯に照らされて艶めかしい。しかも、身体の割に大きな双丘が、馬車の揺れに合わせて弾んでいる。
いくらコウヘイが眠っているからといって、不用心だ。けれども、既にそういう関係であるならば不自然ではない。
「え、う、うん。凄いよ。いつも激しくてぐったりだよ、あははは」
「ほーう、それは意外じゃな」
エルサの反応からして、まだであることがイルマには理解できた。
「ちぇー、イルマには隠せないか」
嘘がバレたことに気付いたエルサは、小さな口を突き出して頬を膨らませた。
そんな子供のような仕草をするエルサは、同じ女であるイルマから見ても魅惑的なボディーラインをしている。それでも、コウヘイの性格を考えると納得できる。
ふと、イルマはエルサを揶揄いたくなった。
「ふむ、もしかしたらじゃが、わしのようなのが好きなのかもしれんぞ」
無い胸を見下ろして両手で揉みながらイルマが言うと、エルサが素っ頓狂な声を上げた。
「しっ、声が大きい!」
イルマが慌てて声を押し殺したように叫んだが、杞憂に終わった。コウヘイは、寝息を立ててぐっすりと眠ったまま目を覚ます様子がない。
夜間の移動中であり、本来は魔獣たちに襲われる危険性を考えたら起きて欲しいところだが、今回は逆に好都合である。
「イルマの意地悪……」
なぜか涙目になっているエルサを他所に、イルマは安全を確認するようにコウヘイの寝顔を覗き込んだ。
「ふんっ、しかし、気持ちよさそうに寝ておるのう。いったいどんな夢を見ているのやら。これなら大丈夫かのう」
イルマは、ローブを脱いでシャツのボタンを一つずつ外していく。上半身が綿布の胸当てだけとなり、エルサの大胆さが伝染したのかそれも一思いに脱ぎ捨てる。
ハイエルフ特有の透き通るような白い肌に形の良い膨らみが二つ。が、大きさが足りないのだ。
「むむ、やっぱり世の中不公平じゃ」
イルマは、手の平にすっぽりおさまってしまう胸を押さえて不満を漏らす。
「ええー可愛くていいじゃん」
「ぬしや。わざと言っておるんじゃあるまいな……」
悔しさから奥歯をギリギリと鳴らしてエルサを睨むが、どうやら他意はないようだ。ニッコリと笑ったエルサが手招きしている。
エルサに、「ほら」と言われて手を掴まれた。イルマは、慎ましい胸を晒したまま彼女の胸を揉まされるのだった。
イルマは、「何じゃこの状況は!」と思いながらもエルサのもっちりと手に吸い付く感触に、「これはこれで悪くない」と素直な感想を漏らした。
「えーどこがよぉ。結構重くない?」
イルマの感想を聞いたエルサは、不満げだ。故に、イルマが重さを確かめるように再び両手で揉んでみたものの、揉む度に心地よい重さを掌に感じて首を傾げる。
「はて」
途端、荷台が撥ねた。
「……んんん? あぁ、ごめん、寝ちゃったみたい……」
両手で顔をゴシゴシと擦りながらコウヘイが目を覚まし、
「あ、えーっと、夢だ、夢……」
と呟いて瞼を閉じた。
コウヘイの反応は尤もなことだろう。目を覚ましたら上半身裸のイルマが、同じく露出させたエルサの胸を揉みしだいていたのだから。
「ぬぬっー!」
イルマは、あられもない姿をコウヘイに見られて発狂する。
「コウヘイ、寝るでない!」
見られ損のイルマがバシバシとコウヘイを叩き起こす。
「わかった。わかったから、身体強化した状態で叩かないでぇーっ」
恥ずかしさのあまり、無意識に身体強化の魔法が発動していたようだ。イルマが意識してパワーブーストを解除する。
はじめて無詠唱で魔法を行使できたことに上機嫌になったイルマは、目の前のコウヘイをどう調理しようかとほくそ笑む。
「で、僕はどうしたらいいの?」
頬を赤く染め、伏し目がちのコウヘイがモジモジとしている。
「わしのを吸うのじゃ」
吹っ切れたイルマは、乙女の恥じらいをかなぐり捨てて無い胸を張るのだった。
「はっ?」
「なんじゃ。そんなところに手を置いて? わしの慎ましくも愛らしい胸を見て反応したんじゃな」
「ち、違うよ。これは寝起きの生理現象だって」
慌てている時点で怪しい。前者なら嬉しい気もするが、イルマにとってそんなのはどっちだっていい。
「くふ、可愛い奴じゃのう。何を吸うつもりなんじゃ?」
「あっ」
反応を楽しまれていることを察したのだろう。コウヘイが深く長い息を漏らした。
「冗談きついよ。何でもいいからさ。二人とも服を着てくれないかな」
「そもそも勘違いしたコウヘイが悪いのじゃ」
「いやあ、そうなんだけど、少しはエルサから吸収した魔力が残ってるし……」
「いやじゃ、いやじゃ、わしのを吸わないと許さんのじゃ」
「何で!」
そうなのである。魔力ゼロのコウヘイは、他人の魔力や大気中の魔素を吸収できるスキルの持ち主である。ただそれも、自分で生み出せない代償であり、マジックポーションを飲んでも増えることがない。
「それはわしの裸を見たバツじゃよ」
イルマは、コウヘイから魔力を吸収される際の感覚にハマってしまったのである。それは、身体の奥底から突き上げられるような快楽で、何とも言えぬ幸福感を与えてくれるのだ。
「それに、じゃ……」
仲間と旅に出ることは二度と無いと諦めていたのにもかかわらず、こうしてコウヘイとエルサに出会ってしまった。
「コウヘイの役に立ちたいのじゃ」
「イルマ……」
「コウヘイ……」
イルマが胸の内を明かすように吐露し、互いの名を呼び合い見つめ合う。コウヘイの頬が赤く染まり、イルマもまた頬に熱を感じる。吐息を感じるほど近付いていた。
が、
「それはわかったから服を着てよ!」
「な!」
どこから出したのか、白いシャツをコウヘイから押し付けられるようにして受け取った。
ウッドエルフ族の頂点に立つ女王であるイルマは、沢山の男に求婚されてきた。にもかかわらず、羞恥心を捨ててまでお願いしたことを拒否されて固まってしまう。さらに、六三二歳も年下のコウヘイにドキドキしてしまったことを自覚したイルマは、恥じるように物言わぬ貝と成り果ててしまうのだった。
ただそれも、コウヘイにも言い分があったようだ。どうやら、イルマの見た目があまりにも幼すぎることが問題なのだとか。
それを聞かされたイルマが余計に心の傷を負うほどの衝撃を受けた訳だが、仲間として大事に思っているのは確かだからとの言葉をコウヘイから聞けただけで十分だった。
仲間――その言葉こそが、イルマが一番望んでいたものなのだから。
いつものことなのだろう。無秩序に門の周りに集まっているのではなく、行儀よく整列している。
イルマは、辺りを観察してから言った。
「コウヘイ、ここからは一言もしゃべるでないぞ」
カタギリ・コウヘイ――サーデン帝国から依頼されたイルマが他の魔法士と協力して勇者召喚の魔法で呼び出した人物。ただそれも、彼は勇者ではなかった。しかも、魔力がゼロという稀有な存在。
そんな彼は、黙したまま頷いて隣にいるエルサの手を握った。
エルサは、コウヘイの奴隷であり魔力ゼロの彼にとって必要不可欠な存在。それは、逆もまた然りで互いに互いを必要としているのだ。
イルマは、あくまでおまけに過ぎない。コウヘイに対する罪滅ぼしとしての同行であり、請われてのことではなく自己満足に近い。コウヘイから信頼めいた感情を寄せられていることをイルマは気付いている。けれども、彼らの間に割って入れるほど親しくもない。
イルマもかつては、ヒューマンや獣人族たちと冒険者をしていたことがある。それは、一〇〇年近くも前の話だ。懐かしい感情の波が押し寄せてきたが、イルマには許されないことかもしれない。
コウヘイとエルサが手を繋いだまま、門へ向かって歩き出した。結束が固い二人の様子を羨望の眼差しを向けて眺めていると、イルマは異変に気付いて視線を行列の方へと向ける。
静かに並んでいた人々は、痺れを切らしたのか列からはみ出すように首を伸ばして前方を確認したり、グループから代表者を出して門の方へ様子を窺いに行かせたりと次第にざわつきはじめる。
とうに開門の時間を過ぎている。けれども、門は開かない。
人相書きを持った兵士四人組が、整列している人物の顔を検めるように、手に持った羊皮紙と列に並ぶ人々の顔との間で視線を往復させていた。
通り過ぎる間際、チラッと見えた羊皮紙にコウヘイに似た少年が描かれていることにイルマは気が付いた。どうやらコウヘイを探しているようだ。
そんな兵士たちを気にも留めず、目深にフードを被った黒いローブ姿の三人は、列を追い越して門へと向かう。かなり体格差があり人目を惹く風貌にもかかわらず、三人の存在にまったく気付いていない様子の兵士たちは、目当ての人物がいなとわかると次の集団を確認するために後方へ移動する。
あまりにも怪しい三人が門の前で立ち止まると、開門が遅れている理由が判明した。
「いやあ、勇者パーティーにいた人物がそんなことをするかね」
「いやいや、だからだろ。そんなことをするから追放されたんだよ」
「なるほど、そう考えればそうだな」
「まあ、もう少しで勇者様たちも来る。そうしたら開門だ」
商人と門番がそんな会話をしていた。
それを聞いたコウヘイは、俯いて拳を指が白くなるほど固く握っていた。濡れ衣を着せられて悔しいのだろう。彼は悔しさに耐えるように下唇を嚙んでいた。
そんなコウヘイの様子にいたたまれなくなったイルマが、空いている片方の手に自分の両手を添える。すると、ハッとなってから恥ずかしそうに微笑んだコウヘイが握った拳を開いてイルマの左手をギュッと握り返した。
握り返された手の感触から、「大丈夫、ありがとう」と言われた気がしてイルマも微笑んだのだった。
三人が纏っている黒いローブは、身隠しのローブという視認障害の効果が施されたマジックアイテムである。人前で声を出さない限りバレることはない。
暫くすると、ようやく勇者パーティーの一人が十数人の騎士を連れて南門に到着した。門が開かれるなり三人は、門を抜けて身体強化魔法の脚力でひたすら南に向けて走り出すのだった。
休憩がてら数時間おきにマジックポーションで魔力の補充をしつつ、南下し続けると辺りはすっかり夜の帳が落ちていた。
夏が近付き昼間は暑いくらいなのだが、夜ともなればまだまだ肌寒い。暖を取るために焚火用の小枝などを森から拾ってきたコウヘイが野営地に戻って来るなり尋ねた。
「大分走ったけど、どの辺りまで来たんだろう」
「ふむ、ここがレーマン侯爵領だと言えばわかるじゃろう?」
「え! じゃ、じゃあ、さっき遠くに見えたのは、もしかして城塞都市レーマン?」
レーマン侯爵領と聞き、現在地を理解したコウヘイが驚いたように声を上げた。突然の大声にイルマが顔を僅かに顰め、頷いてからコウヘイが抱えている小枝を受け取る。
驚くのも仕方のないことだろう。城塞都市レーマンは、帝都に一番近い都市とはいえ、馬車で二日掛かる距離である。それを己が身だけで一二時間程度、つまりは四分の一の時間で到達したのだ。
「イグニション……むむ、火がつかんの」
イルマが生活魔法である着火を唱えたが、なかなか火が付かない。数日前に雨が降ったせいか、小枝が湿っているようなのだ。
「どれどれ、ちょっと僕にやらせてよ」
「いらん。そのうちつくじゃろうて……」
イルマが何度か試すうちに火が付いたものの、直ぐに消えてしまった。
「ほら、言ったじゃないか。魔法はイメージ力なんだって」
結果、コウヘイにやらせてみたら成功した。
イルマとしては釈然としない。つい先日まで魔法が使えなったコウヘイに出来て、エルフの賢者とまで呼ばれている自分が失敗してしまいイルマは納得がいかなかったのだ。
イルマは、焚火で暖を取りながら無言でオークの干し肉をガシガシと齧る。
「あ、あのー、イルマさん? もしかして、怒ってらっしゃる……」
「ふんっ、怒っとらん。しかも、イルマさんとは何じゃ? バカにしておるじゃろ」
大人げないと思いながらも、イルマは子供っぽくぷいっとそっぽを向く。すると、エルサが苦笑いしていた。
「まあまあ、コウヘイだって悪気がある訳じゃないと思うよ。ねーコウヘイ」
「そうそう、エルサの言う通り。何て言ったらいいのかわからないけど、魔法が使えるようになったのが嬉しくて」
そんなのは理解している。イルマは、面白くないだけなのである。コウヘイの魔法をはじめてみたときイルマは相当驚いた。コウヘイの魔法は、イルマが六四八年という長い年月信じてきた魔法の常識を全て覆すものだったのだ。
だがしかし、イルマはそのことを面白いとも思った。コウヘイから聞かされる魔法の話は、全てが新鮮でよく考えてみれば理解できるものばかりだった。
イメージ次第で効果が変わると言われれば、色々な可能性を感じて興奮したものである。
ただ単に、イルマには出来ないのが面白くないのだ。むしろ、才能が無いと言われているような気がして打ちのめされたのである。
「まあ、よかろう。そのうち、わしもできるようになるじゃろ」
「え?」
「なんじゃ?」
「ううん、何でもない」
イルマが漏らした言葉から、コウヘイは察したのだろう。間の抜けた声を出したコウヘイを睨むと、勢いよく首を左右に振っていた。
イルマだってわかっている。たかが一六歳の青年に嫉妬している自分が恥ずかしい。
食後のハーブティーを飲み終えてイルマがティーセットを水洗いしていると、視界の端でコウヘイが立ち上がった。
「それじゃあ、今夜は僕が見張りをするから、エルサとイルマは先に寝ていいよ」
「その必要はない」
ティーセットを洗い終えたイルマがそれを魔法袋にしまいながらそう告げた。それには、コウヘイとエルサの二人が説明してほしそうに首を傾げている。
「これから移動を再開するからじゃよ」
「いやいや、無理でしょ。夜になると魔獣が活発化するし、盗賊だって出る危険性が高いんだよ。って、イルマ!」
コウヘイの指摘は百も承知だ。が、イルマは焚火をウォーターで消して踏み散らす。辺りが真っ暗になったからかコウヘイが非難の声を上げる。
「トーチボール」
イルマが気にせず魔法を唱えると、光の玉が出現して辺りを照らす。
「見張りをしてくれるのはありがたい。じゃが、コウヘイが眠れんじゃろう」
「大丈夫だよ。勇者パーティーのときだって騎士団がいないと僕が担当していたし」
どうやら、コウヘイにはイルマの意図がまったく伝わっていないようだ。それならば、「いいからついて来るのじゃ」と言うにとどめて街道の方へとイルマが歩き出す。
途端、エルサが気付いたように手の平を打ち鳴らした。
「あ、もしかして、明日の移動に支障が出るってこと?」
「うむ、その通りじゃな」
「……いや、そうだけど、数時間寝れば大丈夫だと思う、よ?」
「何で疑問形なんじゃ。まったくお主は……」
自信なさげなコウヘイの言い分に、イルマが呆れたようにはぁーと吐き出すように息をする。けれども、夜通し進んでもいつか休憩する必要が出てくるのは事実だ。
「まあよい。種明かしをするとこれで移動するんじゃよ」
街道まで来たところでイルマが魔法袋から幌付きの大きな荷馬車を取り出した。
「え、馬車? 魔法袋でも生き物は収納できないハズじゃ……」
「そりゃ当たり前じゃ。馬ではなくこれじゃな。これはわしの傑作でな。自律型魔導ゴーレムが引く魔導馬車じゃよ」
馬型のゴーレムを出したところでイルマが、「どうじゃ? 驚いたじゃろ」と無い胸を張る。
今後も今日のように移動しても良いが、身体への負担が大きい。立証されている訳ではないが、ポーション類の過剰使用は人体に悪影響を及ぼすという説がある。
指名手配されているなか、帝都付近でのんびりするのはさすがに危険である。故に、今日は無理を押して急いだに過ぎない。手配されたのは昨日のことであり、馬車で二日掛かるレーマン侯爵領まで来てしまえば十分だろうとの判断である。
イルマが諸々の説明をすると、コウヘイとエルサの二人は、すぐに理解を示して魔導馬車に乗り込んだのであった。
魔導馬車で移動すること十数分。見張りをすると言っていたコウヘイは、既に夢の世界へ旅立ってしまった。
「しかし、なんともまあと言う感じじゃのう」
「いいじゃない。コウヘイにとって長時間の魔法行使は不慣れなことだし、疲れちゃったんだと思うよ」
エルサがコウヘイを庇うような発言をする。彼女が言ったことをイルマも理解できるが、目の前の光景にはさすがに呆れて脱力してしまう。
「じゃが、あれは何じゃったんじゃ? 偉そうに言っていた割には気持ちよさそうに眠っておる。いつもこんな様子じゃあるまいな?」
「うーん、どうだろう。コウヘイは、自分にできることとできないことを理解している感じだよ。むしろ、慎重すぎるくらい。それに、わたしのことも凄い気に掛けてくれるんだよー」
「ふむ、大事にされているようで何よりじゃ」
「そうだねー。奴隷になったことに気付いたときはショックだったけど、コウヘイといると自分が奴隷であることを忘れちゃうんだよね」
自嘲気味に笑うエルサから悲壮感は感じられない。むしろ、コウヘイの奴隷であることが嬉しいようだ。
イルマは思わずエルサに尋ねた。
「それにしても、じゃ。夜も凄いのか?」
エルサが装備を外し、恥じらいもなく胸をはだけさせ身体を拭き始めたのだ。ダークエルフの褐色の肌が魔導ランプの灯に照らされて艶めかしい。しかも、身体の割に大きな双丘が、馬車の揺れに合わせて弾んでいる。
いくらコウヘイが眠っているからといって、不用心だ。けれども、既にそういう関係であるならば不自然ではない。
「え、う、うん。凄いよ。いつも激しくてぐったりだよ、あははは」
「ほーう、それは意外じゃな」
エルサの反応からして、まだであることがイルマには理解できた。
「ちぇー、イルマには隠せないか」
嘘がバレたことに気付いたエルサは、小さな口を突き出して頬を膨らませた。
そんな子供のような仕草をするエルサは、同じ女であるイルマから見ても魅惑的なボディーラインをしている。それでも、コウヘイの性格を考えると納得できる。
ふと、イルマはエルサを揶揄いたくなった。
「ふむ、もしかしたらじゃが、わしのようなのが好きなのかもしれんぞ」
無い胸を見下ろして両手で揉みながらイルマが言うと、エルサが素っ頓狂な声を上げた。
「しっ、声が大きい!」
イルマが慌てて声を押し殺したように叫んだが、杞憂に終わった。コウヘイは、寝息を立ててぐっすりと眠ったまま目を覚ます様子がない。
夜間の移動中であり、本来は魔獣たちに襲われる危険性を考えたら起きて欲しいところだが、今回は逆に好都合である。
「イルマの意地悪……」
なぜか涙目になっているエルサを他所に、イルマは安全を確認するようにコウヘイの寝顔を覗き込んだ。
「ふんっ、しかし、気持ちよさそうに寝ておるのう。いったいどんな夢を見ているのやら。これなら大丈夫かのう」
イルマは、ローブを脱いでシャツのボタンを一つずつ外していく。上半身が綿布の胸当てだけとなり、エルサの大胆さが伝染したのかそれも一思いに脱ぎ捨てる。
ハイエルフ特有の透き通るような白い肌に形の良い膨らみが二つ。が、大きさが足りないのだ。
「むむ、やっぱり世の中不公平じゃ」
イルマは、手の平にすっぽりおさまってしまう胸を押さえて不満を漏らす。
「ええー可愛くていいじゃん」
「ぬしや。わざと言っておるんじゃあるまいな……」
悔しさから奥歯をギリギリと鳴らしてエルサを睨むが、どうやら他意はないようだ。ニッコリと笑ったエルサが手招きしている。
エルサに、「ほら」と言われて手を掴まれた。イルマは、慎ましい胸を晒したまま彼女の胸を揉まされるのだった。
イルマは、「何じゃこの状況は!」と思いながらもエルサのもっちりと手に吸い付く感触に、「これはこれで悪くない」と素直な感想を漏らした。
「えーどこがよぉ。結構重くない?」
イルマの感想を聞いたエルサは、不満げだ。故に、イルマが重さを確かめるように再び両手で揉んでみたものの、揉む度に心地よい重さを掌に感じて首を傾げる。
「はて」
途端、荷台が撥ねた。
「……んんん? あぁ、ごめん、寝ちゃったみたい……」
両手で顔をゴシゴシと擦りながらコウヘイが目を覚まし、
「あ、えーっと、夢だ、夢……」
と呟いて瞼を閉じた。
コウヘイの反応は尤もなことだろう。目を覚ましたら上半身裸のイルマが、同じく露出させたエルサの胸を揉みしだいていたのだから。
「ぬぬっー!」
イルマは、あられもない姿をコウヘイに見られて発狂する。
「コウヘイ、寝るでない!」
見られ損のイルマがバシバシとコウヘイを叩き起こす。
「わかった。わかったから、身体強化した状態で叩かないでぇーっ」
恥ずかしさのあまり、無意識に身体強化の魔法が発動していたようだ。イルマが意識してパワーブーストを解除する。
はじめて無詠唱で魔法を行使できたことに上機嫌になったイルマは、目の前のコウヘイをどう調理しようかとほくそ笑む。
「で、僕はどうしたらいいの?」
頬を赤く染め、伏し目がちのコウヘイがモジモジとしている。
「わしのを吸うのじゃ」
吹っ切れたイルマは、乙女の恥じらいをかなぐり捨てて無い胸を張るのだった。
「はっ?」
「なんじゃ。そんなところに手を置いて? わしの慎ましくも愛らしい胸を見て反応したんじゃな」
「ち、違うよ。これは寝起きの生理現象だって」
慌てている時点で怪しい。前者なら嬉しい気もするが、イルマにとってそんなのはどっちだっていい。
「くふ、可愛い奴じゃのう。何を吸うつもりなんじゃ?」
「あっ」
反応を楽しまれていることを察したのだろう。コウヘイが深く長い息を漏らした。
「冗談きついよ。何でもいいからさ。二人とも服を着てくれないかな」
「そもそも勘違いしたコウヘイが悪いのじゃ」
「いやあ、そうなんだけど、少しはエルサから吸収した魔力が残ってるし……」
「いやじゃ、いやじゃ、わしのを吸わないと許さんのじゃ」
「何で!」
そうなのである。魔力ゼロのコウヘイは、他人の魔力や大気中の魔素を吸収できるスキルの持ち主である。ただそれも、自分で生み出せない代償であり、マジックポーションを飲んでも増えることがない。
「それはわしの裸を見たバツじゃよ」
イルマは、コウヘイから魔力を吸収される際の感覚にハマってしまったのである。それは、身体の奥底から突き上げられるような快楽で、何とも言えぬ幸福感を与えてくれるのだ。
「それに、じゃ……」
仲間と旅に出ることは二度と無いと諦めていたのにもかかわらず、こうしてコウヘイとエルサに出会ってしまった。
「コウヘイの役に立ちたいのじゃ」
「イルマ……」
「コウヘイ……」
イルマが胸の内を明かすように吐露し、互いの名を呼び合い見つめ合う。コウヘイの頬が赤く染まり、イルマもまた頬に熱を感じる。吐息を感じるほど近付いていた。
が、
「それはわかったから服を着てよ!」
「な!」
どこから出したのか、白いシャツをコウヘイから押し付けられるようにして受け取った。
ウッドエルフ族の頂点に立つ女王であるイルマは、沢山の男に求婚されてきた。にもかかわらず、羞恥心を捨ててまでお願いしたことを拒否されて固まってしまう。さらに、六三二歳も年下のコウヘイにドキドキしてしまったことを自覚したイルマは、恥じるように物言わぬ貝と成り果ててしまうのだった。
ただそれも、コウヘイにも言い分があったようだ。どうやら、イルマの見た目があまりにも幼すぎることが問題なのだとか。
それを聞かされたイルマが余計に心の傷を負うほどの衝撃を受けた訳だが、仲間として大事に思っているのは確かだからとの言葉をコウヘイから聞けただけで十分だった。
仲間――その言葉こそが、イルマが一番望んでいたものなのだから。
0
お気に入りに追加
457
あなたにおすすめの小説

百花繚乱 〜国の姫から極秘任務を受けた俺のスキルの行くところ〜
幻月日
ファンタジー
ーー時は魔物時代。
魔王を頂点とする闇の群勢が世界中に蔓延る中、勇者という職業は人々にとって希望の光だった。
そんな勇者の一人であるシンは、逃れ行き着いた村で村人たちに魔物を差し向けた勇者だと勘違いされてしまい、滞在中の兵団によってシーラ王国へ送られてしまった。
「勇者、シン。あなたには魔王の城に眠る秘宝、それを盗み出して来て欲しいのです」
唐突にアリス王女に突きつけられたのは、自分のようなランクの勇者に与えられる任務ではなかった。レベル50台の魔物をようやく倒せる勇者にとって、レベル100台がいる魔王の城は未知の領域。
「ーー王女が頼む、その任務。俺が引き受ける」
シンの持つスキルが頼りだと言うアリス王女。快く引き受けたわけではなかったが、シンはアリス王女の頼みを引き受けることになり、魔王の城へ旅立つ。
これは魔物が世界に溢れる時代、シーラ王国の姫に頼まれたのをきっかけに魔王の城を目指す勇者の物語。

『ラズーン』第二部
segakiyui
ファンタジー
謎を秘めた美貌の付き人アシャとともに、統合府ラズーンへのユーノの旅は続く。様々な国、様々な生き物に出逢ううち、少しずつ気持ちが開いていくのだが、アシャへの揺れる恋心は行き場をなくしたまま。一方アシャも見る見るユーノに引き寄せられていく自分に戸惑う。

メサイア
渡邉 幻月
ファンタジー
幻想が現実になる日。あるいは世界が転生する日。
三度目の核が落ちたあの日、天使が天使であることを止めた。
そして、人は神にさえ抗う術を得る。
リアルが崩壊したあとにあったのは、ファンタジーな日常だった。
世界のこの有り様は、神の気紛れか魔王の戯れか。
世界は、どこへ向かうのか。
人は、かつての世界を取り戻せるのか。今や、夢物語となった、世界を。
※エブリスタ様、小説家になろう様で投稿中の作品です
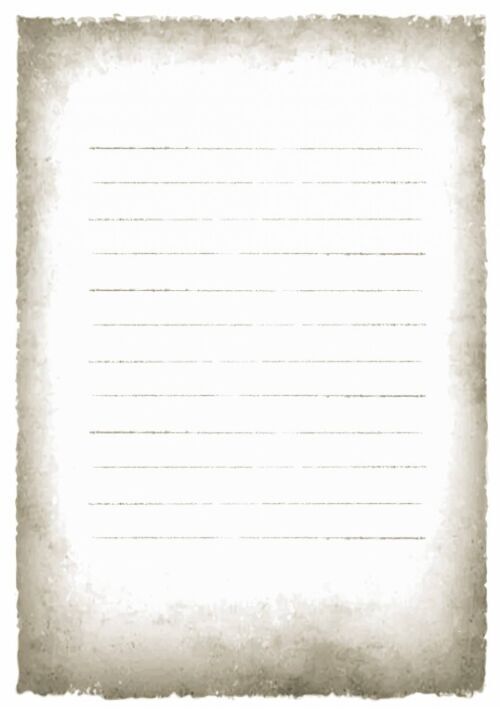
遺された日記【完】
静月
ファンタジー
※鬱描写あり
今では昔、巨大な地響きと共に森の中にダンジョンが出現した。
人々はなんの情報もない未知の構造物に何があるのか心を踊らせ次々にダンジョンへと探索に入った。
しかし、ダンジョンの奥地に入った者はほぼ全て二度と返ってくることはなかった。
偶に生き残って帰還を果たす者もいたがその者たちは口を揃えて『ダンジョンは人が行って良いものではない』といったという。
直に人もダンジョンには近づかなくなっていって今に至る

鬼切りの刀に憑かれた逢神は鬼姫と一緒にいる
ぽとりひょん
ファンタジー
逢神も血筋は鬼切の刀に憑りつかれている、たけるも例外ではなかったが鬼姫鈴鹿が一緒にいることになる。 たけると鈴鹿は今日も鬼を切り続ける。

虹の向こうへ
もりえつりんご
ファンタジー
空の神が創り守る、三種の人間が住まう世界にて。
智慧の種族と呼ばれる心魔の少年・透火(トウカ)は、幼い頃に第一王子・芝蘭(シラン)に助けられ、その恩返しをするべく、従者として働く日々を送っていた。
しかしそれも、透火が種族を代表するヒト「基音」となり、世界と種族の繁栄を維持する「空の神」候補であると判明するまでのこと。
かつて、種族戦争に敗れ、衰退を辿る珠魔の代表・占音(センネ)と、第四の種族「銀の守護者」のハーク。
二人は、穢れていくこの世界を救うべく、相反する目的の元、透火と芝蘭に接触する。
芝蘭のために「基音」の立場すら利用する透火と、透火との時間を守るために「基音」や「空の神」誕生に消極的な芝蘭は、王位継承や種族関係の変化と共に、すれ違っていく。
それぞれの願いと思いを抱えて、透火、芝蘭、占音、ハークの四人は、衝突し、理解し、共有し、拒絶を繰り返して、一つの世界を紡いでいく。
そう、これは、誰かと生きる意味を考えるハイファンタジー。
ーーーーーーーーー
これは、絶望と希望に翻弄されながらも、「自分」とは何かを知っていく少年と、少年の周囲にいる思慮深い人々との関係の変化、そして、世界と個人との結びつきを描いたメリーバッドエンドな物語です。
※文体は硬派、修飾が多いです。
物語自体はRPGのような世界観・設定で作られています。
※第1部全3章までを順次公開しています。
※第2部は2019年5月現在、第1章第4話以降を執筆中です。

終焉の謳い手~破壊の騎士と旋律の戦姫~
柚月 ひなた
ファンタジー
理想郷≪アルカディア≫と名付けられた世界。
世界は紛争や魔獣の出現など、多くの問題を抱え混沌としていた。
そんな世界で、破壊の力を宿す騎士ルーカスは、旋律の戦姫イリアと出会う。
彼女は歌で魔術の奇跡を体現する詠唱士≪コラール≫。過去にルーカスを絶望から救った恩人だ。
だが、再会したイリアは記憶喪失でルーカスを覚えていなかった。
原因は呪詛。記憶がない不安と呪詛に苦しむ彼女にルーカスは「この名に懸けて誓おう。君を助け、君の力になると——」と、騎士の誓いを贈り奮い立つ。
かくして、ルーカスとイリアは仲間達と共に様々な問題と陰謀に立ち向かって行くが、やがて逃れ得ぬ宿命を知り、選択を迫られる。
何を救う為、何を犠牲にするのか——。
これは剣と魔法、歌と愛で紡ぐ、終焉と救済の物語。
ダークでスイートなバトルロマンスファンタジー、開幕。

僕の兄上マジチート ~いや、お前のが凄いよ~
SHIN
ファンタジー
それは、ある少年の物語。
ある日、前世の記憶を取り戻した少年が大切な人と再会したり周りのチートぷりに感嘆したりするけど、実は少年の方が凄かった話し。
『僕の兄上はチート過ぎて人なのに魔王です。』
『そういうお前は、愛され過ぎてチートだよな。』
そんな感じ。
『悪役令嬢はもらい受けます』の彼らが織り成すファンタジー作品です。良かったら見ていってね。
隔週日曜日に更新予定。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















