33 / 36
第32章 金色の悪意(前段)
しおりを挟む
伊川栄信が、阿部備中守の動向について栄に問い質すため、素川と息子の晴川養信に席を外すように求めた。
「お栄、一人で大丈夫か」と不安顔で問う素川に、栄は落ち着いて、「はい」と答えた。
むしろ、望むところである。
栄は、融川門下の弟子の一人に過ぎない。法眼の官位を持つ奥絵師にして御用絵師筆頭・伊川栄信と一対一で向き合える機会など、こちらから作ろうと思っても作れるものではない。
江戸の絵師の世界では、伊川の評判は至極よい。
絵画の腕だけでなく、人柄についても評価が高い。身分の低い弟子や町絵師などにも気さくに声をかける。仕事や報酬の配分も公平で、画壇の総帥に相応しい器量人だと言われている。
しかし、今の伊川には、器量人の雰囲気は微塵もない。先程までとは全く異なる顔をしている。能面のような無表情に、底なしの井戸のような暗い目で、こちらの様子をじっと窺っている。
まるで、蛇のようだ。これが、これがこの人の本性か。栄は、慄然たる思いがした。
「それで、そなた、何をどこまで知っているのだ?」
「それを伺いたいのは、こちらでございます」
「何だと?」
大柄な晴川養信が目の前から消えたので、栄の位置から、床の間の掛け軸がよく見えるようになった。
双幅の「日月瀑布図」だ。右は、しぶきを上げて岩場に落ちる滝の水と大きな旭日。左には、同じ構図で、滝と三日月が描かれている。署名が見えた。どちらにも、「伊川法眼筆」とある。
栄は、ふつふつと怒りが込み上げて来るのを感じた。
見事に金泥と金砂子が用いられているではないか。朝日と月光に照らし出される水しぶきに金砂子を散らし、幻想的な景色を表現している。そして、滝と岩場の立体感を出す技法も巧みだ。
美しい。やはり、この技法の第一人者はこの人なんだ。
「なぜでしょうか」
「なに?」
「なぜ、伊川様は、備中守様に金泥金砂子の使い方について、あの様なことをおっしゃったのでしょうか」
「何のことだ?」
「おとぼけ召さるな!」
栄は、前方の双幅の掛け軸を指さした。
「この見事な技法の、どこが公方様の御用に不適切だというのでしょうか」
「不適切だ」
「馬鹿な。ご自身これだけのものを描けるのです。融川先生が描いた近江八勝図が如何に優れているか。ご承知のはずです」
伊川は、ちらりと後方に目をやった。
「これは試作の試作という段階だ。わしはまだ、この技法を、大きな画面、あの近江八勝のような大画面で試したことはない」
「しかし、伊川様は、備中守様と違い、融川先生の伺下絵もご覧になっています。さらに、屏風として仕上げる前、融川先生が描き上げた十二枚を並べて確認されたではありませんか」
「そなた、わしが浜町に行ったとき、あの場にいたのか」
「いえ。女子の身ゆえ、遠慮いたしました。されど翌日、融川先生から、伊川様からお褒めの言葉をいただいたと伺いました。あの屏風を描くにあたり、先生の助手として、金泥と金砂子の準備をしたのは、このわたくしでございますから、大層嬉しゅうございました」
「そうであったか」
「伊川様は、この金の使い方が、大きな画面でも映えること、十分お分かりだったはず。それなのに、なぜ?」
「新しい技法は、御用絵師筆頭であるわしが、まずは用いるべきなのだ」
「それを融川先生が先んじてやってしまった。だから、ですか。だから不適切であると。そんな理不尽な!」
確かに、これまで伊川が金泥金砂子の新技法を用いたのは、小さな画面の掛け軸などばかりだ。近景と遠景を描き分けるため、金泥の塗りや金砂子の散らし方に濃淡をつけると、全面を金で塗り潰す従来の表現に慣れている者が見れば、所々物足りないと思うかもしれない。
実際、阿部備中守がそうだ。事前に伊川から話を聞き、新しい技法に対する拒否感を強めていたにせよ、彼自身がそう感じたから、専門家である絵師を相手に文句をつけたのだ。
「わしは御用絵師筆頭、画壇の覇者たる狩野派の総帥だ。決して失敗できない。わしの失敗は、狩野派全体の失敗となるからだ」
「見事な責任感ですこと。いえ、違います。それは単なる言い訳。あなたは、あなたには、勇気がなかっただけです」
しかも、融川が描いた「近江八勝図」は水墨画だ。白い画面に墨一色で描く。極彩色の花鳥図などと異なり、清潔感や格調の高さを強く求められる種類の画である。
そこに金を用いる。
これにはさらなる勇気が必要だ。屏風という大きな画面である。足りなければ効果が伝わらない。しかし、やり過ぎれば、致命的に野暮ったくなってしまう。それを、融川は見事に仕上げた。
伊川は驚愕したに違いない。新技法の第一人者であるはずの自分が、一気に後塵を拝することになる。ここ三代、木挽町家の当主が御用絵師筆頭を務めているが、何か決まりがあるわけではない。奥絵師四家の地位は本来対等であり、筆頭は、その時の当主たちの歳周りと技量で決まる。融川と伊川は歳が近い。技量で負ければ、筆頭の交代も十分あり得る。
「いえ、勇気がなかっただけじゃない。あなたは絵師でありながら、融川先生の屏風の素晴らしさを分かっていながら、保身のために姑息な動きを。絵師の総帥が聞いて呆れるわ。あなたはただの卑怯者です!」
その時、栄は、はたと思った。
融川は、口論の相手である阿部備中守に対し、「良工の手段、俗目の知るところにあらず」と言い放ったというが、あれはもしや、伊川栄信に向けた一言ではなかったか。
融川は、仲裁に入ってきた伊川の様子から、伊川の背信に気付いたのではないか。伊川の卑怯な心底を見抜いたのではないか。
だとしたら・・・。
栄は、体中の血が沸騰する感覚に襲われ、勢いよく立ち上がった。乱暴に歩を進め、伊川の横を抜け、床の間の双幅の掛け軸の前に立った。
まず、右側の滝と旭日が描かれた中ほどに手を掛け、思い切り、引き下ろした。次いで、左も。そして、二幅の掛け軸をまとめて一気に真横に引き裂いた。
絹本でなく紙本の作品だ。女性の力でも容易に破ける。案の定、バリバリと音を立て、真っ二つに裂けた。その裂け目から、金泥に使われた金と白い胡粉が、粉となって、ふわっと空中に舞った。
栄は背後に目をやり、伊川栄信の様子を確認した。悔しいかな、微動だにしていない。
何をやってるの? 最低最悪の所業だ。仮にも絵師が、どんな理由があるにしろ、画を引き裂くなんて。こんなこと、こんなこと・・・。
涙がこぼれそうだ。しかし、必死に耐える。そして、黙ったまま座に戻り、伊川の顔を睨み付けた。
「気は済んだかな」と、冷たい目で静かに尋ねられた。
「済むわけがありません!」
「わしも、まさか融川殿が腹を切るとは思わなんだ。薬が効き過ぎた。思えば、あの腕は惜しい。狩野派にとって大変な損失だ」
「何を今更!」
「では、頭を下げて謝ればよいのか。泣きながら悔いて見せればよいか。そんなことは意味がない。今更感傷に浸っても仕方ない。お前はそれを知っている。だから、備中守様とも話を付けたのであろう?」
「そ、それは」
「お前は、わしを何かおぞましい物でも見るような目で見ているが、わしには分かる。お前もこちら側の人間なのだ」
「そ、そんなことは・・・」
「ふん、まあいい。わしも備中守様同様、事を荒立てたくない。要求があれば聞こう」
奥絵師、しかも御用絵師筆頭ともなれば、ただの絵師ではない。幕府の行政官であり政治家でもある。誇りより利害、意地よりも損得か。あっさり折れた伊川に、怒りがさらに増す。
栄は、昨日の昼過ぎまで、ただただ、己の画技を高めることしか考えていなかった。取引、駆け引き、そんなこと、考えもしなかった。
自分も同じ? そんなことはない、断じて。しかし、明日からもこれまでと同じ純粋な気持ちで絵筆を握れるだろうか。同じ目で物が見えるだろうか。
伊川に対する怒りと自分自身に対する不安。彼女は今、収拾のつかない感情に支配されつつあった。
「お栄、一人で大丈夫か」と不安顔で問う素川に、栄は落ち着いて、「はい」と答えた。
むしろ、望むところである。
栄は、融川門下の弟子の一人に過ぎない。法眼の官位を持つ奥絵師にして御用絵師筆頭・伊川栄信と一対一で向き合える機会など、こちらから作ろうと思っても作れるものではない。
江戸の絵師の世界では、伊川の評判は至極よい。
絵画の腕だけでなく、人柄についても評価が高い。身分の低い弟子や町絵師などにも気さくに声をかける。仕事や報酬の配分も公平で、画壇の総帥に相応しい器量人だと言われている。
しかし、今の伊川には、器量人の雰囲気は微塵もない。先程までとは全く異なる顔をしている。能面のような無表情に、底なしの井戸のような暗い目で、こちらの様子をじっと窺っている。
まるで、蛇のようだ。これが、これがこの人の本性か。栄は、慄然たる思いがした。
「それで、そなた、何をどこまで知っているのだ?」
「それを伺いたいのは、こちらでございます」
「何だと?」
大柄な晴川養信が目の前から消えたので、栄の位置から、床の間の掛け軸がよく見えるようになった。
双幅の「日月瀑布図」だ。右は、しぶきを上げて岩場に落ちる滝の水と大きな旭日。左には、同じ構図で、滝と三日月が描かれている。署名が見えた。どちらにも、「伊川法眼筆」とある。
栄は、ふつふつと怒りが込み上げて来るのを感じた。
見事に金泥と金砂子が用いられているではないか。朝日と月光に照らし出される水しぶきに金砂子を散らし、幻想的な景色を表現している。そして、滝と岩場の立体感を出す技法も巧みだ。
美しい。やはり、この技法の第一人者はこの人なんだ。
「なぜでしょうか」
「なに?」
「なぜ、伊川様は、備中守様に金泥金砂子の使い方について、あの様なことをおっしゃったのでしょうか」
「何のことだ?」
「おとぼけ召さるな!」
栄は、前方の双幅の掛け軸を指さした。
「この見事な技法の、どこが公方様の御用に不適切だというのでしょうか」
「不適切だ」
「馬鹿な。ご自身これだけのものを描けるのです。融川先生が描いた近江八勝図が如何に優れているか。ご承知のはずです」
伊川は、ちらりと後方に目をやった。
「これは試作の試作という段階だ。わしはまだ、この技法を、大きな画面、あの近江八勝のような大画面で試したことはない」
「しかし、伊川様は、備中守様と違い、融川先生の伺下絵もご覧になっています。さらに、屏風として仕上げる前、融川先生が描き上げた十二枚を並べて確認されたではありませんか」
「そなた、わしが浜町に行ったとき、あの場にいたのか」
「いえ。女子の身ゆえ、遠慮いたしました。されど翌日、融川先生から、伊川様からお褒めの言葉をいただいたと伺いました。あの屏風を描くにあたり、先生の助手として、金泥と金砂子の準備をしたのは、このわたくしでございますから、大層嬉しゅうございました」
「そうであったか」
「伊川様は、この金の使い方が、大きな画面でも映えること、十分お分かりだったはず。それなのに、なぜ?」
「新しい技法は、御用絵師筆頭であるわしが、まずは用いるべきなのだ」
「それを融川先生が先んじてやってしまった。だから、ですか。だから不適切であると。そんな理不尽な!」
確かに、これまで伊川が金泥金砂子の新技法を用いたのは、小さな画面の掛け軸などばかりだ。近景と遠景を描き分けるため、金泥の塗りや金砂子の散らし方に濃淡をつけると、全面を金で塗り潰す従来の表現に慣れている者が見れば、所々物足りないと思うかもしれない。
実際、阿部備中守がそうだ。事前に伊川から話を聞き、新しい技法に対する拒否感を強めていたにせよ、彼自身がそう感じたから、専門家である絵師を相手に文句をつけたのだ。
「わしは御用絵師筆頭、画壇の覇者たる狩野派の総帥だ。決して失敗できない。わしの失敗は、狩野派全体の失敗となるからだ」
「見事な責任感ですこと。いえ、違います。それは単なる言い訳。あなたは、あなたには、勇気がなかっただけです」
しかも、融川が描いた「近江八勝図」は水墨画だ。白い画面に墨一色で描く。極彩色の花鳥図などと異なり、清潔感や格調の高さを強く求められる種類の画である。
そこに金を用いる。
これにはさらなる勇気が必要だ。屏風という大きな画面である。足りなければ効果が伝わらない。しかし、やり過ぎれば、致命的に野暮ったくなってしまう。それを、融川は見事に仕上げた。
伊川は驚愕したに違いない。新技法の第一人者であるはずの自分が、一気に後塵を拝することになる。ここ三代、木挽町家の当主が御用絵師筆頭を務めているが、何か決まりがあるわけではない。奥絵師四家の地位は本来対等であり、筆頭は、その時の当主たちの歳周りと技量で決まる。融川と伊川は歳が近い。技量で負ければ、筆頭の交代も十分あり得る。
「いえ、勇気がなかっただけじゃない。あなたは絵師でありながら、融川先生の屏風の素晴らしさを分かっていながら、保身のために姑息な動きを。絵師の総帥が聞いて呆れるわ。あなたはただの卑怯者です!」
その時、栄は、はたと思った。
融川は、口論の相手である阿部備中守に対し、「良工の手段、俗目の知るところにあらず」と言い放ったというが、あれはもしや、伊川栄信に向けた一言ではなかったか。
融川は、仲裁に入ってきた伊川の様子から、伊川の背信に気付いたのではないか。伊川の卑怯な心底を見抜いたのではないか。
だとしたら・・・。
栄は、体中の血が沸騰する感覚に襲われ、勢いよく立ち上がった。乱暴に歩を進め、伊川の横を抜け、床の間の双幅の掛け軸の前に立った。
まず、右側の滝と旭日が描かれた中ほどに手を掛け、思い切り、引き下ろした。次いで、左も。そして、二幅の掛け軸をまとめて一気に真横に引き裂いた。
絹本でなく紙本の作品だ。女性の力でも容易に破ける。案の定、バリバリと音を立て、真っ二つに裂けた。その裂け目から、金泥に使われた金と白い胡粉が、粉となって、ふわっと空中に舞った。
栄は背後に目をやり、伊川栄信の様子を確認した。悔しいかな、微動だにしていない。
何をやってるの? 最低最悪の所業だ。仮にも絵師が、どんな理由があるにしろ、画を引き裂くなんて。こんなこと、こんなこと・・・。
涙がこぼれそうだ。しかし、必死に耐える。そして、黙ったまま座に戻り、伊川の顔を睨み付けた。
「気は済んだかな」と、冷たい目で静かに尋ねられた。
「済むわけがありません!」
「わしも、まさか融川殿が腹を切るとは思わなんだ。薬が効き過ぎた。思えば、あの腕は惜しい。狩野派にとって大変な損失だ」
「何を今更!」
「では、頭を下げて謝ればよいのか。泣きながら悔いて見せればよいか。そんなことは意味がない。今更感傷に浸っても仕方ない。お前はそれを知っている。だから、備中守様とも話を付けたのであろう?」
「そ、それは」
「お前は、わしを何かおぞましい物でも見るような目で見ているが、わしには分かる。お前もこちら側の人間なのだ」
「そ、そんなことは・・・」
「ふん、まあいい。わしも備中守様同様、事を荒立てたくない。要求があれば聞こう」
奥絵師、しかも御用絵師筆頭ともなれば、ただの絵師ではない。幕府の行政官であり政治家でもある。誇りより利害、意地よりも損得か。あっさり折れた伊川に、怒りがさらに増す。
栄は、昨日の昼過ぎまで、ただただ、己の画技を高めることしか考えていなかった。取引、駆け引き、そんなこと、考えもしなかった。
自分も同じ? そんなことはない、断じて。しかし、明日からもこれまでと同じ純粋な気持ちで絵筆を握れるだろうか。同じ目で物が見えるだろうか。
伊川に対する怒りと自分自身に対する不安。彼女は今、収拾のつかない感情に支配されつつあった。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

狩野岑信 元禄二刀流絵巻
仁獅寺永雪
歴史・時代
狩野岑信は、江戸中期の幕府御用絵師である。竹川町狩野家の次男に生まれながら、特に分家を許された上、父や兄を差し置いて江戸画壇の頂点となる狩野派総上席の地位を与えられた。さらに、狩野派最初の奥絵師ともなった。
特筆すべき代表作もないことから、従来、時の将軍に気に入られて出世しただけの男と見られてきた。
しかし、彼は、主君が将軍になったその年に死んでいるのである。これはどういうことなのか。
彼の特異な点は、「松本友盛」という主君から賜った別名(むしろ本名)があったことだ。この名前で、土圭之間詰め番士という武官職をも務めていた。
舞台は、赤穂事件のあった元禄時代、生類憐れみの令に支配された江戸の町。主人公は、様々な歴史上の事件や人物とも関りながら成長して行く。
これは、絵師と武士、二つの名前と二つの役職を持ち、張り巡らされた陰謀から主君を守り、遂に六代将軍に押し上げた謎の男・狩野岑信の一生を読み解く物語である。
投稿二作目、最後までお楽しみいただければ幸いです。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)
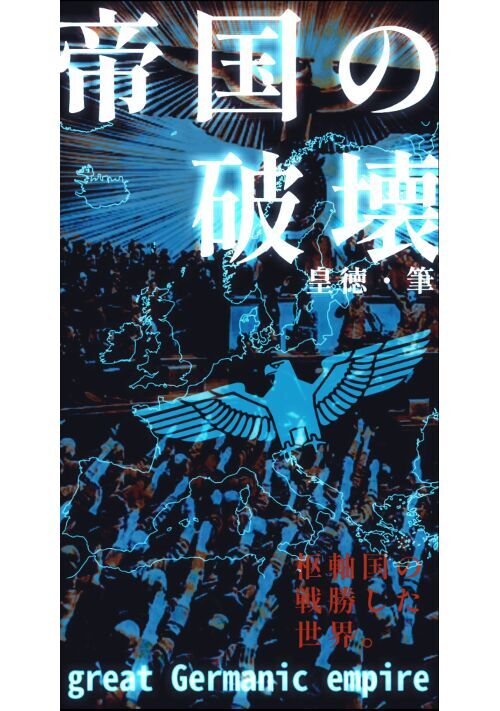
『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−
皇徳❀twitter
歴史・時代
この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。
二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う
ピコサイクス
歴史・時代
1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

枢軸国
よもぎもちぱん
歴史・時代
時は1919年
第一次世界大戦の敗戦によりドイツ帝国は滅亡した。皇帝陛下 ヴィルヘルム二世の退位により、ドイツは共和制へと移行する。ヴェルサイユ条約により1320億金マルク 日本円で200兆円もの賠償金を課される。これに激怒したのは偉大なる我らが総統閣下"アドルフ ヒトラー"である。結果的に敗戦こそしたものの彼の及ぼした影響は非常に大きかった。
主人公はソフィア シュナイダー
彼女もまた、ドイツに転生してきた人物である。前世である2010年頃の記憶を全て保持しており、映像を写真として記憶することが出来る。
生き残る為に、彼女は持てる知識を総動員して戦う
偉大なる第三帝国に栄光あれ!
Sieg Heil(勝利万歳!)

剣客逓信 ―明治剣戟郵便録―
三條すずしろ
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞:痛快! エンタメ剣客賞受賞】
明治6年、警察より早くピストルを装備したのは郵便配達員だった――。
維新の動乱で届くことのなかった手紙や小包。そんな残された思いを配達する「御留郵便御用」の若者と老剣士が、時に不穏な明治の初めをひた走る。
密書や金品を狙う賊を退け大切なものを届ける特命郵便配達人、通称「剣客逓信(けんかくていしん)」。
武装する必要があるほど危険にさらされた初期の郵便時代、二人はやがてさらに大きな動乱に巻き込まれ――。
※エブリスタでも連載中

日本には1942年当時世界最強の機動部隊があった!
明日ハレル
歴史・時代
第2次世界大戦に突入した日本帝国に生き残る道はあったのか?模索して行きたいと思います。
当時6隻の空母を集中使用した南雲機動部隊は航空機300余機を持つ世界最強の戦力でした。
ただ彼らにもレーダーを持たない、空母の直掩機との無線連絡が出来ない、ダメージコントロールが未熟である。制空権の確保という理論が判っていない、空母戦術への理解が無い等多くの問題があります。
空母が誕生して戦術的な物を求めても無理があるでしょう。ただどの様に強力な攻撃部隊を持っていても敵地上空での制空権が確保できなけれな、簡単に言えば攻撃隊を守れなけれな無駄だと言う事です。
空母部隊が対峙した場合敵側の直掩機を強力な戦闘機部隊を攻撃の前の送って一掃する手もあります。
日本のゼロ戦は優秀ですが、悪迄軽戦闘機であり大馬力のPー47やF4U等が出てくれば苦戦は免れません。
この為旧式ですが96式陸攻で使われた金星エンジンをチューンナップし、金星3型エンジン1350馬力に再生させこれを積んだ戦闘機、爆撃機、攻撃機、偵察機を陸海軍共通で戦う。
共通と言う所が大事で国力の小さい日本には試作機も絞って開発すべきで、陸海軍別々に開発する余裕は無いのです。
その他数多くの改良点はありますが、本文で少しづつ紹介して行きましょう。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















