116 / 206
外伝 思緋の色
第三幕 真実
しおりを挟む
その日、その人物とであったのは本当の偶然の産物だった。武はバイトの帰りにこれから向かう先にこの間のお詫びと称して何か手土産にでもするかと洋菓子店に向かったのだが、その店先でばったりと思わぬ顔に出くわしたのだ。
お互いに顔は知っているが、一度も直に言葉を交わしたことのない相手。それがもし遠めに見ただけならきっと素知らぬふりも出来たのだろうが、その接近は気がついた時にはお互いに顔をつき合わせた状況になってしまっていた。武は戸惑うようなその人物の表情をまじまじと見つめながら、考えてみれば生活圏は同じなんだから会う可能性もあるのかと変な納得すら覚える。
「……ちわ。」
「こ…こんにちは。」
お互いに奇妙な雰囲気の上何をどう話していいかもわからない状況で奇妙な挨拶を交わす。片や二十五歳のフリーターの今時の青年、片や四十歳は越しているだろう折り目のついたようなきちんとした身支度をした人物の不思議な組み合わせは誠にもって奇妙な取り合わせではある。だが、お互いに何か聞きたいことがあるとでも言いたい風な様子で、どちらが言うでもなくその場の雰囲気で何故か喫茶店に入ることになってしまった。真見塚成孝と名乗ったかの道場主は、いまだ微かな戸惑うような表情を浮かべながらも武をその性格を表すかのように真っ直ぐに見つめ返す。
「…澪さんは……お元気ですか?」
思っていたよりも穏やかで柔らかく響くような声音は音とこの武が言うのもなんだが耳に心地いい声音だと思う。そう思うと、何だか自分のほうが悪者のような立場にある気すら感じつつ武は「ええ、まァ」とだけ答え目の前のアイスコーヒーを啜った。信哉を迎えに行く時と同じ戸惑うような、それでいてどこか憂いを感じさせる物悲しさを持った表情を見つめる。彼の視線の持つ意味に気がついてもうだいぶ時が経っている事に気がついた途端、思わず何時もの悪い癖が出てしまった。
「どうして、彼女を一人にしたんですか。」
鋭い確信をつく問いにその道場主の表情が、打ちのめされたかのように影をさしたのに気がついて武は微かな後悔を感じた。
自分が立ち入っていい話ではないのに、思わず感情が先に口をついてしまう。感情が顔に出やすいよりももっと悪い癖だと知りつつも、その質問の答えを待つ自分がいるのも確かだった。
「……私は……。」
戸惑うように、それでいて遥か昔を思うように相手は目を伏せる。何をどう表現したらいいのか分からないというかのような感情を溢れさせるその姿を武は、無言のままじっと見つめながら、心の中では目の前の男の事を今も想っているのだろうあの美しい人のことをふと思い起こしていた。その言葉に滲んだ淡い微かな想いを噛み締めるかのような萌黄にも似た色の気配を浮かばせて真見塚成孝は目を伏せたまま静かに口を開いた。
穏やかで静かな声音は、涼やかな彼女の声とは全く対照的にすら感じるものなのだ。なのに何処か心に響く様な彼女と同じ感覚を感じさせるのは、その言葉にきっと嘘がないからなのかもしれないと目の前の男性を見つめながら武は思う。
「私は…一緒にいたいと思っていました…。でも彼女は…。」
ふとその瞳が過去を思うように緩み、苦い思いをうつすかのようにほろ苦い笑みが顔に浮かぶ。自分よりずっと大人のその男性が何を思うのかは想像もできないが、その過去がまるで今も目の前にあるかのように彼は穏やかに目を細める。
「彼女は、とても鮮やかに…私が止めるまもなく私の前から飛び立ってしまった。」
心地いいはずの喫茶店の冷房がまるで氷のように肌に障るような気がして、微かに武の感情がざわめく。やはり聞かなければよかったと心の中で、自分が小さく呟くのを感じながら武'はそれでも目の前の男性から目を離せずにいた。その言葉だけで、過去に彼女と彼が一緒に過ごした時が確かにあったことが分かる。そしてそれを振り切ったのが、ほかならぬ彼女自身だったことすらも。
「理由は分かりません。私は彼女を守りたかった……、でも彼女はもしかしたら。」
言葉の先を紡ごうとするその姿のふと思いがけず信哉の面差しを見つけて、ふいに自分の気持ちのやり場のないことに気がついた。純粋で白い花のような人はまだ目の前のこの人物を想っている。そして、彼には分からなくても武には理解できる事がある。
異能のせいなんだな?…お前がこいつと別れたのは……澪。
「……もしかしたら彼女は私を守ろうとしたのかもしれないと想う事があります……理由はありませんが。」
思考と言葉が重なり、武は押し黙った。
彼女がまだこの人物を思うように、彼もまだ何処かに彼女を思う気持ちを残している。それに二人には信哉というつながりがあるのだ。
……俺のこの気持ちは何処にもやりようがない……。
ふっと心の中でそう呟きながら、分かりましたとだけ言うのが精一杯でその後は言葉も少なく、相手がまだ何か聞きたそうににしているのは分かっていたが早々にその場を辞した。
気持ちのどこかをくじかれてしまったような思いを抱きながら、ふと茜色の空を見上げながら歩く。高校の時にしたような淡い恋心とは違う、今の自分のこの気持ちをどう表現していいのか分からないままボンヤリと見上げる茜の空には、まるでそこに高潔な気高い孤高の気配を持った彼女のような真っ白の月が浮かんでいる。
目に見えるのに手の届かないその月を見上げながら、それでも約束だけは守ろうと呟く自分の心の囁きを武は、まるで他人の囁きの様に心の何処かで聞いていた。結局その後自分にできることは、ただ信哉との約束を守る事だけだと武は思った。
※※※
そうして、自分の気持ちは押し込めたまま時が流れ信哉が、十二の誕生日を越したという時、ほんの道場に久々に足を向けた気まぐれが嫌な偶然と重なってしまうことになったのだ。
「ほら鳥飼ってさ、真見塚先生の隠し子らしいって噂だし。」
その言葉を耳にした瞬間自分が凍りついたのが分かった。
道場からこぼれ出てきた信哉より少し年嵩に見える少年達が言った言葉の背後に、急に背が伸びて小六にして母親を追い越そうという勢いの姿が立ち尽くしているのが見える。
既に、道場では師範である真見塚成孝しか相手ができないほどの技を持つようになってしまったその姿は、彼自身の母にもよく似ていたが、今はその彼は知らないはずの実父である者の面差しも同時に色濃く見える。そして、巡り合わせの悪い事に真見塚成孝の本妻が男児を産んだという話も耳にしたばかりでもあった。その言葉は、子供特有の嫉妬の気持ちも過分にあったのだろう。だが当の彼を傷つけ、疑惑を核心に変えるには十分すぎるほどの下地がありすぎる。
震える視線が、武に気がついて戸惑う様子はどう見ても彼の父親にそっくりとしか言いようがないことに気がついて武は胸が締め付けられるような思いがした。
武が気がついたのは今だとしても、恐らくだいぶ前から師範に特別に眼をかけられる彼にはこんな陰口が聞こえよがしに放たれていたのかもしれない。
彼は微かに弱い微笑を浮かべて武を見てから、丁寧に礼儀作法を守った挨拶を道場主にすると伸び始めたしなやかな四肢を母親によく似た優美にも見える独特の動作で翻し着替えに向かう。その姿を見送る視線に思わず剣呑とした視線を投げた武の様子に気がついた道場主が戸惑うような憂いの表情を浮かべたのに気がついた。
助ければ、噂を肯定するだけ、かよ……だからって見ぬふりか?俺は…。
そんなのは嫌だと本当に小さな呟きが武のその口から零れ落ちる。
「武兄…迎えに来てくれたんだ?珍しいね。」
何事もなかったかのような口調でそう言いながら、まだ子供の瞳は見られたくなかった動揺の色を残している。それが武にははっきりと分かって、思わず普段の彼らしくない酷く鋭いさすような視線が、靴を履くために信哉が屈みこんだ一瞬に周囲に向かって投げつけられる。それは傍目に見ても余りにも鋭く殺意にすら思える視線で、その視線の鋭さに怯えるように陰口を言っていた子供達が口をつぐみ蜘蛛の子を散らすように散っていく。勿論その視線は最後に道場主に向かって投げつけられ、その紅蓮の炎のようにも感じられる視線を相手は静かに、まるで贖罪でうける者のように真正面から受け止めた。理屈は理解できても感情はそうは行かない自分は、まだ大人になりきれていないだけなのだろうかと武は怒りの滲む視線の影で思う。彼は、暫しの後にふとその視線を塗り替えるように穏やかに信哉を見やりグシャグシャと手荒く頭を撫でる。
「何だよ。たまには来たっていだろうが。」
彼には全く直前の視線すら垣間見せず何時もの口調で話しかける武の姿に、頭を久々に撫でられるという行為に微かに不満そうにしながらも信哉が微かな安堵の表情を浮かべたのを見てとった。その視線の意味する事に彼は再び胸が痛くなる気がした。何処かで気がついていて、でも認めたくない現実を知っている瞳。そして、それすらも誰にも気づかれたくないという感情を秘めた瞳がそこにはある。思わず昔のように手を引いて歩きながら何も見なかったふりをする自分は酷く気分の悪いものだったが、今は信哉がそう望んでいるような気もした。
「せっかく給料入ったから何か食わせてやろうと思ったんだけどなァ、最近可愛げがないぞ、信哉。」
「えー、何だよ、それ。武兄が来て嬉しいって。」
少し声変わりしかけた声を聞きながら武は、その手を握ったまま歩く。最近は子供じゃないと嫌がるはずの信哉が大人しくそのまま手を引かれているのは、現実を知りつつある自分が心細いのだとも思う。
生きているといわれていた父が、直ぐ傍の知っている人だったらどうしたいだろうか。
振り返る事もしないまま他愛のない会話を続けながら、そんな考えをした瞬間武の手が不意に強く握り返されて思わず、彼は振り返りその手の主を見つめる。まだ幼さの残る二つの面影を宿した少年は、その母によく似た白い花のような微笑みで、振り返った彼を無言のまま見返すと、何か思いを振り切るようにその手を今度は逆に引き始めた。
「僕、甘いものがいいよ、武兄。」
その嘘のつけない不器用な少年の勤めて明るく放たれた声に、武はただ穏やかに微笑み返し今は彼が一番不得手な感情を押し殺すという行為に必死になる自分を感じる。それでも、そのまだ自分より小さな手を大事なもののようにそっと握り返し武は少年の姿を見つめていた。
お互いに顔は知っているが、一度も直に言葉を交わしたことのない相手。それがもし遠めに見ただけならきっと素知らぬふりも出来たのだろうが、その接近は気がついた時にはお互いに顔をつき合わせた状況になってしまっていた。武は戸惑うようなその人物の表情をまじまじと見つめながら、考えてみれば生活圏は同じなんだから会う可能性もあるのかと変な納得すら覚える。
「……ちわ。」
「こ…こんにちは。」
お互いに奇妙な雰囲気の上何をどう話していいかもわからない状況で奇妙な挨拶を交わす。片や二十五歳のフリーターの今時の青年、片や四十歳は越しているだろう折り目のついたようなきちんとした身支度をした人物の不思議な組み合わせは誠にもって奇妙な取り合わせではある。だが、お互いに何か聞きたいことがあるとでも言いたい風な様子で、どちらが言うでもなくその場の雰囲気で何故か喫茶店に入ることになってしまった。真見塚成孝と名乗ったかの道場主は、いまだ微かな戸惑うような表情を浮かべながらも武をその性格を表すかのように真っ直ぐに見つめ返す。
「…澪さんは……お元気ですか?」
思っていたよりも穏やかで柔らかく響くような声音は音とこの武が言うのもなんだが耳に心地いい声音だと思う。そう思うと、何だか自分のほうが悪者のような立場にある気すら感じつつ武は「ええ、まァ」とだけ答え目の前のアイスコーヒーを啜った。信哉を迎えに行く時と同じ戸惑うような、それでいてどこか憂いを感じさせる物悲しさを持った表情を見つめる。彼の視線の持つ意味に気がついてもうだいぶ時が経っている事に気がついた途端、思わず何時もの悪い癖が出てしまった。
「どうして、彼女を一人にしたんですか。」
鋭い確信をつく問いにその道場主の表情が、打ちのめされたかのように影をさしたのに気がついて武は微かな後悔を感じた。
自分が立ち入っていい話ではないのに、思わず感情が先に口をついてしまう。感情が顔に出やすいよりももっと悪い癖だと知りつつも、その質問の答えを待つ自分がいるのも確かだった。
「……私は……。」
戸惑うように、それでいて遥か昔を思うように相手は目を伏せる。何をどう表現したらいいのか分からないというかのような感情を溢れさせるその姿を武は、無言のままじっと見つめながら、心の中では目の前の男の事を今も想っているのだろうあの美しい人のことをふと思い起こしていた。その言葉に滲んだ淡い微かな想いを噛み締めるかのような萌黄にも似た色の気配を浮かばせて真見塚成孝は目を伏せたまま静かに口を開いた。
穏やかで静かな声音は、涼やかな彼女の声とは全く対照的にすら感じるものなのだ。なのに何処か心に響く様な彼女と同じ感覚を感じさせるのは、その言葉にきっと嘘がないからなのかもしれないと目の前の男性を見つめながら武は思う。
「私は…一緒にいたいと思っていました…。でも彼女は…。」
ふとその瞳が過去を思うように緩み、苦い思いをうつすかのようにほろ苦い笑みが顔に浮かぶ。自分よりずっと大人のその男性が何を思うのかは想像もできないが、その過去がまるで今も目の前にあるかのように彼は穏やかに目を細める。
「彼女は、とても鮮やかに…私が止めるまもなく私の前から飛び立ってしまった。」
心地いいはずの喫茶店の冷房がまるで氷のように肌に障るような気がして、微かに武の感情がざわめく。やはり聞かなければよかったと心の中で、自分が小さく呟くのを感じながら武'はそれでも目の前の男性から目を離せずにいた。その言葉だけで、過去に彼女と彼が一緒に過ごした時が確かにあったことが分かる。そしてそれを振り切ったのが、ほかならぬ彼女自身だったことすらも。
「理由は分かりません。私は彼女を守りたかった……、でも彼女はもしかしたら。」
言葉の先を紡ごうとするその姿のふと思いがけず信哉の面差しを見つけて、ふいに自分の気持ちのやり場のないことに気がついた。純粋で白い花のような人はまだ目の前のこの人物を想っている。そして、彼には分からなくても武には理解できる事がある。
異能のせいなんだな?…お前がこいつと別れたのは……澪。
「……もしかしたら彼女は私を守ろうとしたのかもしれないと想う事があります……理由はありませんが。」
思考と言葉が重なり、武は押し黙った。
彼女がまだこの人物を思うように、彼もまだ何処かに彼女を思う気持ちを残している。それに二人には信哉というつながりがあるのだ。
……俺のこの気持ちは何処にもやりようがない……。
ふっと心の中でそう呟きながら、分かりましたとだけ言うのが精一杯でその後は言葉も少なく、相手がまだ何か聞きたそうににしているのは分かっていたが早々にその場を辞した。
気持ちのどこかをくじかれてしまったような思いを抱きながら、ふと茜色の空を見上げながら歩く。高校の時にしたような淡い恋心とは違う、今の自分のこの気持ちをどう表現していいのか分からないままボンヤリと見上げる茜の空には、まるでそこに高潔な気高い孤高の気配を持った彼女のような真っ白の月が浮かんでいる。
目に見えるのに手の届かないその月を見上げながら、それでも約束だけは守ろうと呟く自分の心の囁きを武は、まるで他人の囁きの様に心の何処かで聞いていた。結局その後自分にできることは、ただ信哉との約束を守る事だけだと武は思った。
※※※
そうして、自分の気持ちは押し込めたまま時が流れ信哉が、十二の誕生日を越したという時、ほんの道場に久々に足を向けた気まぐれが嫌な偶然と重なってしまうことになったのだ。
「ほら鳥飼ってさ、真見塚先生の隠し子らしいって噂だし。」
その言葉を耳にした瞬間自分が凍りついたのが分かった。
道場からこぼれ出てきた信哉より少し年嵩に見える少年達が言った言葉の背後に、急に背が伸びて小六にして母親を追い越そうという勢いの姿が立ち尽くしているのが見える。
既に、道場では師範である真見塚成孝しか相手ができないほどの技を持つようになってしまったその姿は、彼自身の母にもよく似ていたが、今はその彼は知らないはずの実父である者の面差しも同時に色濃く見える。そして、巡り合わせの悪い事に真見塚成孝の本妻が男児を産んだという話も耳にしたばかりでもあった。その言葉は、子供特有の嫉妬の気持ちも過分にあったのだろう。だが当の彼を傷つけ、疑惑を核心に変えるには十分すぎるほどの下地がありすぎる。
震える視線が、武に気がついて戸惑う様子はどう見ても彼の父親にそっくりとしか言いようがないことに気がついて武は胸が締め付けられるような思いがした。
武が気がついたのは今だとしても、恐らくだいぶ前から師範に特別に眼をかけられる彼にはこんな陰口が聞こえよがしに放たれていたのかもしれない。
彼は微かに弱い微笑を浮かべて武を見てから、丁寧に礼儀作法を守った挨拶を道場主にすると伸び始めたしなやかな四肢を母親によく似た優美にも見える独特の動作で翻し着替えに向かう。その姿を見送る視線に思わず剣呑とした視線を投げた武の様子に気がついた道場主が戸惑うような憂いの表情を浮かべたのに気がついた。
助ければ、噂を肯定するだけ、かよ……だからって見ぬふりか?俺は…。
そんなのは嫌だと本当に小さな呟きが武のその口から零れ落ちる。
「武兄…迎えに来てくれたんだ?珍しいね。」
何事もなかったかのような口調でそう言いながら、まだ子供の瞳は見られたくなかった動揺の色を残している。それが武にははっきりと分かって、思わず普段の彼らしくない酷く鋭いさすような視線が、靴を履くために信哉が屈みこんだ一瞬に周囲に向かって投げつけられる。それは傍目に見ても余りにも鋭く殺意にすら思える視線で、その視線の鋭さに怯えるように陰口を言っていた子供達が口をつぐみ蜘蛛の子を散らすように散っていく。勿論その視線は最後に道場主に向かって投げつけられ、その紅蓮の炎のようにも感じられる視線を相手は静かに、まるで贖罪でうける者のように真正面から受け止めた。理屈は理解できても感情はそうは行かない自分は、まだ大人になりきれていないだけなのだろうかと武は怒りの滲む視線の影で思う。彼は、暫しの後にふとその視線を塗り替えるように穏やかに信哉を見やりグシャグシャと手荒く頭を撫でる。
「何だよ。たまには来たっていだろうが。」
彼には全く直前の視線すら垣間見せず何時もの口調で話しかける武の姿に、頭を久々に撫でられるという行為に微かに不満そうにしながらも信哉が微かな安堵の表情を浮かべたのを見てとった。その視線の意味する事に彼は再び胸が痛くなる気がした。何処かで気がついていて、でも認めたくない現実を知っている瞳。そして、それすらも誰にも気づかれたくないという感情を秘めた瞳がそこにはある。思わず昔のように手を引いて歩きながら何も見なかったふりをする自分は酷く気分の悪いものだったが、今は信哉がそう望んでいるような気もした。
「せっかく給料入ったから何か食わせてやろうと思ったんだけどなァ、最近可愛げがないぞ、信哉。」
「えー、何だよ、それ。武兄が来て嬉しいって。」
少し声変わりしかけた声を聞きながら武は、その手を握ったまま歩く。最近は子供じゃないと嫌がるはずの信哉が大人しくそのまま手を引かれているのは、現実を知りつつある自分が心細いのだとも思う。
生きているといわれていた父が、直ぐ傍の知っている人だったらどうしたいだろうか。
振り返る事もしないまま他愛のない会話を続けながら、そんな考えをした瞬間武の手が不意に強く握り返されて思わず、彼は振り返りその手の主を見つめる。まだ幼さの残る二つの面影を宿した少年は、その母によく似た白い花のような微笑みで、振り返った彼を無言のまま見返すと、何か思いを振り切るようにその手を今度は逆に引き始めた。
「僕、甘いものがいいよ、武兄。」
その嘘のつけない不器用な少年の勤めて明るく放たれた声に、武はただ穏やかに微笑み返し今は彼が一番不得手な感情を押し殺すという行為に必死になる自分を感じる。それでも、そのまだ自分より小さな手を大事なもののようにそっと握り返し武は少年の姿を見つめていた。
0
お気に入りに追加
17
あなたにおすすめの小説

赤い部屋
山根利広
ホラー
YouTubeの動画広告の中に、「決してスキップしてはいけない」広告があるという。
真っ赤な背景に「あなたは好きですか?」と書かれたその広告をスキップすると、死ぬと言われている。
東京都内のある高校でも、「赤い部屋」の噂がひとり歩きしていた。
そんな中、2年生の天根凛花は「赤い部屋」の内容が自分のみた夢の内容そっくりであることに気づく。
が、クラスメイトの黒河内莉子は、噂話を一蹴し、誰かの作り話だと言う。
だが、「呪い」は実在した。
「赤い部屋」の手によって残酷な死に方をする犠牲者が、続々現れる。
凛花と莉子は、死の連鎖に歯止めをかけるため、「解決策」を見出そうとする。
そんな中、凛花のスマートフォンにも「あなたは好きですか?」という広告が表示されてしまう。
「赤い部屋」から逃れる方法はあるのか?
誰がこの「呪い」を生み出したのか?
そして彼らはなぜ、呪われたのか?
徐々に明かされる「赤い部屋」の真相。
その先にふたりが見たものは——。


サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
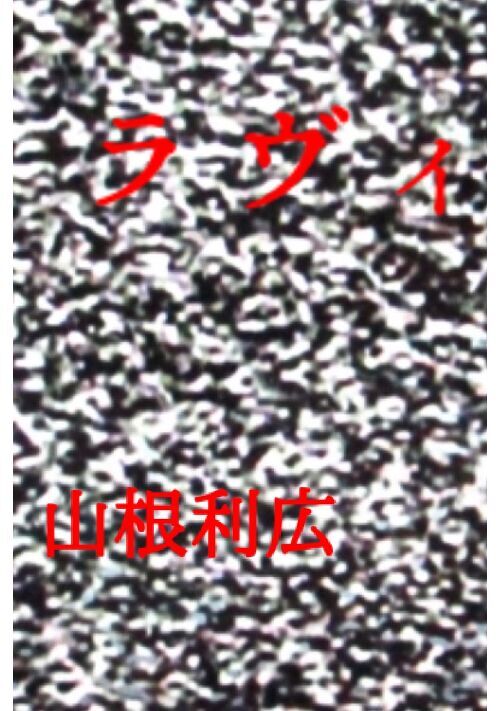
ラヴィ
山根利広
ホラー
男子高校生が不審死を遂げた。
現場から同じクラスの女子生徒のものと思しきペンが見つかる。
そして、解剖中の男子の遺体が突如消失してしまう。
捜査官の遠井マリナは、この事件の現場検証を行う中、奇妙な点に気づく。
「七年前にわたしが体験した出来事と酷似している——」
マリナは、まるで過去をなぞらえたような一連の展開に違和感を覚える。
そして、七年前同じように死んだクラスメイトの存在を思い出す。
だがそれは、連環する狂気の一端にすぎなかった……。

長期休暇で魔境制覇
篠原 皐月
ファンタジー
無事リスベラント聖騎士最高位《ディル》の一員となり、周囲の抵抗勢力を黙らせたつもりだった藍里だったが、本来求めてはいなかった地位には、もれなく義務も付いて来た。しかもそれが辺境地域の魔獣退治、身内は好き勝手し放題、反目している勢力はここぞとばかりに刺客を送り込んで来て、藍里の怒りは沸騰寸前。周囲に迷惑と困惑を振り撒きながら、藍里は取り敢えず夏休み期間中の任務達成を目指す事に。
【リスベラントへようこそ】続編。相変わらずマイペースなヒルシュ(来住)家の面々と、それに振り回される周囲の人間模様を書いていきます。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

不労の家
千年砂漠
ホラー
高校を卒業したばかりの隆志は母を急な病で亡くした数日後、訳も分からず母に連れられて夜逃げして以来八年間全く会わなかった父も亡くし、父の実家の世久家を継ぐことになった。
世久家はかなりの資産家で、古くから続く名家だったが、当主には絶対守らなければならない奇妙なしきたりがあった。
それは「一生働かないこと」。
世久の家には富をもたらす神が住んでおり、その神との約束で代々の世久家の当主は働かずに暮らしていた。
初めは戸惑っていた隆志も裕福に暮らせる楽しさを覚え、昔一年だけこの土地に住んでいたときの同級生と遊び回っていたが、やがて恐ろしい出来事が隆志の周りで起こり始める。
経済的に豊かであっても、心まで満たされるとは限らない。
望んでもいないのに生まれたときから背負わされた宿命に、流されるか。抗うか。
彼の最後の選択を見て欲しい。

都市街下奇譚
碧
ホラー
とある都市。
人の溢れる街の下で起こる不可思議で、時に忌まわしい時に幸いな出来事の数々。
多くの人間が無意識に避けて通る筈の出来事に、間違って足を踏み入れてしまった時、その人間はどうするのだろうか?
多くの人間が気がつかずに過ぎる出来事に、気がついた時人間はどうするのだろうか?それが、どうしても避けられない時何が起こったのか。
忌憚は忌み嫌い避けて通る事。
奇譚は奇妙な出来事を綴ると言う事。
そんな話がとある喫茶店のマスターの元に集まるという。客足がフッと途絶えた時に居合わせると、彼は思い出したように口を開く。それは忌憚を語る奇譚の始まりだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















