1 / 1
102歳のばあちゃんの話
しおりを挟む
「百二歳のばあちゃんの話」
「おばあちゃん、もう危ないんだって」
最近では珍しい母からの電話であった。食事は何を食べているか、ラーメンばかり食べるな、まだビール飲んでるの?などのいつもと同じ聞き飽きた小言のあと母がそう言った。
「たけしにも一応知らせとこうと思って」
そこに別に悲壮感はさほど感じられなかった。
無理もない。ばあちゃんは百歳を超えて東京の病院に入院している。何時亡くなってもおかしくないばあちゃんに、皆出来る限りやさしく接して来たに違いないし、曾孫も三人いる。何時亡くなっても大往生と言えるかも知れない。
百歳を越えた母方の祖母であるばあちゃん、まだまだ生きたいと意欲を示していたと言うが、もう病院暮らしは二年を越えていた。僕にとっては、百歳を越えてもっと生きたいと言う気持ちを持つ事は生命力を越えるの意思があるのだとも思えた。ばあちゃんは別に気丈なタイプではなくって、どちらかと言えば伏せがちでしょっちゅう病院に行っている印象があった。自分の体に気を遣って来た結果こんなにも長生きできたのではとも思う。百歳になった時、東京都から表彰状が届いた。ここまで来たら、もっともっと長生きして欲しいと思っていた。
父方の祖母も大変長生きした(九十六歳没)。父方の祖母は千葉の館山でずっと農業を営んで来た。こちらは七十過ぎても畑仕事を続けた強い人であった。しかし僕の知る限りでは、八十代後半からは「いつお迎えが来るのか待ってるだけだよ」と小さく口癖の様に言っていた。もうこの世に未練はなく、お迎え(死ぬこと)を待って生きているだけだと。
長く生きて老いて行く事は、そう、自然に死を受け入れて行く様になる事かも知れないな、などと朧げながら思っていた。それが自然な姿で、最も幸せな事の一つではないかと。しかし、百歳のばあちゃんはもっと生きたいと言う強い意思を持ち、弱って行く自分の肉体と闘って、そこまでして生きている。それ自体を漠然と「ばあちゃんって凄いな」と思っていた。
僕自身が年齢を重ね、身内の死などを経験するにつれ、その漠然とした考えは次第に現実味を増して行った。いつかは死ぬ。それは当り前の事。しかし自分が生きる世界で、自分自身が周囲に対して意味を持たなくても、生きる喜びが無くなっても、それでもやはり生きたいだろうか。
きっと、生きる事の意味は、生きる事その物であるとばあちゃんの生きざまは僕に感じさせた。
*
その母方のばあちゃんの家、つまり母の実家は東京の大田区にあった。僕の実家の横浜からそう遠くもなく、母に連れられ小学生くらいの頃から気軽に遊びに行っていた。どう行くかは分っていて、十歳位の時に僕が一人でいきなり行って、驚かせた事もある。おじいちゃんは早くに亡くなっていた(僕が六歳のころ)が、まだ幼いかった僕の事を大変かわいがってくれたらしい。病床ついて入院して間もなく亡くなった。病名は僕には分からない。しかし死ぬ間際、自分の息子を差し置いて「たけしは何処だ」と盛んに言っていたらしい。しかしまだ幼かった僕にはおじいちゃんの記憶は薄っすらとしかない。
ばあちゃんの方が物心付いてからの記憶も多くあり、小学校の頃は毎年二回は僕と妹、従妹など親戚が集まって皆で遊んだものだ。近所の公園などの遊び場や、半径一キロくらいの地理、何処のスーパーが安いかなども分かるくらいその土地に慣れていた。今思うと東京の街は近くに何でもあってコンパクトで便利だった。
戦前から東京のばあちゃんの家は、十人位小僧さんを抱える呉服屋だったらしいのだが、空襲で全てが焼けてしまい、引っ越してから今の家になったらしい。戦後に建てられた昔の家の作りで、階段がとても急でしかも一直線。何度か四,五歳の妹が転がり落ちた。今考えるとよくケガをしなかったものである。
ばあちゃんはお正月に遊びに行くとお年玉をくれるのだが、いつも五百円(当時は札だった)で子どもながらにも「ケチなばあちゃんだ」と思っていた。父方の祖母は毎年五千円くれた。また大笑いした時に、総入れ歯が口から外に飛び出した事も良く覚えている。僕も妹も従妹たちも周囲の全員がビックリした。大変熱心な仏教の信者で、朝夕必ずお経らしきものを仏壇の前で数珠をカリカリ鳴らしながら唱えていた。
子供の頃はそんな風だったけれど、社会に出てからは、五年から十年くらい会う事もなく、従弟の家庭教師とかで、たまにばあちゃんの家に行く機会があったりすると、会うたびにさすがに年を取ったなぁと思った。実際、ばあちゃんは身の丈も眼もどんどん小さくなって行った。
そのばあちゃんが、もう危ないと言う。
*
僕は自分の小さな会社を経営していて仕事は休みにくく、なかなか易々と東京の病院まで行く時間が無かった。しかしもう危ないと聞かされ、これは絶対に行かねば、と病院の名前からネットで場所を探し、電車で多分これが最後であろうばあちゃんに会いに出かけた。
前回会ったのは一年前位だったか。ばあちゃんは別の病院に入院していたが、まだ普通に話をして、何を話したか忘れてしまったが頭もしっかりしている様子だった。ただ、とにかく目がしじみの様に小さくなってしまっていて、瞳の色は少し濁った灰色になっていた。その時は嬉しそうで、
「たけしちゃん、よく来てくれたね。あれ、点滴が変だよ」
そう言って僕に見せる腕には点滴の針が刺さっていたが、そこから血が流れていた。僕は看護師を呼ぶボタンを押した。あとで叔父さん(母の弟)に「たけしが来た」と言ってもボケていると思っていて信用しなかったらしい。
祖母との昔の思い出を考えながら、車窓の外を見ていた。思い出は芋づる式に浮かび、当時の事を懐かしむ。
京急線の小さな駅から病院に歩いて向かった。初めて訪れる駅だった。地図を頼りに歩くと、予想以上に駅から遠い様で、病院の面会時間もあるので、足を速めた。きっと何人か知っている人も見舞いに来ているだろう。
初めての駅、初めての町。僕は地図を頼りに進んだけれど、意外と病院は遠く、コンビニに寄って、その病院への道を尋ねるためにペットボトルのお茶を買った。
道は細く人通りもなく、暗かった。周囲に家はあったが、あまり家庭から漏れ出る光の様なものはなく、静かだった。
面会時間終了の三十分前、午後七時半くらいにようやく病院についた。思ったよりも小さな病院で、駐車場も十台分くらいしかなかった。周囲の家並み以上に院内は静まり返っていて人の気配はほとんど無く、まだ消灯時間でもないだろうに電気も消してあった。ベルを押すと受付には当直らしき人が奥から出てきた。
明かりが付いているのはエレベーターをナースセンターだけの様だ。
案内された病棟に行くと、ナースセンターからすぐに見える一つだけ明るいドアのない部屋があった。そこに祖母がいると言われ部屋に入ってみる。意外な事に祖母のベッドの周りには誰も居なかった。個室の真ん中にぽつりと小さな祖母が横たわるベッドがあった。
祖母は目をつぶって天井を向いたまま点滴を打ちながら全く微動だにしない。入れ歯を外してしまっているからだろう、顎がクシャクシャにしぼんで、顔が半分くらいの大きさに見えた。
たぶん異常を感知できるようにだろう、センサーに繋いだ計測器などが幾つか隣りに置いてある。全く静かで、ただ眠っている様に見えた。もうすぐ亡くなるかも知れないと聞いた時に想像された、昏睡状態と言う訳ではない様だった。
あまりの静かさに、
(まだ生きているのだろうか?)
そう思って顔に耳を近づける。呼吸はしている様だ。
「おばあちゃん、たけしだよ、お見舞いに来たよ」
子どもに話し掛けるような大きくはっきりとした口調でそう耳元で話しかけた。微動だにしない。
そのままおそらく意識も無いであろう祖母に向かって、色々な話をした。
「俺は今自分の会社をやってて、大変だけど面白いよ」
「・・・・」
「(孫の)ひとし君の結婚式はとても良かったよ。ひでちゃんももうすぐ結婚するんだよ、おばあちゃん、それまで死んじゃだめだよ」(その年一人の孫が結婚し、もう一人がすぐに結婚することになっていた)
「・・・・」
全く反応のないばあちゃん。意識が無く聞こえていないだろうが僕は話し続けた。
そんないつ死んでもおかしくない状況なのに、別に看護婦や医者が付き添っている訳でもない。
・・・まあ当たり前か。死ぬのを待っているだけの状態なのだ。病気で危篤になっている患者とは少し違う。老衰と言う、人生を全うした死に方なのである。恐らく、その時が訪れた時は、心臓の鼓動が止まった事をセンサーが感知し、ナースセンターに知らせるのだろう。それまでの時間が、淡々とこの室内に流れている気がした。ただただ、終わりを待っている時間。
その時、突如不意に祖母が顔をしかめ、苦しそうな表情になった。そして大きく口を開けた。・・・まさか。
「どうしたの、苦しいの!?看護婦さん呼ぼうか?」
焦って僕がそう言うと、苦しそうに二、三回パクパクと口を開けてからすぐに静かな表情に戻った。その後何を話しかけても、何の反応も無かった。緊急のボタンを押す前に呼吸を確認した。
(ああ、良かった)と安堵する。
そろそろ面会時間のリミットだった。
「じゃあね、おばあちゃん。また来るよ」
僕はそう言い残して、多分これが最後なのだと思い祖母を一瞬強く見つめ、病室を去った。祖母はやはり目を閉じたまま全く動くことはなかった。
*
帰る途中、その初めて訪れる駅の周辺を何となく散策してみた。駅前の商店街はもう夜八時過ぎだったから人通りはそんなには無かったが、小さな駅のわりに賑わっている様だった。軽く食事をとろうと思い適当な店がないか探してみる事にした。
その後、この駅前商店街はいったい何処まで続いているのだろう、とかすかな発見の期待などを持って駅から離れて行く方向にメインの商店街を歩いてみた。まっすぐに伸びていて、見える限り光はあった。五分ほど進み、しかし、やはりどんどん寂しくなり、結局大したものがなくもと来た道を戻った。来る時に開いていた店も次々に閉まって行く。
もう周囲には興味はなくなり、考えながら歩いていた。仕事の事とか明日に予定とか。お腹は空いていたけれど、横浜まで戻ってから食べようかと。
そうやって駅まで戻る道の途中、唐突なひらめきの様な言葉が突然、僕の気持ちを覆い尽くした。
「・・・ありがとう」
さっき僕には聞き取れなかった祖母の言葉が、その時はっきりと聞こえたのだ。あの時の一瞬の祖母の苦しそうなあえぎは、口をぱくぱくと二、三回開けた苦しそうな表情は、あれは僕に最後の力を振り絞って「ありがとう」って言ってくれたのだと。
泣いた。
(了)
「おばあちゃん、もう危ないんだって」
最近では珍しい母からの電話であった。食事は何を食べているか、ラーメンばかり食べるな、まだビール飲んでるの?などのいつもと同じ聞き飽きた小言のあと母がそう言った。
「たけしにも一応知らせとこうと思って」
そこに別に悲壮感はさほど感じられなかった。
無理もない。ばあちゃんは百歳を超えて東京の病院に入院している。何時亡くなってもおかしくないばあちゃんに、皆出来る限りやさしく接して来たに違いないし、曾孫も三人いる。何時亡くなっても大往生と言えるかも知れない。
百歳を越えた母方の祖母であるばあちゃん、まだまだ生きたいと意欲を示していたと言うが、もう病院暮らしは二年を越えていた。僕にとっては、百歳を越えてもっと生きたいと言う気持ちを持つ事は生命力を越えるの意思があるのだとも思えた。ばあちゃんは別に気丈なタイプではなくって、どちらかと言えば伏せがちでしょっちゅう病院に行っている印象があった。自分の体に気を遣って来た結果こんなにも長生きできたのではとも思う。百歳になった時、東京都から表彰状が届いた。ここまで来たら、もっともっと長生きして欲しいと思っていた。
父方の祖母も大変長生きした(九十六歳没)。父方の祖母は千葉の館山でずっと農業を営んで来た。こちらは七十過ぎても畑仕事を続けた強い人であった。しかし僕の知る限りでは、八十代後半からは「いつお迎えが来るのか待ってるだけだよ」と小さく口癖の様に言っていた。もうこの世に未練はなく、お迎え(死ぬこと)を待って生きているだけだと。
長く生きて老いて行く事は、そう、自然に死を受け入れて行く様になる事かも知れないな、などと朧げながら思っていた。それが自然な姿で、最も幸せな事の一つではないかと。しかし、百歳のばあちゃんはもっと生きたいと言う強い意思を持ち、弱って行く自分の肉体と闘って、そこまでして生きている。それ自体を漠然と「ばあちゃんって凄いな」と思っていた。
僕自身が年齢を重ね、身内の死などを経験するにつれ、その漠然とした考えは次第に現実味を増して行った。いつかは死ぬ。それは当り前の事。しかし自分が生きる世界で、自分自身が周囲に対して意味を持たなくても、生きる喜びが無くなっても、それでもやはり生きたいだろうか。
きっと、生きる事の意味は、生きる事その物であるとばあちゃんの生きざまは僕に感じさせた。
*
その母方のばあちゃんの家、つまり母の実家は東京の大田区にあった。僕の実家の横浜からそう遠くもなく、母に連れられ小学生くらいの頃から気軽に遊びに行っていた。どう行くかは分っていて、十歳位の時に僕が一人でいきなり行って、驚かせた事もある。おじいちゃんは早くに亡くなっていた(僕が六歳のころ)が、まだ幼いかった僕の事を大変かわいがってくれたらしい。病床ついて入院して間もなく亡くなった。病名は僕には分からない。しかし死ぬ間際、自分の息子を差し置いて「たけしは何処だ」と盛んに言っていたらしい。しかしまだ幼かった僕にはおじいちゃんの記憶は薄っすらとしかない。
ばあちゃんの方が物心付いてからの記憶も多くあり、小学校の頃は毎年二回は僕と妹、従妹など親戚が集まって皆で遊んだものだ。近所の公園などの遊び場や、半径一キロくらいの地理、何処のスーパーが安いかなども分かるくらいその土地に慣れていた。今思うと東京の街は近くに何でもあってコンパクトで便利だった。
戦前から東京のばあちゃんの家は、十人位小僧さんを抱える呉服屋だったらしいのだが、空襲で全てが焼けてしまい、引っ越してから今の家になったらしい。戦後に建てられた昔の家の作りで、階段がとても急でしかも一直線。何度か四,五歳の妹が転がり落ちた。今考えるとよくケガをしなかったものである。
ばあちゃんはお正月に遊びに行くとお年玉をくれるのだが、いつも五百円(当時は札だった)で子どもながらにも「ケチなばあちゃんだ」と思っていた。父方の祖母は毎年五千円くれた。また大笑いした時に、総入れ歯が口から外に飛び出した事も良く覚えている。僕も妹も従妹たちも周囲の全員がビックリした。大変熱心な仏教の信者で、朝夕必ずお経らしきものを仏壇の前で数珠をカリカリ鳴らしながら唱えていた。
子供の頃はそんな風だったけれど、社会に出てからは、五年から十年くらい会う事もなく、従弟の家庭教師とかで、たまにばあちゃんの家に行く機会があったりすると、会うたびにさすがに年を取ったなぁと思った。実際、ばあちゃんは身の丈も眼もどんどん小さくなって行った。
そのばあちゃんが、もう危ないと言う。
*
僕は自分の小さな会社を経営していて仕事は休みにくく、なかなか易々と東京の病院まで行く時間が無かった。しかしもう危ないと聞かされ、これは絶対に行かねば、と病院の名前からネットで場所を探し、電車で多分これが最後であろうばあちゃんに会いに出かけた。
前回会ったのは一年前位だったか。ばあちゃんは別の病院に入院していたが、まだ普通に話をして、何を話したか忘れてしまったが頭もしっかりしている様子だった。ただ、とにかく目がしじみの様に小さくなってしまっていて、瞳の色は少し濁った灰色になっていた。その時は嬉しそうで、
「たけしちゃん、よく来てくれたね。あれ、点滴が変だよ」
そう言って僕に見せる腕には点滴の針が刺さっていたが、そこから血が流れていた。僕は看護師を呼ぶボタンを押した。あとで叔父さん(母の弟)に「たけしが来た」と言ってもボケていると思っていて信用しなかったらしい。
祖母との昔の思い出を考えながら、車窓の外を見ていた。思い出は芋づる式に浮かび、当時の事を懐かしむ。
京急線の小さな駅から病院に歩いて向かった。初めて訪れる駅だった。地図を頼りに歩くと、予想以上に駅から遠い様で、病院の面会時間もあるので、足を速めた。きっと何人か知っている人も見舞いに来ているだろう。
初めての駅、初めての町。僕は地図を頼りに進んだけれど、意外と病院は遠く、コンビニに寄って、その病院への道を尋ねるためにペットボトルのお茶を買った。
道は細く人通りもなく、暗かった。周囲に家はあったが、あまり家庭から漏れ出る光の様なものはなく、静かだった。
面会時間終了の三十分前、午後七時半くらいにようやく病院についた。思ったよりも小さな病院で、駐車場も十台分くらいしかなかった。周囲の家並み以上に院内は静まり返っていて人の気配はほとんど無く、まだ消灯時間でもないだろうに電気も消してあった。ベルを押すと受付には当直らしき人が奥から出てきた。
明かりが付いているのはエレベーターをナースセンターだけの様だ。
案内された病棟に行くと、ナースセンターからすぐに見える一つだけ明るいドアのない部屋があった。そこに祖母がいると言われ部屋に入ってみる。意外な事に祖母のベッドの周りには誰も居なかった。個室の真ん中にぽつりと小さな祖母が横たわるベッドがあった。
祖母は目をつぶって天井を向いたまま点滴を打ちながら全く微動だにしない。入れ歯を外してしまっているからだろう、顎がクシャクシャにしぼんで、顔が半分くらいの大きさに見えた。
たぶん異常を感知できるようにだろう、センサーに繋いだ計測器などが幾つか隣りに置いてある。全く静かで、ただ眠っている様に見えた。もうすぐ亡くなるかも知れないと聞いた時に想像された、昏睡状態と言う訳ではない様だった。
あまりの静かさに、
(まだ生きているのだろうか?)
そう思って顔に耳を近づける。呼吸はしている様だ。
「おばあちゃん、たけしだよ、お見舞いに来たよ」
子どもに話し掛けるような大きくはっきりとした口調でそう耳元で話しかけた。微動だにしない。
そのままおそらく意識も無いであろう祖母に向かって、色々な話をした。
「俺は今自分の会社をやってて、大変だけど面白いよ」
「・・・・」
「(孫の)ひとし君の結婚式はとても良かったよ。ひでちゃんももうすぐ結婚するんだよ、おばあちゃん、それまで死んじゃだめだよ」(その年一人の孫が結婚し、もう一人がすぐに結婚することになっていた)
「・・・・」
全く反応のないばあちゃん。意識が無く聞こえていないだろうが僕は話し続けた。
そんないつ死んでもおかしくない状況なのに、別に看護婦や医者が付き添っている訳でもない。
・・・まあ当たり前か。死ぬのを待っているだけの状態なのだ。病気で危篤になっている患者とは少し違う。老衰と言う、人生を全うした死に方なのである。恐らく、その時が訪れた時は、心臓の鼓動が止まった事をセンサーが感知し、ナースセンターに知らせるのだろう。それまでの時間が、淡々とこの室内に流れている気がした。ただただ、終わりを待っている時間。
その時、突如不意に祖母が顔をしかめ、苦しそうな表情になった。そして大きく口を開けた。・・・まさか。
「どうしたの、苦しいの!?看護婦さん呼ぼうか?」
焦って僕がそう言うと、苦しそうに二、三回パクパクと口を開けてからすぐに静かな表情に戻った。その後何を話しかけても、何の反応も無かった。緊急のボタンを押す前に呼吸を確認した。
(ああ、良かった)と安堵する。
そろそろ面会時間のリミットだった。
「じゃあね、おばあちゃん。また来るよ」
僕はそう言い残して、多分これが最後なのだと思い祖母を一瞬強く見つめ、病室を去った。祖母はやはり目を閉じたまま全く動くことはなかった。
*
帰る途中、その初めて訪れる駅の周辺を何となく散策してみた。駅前の商店街はもう夜八時過ぎだったから人通りはそんなには無かったが、小さな駅のわりに賑わっている様だった。軽く食事をとろうと思い適当な店がないか探してみる事にした。
その後、この駅前商店街はいったい何処まで続いているのだろう、とかすかな発見の期待などを持って駅から離れて行く方向にメインの商店街を歩いてみた。まっすぐに伸びていて、見える限り光はあった。五分ほど進み、しかし、やはりどんどん寂しくなり、結局大したものがなくもと来た道を戻った。来る時に開いていた店も次々に閉まって行く。
もう周囲には興味はなくなり、考えながら歩いていた。仕事の事とか明日に予定とか。お腹は空いていたけれど、横浜まで戻ってから食べようかと。
そうやって駅まで戻る道の途中、唐突なひらめきの様な言葉が突然、僕の気持ちを覆い尽くした。
「・・・ありがとう」
さっき僕には聞き取れなかった祖母の言葉が、その時はっきりと聞こえたのだ。あの時の一瞬の祖母の苦しそうなあえぎは、口をぱくぱくと二、三回開けた苦しそうな表情は、あれは僕に最後の力を振り絞って「ありがとう」って言ってくれたのだと。
泣いた。
(了)
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

SNS漁りを始めた私、nostrとかいうプロトコルでのんびり過ごします!
獅子倉 八鹿
エッセイ・ノンフィクション
⚠︎注意
こちらに記入している用語の理解、解釈は誤っている可能性があります。
決して鵜呑みにせず、他情報も参照にして頂くようお願いいたします。
nostrからこんにちは。
技術者でもエンジニアでもないけど、
私はのんびり過ごしています。
ある日私は、気を病んでしまいTwitterを退会する。
復帰しても、Twitterに対する不安を拭いきれず、新天地を見出す旅に出た。
ネットの波から見つけ出した分散型SNS「damus」。
そして分散型プロトコル「nostr」。
なにがなんだか分からないまま歩み出したnostr生活をマイペースに綴る体験記及びエッセイのような書き物。
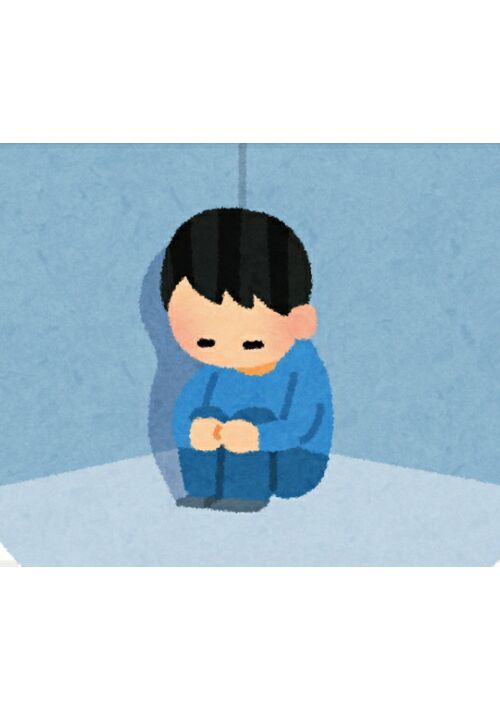

「私はまた、失う」
うた子
エッセイ・ノンフィクション
私の身の上に起こった「東日本大震災」による「原発事故」での避難、被災生活中の出来事を書いた、ノンフィクションの話です。
2011年3月11日、東日本大震災により、原発は事故を起こした。
放射能を巻き散らかした福島第一原子力発電所のある町からの被災者である私や家族たち、町の人々への偏見や差別。
私たちは、すぐには故郷へと戻ることは許されなかった。
すぐには、ではない。
永遠に、だ。
何もかもに絶望し、私は生きる気力を失いかける。
救ってくれようとしてくれている人の手や、助けようとしてくれている人の声が、私には届かなかった。
ひどい惨状を見た。
全てが虚しく感じた。
私はまだ、もっと、何もかもを、失うの。
これは、「私にだけ起こりえること」じゃなかった。
誰にでも、起こりえることだった。
何度も諦めようとした。
もう無理だと思った。
私には何もなくなってしまったのだと思った。
それでも生きた理由がある。
生きることをなんとか選択出来た理由がある。
私が「失って失って失って」「傷ついて傷ついて傷ついて」も、生きて行くことを諦めず、「生きなければ」と思わせてもらうことが出来たのは、ただの小さな日々の積み重ね。
私を今、生かすものは、何だろう。

子宮筋腫と診断されまして。《12/23 完結》
アーエル
エッセイ・ノンフィクション
徐々に悪くなる体調
気付いたら大変なことに!?
貴方ならどうしますか?
ハッピーエンドで終われるといいですねー。
❄12月23日完結しました
閲覧ありがとうございました
☆ここに出てくる病院は実在します。
病院名と個人名は伏せていますが、すべて実際に現在進行形で起きていることです。
(だから「ノンフィクション」のジャンルです)
特定するのはご自由ですが、言い回るのはおやめください。
問い合わせもお断りします。

見えない鎖 〜育児放棄・薬・風俗の中で生きてきて〜
ぶう子
エッセイ・ノンフィクション
育児放棄、男ボケ、ギャンブル依存
ホスト、風俗、子供を捨てた姉
アル中
女をあさり借金まみれの父
薬物、風俗、家出、癌、難病の私
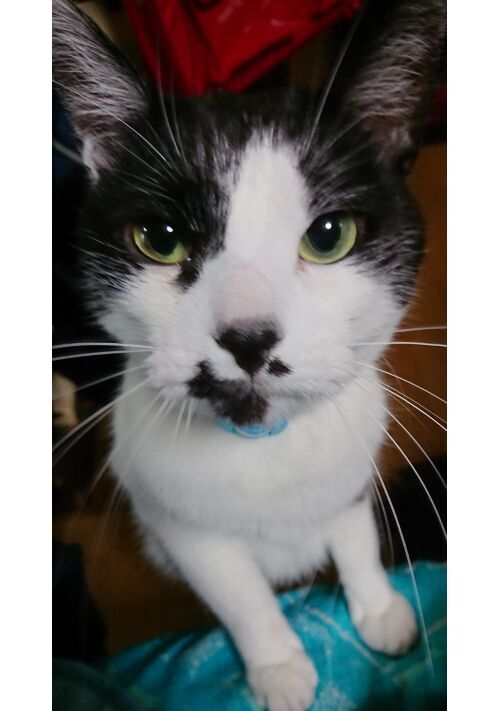
ミーちゃん日和
みるく♪
エッセイ・ノンフィクション
詩集です。
わが家の長男。名前は黒ミー。
私たちが出会ったのは、いまから数年前のこと。
里親広場で出会い、うちの子になりました。
生後1年の大きな猫でしたが、甘えん坊です。
抱っこされるのが大好き。
そのころに書きためた詩です。

あなたの隣で愛を囁く
ハゼミ
エッセイ・ノンフィクション
ある日、夫が腸穿孔を起こし緊急入院してしまった。
しかしそれはこれから起こる事の序盤でしかなかった。
命の危機に見舞われる夫と、何もできないもどかしさを感じながらも、奮闘する妻のお話。

【完結】筋力も体力もない小太り用ダイエット(【係数】逆算法)
まみ夜
エッセイ・ノンフィクション
ダイエットで「痩せる」のに失敗した経験はありますか?
それは、どうしてでしょう?
こんなにも、科学が発達し、ネットに情報も溢れている、というのにです。
・「一日の消費カロリー」に騙されるな
性別、身長、体重、年齢が同じで「事務仕事で週に1-2回軽く運動」している百人は、基礎代謝も「一日の消費カロリー」も同じ、と思いますか?
でも、計算上、上記の百人は、同じ値です。
これを元に、-250kcalにして「痩せない」のは当然です。
だって、この「一日の消費カロリー」は、アナタの生活を反映していないのですから。
・対象の違いに騙されるな
アナタが求めているダイエット法は、「筋力も体力もない小太り」が対象ではありませんか?
「筋肉も体力もあり脂肪が少ない体形」なモデルやアスリートが勧める方法では、同じようには痩せられないのです。
お勧め筋トレの半分もできなくて、挫折しませんでしたか?
・商売人に騙されるな
基本、ダイエット法の紹介は、商売です。
本、器具、サプリ、食品などを買わせ、情報番組やネットでの広告収入、ジムの会費が目的です。
だから、ダイエットを「成功」されては、売り上げがなくなって困ります。
失敗したら、評判が悪くなる?
いえいえ、逆に評価が高くなるカラクリがあるのです。
そもそも、そんなに効果のあるダイエット法なら、そろそろ肥満が根絶されていてもよくないですか?
誰だって、楽で派手で短期間でたくさん体重が減るダイエット法が好きなのです。
でもそれで、痩せました?
その幻想を捨てなければ、楽な脇道に逸れて、ダイエットは成功しませんので、それらの矛盾点も指摘していきます。
では、どうするか?
・アナタの生活や運動を反映させた「1日の必要カロリー(基礎代謝×【係数】)」を知るための【係数】を3ケ月かけて測定、算出(逆算)します
・「筋力も体力もない小太り」向けの運動をご提案します
・摂らないと健康を害するもの、自炊ではなくコンビニ弁当で大丈夫、といった食事をご提案します
あとは、痩せるカロリーを摂り、運動するだけのダイエット法です。
先に述べたように準備に、3ケ月間かかりますが、逆に言えば、それで「痩せる」のです。
※ダイエット成功=健康障害を起こさずに「痩せる」と定義
※痩せる=「筋肉の維持は考えない」と定義
ダイエット失敗の真の原因・誤解、普通に基礎代謝を計算してはどうして痩せられないのか、どう「痩せる」か実践方法などを、BMI28をダイエットでBMI21にした実体験、そのために調査した内容、最新のトピックスなどを交えて、解説します。
表紙イラストは、lllust ACより、せいじん様の「もだえる 女性」を使用させていただいております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















