お気に入りに追加
44
あなたにおすすめの小説

転生したら貴族の息子の友人A(庶民)になりました。
襲
ファンタジー
〈あらすじ〉
信号無視で突っ込んできたトラックに轢かれそうになった子どもを助けて代わりに轢かれた俺。
目が覚めると、そこは異世界!?
あぁ、よくあるやつか。
食堂兼居酒屋を営む両親の元に転生した俺は、庶民なのに、領主の息子、つまりは貴族の坊ちゃんと関わることに……
面倒ごとは御免なんだが。
魔力量“だけ”チートな主人公が、店を手伝いながら、学校で学びながら、冒険もしながら、領主の息子をからかいつつ(オイ)、のんびり(できたらいいな)ライフを満喫するお話。
誤字脱字の訂正、感想、などなど、お待ちしております。
やんわり決まってるけど、大体行き当たりばったりです。

貴族家三男の成り上がりライフ 生まれてすぐに人外認定された少年は異世界を満喫する
美原風香
ファンタジー
「残念ながらあなたはお亡くなりになりました」
御山聖夜はトラックに轢かれそうになった少女を助け、代わりに死んでしまう。しかし、聖夜の心の内の一言を聴いた女神から気に入られ、多くの能力を貰って異世界へ転生した。
ーけれども、彼は知らなかった。数多の神から愛された彼は生まれた時点で人外の能力を持っていたことを。表では貴族として、裏では神々の使徒として、異世界のヒエラルキーを駆け上っていく!これは生まれてすぐに人外認定された少年の最強に無双していく、そんなお話。
✳︎不定期更新です。
21/12/17 1巻発売!
22/05/25 2巻発売!
コミカライズ決定!
20/11/19 HOTランキング1位
ありがとうございます!

せっかくのクラス転移だけども、俺はポテトチップスでも食べながらクラスメイトの冒険を見守りたいと思います
霖空
ファンタジー
クラス転移に巻き込まれてしまった主人公。
得た能力は悪くない……いや、むしろ、チートじみたものだった。
しかしながら、それ以上のデメリットもあり……。
傍観者にならざるをえない彼が傍観者するお話です。
基本的に、勇者や、影井くんを見守りつつ、ほのぼの?生活していきます。
が、そのうち、彼自身の物語も始まる予定です。

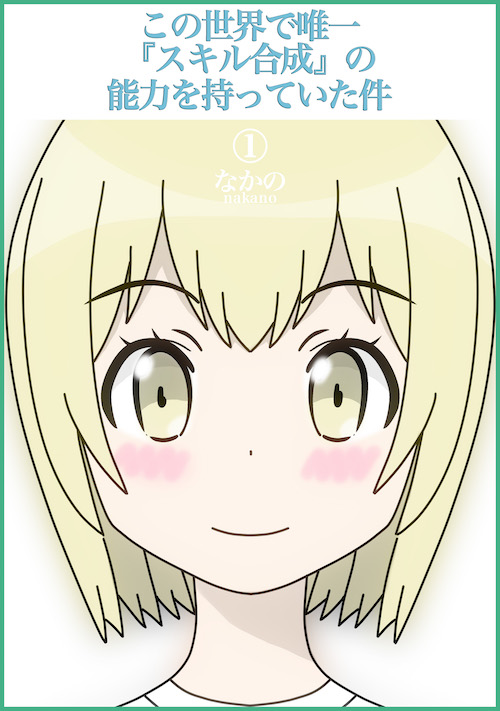
この世界で唯一『スキル合成』の能力を持っていた件
なかの
ファンタジー
異世界に転生した僕。
そこで与えられたのは、この世界ただ一人だけが持つ、ユニークスキル『スキル合成 - シンセサイズ』だった。
このユニークスキルを武器にこの世界を無双していく。
【web累計100万PV突破!】
著/イラスト なかの

異世界召喚でクラスの勇者達よりも強い俺は無能として追放処刑されたので自由に旅をします
Dakurai
ファンタジー
クラスで授業していた不動無限は突如と教室が光に包み込まれ気がつくと異世界に召喚されてしまった。神による儀式でとある神によってのスキルを得たがスキルが強すぎてスキル無しと勘違いされ更にはクラスメイトと王女による思惑で追放処刑に会ってしまうしかし最強スキルと聖獣のカワウソによって難を逃れと思ったらクラスの女子中野蒼花がついてきた。
相棒のカワウソとクラスの中野蒼花そして異世界の仲間と共にこの世界を自由に旅をします。
現在、第三章フェレスト王国エルフ編

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」
音爽(ネソウ)
ファンタジー
容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。
本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。
しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。
*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

のほほん異世界暮らし
みなと劉
ファンタジー
異世界に転生するなんて、夢の中の話だと思っていた。
それが、目を覚ましたら見知らぬ森の中、しかも手元にはなぜかしっかりとした地図と、ちょっとした冒険に必要な道具が揃っていたのだ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















