29 / 139
2. 依頼
私はすごくないです
しおりを挟む
こんなに足取りが軽いのは、いつ以来でしょうか?
放課後、私は学院の中を歩きながら、今日の合同授業を思い出します。
私たちのチームは三人しかいないのに、そのあとの試合でも、何度も勝つことができました。何回かは負けてしまいましたけど、ユートさんもシルファさんも、私を冷たい目で見たりしませんでした。逆に、今のは仕方ないとか、負けた方が成長できるとか、優しく励ましてくれました。
ユートさんとシルファさんは、すごいだけじゃなくて、とても優しい人でした。
今日の授業は、ここに来てから一番楽しい授業でした。私が誰かのお役に立てていることが、すごく嬉しく感じました。
またあの二人とチームになれたらな……。
「今日の合同授業、ひどくなかった?」
「うんうん。『暴君』と『小物』でしょ? あんなのズルよね」
そう思っていた時、建物の外から、そんな声が聞こえてきました。私は咄嗟に窓の近くに立って、耳を澄まします。
「『小物』の奴さあ、魔法使いのくせに近づいてくるとか意味分かんない。そんな奴と戦う訓練なんて受けてないって」
「少なくとも魔法使いがする戦い方じゃないよね。こっちの魔法も、防ぐよりも避ける方が多かったし」
聞き覚えのある声でした。話しているのは、私と同じクラスの女の人でしょう。確か、私たちのチームに負けたチームの方だと思います。
「『小物』さえいなければ、『暴君』の魔法も使わせなかったのに」
「確かあいつがリーダーだったっけ? 『暴君』もよくあんな奴とチームを組んだよね」
「まあお似合いじゃない? 『小物』を引き連れる『暴君』って、いかにもそれらしいじゃん」
「あははっ! それもそうね!」
ユートさんとシルファさんの悪口を言っているようでした。私はそれを聞いて、自分のことを言われてるわけでもないのに、なぜかそれと同じくらい悲しい気持ちになってしまいます。
ユートさんもシルファさんも、悪いことなんて何もしていません。むしろ人数が少ないのに勝つことができたのは、それだけ二人がすごかったからです。褒められこそすれ、悪く言われることなんてないはずなのに、どうしてあんな風に言うんでしょう?
「そう言えば、あいつもいた。『お荷物』」
「……っ!」
私は思わず、息を呑みました。
「そうそう、あいつもむかついたよね」
「私たちに勝ったとき、飛び跳ねたの見た?」
「それそれ。自分は大したことしてないのに、それで勝った気になってんの」
「あんなことできて当然なのにね。それで喜べるなんて、本当に意識が低いんだから」
「そんなだから『お荷物』って呼ばれてることにどうして気づかないのかしらね?」
「………………」
私は目を閉じて、両手で耳を塞ぎます。けれど女の人たちの声は、手を通り抜けて耳に入ってきます。
「まったく、どうしてあんな奴らが同じ学年にいるんだか」
「あれがこの学院の生徒なんだって見られるのは、勘弁してほしいよね」
「奇遇ね。私もあなたたちみたいな人間と同列に扱われるのはまっぴらだわ」
その言葉を聞いて、私ははっと目を開けて、ゆっくりと両手を耳から離しました。
「し、シルファ!? それに『小物』も!」
「盗み聞きしてたの!?」
「あんな大きな声で、聞きたくもない汚い言葉をまき散らしておいて、よく言うわね」
「『小物』って俺のことか? あのあだ名そんなに広まっているのか……」
二人に話しかけたのは、シルファさんとユートさんのようでした。ユートさんの声は授業中に聞いたものと同じでしたが、シルファさんは、私が聞いたことのないような冷たい口調でした。
「フルルに対して随分な言いようだったけど、あなたたちが偉そうに言う権利なんてないんじゃない? 四人もいた割に、『小物』だの『お荷物』だのと馬鹿にしてた三人の相手に負けたのだし」
「うっさい! 負けたのは『小物』の動きがズルかったせいよ!」
「あんな動きするなんて、魔法使いでも何でもないじゃない!」
「はは、確かに魔法使いっぽくはないよな。けどあれに近い動きをする魔物もいるだろうし、対処できないのはまずいと思うぞ?」
「うっ……」
あっけらかんとしたユートさんの言葉に、女の人は言い返せないみたいです。シルファさんが小さく笑います。
「ズルって、ふふ、いくら負けたのが悔しいからって、そんな幼稚な言い訳をするなんてね。本気でそう思っているなら、先生方に訴えればいいんじゃない? 無駄でしょうけど」
「黙って! あんな戦い方、この学院の生徒として認められないわ」
「あんな小さな魔術式しか作れないような奴が、私たちと同じ制服着ないでよね!」
「なら私よりも魔術式の小さいあなたたちも、その制服を着ないでほしいのだけれど」
「なんですって!?」
「まあまあ、どっちも落ち着けよ」
嫌な空気が伝わってくる中、ユートさんのいつもの口調が、それを和らげるように響きました。
「とりあえず話を聞こう。まず、二人はどうしてあんなことを言ってたんだ?」
「知らないわよ」
「自分で知らないうちに声が出てたのか?」
ユートさんは本当に驚いているみたいでした。ふふ、とシルファさんが笑ったのが聞こえます。
「……っ! あんたたちがむかつくのよ!」
「私たちよりも小さい魔術式しか作れないくせに、まぐれで勝ったからっていい気にならないで!」
「そうか、負けたのが悔しかったんだな。気持ちは分かるけど、それで人を悪く言うのは違うと思うぞ」
ユートさんは、自分のことも悪く言われているのに、それに対する悲しみも怒りも、その声には乗っていないようでした。本当にただ、自分の考えを話しているだけという感じです。
ユートさんは多分、そこにいる四人の中で一番冷静でした。大人びていて、すごいです。
「……ふん、偉そうに……」
「弱いくせに、調子に乗らないでよね」
「……弱い?」
その時、さっきまでずっと変わらなかったユートさんの声が、確かに変わりました。私は一瞬、肩が跳ね上がります。
「弱いって、俺のことを言ったのか?」
「そうに決まってんでしょ」
「『小物』の他に誰がいるのよ?」
「どうして俺が弱いんだ? 魔術式の大きさと俺の実力は関係ないだろ?」
「関係あるに決まってんじゃない!」
「本気で自分が弱くないって思ってんの?」
今度は女の人たちが笑いました。私は嫌な予感がしてきて、両手をまた耳元に近づけます。
「ならユートに負けたあなたたちはそれ以下ね」
「あんなもの、まぐれよ」
「次からは絶対に負けないわ」
「だったら、今から試合しよう」
ユートさんの言葉には、重く暗い感情が乗っているようでした。
「一対一だ。それならどっちが強いかはっきりするだろ?」
「はあ? なんでわざわざあんたなんかと試合しなくちゃならないの?」
「もし俺が勝ったら、弱いって言葉を取り消してほしい」
「……あほくさ。もう行こうよ」
「うん、時間の無駄だよね」
「あら、あれだけ大口叩いていた割に、いざ戦うとなると怖くて逃げるのかしら?」
「あんたたちに付き合うほど暇じゃないの」
「………………」
二人の女の人の声が離れていきました。やがてそれが聞こえなくなり、私はほっと胸を撫でおろします。もし大ゲンカが始まってしまったら、どうしようかと思っていました。
「ユート、大丈夫?」
「……ああ。悪い、少し冷静さを失ってた」
「謝ることなんてないわ。寧ろ、あなたもちゃんと怒ることができるんだって分かって、嬉しかったくらいよ」
「俺をなんだと思ってたんだ?」
ユートさんが苦笑したようです。その声はもう、元に戻っていました。
「あいつらの言葉なら、気にすることないわ。所詮負け犬の遠吠えなのだし」
「そうする。さっきの言葉は、次の試合で撤回してもらうさ。ただ今回勝てたから次も勝てるってわけでもないからな。やっぱり弱かった、なんて言われないように頑張らないと」
「……ほんと、あなたって前向きよね」
「そうか?」
「そうよ」
そして、二人の笑い声が聞こえました。私もつられて、笑ってしまいそうになりました。
「話は戻るけど、チームメンバーの件、どうするつもりなんだ?」
ユートさんのその言葉に、私ははっとして、また耳を澄まします。
そうでした。ユートさんはチームメンバーを探していて、それで私とチームを組んでくれたのでした。
もしかして、また二人と一緒のチームになれるんでしょうか? 私はどきどきしながら二人の言葉を待ちました。
「俺はフルルのこと、結構良かったと思うんだけど。シルファが魔術式を形成する時間を稼いでくれたし、あとの方は失敗も全然しなくなったしさ」
「そうね。言われたことはきちんとやってくれたわ」
また褒められてしまいました。私はその場で飛び跳ねたくなって、なんとか我慢します。
「けどさっきも言った通り、今の彼女じゃ私たちのチームには入れられないわ」
「……え?」
シルファさんの声を聞いて、すとん、と気持ちが落ちたみたいでした。
「どうしてだ? フルルは一生懸命頑張ってくれたじゃないか」
「だからあなたはお人好しなのよ、ユート。確かにフルルは頑張ってくれた。けれどあの程度の魔法、ここの生徒ならできて当然なのよ。一年飛び級しているあの子なら、尚更ね」
「っ……!」
さっきの女の人たちの言葉を思い出してしまいます。両手が自然と持ち上がりました。
「飛び級ってことは、フルルは年下なのか?」
「ええ。一年分の差があるにも関わらず私たちと同じ学年にいられるのは、他の生徒よりも突出した才能があると認められたから。でも授業でフルルが見せてくれた実力は年相応のものだった。この学年の平均に達してない彼女をチームに入れることはできないわ」
「………………」
シルファさんの言うことは、何も間違っていませんでした。飛び級を認められた私は、他の人と同じくらい、いえ、それ以上の魔法を使えないといけないんです。なのに今の私は、他の人よりも小さな魔法しか使えません。そんな私が、チームメンバーとして認められるはずがありませんでした。
「けれど飛び級できたってことは、実はすごい魔法が使えるんじゃないか?」
「どうかしらね。ただ少なくとも、今の彼女は実力不足だわ。飛び級が認められたのは過去のことよ。その情報に囚われて、私たちが見た現状のフルルを誤認するのは、お互いにとって良くないわ」
「………………」
私はゆっくりと手を下ろして、足元に目を向けます。
シルファさんの言う通り、飛び級が認められたのは前のことです。今の私なら、間違いなく飛び級は認められなかったでしょう。シルファさんは、ちゃんと今の私を見てくれていました。
だから、悲しいと思う理由なんて、何もないんです。
「でもシルファもフルルのこと褒めてただろ? あれはフルルのことを認めていたからじゃないのか?」
「最初に会ったときのあの子は、とても暗い表情をしていたわ。多分、さっきの奴らが言ってたような心ない言葉をぶつけられて、自分に自信が持ててなかったのでしょうね。そんな精神状態じゃろくに魔法も使えないで、それがまた自己嫌悪に繋がる悪循環に陥る。そうはなって欲しくなかったのよ」
「……じゃあ、認めてもないのにおだてたのか?」
「過度に褒めたつもりはないわ。練習ではできなかったことができるようになったことと、きちんと仕事をこなしたことは確かに認めていたしね。けれど私が求める水準には至らなかった。それだけのことよ」
「……うっ……!」
私はもう、それ以上聞いていられませんでした。二人に見つからないよう、窓のない方へと走り出します。
いつの間にか流れていた涙を拭いながら、私は二人から逃げるように、暗い廊下を駆けていきました。
◇ ◇ ◇
「……冷たいって思った?」
シルファは少し視線を外して問いかけてきた。俺は小さく頷く。
「少しな。シルファの言うことも分からないわけじゃないけど、誰だって初めは強くないんだ。フルルも、今は平均以下かもしれないけど、これからぐんと成長するかもしれない。なのに一度チームを組んだだけで判断して、もう二度と組まないってのは、見切りをつけるのが早すぎると思う」
もしメンバーの候補がたくさんいるというのなら仕方ないのかもしれないけれど、話を聞く限り、シルファの方も良さそうな生徒を見つけられてないみたいだ。そんな状況で、初めからフルルをメンバー候補から除外するのは間違っている。少なくとも、メンバーが二人のままでいるよりかは、フルルがチームに入ってくれた方がよっぽどいい。
「それにフルルは、俺の魔法を褒めてくれただろ? そんな生徒、なかなか見つからないんじゃないか?」
「それは、確かにそうね」
昨日の授業でも、俺の魔法を見たクラスメイトの多くは、俺たちのチームが勝ってもどこか複雑そうな表情を浮かべていた。
小さな魔術式をどうにかやりくりして勝機を見出す俺の戦い方は、ここの生徒にとっては異端だ。そんな俺が他の生徒を出し抜くことに、ほとんどの生徒はいい感情を抱かない。そのシルファの言葉は、実際にクラスメイトの顔を見て、正しいのだと実感した。アランやシルファ、シイキみたいな生徒は少数派で、多くの生徒は俺の戦い方を認めてはいないようだった。
そんな中フルルは、俺の魔法をすごいと認めてくれた。それだけじゃなく、なぜか他の生徒が避けがちなシルファのことだって、ちゃんと信頼しているようだった。
「フルルは俺たちのチームメンバーになるための、一番大切な条件を満たしている。そう思わないか?」
「………………」
シルファは口元に手を当て暫く黙っていると、ゆっくりと頷いた。
「あなたの言う通りね。少し高望みしすぎていたわ」
「じゃあ!」
「けれど、授業で見た彼女の実力が足らないというのも事実よ。実力があるだけではメンバーになれないように、信頼だけでもメンバーにすることはできないわ。だからもう一度一緒に行動して、フルルがどこまでやれるか見てみようと思う。判断はその後まで保留するわ」
「分かった。……あれ? けれど一緒に行動するったって、もうジェンヌ先生のクラスとの合同授業は無いんだろ? どうするんだ?」
「チームでなくても一緒に行動する機会は、授業以外でもあるわ」
シルファが人差し指を伸ばした。
「フルルを誘って、依頼を受けるのよ」
放課後、私は学院の中を歩きながら、今日の合同授業を思い出します。
私たちのチームは三人しかいないのに、そのあとの試合でも、何度も勝つことができました。何回かは負けてしまいましたけど、ユートさんもシルファさんも、私を冷たい目で見たりしませんでした。逆に、今のは仕方ないとか、負けた方が成長できるとか、優しく励ましてくれました。
ユートさんとシルファさんは、すごいだけじゃなくて、とても優しい人でした。
今日の授業は、ここに来てから一番楽しい授業でした。私が誰かのお役に立てていることが、すごく嬉しく感じました。
またあの二人とチームになれたらな……。
「今日の合同授業、ひどくなかった?」
「うんうん。『暴君』と『小物』でしょ? あんなのズルよね」
そう思っていた時、建物の外から、そんな声が聞こえてきました。私は咄嗟に窓の近くに立って、耳を澄まします。
「『小物』の奴さあ、魔法使いのくせに近づいてくるとか意味分かんない。そんな奴と戦う訓練なんて受けてないって」
「少なくとも魔法使いがする戦い方じゃないよね。こっちの魔法も、防ぐよりも避ける方が多かったし」
聞き覚えのある声でした。話しているのは、私と同じクラスの女の人でしょう。確か、私たちのチームに負けたチームの方だと思います。
「『小物』さえいなければ、『暴君』の魔法も使わせなかったのに」
「確かあいつがリーダーだったっけ? 『暴君』もよくあんな奴とチームを組んだよね」
「まあお似合いじゃない? 『小物』を引き連れる『暴君』って、いかにもそれらしいじゃん」
「あははっ! それもそうね!」
ユートさんとシルファさんの悪口を言っているようでした。私はそれを聞いて、自分のことを言われてるわけでもないのに、なぜかそれと同じくらい悲しい気持ちになってしまいます。
ユートさんもシルファさんも、悪いことなんて何もしていません。むしろ人数が少ないのに勝つことができたのは、それだけ二人がすごかったからです。褒められこそすれ、悪く言われることなんてないはずなのに、どうしてあんな風に言うんでしょう?
「そう言えば、あいつもいた。『お荷物』」
「……っ!」
私は思わず、息を呑みました。
「そうそう、あいつもむかついたよね」
「私たちに勝ったとき、飛び跳ねたの見た?」
「それそれ。自分は大したことしてないのに、それで勝った気になってんの」
「あんなことできて当然なのにね。それで喜べるなんて、本当に意識が低いんだから」
「そんなだから『お荷物』って呼ばれてることにどうして気づかないのかしらね?」
「………………」
私は目を閉じて、両手で耳を塞ぎます。けれど女の人たちの声は、手を通り抜けて耳に入ってきます。
「まったく、どうしてあんな奴らが同じ学年にいるんだか」
「あれがこの学院の生徒なんだって見られるのは、勘弁してほしいよね」
「奇遇ね。私もあなたたちみたいな人間と同列に扱われるのはまっぴらだわ」
その言葉を聞いて、私ははっと目を開けて、ゆっくりと両手を耳から離しました。
「し、シルファ!? それに『小物』も!」
「盗み聞きしてたの!?」
「あんな大きな声で、聞きたくもない汚い言葉をまき散らしておいて、よく言うわね」
「『小物』って俺のことか? あのあだ名そんなに広まっているのか……」
二人に話しかけたのは、シルファさんとユートさんのようでした。ユートさんの声は授業中に聞いたものと同じでしたが、シルファさんは、私が聞いたことのないような冷たい口調でした。
「フルルに対して随分な言いようだったけど、あなたたちが偉そうに言う権利なんてないんじゃない? 四人もいた割に、『小物』だの『お荷物』だのと馬鹿にしてた三人の相手に負けたのだし」
「うっさい! 負けたのは『小物』の動きがズルかったせいよ!」
「あんな動きするなんて、魔法使いでも何でもないじゃない!」
「はは、確かに魔法使いっぽくはないよな。けどあれに近い動きをする魔物もいるだろうし、対処できないのはまずいと思うぞ?」
「うっ……」
あっけらかんとしたユートさんの言葉に、女の人は言い返せないみたいです。シルファさんが小さく笑います。
「ズルって、ふふ、いくら負けたのが悔しいからって、そんな幼稚な言い訳をするなんてね。本気でそう思っているなら、先生方に訴えればいいんじゃない? 無駄でしょうけど」
「黙って! あんな戦い方、この学院の生徒として認められないわ」
「あんな小さな魔術式しか作れないような奴が、私たちと同じ制服着ないでよね!」
「なら私よりも魔術式の小さいあなたたちも、その制服を着ないでほしいのだけれど」
「なんですって!?」
「まあまあ、どっちも落ち着けよ」
嫌な空気が伝わってくる中、ユートさんのいつもの口調が、それを和らげるように響きました。
「とりあえず話を聞こう。まず、二人はどうしてあんなことを言ってたんだ?」
「知らないわよ」
「自分で知らないうちに声が出てたのか?」
ユートさんは本当に驚いているみたいでした。ふふ、とシルファさんが笑ったのが聞こえます。
「……っ! あんたたちがむかつくのよ!」
「私たちよりも小さい魔術式しか作れないくせに、まぐれで勝ったからっていい気にならないで!」
「そうか、負けたのが悔しかったんだな。気持ちは分かるけど、それで人を悪く言うのは違うと思うぞ」
ユートさんは、自分のことも悪く言われているのに、それに対する悲しみも怒りも、その声には乗っていないようでした。本当にただ、自分の考えを話しているだけという感じです。
ユートさんは多分、そこにいる四人の中で一番冷静でした。大人びていて、すごいです。
「……ふん、偉そうに……」
「弱いくせに、調子に乗らないでよね」
「……弱い?」
その時、さっきまでずっと変わらなかったユートさんの声が、確かに変わりました。私は一瞬、肩が跳ね上がります。
「弱いって、俺のことを言ったのか?」
「そうに決まってんでしょ」
「『小物』の他に誰がいるのよ?」
「どうして俺が弱いんだ? 魔術式の大きさと俺の実力は関係ないだろ?」
「関係あるに決まってんじゃない!」
「本気で自分が弱くないって思ってんの?」
今度は女の人たちが笑いました。私は嫌な予感がしてきて、両手をまた耳元に近づけます。
「ならユートに負けたあなたたちはそれ以下ね」
「あんなもの、まぐれよ」
「次からは絶対に負けないわ」
「だったら、今から試合しよう」
ユートさんの言葉には、重く暗い感情が乗っているようでした。
「一対一だ。それならどっちが強いかはっきりするだろ?」
「はあ? なんでわざわざあんたなんかと試合しなくちゃならないの?」
「もし俺が勝ったら、弱いって言葉を取り消してほしい」
「……あほくさ。もう行こうよ」
「うん、時間の無駄だよね」
「あら、あれだけ大口叩いていた割に、いざ戦うとなると怖くて逃げるのかしら?」
「あんたたちに付き合うほど暇じゃないの」
「………………」
二人の女の人の声が離れていきました。やがてそれが聞こえなくなり、私はほっと胸を撫でおろします。もし大ゲンカが始まってしまったら、どうしようかと思っていました。
「ユート、大丈夫?」
「……ああ。悪い、少し冷静さを失ってた」
「謝ることなんてないわ。寧ろ、あなたもちゃんと怒ることができるんだって分かって、嬉しかったくらいよ」
「俺をなんだと思ってたんだ?」
ユートさんが苦笑したようです。その声はもう、元に戻っていました。
「あいつらの言葉なら、気にすることないわ。所詮負け犬の遠吠えなのだし」
「そうする。さっきの言葉は、次の試合で撤回してもらうさ。ただ今回勝てたから次も勝てるってわけでもないからな。やっぱり弱かった、なんて言われないように頑張らないと」
「……ほんと、あなたって前向きよね」
「そうか?」
「そうよ」
そして、二人の笑い声が聞こえました。私もつられて、笑ってしまいそうになりました。
「話は戻るけど、チームメンバーの件、どうするつもりなんだ?」
ユートさんのその言葉に、私ははっとして、また耳を澄まします。
そうでした。ユートさんはチームメンバーを探していて、それで私とチームを組んでくれたのでした。
もしかして、また二人と一緒のチームになれるんでしょうか? 私はどきどきしながら二人の言葉を待ちました。
「俺はフルルのこと、結構良かったと思うんだけど。シルファが魔術式を形成する時間を稼いでくれたし、あとの方は失敗も全然しなくなったしさ」
「そうね。言われたことはきちんとやってくれたわ」
また褒められてしまいました。私はその場で飛び跳ねたくなって、なんとか我慢します。
「けどさっきも言った通り、今の彼女じゃ私たちのチームには入れられないわ」
「……え?」
シルファさんの声を聞いて、すとん、と気持ちが落ちたみたいでした。
「どうしてだ? フルルは一生懸命頑張ってくれたじゃないか」
「だからあなたはお人好しなのよ、ユート。確かにフルルは頑張ってくれた。けれどあの程度の魔法、ここの生徒ならできて当然なのよ。一年飛び級しているあの子なら、尚更ね」
「っ……!」
さっきの女の人たちの言葉を思い出してしまいます。両手が自然と持ち上がりました。
「飛び級ってことは、フルルは年下なのか?」
「ええ。一年分の差があるにも関わらず私たちと同じ学年にいられるのは、他の生徒よりも突出した才能があると認められたから。でも授業でフルルが見せてくれた実力は年相応のものだった。この学年の平均に達してない彼女をチームに入れることはできないわ」
「………………」
シルファさんの言うことは、何も間違っていませんでした。飛び級を認められた私は、他の人と同じくらい、いえ、それ以上の魔法を使えないといけないんです。なのに今の私は、他の人よりも小さな魔法しか使えません。そんな私が、チームメンバーとして認められるはずがありませんでした。
「けれど飛び級できたってことは、実はすごい魔法が使えるんじゃないか?」
「どうかしらね。ただ少なくとも、今の彼女は実力不足だわ。飛び級が認められたのは過去のことよ。その情報に囚われて、私たちが見た現状のフルルを誤認するのは、お互いにとって良くないわ」
「………………」
私はゆっくりと手を下ろして、足元に目を向けます。
シルファさんの言う通り、飛び級が認められたのは前のことです。今の私なら、間違いなく飛び級は認められなかったでしょう。シルファさんは、ちゃんと今の私を見てくれていました。
だから、悲しいと思う理由なんて、何もないんです。
「でもシルファもフルルのこと褒めてただろ? あれはフルルのことを認めていたからじゃないのか?」
「最初に会ったときのあの子は、とても暗い表情をしていたわ。多分、さっきの奴らが言ってたような心ない言葉をぶつけられて、自分に自信が持ててなかったのでしょうね。そんな精神状態じゃろくに魔法も使えないで、それがまた自己嫌悪に繋がる悪循環に陥る。そうはなって欲しくなかったのよ」
「……じゃあ、認めてもないのにおだてたのか?」
「過度に褒めたつもりはないわ。練習ではできなかったことができるようになったことと、きちんと仕事をこなしたことは確かに認めていたしね。けれど私が求める水準には至らなかった。それだけのことよ」
「……うっ……!」
私はもう、それ以上聞いていられませんでした。二人に見つからないよう、窓のない方へと走り出します。
いつの間にか流れていた涙を拭いながら、私は二人から逃げるように、暗い廊下を駆けていきました。
◇ ◇ ◇
「……冷たいって思った?」
シルファは少し視線を外して問いかけてきた。俺は小さく頷く。
「少しな。シルファの言うことも分からないわけじゃないけど、誰だって初めは強くないんだ。フルルも、今は平均以下かもしれないけど、これからぐんと成長するかもしれない。なのに一度チームを組んだだけで判断して、もう二度と組まないってのは、見切りをつけるのが早すぎると思う」
もしメンバーの候補がたくさんいるというのなら仕方ないのかもしれないけれど、話を聞く限り、シルファの方も良さそうな生徒を見つけられてないみたいだ。そんな状況で、初めからフルルをメンバー候補から除外するのは間違っている。少なくとも、メンバーが二人のままでいるよりかは、フルルがチームに入ってくれた方がよっぽどいい。
「それにフルルは、俺の魔法を褒めてくれただろ? そんな生徒、なかなか見つからないんじゃないか?」
「それは、確かにそうね」
昨日の授業でも、俺の魔法を見たクラスメイトの多くは、俺たちのチームが勝ってもどこか複雑そうな表情を浮かべていた。
小さな魔術式をどうにかやりくりして勝機を見出す俺の戦い方は、ここの生徒にとっては異端だ。そんな俺が他の生徒を出し抜くことに、ほとんどの生徒はいい感情を抱かない。そのシルファの言葉は、実際にクラスメイトの顔を見て、正しいのだと実感した。アランやシルファ、シイキみたいな生徒は少数派で、多くの生徒は俺の戦い方を認めてはいないようだった。
そんな中フルルは、俺の魔法をすごいと認めてくれた。それだけじゃなく、なぜか他の生徒が避けがちなシルファのことだって、ちゃんと信頼しているようだった。
「フルルは俺たちのチームメンバーになるための、一番大切な条件を満たしている。そう思わないか?」
「………………」
シルファは口元に手を当て暫く黙っていると、ゆっくりと頷いた。
「あなたの言う通りね。少し高望みしすぎていたわ」
「じゃあ!」
「けれど、授業で見た彼女の実力が足らないというのも事実よ。実力があるだけではメンバーになれないように、信頼だけでもメンバーにすることはできないわ。だからもう一度一緒に行動して、フルルがどこまでやれるか見てみようと思う。判断はその後まで保留するわ」
「分かった。……あれ? けれど一緒に行動するったって、もうジェンヌ先生のクラスとの合同授業は無いんだろ? どうするんだ?」
「チームでなくても一緒に行動する機会は、授業以外でもあるわ」
シルファが人差し指を伸ばした。
「フルルを誘って、依頼を受けるのよ」
0
お気に入りに追加
215
あなたにおすすめの小説

S級騎士の俺が精鋭部隊の隊長に任命されたが、部下がみんな年上のS級女騎士だった
ミズノみすぎ
ファンタジー
「黒騎士ゼクード・フォルス。君を竜狩り精鋭部隊【ドラゴンキラー隊】の隊長に任命する」
15歳の春。
念願のS級騎士になった俺は、いきなり国王様からそんな命令を下された。
「隊長とか面倒くさいんですけど」
S級騎士はモテるって聞いたからなったけど、隊長とかそんな重いポジションは……
「部下は美女揃いだぞ?」
「やらせていただきます!」
こうして俺は仕方なく隊長となった。
渡された部隊名簿を見ると隊員は俺を含めた女騎士3人の計4人構成となっていた。
女騎士二人は17歳。
もう一人の女騎士は19歳(俺の担任の先生)。
「あの……みんな年上なんですが」
「だが美人揃いだぞ?」
「がんばります!」
とは言ったものの。
俺のような若輩者の部下にされて、彼女たちに文句はないのだろうか?
と思っていた翌日の朝。
実家の玄関を部下となる女騎士が叩いてきた!
★のマークがついた話数にはイラストや4コマなどが後書きに記載されています。
※2023年11月25日に書籍が発売しています!
イラストレーターはiltusa先生です!
※コミカライズも進行中!
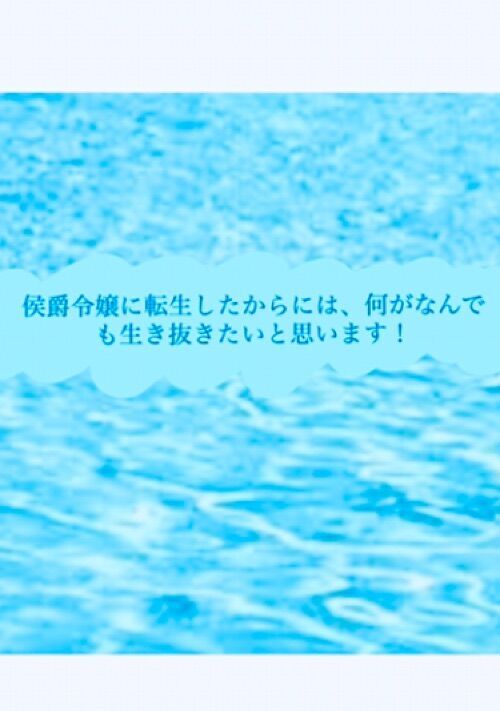
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

私は心を捨てました 〜「お前なんかどうでもいい」と言ったあなた、どうして今更なのですか?〜
月橋りら
恋愛
私に婚約の打診をしてきたのは、ルイス・フォン・ラグリー侯爵子息。
だが、彼には幼い頃から大切に想う少女がいたーー。
「お前なんかどうでもいい」 そうあなたが言ったから。
私は心を捨てたのに。
あなたはいきなり許しを乞うてきた。
そして優しくしてくるようになった。
ーー私が想いを捨てた後で。
どうして今更なのですかーー。
*この小説はカクヨム様、エブリスタ様でも連載しております。

追い出された万能職に新しい人生が始まりました
東堂大稀(旧:To-do)
ファンタジー
「お前、クビな」
その一言で『万能職』の青年ロアは勇者パーティーから追い出された。
『万能職』は冒険者の最底辺職だ。
冒険者ギルドの区分では『万能職』と耳触りのいい呼び方をされているが、めったにそんな呼び方をしてもらえない職業だった。
『雑用係』『運び屋』『なんでも屋』『小間使い』『見習い』。
口汚い者たちなど『寄生虫」と呼んだり、あえて『万能様』と皮肉を効かせて呼んでいた。
要するにパーティーの戦闘以外の仕事をなんでもこなす、雑用専門の最下級職だった。
その底辺職を7年も勤めた彼は、追い出されたことによって新しい人生を始める……。

白い結婚を言い渡されたお飾り妻ですが、ダンジョン攻略に励んでいます
時岡継美
ファンタジー
初夜に旦那様から「白い結婚」を言い渡され、お飾り妻としての生活が始まったヴィクトリアのライフワークはなんとダンジョンの攻略だった。
侯爵夫人として最低限の仕事をする傍ら、旦那様にも使用人たちにも内緒でダンジョンのラスボス戦に向けて準備を進めている。
しかし実は旦那様にも何やら秘密があるようで……?
他サイトでは「お飾り妻の趣味はダンジョン攻略です」のタイトルで公開している作品を加筆修正しております。
誤字脱字報告ありがとうございます!

平凡冒険者のスローライフ
上田なごむ
ファンタジー
26歳独身動物好きの主人公大和希は、神様によって魔物・魔法・獣人等ファンタジーな世界観の異世界に転移させられる。
平凡な能力値、野望など抱いていない彼は、冒険者としてスローライフを目標に日々を過ごしていく。
果たして、彼を待ち受ける出会いや試練は如何なるものか……
ファンタジー世界に向き合う、平凡な冒険者の物語。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















