4 / 54
子ども
しおりを挟むこれはまだ、事務所が男二人で経営されていた頃の話。
九条氏が経営する事務所に勤める伊藤は、両手に沢山のお菓子を持って歩いていた。
道ですれ違う人々が時々不思議そうな顔をして振り返る。ああ、透明のビニール袋にするんじゃなかった、と彼は後悔した。
ぶら下げている袋の中にはポッキーで溢れかえっていた。
ここ最近、かなり内容的に厳しい調査があり、昨日夜ようやく解決を迎えた。多分、あの九条さんだから家にも帰らず事務所で寝入っているに違いない。そう彼は確信していた。
仕事を終えた後、普通の人間ならば酒を飲んだり、美味しい食事をしたりして打ち上げるだろうが彼は違う。酒よりA5ランクのステーキより好きなものがある。
見慣れたビルに入りエレベーターで5階へ上がる。一番奥の扉を開けた途端、まずソファから飛び出ている足が見えた。やはり、九条氏だった。
「九条さーん! 疲れてるのわかりますけど、風邪ひきますよー?」
呆れて彼は大きな声をかける。寝起きの悪い九条氏は普通の呼びかけではなかなか起きない。ため息をついた伊藤は、持っていた袋からポッキーを取り出して一本寝ている男の口に突っ込んだ。そこでようやく、ゆっくり九条氏が目を開ける。
「九条さーん!」
「……ふぁい」
「せめて仮眠室で寝たらどうですか! 風邪ひきますよ」
寝起きのぼんやりした顔で、とりあえずもぐもぐと棒を食べる。面倒くさそうに起き上がった彼の後頭部には立派な寝癖がついていた。
「まあ今回の調査大変だったでしょうけどー。普通家の方がゆっくりできるじゃないですか、こんな狭いソファで寝なくても」
「帰るのが面倒で、次の日出勤するのも面倒で」
「もう、今日は休みにして帰ったらどうですか」
「ところで伊藤さん、ずいぶんまた大量に購入してきてくださったんですね?」
九条氏は置いてあるビニール袋を指さした。普段から事務所には大量のポッキーのストックがあるのだが、今日はまた山盛りだ。
伊藤がああ、と思い出したようにいう。
「ほら、今日って11月11日! ポッキーの日じゃないですか、安売りしてたから沢山買っちゃいました!」
笑顔でそう告げた途端だ。九条氏が目を丸くして勢いよく伊藤を振り返る。その様子に少し驚いた伊藤がたじろいだ。
「え。ど、どうしました九条さん」
「……不覚」
「え?」
「私ともあろうが……そんな一大イベントを忘れていたなど……! 土下座して謝りたい……」
「誰に土下座するつもりなんですか」
呆れて伊藤は言う。
この九条という男、天然なのかいつも人とズレているし意味がわからないことが多々ある。そんな彼に突っ込むのも伊藤の仕事の一つだ。
「そもそも一大イベントって言ったって、何かするわけでもないでしょう? 普通の人は今日はポッキー食べよ♪ ってなるけど、九条さんは毎日食べてるんだから」
「いえ、毎年この日はポッキーが生まれてきたことに感謝して三食ポッキーにするようにしてるんです」
「彼女の誕生日と勘違いしてませんか?」
「何言ってるんですか伊藤さん、私今彼女なんていませんよ」
「たとえですよ、例ええええ!!」
だめだ、ツッコミ疲れる! 毎日毎日、どうして九条さんはこんなにボケてるんだ! 伊藤は心の中で嘆く。
九条氏ははあと切なげにため息をつき、新しくポッキーを齧った。
「忘れていたなんて……ポッキーの日を……」
「前から思ってたんですけど九条さん、もし今彼女がいたとして、ポッキーと私どっちが好きなの!? って迫られたらどうするつもりなんですか」
自分でも馬鹿馬鹿しいと思う質問を投げかけた。でもそういう状況が安易に想像ついてしまう。てゆうか経験あるんじゃないかな九条さん。
彼はぽりぽりとお菓子を食べながら平然と言った。
「そんなことを言う人とはお付き合いしません」
「わあ……揺るがないなあ……」
「その代わり私も相手が好きなものは尊重します。相手が好きなものを否定するのはいかなる仲でも行わないべきだと思います」
まあ、意外とまともな答え。伊藤は納得する。九条さんの場合度を超えてるんだけども。
九条氏はなお続ける。
「伊藤さんお米好きですよね」
「好きですよ、日本人ですもん、米ない生活なんて無理です」
「私の場合それがたまたまポッキーだっただけです。おにぎりと同じ立ち位置です。主食でこれがないと無理なんです」
「ううん、なんかうまいこと言って納得させられてる気がするけど、とりあえずいつか九条さんと付き合う彼女は大変だろうなってことだけはわかりましたよ」
「それは同感です」
「同感するんですか」
伊藤は大きく笑う。顔はいいけど中身これじゃあな。扱いが上手い人じゃなきゃ九条さんの相手は務まらない。
そう思えば、彼女じゃなくたって……。今この事務所でもう一人誰かを雇いたがってるけど、九条さんとペアで調査するなんてめちゃくちゃ苦労するだろうな。どんな人が来るかわからないけど、今から心配だ。
「どうしました伊藤さん」
「いや。もしうちにもう一人増えたとして、その人は大変だろうなって同情してたんです」
「はあ、霊相手に働くのは根気がいりますからね」
(霊よりも九条さんとやって行く方が根気いると思う)
口には出さず、心の中だけで彼はつぶやいた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

求不得苦 -ぐふとくく-
こあら
キャラ文芸
看護師として働く主人公は小さな頃から幽霊の姿が見える体質
毎日懸命に仕事をする中、ある意識不明の少女と出会い不思議なビジョンを見る
少女が見せるビジョンを読み取り解読していく
少女の伝えたい想いとは…
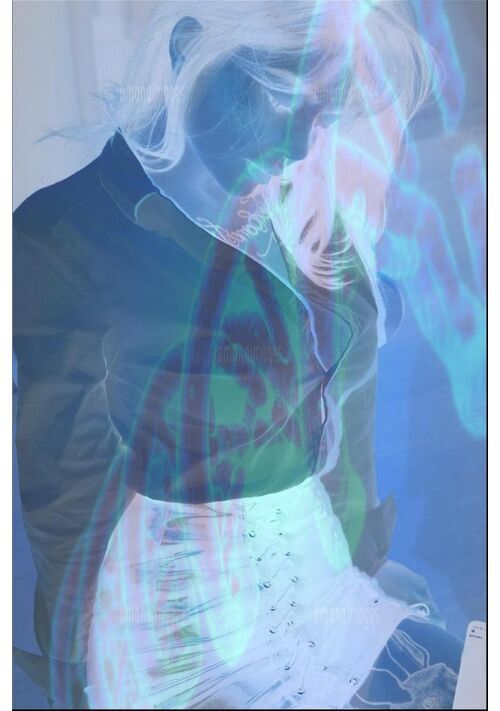
戒め
ムービーマスター
キャラ文芸
悪魔サタン=ルシファーの涙ほどの正義の意志から生まれたメイと、神が微かに抱いた悪意から生まれた天使・シンが出会う現世は、世界の滅びる時代なのか、地球上の人間や動物に次々と未知のウイルスが襲いかかり、ダークヒロイン・メイの不思議な超能力「戒め」も発動され、更なる混乱と恐怖が押し寄せる・・・

貧乏神の嫁入り
石田空
キャラ文芸
先祖が貧乏神のせいで、どれだけ事業を起こしても失敗ばかりしている中村家。
この年もめでたく御店を売りに出すことになり、長屋生活が終わらないと嘆いているいろりの元に、一発逆転の縁談の話が舞い込んだ。
風水師として名を馳せる鎮目家に、ぜひともと呼ばれたのだ。
貧乏神の末裔だけど受け入れてもらえるかしらと思いながらウキウキで嫁入りしたら……鎮目家の虚弱体質な跡取りのもとに嫁入りしろという。
貧乏神なのに、虚弱体質な旦那様の元に嫁いで大丈夫?
いろりと桃矢のおかしなおかしな夫婦愛。
*カクヨム、エブリスタにも掲載中。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















