お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

鎌倉古民家カフェ「かおりぎ」
水川サキ
ライト文芸
旧題」:かおりぎの庭~鎌倉薬膳カフェの出会い~
【私にとって大切なものが、ここには満ちあふれている】
彼氏と別れて、会社が倒産。
不運に見舞われていた夏芽(なつめ)に、父親が見合いを勧めてきた。
夏芽は見合いをする前に彼が暮らしているというカフェにこっそり行ってどんな人か見てみることにしたのだが。
静かで、穏やかだけど、たしかに強い生彩を感じた。

アーコレードへようこそ
松穂
ライト文芸
洋食レストラン『アーコレード(Accolade)』慧徳学園前店のひよっこ店長、水奈瀬葵。
楽しいスタッフや温かいお客様に囲まれて毎日大忙し。
やっと軌道に乗り始めたこの時期、突然のマネージャー交代?
異名サイボーグの新任上司とは?
葵の抱える過去の傷とは?
変化する日常と動き出す人間模様。
二人の間にめでたく恋情は芽生えるのか?
どこか懐かしくて最高に美味しい洋食料理とご一緒に、一読いかがですか。
※ 完結いたしました。ありがとうございました。
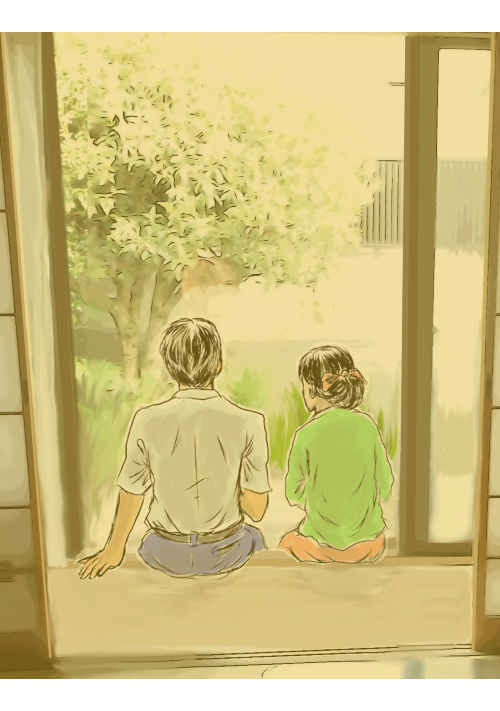
雨音
宮ノ上りよ
ライト文芸
夫を亡くし息子とふたり肩を寄せ合って生きていた祐子を日々支え力づけてくれたのは、息子と同い年の隣家の一人娘とその父・宏の存在だった。子ども達の成長と共に親ふたりの関係も少しずつ変化して、そして…。
※時代設定は1980年代後半~90年代後半(最終のエピソードのみ2010年代)です。現代と異なる点が多々あります。(学校週六日制等)


真夏の因果律
渋川宙
ライト文芸
夏の長期休暇を利用して祖父母の家を片付けることになった桐山夏樹。研究室の仲間を引き連れ、堂穴村に向うことに!
その堂穴村ではかつて、対立する名家の跡継ぎ同士が大恋愛を成し遂げたという話があって……
夏樹の先祖の秘密が解き明かされる!!

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

【3】Not equal romance【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
大学生の桂咲(かつら えみ)には異性の友人が一人だけいる。駿河総一郎(するが そういちろう)だ。同じ年齢、同じ学科、同じ趣味、そしてマンションの隣人ということもあり、いつも一緒にいる。ずっと友達だと思っていた咲は駿河とともに季節を重ねていくたび、感情の変化を感じるようになり……。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ三作目(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。(過去に「エブリスタ」にも掲載)

白鬼
藤田 秋
キャラ文芸
ホームレスになった少女、千真(ちさな)が野宿場所に選んだのは、とある寂れた神社。しかし、夜の神社には既に危険な先客が居座っていた。化け物に襲われた千真の前に現れたのは、神職の衣装を身に纏った白き鬼だった――。
普通の人間、普通じゃない人間、半分妖怪、生粋の妖怪、神様はみんなお友達?
田舎町の端っこで繰り広げられる、巫女さんと神主さんの(頭の)ユルいグダグダな魑魅魍魎ライフ、開幕!
草食系どころか最早キャベツ野郎×鈍感なアホの子。
少年は正体を隠し、少女を守る。そして、少女は当然のように正体に気付かない。
二人の主人公が織り成す、王道を走りたかったけど横道に逸れるなんちゃってあやかし奇譚。
コメディとシリアスの温度差にご注意を。
他サイト様でも掲載中です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















