63 / 63
終章
明治十年、銀座(三)
しおりを挟む
珠希は思う。
――変わって行く時代の中に、僕は…希望を探したい。
だってね。文明開化は、僕たちの物理的な距離を縮めてくれた。東京と横濱はもう、遠くじゃない。
江戸の頃は、休みながら歩いたら一日がかりだった。でも明治に入ってすぐに、まずは鉄道馬車が敷かれて、五年前にはいよいよ蒸気機関鉄道が開通して。新橋停車場から横濱停車場まで、たったの五十三分だよ?
これぞ素晴らしい開化じゃないかって、本当に、本当に…嬉しかった。
海を見ながら走るあの鉄道が、僕はとても好きだ。真っ直ぐに伸びた線路が、僕と諒さんの心を、ずっとこの先も…繋いでくれるから。
今では外国人の経営する園芸会社で、外国人を相手に商売をしている諒さん。洋装を身にまとい、英語まであやつるんだから…あの頃とは一番変わったかもしれないね。ふふ。中身が変わらないのが、また素敵なんだけど。
諒さんは、いつか横濱で日本人による園芸会社を立ち上げるって夢を…口髭の似合う、ますます恰幅の良くなった鉄二郎さんと一緒に、きっと叶えるだろうな。
僕は東京で、平民でも分かりやすく読める、素敵な錦絵入りの仮名新聞を作り続ける。錦絵新聞は、東京土産としても大人気だしね。
何よりも大切なのは、地方の平民にまで等しく情報を広げること。それが『東京仮名絵新聞社』の信念だ。新聞は広く万人に向けて開かれるべき、社会への扉なんだよ。
***
新橋停車場を目指し、明治の街並みを歩く。
同じ時代を走り抜けた仲間たち。今夜会う彼らのことを、珠希は考えていた。
――冬儀さん。
冬儀さんが遠邊家を離れ、髷を落としたのは…うん、明治に入って間もなくだった。遠邊家のお殿様は早々に士族の身分を捨てて平民になられ、田舎に引っ込んでしまわれたから。
薩摩藩邸の戦いのあと、冬儀さんは遠邊家の方々に全てをお話ししたそうだ。
お殿様はただ唖然とされ、奥方様はこう言ってお泣きになったという。
『女の身で、利根屋を継ぐことは叶いませぬ。ならば父の望みを叶えることで、私も父に認められたかった…』
程なくお殿様は奥方様を離縁された。
奥方様はお子様を連れ、お義兄様が跡を継がれていた利根屋に戻ると、力を合わせて御商売に精を出す。
あのあとすぐに時代が変わったことで、利根屋惣右衛門は死後逆賊どころか新政府の功労者に位置付けられたんだ。今じゃ利根屋は江戸の頃より一層繁盛しているよ。勝てば官軍とは、まさにこのことだね。
遠邊家を去ることになった冬儀さんはしばらく私塾で教鞭をとったあと、明治五年になってやっと、凛さんの住む庄内を訪れる。
幕末の戊辰戦争の折、政府軍と敵対した庄内藩は、逆賊として石高激減の憂き目にあっていた。困窮状態の解消を目指し、開墾事業に従事していた旧新徴組の皆さん。その皆さんと合流することで、冬儀さんは全く新しい世界を知った。何も無かった土地を切り開き、建物を作り、養蚕事業を始めて…。
机の上だけじゃなく、実際に体を動かして学ぶことの大切さに触れたんだ。いわゆる実学主義ってやつだね。
ふふ、あの勝負の行方はどうなったのか、照れて教えてくれないけれど…冬儀さんと凛さんは今ではご夫婦だ。お人形さんみたいに可愛くて、なかなかやんちゃな…素敵なお嬢さんもいる。
養蚕事業が軌道に乗るのを見届けて、今年武崎家はご家族で東京に移り住んだ。今じゃ冬儀さんは、以前お勤めしていた私塾で教鞭をとりながら、女子学校設立のために凛さんと一緒に奔走する日々だ。国民皆学の方針とは言っても、女子の高等教育はまだまだ発展途上だからね。
…冬儀さんの、口癖のようなあの言葉。
『誰もが自分らしく、生き方を希求できるような…そんな世の中であるべきなんだ』
冬儀さん、ありがとう。いつもあの言葉で僕の生き方を…肯定してくれて。
――秋司さん。
新政府の元で働くことや、警察のお仕事をすることには、葛藤もあるんだろうな。
ふふ、身近に僕みたいなのがいるとなおさらね。
それでも秋司さんは…翠さんと誠一君を守るために、その道を選んだ。
利発で心優しい誠一君は、秋司さんを本当のお父様だと思ってる。
明治五年に壬申戸籍が整備された時、秋司さんと冬儀さんで散々話し合って、翠さんと誠一君を秋司さんの籍に入れようと決めた。二人は誠一君を、どうしても『士族の息子』にしたかったんだそうだ。それは本来、誠一君が持つ権利だからだと。
冬儀さんはそれを見届けてから、庄内へと旅立った。
祝言は挙げなかったけれど、秋司さんと翠さん、誠一君の三人は確かに家族だ。そういう形で翠さんと誠一君を守ろうって、夫婦でなくても、本当の親子でなくても、家族を作ろうって…そう決めたんだって秋司さんは言っていた。
僕はそういう秋司さんの生き方を素敵だと思う。そういう家族のあり方も、なんて言うか…江戸的でも明治的でもなく…うん、それ以前に…そう、人間的だよ。あれは決して犠牲なんかじゃない。秋司さんの、一途な心なんだ。
何だか不思議だな。人の数だけ、それぞれの心があることが。
この世界には、きっと幾つもの時代を経て、数えきれないほどの心が本の頁のように折り重なっていて…また明日も、どこまでもずっと続いていくんだろうな。新しい頁を、日々そこに重ねながらね。
***
「諒さん!」
「珠希!」
駅舎の入り口の階段を、ゆっくり降りてくる諒。
珠希は諒を目指して一直線に走る。
あの浅草の夜のように、息を切らしながら。
――僕らは共にいくつもの夜を越え、朝の光の中を駆け出して行く。
「さあ、行こうよ諒さん!」
笑顔も泣き顔も苦しみも幸せも、この世の全てを受け止めるように珠希は手を広げて、諒に向かい真っ直ぐに差し伸べた。
(完)
――変わって行く時代の中に、僕は…希望を探したい。
だってね。文明開化は、僕たちの物理的な距離を縮めてくれた。東京と横濱はもう、遠くじゃない。
江戸の頃は、休みながら歩いたら一日がかりだった。でも明治に入ってすぐに、まずは鉄道馬車が敷かれて、五年前にはいよいよ蒸気機関鉄道が開通して。新橋停車場から横濱停車場まで、たったの五十三分だよ?
これぞ素晴らしい開化じゃないかって、本当に、本当に…嬉しかった。
海を見ながら走るあの鉄道が、僕はとても好きだ。真っ直ぐに伸びた線路が、僕と諒さんの心を、ずっとこの先も…繋いでくれるから。
今では外国人の経営する園芸会社で、外国人を相手に商売をしている諒さん。洋装を身にまとい、英語まであやつるんだから…あの頃とは一番変わったかもしれないね。ふふ。中身が変わらないのが、また素敵なんだけど。
諒さんは、いつか横濱で日本人による園芸会社を立ち上げるって夢を…口髭の似合う、ますます恰幅の良くなった鉄二郎さんと一緒に、きっと叶えるだろうな。
僕は東京で、平民でも分かりやすく読める、素敵な錦絵入りの仮名新聞を作り続ける。錦絵新聞は、東京土産としても大人気だしね。
何よりも大切なのは、地方の平民にまで等しく情報を広げること。それが『東京仮名絵新聞社』の信念だ。新聞は広く万人に向けて開かれるべき、社会への扉なんだよ。
***
新橋停車場を目指し、明治の街並みを歩く。
同じ時代を走り抜けた仲間たち。今夜会う彼らのことを、珠希は考えていた。
――冬儀さん。
冬儀さんが遠邊家を離れ、髷を落としたのは…うん、明治に入って間もなくだった。遠邊家のお殿様は早々に士族の身分を捨てて平民になられ、田舎に引っ込んでしまわれたから。
薩摩藩邸の戦いのあと、冬儀さんは遠邊家の方々に全てをお話ししたそうだ。
お殿様はただ唖然とされ、奥方様はこう言ってお泣きになったという。
『女の身で、利根屋を継ぐことは叶いませぬ。ならば父の望みを叶えることで、私も父に認められたかった…』
程なくお殿様は奥方様を離縁された。
奥方様はお子様を連れ、お義兄様が跡を継がれていた利根屋に戻ると、力を合わせて御商売に精を出す。
あのあとすぐに時代が変わったことで、利根屋惣右衛門は死後逆賊どころか新政府の功労者に位置付けられたんだ。今じゃ利根屋は江戸の頃より一層繁盛しているよ。勝てば官軍とは、まさにこのことだね。
遠邊家を去ることになった冬儀さんはしばらく私塾で教鞭をとったあと、明治五年になってやっと、凛さんの住む庄内を訪れる。
幕末の戊辰戦争の折、政府軍と敵対した庄内藩は、逆賊として石高激減の憂き目にあっていた。困窮状態の解消を目指し、開墾事業に従事していた旧新徴組の皆さん。その皆さんと合流することで、冬儀さんは全く新しい世界を知った。何も無かった土地を切り開き、建物を作り、養蚕事業を始めて…。
机の上だけじゃなく、実際に体を動かして学ぶことの大切さに触れたんだ。いわゆる実学主義ってやつだね。
ふふ、あの勝負の行方はどうなったのか、照れて教えてくれないけれど…冬儀さんと凛さんは今ではご夫婦だ。お人形さんみたいに可愛くて、なかなかやんちゃな…素敵なお嬢さんもいる。
養蚕事業が軌道に乗るのを見届けて、今年武崎家はご家族で東京に移り住んだ。今じゃ冬儀さんは、以前お勤めしていた私塾で教鞭をとりながら、女子学校設立のために凛さんと一緒に奔走する日々だ。国民皆学の方針とは言っても、女子の高等教育はまだまだ発展途上だからね。
…冬儀さんの、口癖のようなあの言葉。
『誰もが自分らしく、生き方を希求できるような…そんな世の中であるべきなんだ』
冬儀さん、ありがとう。いつもあの言葉で僕の生き方を…肯定してくれて。
――秋司さん。
新政府の元で働くことや、警察のお仕事をすることには、葛藤もあるんだろうな。
ふふ、身近に僕みたいなのがいるとなおさらね。
それでも秋司さんは…翠さんと誠一君を守るために、その道を選んだ。
利発で心優しい誠一君は、秋司さんを本当のお父様だと思ってる。
明治五年に壬申戸籍が整備された時、秋司さんと冬儀さんで散々話し合って、翠さんと誠一君を秋司さんの籍に入れようと決めた。二人は誠一君を、どうしても『士族の息子』にしたかったんだそうだ。それは本来、誠一君が持つ権利だからだと。
冬儀さんはそれを見届けてから、庄内へと旅立った。
祝言は挙げなかったけれど、秋司さんと翠さん、誠一君の三人は確かに家族だ。そういう形で翠さんと誠一君を守ろうって、夫婦でなくても、本当の親子でなくても、家族を作ろうって…そう決めたんだって秋司さんは言っていた。
僕はそういう秋司さんの生き方を素敵だと思う。そういう家族のあり方も、なんて言うか…江戸的でも明治的でもなく…うん、それ以前に…そう、人間的だよ。あれは決して犠牲なんかじゃない。秋司さんの、一途な心なんだ。
何だか不思議だな。人の数だけ、それぞれの心があることが。
この世界には、きっと幾つもの時代を経て、数えきれないほどの心が本の頁のように折り重なっていて…また明日も、どこまでもずっと続いていくんだろうな。新しい頁を、日々そこに重ねながらね。
***
「諒さん!」
「珠希!」
駅舎の入り口の階段を、ゆっくり降りてくる諒。
珠希は諒を目指して一直線に走る。
あの浅草の夜のように、息を切らしながら。
――僕らは共にいくつもの夜を越え、朝の光の中を駆け出して行く。
「さあ、行こうよ諒さん!」
笑顔も泣き顔も苦しみも幸せも、この世の全てを受け止めるように珠希は手を広げて、諒に向かい真っ直ぐに差し伸べた。
(完)
3
お気に入りに追加
12
この作品の感想を投稿する
みんなの感想(1件)
あなたにおすすめの小説

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい
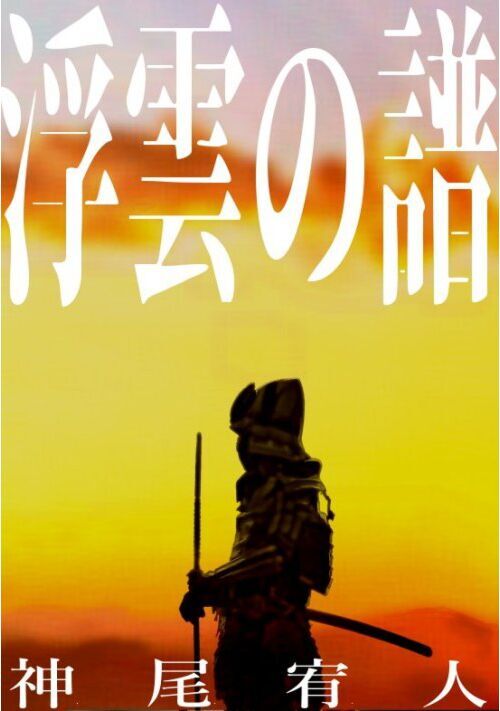
浮雲の譜
神尾 宥人
歴史・時代
時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。
峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……
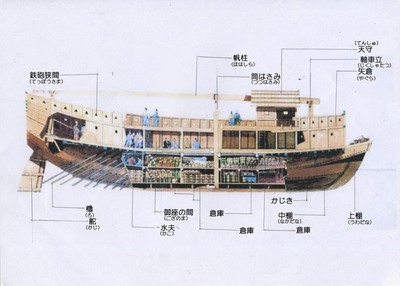

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

北宮純 ~祖国無き戦士~
水城洋臣
歴史・時代
三国時代を統一によって終わらせた晋(西晋)は、八王の乱と呼ばれる内紛で内部から腐り、異民族である匈奴によって滅ぼされた。
そんな匈奴が漢王朝の正統後継を名乗って建国した漢(匈奴漢)もまた、僅か十年で崩壊の時を迎える。
そんな時代に、ただ戦場を駆けて死ぬ事を望みながらも、二つの王朝の滅亡を見届けた数奇な運命の将がいた。
その名は北宮純。
漢民族消滅の危機とまで言われた五胡十六国時代の始まりを告げる戦いを、そんな彼の視点から描く。

獅子の末裔
卯花月影
歴史・時代
未だ戦乱続く近江の国に生まれた蒲生氏郷。主家・六角氏を揺るがした六角家騒動がようやく落ち着いてきたころ、目の前に現れたのは天下を狙う織田信長だった。
和歌をこよなく愛する温厚で無力な少年は、信長にその非凡な才を見いだされ、戦国武将として成長し、開花していく。
前作「滝川家の人びと」の続編です。途中、エピソードの被りがありますが、蒲生氏郷視点で描かれます。

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~
橋本洋一
歴史・時代
この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。
記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。
これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語
※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















無駄がなく、キリリと引き締まった文体が素晴らしいですね。 (Holy Yume)
holy様、お目に留めてくださりありがとうございます!
嬉しいお言葉、励みになります……!!