42 / 63
第二章 寺小姓立志譚
4.邂逅(かいこう)(四)
しおりを挟む
次の日。
稲荷の祠の前で待ち合わせた、見違えるような秋司の姿に珠希は感嘆の声を上げた。
「松波様…御立派です!」
髪結床で整えたのだろう。綺麗に剃りあがった月代。固く結われた髷。昨日までの乱れた風情とはまるで別人の精悍さだった。そして何より、きっちり着込んだ羽織袴に腰から下げた大小の刀。
――あれ、この羽織どこかで…。
お寺にいらしてたお武家様が着てらしたのかもね。
すっかり見違えた秋司のどこか晴れやかな顔に、珠希は何だか嬉しくなった。
秋司は照れくさそうに、まじまじと自分の姿を見下ろす。
――冬儀が無理やり俺の行李にしまい込んでいた遠邊家の羽織袴。もう二度とまとうことなど無いと…思っていたが。
「御立派です、か…。はは、これから出陣でもするみたいだな」
「ふふ、じゃあ今日の僕は寺小姓ならぬ小姓、森蘭丸の御役を頂戴しますね」
「それは大きく出たな。じゃあ俺は信長公か。鼻の下に髭でも描くか」
珠希の軽口につられて久しぶりに気分が高揚するのを感じながら、秋司は一路深川の町へと繰り出した。
「…ちょ、ちょっと差配さん、あれ…!」
「え…!」
いつものように立ち話をしていた差配と木戸番は目の前の光景に言葉を失う。
珠希はにこにこと、そんな二人に声をかけた。その隣には涼やかな目をした秋司が、遠邊家の正装を身にまとい立っている。
「こんにちは差配さん、番太郎さん。僕、松波様と一緒にお仕事を辞めてきます!」
「…ちょっとした出陣だ。その…行ってくる」
「え?…あ、あはは、そりゃ豪気な…い、行ってらっしゃいませ松波様、珠希」
「ご、御武運を…」
二人の後ろ姿を差配と木戸番はあんぐり口を開け、ぼんやりと見送った。
「珠希が、松波様と一緒に仕事を辞めてくる? 差配さん、こりゃ一体どういう…」
年のせいか、すっかり涙もろくなった差配は、熱くなった目頭をそっと押さえた。
「何でもいいさ。松波様も珠希も…きっとそれぞれの駒をひとつ前に進めようって、そう決めたんだよ…」
長い梅雨もそろそろ終わりの気配を見せていた。
「今年の夏はさ、かあっと暑くなりゃいいね」
海を目指す鴎が二羽、晴れ渡る深川の空をゆっくり横切った。
***
深川木場は材木の町である。碁盤の目のように張り巡らされた運河には、各地で切り出された丸太が所狭しと浮かんでいた。明暦の大火後、可燃性のものを扱っているからと埋立地への移転を命じられた日本橋や神田の材木問屋らが作り上げた町。それがここ、深川木場だった。
何しろ建物から家財道具、食器に至るまで、この世を形成するほとんどは木製である。木材は、燃えてしまえば灰燼に帰す。朽ち果てもする。それを再建するには、また同じだけの木材が必要で…と、その需要は永遠に続いて行く。
江戸の暮らしを維持するには、常に大量の木材の備蓄が必要だ。それを商う材木問屋は、まさに社会の根幹を担う重要な商売だった。
運河に浮かんだ丸太の上には、川並と呼ばれる筏師たちが乗っている。鳶口という長い棒をあやつり、丸太を乗りこなしながら筏の形に組む様は、まさに職人技。ここから角乗という芸能も生まれた。
「…壮観だな。珍しい眺めだ」
水面を照り返す日差しにまぶしく目を細めながら、秋司が辺りを眺める。
「松波様、こちらまでいらしたことなかったんですね。ほら、師走にずいぶん雪が降った日…あの時は歌川広重の江戸百景に描かれたとおりの素敵な景色でした」
――あの雪の日。
誠之助様のことがあったのは…あれからすぐのことだった。
そう思い表情を曇らせた秋司の様子に、珠希はさりげなく話題を逸らした。
「ね、松波様聞いてください。ああやって川並さんたちはこともなげに丸太に乗っていますよね? 僕、てっきり簡単に乗れるもんだと思って、こっそり乗ってみたんです。そしたら、ふふ、あっという間にひっくり返っちゃって! 溺れそうになったところを川並さんたちに引き上げられて。あはは。もう大変な騒ぎになったんですよ」
「さすがにそれは無謀だぞ、珠希。でも分かるよ、こうやって見ていると、何だか自分にも…簡単にできそうだ」
「なら…二人で乗ってみますか? こっそり」
――珠希は…いい奴だな。一瞬翳った俺の気持ちが、知らぬ間にもうほぐれている。
今まで色々なことがあったのだろう。
寺小姓をしていたというのも、その寺を出たのも、それからの苦労も昨夜のことも…。それなのに、つい表情を曇らせた俺を気遣い自然に寄り添ってくれている。
「…揃ってずぶ濡れで帰ったら、差配が腰を抜かすだろうな」
秋司も軽い調子を作り珠希に言葉を返す。
――そうか。人とは、そういうものなんだな…。
痛んだ人に寄り添うには、自分にも痛みの記憶が必要なんだ。
思えば俺はあのことがあるまで、常に陽の当たる道を…何のてらいもなく歩いていた。そんな俺は知らず他人に…誠之助様にも、そして俺自身にも…その王道を歩み続けることを強いていたのかもしれない。
痛みや苦しみを、俺は知らなさすぎた。
だから俺はあの頃の誠之助様に寄り添えなかった。だから誠之助様は俺に何も打ち明けられなかったんだ…きっと。
痛みを得た今なら…あの頃の誠之助様の痛みに寄り添うことができるだろうか。
「松波様。あれが僕の働いている材木問屋です」
真新しい木の香りが心地よく鼻をつく。物思いにふける秋司は我に返った。
***
稲荷の祠の前で待ち合わせた、見違えるような秋司の姿に珠希は感嘆の声を上げた。
「松波様…御立派です!」
髪結床で整えたのだろう。綺麗に剃りあがった月代。固く結われた髷。昨日までの乱れた風情とはまるで別人の精悍さだった。そして何より、きっちり着込んだ羽織袴に腰から下げた大小の刀。
――あれ、この羽織どこかで…。
お寺にいらしてたお武家様が着てらしたのかもね。
すっかり見違えた秋司のどこか晴れやかな顔に、珠希は何だか嬉しくなった。
秋司は照れくさそうに、まじまじと自分の姿を見下ろす。
――冬儀が無理やり俺の行李にしまい込んでいた遠邊家の羽織袴。もう二度とまとうことなど無いと…思っていたが。
「御立派です、か…。はは、これから出陣でもするみたいだな」
「ふふ、じゃあ今日の僕は寺小姓ならぬ小姓、森蘭丸の御役を頂戴しますね」
「それは大きく出たな。じゃあ俺は信長公か。鼻の下に髭でも描くか」
珠希の軽口につられて久しぶりに気分が高揚するのを感じながら、秋司は一路深川の町へと繰り出した。
「…ちょ、ちょっと差配さん、あれ…!」
「え…!」
いつものように立ち話をしていた差配と木戸番は目の前の光景に言葉を失う。
珠希はにこにこと、そんな二人に声をかけた。その隣には涼やかな目をした秋司が、遠邊家の正装を身にまとい立っている。
「こんにちは差配さん、番太郎さん。僕、松波様と一緒にお仕事を辞めてきます!」
「…ちょっとした出陣だ。その…行ってくる」
「え?…あ、あはは、そりゃ豪気な…い、行ってらっしゃいませ松波様、珠希」
「ご、御武運を…」
二人の後ろ姿を差配と木戸番はあんぐり口を開け、ぼんやりと見送った。
「珠希が、松波様と一緒に仕事を辞めてくる? 差配さん、こりゃ一体どういう…」
年のせいか、すっかり涙もろくなった差配は、熱くなった目頭をそっと押さえた。
「何でもいいさ。松波様も珠希も…きっとそれぞれの駒をひとつ前に進めようって、そう決めたんだよ…」
長い梅雨もそろそろ終わりの気配を見せていた。
「今年の夏はさ、かあっと暑くなりゃいいね」
海を目指す鴎が二羽、晴れ渡る深川の空をゆっくり横切った。
***
深川木場は材木の町である。碁盤の目のように張り巡らされた運河には、各地で切り出された丸太が所狭しと浮かんでいた。明暦の大火後、可燃性のものを扱っているからと埋立地への移転を命じられた日本橋や神田の材木問屋らが作り上げた町。それがここ、深川木場だった。
何しろ建物から家財道具、食器に至るまで、この世を形成するほとんどは木製である。木材は、燃えてしまえば灰燼に帰す。朽ち果てもする。それを再建するには、また同じだけの木材が必要で…と、その需要は永遠に続いて行く。
江戸の暮らしを維持するには、常に大量の木材の備蓄が必要だ。それを商う材木問屋は、まさに社会の根幹を担う重要な商売だった。
運河に浮かんだ丸太の上には、川並と呼ばれる筏師たちが乗っている。鳶口という長い棒をあやつり、丸太を乗りこなしながら筏の形に組む様は、まさに職人技。ここから角乗という芸能も生まれた。
「…壮観だな。珍しい眺めだ」
水面を照り返す日差しにまぶしく目を細めながら、秋司が辺りを眺める。
「松波様、こちらまでいらしたことなかったんですね。ほら、師走にずいぶん雪が降った日…あの時は歌川広重の江戸百景に描かれたとおりの素敵な景色でした」
――あの雪の日。
誠之助様のことがあったのは…あれからすぐのことだった。
そう思い表情を曇らせた秋司の様子に、珠希はさりげなく話題を逸らした。
「ね、松波様聞いてください。ああやって川並さんたちはこともなげに丸太に乗っていますよね? 僕、てっきり簡単に乗れるもんだと思って、こっそり乗ってみたんです。そしたら、ふふ、あっという間にひっくり返っちゃって! 溺れそうになったところを川並さんたちに引き上げられて。あはは。もう大変な騒ぎになったんですよ」
「さすがにそれは無謀だぞ、珠希。でも分かるよ、こうやって見ていると、何だか自分にも…簡単にできそうだ」
「なら…二人で乗ってみますか? こっそり」
――珠希は…いい奴だな。一瞬翳った俺の気持ちが、知らぬ間にもうほぐれている。
今まで色々なことがあったのだろう。
寺小姓をしていたというのも、その寺を出たのも、それからの苦労も昨夜のことも…。それなのに、つい表情を曇らせた俺を気遣い自然に寄り添ってくれている。
「…揃ってずぶ濡れで帰ったら、差配が腰を抜かすだろうな」
秋司も軽い調子を作り珠希に言葉を返す。
――そうか。人とは、そういうものなんだな…。
痛んだ人に寄り添うには、自分にも痛みの記憶が必要なんだ。
思えば俺はあのことがあるまで、常に陽の当たる道を…何のてらいもなく歩いていた。そんな俺は知らず他人に…誠之助様にも、そして俺自身にも…その王道を歩み続けることを強いていたのかもしれない。
痛みや苦しみを、俺は知らなさすぎた。
だから俺はあの頃の誠之助様に寄り添えなかった。だから誠之助様は俺に何も打ち明けられなかったんだ…きっと。
痛みを得た今なら…あの頃の誠之助様の痛みに寄り添うことができるだろうか。
「松波様。あれが僕の働いている材木問屋です」
真新しい木の香りが心地よく鼻をつく。物思いにふける秋司は我に返った。
***
2
お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい
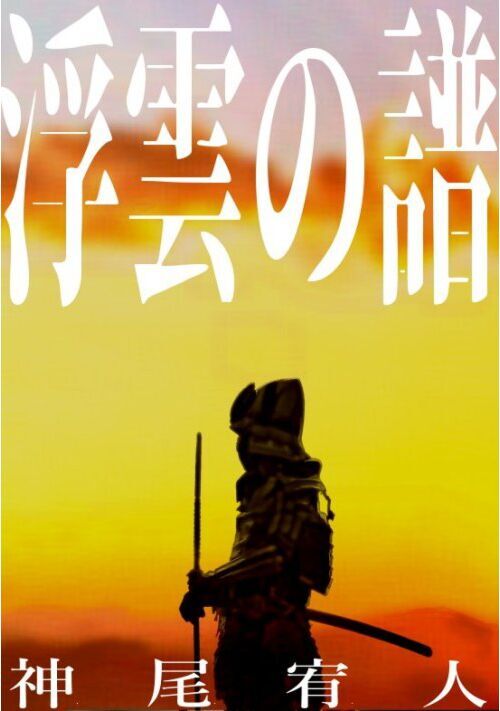
浮雲の譜
神尾 宥人
歴史・時代
時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。
峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……
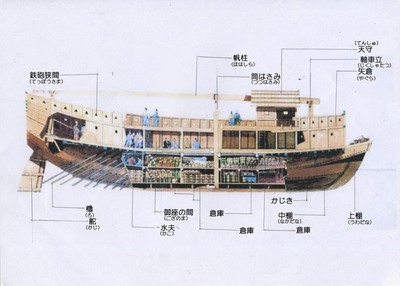

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

北宮純 ~祖国無き戦士~
水城洋臣
歴史・時代
三国時代を統一によって終わらせた晋(西晋)は、八王の乱と呼ばれる内紛で内部から腐り、異民族である匈奴によって滅ぼされた。
そんな匈奴が漢王朝の正統後継を名乗って建国した漢(匈奴漢)もまた、僅か十年で崩壊の時を迎える。
そんな時代に、ただ戦場を駆けて死ぬ事を望みながらも、二つの王朝の滅亡を見届けた数奇な運命の将がいた。
その名は北宮純。
漢民族消滅の危機とまで言われた五胡十六国時代の始まりを告げる戦いを、そんな彼の視点から描く。

獅子の末裔
卯花月影
歴史・時代
未だ戦乱続く近江の国に生まれた蒲生氏郷。主家・六角氏を揺るがした六角家騒動がようやく落ち着いてきたころ、目の前に現れたのは天下を狙う織田信長だった。
和歌をこよなく愛する温厚で無力な少年は、信長にその非凡な才を見いだされ、戦国武将として成長し、開花していく。
前作「滝川家の人びと」の続編です。途中、エピソードの被りがありますが、蒲生氏郷視点で描かれます。

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~
橋本洋一
歴史・時代
この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。
記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。
これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語
※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















