335 / 389
第二四話 失われたもの
第二四話 七
しおりを挟む
白の光が自身から膨れ上がり、秋之介の気がみるみるうちに周囲に広がっていく。そうして触れたのは探し求めていた赤色が印象的な魂だった。
(あかり‼)
ぼんやりとあたりをさまよっていた赤色の魂は、秋之介が呼びかけるとぴたりと動きを止めた。しかし反応はそれだけで、すぐに再びふらふらと動き出す。
(くそっ、結構まずいな……!)
降霊術の経験からいって、魂に自我が残っていれば何かしらの反応を示すはずだった。名前を呼びかければ、返事をするなり秋之介の方へやって来るなりするのだと予想していたのだが、それは大きく裏切られた。
(魂にほとんどあかりの自我が残ってないのか⁉ だとしたらどうやって呼び戻す……⁉)
焦れば焦るほど思考が空回ってしまう。
(ああ、もう!)
そもそも頭を使うのは苦手なのだ。昴や結月ならうまく立ち回れたのかもしれないが、秋之介には真似できない芸当だ。ならば己のやり方で現状を打破するしかないと秋之介は開き直った。
(あかり、聞いてくれ!)
馬鹿みたいに愚直に語りかけることでしか解決方法が見いだせなかった秋之介は、ひたすらにあかりの魂に向かって叫び続けた。
積み重ねてきた思い出や交わした約束をぶつけることで、あかりの魂が自我を取り戻すきっかけになるかもしれない。
(側にいるって、一緒に強くなろうって約束しただろ! 勝手にひとりでいなくなるなよ!)
なおもあかりの魂は浮遊し続ける。
(一緒に笑って生きるんだろ! 俺とあかりとゆづと昴で!)
いよいよ秋之介は人間姿がとれなくなり、本来の白虎姿に戻ってしまった。残された霊力はもうないも同然だった。
腹の傷は熱をもってじくじくと痛む。おまけに目の前がちかちかと瞬き出した。
(こんなとこでぶっ倒れるわけにはいかねぇ!)
命を霊力に変換して、秋之介は招魂祭を強行した。
一瞬息が詰まってたまらなく苦しくなったが、祭文を唱える口はなんとか意地で動かした。
何度目かになるかわからないほどに、秋之介はあかりの名前を呼び続けた。
(あかり、戻って来い!)
すると、迷うように揺れ動いていたあかりの魂が動きを止めた。
(かえり、たい、よ)
ささやかな声はともすれば気のせいかと聞き逃してしまいそうなほどに小さなものだったが、秋之介の耳にはしっかりと届いた。
(ああ、帰ろう!)
(でも、どこ、に?)
(そんなの決まってるだろ)
秋之介はあかりの魂に向かって手を伸ばした。もう離れていかないように、消えてなくならないように。
そうして身体中の苦痛を振り払って、秋之介はにっと笑ってみせた。
(俺とゆづと昴が待つ場所に!)
(あかり‼)
ぼんやりとあたりをさまよっていた赤色の魂は、秋之介が呼びかけるとぴたりと動きを止めた。しかし反応はそれだけで、すぐに再びふらふらと動き出す。
(くそっ、結構まずいな……!)
降霊術の経験からいって、魂に自我が残っていれば何かしらの反応を示すはずだった。名前を呼びかければ、返事をするなり秋之介の方へやって来るなりするのだと予想していたのだが、それは大きく裏切られた。
(魂にほとんどあかりの自我が残ってないのか⁉ だとしたらどうやって呼び戻す……⁉)
焦れば焦るほど思考が空回ってしまう。
(ああ、もう!)
そもそも頭を使うのは苦手なのだ。昴や結月ならうまく立ち回れたのかもしれないが、秋之介には真似できない芸当だ。ならば己のやり方で現状を打破するしかないと秋之介は開き直った。
(あかり、聞いてくれ!)
馬鹿みたいに愚直に語りかけることでしか解決方法が見いだせなかった秋之介は、ひたすらにあかりの魂に向かって叫び続けた。
積み重ねてきた思い出や交わした約束をぶつけることで、あかりの魂が自我を取り戻すきっかけになるかもしれない。
(側にいるって、一緒に強くなろうって約束しただろ! 勝手にひとりでいなくなるなよ!)
なおもあかりの魂は浮遊し続ける。
(一緒に笑って生きるんだろ! 俺とあかりとゆづと昴で!)
いよいよ秋之介は人間姿がとれなくなり、本来の白虎姿に戻ってしまった。残された霊力はもうないも同然だった。
腹の傷は熱をもってじくじくと痛む。おまけに目の前がちかちかと瞬き出した。
(こんなとこでぶっ倒れるわけにはいかねぇ!)
命を霊力に変換して、秋之介は招魂祭を強行した。
一瞬息が詰まってたまらなく苦しくなったが、祭文を唱える口はなんとか意地で動かした。
何度目かになるかわからないほどに、秋之介はあかりの名前を呼び続けた。
(あかり、戻って来い!)
すると、迷うように揺れ動いていたあかりの魂が動きを止めた。
(かえり、たい、よ)
ささやかな声はともすれば気のせいかと聞き逃してしまいそうなほどに小さなものだったが、秋之介の耳にはしっかりと届いた。
(ああ、帰ろう!)
(でも、どこ、に?)
(そんなの決まってるだろ)
秋之介はあかりの魂に向かって手を伸ばした。もう離れていかないように、消えてなくならないように。
そうして身体中の苦痛を振り払って、秋之介はにっと笑ってみせた。
(俺とゆづと昴が待つ場所に!)
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

【完結】貧乏令嬢の野草による領地改革
うみの渚
ファンタジー
八歳の時に木から落ちて頭を打った衝撃で、前世の記憶が蘇った主人公。
優しい家族に恵まれたが、家はとても貧乏だった。
家族のためにと、前世の記憶を頼りに寂れた領地を皆に支えられて徐々に発展させていく。
主人公は、魔法・知識チートは持っていません。
加筆修正しました。
お手に取って頂けたら嬉しいです。

【完結】転生7年!ぼっち脱出して王宮ライフ満喫してたら王国の動乱に巻き込まれた少女戦記 〜愛でたいアイカは救国の姫になる
三矢さくら
ファンタジー
【完結しました】異世界からの召喚に応じて6歳児に転生したアイカは、護ってくれる結界に逆に閉じ込められた結果、山奥でサバイバル生活を始める。
こんなはずじゃなかった!
異世界の山奥で過ごすこと7年。ようやく結界が解けて、山を下りたアイカは王都ヴィアナで【天衣無縫の無頼姫】の異名をとる第3王女リティアと出会う。
珍しい物好きの王女に気に入られたアイカは、なんと侍女に取り立てられて王宮に!
やっと始まった異世界生活は、美男美女ぞろいの王宮生活!
右を見ても左を見ても「愛でたい」美人に美少女! 美男子に美少年ばかり!
アイカとリティア、まだまだ幼い侍女と王女が数奇な運命をたどる異世界王宮ファンタジー戦記。

旦那様、前世の記憶を取り戻したので離縁させて頂きます
結城芙由奈@コミカライズ発売中
恋愛
【前世の記憶が戻ったので、貴方はもう用済みです】
ある日突然私は前世の記憶を取り戻し、今自分が置かれている結婚生活がとても理不尽な事に気が付いた。こんな夫ならもういらない。前世の知識を活用すれば、この世界でもきっと女1人で生きていけるはず。そして私はクズ夫に離婚届を突きつけた―。

魔法が使えない令嬢は住んでいた小屋が燃えたので家出します
怠惰るウェイブ
ファンタジー
グレイの世界は狭く暗く何よりも灰色だった。
本来なら領主令嬢となるはずの彼女は領主邸で住むことを許されず、ボロ小屋で暮らしていた。
彼女はある日、棚から落ちてきた一冊の本によって人生が変わることになる。
世界が色づき始めた頃、ある事件をきっかけに少女は旅をすることにした。
喋ることのできないグレイは旅を通して自身の世界を色付けていく。
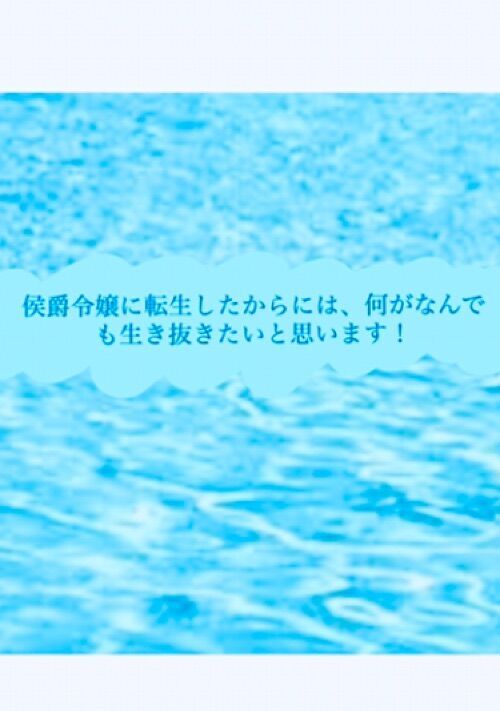
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

【完結】仰る通り、貴方の子ではありません
ユユ
恋愛
辛い悪阻と難産を経て産まれたのは
私に似た待望の男児だった。
なのに認められず、
不貞の濡れ衣を着せられ、
追い出されてしまった。
実家からも勘当され
息子と2人で生きていくことにした。
* 作り話です
* 暇つぶしにどうぞ
* 4万文字未満
* 完結保証付き
* 少し大人表現あり

私と母のサバイバル
だましだまし
ファンタジー
侯爵家の庶子だが唯一の直系の子として育てられた令嬢シェリー。
しかしある日、母と共に魔物が出る森に捨てられてしまった。
希望を諦めず森を進もう。
そう決意するシャリーに異変が起きた。
「私、別世界の前世があるみたい」
前世の知識を駆使し、二人は無事森を抜けられるのだろうか…?

出来損ないと呼ばれた伯爵令嬢は出来損ないを望む
家具屋ふふみに
ファンタジー
この世界には魔法が存在する。
そして生まれ持つ適性がある属性しか使えない。
その属性は主に6つ。
火・水・風・土・雷・そして……無。
クーリアは伯爵令嬢として生まれた。
貴族は生まれながらに魔力、そして属性の適性が多いとされている。
そんな中で、クーリアは無属性の適性しかなかった。
無属性しか扱えない者は『白』と呼ばれる。
その呼び名は貴族にとって屈辱でしかない。
だからクーリアは出来損ないと呼ばれた。
そして彼女はその通りの出来損ない……ではなかった。
これは彼女の本気を引き出したい彼女の周りの人達と、絶対に本気を出したくない彼女との攻防を描いた、そんな物語。
そしてクーリアは、自身に隠された秘密を知る……そんなお話。
設定揺らぎまくりで安定しないかもしれませんが、そういうものだと納得してくださいm(_ _)m
※←このマークがある話は大体一人称。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















