18 / 389
第三話 欠落の二年間
第三話 一
しおりを挟む
第三話 欠落の二年間
真っ白な百合の花束を南朱湖に供えて、そっと目を閉じ手を合わせる。朱咲の地に住んでいた二人を除く皆の冥福を心から祈り、同時にあかりの無事を願った。懐にしまったあかりの力を吸収した式神の符は、今もほのかに温かい。
(あかりは、生きてる)
結月が踵をかえすと、いつからいたのか秋之介と昴が背後に佇んでいた。
「よう」
「先に来てたんだね」
二人は白百合の花束を見てから、眼前いっぱいに広がる南朱湖に視線を滑らせた。
「大分水は引いたね」
水位はもとの状態に近づいており、茶色く濁っていた色も今は目を凝らせば水底が見えるくらいには透明さを取り戻している。亡骸の葬送は先日終えたばかりだった。その中にはあかりとあかりの父の姿だけがなく、あとの朱咲本家、分家、家臣、民は皆亡くなったことも確認された。
「……どこにいるの、あかり……」
結月が胸元をおさえて、呟く。秋之介と昴はそれには何も答えず、沈痛な面持ちで俯くだけだった。
おそらく陰の国に連れ去られただろうことだけはわかるが、半月経った今も足取りは追えずにいる。一か月半前に全開となった陽の国と陰の国を隔てる結界は、こんなときに限ってかたく閉ざされ、焦る気持ちそのままに御上に奏上しようにも取り次いですらもらえなかった。四家当主である結月たちの父親は、親としては結月たちの希望に沿いたいようだったが、当主としてそれは容易に認められないとはっきりとした拒否を示してきた。
いくら四家最強と謳われる彼らであっても、たった三人、なおかつあかりが欠けた状態では為す術がないのが現実だった。
「なんで、こんなに力が足りないんだろう……」
周囲になんと称賛されようとも、あかりを、大切な女の子を護れないならば意味がない。結月が拳を握りしめると、秋之介がぽんと肩を叩いた。
「言ってても始まらないだろ。今できることをするしかねえ。だろ?」
「……そう、だね」
秋之介は満足そうに笑うと、結月の肩を組んで歩き出した。黙禱を捧げ終えた昴も後をついてくる。
「今日は艮の結界を見に行くんだっけか?」
秋之介の確認の問いに、昴が大きく頷く。
「うん、見るだけって条件付きでね。あそこの結界周辺は特に瘴気が濃いから、気を付けるようにって」
結界関連は玄舞家の担当である。昴が当主に直談判して、ようやく立ち入りの許可を得た。
「艮の結界って最初に破られたとこだよな。やっぱ鬼門だからか」
「だろうね。あそこの結界維持が一番手がかかるし」
大路小路を歩みながらあれこれ話していたが、突然結月が足を止めて、首を傾げた。
「どうした、ゆづ」
結月は無言で懐から清め包みを取り出した。中には例の式神の符を入れてある。包みを解いて、符に左手をかざすと、結月ははっと息をのんだ。
「気配が変わった……!」
秋之介と昴も大きく目を見開く。
「どういうこと?」
「あかりになんかあったってことか?」
結月は「詳しくはわからないけど……」と呟き、符を凝視した。
「気が強くなった。……もしかしたら目が覚めたとか、力が少し戻ったとか。いずれにせよ吉兆。……よかった……」
安堵の息を吐きだす結月の顔は今にも泣きだしそうなものだった。表情こそ異なるものの、昴と秋之介もほっとした様子であることには変わりない。
「早く迎えに行ってあげないとね」
「だな。どんだけ放っておくんだーって拗ねられたらかなわねえし」
あえて明るく装うが、陰の国の式神の扱いについては結月たちもよく知っている。今は無事であっても、明日の命の保証があるとは限らないのだ。どんな仕打ちを受けるかわからない。どんな環境に置かれるかわからない。気が強くなったとはいえ、一刻も早くあかりを救い出さなければいけないことに変わりはない。
「うん、あかりはひとりきり、嫌い。早く連れて帰らないと」
結月は丁寧に符を包みなおし、優しく懐に戻した。
真っ白な百合の花束を南朱湖に供えて、そっと目を閉じ手を合わせる。朱咲の地に住んでいた二人を除く皆の冥福を心から祈り、同時にあかりの無事を願った。懐にしまったあかりの力を吸収した式神の符は、今もほのかに温かい。
(あかりは、生きてる)
結月が踵をかえすと、いつからいたのか秋之介と昴が背後に佇んでいた。
「よう」
「先に来てたんだね」
二人は白百合の花束を見てから、眼前いっぱいに広がる南朱湖に視線を滑らせた。
「大分水は引いたね」
水位はもとの状態に近づいており、茶色く濁っていた色も今は目を凝らせば水底が見えるくらいには透明さを取り戻している。亡骸の葬送は先日終えたばかりだった。その中にはあかりとあかりの父の姿だけがなく、あとの朱咲本家、分家、家臣、民は皆亡くなったことも確認された。
「……どこにいるの、あかり……」
結月が胸元をおさえて、呟く。秋之介と昴はそれには何も答えず、沈痛な面持ちで俯くだけだった。
おそらく陰の国に連れ去られただろうことだけはわかるが、半月経った今も足取りは追えずにいる。一か月半前に全開となった陽の国と陰の国を隔てる結界は、こんなときに限ってかたく閉ざされ、焦る気持ちそのままに御上に奏上しようにも取り次いですらもらえなかった。四家当主である結月たちの父親は、親としては結月たちの希望に沿いたいようだったが、当主としてそれは容易に認められないとはっきりとした拒否を示してきた。
いくら四家最強と謳われる彼らであっても、たった三人、なおかつあかりが欠けた状態では為す術がないのが現実だった。
「なんで、こんなに力が足りないんだろう……」
周囲になんと称賛されようとも、あかりを、大切な女の子を護れないならば意味がない。結月が拳を握りしめると、秋之介がぽんと肩を叩いた。
「言ってても始まらないだろ。今できることをするしかねえ。だろ?」
「……そう、だね」
秋之介は満足そうに笑うと、結月の肩を組んで歩き出した。黙禱を捧げ終えた昴も後をついてくる。
「今日は艮の結界を見に行くんだっけか?」
秋之介の確認の問いに、昴が大きく頷く。
「うん、見るだけって条件付きでね。あそこの結界周辺は特に瘴気が濃いから、気を付けるようにって」
結界関連は玄舞家の担当である。昴が当主に直談判して、ようやく立ち入りの許可を得た。
「艮の結界って最初に破られたとこだよな。やっぱ鬼門だからか」
「だろうね。あそこの結界維持が一番手がかかるし」
大路小路を歩みながらあれこれ話していたが、突然結月が足を止めて、首を傾げた。
「どうした、ゆづ」
結月は無言で懐から清め包みを取り出した。中には例の式神の符を入れてある。包みを解いて、符に左手をかざすと、結月ははっと息をのんだ。
「気配が変わった……!」
秋之介と昴も大きく目を見開く。
「どういうこと?」
「あかりになんかあったってことか?」
結月は「詳しくはわからないけど……」と呟き、符を凝視した。
「気が強くなった。……もしかしたら目が覚めたとか、力が少し戻ったとか。いずれにせよ吉兆。……よかった……」
安堵の息を吐きだす結月の顔は今にも泣きだしそうなものだった。表情こそ異なるものの、昴と秋之介もほっとした様子であることには変わりない。
「早く迎えに行ってあげないとね」
「だな。どんだけ放っておくんだーって拗ねられたらかなわねえし」
あえて明るく装うが、陰の国の式神の扱いについては結月たちもよく知っている。今は無事であっても、明日の命の保証があるとは限らないのだ。どんな仕打ちを受けるかわからない。どんな環境に置かれるかわからない。気が強くなったとはいえ、一刻も早くあかりを救い出さなければいけないことに変わりはない。
「うん、あかりはひとりきり、嫌い。早く連れて帰らないと」
結月は丁寧に符を包みなおし、優しく懐に戻した。
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

【完結】貧乏令嬢の野草による領地改革
うみの渚
ファンタジー
八歳の時に木から落ちて頭を打った衝撃で、前世の記憶が蘇った主人公。
優しい家族に恵まれたが、家はとても貧乏だった。
家族のためにと、前世の記憶を頼りに寂れた領地を皆に支えられて徐々に発展させていく。
主人公は、魔法・知識チートは持っていません。
加筆修正しました。
お手に取って頂けたら嬉しいです。

【完結】転生7年!ぼっち脱出して王宮ライフ満喫してたら王国の動乱に巻き込まれた少女戦記 〜愛でたいアイカは救国の姫になる
三矢さくら
ファンタジー
【完結しました】異世界からの召喚に応じて6歳児に転生したアイカは、護ってくれる結界に逆に閉じ込められた結果、山奥でサバイバル生活を始める。
こんなはずじゃなかった!
異世界の山奥で過ごすこと7年。ようやく結界が解けて、山を下りたアイカは王都ヴィアナで【天衣無縫の無頼姫】の異名をとる第3王女リティアと出会う。
珍しい物好きの王女に気に入られたアイカは、なんと侍女に取り立てられて王宮に!
やっと始まった異世界生活は、美男美女ぞろいの王宮生活!
右を見ても左を見ても「愛でたい」美人に美少女! 美男子に美少年ばかり!
アイカとリティア、まだまだ幼い侍女と王女が数奇な運命をたどる異世界王宮ファンタジー戦記。

旦那様、前世の記憶を取り戻したので離縁させて頂きます
結城芙由奈@コミカライズ発売中
恋愛
【前世の記憶が戻ったので、貴方はもう用済みです】
ある日突然私は前世の記憶を取り戻し、今自分が置かれている結婚生活がとても理不尽な事に気が付いた。こんな夫ならもういらない。前世の知識を活用すれば、この世界でもきっと女1人で生きていけるはず。そして私はクズ夫に離婚届を突きつけた―。

主人公の恋敵として夫に処刑される王妃として転生した私は夫になる男との結婚を阻止します
白雪の雫
ファンタジー
突然ですが質問です。
あなたは【真実の愛】を信じますか?
そう聞かれたら私は『いいえ!』『No!』と答える。
だって・・・そうでしょ?
ジュリアーノ王太子の(名目上の)父親である若かりし頃の陛下曰く「私と彼女は真実の愛で結ばれている」という何が何だか訳の分からない理屈で、婚約者だった大臣の姫ではなく平民の女を妃にしたのよ!?
それだけではない。
何と平民から王妃になった女は庭師と不倫して不義の子を儲け、その不義の子ことジュリアーノは陛下が側室にも成れない身分の低い女が産んだ息子のユーリアを後宮に入れて妃のように扱っているのよーーーっ!!!
私とジュリアーノの結婚は王太子の後見になって欲しいと陛下から土下座をされてまで請われたもの。
それなのに・・・ジュリアーノは私を後宮の片隅に追いやりユーリアと毎晩「アッー!」をしている。
しかも!
ジュリアーノはユーリアと「アッー!」をするにしてもベルフィーネという存在が邪魔という理由だけで、正式な王太子妃である私を車裂きの刑にしやがるのよ!!!
マジかーーーっ!!!
前世は腐女子であるが会社では働く女性向けの商品開発に携わっていた私は【夢色の恋人達】というBLゲームの、悪役と位置づけられている王太子妃のベルフィーネに転生していたのよーーーっ!!!
思い付きで書いたので、ガバガバ設定+矛盾がある+ご都合主義。
世界観、建築物や衣装等は古代ギリシャ・ローマ神話、古代バビロニアをベースにしたファンタジー、ベルフィーネの一人称は『私』と書いて『わたくし』です。

愛していました。待っていました。でもさようなら。
彩柚月
ファンタジー
魔の森を挟んだ先の大きい街に出稼ぎに行った夫。待てども待てども帰らない夫を探しに妻は魔の森に脚を踏み入れた。
やっと辿り着いた先で見たあなたは、幸せそうでした。

魔法が使えない令嬢は住んでいた小屋が燃えたので家出します
怠惰るウェイブ
ファンタジー
グレイの世界は狭く暗く何よりも灰色だった。
本来なら領主令嬢となるはずの彼女は領主邸で住むことを許されず、ボロ小屋で暮らしていた。
彼女はある日、棚から落ちてきた一冊の本によって人生が変わることになる。
世界が色づき始めた頃、ある事件をきっかけに少女は旅をすることにした。
喋ることのできないグレイは旅を通して自身の世界を色付けていく。
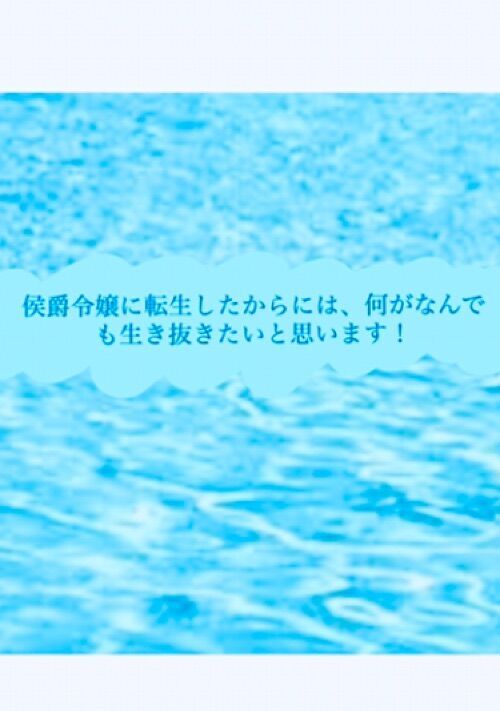
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

【完結】仰る通り、貴方の子ではありません
ユユ
恋愛
辛い悪阻と難産を経て産まれたのは
私に似た待望の男児だった。
なのに認められず、
不貞の濡れ衣を着せられ、
追い出されてしまった。
実家からも勘当され
息子と2人で生きていくことにした。
* 作り話です
* 暇つぶしにどうぞ
* 4万文字未満
* 完結保証付き
* 少し大人表現あり
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















