お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

赤い車の少女
きーぼー
ホラー
ある夏の日、少年は幽霊と出会った。
舞台となる地方都市では何ヶ月か前から自分を轢き逃げした赤い色の自動車を探す少女の幽霊が出没していた。
とある出来事がきっかけで3人の中学生の男女がこの奇妙な幽霊騒ぎに巻き込まれるのだがー。
果たして彼等はこの不可思議な事件に秘められた謎を解き明かすことができるのか?
恐怖と伝説に彩られた妖魔の夏が今始まる!!
真夏の夜の幽霊物語(ゴーストストーリー)。
是非、御一読下さい!

逢魔が時。それは人と人ならざるモノたちが出逢う時
岡本梨紅
ホラー
「逢魔が時。あなたはこの意味を、知っていますか? これは読んで字の如く、人と人ならざるモノたちが出逢う時のことをいいます。
人ならざるモノ。彼らは、人の心の闇を好みます。甘い言葉で、人間を誘惑するのです。
お聞かせいたしましょう。魔に魅入られてしまった、哀れな人間たちの末路を……」

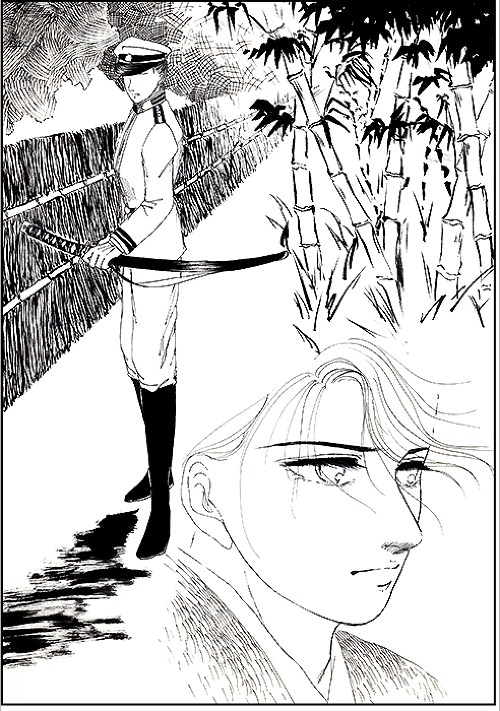
あやかしのうた
akikawa
ホラー
あやかしと人間の孤独な愛の少し不思議な物語を描いた短編集(2編)。
第1部 虚妄の家
「冷たい水底であなたの名を呼んでいた。会いたくて、哀しくて・・・」
第2部 神婚
「一族の総領以外、この儀式を誰も覗き見てはならぬ。」
好奇心おう盛な幼き弟は、その晩こっそりと神の部屋に忍び込み、美しき兄と神との秘密の儀式を覗き見たーーー。
虚空に揺れし君の袖。
汝、何故に泣く?
夢さがなく我愁うれう。
夢通わせた君憎し。
想いとどめし乙女が心の露(なみだ)。
哀しき愛の唄。

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!


傷心中の女性のホラーAI話
月歌(ツキウタ)
ホラー
傷心中の女性のホラー話を500文字以内で。AIが考える傷心とは。
☆月歌ってどんな人?こんな人↓↓☆
『嫌われ悪役令息は王子のベッドで前世を思い出す』が、アルファポリスの第9回BL小説大賞にて奨励賞を受賞(#^.^#)
その後、幸運な事に書籍化の話が進み、2023年3月13日に無事に刊行される運びとなりました。49歳で商業BL作家としてデビューさせていただく機会を得ました。
☆表紙絵、挿絵は全てAIイラスです

愛された青年は、生贄に
製作する黒猫
ホラー
自然に囲まれ、都市から隔絶された村。そこは昔森の神に生贄を捧げていたらしい。
そんな森で、少女は一人の青年と出会う。
「あなたが、昔いけにえにされた、可哀そうな人?」
誰からも愛された青年が、いけにえにされた理由とは?
小説家になろうにも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















