28 / 53
第28話 館長と副館長は了解にいたる
しおりを挟む最後はひとりで出ていってしまったし、勝手に期待して、また気持ちを落とされるのはつらい。できるだけ楽観的な憶測はしないようにしなくっちゃ。
昨夜の彼の言葉の一部が、脳内によみがえってくる。
『俺が、どれだけ我慢してきたと思っている』
『知らなかったか? 媚薬など飲まなくても、俺はいつでもきみに欲情している』
まるでわたしに興味があるかのような言い方。でも、きっと女性みんなにささやいているリップサービスなのだ。だって『こういうことは、もっと心身ともに成長してからでないと』って言っていたもの。
しかも、わたしから誘惑したのに号泣して終わるなんて、子ども扱いされても当然だ。
「そのうえ、不甲斐なくて申し訳ございませんでした」
わたしとクリストフの間の変な空気に気づいたのか、周囲に控えているメイドたちが目を見合わせている。
どうしよう。メイドたちは主人夫婦がまだ初夜を迎えていないという事実を知っているはずだ。これまでシーツが汚れていたこともないし、わたしの体に愛された痕跡が残っていたこともない。
そして、昨夜なにかがあったらしいというのも薄々わかっているはず。
情けなくて、また恥ずかしさが込み上げてくる。
頬がかっと熱くなった。
きっとわたしも、クリストフに負けないくらい赤くなっているだろう。
彼もやっと周囲の目に気づいたのか、小声で話を続けた。
「きみは悪くない。いや……やっぱりきみが悪いのか?」
「え? わたくしがなんですの?」
クリストフのつぶやきが低すぎて聞き取りづらい。
「きみが、か、かわいすぎて……なんでもない」
「はい? かかわ? 今、なんておっしゃいました?」
さらに小さな声でブツブツと言っているので聞き直すと、クリストフはまた黙ってしまった。
居心地の悪い沈黙が流れる。
なんだかあまりに意思の疎通が取れなくて、どんどん悲しくなってきてしまった。
もともとなかった食欲が完全に消え、わたしはカトラリーをテーブルに戻した。
しばらく無言だったクリストフが、ふたたび口を開く。
「明日から王族の地方視察に同行する。ひと月ほど留守にするが、大丈夫か?」
「そういえば、明日からでしたか」
結婚式の前から話は聞いていたけれど、わたしが準備することはなにもないと言われていたし、今日まで話題にものぼらなかったので忘れかけていた。
クリストフの仕事は、王族を警護する近衛騎士団の騎士団長。王族の行くところには伺候しなければならない。
とくに今回は長期の視察になるので、団長自ら指揮を取るのだろう。
最初にその話を告げられたときは、新婚早々長期出張なんて王族も気が利かないと内心思っていたけれど、もしかしたらちょうどいいタイミングかもしれない。
(わたしもいい加減頭を冷やして、クリストフさまとの関係に向き合わなくちゃ)
クリストフが帰ってくるまでに、今後自分がどうしていくのか態度を決めよう。
わたしはどういう妻を目指すのか、どんな夫婦関係を築いていきたいのか。
思えば彼と婚約できてから浮かれてばかりで、具体的な未来のことなど考えもしなかった。結婚さえすれば甘くて幸せな生活が待っていると、無邪気に信じていた。
「クリストフさまの無事のお帰りをお待ちしております」
そんなわたしをクリストフがじっと見つめていた。
その視線が鋭すぎて、やっぱりわたしは嫌われてしまったのかとますますつらい気持ちになったのだった。
793
お気に入りに追加
1,356
あなたにおすすめの小説

俺は北国の王子の失脚を狙う悪の側近に転生したらしいが、寒いのは苦手なのでトンズラします
椿谷あずる
BL
ここはとある北の国。綺麗な金髪碧眼のイケメン王子様の側近に転生した俺は、どうやら彼を失脚させようと陰謀を張り巡らせていたらしい……。いやいや一切興味がないし!寒いところ嫌いだし!よし、やめよう!
こうして俺は逃亡することに決めた。

白い結婚三年目。つまり離縁できるまで、あと七日ですわ旦那様。
あさぎかな@電子書籍二作目発売中
恋愛
異世界に転生したフランカは公爵夫人として暮らしてきたが、前世から叶えたい夢があった。パティシエールになる。その夢を叶えようと夫である王国財務総括大臣ドミニクに相談するも答えはノー。夫婦らしい交流も、信頼もない中、三年の月日が近づき──フランカは賭に出る。白い結婚三年目で離縁できる条件を満たしていると迫り、夢を叶えられないのなら離縁すると宣言。そこから公爵家一同でフランカに考え直すように動き、ドミニクと話し合いの機会を得るのだがこの夫、山のように隠し事はあった。
無言で睨む夫だが、心の中は──。
【詰んだああああああああああ! もうチェックメイトじゃないか!? 情状酌量の余地はないと!? ああ、どうにかして侍女の準備を阻まなければ! いやそれでは根本的な解決にならない! だいたいなぜ後妻? そんな者はいないのに……。ど、どどどどどうしよう。いなくなるって聞いただけで悲しい。死にたい……うう】
4万文字ぐらいの中編になります。
※小説なろう、エブリスタに記載してます
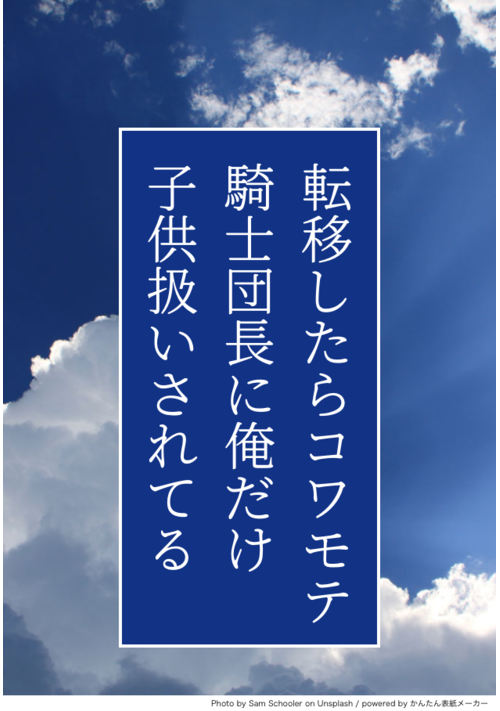
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

【コミカライズ2月28日引き下げ予定】実は白い結婚でしたの。元悪役令嬢は未亡人になったので今度こそ推しを見守りたい。
氷雨そら
恋愛
悪役令嬢だと気がついたのは、断罪直後。
私は、五十も年上の辺境伯に嫁いだのだった。
「でも、白い結婚だったのよね……」
奥様を愛していた辺境伯に、孫のように可愛がられた私は、彼の亡き後、王都へと戻ってきていた。
全ては、乙女ゲームの推しを遠くから眺めるため。
一途な年下枠ヒーローに、元悪役令嬢は溺愛される。
断罪に引き続き、私に拒否権はない……たぶん。

聖女召喚されて『お前なんか聖女じゃない』って断罪されているけど、そんなことよりこの国が私を召喚したせいで滅びそうなのがこわい
金田のん
恋愛
自室で普通にお茶をしていたら、聖女召喚されました。
私と一緒に聖女召喚されたのは、若くてかわいい女の子。
勝手に召喚しといて「平凡顔の年増」とかいう王族の暴言はこの際、置いておこう。
なぜなら、この国・・・・私を召喚したせいで・・・・いまにも滅びそうだから・・・・・。
※小説家になろうさんにも投稿しています。

政略より愛を選んだ結婚。~後悔は十年後にやってきた。~
つくも茄子
恋愛
幼い頃からの婚約者であった侯爵令嬢との婚約を解消して、学生時代からの恋人と結婚した王太子殿下。
政略よりも愛を選んだ生活は思っていたのとは違っていた。「お幸せに」と微笑んだ元婚約者。結婚によって去っていた側近達。愛する妻の妃教育がままならない中での出産。世継ぎの王子の誕生を望んだものの産まれたのは王女だった。妻に瓜二つの娘は可愛い。無邪気な娘は欲望のままに動く。断罪の時、全てが明らかになった。王太子の思い描いていた未来は元から無かったものだった。後悔は続く。どこから間違っていたのか。
他サイトにも公開中。

そばかす糸目はのんびりしたい
楢山幕府
BL
由緒ある名家の末っ子として生まれたユージン。
母親が後妻で、眉目秀麗な直系の遺伝を受け継がなかったことから、一族からは空気として扱われていた。
ただ一人、溺愛してくる老いた父親を除いて。
ユージンは、のんびりするのが好きだった。
いつでも、のんびりしたいと思っている。
でも何故か忙しい。
ひとたび出張へ出れば、冒険者に囲まれる始末。
いつになったら、のんびりできるのか。もう開き直って、のんびりしていいのか。
果たして、そばかす糸目はのんびりできるのか。
懐かれ体質が好きな方向けです。今のところ主人公は、のんびり重視の恋愛未満です。
全17話、約6万文字。

愛されない皇妃~最強の母になります!~
椿蛍
ファンタジー
愛されない皇妃『ユリアナ』
やがて、皇帝に愛される寵妃『クリスティナ』にすべてを奪われる運命にある。
夫も子どもも――そして、皇妃の地位。
最後は嫉妬に狂いクリスティナを殺そうとした罪によって処刑されてしまう。
けれど、そこからが問題だ。
皇帝一家は人々を虐げ、『悪逆皇帝一家』と呼ばれるようになる。
そして、最後は大魔女に悪い皇帝一家が討伐されて終わるのだけど……
皇帝一家を倒した大魔女。
大魔女の私が、皇妃になるなんて、どういうこと!?
※表紙は作成者様からお借りしてます。
※他サイト様に掲載しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















