お気に入りに追加
1,272
あなたにおすすめの小説

白い結婚三年目。つまり離縁できるまで、あと七日ですわ旦那様。
あさぎかな@電子書籍二作目発売中
恋愛
異世界に転生したフランカは公爵夫人として暮らしてきたが、前世から叶えたい夢があった。パティシエールになる。その夢を叶えようと夫である王国財務総括大臣ドミニクに相談するも答えはノー。夫婦らしい交流も、信頼もない中、三年の月日が近づき──フランカは賭に出る。白い結婚三年目で離縁できる条件を満たしていると迫り、夢を叶えられないのなら離縁すると宣言。そこから公爵家一同でフランカに考え直すように動き、ドミニクと話し合いの機会を得るのだがこの夫、山のように隠し事はあった。
無言で睨む夫だが、心の中は──。
【詰んだああああああああああ! もうチェックメイトじゃないか!? 情状酌量の余地はないと!? ああ、どうにかして侍女の準備を阻まなければ! いやそれでは根本的な解決にならない! だいたいなぜ後妻? そんな者はいないのに……。ど、どどどどどうしよう。いなくなるって聞いただけで悲しい。死にたい……うう】
4万文字ぐらいの中編になります。
※小説なろう、エブリスタに記載してます

俺は北国の王子の失脚を狙う悪の側近に転生したらしいが、寒いのは苦手なのでトンズラします
椿谷あずる
BL
ここはとある北の国。綺麗な金髪碧眼のイケメン王子様の側近に転生した俺は、どうやら彼を失脚させようと陰謀を張り巡らせていたらしい……。いやいや一切興味がないし!寒いところ嫌いだし!よし、やめよう!
こうして俺は逃亡することに決めた。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

お兄様の指輪が壊れたら、溺愛が始まりまして
みこと。
恋愛
お兄様は女王陛下からいただいた指輪を、ずっと大切にしている。
きっと苦しい片恋をなさっているお兄様。
私はただ、お兄様の家に引き取られただけの存在。血の繋がってない妹。
だから、早々に屋敷を出なくては。私がお兄様の恋路を邪魔するわけにはいかないの。私の想いは、ずっと秘めて生きていく──。
なのに、ある日、お兄様の指輪が壊れて?
全7話、ご都合主義のハピエンです! 楽しんでいただけると嬉しいです!
※「小説家になろう」様にも掲載しています。
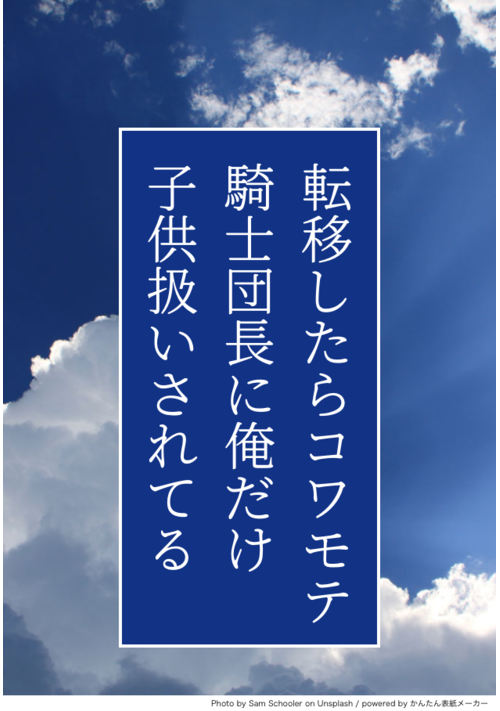
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

急に運命の番と言われても。夜会で永遠の愛を誓われ駆け落ちし、数年後ぽい捨てされた母を持つ平民娘は、氷の騎士の甘い求婚を冷たく拒む。
石河 翠
恋愛
ルビーの花屋に、隣国の氷の騎士ディランが現れた。
雪豹の獣人である彼は番の匂いを追いかけていたらしい。ところが花屋に着いたとたんに、手がかりを失ってしまったというのだ。
一時的に鼻が詰まった人間並みの嗅覚になったディランだが、番が見つかるまでは帰らないと言い張る始末。ルビーは彼の世話をする羽目に。
ルビーと喧嘩をしつつ、人間についての理解を深めていくディラン。
その後嗅覚を取り戻したディランは番の正体に歓喜し、公衆の面前で結婚を申し込むが冷たく拒まれる。ルビーが求婚を断ったのには理由があって……。
愛されることが怖い臆病なヒロインと、彼女のためならすべてを捨てる一途でだだ甘なヒーローの恋物語。
この作品は、他サイトにも投稿しております。
扉絵は写真ACより、チョコラテさまの作品(ID25481643)をお借りしています。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

転生先がヒロインに恋する悪役令息のモブ婚約者だったので、推しの為に身を引こうと思います
結城芙由奈@12/27電子書籍配信
恋愛
【だって、私はただのモブですから】
10歳になったある日のこと。「婚約者」として現れた少年を見て思い出した。彼はヒロインに恋するも報われない悪役令息で、私の推しだった。そして私は名も無いモブ婚約者。ゲームのストーリー通りに進めば、彼と共に私も破滅まっしぐら。それを防ぐにはヒロインと彼が結ばれるしか無い。そこで私はゲームの知識を利用して、彼とヒロインとの仲を取り持つことにした――
※他サイトでも投稿中
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















