お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

地獄の上司
マーベル4
ホラー
美希25歳は新しい就職先が決まりなんとなくホッとしていたが
一つ気になることがあった
短期間でやめてしまう人が多いということだった
美希が思っていたことはそうかるいことではなかった
「まさか上司しなわけないか」とつぶきやく
美希は前の職場で上司に悪口やなんとなく合わなかった
のでやめたのだ
そのせいか上司との関係にトラウマができてしまった
その原因がわかるにつれ美希は残酷な被害に襲われる
一体なにが原因なのか...
次は私の番なのかもしれない
怖いのはお化けてはなく人間
人間関係の怖さを描いた短編ホラー小説

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活
XD
恋愛
誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。

我らおっさん・サークル「異世界召喚予備軍」
虚仮橋陣屋(こけばしじんや)
青春
おっさんの、おっさんによる、おっさんのためのほろ苦い青春ストーリー
サラリーマン・寺崎正・四〇歳。彼は何処にでもいるごく普通のおっさんだ。家族のために黙々と働き、家に帰って夕食を食べ、風呂に入って寝る。そんな真面目一辺倒の毎日を過ごす、無趣味な『つまらない人間』がある時見かけた奇妙なポスターにはこう書かれていた――サークル「異世界召喚予備軍」、メンバー募集!と。そこから始まるちょっと笑えて、ちょっと勇気を貰えて、ちょっと泣ける、おっさんたちのほろ苦い青春ストーリー。

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
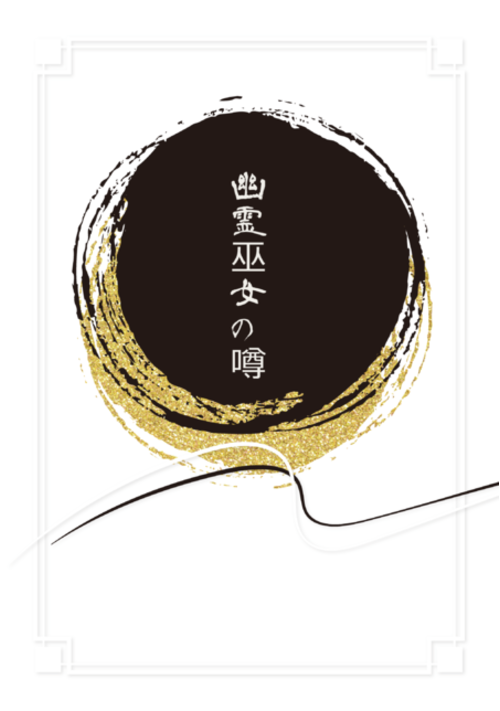
幽霊巫女の噂【読み切り版】
れく
ホラー
先に連載していたシリーズ『幽霊巫女の噂』第一章『蛇帯』を設定見直し・構成を練り直した読み切り版です。
舞台は八野坂町ですが、キャラクター設定・基本設定が既存のシリーズより大きく異なっています。
以下、あらすじ
ネット・電話・場所。あらゆる制約に縛られず、本当に困っている人々の元に『幽霊巫女』は現れる。そんな噂を頼りに命の危機を感じながら、樺倉望の呪い『蛇帯』に追い詰められていた新條涼佑は死の間際、幽霊巫女さんが住むとされている『願いを叶える神社』に迷い込む。彼を『客』として迎えた巫女とその式神・八坂童子は彼の願いを叶えると約束した上で、どうしてここまでのことになってしまったのか訳を訊く。生きながら『死んで』しまった涼佑は、自分の体験した出来事を話し始めるのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















