2 / 18
二話
しおりを挟むもうすぐ日を跨ごうとしている時計を盗み見て、未汐は小さく溜息を吐いた。
あの後、父の車に乗せられて、県内でも有数の大病院に連れてこられた。地域住民に「金の使い所を間違えている」などと陰口を叩かれている豪勢な正面玄関は閉じられているため、夜間救急の出入口を使う。
車を出ると、ほとんど寝巻きのままの女性が立っていた。年は五十代後半と言ったところで、肩を過ぎたくらいの長さの明るい茶髪を雑に後ろで纏めている。父は未汐に、僕の姉さんだよ、と耳打ちした。面識は無いが、叔母と言うことになる。未汐が軽く会釈をすると、ふん、と鼻を鳴らした女性が父に何事か言っていたようだが、よく聞き取れなかった。
病室には入れて貰えなかった。集まった親戚の無言の圧が、未汐の入室を許さなかったのだ。父は申し訳なさそうに肩を竦めて、送っていくからもう少し待っていてと曖昧に笑っている。
態々連れて来ておいてそれかとも思ったが、死にかけている人間を目の当たりにして嫌味を言えるほど豪胆でも無遠慮でもないので黙っていた。
暇を持て余した未汐は、病室から少し離れたエレベーターホール横の、共有スペースにある椅子に腰掛ける。消灯後の病院は最低限の灯りのみで薄暗く、やはり不気味だった。長い廊下の向こうに誰かが立っている気がする。
次にエレベーターの扉が開いたら、そこに乗っているのは人間だろうか?ざわざわと全身の産毛が震えるのが分かる。呼吸が浅くなり、些細な物音にさえ敏感になってしまう。気にしないようにしようとすればするほど「それ」が輪郭を濃くしていくように思えて、未汐は目を強く瞑って頭を振った。変な手紙を見たせいか、疲れているのかも知れない。
嫌でもあの手紙のことを考えてしまう。短い文面が尚のこと不気味だった。汚い紙と赤黒い文字が生理的嫌悪をこれでもかと煽り立ててくる。「みつけた」と言われても、未汐には何のことを言っているのか見当もつかない。
こんな悪趣味な悪戯をする友人は思い当たらず、ストーカーに遭うような心当たりも無かった。
何度目かの溜息を漏らして目を開けると、未汐の足元に小さな、顔のふやけた乳児が這いつくばってニタニタと笑っていた。
「あ」
ヒュッ、と呼吸が喉の奥で堰き止められて、脂汗が吹き出す。その乳児は張り付いたような満面の笑みを浮かべながら、未汐の右足首を掴んだ。
ま、ま、ま
ごぼごぼと小さな口から黄色い泡を吹いて、まるで溺れながら喋っているようだった。掴まれた右足がじっとりと濡れているのが分かる。
乳児の身体には所々にフジツボや蜂の巣を思わせる密集した穴が空いていた。本能的な恐怖でざわざわと背筋が粟立つ。椅子の上によじ登ったそいつは眼球が溶けて無くなってしまったかのような空っぽの眼窩をめいっぱい細めて、痰が絡んだような甲高い笑い声を上げた。
それはっきりとした発音で未汐を「まま」と呼んで、未汐の腹に触れる。
絞られるような、内側から刺されるような激痛が下腹部を襲った。酷い生理痛のような痛みに、意識が朦朧としていく。
そこから先の記憶は無い。
父に揺すられて目を覚ました。いつの間にか眠ってしまっていたらしい。乳児は跡形もなく姿を消していて、眩しいほどの蛍光灯の光が共有スペースを照らしていた。
救急搬送口付近の駐車場に停められていた父の車に乗り込んで帰途につく。ナビの時計は午前四時を示していた。カーステレオから流れる平成初期に流行ったらしい女性歌手の流暢な英語だけが、車内を満たしている。
「みっちゃん」
「なーに」
「今日はごめんね」
「いいよ」
おじいちゃんな、だめだったよ、と父が絞り出すように言った。
未汐が病室を締め出されてホラー映画さながらの恐怖体験をしている頃、祖父は苦しみながら息を引き取ったと言う。小さい頃の祖父に関しての記憶が殆ど無い未汐は大した悲しみも持てず、ただ頷くことしか出来なかった。
「何でわたしのこと呼んだの」
結局未汐は祖父の死に立ち会えなかったばかりか、病室に入ることすら許されなかったのだ。これではただ親戚連中に渋い顔をされるために出向いたようなものだし、そもそも病院に行かなければあんな化け物じみた乳児に母親呼ばわりされることも無かった。
父は空いた方の手で頭をガリガリと掻き、数秒考え込んだあと口を開いた。
「おじいちゃんがね、みっちゃんのこと呼んだんだよ」
「なに?」
「おじいちゃん、ここ二週間くらいずっと意識が無かったんだ。それが昨夜顔を見に行ったら、突然ぱっと目を開けて「未汐を連れて来い」って言ったんだよね」
予想外の父の答えに、返事に詰まってしまう。
未汐は祖父の顔を殆ど覚えていない。最後に会ったのは、十数年前かその辺りだ。
未汐は十歳前後より前の記憶がごっそり抜け落ちている。両親からは足を滑らせ階段から転落して、その影響で一部の記憶が消失したのだと聞いた。
それ以上の後遺症は無く、生活に支障もきたしていないので放置している。
だから、記憶が消失するよりも前に祖父と会っていて、話をしていたとしても、遊んで貰っていたとしても、覚えていないのだ。何だか申し訳ない気持ちになって俯くと、足元の暗がりからあの乳児が湧いて出てきそうで、体の奥から震えが来る。
顔を上げると、自宅アパートの近くまで差し掛かっていた。父は、葬儀には無理して来なくてもいいと言う。行っても良かったけれど、またあの親戚たちと顔を合わせるのは御免だった。未汐は素直に頷いて、鞄から部屋の鍵を取り出す。
アパート脇に止まった車から降りて、運転席を覗き込んだ。
「気をつけて帰ってね」
「みっちゃん」
「なに」
「何か変なことがあったら、すぐに連絡してきなさい」
いいね?と、父は念を押した。
穏やかで気弱な彼らしくなく、芯を持った強い声音だ。
一瞬、手紙と先程の乳児のことが頭を掠める。しかし、これから祖父の葬儀の手続きや仕事のスケジュールの調整などで忙しくなるだろう父に、そんなことを相談出来るわけもなかった。話すにしても今である必要は無い。祖父のことが落ち着いてからでも充分だ。
「わかったよ、何かあったら連絡するね」
未汐が笑いながら言うと、父は安心したように息を吐いた。助手席のドアを閉めて、走っていく父の車に手を振る。
錆びた階段を登り、一番奥の部屋の前に立つ。二〇五号室、角部屋だ。ポストには何も入っていない。
鍵を開けて玄関で靴を脱ぎ捨て、ベッドに寝転がる。着替えるのも、靴下を脱ぐのも億劫だった。外は夜明け独特の赤紫に覆われている。
手紙はテーブルの上に放られていた。これがホラー映画なら内容が変わっていたり、手紙そのものが消えてなくなっていたりするものだが、そんなことは起こらなかった。仰向けになって、ぼんやりと天井を眺める。
葬儀に行かないにしても祖父が死んだのは事実なのだから、バイトを休んでも許されるのでは、などと考えていた。下腹部の痛みは殆どなりを潜めている。
携帯のアラームを三時間後に設定して、未汐は押し寄せる眠気に意識を手放した。
あの後、父の車に乗せられて、県内でも有数の大病院に連れてこられた。地域住民に「金の使い所を間違えている」などと陰口を叩かれている豪勢な正面玄関は閉じられているため、夜間救急の出入口を使う。
車を出ると、ほとんど寝巻きのままの女性が立っていた。年は五十代後半と言ったところで、肩を過ぎたくらいの長さの明るい茶髪を雑に後ろで纏めている。父は未汐に、僕の姉さんだよ、と耳打ちした。面識は無いが、叔母と言うことになる。未汐が軽く会釈をすると、ふん、と鼻を鳴らした女性が父に何事か言っていたようだが、よく聞き取れなかった。
病室には入れて貰えなかった。集まった親戚の無言の圧が、未汐の入室を許さなかったのだ。父は申し訳なさそうに肩を竦めて、送っていくからもう少し待っていてと曖昧に笑っている。
態々連れて来ておいてそれかとも思ったが、死にかけている人間を目の当たりにして嫌味を言えるほど豪胆でも無遠慮でもないので黙っていた。
暇を持て余した未汐は、病室から少し離れたエレベーターホール横の、共有スペースにある椅子に腰掛ける。消灯後の病院は最低限の灯りのみで薄暗く、やはり不気味だった。長い廊下の向こうに誰かが立っている気がする。
次にエレベーターの扉が開いたら、そこに乗っているのは人間だろうか?ざわざわと全身の産毛が震えるのが分かる。呼吸が浅くなり、些細な物音にさえ敏感になってしまう。気にしないようにしようとすればするほど「それ」が輪郭を濃くしていくように思えて、未汐は目を強く瞑って頭を振った。変な手紙を見たせいか、疲れているのかも知れない。
嫌でもあの手紙のことを考えてしまう。短い文面が尚のこと不気味だった。汚い紙と赤黒い文字が生理的嫌悪をこれでもかと煽り立ててくる。「みつけた」と言われても、未汐には何のことを言っているのか見当もつかない。
こんな悪趣味な悪戯をする友人は思い当たらず、ストーカーに遭うような心当たりも無かった。
何度目かの溜息を漏らして目を開けると、未汐の足元に小さな、顔のふやけた乳児が這いつくばってニタニタと笑っていた。
「あ」
ヒュッ、と呼吸が喉の奥で堰き止められて、脂汗が吹き出す。その乳児は張り付いたような満面の笑みを浮かべながら、未汐の右足首を掴んだ。
ま、ま、ま
ごぼごぼと小さな口から黄色い泡を吹いて、まるで溺れながら喋っているようだった。掴まれた右足がじっとりと濡れているのが分かる。
乳児の身体には所々にフジツボや蜂の巣を思わせる密集した穴が空いていた。本能的な恐怖でざわざわと背筋が粟立つ。椅子の上によじ登ったそいつは眼球が溶けて無くなってしまったかのような空っぽの眼窩をめいっぱい細めて、痰が絡んだような甲高い笑い声を上げた。
それはっきりとした発音で未汐を「まま」と呼んで、未汐の腹に触れる。
絞られるような、内側から刺されるような激痛が下腹部を襲った。酷い生理痛のような痛みに、意識が朦朧としていく。
そこから先の記憶は無い。
父に揺すられて目を覚ました。いつの間にか眠ってしまっていたらしい。乳児は跡形もなく姿を消していて、眩しいほどの蛍光灯の光が共有スペースを照らしていた。
救急搬送口付近の駐車場に停められていた父の車に乗り込んで帰途につく。ナビの時計は午前四時を示していた。カーステレオから流れる平成初期に流行ったらしい女性歌手の流暢な英語だけが、車内を満たしている。
「みっちゃん」
「なーに」
「今日はごめんね」
「いいよ」
おじいちゃんな、だめだったよ、と父が絞り出すように言った。
未汐が病室を締め出されてホラー映画さながらの恐怖体験をしている頃、祖父は苦しみながら息を引き取ったと言う。小さい頃の祖父に関しての記憶が殆ど無い未汐は大した悲しみも持てず、ただ頷くことしか出来なかった。
「何でわたしのこと呼んだの」
結局未汐は祖父の死に立ち会えなかったばかりか、病室に入ることすら許されなかったのだ。これではただ親戚連中に渋い顔をされるために出向いたようなものだし、そもそも病院に行かなければあんな化け物じみた乳児に母親呼ばわりされることも無かった。
父は空いた方の手で頭をガリガリと掻き、数秒考え込んだあと口を開いた。
「おじいちゃんがね、みっちゃんのこと呼んだんだよ」
「なに?」
「おじいちゃん、ここ二週間くらいずっと意識が無かったんだ。それが昨夜顔を見に行ったら、突然ぱっと目を開けて「未汐を連れて来い」って言ったんだよね」
予想外の父の答えに、返事に詰まってしまう。
未汐は祖父の顔を殆ど覚えていない。最後に会ったのは、十数年前かその辺りだ。
未汐は十歳前後より前の記憶がごっそり抜け落ちている。両親からは足を滑らせ階段から転落して、その影響で一部の記憶が消失したのだと聞いた。
それ以上の後遺症は無く、生活に支障もきたしていないので放置している。
だから、記憶が消失するよりも前に祖父と会っていて、話をしていたとしても、遊んで貰っていたとしても、覚えていないのだ。何だか申し訳ない気持ちになって俯くと、足元の暗がりからあの乳児が湧いて出てきそうで、体の奥から震えが来る。
顔を上げると、自宅アパートの近くまで差し掛かっていた。父は、葬儀には無理して来なくてもいいと言う。行っても良かったけれど、またあの親戚たちと顔を合わせるのは御免だった。未汐は素直に頷いて、鞄から部屋の鍵を取り出す。
アパート脇に止まった車から降りて、運転席を覗き込んだ。
「気をつけて帰ってね」
「みっちゃん」
「なに」
「何か変なことがあったら、すぐに連絡してきなさい」
いいね?と、父は念を押した。
穏やかで気弱な彼らしくなく、芯を持った強い声音だ。
一瞬、手紙と先程の乳児のことが頭を掠める。しかし、これから祖父の葬儀の手続きや仕事のスケジュールの調整などで忙しくなるだろう父に、そんなことを相談出来るわけもなかった。話すにしても今である必要は無い。祖父のことが落ち着いてからでも充分だ。
「わかったよ、何かあったら連絡するね」
未汐が笑いながら言うと、父は安心したように息を吐いた。助手席のドアを閉めて、走っていく父の車に手を振る。
錆びた階段を登り、一番奥の部屋の前に立つ。二〇五号室、角部屋だ。ポストには何も入っていない。
鍵を開けて玄関で靴を脱ぎ捨て、ベッドに寝転がる。着替えるのも、靴下を脱ぐのも億劫だった。外は夜明け独特の赤紫に覆われている。
手紙はテーブルの上に放られていた。これがホラー映画なら内容が変わっていたり、手紙そのものが消えてなくなっていたりするものだが、そんなことは起こらなかった。仰向けになって、ぼんやりと天井を眺める。
葬儀に行かないにしても祖父が死んだのは事実なのだから、バイトを休んでも許されるのでは、などと考えていた。下腹部の痛みは殆どなりを潜めている。
携帯のアラームを三時間後に設定して、未汐は押し寄せる眠気に意識を手放した。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

機織姫
ワルシャワ
ホラー
栃木県日光市にある鬼怒沼にある伝説にこんな話がありました。そこで、とある美しい姫が現れてカタンコトンと音を鳴らす。声をかけるとその姫は一変し沼の中へ誘うという恐ろしい話。一人の少年もまた誘われそうになり、どうにか命からがら助かったというが。その話はもはや忘れ去られてしまうほど時を超えた現代で起きた怖いお話。はじまりはじまり
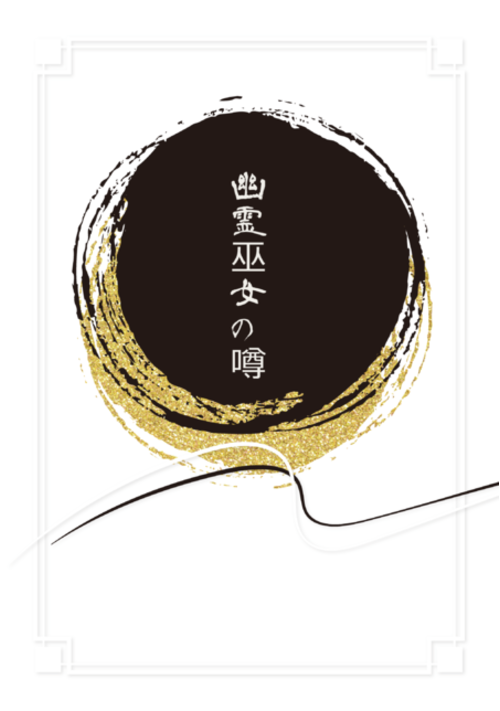
幽霊巫女の噂【読み切り版】
れく
ホラー
先に連載していたシリーズ『幽霊巫女の噂』第一章『蛇帯』を設定見直し・構成を練り直した読み切り版です。
舞台は八野坂町ですが、キャラクター設定・基本設定が既存のシリーズより大きく異なっています。
以下、あらすじ
ネット・電話・場所。あらゆる制約に縛られず、本当に困っている人々の元に『幽霊巫女』は現れる。そんな噂を頼りに命の危機を感じながら、樺倉望の呪い『蛇帯』に追い詰められていた新條涼佑は死の間際、幽霊巫女さんが住むとされている『願いを叶える神社』に迷い込む。彼を『客』として迎えた巫女とその式神・八坂童子は彼の願いを叶えると約束した上で、どうしてここまでのことになってしまったのか訳を訊く。生きながら『死んで』しまった涼佑は、自分の体験した出来事を話し始めるのだった。

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

サトウヒロシ
白い黒猫
ホラー
平凡な名前と平凡な容姿をもつ、この日本で最も凡庸な男ともいえる【サトウヒロシ】。
サトウヒロシという男に降りかかる様々な災難。
平凡な名前の男の非凡な運命を描いた短編集。
サトウヒロシという男が巻き込まれた様々な奇妙は出来事を描いたホラー短編集。

ラ・プラスの島
輪島ライ
ホラー
恋愛シミュレーションゲーム「ラ・プラス」最新作の海外展開のためアメリカに向かっていたゲーム制作者は、飛行機事故により海上を漂流することになる。通りがかった漁船に救われ、漁民たちが住む島へと向かった彼が見たものとは……
※この作品は「小説家になろう」「アルファポリス」「カクヨム」「エブリスタ」に投稿しています。

#彼女を探して・・・
杉 孝子
ホラー
佳苗はある日、SNSで不気味なハッシュタグ『#彼女を探して』という投稿を偶然見かける。それは、特定の人物を探していると思われたが、少し不気味な雰囲気を醸し出していた。日が経つにつれて、そのタグの投稿が急増しSNS上では都市伝説の話も出始めていた。

「僕」と「彼女」の、夏休み~おんぼろアパートの隣人妖怪たちによるよくある日常~
石河 翠
ホラー
夏休み中につき、おんぼろアパートでのんびり過ごす主人公。このアパートに住む隣人たちはみな現代に生きる妖(あやかし)だが、主人公から見た日常はまさに平和そのものである。
主人公の恋人である雪女はバイトに明け暮れているし、金髪褐色ギャルの河童は海辺で逆ナンばかりしている。猫又はのんびり町内を散歩し、アパートの管理人さんはいつも笑顔だ。
ところが雪女には何やら心配事があるようで、主人公に内緒でいろいろと画策しているらしい。実は主人公には彼自身が気がついていない秘密があって……。
ごくごく普通の「僕」と雪女によるラブストーリー。
「僕」と妖怪たちの視点が交互にきます。「僕」視点ではほのぼの日常、妖怪視点では残酷な要素ありの物語です。ホラーが苦手な方は、「僕」視点のみでどうぞ。
扉絵は、遥彼方様に描いて頂きました。ありがとうございます。
この作品は、小説家になろうにも投稿しております。
また、小説家になろうで投稿しております短編集「『あい』を失った女」より「『おばけ』なんていない」(2018年7月3日投稿)、「『ほね』までとろける熱帯夜」(2018年8月14日投稿) 、「『こまりました』とは言えなくて」(2019年5月20日投稿)をもとに構成しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















