7 / 27
第七話
しおりを挟む
いつも宴は苦手だ。つまらない話がよく次々に口から出てくるものだ。
作り笑いを浮かべて、話を楽しんでいるふりをする。そうしなければ、彼らの機嫌を損ねてしまう。
こんな時にボイコットをされるとたまったものじゃない。
「姫様。大丈夫でございますか?」
そう言ってから、ヴァンは新しいエールを銅製の盃に注いでくれた。私は少しだけ疲れた顔をして笑みを返す。そうしてから、小さく切られたチーズを摘まんで食べる。少しだけ柔らかく、この独特の風味は酒の味によく合う。
椅子に大きく腰を掛けて、夜空をみた。
中央に燃えているかがり火は、弱弱しい星の光を飲み込んでしまっている。見えるのは一番大きい星だけ。
今頃、フィオ達も宴を始めている頃だろう。大きな初戦は勝利に終わった。
次の戦争に備えなくてはいけませんね。
「ヴァン?少しこちらに」
足を組み替えてから、ヴァンに対して手招きをした。私の左側に片足を着いて顔を近づける。ヴァンの耳に口を近づけて片手で口の動きを読まれない様にする。
「精鋭を10名ほどあなたの軍隊から抜き出してください。敵拠点に対して襲撃を行います」
ヴァンは少し驚いた表情をして聞き返した。当然だろう。夜襲は念密な作戦を立てた上に行うものだ。
「今からですか?」
「もちろん。あくまでサポートとして、参加してもらいます。主要箇所は私の1部隊で進めさせていただきますから」
私は立ち上がってから、後方に待機させている黒いフードを頭からかぶっている男に視線を送って呼び寄せる。
準備を始めてくださいと伝えると、静かに闇の中へと姿を消した。
机に立て掛けていた私のサーベルを携えて、口直しに水を一口のみ込む。すぐに終わる戦闘。酔い直しにはちょうどいい。
「私は先に行っておきますから、荷馬車を5台ほど率いて連れてきてください」
彼は小さく返事をして、場所を記した地図を渡した。
静かににぎやかな場所を離れて、黒いローブに身を包む。背中まである赤い髪を頭の後ろで団子の形にまとめた。
既に馬に跨っており、一人だけ私の馬の手綱を持ってから待っている。
その男に小さく礼を言ってから馬に乗りこんた。
「皆さん、この度は私の無茶苦茶な作戦に協力してくれてありがとうございます。あなた達は勇敢な騎士ですが、これから行う事は騎士の栄養とはかけ離れた盗賊まがいの行いです。気に食わなければ離れてもらっても構いません」
その言葉に誰一人、馬から降りる事はなかった。フードの下から見える眼光はまるで狼の様に鋭い。今夜、ここに集まった兵士は狩人になる。敵兵をひたすらに追いかけ仕留める。
私が先頭を走る。ひたすら、無心に早く走る事だけを考えて進む。
目的地は本陣営から北西側にある5キロほど離れた集落。もっと近い距離にも敵拠点が存在している事は確認済みだが、あえてここを選んだのは理由がある。フィオが討ち取った残党兵はここに居る可能性が高い。
大将を討ち取ったとはいえ、残った兵士をかき集められてしまえばそれなりの戦力になる。
それにそれだけの兵士達を受け入れる事が出来るほどの物資が集められている証拠だ。
途中で部隊を3つに分けた。それぞれ、10名ずつに分けて拠点に繋がる道へと回した。
「始めましょうか。拠点にいる人はすべて討ち取りなさい」
茂みの中に馬を隠して、地面に伏せて号令をかけた。一斉に兵士達が拠点内に飛び込んだ。
拠点は一つの物見やぐらと丸太で柵を作って拠点を円状に囲んでいるが、道の部分には見張り番が立っているだけで門はない。
中にはいくつかの家とテントが立てられて、簡易的な馬小屋と荷馬車が20ほど並んでいた。
拠点内の広場には兵たちが横たわっている。外れている漆黒の鎧を見る限りフィオが撃退した部隊だろう。衛生兵や医師たちが忙しなく働いている。
やがて拠点内に入ると、悲鳴が拠点内に鳴り響いた。
始まった。後は殲滅するだけ。そんなに多く時間は残されていない。私はゆっくりと広場へと歩みを進める。負傷兵でも勇敢に武器を持って襲ってくる。
手負いの者を手に掛ける趣味は無いですが、仕方ありませんね。
サーベルを静かに抜いて、右肩と右腕の付け根を突き刺してから、腹部を切り裂く。腹部に致命傷を与えるには、内臓に到達するほどの深さを与えれば十分だ。あとは出血して死を待つだけ。
次は手首を切り落として、頭を掴んだ。
「燃えなさい」
頭を掴んだ手に力を入れると男の全身は真っ赤な炎に包まれて、塵になってしまった。
その塵を踏みつけて、歩みを進める。私が向かう先は大きな茶色のテント。中を開いてみると、武器から小麦粉が入った麻袋に酒類やたばこなどの嗜好品で埋め尽くされいてた。これだけあれば十分。荷馬車にもまだ、この倉庫代わりにしているテントに入り切れていない物資が詰まっているだろう。
何か足首に当たる。見下ろすとそれは血にまみれた中年の女性だ。
憎悪で満たされた視線と声を振り絞って私に投げかける。
「どうしてこんなことを……!」
私は足を振り払って、サーベルで首の後ろを突き刺した。すぐに静かになる。
何を言っているのか。敵を打ち倒すのにそのような事を言ったところでどうするのか。
サーベルを振り払って、着いていた血を振り落とす。私はその転がっている肉の塊を踏みつけて、戦火の風に吹かれた。
そうして、時が経つのを静かに待つ。時折、私に向かって刃を振るう物もいた。
手負いの兵に私を傷つける事は出来ない
誰かが火を付けたのだろう。民家が真っ赤に燃えていた。その炎の中に人の影が見えた。叫び声を上げて、踊り狂うようにして苦しんでいる人の影。やがて、力尽きて影は消える。
次第に叫び声の数は少しずつ減っていき、次第に降伏した兵士が広場の中央に集められていく。
「降伏した兵士達の処遇はいかがいたしますか?」
頭に両手を置いて、跪いて皆うつ向いていた。大体20名ほどか。
その周りに剣を向けて取り囲んでいる。サーベルを静かに鞘に納めて、兵士達を見る。
「殺しなさい。残った死体は埋めてしまいましょう」
そこにいた兵士達はすぐに死体の山へと姿を変えた。後ろにはいそいそと死体埋める兵士達に背を向けて、私は振り返って拠点の入口へ向かう。遥か彼方、私達が来た方向から明かりが見える。ヴァン達だろう。
私の兵士だけになった拠点の中に馬車が5台新しく並んだ。一番最後に並んだ馬車に乗っており、着くと同時に飛び降りて私の元へと駆け寄った。
「姫様!これは一体……」
驚くのも無理が無いだろう。到着したと同時に拠点のほとんどが燃えて、敵兵士の死体を埋める私の兵士達。
「後始末です。汚れたところを掃除するのは当たり前でしょう?」
そう言い捨てて、ヴァンの隣を抜けて馬車に乗ってきた兵士達に物資が詰まったテントを指さして積み込むように指示をする。何人かは困惑した表情をしていたが、言い返す者はいない。
一瞬だけ私がサーベルで突き刺した中年女性の顔が思い浮かんだ。
これは戦争、仕方の無い事。敵兵士に情けをいくらかけたところできりが無い。
泣くも喚くもすべてが終わってからでいい。今のうちは。
「姫様。本当に敵国の兵士だけだったのですか?」
この辺りは先の戦争で義勇軍が立ち上がりほとんど虐殺に近い形で撃退されてしまったと聞く。
あの中年女性は私の顔を知っているような表情をしていた。しかし、私の顔を敵国の市民までが知っていても可笑しくはない。それに、戦争中の敵国王族を知らない方が不思議。知らなかったとしてもよほど自国の事に興味が無いのだろう。
「無論です。先ほどの負傷兵を看護していましたから」
ヴァンはそれ以上は何も言わなかった。難しい顔だけをしている。
今は理解して貰おうとは思わない。そう、私を理解してくれる人なんていないのだから。
強く胸の紅いペンダントを両手で握り占めた。今は迷う事はやめよう。
すべて荷台に積み込まれるまではあっという間だった。すぐに撤収を始めさせ、急いで本陣に戻る。
本陣に戻るまでは密偵に見られてしまっては意味がない。
荷馬車を囲んだ黒いローブに身を包んだ兵士達。私はヴァンが操縦する最後列の荷台に乗って、燃やし尽くされた拠点が小さくなっていくのをただ眺める。
「ヴァン。あなたは何のために戦うのですか?」
屋根のない荷台から雲の無い空を見上げた。満月が私を見ている気分。
私が投げかけた言葉に対してしばらく間を置いて、ヴァンの言葉が返ってくる。
「姫様の為に戦うのです。それ以上でもそれ以下でもありません」
生真面目な彼らしい言葉だった。
本当に私が聞きたいのはそのもう一つ先。
「もし、私が姫じゃなくなっても着いてきてくれますか?」
その言葉を投げ返すとすぐに言葉は戻ってくる。
「もちろんでございます。私は姫様の命でございますから」
迷いのない返事だった。それ以上は言葉を交わさなかった。
本陣に戻ると私は自分のテントに戻る。出撃する前と変わらない光景が広がっていた。
一つだけ違っているのは祝宴は終わっており、とても静かだ。見張りの兵士達が巡回しているだけでそれ以外の音は聞こえない。
私は赤い軍服と装備を外してからベットへと倒れ込むように眠りにつく。
今日は疲れました。久しぶりに長い一日であっという間です。
作り笑いを浮かべて、話を楽しんでいるふりをする。そうしなければ、彼らの機嫌を損ねてしまう。
こんな時にボイコットをされるとたまったものじゃない。
「姫様。大丈夫でございますか?」
そう言ってから、ヴァンは新しいエールを銅製の盃に注いでくれた。私は少しだけ疲れた顔をして笑みを返す。そうしてから、小さく切られたチーズを摘まんで食べる。少しだけ柔らかく、この独特の風味は酒の味によく合う。
椅子に大きく腰を掛けて、夜空をみた。
中央に燃えているかがり火は、弱弱しい星の光を飲み込んでしまっている。見えるのは一番大きい星だけ。
今頃、フィオ達も宴を始めている頃だろう。大きな初戦は勝利に終わった。
次の戦争に備えなくてはいけませんね。
「ヴァン?少しこちらに」
足を組み替えてから、ヴァンに対して手招きをした。私の左側に片足を着いて顔を近づける。ヴァンの耳に口を近づけて片手で口の動きを読まれない様にする。
「精鋭を10名ほどあなたの軍隊から抜き出してください。敵拠点に対して襲撃を行います」
ヴァンは少し驚いた表情をして聞き返した。当然だろう。夜襲は念密な作戦を立てた上に行うものだ。
「今からですか?」
「もちろん。あくまでサポートとして、参加してもらいます。主要箇所は私の1部隊で進めさせていただきますから」
私は立ち上がってから、後方に待機させている黒いフードを頭からかぶっている男に視線を送って呼び寄せる。
準備を始めてくださいと伝えると、静かに闇の中へと姿を消した。
机に立て掛けていた私のサーベルを携えて、口直しに水を一口のみ込む。すぐに終わる戦闘。酔い直しにはちょうどいい。
「私は先に行っておきますから、荷馬車を5台ほど率いて連れてきてください」
彼は小さく返事をして、場所を記した地図を渡した。
静かににぎやかな場所を離れて、黒いローブに身を包む。背中まである赤い髪を頭の後ろで団子の形にまとめた。
既に馬に跨っており、一人だけ私の馬の手綱を持ってから待っている。
その男に小さく礼を言ってから馬に乗りこんた。
「皆さん、この度は私の無茶苦茶な作戦に協力してくれてありがとうございます。あなた達は勇敢な騎士ですが、これから行う事は騎士の栄養とはかけ離れた盗賊まがいの行いです。気に食わなければ離れてもらっても構いません」
その言葉に誰一人、馬から降りる事はなかった。フードの下から見える眼光はまるで狼の様に鋭い。今夜、ここに集まった兵士は狩人になる。敵兵をひたすらに追いかけ仕留める。
私が先頭を走る。ひたすら、無心に早く走る事だけを考えて進む。
目的地は本陣営から北西側にある5キロほど離れた集落。もっと近い距離にも敵拠点が存在している事は確認済みだが、あえてここを選んだのは理由がある。フィオが討ち取った残党兵はここに居る可能性が高い。
大将を討ち取ったとはいえ、残った兵士をかき集められてしまえばそれなりの戦力になる。
それにそれだけの兵士達を受け入れる事が出来るほどの物資が集められている証拠だ。
途中で部隊を3つに分けた。それぞれ、10名ずつに分けて拠点に繋がる道へと回した。
「始めましょうか。拠点にいる人はすべて討ち取りなさい」
茂みの中に馬を隠して、地面に伏せて号令をかけた。一斉に兵士達が拠点内に飛び込んだ。
拠点は一つの物見やぐらと丸太で柵を作って拠点を円状に囲んでいるが、道の部分には見張り番が立っているだけで門はない。
中にはいくつかの家とテントが立てられて、簡易的な馬小屋と荷馬車が20ほど並んでいた。
拠点内の広場には兵たちが横たわっている。外れている漆黒の鎧を見る限りフィオが撃退した部隊だろう。衛生兵や医師たちが忙しなく働いている。
やがて拠点内に入ると、悲鳴が拠点内に鳴り響いた。
始まった。後は殲滅するだけ。そんなに多く時間は残されていない。私はゆっくりと広場へと歩みを進める。負傷兵でも勇敢に武器を持って襲ってくる。
手負いの者を手に掛ける趣味は無いですが、仕方ありませんね。
サーベルを静かに抜いて、右肩と右腕の付け根を突き刺してから、腹部を切り裂く。腹部に致命傷を与えるには、内臓に到達するほどの深さを与えれば十分だ。あとは出血して死を待つだけ。
次は手首を切り落として、頭を掴んだ。
「燃えなさい」
頭を掴んだ手に力を入れると男の全身は真っ赤な炎に包まれて、塵になってしまった。
その塵を踏みつけて、歩みを進める。私が向かう先は大きな茶色のテント。中を開いてみると、武器から小麦粉が入った麻袋に酒類やたばこなどの嗜好品で埋め尽くされいてた。これだけあれば十分。荷馬車にもまだ、この倉庫代わりにしているテントに入り切れていない物資が詰まっているだろう。
何か足首に当たる。見下ろすとそれは血にまみれた中年の女性だ。
憎悪で満たされた視線と声を振り絞って私に投げかける。
「どうしてこんなことを……!」
私は足を振り払って、サーベルで首の後ろを突き刺した。すぐに静かになる。
何を言っているのか。敵を打ち倒すのにそのような事を言ったところでどうするのか。
サーベルを振り払って、着いていた血を振り落とす。私はその転がっている肉の塊を踏みつけて、戦火の風に吹かれた。
そうして、時が経つのを静かに待つ。時折、私に向かって刃を振るう物もいた。
手負いの兵に私を傷つける事は出来ない
誰かが火を付けたのだろう。民家が真っ赤に燃えていた。その炎の中に人の影が見えた。叫び声を上げて、踊り狂うようにして苦しんでいる人の影。やがて、力尽きて影は消える。
次第に叫び声の数は少しずつ減っていき、次第に降伏した兵士が広場の中央に集められていく。
「降伏した兵士達の処遇はいかがいたしますか?」
頭に両手を置いて、跪いて皆うつ向いていた。大体20名ほどか。
その周りに剣を向けて取り囲んでいる。サーベルを静かに鞘に納めて、兵士達を見る。
「殺しなさい。残った死体は埋めてしまいましょう」
そこにいた兵士達はすぐに死体の山へと姿を変えた。後ろにはいそいそと死体埋める兵士達に背を向けて、私は振り返って拠点の入口へ向かう。遥か彼方、私達が来た方向から明かりが見える。ヴァン達だろう。
私の兵士だけになった拠点の中に馬車が5台新しく並んだ。一番最後に並んだ馬車に乗っており、着くと同時に飛び降りて私の元へと駆け寄った。
「姫様!これは一体……」
驚くのも無理が無いだろう。到着したと同時に拠点のほとんどが燃えて、敵兵士の死体を埋める私の兵士達。
「後始末です。汚れたところを掃除するのは当たり前でしょう?」
そう言い捨てて、ヴァンの隣を抜けて馬車に乗ってきた兵士達に物資が詰まったテントを指さして積み込むように指示をする。何人かは困惑した表情をしていたが、言い返す者はいない。
一瞬だけ私がサーベルで突き刺した中年女性の顔が思い浮かんだ。
これは戦争、仕方の無い事。敵兵士に情けをいくらかけたところできりが無い。
泣くも喚くもすべてが終わってからでいい。今のうちは。
「姫様。本当に敵国の兵士だけだったのですか?」
この辺りは先の戦争で義勇軍が立ち上がりほとんど虐殺に近い形で撃退されてしまったと聞く。
あの中年女性は私の顔を知っているような表情をしていた。しかし、私の顔を敵国の市民までが知っていても可笑しくはない。それに、戦争中の敵国王族を知らない方が不思議。知らなかったとしてもよほど自国の事に興味が無いのだろう。
「無論です。先ほどの負傷兵を看護していましたから」
ヴァンはそれ以上は何も言わなかった。難しい顔だけをしている。
今は理解して貰おうとは思わない。そう、私を理解してくれる人なんていないのだから。
強く胸の紅いペンダントを両手で握り占めた。今は迷う事はやめよう。
すべて荷台に積み込まれるまではあっという間だった。すぐに撤収を始めさせ、急いで本陣に戻る。
本陣に戻るまでは密偵に見られてしまっては意味がない。
荷馬車を囲んだ黒いローブに身を包んだ兵士達。私はヴァンが操縦する最後列の荷台に乗って、燃やし尽くされた拠点が小さくなっていくのをただ眺める。
「ヴァン。あなたは何のために戦うのですか?」
屋根のない荷台から雲の無い空を見上げた。満月が私を見ている気分。
私が投げかけた言葉に対してしばらく間を置いて、ヴァンの言葉が返ってくる。
「姫様の為に戦うのです。それ以上でもそれ以下でもありません」
生真面目な彼らしい言葉だった。
本当に私が聞きたいのはそのもう一つ先。
「もし、私が姫じゃなくなっても着いてきてくれますか?」
その言葉を投げ返すとすぐに言葉は戻ってくる。
「もちろんでございます。私は姫様の命でございますから」
迷いのない返事だった。それ以上は言葉を交わさなかった。
本陣に戻ると私は自分のテントに戻る。出撃する前と変わらない光景が広がっていた。
一つだけ違っているのは祝宴は終わっており、とても静かだ。見張りの兵士達が巡回しているだけでそれ以外の音は聞こえない。
私は赤い軍服と装備を外してからベットへと倒れ込むように眠りにつく。
今日は疲れました。久しぶりに長い一日であっという間です。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

最強の職業は付与魔術師かもしれない
カタナヅキ
ファンタジー
現実世界から異世界に召喚された5人の勇者。彼等は同じ高校のクラスメイト同士であり、彼等を召喚したのはバルトロス帝国の3代目の国王だった。彼の話によると現在こちらの世界では魔王軍と呼ばれる組織が世界各地に出現し、数多くの人々に被害を与えている事を伝える。そんな魔王軍に対抗するために帝国に代々伝わる召喚魔法によって異世界から勇者になれる素質を持つ人間を呼びだしたらしいが、たった一人だけ巻き込まれて召喚された人間がいた。
召喚された勇者の中でも小柄であり、他の4人には存在するはずの「女神の加護」と呼ばれる恩恵が存在しなかった。他の勇者に巻き込まれて召喚された「一般人」と判断された彼は魔王軍に対抗できないと見下され、召喚を実行したはずの帝国の人間から追い出される。彼は普通の魔術師ではなく、攻撃魔法は覚えられない「付与魔術師」の職業だったため、この職業の人間は他者を支援するような魔法しか覚えられず、強力な魔法を扱えないため、最初から戦力外と判断されてしまった。
しかし、彼は付与魔術師の本当の力を見抜き、付与魔法を極めて独自の戦闘方法を見出す。後に「聖天魔導士」と名付けられる「霧崎レナ」の物語が始まる――
※今月は毎日10時に投稿します。

旦那様に愛されなかった滑稽な妻です。
アズやっこ
恋愛
私は旦那様を愛していました。
今日は三年目の結婚記念日。帰らない旦那様をそれでも待ち続けました。
私は旦那様を愛していました。それでも旦那様は私を愛してくれないのですね。
これはお別れではありません。役目が終わったので交代するだけです。役立たずの妻で申し訳ありませんでした。

転生騎士団長の歩き方
Akila
ファンタジー
【第2章 完 約13万字】&【第1章 完 約12万字】
たまたま運よく掴んだ功績で第7騎士団の団長になってしまった女性騎士のラモン。そんなラモンの中身は地球から転生した『鈴木ゆり』だった。女神様に転生するに当たってギフトを授かったのだが、これがとっても役立った。ありがとう女神さま! と言う訳で、小娘団長が汗臭い騎士団をどうにか立て直す為、ドーン副団長や団員達とキレイにしたり、旨〜いしたり、キュンキュンしたりするほのぼの物語です。
【第1章 ようこそ第7騎士団へ】 騎士団の中で窓際? 島流し先? と囁かれる第7騎士団を立て直すべく、前世の知識で働き方改革を強行するモラン。 第7は改善されるのか? 副団長のドーンと共にあれこれと毎日大忙しです。
【第2章 王城と私】 第7騎士団での功績が認められて、次は第3騎士団へ行く事になったラモン。勤務地である王城では毎日誰かと何かやらかしてます。第3騎士団には馴染めるかな? って、またまた異動? 果たしてラモンの行き着く先はどこに?
※誤字脱字マジですみません。懲りずに読んで下さい。

最低最悪の悪役令息に転生しましたが、神スキル構成を引き当てたので思うままに突き進みます! 〜何やら転生者の勇者から強いヘイトを買っている模様
コレゼン
ファンタジー
「おいおい、嘘だろ」
ある日、目が覚めて鏡を見ると俺はゲーム「ブレイス・オブ・ワールド」の公爵家三男の悪役令息グレイスに転生していた。
幸いにも「ブレイス・オブ・ワールド」は転生前にやりこんだゲームだった。
早速、どんなスキルを授かったのかとステータスを確認してみると――
「超低確率の神スキル構成、コピースキルとスキル融合の組み合わせを神引きしてるじゃん!!」
やったね! この神スキル構成なら処刑エンドを回避して、かなり有利にゲーム世界を進めることができるはず。
一方で、別の転生者の勇者であり、元エリートで地方自治体の首長でもあったアルフレッドは、
「なんでモブキャラの悪役令息があんなに強力なスキルを複数持ってるんだ! しかも俺が目指してる国王エンドを邪魔するような行動ばかり取りやがって!!」
悪役令息のグレイスに対して日々不満を高まらせていた。
なんか俺、勇者のアルフレッドからものすごいヘイト買ってる?
でもまあ、勇者が最強なのは検証が進む前の攻略情報だから大丈夫っしょ。
というわけで、ゲーム知識と神スキル構成で思うままにこのゲーム世界を突き進んでいきます!

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる
農民ヤズ―
ファンタジー
「ようこそおいでくださいました。勇者さま」
そんな言葉から始まった異世界召喚。
呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?
そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!
このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。
勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定
私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。
ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。
他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。
なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。
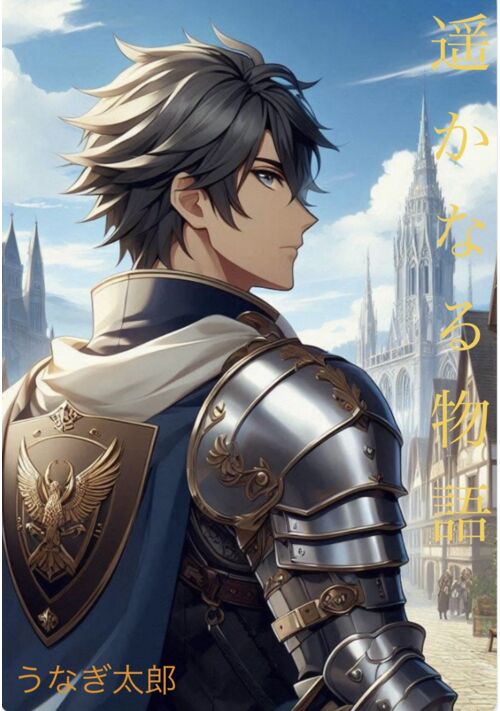
遥かなる物語
うなぎ太郎
ファンタジー
スラーレン帝国の首都、エラルトはこの世界最大の都市。この街に貴族の令息や令嬢達が通う学園、スラーレン中央学園があった。
この学園にある一人の男子生徒がいた。彼の名は、シャルル・ベルタン。ノア・ベルタン伯爵の息子だ。
彼と友人達はこの学園で、様々なことを学び、成長していく。
だが彼が帝国の歴史を変える英雄になろうとは、誰も想像もしていなかったのであった…彼は日々動き続ける世界で何を失い、何を手に入れるのか?
ーーーーーーーー
序盤はほのぼのとした学園小説にしようと思います。中盤以降は戦闘や魔法、政争がメインで異世界ファンタジー的要素も強いです。
※作者独自の世界観です。
※甘々ご都合主義では無いですが、一応ハッピーエンドです。

最強騎士は料理が作りたい
菁 犬兎
ファンタジー
こんにちわ!!私はティファ。18歳。
ある国で軽い気持ちで兵士になったら気付いたら最強騎士になってしまいました!でも私、本当は小さな料理店を開くのが夢なんです。そ・れ・な・の・に!!私、仲間に裏切られて敵国に捕まってしまいました!!あわわどうしましょ!でも、何だか王様の様子がおかしいのです。私、一体どうなってしまうんでしょうか?
*小説家になろう様にも掲載されております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















