お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

【完結】夜に咲く花
すだもみぢ
現代文学
タワーマンションの最上階にある展望台。ショウコとアズサとレイはいつもそこで出会う。
お互いのことを深く訊いたりせず、暗闇の中で会うだけのそれが暗黙のルールだ。
だからお互いに知っていることはわずかなことだけ。
普通すぎるショウコに比べて、アズサとレイは神様から特別を与えられている存在だった。
アズサは優秀さで。レイは儚い美しさで。
しかし二人はショウコに言うのだ。「貴方はそのままでいて」と。
ショウコは夢を持つこともできずにいるのに。
自分はこのまま枯れるだけの存在だというのに、なぜ二人はそんなことを言うのだろうか。
そんなある日、レイが二人の側からいなくなった。
そして、ショウコも引っ越すことを親から告げられて……。
大人になる前の少女の気持ちを書いた作品です。
6/1 現代文学ジャンル1位ありがとうございました<(_ _)>


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

我ら同級生たち
相良武有
現代文学
この物語は高校の同級生である男女五人が、卒業後に様々な形で挫折に直面し、挫折を乗り越えたり、挫折に押し潰されたりする姿を描いた青春群像小説である。
人間は生きている時間の長短ではなく、何を思い何をしたか、が重要なのである。如何に納得した充実感を持ち乍ら生きるかが重要なのである。自分の信じるものに向かって闘い続けることが生きるということである・・・
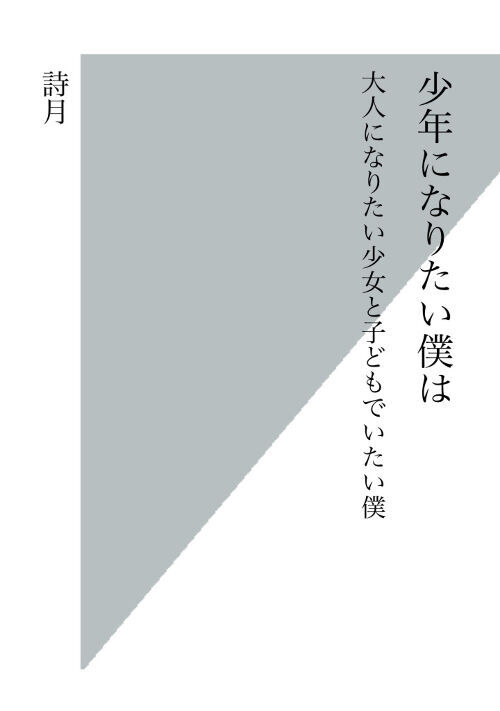
少年になりたい僕は-大人になりたい君と子どもでいたい僕の青春ストーリー-
詩月
現代文学
高校生1年生である的羽暁人は、少年の頃都会で出会った少女を絵に描きたいと思っていた。その少女の言葉は幼く、芯をついているとは到底言えない。だが彼女の言葉には無知だからこそ私たちに共感を得られるものがあったのかもしれない。

体育座りでスカートを汚してしまったあの日々
yoshieeesan
現代文学
学生時代にやたらとさせられた体育座りですが、女性からすると服が汚れた嫌な思い出が多いです。そういった短編小説を書いていきます。

その男、人の人生を狂わせるので注意が必要
いちごみるく
現代文学
「あいつに関わると、人生が狂わされる」
「密室で二人きりになるのが禁止になった」
「関わった人みんな好きになる…」
こんな伝説を残した男が、ある中学にいた。
見知らぬ小グレ集団、警察官、幼馴染の年上、担任教師、部活の後輩に顧問まで……
関わる人すべてを夢中にさせ、頭の中を自分のことで支配させてしまう。
無意識に人を惹き込むその少年を、人は魔性の男と呼ぶ。
そんな彼に関わった人たちがどのように人生を壊していくのか……
地位や年齢、性別は関係ない。
抱える悩みや劣等感を少し刺激されるだけで、人の人生は呆気なく崩れていく。
色んな人物が、ある一人の男によって人生をジワジワと壊していく様子をリアルに描いた物語。
嫉妬、自己顕示欲、愛情不足、孤立、虚言……
現代に溢れる人間の醜い部分を自覚する者と自覚せずに目を背ける者…。
彼らの運命は、主人公・醍醐隼に翻弄される中で確実に分かれていく。
※なお、筆者の拙作『あんなに堅物だった俺を、解してくれたお前の腕が』に出てくる人物たちがこの作品でもメインになります。ご興味があれば、そちらも是非!
※長い作品ですが、1話が300〜1500字程度です。少しずつ読んで頂くことも可能です!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















