7 / 29
第7話 親子の遭遇は唐突に
しおりを挟む
晴天に眺められ上空から降り注ぐ陽光に注がれながら俺は自転車を押しながら栗之先輩と一緒に歩道を歩いていた。自分たちの前や後ろにも同じ高校の生徒たちがおり、仲良く話している友達同士や一人で急ぐように移動する生徒などが見受けられた。俺と栗之先輩は最近学校で会った出来事を話題にしながら喋り合っていた。笑う場面もあったが基本的には平静な空気が流れていた。賑やかな会話もいいがのんびりとするのも嫌いではなかった。
「進学先適当に選んだら姉さんに怒られそうだな」
俺は今頃仕事をしている姉さんを思い浮かべながら朗らかな声で大げさ気味に言う。栗之先輩の中学時代の受験勉強の話題で語り合っていたが俺の受験勉強に話題が移っていた。受験生だった時には既に高校進学後アルバイトをして姉さんの借金返済を手伝うと決めていた。公立高校に進学したのもアルバイト可能と親に金銭的負担を掛けたくなかったためだ。
しかし借金返済の協力を申し出た際姉さんの反応は好ましいとはいえずその件で咎められた。必死に何度も説得したことで最終的には容認したが長い時間を要した。それでも姉さんは俺に対して激怒したり冷遇はしなかった。因みに父さんからは偏差値の高い高校であれば私立高校への進学を認める伝えられていた。
「松貴くんお姉さんいるんだ」
栗之先輩は少し驚いたようで声量が大きくなっていた。
「もう社会人ですけどいますよ。今は実家を出て一人暮らししていますけど」
「怒られるって言ってたけどそんな勉強に厳しいの?」
栗之先輩は興味津々な目つきでじろじろと俺の顔を伺っている。俺の言い方的にそこまで深刻な怒られ方はしていないと理解しているようだ。ただ姉という存在にかなり興味を持ったみたいだった。
「あまりにもひどい場合だと怒られるかもしれないです。けど基本的には勉強とかで相談に乗ってもらうことも多くて頼りになる人ですね」
中学時代の記憶を大雑把に探るだけでも電話とかでよく勉強を教えてもらっていた。部活動の相談とかも熱心に乗ってくれた。だからこそ姉さんは家族の中でもっとも信頼を置ける人物だった。
「松貴くんのお姉さんいい人そうだね。わたしも問題があったときはお母さんによく相談するから、頼れる人って大切だよね」
栗之先輩は柔らかい口調で話す。その声からはお母さんに対する深い信頼を連想させる。
「俺は両親にはあんまり相談できないので姉さんに頼りっぱなしですね」
俺は達観したように淡白に言う。姉さんの一件で両親は相談に応じるどころか説教されかねないことを学習しているため、些細な事柄以外は姉さんに相談している。もちろん姉さんのことを相談したら少なくとも父さんは激怒するのは間違いない。
「私もお父さんには相談できないかな。親なんだけど頼りづらいというか考えていることがわからないのよね」
栗之先輩は空を仰ぎながら表情を歪ませる。栗之先輩の言うとおり親というのは一番身近な人間なはずだが、時折何を考えているか分からないときはある。せめて親の気持ちを完全理解できればと思わなくもない。いくら学歴第一主義の父さんでも何故姉さんの決断に猛反対したのか未だに疑問が残っていた。
「僕は親の考えが理解できなくて距離を取ってしまいがちですね。まあ親子とはいえ相手の気持ちを測ることは難しいですね」
「本当にそうだね」
温い風が静かに側をかすめながら空には雲が学校を出る前と比べて増え太陽を隠そうとしていた。雨が降る予報ではなかったので雨雲ではないはずだが、本能的に気になる空の動きだった。
「そういえば僕も卒業したら一人暮らし始めようと考えているんですけど、なにかアドバイスとかありますか?」
場の空気が微妙になりかけていたため、俺は新たな話題を振ってみる。高校卒業後は一人暮らしを希望していた俺にとってその先輩である栗之先輩から助言を貰いたかった。
「そういえば僕も卒業したら一人暮らし始めようと考えているんですけど、なにかアドバイスとかありますか?」
質問を受けた栗之先輩は「一人暮らしのコツか」と意外そうに呟いた。
「一人暮らしをする前に家族との時間を大切にすることかな。実家から離れたら簡単には会えないからね」
栗之先輩の答えは俺にとって意図もしておらず、胸中で思わず苦笑いしてしまう。仲を悪化させて家を飛び出していった姉さんのことを思うとこの助言は肝に銘じなければならない。
「難しそうな課題ですね。だけど離れる前に家族との思い出を一杯作っておかないと寂しくなりそうですね」
「松貴くんなら問題な――」
栗之先輩は言葉を言いかけたまま顔が物凄い速度で凍りつく。俺は栗之先輩が向いている方向に目をやると一人の男性が近づいてくる。髪の長さは首と頭の境目辺りで耳は耳は出ており、前髪は眉毛にかかる程度に垂らしている。その男性の顔付きは近くから見なくても貫禄を感じさせられた。近づくに連れ男性の来ているスーツがどこか高級感のあるものだと学生である俺でも見受けられた。
スーツの男性は栗之先輩の前方から数歩離れた位置で立ち止まると「元気にしていたか?」と親しくも隔たりのある口調で栗之先輩に言葉をかける。
「元気だけど、お父さんがなんでこんなところにいるの?」
栗之先輩の声は少しばかし上擦っており、男性への視線には複雑なものを感じ取れた。。そして俺も「お父さん」という言葉に耳を疑った。確かに男性と栗之先輩の顔は似ている箇所がいくつもあり、親子だと教えられれば納得できる。
「仕事でこの辺りに訪れていた。近くの駐車場に車を止めていたからそこに向かう最中だよ」 「そうだったんだ」
「栗之の隣にいるのは君は栗之のお友達かい?」
二人のやり取りを呆然のように眺めていた俺は栗之のお父さんに話しかけられて角張ってしまう。
「学校の後輩で椎橋松貴といいます」
「私は栗之の父親の景賀といいます。二人で帰宅していたところ申し訳ないが少しばかし栗之と二人で話をさせてもらえないだろうか」
丁寧な話し方に栗之先輩のお父さんへの印象は良いものだった。提案に関しても俺は「いいですよ」と言いそうになったが、栗之先輩の様子からして素直にその提案を受け入れられなかった。
「話ってどれぐらい?」
栗之先輩は何かを諦めたような雰囲気で会話に割り込んでくる。その言葉に栗之のお父さんは「職場に帰らないといけないから、すぐに終わる」と返事をする。栗之先輩は浮かない面差しで「申し訳ないけど少しだけ待ってて」と俺に謝ると「早く話をしよ」と栗之先輩のお父さんを連れて俺から離れていく。
二人は僅かに見える範囲には立っていたが話し声は一切聞こえない。話し合いは栗之のお父さんの言葉通り、数分程度とすぐ終わり、栗之先輩は早歩きでこちらに戻ってくるが、栗之先輩のお父さんは俺に対して頭を下げると栗之先輩とは逆方向に歩いていく。戻ってきた栗之先輩の表情は張り詰めていたが無理に表情を緩めながら「待たせてごめんね」とだけ申し訳なさそうに伝えると足を前に歩み進める。俺は栗之先輩が心配になり言葉をかける。
「栗之先輩は大丈夫ですか? あまり様子がいいとは思えないので」
「気を配ってくれるのは有り難いけど今日のところはこのことについてあまり話したくないかな」
俺から顔を背けながら返事をする栗之先輩の様子は顕著に気落ちしていた。このあと俺と栗之先輩との間に会話は殆どなかった。
「進学先適当に選んだら姉さんに怒られそうだな」
俺は今頃仕事をしている姉さんを思い浮かべながら朗らかな声で大げさ気味に言う。栗之先輩の中学時代の受験勉強の話題で語り合っていたが俺の受験勉強に話題が移っていた。受験生だった時には既に高校進学後アルバイトをして姉さんの借金返済を手伝うと決めていた。公立高校に進学したのもアルバイト可能と親に金銭的負担を掛けたくなかったためだ。
しかし借金返済の協力を申し出た際姉さんの反応は好ましいとはいえずその件で咎められた。必死に何度も説得したことで最終的には容認したが長い時間を要した。それでも姉さんは俺に対して激怒したり冷遇はしなかった。因みに父さんからは偏差値の高い高校であれば私立高校への進学を認める伝えられていた。
「松貴くんお姉さんいるんだ」
栗之先輩は少し驚いたようで声量が大きくなっていた。
「もう社会人ですけどいますよ。今は実家を出て一人暮らししていますけど」
「怒られるって言ってたけどそんな勉強に厳しいの?」
栗之先輩は興味津々な目つきでじろじろと俺の顔を伺っている。俺の言い方的にそこまで深刻な怒られ方はしていないと理解しているようだ。ただ姉という存在にかなり興味を持ったみたいだった。
「あまりにもひどい場合だと怒られるかもしれないです。けど基本的には勉強とかで相談に乗ってもらうことも多くて頼りになる人ですね」
中学時代の記憶を大雑把に探るだけでも電話とかでよく勉強を教えてもらっていた。部活動の相談とかも熱心に乗ってくれた。だからこそ姉さんは家族の中でもっとも信頼を置ける人物だった。
「松貴くんのお姉さんいい人そうだね。わたしも問題があったときはお母さんによく相談するから、頼れる人って大切だよね」
栗之先輩は柔らかい口調で話す。その声からはお母さんに対する深い信頼を連想させる。
「俺は両親にはあんまり相談できないので姉さんに頼りっぱなしですね」
俺は達観したように淡白に言う。姉さんの一件で両親は相談に応じるどころか説教されかねないことを学習しているため、些細な事柄以外は姉さんに相談している。もちろん姉さんのことを相談したら少なくとも父さんは激怒するのは間違いない。
「私もお父さんには相談できないかな。親なんだけど頼りづらいというか考えていることがわからないのよね」
栗之先輩は空を仰ぎながら表情を歪ませる。栗之先輩の言うとおり親というのは一番身近な人間なはずだが、時折何を考えているか分からないときはある。せめて親の気持ちを完全理解できればと思わなくもない。いくら学歴第一主義の父さんでも何故姉さんの決断に猛反対したのか未だに疑問が残っていた。
「僕は親の考えが理解できなくて距離を取ってしまいがちですね。まあ親子とはいえ相手の気持ちを測ることは難しいですね」
「本当にそうだね」
温い風が静かに側をかすめながら空には雲が学校を出る前と比べて増え太陽を隠そうとしていた。雨が降る予報ではなかったので雨雲ではないはずだが、本能的に気になる空の動きだった。
「そういえば僕も卒業したら一人暮らし始めようと考えているんですけど、なにかアドバイスとかありますか?」
場の空気が微妙になりかけていたため、俺は新たな話題を振ってみる。高校卒業後は一人暮らしを希望していた俺にとってその先輩である栗之先輩から助言を貰いたかった。
「そういえば僕も卒業したら一人暮らし始めようと考えているんですけど、なにかアドバイスとかありますか?」
質問を受けた栗之先輩は「一人暮らしのコツか」と意外そうに呟いた。
「一人暮らしをする前に家族との時間を大切にすることかな。実家から離れたら簡単には会えないからね」
栗之先輩の答えは俺にとって意図もしておらず、胸中で思わず苦笑いしてしまう。仲を悪化させて家を飛び出していった姉さんのことを思うとこの助言は肝に銘じなければならない。
「難しそうな課題ですね。だけど離れる前に家族との思い出を一杯作っておかないと寂しくなりそうですね」
「松貴くんなら問題な――」
栗之先輩は言葉を言いかけたまま顔が物凄い速度で凍りつく。俺は栗之先輩が向いている方向に目をやると一人の男性が近づいてくる。髪の長さは首と頭の境目辺りで耳は耳は出ており、前髪は眉毛にかかる程度に垂らしている。その男性の顔付きは近くから見なくても貫禄を感じさせられた。近づくに連れ男性の来ているスーツがどこか高級感のあるものだと学生である俺でも見受けられた。
スーツの男性は栗之先輩の前方から数歩離れた位置で立ち止まると「元気にしていたか?」と親しくも隔たりのある口調で栗之先輩に言葉をかける。
「元気だけど、お父さんがなんでこんなところにいるの?」
栗之先輩の声は少しばかし上擦っており、男性への視線には複雑なものを感じ取れた。。そして俺も「お父さん」という言葉に耳を疑った。確かに男性と栗之先輩の顔は似ている箇所がいくつもあり、親子だと教えられれば納得できる。
「仕事でこの辺りに訪れていた。近くの駐車場に車を止めていたからそこに向かう最中だよ」 「そうだったんだ」
「栗之の隣にいるのは君は栗之のお友達かい?」
二人のやり取りを呆然のように眺めていた俺は栗之のお父さんに話しかけられて角張ってしまう。
「学校の後輩で椎橋松貴といいます」
「私は栗之の父親の景賀といいます。二人で帰宅していたところ申し訳ないが少しばかし栗之と二人で話をさせてもらえないだろうか」
丁寧な話し方に栗之先輩のお父さんへの印象は良いものだった。提案に関しても俺は「いいですよ」と言いそうになったが、栗之先輩の様子からして素直にその提案を受け入れられなかった。
「話ってどれぐらい?」
栗之先輩は何かを諦めたような雰囲気で会話に割り込んでくる。その言葉に栗之のお父さんは「職場に帰らないといけないから、すぐに終わる」と返事をする。栗之先輩は浮かない面差しで「申し訳ないけど少しだけ待ってて」と俺に謝ると「早く話をしよ」と栗之先輩のお父さんを連れて俺から離れていく。
二人は僅かに見える範囲には立っていたが話し声は一切聞こえない。話し合いは栗之のお父さんの言葉通り、数分程度とすぐ終わり、栗之先輩は早歩きでこちらに戻ってくるが、栗之先輩のお父さんは俺に対して頭を下げると栗之先輩とは逆方向に歩いていく。戻ってきた栗之先輩の表情は張り詰めていたが無理に表情を緩めながら「待たせてごめんね」とだけ申し訳なさそうに伝えると足を前に歩み進める。俺は栗之先輩が心配になり言葉をかける。
「栗之先輩は大丈夫ですか? あまり様子がいいとは思えないので」
「気を配ってくれるのは有り難いけど今日のところはこのことについてあまり話したくないかな」
俺から顔を背けながら返事をする栗之先輩の様子は顕著に気落ちしていた。このあと俺と栗之先輩との間に会話は殆どなかった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
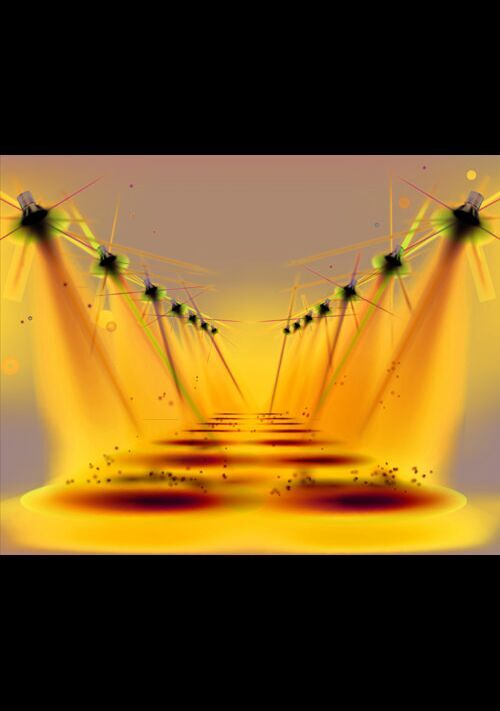
私のなかの、なにか
ちがさき紗季
青春
中学三年生の二月のある朝、川奈莉子の両親は消えた。叔母の曜子に引き取られて、大切に育てられるが、心に刻まれた深い傷は癒えない。そればかりか両親失踪事件をあざ笑う同級生によって、ネットに残酷な書きこみが連鎖し、対人恐怖症になって引きこもる。
やがて自分のなかに芽生える〝なにか〟に気づく莉子。かつては気持ちを満たす幸せの象徴だったそれが、不穏な負の象徴に変化しているのを自覚する。同時に両親が大好きだったビートルズの名曲『Something』を聴くことすらできなくなる。
春が訪れる。曜子の勧めで、独自の教育方針の私立高校に入学。修と咲南に出会い、音楽を通じてどこかに生きているはずの両親に想いを届けようと考えはじめる。
大学一年の夏、莉子は修と再会する。特別な歌声と特異の音域を持つ莉子の才能に気づいていた修の熱心な説得により、ふたたび歌うようになる。その後、修はネットの音楽配信サービスに楽曲をアップロードする。間もなく、二人の世界が動きはじめた。
大手レコード会社の新人発掘プロデューサー澤と出会い、修とともにライブに出演する。しかし、両親の失踪以来、莉子のなかに巣食う不穏な〝なにか〟が膨張し、大勢の観客を前にしてパニックに陥り、倒れてしまう。それでも奮起し、ぎりぎりのメンタルで歌いつづけるものの、さらに難題がのしかかる。音楽フェスのオープニングアクトの出演が決定した。直後、おぼろげに悟る両親の死によって希望を失いつつあった莉子は、プレッシャーからついに心が折れ、プロデビューを辞退するも、曜子から耳を疑う内容の電話を受ける。それは、両親が生きている、という信じがたい話だった。
歌えなくなった莉子は、葛藤や混乱と闘いながら――。


幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。

真夏の温泉物語
矢木羽研
青春
山奥の温泉にのんびり浸かっていた俺の前に現れた謎の少女は何者……?ちょっとエッチ(R15)で切ない、真夏の白昼夢。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

窓際の君
気衒い
青春
俺こと如月拓也はとある一人の女子生徒に恋をしていた。とはいっても告白なんて以ての外。積極的に声を掛けることすら出来なかった。そんなある日、憂鬱そうに外を見つめるクラスメイト、霜月クレアが目に入る。彼女の瞳はまるでここではないどこか遠くの方を見ているようで俺は気が付けば、彼女に向かってこう言っていた。
「その瞳には一体、何が映ってる?」
その日を境に俺の変わり映えのしなかった日常が動き出した。

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。

【完結】碧よりも蒼く
多田莉都
青春
中学二年のときに、陸上競技の男子100m走で全国制覇を成し遂げたことのある深田碧斗は、高校になってからは何の実績もなかった。実績どころか、陸上部にすら所属していなかった。碧斗が走ることを辞めてしまったのにはある理由があった。
それは中学三年の大会で出会ったある才能の前に、碧斗は走ることを諦めてしまったからだった。中学を卒業し、祖父母の住む他県の高校を受験し、故郷の富山を離れた碧斗は無気力な日々を過ごす。
ある日、地元で深田碧斗が陸上の大会に出ていたということを知り、「何のことだ」と陸上雑誌を調べたところ、ある高校の深田碧斗が富山の大会に出場していた記録をみつけだした。
これは一体、どういうことなんだ? 碧斗は一路、富山へと帰り、事実を確かめることにした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















