47 / 64
第25話 せっかくだからBルートを選んでみる。
Chapter-44
しおりを挟む
「確かに、状況は最悪ですな」
セニールダー主席宣教師がそう言った。
「陛下はこの状況を打破すべく勅令を出そうとしましたが、側近の貴族達に制止されています」
「やはりそうでしたか……」
主席宣教師の言葉に、俺は口元に当てて少し考える。
「それどころか、帝都内の騒乱に備えて地方領主に、あろうことか帝都に向かって挙兵せよと。その勅令を出さざるを得なくなっています」
「民衆の陛下に対する信頼はどうですか?」
俺は訊き返した。
「今のところ、陛下に直接民衆の不満が募っているとは思えません。これまでも、陛下は民衆の不満を和らげる方向で動いてきたので、今回もそれを期待しているものが多いかと……ただ、あくまで私の主観になるということと……」
「いうことと?」
渋い表情をする主席宣教師に、俺は続きを促す。
「実は国の備蓄もそろそろ尽きかけているのです」
「う」
俺は表情が強ばるのが解った。
「ちょっと待って、それじゃあ、今年に限ってこんな騒ぎになったのは」
エミやミーラなら想定できたが、キャロが気付くか。
いや、出発前に現状について一番話し込んでいたのはキャロだ。
「アルヴィンは、今年なのはたまたまだ、って言ってたけど……」
「ああ、これは必然だ。たまたま今年だったんじゃない」
キャロの言葉に頷く。
国に市場価格を抑制できるほどの備蓄がもう残っていない。
「セニールダー主席宣教師、それは国庫のすべてが尽きかけているということですか?」
「それは……何分、私は専門外ですし、そうした会計の部門は……」
くっそ、そうだよな、本祖派連中が中枢を固めてんだ。
新教派の第二枢機卿に教えるわけなんかない。
最低限の備蓄はまだ残っている、ならまだいい。
だが、本気で備蓄を使い果たしてしまっていると、ちょっとした天災でも起ころうものなら、その救援すらできない。
地方には、帝都とは別にそれなりの備蓄はあるだろうが……
幸いなのは、日本と違って災害天国な国情じゃないことか。
「できるだけ慎重に、穏便にやろうと思っていたが、もう、時間との戦いになってきた」
「アルヴィン殿には、なにか打開策が会って帝都に乗り込んできたのですかな?」
主席宣教師の言葉に、俺は頷く。
「錦の御旗を──いえ、つまり、皇帝陛下の御印をこちらの手に入れます。ただ、地方領主の兵団が帝都に乗り込む状態になっては、もう、遅い」
「なるほど、それで、皇宮に手はずを整えるのに、私のもとに来たということですな?」
俺は再度頷いた。
「なんとかして、皇宮内に入り、陛下が勅令を出せる状況にしなければなりません」
「承知しました。それは、私が手引いたしましょう。ただ、この人数はまずい。せいぜい2・3人が限度です」
確かに、それもそうだな。2・3人か。
1人は姉弟子で決まりだ。中でどんな事態になっても、俺と姉弟子がいれば対処できる。
あとは……
「そうだな、エミ、ついてきてくれるか?」
いろいろな意味で、やはりエミを選ぶべきだろう。
まず考えたくないことだが、中で戦闘になった場合。
フィールド型の戦場では槍のキャロやロングメイスのミーラが有利だが、屋内だとエミの剣の方が取り回しの面で有利だ。
もっとも、そんな事態になったら、完全に負け戦なのだが。
できるだけ穏便に、陛下を確保しなければならない。
そして、エミを連れて行く理由はもうひとつ。
「キャロ、ミーラ、済まないが、俺達が出発した後、ローチ伯爵家の帝都屋敷まで走ってくれないか? エミは皇宮の中にいると伝えてほしいんだ」
「ローチ家の兵団の力を借りることになるかも知れない、ということですね?」
ミーラが、問い返すようにしてきた。
「ああ、そうだ。現状、近衛兵団が陛下の思い通りに動かせる状況かわからないし、騒乱が起きたら、アテにできるのはローチ伯爵とブリュサンメル上級伯ぐらいしかいないからな」
ブリュサンメル上級伯が出兵に応じていたとして、兵団が到着するまでには、まだしばらく時間がかかるだろう。
「早速行動を開始したいのですが、セニールダー主席宣教師、お願いできますか?」
俺は、突き動かされるように、主席宣教師に頼む。
「今戻ったばかりで、また……というのは、訝しがられる気がしますが、もはやその猶予はないのですね?」
「ええ」
主席宣教師の言葉に、俺は頷く。
「わかりました。とにかく、行くだけ行ってみましょう」
主席宣教師に連れられて、俺、エミ、姉弟子は皇宮の通用門までやってきた。
まずいな……
ひと目見て、焦燥感が一気に跳ね上がるのが解った。
多くの民衆が、城門前でデモを行っている。
プラカードと言うか、木の支柱に布地で作った、アジテーションの入った旗を掲げていた。
ここで揉み合いがあったためか、扉は固く閉ざされているだけではなく、通用門の部分にかかる橋の、堀の外側に柵が立てられ、その前に近衛兵が立っている。
「陛下らしくないな。市民を威嚇する場所に兵を立たせるなど」
姉弟子がそう言った。
だが、静かな口調で言った、その理由はわかっているのだろう、今はそう言う事態なのだ。
「ルイス・モーリス・セニールダー伯爵である。火急の用にて、陛下にお会いしたく、アルヴィン・バックエショフ子爵と、シャーロット・キャロッサ準男爵とともに参った。陛下に謁見願いたい」
主席宣教師がそう伝えると、通用門につながる橋の前で立ち番をしていた兵士は、慌てて通用門の方に走っていく。
通用門が開き、どうやら兵士の上役らしい人間と、立ち番をしていた兵とが、なにか興奮したように会話をしていた。
やがて、上役の兵士長と、先程の兵士とが、駆け寄ってくる。
「お待ちしておりました、アルヴィン・バックエショフ卿」
ん? 何?
「陛下がお待ちになられています、中にお入りください」
ちょっと意外な展開になってきたぞ。
俺はてっきり、最初は拒絶される可能性もあると考えてここまで来た。
それが、陛下が俺を待っている、だと?
「エミ、姉弟子、気をつけてください、何かの罠かもしれない」
俺は、2人に警戒を促す。
もし俺達になにかあっても、ローチ伯がうまく立ち回ってくれれば良いのだが、俺の考えている通りの動きまでは期待できないだろう。
「こちらです」
兵士長が俺達を案内してきたのは、儀式の時に使う謁見の間ではなく、普段、陛下が執政を取り仕切るための部屋だった。
と言っても、俺のマークリスの屋敷の執務室とは、質に天と地ほどの開きがあった。前世に例えるなら、ホワイトハウスのオーバル・オフィスか。
「待っていたわ、アルヴィン! それにリリーも!」
一段高い位置にある執務机の椅子にかけていた陛下が、ぱっと顔を綻ばせるようにして、俺達を歓迎する言葉をかけてくれた。
あれーぇ?
良いのか、こんなに順調に事が進んで。
「アルヴィン・バックエショフ。この折、必ずあなたが来てくれると私は、いえ、余は信じておった」
陛下の口調が変わった。私的な接し方から、皇帝としてのそれになったのだ。
「陛下、火急の事態と訊いて、参上仕りますれば、現状、自分に何をお望みなのか、お聞かせ願えますか?」
俺は、険しい表情をしつつ、やはり、皇帝陛下に対する公的な態度で、それを訊ねた。
「余には…………」
陛下は、ふるふると震えながら、言う。
「もとより余にこの皇帝の座は似つかわしくなかったのやも知れぬ。もう、余には民の心がわからぬ。臣下の真意がわからぬ。従って皇帝として何を為すべきかもわからぬ」
その声は、泣きそうですらあった。
「陛下! それは、我ら臣下の不足にござります。陛下が心を痛めるべきことではありませぬ」
そう言ったのは、陛下の傍らにいた、宰相サッチュス侯爵だった。
そうだ、この人は本祖派ではあるが、それ以上に陛下に心酔している人だったな。
「否!」
俺は敢えて言う。
「以前、茶会の場で自分は言ったはずです、改革なければこの国の行く末は昏い、と。その不足が今、民の怒りを、この混沌を呼んでいるのです、それを直視していただきたい!」
「!?」
サッチュス候を始めとする、陛下の側近たち、さらには、主席宣教師や、エミまでもが、信じられない、驚愕した、という感じで、俺を見ている。
そりゃそうだろう。今まで、陛下には当たり障りのない範囲でしか、陛下に物事を伝えてこなかったのだから。だが、その結果が、これだ。
「やはり余に皇帝の座は荷が勝ちすぎたということか……」
陛下は、俺の言葉に、肩を落とすようにして、弱気にそう言った。
「いいえ! 皇帝なくしてこの国はあり得ませぬ。そして、今、その座にあるのは、他ならぬ陛下であります。ならば、皇帝以外に──陛下以外にこの事態は収集できませぬ」
俺は、敢えて叱咤するように、そう言った。
この人は本来、聡いはずだ。
だから以前、美辞麗句を並べる側近たちとは違う切り口から、物事を見られるだろうと、俺を茶会に呼び出した。
残念ながら、穏便な改革は、すでに不可能になったが、それでも────
「選択肢は2つに1つ、このまま帝国が瓦解するのを目の当たりにし、長きに渡って民を飢えさせ、苦しませるか。あるいは、今ここで一時の痛みに耐え、帝国の繁栄を取り戻すか。すべては、陛下の御意志にかかっております!」
「余は……余に、できるというのか、そのような、大胆なことが……」
「陛下にしか、皇帝にしかできませぬ!」
俺は陛下に決断を迫る。
もう時間がない。
なにより、この人なくして俺達の目的は達成できない。
「アルヴィン・バックエショフ卿の真意の程は測りかねますが」
サッチュス候が言う。
「不肖、バーナード・センツベリー・サッチュス、私も、帝国をまとめ得るのは、陛下以外におられぬと信じております」
ありがたい、サッチュス候の援護射撃だ。
「どうすればいい。余は、何をすればいい。アルヴィン・バックエショフ。そなたには世の真に為すべきことが、なんなのかを解っているのなら、皇帝の恥を承知で言う、教えてはくれぬか」
「簡単なことです」
爆弾、あるいは、毒。そう例えられるべきことを、俺は敢えて口にする。
「今、この帝国は一握りの貴族の秘密政治によって動かされている。その結果が、民の怒り。ならば、為すべきことは2つ、国を真に、皇帝の下において動かすこと。そして、それを公明正大なものであることを民に示すこと!」
セニールダー主席宣教師がそう言った。
「陛下はこの状況を打破すべく勅令を出そうとしましたが、側近の貴族達に制止されています」
「やはりそうでしたか……」
主席宣教師の言葉に、俺は口元に当てて少し考える。
「それどころか、帝都内の騒乱に備えて地方領主に、あろうことか帝都に向かって挙兵せよと。その勅令を出さざるを得なくなっています」
「民衆の陛下に対する信頼はどうですか?」
俺は訊き返した。
「今のところ、陛下に直接民衆の不満が募っているとは思えません。これまでも、陛下は民衆の不満を和らげる方向で動いてきたので、今回もそれを期待しているものが多いかと……ただ、あくまで私の主観になるということと……」
「いうことと?」
渋い表情をする主席宣教師に、俺は続きを促す。
「実は国の備蓄もそろそろ尽きかけているのです」
「う」
俺は表情が強ばるのが解った。
「ちょっと待って、それじゃあ、今年に限ってこんな騒ぎになったのは」
エミやミーラなら想定できたが、キャロが気付くか。
いや、出発前に現状について一番話し込んでいたのはキャロだ。
「アルヴィンは、今年なのはたまたまだ、って言ってたけど……」
「ああ、これは必然だ。たまたま今年だったんじゃない」
キャロの言葉に頷く。
国に市場価格を抑制できるほどの備蓄がもう残っていない。
「セニールダー主席宣教師、それは国庫のすべてが尽きかけているということですか?」
「それは……何分、私は専門外ですし、そうした会計の部門は……」
くっそ、そうだよな、本祖派連中が中枢を固めてんだ。
新教派の第二枢機卿に教えるわけなんかない。
最低限の備蓄はまだ残っている、ならまだいい。
だが、本気で備蓄を使い果たしてしまっていると、ちょっとした天災でも起ころうものなら、その救援すらできない。
地方には、帝都とは別にそれなりの備蓄はあるだろうが……
幸いなのは、日本と違って災害天国な国情じゃないことか。
「できるだけ慎重に、穏便にやろうと思っていたが、もう、時間との戦いになってきた」
「アルヴィン殿には、なにか打開策が会って帝都に乗り込んできたのですかな?」
主席宣教師の言葉に、俺は頷く。
「錦の御旗を──いえ、つまり、皇帝陛下の御印をこちらの手に入れます。ただ、地方領主の兵団が帝都に乗り込む状態になっては、もう、遅い」
「なるほど、それで、皇宮に手はずを整えるのに、私のもとに来たということですな?」
俺は再度頷いた。
「なんとかして、皇宮内に入り、陛下が勅令を出せる状況にしなければなりません」
「承知しました。それは、私が手引いたしましょう。ただ、この人数はまずい。せいぜい2・3人が限度です」
確かに、それもそうだな。2・3人か。
1人は姉弟子で決まりだ。中でどんな事態になっても、俺と姉弟子がいれば対処できる。
あとは……
「そうだな、エミ、ついてきてくれるか?」
いろいろな意味で、やはりエミを選ぶべきだろう。
まず考えたくないことだが、中で戦闘になった場合。
フィールド型の戦場では槍のキャロやロングメイスのミーラが有利だが、屋内だとエミの剣の方が取り回しの面で有利だ。
もっとも、そんな事態になったら、完全に負け戦なのだが。
できるだけ穏便に、陛下を確保しなければならない。
そして、エミを連れて行く理由はもうひとつ。
「キャロ、ミーラ、済まないが、俺達が出発した後、ローチ伯爵家の帝都屋敷まで走ってくれないか? エミは皇宮の中にいると伝えてほしいんだ」
「ローチ家の兵団の力を借りることになるかも知れない、ということですね?」
ミーラが、問い返すようにしてきた。
「ああ、そうだ。現状、近衛兵団が陛下の思い通りに動かせる状況かわからないし、騒乱が起きたら、アテにできるのはローチ伯爵とブリュサンメル上級伯ぐらいしかいないからな」
ブリュサンメル上級伯が出兵に応じていたとして、兵団が到着するまでには、まだしばらく時間がかかるだろう。
「早速行動を開始したいのですが、セニールダー主席宣教師、お願いできますか?」
俺は、突き動かされるように、主席宣教師に頼む。
「今戻ったばかりで、また……というのは、訝しがられる気がしますが、もはやその猶予はないのですね?」
「ええ」
主席宣教師の言葉に、俺は頷く。
「わかりました。とにかく、行くだけ行ってみましょう」
主席宣教師に連れられて、俺、エミ、姉弟子は皇宮の通用門までやってきた。
まずいな……
ひと目見て、焦燥感が一気に跳ね上がるのが解った。
多くの民衆が、城門前でデモを行っている。
プラカードと言うか、木の支柱に布地で作った、アジテーションの入った旗を掲げていた。
ここで揉み合いがあったためか、扉は固く閉ざされているだけではなく、通用門の部分にかかる橋の、堀の外側に柵が立てられ、その前に近衛兵が立っている。
「陛下らしくないな。市民を威嚇する場所に兵を立たせるなど」
姉弟子がそう言った。
だが、静かな口調で言った、その理由はわかっているのだろう、今はそう言う事態なのだ。
「ルイス・モーリス・セニールダー伯爵である。火急の用にて、陛下にお会いしたく、アルヴィン・バックエショフ子爵と、シャーロット・キャロッサ準男爵とともに参った。陛下に謁見願いたい」
主席宣教師がそう伝えると、通用門につながる橋の前で立ち番をしていた兵士は、慌てて通用門の方に走っていく。
通用門が開き、どうやら兵士の上役らしい人間と、立ち番をしていた兵とが、なにか興奮したように会話をしていた。
やがて、上役の兵士長と、先程の兵士とが、駆け寄ってくる。
「お待ちしておりました、アルヴィン・バックエショフ卿」
ん? 何?
「陛下がお待ちになられています、中にお入りください」
ちょっと意外な展開になってきたぞ。
俺はてっきり、最初は拒絶される可能性もあると考えてここまで来た。
それが、陛下が俺を待っている、だと?
「エミ、姉弟子、気をつけてください、何かの罠かもしれない」
俺は、2人に警戒を促す。
もし俺達になにかあっても、ローチ伯がうまく立ち回ってくれれば良いのだが、俺の考えている通りの動きまでは期待できないだろう。
「こちらです」
兵士長が俺達を案内してきたのは、儀式の時に使う謁見の間ではなく、普段、陛下が執政を取り仕切るための部屋だった。
と言っても、俺のマークリスの屋敷の執務室とは、質に天と地ほどの開きがあった。前世に例えるなら、ホワイトハウスのオーバル・オフィスか。
「待っていたわ、アルヴィン! それにリリーも!」
一段高い位置にある執務机の椅子にかけていた陛下が、ぱっと顔を綻ばせるようにして、俺達を歓迎する言葉をかけてくれた。
あれーぇ?
良いのか、こんなに順調に事が進んで。
「アルヴィン・バックエショフ。この折、必ずあなたが来てくれると私は、いえ、余は信じておった」
陛下の口調が変わった。私的な接し方から、皇帝としてのそれになったのだ。
「陛下、火急の事態と訊いて、参上仕りますれば、現状、自分に何をお望みなのか、お聞かせ願えますか?」
俺は、険しい表情をしつつ、やはり、皇帝陛下に対する公的な態度で、それを訊ねた。
「余には…………」
陛下は、ふるふると震えながら、言う。
「もとより余にこの皇帝の座は似つかわしくなかったのやも知れぬ。もう、余には民の心がわからぬ。臣下の真意がわからぬ。従って皇帝として何を為すべきかもわからぬ」
その声は、泣きそうですらあった。
「陛下! それは、我ら臣下の不足にござります。陛下が心を痛めるべきことではありませぬ」
そう言ったのは、陛下の傍らにいた、宰相サッチュス侯爵だった。
そうだ、この人は本祖派ではあるが、それ以上に陛下に心酔している人だったな。
「否!」
俺は敢えて言う。
「以前、茶会の場で自分は言ったはずです、改革なければこの国の行く末は昏い、と。その不足が今、民の怒りを、この混沌を呼んでいるのです、それを直視していただきたい!」
「!?」
サッチュス候を始めとする、陛下の側近たち、さらには、主席宣教師や、エミまでもが、信じられない、驚愕した、という感じで、俺を見ている。
そりゃそうだろう。今まで、陛下には当たり障りのない範囲でしか、陛下に物事を伝えてこなかったのだから。だが、その結果が、これだ。
「やはり余に皇帝の座は荷が勝ちすぎたということか……」
陛下は、俺の言葉に、肩を落とすようにして、弱気にそう言った。
「いいえ! 皇帝なくしてこの国はあり得ませぬ。そして、今、その座にあるのは、他ならぬ陛下であります。ならば、皇帝以外に──陛下以外にこの事態は収集できませぬ」
俺は、敢えて叱咤するように、そう言った。
この人は本来、聡いはずだ。
だから以前、美辞麗句を並べる側近たちとは違う切り口から、物事を見られるだろうと、俺を茶会に呼び出した。
残念ながら、穏便な改革は、すでに不可能になったが、それでも────
「選択肢は2つに1つ、このまま帝国が瓦解するのを目の当たりにし、長きに渡って民を飢えさせ、苦しませるか。あるいは、今ここで一時の痛みに耐え、帝国の繁栄を取り戻すか。すべては、陛下の御意志にかかっております!」
「余は……余に、できるというのか、そのような、大胆なことが……」
「陛下にしか、皇帝にしかできませぬ!」
俺は陛下に決断を迫る。
もう時間がない。
なにより、この人なくして俺達の目的は達成できない。
「アルヴィン・バックエショフ卿の真意の程は測りかねますが」
サッチュス候が言う。
「不肖、バーナード・センツベリー・サッチュス、私も、帝国をまとめ得るのは、陛下以外におられぬと信じております」
ありがたい、サッチュス候の援護射撃だ。
「どうすればいい。余は、何をすればいい。アルヴィン・バックエショフ。そなたには世の真に為すべきことが、なんなのかを解っているのなら、皇帝の恥を承知で言う、教えてはくれぬか」
「簡単なことです」
爆弾、あるいは、毒。そう例えられるべきことを、俺は敢えて口にする。
「今、この帝国は一握りの貴族の秘密政治によって動かされている。その結果が、民の怒り。ならば、為すべきことは2つ、国を真に、皇帝の下において動かすこと。そして、それを公明正大なものであることを民に示すこと!」
0
お気に入りに追加
87
あなたにおすすめの小説

義母に毒を盛られて前世の記憶を取り戻し覚醒しました、貴男は義妹と仲良くすればいいわ。
克全
ファンタジー
「カクヨム」と「小説家になろう」にも投稿しています。
11月9日「カクヨム」恋愛日間ランキング15位
11月11日「カクヨム」恋愛週間ランキング22位
11月11日「カクヨム」恋愛月間ランキング71位
11月4日「小説家になろう」恋愛異世界転生/転移恋愛日間78位

オカン公爵令嬢はオヤジを探す
清水柚木
ファンタジー
フォルトゥーナ王国の唯一の後継者、アダルベルト・フォルトゥーナ・ミケーレは落馬して、前世の記憶を取り戻した。
ハイスペックな王太子として転生し、喜んだのも束の間、転生した世界が乙女ゲームの「愛する貴方と見る黄昏」だと気付く。
そして自身が攻略対象である王子だったと言うことも。
ヒロインとの恋愛なんて冗談じゃない!、とゲームシナリオから抜け出そうとしたところ、前世の母であるオカンと再会。
オカンに振り回されながら、シナリオから抜け出そうと頑張るアダルベルト王子。
オカンにこき使われながら、オヤジ探しを頑張るアダルベルト王子。
あげく魔王までもが復活すると言う。
そんな彼に幸せは訪れるのか?
これは最初から最後まで、オカンに振り回される可哀想なイケメン王子の物語。
※ 「第15回ファンタジー小説大賞」用に過去に書いたものを修正しながらあげていきます。その為、今月中には完結します。
※ 追記 今月中に完結しようと思いましたが、修正が追いつかないので、来月初めに完結になると思います。申し訳ありませんが、もう少しお付き合い頂けるとありがたいです。
※追記 続編を11月から始める予定です。まずは手始めに番外編を書いてみました。よろしくお願いします。

【完結】悪役令嬢に転生したけど、王太子妃にならない方が幸せじゃない?
みちこ
ファンタジー
12歳の時に前世の記憶を思い出し、自分が悪役令嬢なのに気が付いた主人公。
ずっと王太子に片思いしていて、将来は王太子妃になることしか頭になかった主人公だけど、前世の記憶を思い出したことで、王太子の何が良かったのか疑問に思うようになる
色々としがらみがある王太子妃になるより、このまま公爵家の娘として暮らす方が幸せだと気が付く

俺に王太子の側近なんて無理です!
クレハ
ファンタジー
5歳の時公爵家の家の庭にある木から落ちて前世の記憶を思い出した俺。
そう、ここは剣と魔法の世界!
友達の呪いを解くために悪魔召喚をしたりその友達の側近になったりして大忙し。
ハイスペックなちゃらんぽらんな人間を演じる俺の奮闘記、ここに開幕。

最強令嬢とは、1%のひらめきと99%の努力である
megane-san
ファンタジー
私クロエは、生まれてすぐに傷を負った母に抱かれてブラウン辺境伯城に転移しましたが、母はそのまま亡くなり、辺境伯夫妻の養子として育てていただきました。3歳になる頃には闇と光魔法を発現し、さらに暗黒魔法と膨大な魔力まで持っている事が分かりました。そしてなんと私、前世の記憶まで思い出し、前世の知識で辺境伯領はかなり大儲けしてしまいました。私の力は陰謀を企てる者達に狙われましたが、必〇仕事人バリの方々のおかげで悪者は一層され、無事に修行を共にした兄弟子と婚姻することが出来ました。……が、なんと私、魔王に任命されてしまい……。そんな波乱万丈に日々を送る私のお話です。

王女の中身は元自衛官だったので、継母に追放されたけど思い通りになりません
きぬがやあきら
恋愛
「妻はお妃様一人とお約束されたそうですが、今でもまだ同じことが言えますか?」
「正直なところ、不安を感じている」
久方ぶりに招かれた故郷、セレンティア城の月光満ちる庭園で、アシュレイは信じ難い光景を目撃するーー
激闘の末、王座に就いたアルダシールと結ばれた、元セレンティア王国の王女アシュレイ。
アラウァリア国では、新政権を勝ち取ったアシュレイを国母と崇めてくれる国民も多い。だが、結婚から2年、未だ後継ぎに恵まれないアルダシールに側室を推す声も上がり始める。そんな頃、弟シュナイゼルから結婚式の招待が舞い込んだ。
第2幕、連載開始しました!
お気に入り登録してくださった皆様、ありがとうございます! 心より御礼申し上げます。
以下、1章のあらすじです。
アシュレイは前世の記憶を持つ、セレンティア王国の皇女だった。後ろ盾もなく、継母である王妃に体よく追い出されてしまう。
表向きは外交の駒として、アラウァリア王国へ嫁ぐ形だが、国王は御年50歳で既に18人もの妃を持っている。
常に不遇の扱いを受けて、我慢の限界だったアシュレイは、大胆な計画を企てた。
それは輿入れの道中を、自ら雇った盗賊に襲撃させるもの。
サバイバルの知識もあるし、宝飾品を処分して生き抜けば、残りの人生を自由に謳歌できると踏んでいた。
しかし、輿入れ当日アシュレイを攫い出したのは、アラウァリアの第一王子・アルダシール。
盗賊団と共謀し、晴れて自由の身を望んでいたのに、アルダシールはアシュレイを手放してはくれず……。
アシュレイは自由と幸福を手に入れられるのか?
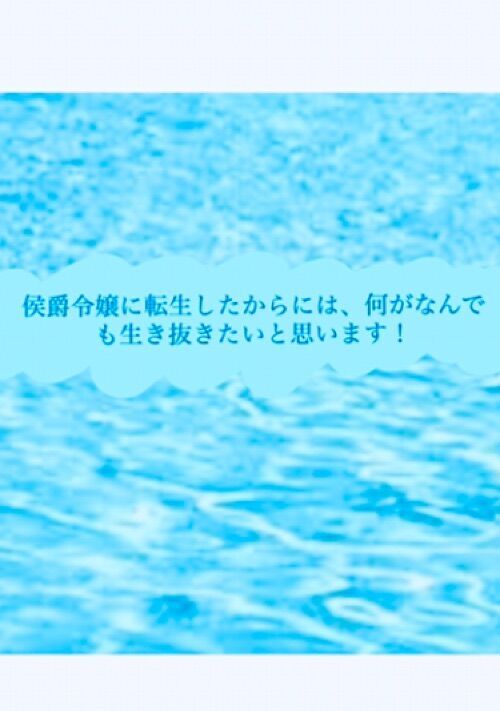
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

我が家に子犬がやって来た!
もも野はち助(旧ハチ助)
ファンタジー
【あらすじ】ラテール伯爵家の令嬢フィリアナは、仕事で帰宅できない父の状況に不満を抱きながら、自身の6歳の誕生日を迎えていた。すると、遅くに帰宅した父が白黒でフワフワな毛をした足の太い子犬を連れ帰る。子犬の飼い主はある高貴な人物らしいが、訳あってラテール家で面倒を見る事になったそうだ。その子犬を自身の誕生日プレゼントだと勘違いしたフィリアナは、兄ロアルドと取り合いながら、可愛がり始める。子犬はすでに名前が決まっており『アルス』といった。
アルスは当初かなり周囲の人間を警戒していたのだが、フィリアナとロアルドが甲斐甲斐しく世話をする事で、すぐに二人と打ち解ける。
だがそんな子犬のアルスには、ある重大な秘密があって……。
この話は、子犬と戯れながら巻き込まれ成長をしていく兄妹の物語。
※全102話で完結済。
★『小説家になろう』でも読めます★
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















