22 / 23
回想~過去編
第二十一話 「ひまわり園~父の思い」
しおりを挟む
やがて廊下の奥から小走りで駆けてくる父の姿が目に入った。
「はぁ、はぁ…………ふぅ、何だお前こんなところにいたのか。玄関で待ってろって言ったろ?心配したじゃないか」
俺が言いつけを守らず玄関を離れてしまったので、血相を変えて……とはいかないが、探しに来てくれたようだった。
「――ああ、ごめんなさい」
「どうした?何かあったのか?」
「いや、別に何も……。それよりもさ、父さんは今まで何やってたの?」
「父さんか?父さんはな、お前がここに通うための手続きをしてたんだよ。すぐに終わると思ってたんだけどこれが意外とややこしくてな……」
「ふぅん、今日はそのために来たんだ?」
「ああ、そうだよ。でも本当は夏休み前に済ませときたかったんだけどな」
「あー、そうなの」
こうして適当に相槌を打っているが、こっちとしては奥の三人のやり取りが気になって仕方が無い。
父の半身に阻まれた先を垣間見るため体を左右させていると、そんな自分の様子に気付いたのか、父は俺の目線の先を辿る様に後ろを振り返った。
「――いや、申し訳ありません。今まで出来る限りこの子と一緒に居られるように時間を作っていたんですが、今回ばかりはどうにも」
「その気苦労、お察し致します。仕事に忙殺されて、とても時間を作れる余裕なんて無かったでしょう」
「ええ、全くです。今更ながら、私と美紗の二人だけでよく今までやってこれたなと思いますよ。本当に、この子には助けられました……」
「秋になればお仕事の方は落ち着くんですか?」
「恐らく……ですがね。私自身、この夏は絶対に落とすことが出来ないんです。今回のチャンスをものにすることが出来れば、会社にとっても、自分にとっても非常に有益なものになります。そして美紗にとっても……ね」
黒川の父親はそう言うと、彼女の頭をそっと撫でた。
――しかし美紗と呼ばれる少女は、顔を上げたりすることはなく、両目を擦りながら嗚咽を漏らしている。
「……まあ、いつかはこんな時も来るだろうと思っていましたが、やはり避けては通れない道なんだと思っています。夏休みが終わるまでの一ヶ月ちょっと。私が迎えに来るまで面倒を見てやってください。宜しくお願いします」
「ええ、こちらこそ宜しくお願いします」
黒川の父親と指導員の女性は、互いに深々とお辞儀をした。
どうやらあの親子もこの施設を利用するのだろう。
しかし当の本人はあまり気が進まないようだが……。
そしてお辞儀を終えると、指導員の女性がおもむろに口を開く。
「……慣れるまでの辛抱、とでも言いましょうか。美紗ちゃんにとって、不安に思うのは最初だけでしょう。慣れてくればきっと楽しいに違いありませんよ。ここには素直で良い子がたくさんいますから」
恐らくあの女性指導員は親の同調を誘いたいのだろう。
知らない人に諭されるよりも、親に諭されたほうが幾分子どもも気が進む。
そのための常套句なのかもしれない。
これを聞いた黒川の父親は、そっと黒川の頭に手を添えて言った。
「……美紗は見ての通り寂しがり屋ですが、いつもは本当にしっかりしているんです。だから私も、慣れるのは時間の問題だと思っています」
指導員の女性は、黒川の父親も自分と同じように考えていることを知り、やんわり笑みを浮かべながら言った。
「ええ、最初は誰だって不安になるものです。それに夏休みの間だけなんですからね。きっと良い思い出が作れるに違いありませんよ」
「はい、私としてもこのひまわり園で良い思い出を作ってほしいです。……ただ」
「ただ……何でしょう?」
黒川の父親は軽く一考したのち、
「私たちからすれば、たった一ヶ月の間だけ、夏休みの間だけなんだから。と思ってしまいますが、本人からしてみればそんな楽観は出来ないでしょう……美紗くらいの年齢であれば尚更ね」
と、黒川に同情するようなことを口にした。
女性指導員はこの言葉に一瞬面食らった様だったが、すぐにその真意を理解したのか、
「申し訳ありません……。ちょっと軽率過ぎましたね。黒川さんたちの気も知らないで……」
と謝罪した。
「いやっ、……ははは、そういった意味で言ったのではありませんよ。親の心配からですのでどうかお気になさらずに」
「いやそんな、滅相もありません。この年齢のお子さんは環境というものに大きく左右されてしまいます。だから黒川さんの言うことはごもっともです。私もこれからは気を付けて参りますわ」
指導員の女性は再度一礼した。
「まあ何はともあれ、この期間中美紗を宜しくお願いします。でも今日は会社からお休みを頂いてますので、このまま美紗を遊園地にでも連れて行ってあげるつもりです。美紗と一緒に居られるせっかくの機会ですからね」
「それが良いと思います。親子水入らず、楽しんできてください」
「ありがとうございます。――さあ美紗、行こう」
挨拶が終わり、これから遊園地に行けるようになったのにもかかわらず、黒川は未だすすり泣いていた。
――ひまわり園のような学童保育施設は、親の仕事の都合など何らかの理由で保育を必要とする児童を、放課後や学校の長期休業の間受け入れ、親や保護者に代わって保育をしてくれる場所だ。
普通に勉強したり、遊んだり。
学校の延長線上に存在しているような施設と言える。
だから何も不安に思うことはない。
何もこのひまわり園に入ったからといって、親とずっと離れ離れになるわけじゃないのだし。
親が不在の間、子どもたちを見てくれる人がいて、その子どもたちは同年代の子どもたちと一緒に過ごせる。
親の身になってみれば、この上ない環境に違いない。
俺はその事をよく理解していたから、このような施設を利用することになってもそれほど不安には思わなかった。
だから、この時彼女がなぜ泣いているのか不思議だったし、同情こそすれど、共感が湧くことはなかった。
「――へえ、何だか家みたいだな」
皮肉ったような言い種で父が口を開いた。
それに対し、前方でのやり取りを見ていて率直に思ったことを呟いてみた。
「あの女の子。なんだか可愛そうだね」
自分の呟きが耳に入ったのか、ふと父は険しい顔で俺に聞いてきた。
「……お前自身はどうなんだ?」
「僕?僕は別に普通だけど」
それを聞いた父は、軽く頭を掻くと困った様にこう言ってきた。
「そうか。…………んー、まああれだ。お前が気丈な奴で良かったよ。「僕も行きたくないよー!やだぁ!」なんて泣かれたらどうしようかと思ったぜ。そんな事言われたら父さん耳塞ぎたくなるから」
表現しづらかったのか、父は遠回しに言ったみたいだが、俺には言っている意味が良く分かった。
「大丈夫だって!夏休みの間はちゃんと毎日行くからさ」
「おっ、……やっぱりお前は親心の分かる奴だねぇ」
「ん?何さその言い方は。なんかおかしいな……やっぱり行くの止めようかなぁ……」
「いやいや、特に意味は御座いませんよ!決断してくださりありがとうございますっ!」
父は大きな声でそう言うと、慌てて俺の方向に向き直り、最敬礼してきた。
――この人は良い歳して何をやっているのだ。
「……父さん、もういいからさ。今日仕事は?」
「よし!海行くか!」
「……えっ?」
いきなり何を言い出すんだ?と思った。
「なんかさ、今日からもうお前を迎え入れてくれるらしいんだよここ。でも実は父さん今日仕事休みなんだよ」
「……あっ、そうだったんだ」
「でさ、お前水着持ってるわけだし、このまま海にでも行かないかと思うんだが……どうする?」
どうするって、そりゃあもちろん……。
「海行きたい!」
――久しぶりの海水浴を満喫し、夕食は贅沢にステーキも食べた。
とても充実した一日だったので、ひまわり園に行くことに対しての抵抗なんてものは何も無くなっていた。
「ねえ、僕が子どもか大人かって言ったらさ、やっぱり僕大人じゃない?」
レストランからの帰りの車中で、俺は父に言ってやった。
「やっぱりってなんだよ。まだ自分が大人だと思ってるのか?」
「当たり前じゃないか。今日見たでしょあの親子!あの女の子泣いてたじゃん。でも僕は泣いてない。泣かないってことは大人なんだ」
「ふっ、お前は何がしたいんだよ。人間誰でも泣くぜ?」
父は鼻で笑い、実にくだらなそうな顔をしている。
「あの女の子は親といられないと泣いちゃうんだ。子どもだから一人になるのが怖いんだ」
「はいはい、じゃあ大人だと一人になるのは怖くないんだよな?」
「その通りさ。僕は別に父さんがずっと仕事で居なくても大丈夫だし、一人でもへっちゃらさ!」
父は大袈裟に声を出して笑った後、ニヤニヤしながら言ってきた。
「……じゃあさ、お前はここで降りるか?」
「えっ?降りるって何をさ」
「車だよ車。そんなに言うんならここからでも一人で帰れるよな?……父さん今どこか遊びに行きたい気分なんだよなぁ。お前が一人で帰れるってんなら、お前降ろして父さんは一人で遊びに行こうかなぁ」
「それは……」
「くっくっく、お前ならここから一人でも帰れるよなぁ。大人なんだしなぁ」
「いや、僕帰り道分からないし……」
「大人だったら何とか出来るだろ?人に聞くなりなんなりさぁ。……あっ、おまわりさんに聞けばすぐに帰れるな。迷子か家出だと思って家まで送ってくれると思うぜ?くくくっ!あー、いやその前に大人である父さんに電話が掛かってくるかな?「お子さんを預かってますので迎えに来てください」ってな!――はっはっは!」
「…………っ!」
父はムッとしている俺の顔を見て笑いが止まらないようだった。
――くそ、いつか見てろよ。
「……ははは、まったく小生意気な奴だよお前は。今お前に必要なものは立場を弁えることだな」
「……うるさいな」
「まあとにかく、明日から俺が仕事の間はしっかり頼むな。お前なら心配ないと思うけど」
「……うん、楽しい夏休みにするよ」
この時の父は、何だか嬉しそうだった。
車が見覚えのある道に差し掛かると、家まではもうすぐだった。
「はぁ、はぁ…………ふぅ、何だお前こんなところにいたのか。玄関で待ってろって言ったろ?心配したじゃないか」
俺が言いつけを守らず玄関を離れてしまったので、血相を変えて……とはいかないが、探しに来てくれたようだった。
「――ああ、ごめんなさい」
「どうした?何かあったのか?」
「いや、別に何も……。それよりもさ、父さんは今まで何やってたの?」
「父さんか?父さんはな、お前がここに通うための手続きをしてたんだよ。すぐに終わると思ってたんだけどこれが意外とややこしくてな……」
「ふぅん、今日はそのために来たんだ?」
「ああ、そうだよ。でも本当は夏休み前に済ませときたかったんだけどな」
「あー、そうなの」
こうして適当に相槌を打っているが、こっちとしては奥の三人のやり取りが気になって仕方が無い。
父の半身に阻まれた先を垣間見るため体を左右させていると、そんな自分の様子に気付いたのか、父は俺の目線の先を辿る様に後ろを振り返った。
「――いや、申し訳ありません。今まで出来る限りこの子と一緒に居られるように時間を作っていたんですが、今回ばかりはどうにも」
「その気苦労、お察し致します。仕事に忙殺されて、とても時間を作れる余裕なんて無かったでしょう」
「ええ、全くです。今更ながら、私と美紗の二人だけでよく今までやってこれたなと思いますよ。本当に、この子には助けられました……」
「秋になればお仕事の方は落ち着くんですか?」
「恐らく……ですがね。私自身、この夏は絶対に落とすことが出来ないんです。今回のチャンスをものにすることが出来れば、会社にとっても、自分にとっても非常に有益なものになります。そして美紗にとっても……ね」
黒川の父親はそう言うと、彼女の頭をそっと撫でた。
――しかし美紗と呼ばれる少女は、顔を上げたりすることはなく、両目を擦りながら嗚咽を漏らしている。
「……まあ、いつかはこんな時も来るだろうと思っていましたが、やはり避けては通れない道なんだと思っています。夏休みが終わるまでの一ヶ月ちょっと。私が迎えに来るまで面倒を見てやってください。宜しくお願いします」
「ええ、こちらこそ宜しくお願いします」
黒川の父親と指導員の女性は、互いに深々とお辞儀をした。
どうやらあの親子もこの施設を利用するのだろう。
しかし当の本人はあまり気が進まないようだが……。
そしてお辞儀を終えると、指導員の女性がおもむろに口を開く。
「……慣れるまでの辛抱、とでも言いましょうか。美紗ちゃんにとって、不安に思うのは最初だけでしょう。慣れてくればきっと楽しいに違いありませんよ。ここには素直で良い子がたくさんいますから」
恐らくあの女性指導員は親の同調を誘いたいのだろう。
知らない人に諭されるよりも、親に諭されたほうが幾分子どもも気が進む。
そのための常套句なのかもしれない。
これを聞いた黒川の父親は、そっと黒川の頭に手を添えて言った。
「……美紗は見ての通り寂しがり屋ですが、いつもは本当にしっかりしているんです。だから私も、慣れるのは時間の問題だと思っています」
指導員の女性は、黒川の父親も自分と同じように考えていることを知り、やんわり笑みを浮かべながら言った。
「ええ、最初は誰だって不安になるものです。それに夏休みの間だけなんですからね。きっと良い思い出が作れるに違いありませんよ」
「はい、私としてもこのひまわり園で良い思い出を作ってほしいです。……ただ」
「ただ……何でしょう?」
黒川の父親は軽く一考したのち、
「私たちからすれば、たった一ヶ月の間だけ、夏休みの間だけなんだから。と思ってしまいますが、本人からしてみればそんな楽観は出来ないでしょう……美紗くらいの年齢であれば尚更ね」
と、黒川に同情するようなことを口にした。
女性指導員はこの言葉に一瞬面食らった様だったが、すぐにその真意を理解したのか、
「申し訳ありません……。ちょっと軽率過ぎましたね。黒川さんたちの気も知らないで……」
と謝罪した。
「いやっ、……ははは、そういった意味で言ったのではありませんよ。親の心配からですのでどうかお気になさらずに」
「いやそんな、滅相もありません。この年齢のお子さんは環境というものに大きく左右されてしまいます。だから黒川さんの言うことはごもっともです。私もこれからは気を付けて参りますわ」
指導員の女性は再度一礼した。
「まあ何はともあれ、この期間中美紗を宜しくお願いします。でも今日は会社からお休みを頂いてますので、このまま美紗を遊園地にでも連れて行ってあげるつもりです。美紗と一緒に居られるせっかくの機会ですからね」
「それが良いと思います。親子水入らず、楽しんできてください」
「ありがとうございます。――さあ美紗、行こう」
挨拶が終わり、これから遊園地に行けるようになったのにもかかわらず、黒川は未だすすり泣いていた。
――ひまわり園のような学童保育施設は、親の仕事の都合など何らかの理由で保育を必要とする児童を、放課後や学校の長期休業の間受け入れ、親や保護者に代わって保育をしてくれる場所だ。
普通に勉強したり、遊んだり。
学校の延長線上に存在しているような施設と言える。
だから何も不安に思うことはない。
何もこのひまわり園に入ったからといって、親とずっと離れ離れになるわけじゃないのだし。
親が不在の間、子どもたちを見てくれる人がいて、その子どもたちは同年代の子どもたちと一緒に過ごせる。
親の身になってみれば、この上ない環境に違いない。
俺はその事をよく理解していたから、このような施設を利用することになってもそれほど不安には思わなかった。
だから、この時彼女がなぜ泣いているのか不思議だったし、同情こそすれど、共感が湧くことはなかった。
「――へえ、何だか家みたいだな」
皮肉ったような言い種で父が口を開いた。
それに対し、前方でのやり取りを見ていて率直に思ったことを呟いてみた。
「あの女の子。なんだか可愛そうだね」
自分の呟きが耳に入ったのか、ふと父は険しい顔で俺に聞いてきた。
「……お前自身はどうなんだ?」
「僕?僕は別に普通だけど」
それを聞いた父は、軽く頭を掻くと困った様にこう言ってきた。
「そうか。…………んー、まああれだ。お前が気丈な奴で良かったよ。「僕も行きたくないよー!やだぁ!」なんて泣かれたらどうしようかと思ったぜ。そんな事言われたら父さん耳塞ぎたくなるから」
表現しづらかったのか、父は遠回しに言ったみたいだが、俺には言っている意味が良く分かった。
「大丈夫だって!夏休みの間はちゃんと毎日行くからさ」
「おっ、……やっぱりお前は親心の分かる奴だねぇ」
「ん?何さその言い方は。なんかおかしいな……やっぱり行くの止めようかなぁ……」
「いやいや、特に意味は御座いませんよ!決断してくださりありがとうございますっ!」
父は大きな声でそう言うと、慌てて俺の方向に向き直り、最敬礼してきた。
――この人は良い歳して何をやっているのだ。
「……父さん、もういいからさ。今日仕事は?」
「よし!海行くか!」
「……えっ?」
いきなり何を言い出すんだ?と思った。
「なんかさ、今日からもうお前を迎え入れてくれるらしいんだよここ。でも実は父さん今日仕事休みなんだよ」
「……あっ、そうだったんだ」
「でさ、お前水着持ってるわけだし、このまま海にでも行かないかと思うんだが……どうする?」
どうするって、そりゃあもちろん……。
「海行きたい!」
――久しぶりの海水浴を満喫し、夕食は贅沢にステーキも食べた。
とても充実した一日だったので、ひまわり園に行くことに対しての抵抗なんてものは何も無くなっていた。
「ねえ、僕が子どもか大人かって言ったらさ、やっぱり僕大人じゃない?」
レストランからの帰りの車中で、俺は父に言ってやった。
「やっぱりってなんだよ。まだ自分が大人だと思ってるのか?」
「当たり前じゃないか。今日見たでしょあの親子!あの女の子泣いてたじゃん。でも僕は泣いてない。泣かないってことは大人なんだ」
「ふっ、お前は何がしたいんだよ。人間誰でも泣くぜ?」
父は鼻で笑い、実にくだらなそうな顔をしている。
「あの女の子は親といられないと泣いちゃうんだ。子どもだから一人になるのが怖いんだ」
「はいはい、じゃあ大人だと一人になるのは怖くないんだよな?」
「その通りさ。僕は別に父さんがずっと仕事で居なくても大丈夫だし、一人でもへっちゃらさ!」
父は大袈裟に声を出して笑った後、ニヤニヤしながら言ってきた。
「……じゃあさ、お前はここで降りるか?」
「えっ?降りるって何をさ」
「車だよ車。そんなに言うんならここからでも一人で帰れるよな?……父さん今どこか遊びに行きたい気分なんだよなぁ。お前が一人で帰れるってんなら、お前降ろして父さんは一人で遊びに行こうかなぁ」
「それは……」
「くっくっく、お前ならここから一人でも帰れるよなぁ。大人なんだしなぁ」
「いや、僕帰り道分からないし……」
「大人だったら何とか出来るだろ?人に聞くなりなんなりさぁ。……あっ、おまわりさんに聞けばすぐに帰れるな。迷子か家出だと思って家まで送ってくれると思うぜ?くくくっ!あー、いやその前に大人である父さんに電話が掛かってくるかな?「お子さんを預かってますので迎えに来てください」ってな!――はっはっは!」
「…………っ!」
父はムッとしている俺の顔を見て笑いが止まらないようだった。
――くそ、いつか見てろよ。
「……ははは、まったく小生意気な奴だよお前は。今お前に必要なものは立場を弁えることだな」
「……うるさいな」
「まあとにかく、明日から俺が仕事の間はしっかり頼むな。お前なら心配ないと思うけど」
「……うん、楽しい夏休みにするよ」
この時の父は、何だか嬉しそうだった。
車が見覚えのある道に差し掛かると、家まではもうすぐだった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
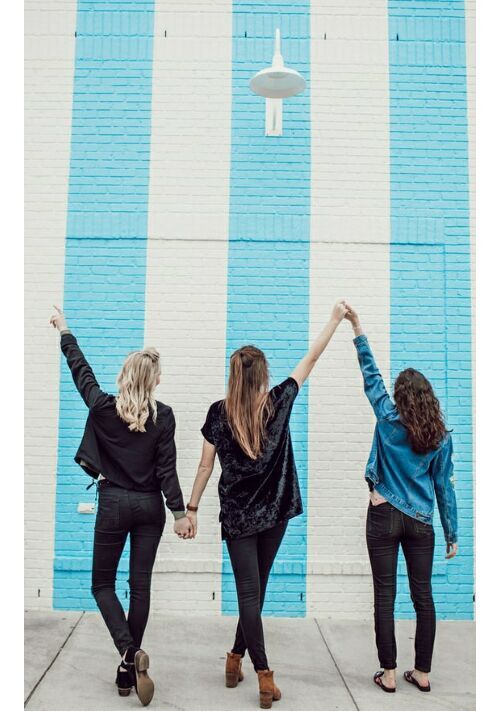
女子高生は小悪魔だ~教師のボクはこんな毎日送ってます
藤 ゆう
青春
ボクはある私立女子高の体育教師。大学をでて、初めての赴任だった。
「男子がいないからなぁ、ブリっ子もしないし、かなり地がでるぞ…おまえ食われるなよ(笑)」
先輩に聞いていたから少しは身構えていたけれど…
色んな(笑)事件がまきおこる。
どこもこんなものなのか?
新米のボクにはわからないけれど、ついにスタートした可愛い小悪魔たちとの毎日。

自称未来の妻なヤンデレ転校生に振り回された挙句、最終的に責任を取らされる話
水島紗鳥
青春
成績優秀でスポーツ万能な男子高校生の黒月拓馬は、学校では常に1人だった。
そんなハイスペックぼっちな拓馬の前に未来の妻を自称する日英ハーフの美少女転校生、十六夜アリスが現れた事で平穏だった日常生活が激変する。
凄まじくヤンデレなアリスは拓馬を自分だけの物にするためにありとあらゆる手段を取り、どんどん外堀を埋めていく。
「なあ、サインと判子欲しいって渡された紙が記入済婚姻届なのは気のせいか?」
「気にしない気にしない」
「いや、気にするに決まってるだろ」
ヤンデレなアリスから完全にロックオンされてしまった拓馬の運命はいかに……?(なお、もう一生逃げられない模様)
表紙はイラストレーターの谷川犬兎様に描いていただきました。
小説投稿サイトでの利用許可を頂いております。

何故か超絶美少女に嫌われる日常
やまたけ
青春
K市内一と言われる超絶美少女の高校三年生柊美久。そして同じ高校三年生の武智悠斗は、何故か彼女に絡まれ疎まれる。何をしたのか覚えがないが、とにかく何かと文句を言われる毎日。だが、それでも彼女に歯向かえない事情があるようで……。疋田美里という、主人公がバイト先で知り合った可愛い女子高生。彼女の存在がより一層、この物語を複雑化させていくようで。
しょっぱなヒロインから嫌われるという、ちょっとひねくれた恋愛小説。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

隣人の女性がDVされてたから助けてみたら、なぜかその人(年下の女子大生)と同棲することになった(なんで?)
チドリ正明@不労所得発売中!!
青春
マンションの隣の部屋から女性の悲鳴と男性の怒鳴り声が聞こえた。
主人公 時田宗利(ときたむねとし)の判断は早かった。迷わず訪問し時間を稼ぎ、確証が取れた段階で警察に通報。DV男を現行犯でとっちめることに成功した。
ちっぽけな勇気と小心者が持つ単なる親切心でやった宗利は日常に戻る。
しかし、しばらくして宗時は見覚えのある女性が部屋の前にしゃがみ込んでいる姿を発見した。
その女性はDVを受けていたあの時の隣人だった。
「頼れる人がいないんです……私と一緒に暮らしてくれませんか?」
これはDVから女性を守ったことで始まる新たな恋物語。

転校して来た美少女が前幼なじみだった件。
ながしょー
青春
ある日のHR。担任の呼び声とともに教室に入ってきた子は、とてつもない美少女だった。この世とはかけ離れた美貌に、男子はおろか、女子すらも言葉を詰まらせ、何も声が出てこない模様。モデルでもやっていたのか?そんなことを思いながら、彼女の自己紹介などを聞いていると、担任の先生がふと、俺の方を……いや、隣の席を指差す。今朝から気になってはいたが、彼女のための席だったということに今知ったのだが……男子たちの目線が異様に悪意の籠ったものに感じるが気のせいか?とにもかくにも隣の席が学校一の美少女ということになったわけで……。
このときの俺はまだ気づいていなかった。この子を軸として俺の身の回りが修羅場と化すことに。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















