14 / 23
物語が動き始める章
第十三話 「二人の関係」
しおりを挟む
誰か砂時計をひっくり返すのを忘れてしまったのだろうか?
さららと流れ落ちる砂のささやきさえも聞こえず、まるで時が止まってしまったかのようだった。
顔を上げたくない――。
衝突の寸前に、一瞬目に映ったのがちょうど俺が探していた「彼女」だった。
目の前に佇む「彼女」は、間違いなく昨日美術室で会ったその人、「神川」という女子生徒なのだ。
でも……これから何を話す?
俺もさっさと顔を上げてしまいたいが、話す内容が思いつかない……。
向こうも黙り込んだまま。
神川もまた、俺に発する言葉でも選んでいるのだろうか。
ほんの少し、このたった数秒の沈黙が何時間にも感じてしまう。
この間に、考えていた内容を原稿用紙十枚分でまとめなさいと問われたら、間違いなく十分に余裕を持ってまとめられるに違いない。そんな時間の感覚だ。
しかし十枚目のたった残り一行にさしかかろうとした辺りで、その確信は砕かれた。
「まさか…………君ってもしかして……高月くん……なの?」
「え?えっと……」
――いえ、違います。などと冗談を言える余裕は無かった。
なぜなら、向こうも時間の感覚が自分と同じようになっているのだろうと高を括っていたので、思わぬ彼女の問い掛けに言葉が詰まってしまった。
「高月くん……なんだよね。そう……だよね?」
彼女の声色には、実に大きな不安が含まれているのを感じる。
そんな声を聞かされては黙っているのも可愛そうに思えてきた。
「そうだよ。俺は高月、高月望。君が思っている通りの人間で間違いないよ」
彼女の問い掛けに答えてやると、流れに身を任せるように顔を上げて、彼女をしっかりと見据えた。
……が、彼女は後ろを向いていた。
「で、君は神川さんだよね」
後姿に声を掛けると、五限は体育なのかジャージ姿の彼女が無言で肯く。
「昨日はあれからすぐ帰ったの?」
「……うん」
「そっか。最近はすぐ暗くなっちゃうからね。気をつけないと」
「……うん」
「まあでも家近いって言ってたしそんなでもないか」
「…………」
目の前にいる相手は俺だ、高月望なんだ。
と、彼女の不安を取り払うべく、立て続けに言葉を投げかけたが何か様子がおかしい。
美術室で話した時はこんな感じじゃなかったよな?
というか……泣いてる?
「神川さん?あの…………何かあったの?大丈夫?」
「…………いや、何でも……ない……よ…………う……うっ…………く」
――これは何でもないわけがない。
恐らく彼女は泣いているのだ。
肩を震わせ、元々小柄な体を更に小さくして泣いている。
嫌なことや辛いことがあっても、それを他人に見せないように懸命に堪えるが、涙が溢れ出て止まらない。
そんなところだろう。
しかしそれでも前を向いていかなくちゃダメだ。
遅かれ早かれ避けては通れないイベントが人生にはいくつも待ち受けている。
ただ今回はそれが早く来てしまっただけなんだ。
だから立ち向かって今のうちに乗り越えよう!
不幸は早いうちに摘んでおきたいもの!
幸せなんて後からいくらでも作れるさ。
今は泣いている場合じゃない。
涙は嬉しいときに流すもの!
俺は人が悲しむ姿なんて見たくないんだ!
だから俺が手を貸してやる。
俺が何とかしてやる。
さあ、泣くのはそこまでだ!
涙を拭いて――。
「どしたの?」
「……………………えっ?」
ふと気付くと、いきなり眼前に神川の顔が現れた。
――いや、ただ俺が気付かなかっただけか。
「たーかつーき君っ!どーしったのっ!?」
「うわっ!な、何?」
続けざまに大きな声を出されたので、俺はまた尻餅をついてしまいそうになった。
「……プッ!アッハハハハッ!!!」
よっぽど間抜け面をしていたのか、神川は大きな声で文字通り腹を抱えて笑っていた。
「あの……神川さん?」
俺が唖然としている間もまだ笑いが止まらないようだ。
「状況が飲み込めないんだけど……。俺、そんなに面白いこと言った?というか神川さん泣いてなかった?」
神川は笑い過ぎて言葉を発しようにも発せない様子だった。
――何だ?変なキノコでも食ってしまったのか?
「はぁ、はぁ……っく、いや……あの、ごめんね?ちょっと驚かせようとしてやっただけなの。気にしないでね」
ようやく笑いが鎮まったのか、神川は徐々に冷静さを取り戻していった。
――しかし、馬鹿にされたような感じがして逆に俺の不快感が徐々に増して来た。
「いや、気にするよ。いきなり泣き出したのかと思ったら何か笑い出すし……」
「ああ…………そうだよね。ちょっとやり過ぎたかもね。でもでも!本気にするとは思ってなくて……あ、もしかして気分悪くしちゃった?」
「気分悪いっていうか……心配したよ。ほら、結構勢いよくぶつかっちゃったでしょ?それで何かおかしくなったんじゃないかなぁって」
遠まわしに皮肉を投げたつもりだったが、神川はそう受け取らなかったようだ。
なぜか俯いて若干顔を赤くしている。
「そっか、心配させちゃってホントごめんね。でもあたしは大丈夫だよ。どこも怪我したりしてないし。それより高月くんはどう?お尻打っちゃったんじゃない?」
「……いや、俺も大丈夫だよ。ただ尻餅ついただけだし」
――腰の痛みなんてもうとっくに無くなっている。
それよりも突っ込んできた神川のほうが心配だ。
「そっか。まあ、おしりはお餅みたいに柔らかいからね!」
「ああ、そうだな……。確かに体の部位では柔らかいほうだよな…………」
「ん?あたし何か変なこと言った?」
「いや、何でもないよ」
「うーん、気になるなぁ……」
腕組みをしながら人差し指を口にあてて考え込む神川。
――愉快な人だなと思った。
「神川さん、お考え事中悪いけど……」
「ちょっと待って!そこ違う!」
荒々しく俺の言葉を遮り、神川は凛々しい表情で口に当てていた人差し指を真っ直ぐ俺に向けた。
「違う?」
「そうそう。何ていうのかな……さっきから思ってたんだけど微妙なんだよね」
微妙って……いきなり何を言い出すのだろうか?
「微妙?また俺変なこと言った?」
「ううん、言ってないけど……別にそういうことじゃないよ」
なんだか一々癪に障るな……何かあるならハッキリ言えばいいのに。
「じゃあ何?言いたいことがあるならハッキリ言ってくれない?」
俺が若干口調を強めて追求すると、神川は俺に向けた指を力無く下ろし俯いてしまった。
「いや……ごめんなさい。何でもないの」
そして徐々に情けない表情になっていく。
――これはどうしたもんだろう。
「何でもないなら別に良いんだけど……それより神川さんさ、俺……」
「ああ、あの!えっと……や、やっぱり何でも無くない!」
そう言いつつ、顔を上げた神川と目が合った。
すると、慌てて後ろを向いてしまった。
――何か前にもこんな時がなかったっけ?
「一体どうしたんだよ?」
俺には何となく神川が後ろを向くことが何を意味するか、大体理解出来る。
「あたし……神川亜希っていうの…………」
「知ってる」
――荻原のメモに書かれていたのですでに知っていた。
「そう……なんだ。ありがと」
「どういたしまして。でもそれがどうかした?」
名前を聞かされただけじゃ、普通「あ、そうですか」くらいしか出てこない。だから何?って話だ。
「あのね?さん…………とか付けなくていいから……」
なるほど、ここで彼女の意図は完全に理解出来た。
呼び捨てでも構わないっていうんだな?
――すでに心の中では呼び捨てなので別に違和感などはないが。
「なんだ、それなら早く言ってくれればいいのに。じゃあこれからは神川って呼ぶよ」
「……やだ。それはやめて」
「はぁ?」
後ろ手を組んで右足のつま先をトントンさせている神川は、きっと笑い出したいのを堪えているに違いない。
また困惑した俺を小馬鹿にするつもりだろう。
「じゃあ何がしたいんだよ。さんを付けないで一体どう……」
「亜希……がいい」
「亜希?」
「あたしのこと、亜希って呼んで欲しいな……」
――ボソッと聞こえたそれは、俺がズレているんだなと思わせるに十分な一言だった。
実際、そんなことを一瞬たりも思わなかった。
「あ……ああ、いいけど」
「…………ほんとに?」
俺の返事を聞き、神川はこっちを振り返って尋ねた。
――今度は俺の両目をしっかりと見つめてくる。
しかしそれは、すぐに目を逸らしてしまいたくなるほどの不安を湛えた瞳だった。
神川の気持ちがフィルターも通さずに直に伝わってくる。
このまま直視して良いものかと俺でさえ不安にさせてしまうほどの眼差しだ。
「そ、そんな心配しなくても大丈夫だって。……よし、これからは亜希だ!よろしくな、亜希!」
亜希の不安を取り払うため努めて明るく振舞うと、彼女はさっきと打って変わり、屈託のない笑顔を見せてくれた。
「えへへ、嬉しい……」
「そんなに嬉しかった?」
「もちろん!」
ニコッと並びの良い真っ白な歯を覗かせて喜ぶ亜希。
彼女の笑顔を見ていると、こっちまで自然と笑みが零れてくる。
――今までの誰よりも可愛らしい笑顔だった。
「ねえ、高月くん……聞いていい?」
「どうかした?……もしかして俺のことは何て呼べば良いかって?それは君に任せるよ」
のぞみ……だけは嫌だな。
いつかの誰かさんがそう呼んだおかげで昔散々からかわれたからな……。
「ううん、そうじゃなくて。あたしたちって一体どんな関係なのかなって」
「えっ?」
――ごく自然な流れでサラッと言われたので若干困惑した。
「どんな関係なんだろうね、あたしたちって」
「それは……」
亜希は近くにあった体重計に乗っており、その針の揺れは中々定まらない。
どんな関係かって俺に聞かれてもなぁ……。
ただの知り合い?友達同士?それとも……恋人同士?
「確かに何なんだろう。――亜希はどう思ってる?」
体重計の針が重さを示す前に、亜希はピョンとカエルよろしく台から飛び降りて俺に告げた。
「――それは高月くんに任せる」
彼女は、とても優しい微笑みで俺に判断を委ねた。
「俺達は……」
と、口は動くがこれに続く言葉などない。
俺はどう答えて良いか思いつかなかった。
思いつかなかった?いや、それは違う。俺はただ――。
自問自答でうろたえる俺を知ってか知らずか、亜希はさっさと保健室から出ようとしていた。
「亜希!ちょっと待ってくれ、どこに行くんだ?」
亜希は振り返ることなく「もう昼休み終わるから」と冷淡に言い放つ。
――時計を見ると、後二分で五限のチャイムが鳴ってしまう時間だ。
「高月くん……今日さ、一緒に帰ろ?」
「え?あ、ああいいよ。一緒に帰ろう、亜希が良いなら」
「……じゃあ待ってるね?教室でずっと」
「教室?そうだね、じゃ授業終わったら行くよ」
俺との約束を済ませると、彼女は足早に保健室から出て行った。
さららと流れ落ちる砂のささやきさえも聞こえず、まるで時が止まってしまったかのようだった。
顔を上げたくない――。
衝突の寸前に、一瞬目に映ったのがちょうど俺が探していた「彼女」だった。
目の前に佇む「彼女」は、間違いなく昨日美術室で会ったその人、「神川」という女子生徒なのだ。
でも……これから何を話す?
俺もさっさと顔を上げてしまいたいが、話す内容が思いつかない……。
向こうも黙り込んだまま。
神川もまた、俺に発する言葉でも選んでいるのだろうか。
ほんの少し、このたった数秒の沈黙が何時間にも感じてしまう。
この間に、考えていた内容を原稿用紙十枚分でまとめなさいと問われたら、間違いなく十分に余裕を持ってまとめられるに違いない。そんな時間の感覚だ。
しかし十枚目のたった残り一行にさしかかろうとした辺りで、その確信は砕かれた。
「まさか…………君ってもしかして……高月くん……なの?」
「え?えっと……」
――いえ、違います。などと冗談を言える余裕は無かった。
なぜなら、向こうも時間の感覚が自分と同じようになっているのだろうと高を括っていたので、思わぬ彼女の問い掛けに言葉が詰まってしまった。
「高月くん……なんだよね。そう……だよね?」
彼女の声色には、実に大きな不安が含まれているのを感じる。
そんな声を聞かされては黙っているのも可愛そうに思えてきた。
「そうだよ。俺は高月、高月望。君が思っている通りの人間で間違いないよ」
彼女の問い掛けに答えてやると、流れに身を任せるように顔を上げて、彼女をしっかりと見据えた。
……が、彼女は後ろを向いていた。
「で、君は神川さんだよね」
後姿に声を掛けると、五限は体育なのかジャージ姿の彼女が無言で肯く。
「昨日はあれからすぐ帰ったの?」
「……うん」
「そっか。最近はすぐ暗くなっちゃうからね。気をつけないと」
「……うん」
「まあでも家近いって言ってたしそんなでもないか」
「…………」
目の前にいる相手は俺だ、高月望なんだ。
と、彼女の不安を取り払うべく、立て続けに言葉を投げかけたが何か様子がおかしい。
美術室で話した時はこんな感じじゃなかったよな?
というか……泣いてる?
「神川さん?あの…………何かあったの?大丈夫?」
「…………いや、何でも……ない……よ…………う……うっ…………く」
――これは何でもないわけがない。
恐らく彼女は泣いているのだ。
肩を震わせ、元々小柄な体を更に小さくして泣いている。
嫌なことや辛いことがあっても、それを他人に見せないように懸命に堪えるが、涙が溢れ出て止まらない。
そんなところだろう。
しかしそれでも前を向いていかなくちゃダメだ。
遅かれ早かれ避けては通れないイベントが人生にはいくつも待ち受けている。
ただ今回はそれが早く来てしまっただけなんだ。
だから立ち向かって今のうちに乗り越えよう!
不幸は早いうちに摘んでおきたいもの!
幸せなんて後からいくらでも作れるさ。
今は泣いている場合じゃない。
涙は嬉しいときに流すもの!
俺は人が悲しむ姿なんて見たくないんだ!
だから俺が手を貸してやる。
俺が何とかしてやる。
さあ、泣くのはそこまでだ!
涙を拭いて――。
「どしたの?」
「……………………えっ?」
ふと気付くと、いきなり眼前に神川の顔が現れた。
――いや、ただ俺が気付かなかっただけか。
「たーかつーき君っ!どーしったのっ!?」
「うわっ!な、何?」
続けざまに大きな声を出されたので、俺はまた尻餅をついてしまいそうになった。
「……プッ!アッハハハハッ!!!」
よっぽど間抜け面をしていたのか、神川は大きな声で文字通り腹を抱えて笑っていた。
「あの……神川さん?」
俺が唖然としている間もまだ笑いが止まらないようだ。
「状況が飲み込めないんだけど……。俺、そんなに面白いこと言った?というか神川さん泣いてなかった?」
神川は笑い過ぎて言葉を発しようにも発せない様子だった。
――何だ?変なキノコでも食ってしまったのか?
「はぁ、はぁ……っく、いや……あの、ごめんね?ちょっと驚かせようとしてやっただけなの。気にしないでね」
ようやく笑いが鎮まったのか、神川は徐々に冷静さを取り戻していった。
――しかし、馬鹿にされたような感じがして逆に俺の不快感が徐々に増して来た。
「いや、気にするよ。いきなり泣き出したのかと思ったら何か笑い出すし……」
「ああ…………そうだよね。ちょっとやり過ぎたかもね。でもでも!本気にするとは思ってなくて……あ、もしかして気分悪くしちゃった?」
「気分悪いっていうか……心配したよ。ほら、結構勢いよくぶつかっちゃったでしょ?それで何かおかしくなったんじゃないかなぁって」
遠まわしに皮肉を投げたつもりだったが、神川はそう受け取らなかったようだ。
なぜか俯いて若干顔を赤くしている。
「そっか、心配させちゃってホントごめんね。でもあたしは大丈夫だよ。どこも怪我したりしてないし。それより高月くんはどう?お尻打っちゃったんじゃない?」
「……いや、俺も大丈夫だよ。ただ尻餅ついただけだし」
――腰の痛みなんてもうとっくに無くなっている。
それよりも突っ込んできた神川のほうが心配だ。
「そっか。まあ、おしりはお餅みたいに柔らかいからね!」
「ああ、そうだな……。確かに体の部位では柔らかいほうだよな…………」
「ん?あたし何か変なこと言った?」
「いや、何でもないよ」
「うーん、気になるなぁ……」
腕組みをしながら人差し指を口にあてて考え込む神川。
――愉快な人だなと思った。
「神川さん、お考え事中悪いけど……」
「ちょっと待って!そこ違う!」
荒々しく俺の言葉を遮り、神川は凛々しい表情で口に当てていた人差し指を真っ直ぐ俺に向けた。
「違う?」
「そうそう。何ていうのかな……さっきから思ってたんだけど微妙なんだよね」
微妙って……いきなり何を言い出すのだろうか?
「微妙?また俺変なこと言った?」
「ううん、言ってないけど……別にそういうことじゃないよ」
なんだか一々癪に障るな……何かあるならハッキリ言えばいいのに。
「じゃあ何?言いたいことがあるならハッキリ言ってくれない?」
俺が若干口調を強めて追求すると、神川は俺に向けた指を力無く下ろし俯いてしまった。
「いや……ごめんなさい。何でもないの」
そして徐々に情けない表情になっていく。
――これはどうしたもんだろう。
「何でもないなら別に良いんだけど……それより神川さんさ、俺……」
「ああ、あの!えっと……や、やっぱり何でも無くない!」
そう言いつつ、顔を上げた神川と目が合った。
すると、慌てて後ろを向いてしまった。
――何か前にもこんな時がなかったっけ?
「一体どうしたんだよ?」
俺には何となく神川が後ろを向くことが何を意味するか、大体理解出来る。
「あたし……神川亜希っていうの…………」
「知ってる」
――荻原のメモに書かれていたのですでに知っていた。
「そう……なんだ。ありがと」
「どういたしまして。でもそれがどうかした?」
名前を聞かされただけじゃ、普通「あ、そうですか」くらいしか出てこない。だから何?って話だ。
「あのね?さん…………とか付けなくていいから……」
なるほど、ここで彼女の意図は完全に理解出来た。
呼び捨てでも構わないっていうんだな?
――すでに心の中では呼び捨てなので別に違和感などはないが。
「なんだ、それなら早く言ってくれればいいのに。じゃあこれからは神川って呼ぶよ」
「……やだ。それはやめて」
「はぁ?」
後ろ手を組んで右足のつま先をトントンさせている神川は、きっと笑い出したいのを堪えているに違いない。
また困惑した俺を小馬鹿にするつもりだろう。
「じゃあ何がしたいんだよ。さんを付けないで一体どう……」
「亜希……がいい」
「亜希?」
「あたしのこと、亜希って呼んで欲しいな……」
――ボソッと聞こえたそれは、俺がズレているんだなと思わせるに十分な一言だった。
実際、そんなことを一瞬たりも思わなかった。
「あ……ああ、いいけど」
「…………ほんとに?」
俺の返事を聞き、神川はこっちを振り返って尋ねた。
――今度は俺の両目をしっかりと見つめてくる。
しかしそれは、すぐに目を逸らしてしまいたくなるほどの不安を湛えた瞳だった。
神川の気持ちがフィルターも通さずに直に伝わってくる。
このまま直視して良いものかと俺でさえ不安にさせてしまうほどの眼差しだ。
「そ、そんな心配しなくても大丈夫だって。……よし、これからは亜希だ!よろしくな、亜希!」
亜希の不安を取り払うため努めて明るく振舞うと、彼女はさっきと打って変わり、屈託のない笑顔を見せてくれた。
「えへへ、嬉しい……」
「そんなに嬉しかった?」
「もちろん!」
ニコッと並びの良い真っ白な歯を覗かせて喜ぶ亜希。
彼女の笑顔を見ていると、こっちまで自然と笑みが零れてくる。
――今までの誰よりも可愛らしい笑顔だった。
「ねえ、高月くん……聞いていい?」
「どうかした?……もしかして俺のことは何て呼べば良いかって?それは君に任せるよ」
のぞみ……だけは嫌だな。
いつかの誰かさんがそう呼んだおかげで昔散々からかわれたからな……。
「ううん、そうじゃなくて。あたしたちって一体どんな関係なのかなって」
「えっ?」
――ごく自然な流れでサラッと言われたので若干困惑した。
「どんな関係なんだろうね、あたしたちって」
「それは……」
亜希は近くにあった体重計に乗っており、その針の揺れは中々定まらない。
どんな関係かって俺に聞かれてもなぁ……。
ただの知り合い?友達同士?それとも……恋人同士?
「確かに何なんだろう。――亜希はどう思ってる?」
体重計の針が重さを示す前に、亜希はピョンとカエルよろしく台から飛び降りて俺に告げた。
「――それは高月くんに任せる」
彼女は、とても優しい微笑みで俺に判断を委ねた。
「俺達は……」
と、口は動くがこれに続く言葉などない。
俺はどう答えて良いか思いつかなかった。
思いつかなかった?いや、それは違う。俺はただ――。
自問自答でうろたえる俺を知ってか知らずか、亜希はさっさと保健室から出ようとしていた。
「亜希!ちょっと待ってくれ、どこに行くんだ?」
亜希は振り返ることなく「もう昼休み終わるから」と冷淡に言い放つ。
――時計を見ると、後二分で五限のチャイムが鳴ってしまう時間だ。
「高月くん……今日さ、一緒に帰ろ?」
「え?あ、ああいいよ。一緒に帰ろう、亜希が良いなら」
「……じゃあ待ってるね?教室でずっと」
「教室?そうだね、じゃ授業終わったら行くよ」
俺との約束を済ませると、彼女は足早に保健室から出て行った。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

ユキ・almighty
綾羽 ミカ
青春
新宿区の高校に通う益田ユキは、どこから見てもただの優等生だった。
黒髪を綺麗にまとめ、制服の襟元を正し、図書館ではいつも詩集や古典文学を読んでいる。
クラスメートからは「おしとやかで物静かな子」と評され、教師たちからも模範的な生徒として目をかけられていた。
しかし、それは彼女の一面でしかない。

おてんばプロレスの女神たち ~男子で、女子大生で、女子プロレスラーのジュリーという生き方~
ちひろ
青春
おてんば女子大学初の“男子の女子大生”ジュリー。憧れの大学生活では想定外のジレンマを抱えながらも、涼子先輩が立ち上げた女子プロレスごっこ団体・おてんばプロレスで開花し、地元のプロレスファン(特にオッさん連中!)をとりこに。青春派プロレスノベル「おてんばプロレスの女神たち」のアナザーストーリー。
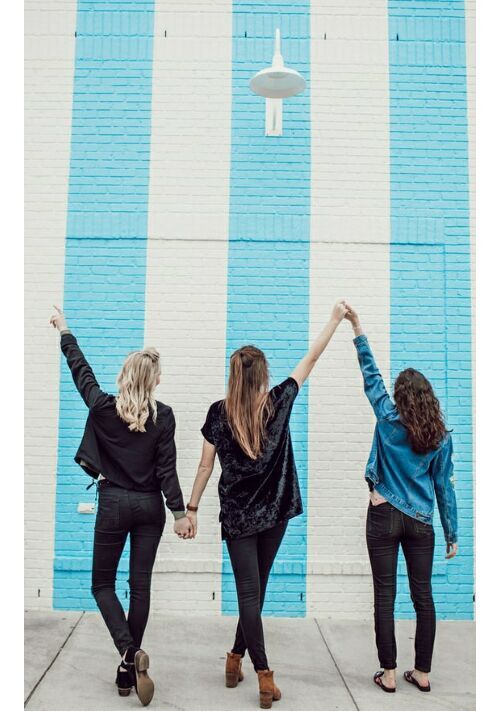
女子高生は小悪魔だ~教師のボクはこんな毎日送ってます
藤 ゆう
青春
ボクはある私立女子高の体育教師。大学をでて、初めての赴任だった。
「男子がいないからなぁ、ブリっ子もしないし、かなり地がでるぞ…おまえ食われるなよ(笑)」
先輩に聞いていたから少しは身構えていたけれど…
色んな(笑)事件がまきおこる。
どこもこんなものなのか?
新米のボクにはわからないけれど、ついにスタートした可愛い小悪魔たちとの毎日。

何故か超絶美少女に嫌われる日常
やまたけ
青春
K市内一と言われる超絶美少女の高校三年生柊美久。そして同じ高校三年生の武智悠斗は、何故か彼女に絡まれ疎まれる。何をしたのか覚えがないが、とにかく何かと文句を言われる毎日。だが、それでも彼女に歯向かえない事情があるようで……。疋田美里という、主人公がバイト先で知り合った可愛い女子高生。彼女の存在がより一層、この物語を複雑化させていくようで。
しょっぱなヒロインから嫌われるという、ちょっとひねくれた恋愛小説。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

何でも出来る親友がいつも隣にいるから俺は恋愛が出来ない
釧路太郎
青春
俺の親友の鬼仏院右近は顔も良くて身長も高く実家も金持ちでおまけに性格も良い。
それに比べて俺は身長も普通で金もあるわけではなく、性格も良いとは言えない。
勉強も運動も何でも出来る鬼仏院右近は大学生になっても今までと変わらずモテているし、高校時代に比べても言い寄ってくる女の数は増えているのだ。
その言い寄ってくる女の中に俺が小学生の時からずっと好きな桜唯菜ちゃんもいるのだけれど、俺に気を使ってなのか鬼仏院右近は桜唯菜ちゃんとだけは付き合う事が無かったのだ。
鬼仏院右近と親友と言うだけで優しくしてくれる人も多くいるのだけれど、ちょっと話すだけで俺と距離をあける人間が多いのは俺の性格が悪いからだと鬼仏院右近はハッキリというのだ。そんな事を言う鬼仏院右近も性格が悪いと思うのだけれど、こいつは俺以外には優しく親切な態度を崩さない。
そんな中でもなぜか俺と話をしてくれる女性が二人いるのだけれど、鵜崎唯は重度の拗らせ女子でさすがの俺も付き合いを考えてしまうほどなのだ。だが、そんな鵜崎唯はおそらく世界で数少ない俺に好意を向けてくれている女性なのだ。俺はその気持ちに応えるつもりはないのだけれど、鵜崎唯以上に俺の事を好きになってくれる人なんていないという事は薄々感じてはいる。
俺と話をしてくれるもう一人の女性は髑髏沼愛華という女だ。こいつはなぜか俺が近くにいれば暴言を吐いてくるような女でそこまで嫌われるような事をしてしまったのかと反省してしまう事もあったのだけれど、その理由は誰が聞いても教えてくれることが無かった。
完璧超人の親友と俺の事を好きな拗らせ女子と俺の事を憎んでいる女性が近くにいるお陰で俺は恋愛が出来ないのだ。
恋愛が出来ないのは俺の性格に問題があるのではなく、こいつらがいつも近くにいるからなのだ。そう思うしかない。
俺に原因があるなんて思ってしまうと、今までの人生をすべて否定する事になってしまいかねないのだ。
いつか俺が唯菜ちゃんと付き合えるようになることを夢見ているのだが、大学生活も残りわずかとなっているし、来年からはいよいよ就職活動も始まってしまう。俺に残された時間は本当に残りわずかしかないのだ。
この作品は「小説家になろう」「ノベルアッププラス」「カクヨム」「ノベルピア」にも投稿しています。


Toward a dream 〜とあるお嬢様の挑戦〜
green
青春
一ノ瀬財閥の令嬢、一ノ瀬綾乃は小学校一年生からサッカーを始め、プロサッカー選手になることを夢見ている。
しかし、父である浩平にその夢を反対される。
夢を諦めきれない綾乃は浩平に言う。
「その夢に挑戦するためのお時間をいただけないでしょうか?」
一人のお嬢様の挑戦が始まる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















