1 / 27
鞍馬より 1
しおりを挟む
一、
文治三年(一一八七) 霜月晦日、陸奥国上折壁村高沢付近。
深山に囲まれた晩秋の夕闇は既に深く、麓に吹き降ろす室根颪の凍てついた風には時折霙が混じり、今宵は荒天が予想された。
奥州の冬の到来は早い。特にこの冬は霜月迎えて間もない頃に初雪が磐井郷一面を白く染め、北国の人々を慌ただしく冬支度に駆り出した。
冷たい氷雨の中、凍てつく山風に震えるような鉛色の街道を、二人の旅人が馬を急がせていた。
先頭を進む一騎は三十路を過ぎて間もないと見える武家風の男。何処となく都人風の涼しい顔立ちに、常にそうしているのか眉間に深い皴を寄せ、恐ろしく峻厳な面持ちで白い息を吐きながら行く先を睨み据えている。主を乗せた栗色の若駒の長い房尾も粗飴のような霙の粒が張り付いている。
その後ろに続く見事な黒駒を駆るのは、対照的に体格の良い肥満漢。だが手綱を握る盛り上がった剛腕を見ると、男が相当の豪傑であることが知れる。蝦夷の血を強く引いているのか、眉太く大きな鼻を膨らませた顔立ちには人懐こい柔和さがあり、前を行く強面の男よりやや年長と見える。
彼らの他に街道を行く人の姿はなく、辺りを見渡しても人家の明かりも見つからない。まもなく山裾の寒々しい街道は文目も分かぬ夜の闇が訪れるであろう。
びゅう、と虎鳴笛も物凄く凍風が二人の両肩を叩いた。
「……いやはや、これはたまらぬ。こんなことなら田束山の住職の言葉に甘えて一宿世話になるのだったな」
後ろに続く大柄の男が馬上で掌に白い息を吐きながらうんざりした様子で鼻を啜った。
「仕方あるまい。志津川を発つ時には雲一つ無かったのだ。兄上の日頃の行いであろう。……しかし」
前を行く強面の男が言葉を切って笠を上げる。
目的地までは小道で六十里。思いの外道草を食ってしまった。
霙交じりの細雨は何時しか重たい水雪に変わり、空模様は荒れ行くばかり。
「間もなく高沢の村落に着く。そこで宿を問うてみよう」
俄吹雪に難儀しながらも漸く人家の明かりらしきを認めた二人はほっと白い息を吐きながら笑顔を見せた。
近づいてみると、幸いなことに荒天に随分無理をさせた馬達を休ませることが出来る厩もある。
(しかし、随分と朽ち果てているな。暫く使った形跡がないようだが)
馬を繋ぎながら首を傾げるも、二人が目指して来た明かりはすぐ傍らの母屋の方から漏れている様子。ずんずんと明かりの方へ歩み行く大柄の男に続いて強面も「御免!」と戸口に声を掛ける。
ぼぅ、と仄明るい家屋の中にきらりと青白い双眸が光った。
刺すような眼差しに、思わず二人が身構える。
顔をすっぽりと覆った真っ黒な頭巾の下の面相は窺えないが、首元から鴉色の黒髪が覗いており、襤褸じみた毛皮の外套の上からも判る華奢な身体から、恐らくまだ年若い青年と見える。囲炉裏の火の傍に座したまま片膝立ちに傍らの大振りの太刀に手を遣り、戸口に立つ二人に鋭い視線を向けていた。
「怪しい者ではない」
刀に手を遣る青年の警戒を掌で制しながら大柄の男が前に出た。
「我らは平泉の官僚の者じゃ。帰路の途中、この悪天に往生してな。不躾だが、一夜の宿を願いたいのだ」
青年が刀から手を引き、二人に向き直った。
「私もこの天気に難儀し、空き家と見えたので勝手に使わせてもらっているのです。どうぞ遠慮なさらず火の傍へ」
「忝(かたじけな)い」
思いの外幼い声音にホッと息を吐きながら、蓑の雪を払って上がり込む。
笠を脱ぎながら二人して囲炉裏の火に当たると、室根颪の寒風に凍えた身体に火の温もりが染みる。
「火とは有り難いものだなあ」
にこにこしながら手を擦り合わせる大男の様子に愛嬌を感じたか、向かい側に座る青年がフッと頬を緩める気配が聞こえる。
一方で、強面の男は青年の様子をしげしげと見やる。
改めて見ると、この青年は最初の印象よりも随分年若い様子だった。頭巾で素顔は判らぬが、その下は女人の顔だと言われても信じたかもしれない。
身に着けた毛皮の外套やその他の装束も、見るからに接ぎを当てたような風雨に揉まれた様な風体で、恐らく相当な長旅を経て此処に至ったものと思われる。
それにも関わらず、流浪の無頼者とも思われぬ印象を覚えるのは、最初にこちらに向けられた強い眼差しのせいか。
(……まさか落人の類か?)
訝る武者の視線に気づいたか、青年がちらりとこちらに目を向ける。
「ところで、お二人は先程平泉の御役人様と名乗られておりましたが」
「左様。まあ、大した位の者ではない木っ端役人じゃがの。今朝早く志津川を発ったが、御覧の通りここで足止めさ」
すっかり気を許した態で大柄の男が答える。
「それではこれから平泉に戻られるのですね?」
微かに青年が身を乗り出すのを強面の男は見逃さなかった。
「実は私も平泉へ赴く途中なのです。宜しければお二人の道中をお供させていただけないでしょうか?」
「ほう。見ると随分遠方からこの地へ辿り着いた様子。どういった用向きで遥々参られたのかな?」
大男が口を開く前に強面が問い返す。
「……古い知己の者の消息を尋ねに来たのです」
強面の詰問の調子に気付いてか、青年はそれきり顔を伏せ、口を噤んだ。
外は愈々大荒れらしく、みしみしと家鳴りの軋みから時折隙間風が吹き込み、ぶわりと囲炉裏の煙を乱す。
ジジ、と火の中の炭が小さく啼いた。
「……ところで、其許はどちらから参られたのかな? 随分と長旅をされてきたように見受けられるが」
沈黙を慮ってか、大男が気さくな笑顔を青年に向ける。
「今朝、松崎の母体田を出ました。その前は諸国各地を流々と」
「おお、では昨日我らと知らず行き逢うていたかもしれんな。我らもこの数日その辺りを巡っていたところじゃて」
「兄上」
気安い様子を窘めるように強面が再び口を出す。
「ですが、流石にここまで四里の険しい道程は堪えました。道中土地の人に尋ねると平泉まであと六十里とのこと。何分この土地は不案内故、どうかお供させていただきとう存じます」
青年の声には少し切実さが伺え、強面は少しだけ気の毒に感じ始めた。しかし、
「む、松崎から四里? はて」
大男が首を傾げる。強面も暫し考え込むが、ふと思い至って膝を打った。
「もしや、其許は西国の生まれか?」
「如何にも、私は山城の生まれですが」
そこで大男の方も合点が入ったとばかりに頷いた。
「そういえば昔吉治から西国の尺貫は三十六町の大道を使うと聞いたことがある。陸奥では六町を一里というのだよ」
青年が驚いて目を見開く。因みにこの時代の尺貫法は地域によって大きく異なるため単純に現在の距離単位に換算することは難しいが、後世では大道の一里が一般的となる。
「成程。私は思いの外目的の地に近づいていたのですね」
ホッとした、というより気抜けしたという様子で青年は微かに笑った。
「しかし遥々山城国からこんな遠方の地までのう。どうじゃ、次郎よ? これも縁ゆえ、道行は賑やかな方が良かろう。祖父上もよく言っておった、奥州を訪ねる旅人はくれぐれも手厚くもてなせとな」
気安いことのように大男が傍らに問う。
「確かに、臨終の際までしつこく宣っておられたが」
頭巾の奥で縋るような視線を向ける青年の眼差しの手前、兄にそんな水の向け方をされては吝かにもいかない。加えて、今までの遣り取りで青年の一挙手を見るうち強面の警戒も薄れて来ていた。
(それに、この青年の風体を見る限り、ここに至るまでの道中危険な場面にも少なからず逢ってきたのだろう。これまでの一人旅、見るからに頼りなき身の上では余程心細かったに違いない)
聊かの同情も感じ始めた強面は初めて青年に笑いかけた。
「まあ、京の界隈に比べればこの陸奥の国では検非違使も閑職同然じゃ。安心して付いてこられよ」
「うむ。となれば明日も早い。火の番は我らに任せて其許は先に休まれるがよいぞ」
親し気に笑う二人を前に、青年も「忝く存じます」と深く頭を下げた。
言葉に甘えて先に就寝した青年の寝息を聞きながら、二人は火を囲んでポツポツと語り合った。
「あの若者、まるで我らを警戒せなんだな。実は我らは悪い追剥かもしれぬぞ」
「兄上の木っ端役人とかいう名乗りを真に受けたのでしょう。確かに今の兄上の風体、言いえて妙ですぞ」
「戯言を」
「しかしあの様子では、余程の流浪を経て此処まで辿り着いたと見えます。嫌味のない涼しい印象ではありましたが、父上が身罷ったことはとうに坂東にも聞こえているはず。まさかとは思いますが」
「油断はせぬことだな」
そう答える大男の表情は先程の遣り取りからは思いもつかぬほど厳しいものだった。
二、
翌朝には昨夜の霙吹雪が嘘のような雲一つない晴天となり、日が昇る頃には昨夜の残雪は粗方溶けて消えてしまっていた。
三人は一夜の世話になったあばら家に、もしも後で家の住人が戻ってきた場合を考え、気持ちばかりを一包み置いて村を後にした。
「其許だけ徒をさせるのでは具合が悪い。某の馬に乗られよ」
同乗を勧められ恐縮する青年に、
「なに、この高楯黒は奥州一の駿馬。某の様な図体が一人二人増えたところでびくともせぬよ」
そう言ってヒョイと青年の手を取って馬上へ抱え上げる。
「む?」
「どうかされたか兄上?」
首を傾げる大男を強面の男が訝しそうに振り向く。
「いや、気のせいだろう」
青年を前に乗せた兄が心なしか身を引き気味に妙な表情を浮かべる。
「そういえば其許の名をまだ聞いておらなかったな」
そう問われた青年は何故か少し恥ずかし気に名乗った。
「キイチと申します」
昨夜の吹雪は三人が夜を明かした山麓よりも内陸側の方が一層激しく吹き荒れていたものと見え、一行が目的地である平泉を目指すにつれ溶け残った牡丹雪の名残が街道にちらほらと目に付くようになり、ぬかるんだ泥道に馬の脚を屡々取られることもあったせいで、漸く河崎柵までもう数刻というところまで辿り着いた頃には既に正午を回っていた。
「やれやれ、つくづく馬達には難儀を強いてしまうのう」
恰幅の良い体格の割に軽やかな身のこなしで大男が馬から降りると、同乗していた青年へ手を添えてやる。あまり馬には乗り慣れていない様子の青年は礼を言いながら下馬しようと地面に足を下ろした途端に少しよろめいた。その様子が微笑ましく強面が微笑んだ。
「ここで少し休んでいこう。北上川が見えてくれば平泉はすぐ目の前じゃ」
その言葉にほっとした様子で青年は道中乗せてくれた黒馬を労うように鬣を撫でる。
馬も嬉しそうに目を細め首を揺らした。
「ほう、高楯黒が慣れぬ人に愛嬌を見せるとは珍しいのう」
意外なものを見るように大男が呟いた。
(馬に慣れぬ者が手を出そうものなら、途端に舐めてかかるようなじゃじゃ馬なのだが)
内心で独り言ちる兄の前で、黒馬は甘えるように青年の袖を咥えてみたりする。
青年は嬉しそうに高楯黒とじゃれ合っている。
「良い馬です。都でもこれ程しっかりと筋の張った名馬はなかなか見かけませぬ」
「おお、貴公は馬がわかるか」
乾いた岩を見つけ腰を下ろして飯の包みを広げていた強面が顔を上げる。
「この奥州は名馬の産地として名が通っておる。中でも磐井郷一帯で育まれた黒馬は京でも名のある武家の間で高値が付くほどじゃ。昨今の合戦でもこの高楯黒の親兄弟筋達が名将と戦いを共にし、大いに武勲の助けとしたと聞く」
誇らしげに語る強面だが、微かに寂し気に目を落とす。
「いったいどれほどの兄弟馬達が、合戦を生き伸びて主と共に帰ってきたものか」
「何、世は既に泰平じゃ。この奥州は百歳(ももとせ)の平穏を謳歌しておる。戦など遠い彼方の話よ」
大男が腰を下ろしながら気安げに笑い、青年に乾飯を勧める。
青年も礼を言いながら飯を受け取り、その傍らに座した。
一行が長島の高台から大河の畔に街明かりを望める頃にはすっかり日も暮れ、金鶏山の彼方へ夕陽の最後の一片が沈もうとしていた。
とはいえ道中は若者との話も和やかに弾み、快い疲労感の溜息を吐きながら三人は鞍から降りてポキポキと肩を鳴らした。
「あれが北上川ですか」
ほぅ、と白い息をついて青年が指さす。
「左様。その両岸に見える灯りが平泉じゃ」
眼下に広がるその街並みに青年は目を見張った。
なんという広大な都市だろう。北上川の川上の向こうまで果てが見えぬほど宵の夜景が山々の狭間を縫って続いている。その中心市街の街明かりの賑わいは、夕餉の竈の煙の匂いがここまで漂ってきそうなほど。
当時の平泉最盛期の人口は十万とも十五万ともいわれている。同じ頃、源頼朝が武家社会の首都を築き上げつつある鎌倉に匹敵あるいはそれを凌ぐほどの都市規模であった。
決して鎌倉や京との優劣を比して俯瞰しているわけではないが、源平の合戦をはじめ、度重なる戦や混乱に翻弄され続けた京をはじめ西国の各都市と比べれば、この都は遥かに人々の活気に満ちた息遣いが聞こえるようだ。
「もうじきに日も落ちる。急ごう」
「ここまでの道中、ありがとうございました」
青年が深々と頭を下げる。
街の入口に辿り着いた時には宵の賑わいも夜の静寂に落ち着き、大路には人の姿も殆ど見えない。何処からか聞こえる夜谺のような狐の遠啼きが侘しい。
「いや、お陰で我らも楽しい道行であったぞ」
大男が親し気に破顔する。
「今宵は我らの官舎で休まれよ。知人を訪ねるのは明日になさるが良い」
昨夜に比べれば大分打ち解けた様子で強面も笑顔を見せる。
「何から何まで忝く存じます」
恐縮の態で礼を言う青年に、
「ところで」
何気なく兄が青年に問いかけた。
「其許の尋ね人というのは何という御方かな? 京に所縁のある御方なら大体は存じておるが」
「はい。その御方の名前は――」
青年が顔を上げ、グイと頭巾の口元を見せる。
怪訝な顔をする二人の前に意外なほど艶めかしい唇が覗いた。その上では、昨夜始めて対峙した時と同じ鋭い双眸が二人に向けられた。
「――源九郎義経様にございます」
「っ!?」
戦慄に近い驚愕の表情で二人が同時に身を引いた。
「……矢張り居場所をご存じなのですね?」
二人の様子に青年の視線がすぅ、と細くなる。
「鎌倉かっ!」
大男が腰の太刀に手を掛ける。それを見たキイチの太刀の鞘がちらりと揺れた。
「待て、兄上。キイチ殿が鎌倉の隠密ならこんな所で堂々と九郎殿の名を口にしたりはせぬ」
兄を制しながら兄よりも一層厳しい面持ちで強面が青年を見据える。
「その尋ね人とやらについて詳しく話を聞きたい。我らと共に来てもらうぞ」
文治三年(一一八七) 霜月晦日、陸奥国上折壁村高沢付近。
深山に囲まれた晩秋の夕闇は既に深く、麓に吹き降ろす室根颪の凍てついた風には時折霙が混じり、今宵は荒天が予想された。
奥州の冬の到来は早い。特にこの冬は霜月迎えて間もない頃に初雪が磐井郷一面を白く染め、北国の人々を慌ただしく冬支度に駆り出した。
冷たい氷雨の中、凍てつく山風に震えるような鉛色の街道を、二人の旅人が馬を急がせていた。
先頭を進む一騎は三十路を過ぎて間もないと見える武家風の男。何処となく都人風の涼しい顔立ちに、常にそうしているのか眉間に深い皴を寄せ、恐ろしく峻厳な面持ちで白い息を吐きながら行く先を睨み据えている。主を乗せた栗色の若駒の長い房尾も粗飴のような霙の粒が張り付いている。
その後ろに続く見事な黒駒を駆るのは、対照的に体格の良い肥満漢。だが手綱を握る盛り上がった剛腕を見ると、男が相当の豪傑であることが知れる。蝦夷の血を強く引いているのか、眉太く大きな鼻を膨らませた顔立ちには人懐こい柔和さがあり、前を行く強面の男よりやや年長と見える。
彼らの他に街道を行く人の姿はなく、辺りを見渡しても人家の明かりも見つからない。まもなく山裾の寒々しい街道は文目も分かぬ夜の闇が訪れるであろう。
びゅう、と虎鳴笛も物凄く凍風が二人の両肩を叩いた。
「……いやはや、これはたまらぬ。こんなことなら田束山の住職の言葉に甘えて一宿世話になるのだったな」
後ろに続く大柄の男が馬上で掌に白い息を吐きながらうんざりした様子で鼻を啜った。
「仕方あるまい。志津川を発つ時には雲一つ無かったのだ。兄上の日頃の行いであろう。……しかし」
前を行く強面の男が言葉を切って笠を上げる。
目的地までは小道で六十里。思いの外道草を食ってしまった。
霙交じりの細雨は何時しか重たい水雪に変わり、空模様は荒れ行くばかり。
「間もなく高沢の村落に着く。そこで宿を問うてみよう」
俄吹雪に難儀しながらも漸く人家の明かりらしきを認めた二人はほっと白い息を吐きながら笑顔を見せた。
近づいてみると、幸いなことに荒天に随分無理をさせた馬達を休ませることが出来る厩もある。
(しかし、随分と朽ち果てているな。暫く使った形跡がないようだが)
馬を繋ぎながら首を傾げるも、二人が目指して来た明かりはすぐ傍らの母屋の方から漏れている様子。ずんずんと明かりの方へ歩み行く大柄の男に続いて強面も「御免!」と戸口に声を掛ける。
ぼぅ、と仄明るい家屋の中にきらりと青白い双眸が光った。
刺すような眼差しに、思わず二人が身構える。
顔をすっぽりと覆った真っ黒な頭巾の下の面相は窺えないが、首元から鴉色の黒髪が覗いており、襤褸じみた毛皮の外套の上からも判る華奢な身体から、恐らくまだ年若い青年と見える。囲炉裏の火の傍に座したまま片膝立ちに傍らの大振りの太刀に手を遣り、戸口に立つ二人に鋭い視線を向けていた。
「怪しい者ではない」
刀に手を遣る青年の警戒を掌で制しながら大柄の男が前に出た。
「我らは平泉の官僚の者じゃ。帰路の途中、この悪天に往生してな。不躾だが、一夜の宿を願いたいのだ」
青年が刀から手を引き、二人に向き直った。
「私もこの天気に難儀し、空き家と見えたので勝手に使わせてもらっているのです。どうぞ遠慮なさらず火の傍へ」
「忝(かたじけな)い」
思いの外幼い声音にホッと息を吐きながら、蓑の雪を払って上がり込む。
笠を脱ぎながら二人して囲炉裏の火に当たると、室根颪の寒風に凍えた身体に火の温もりが染みる。
「火とは有り難いものだなあ」
にこにこしながら手を擦り合わせる大男の様子に愛嬌を感じたか、向かい側に座る青年がフッと頬を緩める気配が聞こえる。
一方で、強面の男は青年の様子をしげしげと見やる。
改めて見ると、この青年は最初の印象よりも随分年若い様子だった。頭巾で素顔は判らぬが、その下は女人の顔だと言われても信じたかもしれない。
身に着けた毛皮の外套やその他の装束も、見るからに接ぎを当てたような風雨に揉まれた様な風体で、恐らく相当な長旅を経て此処に至ったものと思われる。
それにも関わらず、流浪の無頼者とも思われぬ印象を覚えるのは、最初にこちらに向けられた強い眼差しのせいか。
(……まさか落人の類か?)
訝る武者の視線に気づいたか、青年がちらりとこちらに目を向ける。
「ところで、お二人は先程平泉の御役人様と名乗られておりましたが」
「左様。まあ、大した位の者ではない木っ端役人じゃがの。今朝早く志津川を発ったが、御覧の通りここで足止めさ」
すっかり気を許した態で大柄の男が答える。
「それではこれから平泉に戻られるのですね?」
微かに青年が身を乗り出すのを強面の男は見逃さなかった。
「実は私も平泉へ赴く途中なのです。宜しければお二人の道中をお供させていただけないでしょうか?」
「ほう。見ると随分遠方からこの地へ辿り着いた様子。どういった用向きで遥々参られたのかな?」
大男が口を開く前に強面が問い返す。
「……古い知己の者の消息を尋ねに来たのです」
強面の詰問の調子に気付いてか、青年はそれきり顔を伏せ、口を噤んだ。
外は愈々大荒れらしく、みしみしと家鳴りの軋みから時折隙間風が吹き込み、ぶわりと囲炉裏の煙を乱す。
ジジ、と火の中の炭が小さく啼いた。
「……ところで、其許はどちらから参られたのかな? 随分と長旅をされてきたように見受けられるが」
沈黙を慮ってか、大男が気さくな笑顔を青年に向ける。
「今朝、松崎の母体田を出ました。その前は諸国各地を流々と」
「おお、では昨日我らと知らず行き逢うていたかもしれんな。我らもこの数日その辺りを巡っていたところじゃて」
「兄上」
気安い様子を窘めるように強面が再び口を出す。
「ですが、流石にここまで四里の険しい道程は堪えました。道中土地の人に尋ねると平泉まであと六十里とのこと。何分この土地は不案内故、どうかお供させていただきとう存じます」
青年の声には少し切実さが伺え、強面は少しだけ気の毒に感じ始めた。しかし、
「む、松崎から四里? はて」
大男が首を傾げる。強面も暫し考え込むが、ふと思い至って膝を打った。
「もしや、其許は西国の生まれか?」
「如何にも、私は山城の生まれですが」
そこで大男の方も合点が入ったとばかりに頷いた。
「そういえば昔吉治から西国の尺貫は三十六町の大道を使うと聞いたことがある。陸奥では六町を一里というのだよ」
青年が驚いて目を見開く。因みにこの時代の尺貫法は地域によって大きく異なるため単純に現在の距離単位に換算することは難しいが、後世では大道の一里が一般的となる。
「成程。私は思いの外目的の地に近づいていたのですね」
ホッとした、というより気抜けしたという様子で青年は微かに笑った。
「しかし遥々山城国からこんな遠方の地までのう。どうじゃ、次郎よ? これも縁ゆえ、道行は賑やかな方が良かろう。祖父上もよく言っておった、奥州を訪ねる旅人はくれぐれも手厚くもてなせとな」
気安いことのように大男が傍らに問う。
「確かに、臨終の際までしつこく宣っておられたが」
頭巾の奥で縋るような視線を向ける青年の眼差しの手前、兄にそんな水の向け方をされては吝かにもいかない。加えて、今までの遣り取りで青年の一挙手を見るうち強面の警戒も薄れて来ていた。
(それに、この青年の風体を見る限り、ここに至るまでの道中危険な場面にも少なからず逢ってきたのだろう。これまでの一人旅、見るからに頼りなき身の上では余程心細かったに違いない)
聊かの同情も感じ始めた強面は初めて青年に笑いかけた。
「まあ、京の界隈に比べればこの陸奥の国では検非違使も閑職同然じゃ。安心して付いてこられよ」
「うむ。となれば明日も早い。火の番は我らに任せて其許は先に休まれるがよいぞ」
親し気に笑う二人を前に、青年も「忝く存じます」と深く頭を下げた。
言葉に甘えて先に就寝した青年の寝息を聞きながら、二人は火を囲んでポツポツと語り合った。
「あの若者、まるで我らを警戒せなんだな。実は我らは悪い追剥かもしれぬぞ」
「兄上の木っ端役人とかいう名乗りを真に受けたのでしょう。確かに今の兄上の風体、言いえて妙ですぞ」
「戯言を」
「しかしあの様子では、余程の流浪を経て此処まで辿り着いたと見えます。嫌味のない涼しい印象ではありましたが、父上が身罷ったことはとうに坂東にも聞こえているはず。まさかとは思いますが」
「油断はせぬことだな」
そう答える大男の表情は先程の遣り取りからは思いもつかぬほど厳しいものだった。
二、
翌朝には昨夜の霙吹雪が嘘のような雲一つない晴天となり、日が昇る頃には昨夜の残雪は粗方溶けて消えてしまっていた。
三人は一夜の世話になったあばら家に、もしも後で家の住人が戻ってきた場合を考え、気持ちばかりを一包み置いて村を後にした。
「其許だけ徒をさせるのでは具合が悪い。某の馬に乗られよ」
同乗を勧められ恐縮する青年に、
「なに、この高楯黒は奥州一の駿馬。某の様な図体が一人二人増えたところでびくともせぬよ」
そう言ってヒョイと青年の手を取って馬上へ抱え上げる。
「む?」
「どうかされたか兄上?」
首を傾げる大男を強面の男が訝しそうに振り向く。
「いや、気のせいだろう」
青年を前に乗せた兄が心なしか身を引き気味に妙な表情を浮かべる。
「そういえば其許の名をまだ聞いておらなかったな」
そう問われた青年は何故か少し恥ずかし気に名乗った。
「キイチと申します」
昨夜の吹雪は三人が夜を明かした山麓よりも内陸側の方が一層激しく吹き荒れていたものと見え、一行が目的地である平泉を目指すにつれ溶け残った牡丹雪の名残が街道にちらほらと目に付くようになり、ぬかるんだ泥道に馬の脚を屡々取られることもあったせいで、漸く河崎柵までもう数刻というところまで辿り着いた頃には既に正午を回っていた。
「やれやれ、つくづく馬達には難儀を強いてしまうのう」
恰幅の良い体格の割に軽やかな身のこなしで大男が馬から降りると、同乗していた青年へ手を添えてやる。あまり馬には乗り慣れていない様子の青年は礼を言いながら下馬しようと地面に足を下ろした途端に少しよろめいた。その様子が微笑ましく強面が微笑んだ。
「ここで少し休んでいこう。北上川が見えてくれば平泉はすぐ目の前じゃ」
その言葉にほっとした様子で青年は道中乗せてくれた黒馬を労うように鬣を撫でる。
馬も嬉しそうに目を細め首を揺らした。
「ほう、高楯黒が慣れぬ人に愛嬌を見せるとは珍しいのう」
意外なものを見るように大男が呟いた。
(馬に慣れぬ者が手を出そうものなら、途端に舐めてかかるようなじゃじゃ馬なのだが)
内心で独り言ちる兄の前で、黒馬は甘えるように青年の袖を咥えてみたりする。
青年は嬉しそうに高楯黒とじゃれ合っている。
「良い馬です。都でもこれ程しっかりと筋の張った名馬はなかなか見かけませぬ」
「おお、貴公は馬がわかるか」
乾いた岩を見つけ腰を下ろして飯の包みを広げていた強面が顔を上げる。
「この奥州は名馬の産地として名が通っておる。中でも磐井郷一帯で育まれた黒馬は京でも名のある武家の間で高値が付くほどじゃ。昨今の合戦でもこの高楯黒の親兄弟筋達が名将と戦いを共にし、大いに武勲の助けとしたと聞く」
誇らしげに語る強面だが、微かに寂し気に目を落とす。
「いったいどれほどの兄弟馬達が、合戦を生き伸びて主と共に帰ってきたものか」
「何、世は既に泰平じゃ。この奥州は百歳(ももとせ)の平穏を謳歌しておる。戦など遠い彼方の話よ」
大男が腰を下ろしながら気安げに笑い、青年に乾飯を勧める。
青年も礼を言いながら飯を受け取り、その傍らに座した。
一行が長島の高台から大河の畔に街明かりを望める頃にはすっかり日も暮れ、金鶏山の彼方へ夕陽の最後の一片が沈もうとしていた。
とはいえ道中は若者との話も和やかに弾み、快い疲労感の溜息を吐きながら三人は鞍から降りてポキポキと肩を鳴らした。
「あれが北上川ですか」
ほぅ、と白い息をついて青年が指さす。
「左様。その両岸に見える灯りが平泉じゃ」
眼下に広がるその街並みに青年は目を見張った。
なんという広大な都市だろう。北上川の川上の向こうまで果てが見えぬほど宵の夜景が山々の狭間を縫って続いている。その中心市街の街明かりの賑わいは、夕餉の竈の煙の匂いがここまで漂ってきそうなほど。
当時の平泉最盛期の人口は十万とも十五万ともいわれている。同じ頃、源頼朝が武家社会の首都を築き上げつつある鎌倉に匹敵あるいはそれを凌ぐほどの都市規模であった。
決して鎌倉や京との優劣を比して俯瞰しているわけではないが、源平の合戦をはじめ、度重なる戦や混乱に翻弄され続けた京をはじめ西国の各都市と比べれば、この都は遥かに人々の活気に満ちた息遣いが聞こえるようだ。
「もうじきに日も落ちる。急ごう」
「ここまでの道中、ありがとうございました」
青年が深々と頭を下げる。
街の入口に辿り着いた時には宵の賑わいも夜の静寂に落ち着き、大路には人の姿も殆ど見えない。何処からか聞こえる夜谺のような狐の遠啼きが侘しい。
「いや、お陰で我らも楽しい道行であったぞ」
大男が親し気に破顔する。
「今宵は我らの官舎で休まれよ。知人を訪ねるのは明日になさるが良い」
昨夜に比べれば大分打ち解けた様子で強面も笑顔を見せる。
「何から何まで忝く存じます」
恐縮の態で礼を言う青年に、
「ところで」
何気なく兄が青年に問いかけた。
「其許の尋ね人というのは何という御方かな? 京に所縁のある御方なら大体は存じておるが」
「はい。その御方の名前は――」
青年が顔を上げ、グイと頭巾の口元を見せる。
怪訝な顔をする二人の前に意外なほど艶めかしい唇が覗いた。その上では、昨夜始めて対峙した時と同じ鋭い双眸が二人に向けられた。
「――源九郎義経様にございます」
「っ!?」
戦慄に近い驚愕の表情で二人が同時に身を引いた。
「……矢張り居場所をご存じなのですね?」
二人の様子に青年の視線がすぅ、と細くなる。
「鎌倉かっ!」
大男が腰の太刀に手を掛ける。それを見たキイチの太刀の鞘がちらりと揺れた。
「待て、兄上。キイチ殿が鎌倉の隠密ならこんな所で堂々と九郎殿の名を口にしたりはせぬ」
兄を制しながら兄よりも一層厳しい面持ちで強面が青年を見据える。
「その尋ね人とやらについて詳しく話を聞きたい。我らと共に来てもらうぞ」
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

蒼旗翻天 -彼方へ 高衡後記-
香竹薬孝
歴史・時代
文治五年(一一八九)九月、源頼朝率いる鎌倉軍の侵略により、奥州藤原氏は滅亡。
その十余年後、生き残った者達は、再び新たな戦乱に身を投じようとしていた――
(※前作「彼方へ -皆鶴姫伝説異聞-」から10年後の物語を描いています)

華闘記 ー かとうき ー
早川隆
歴史・時代
小牧・長久手の戦いのさなか、最前線の犬山城で、のちの天下人羽柴秀吉は二人の織田家旧臣と再会し、昔語りを行う。秀吉も知らぬ、かつての巨大な主家のまとう綺羅びやかな光と、あまりにも深い闇。近習・馬廻・母衣衆など、旧主・織田信長の側近たちが辿った過酷な、しかし極彩色の彩りを帯びた華やかなる戦いと征旅、そして破滅の物語。
ー 織田家を語る際に必ず参照される「信長公記」の記述をふたたび見直し、織田軍事政権の真実に新たな光を当てる野心的な挑戦作です。ゴリゴリ絢爛戦国ビューティバトル、全四部構成の予定。まだ第一部が終わりかけている段階ですが、2021年は本作に全力投入します! (早川隆)

かくされた姫
葉月葵
歴史・時代
慶長二十年、大坂夏の陣により豊臣家は滅亡。秀頼と正室である千姫の間に子はなく、側室との間に成した息子は殺され娘は秀頼の正室・千姫の嘆願によって仏門に入ることを条件に助命された――それが、現代にまで伝わる通説である。
しかし。大坂夏の陣の折。大坂城から脱出した千姫は、秀頼の子を宿していた――これは、歴史上にその血筋を隠された姫君の物語である。


忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……
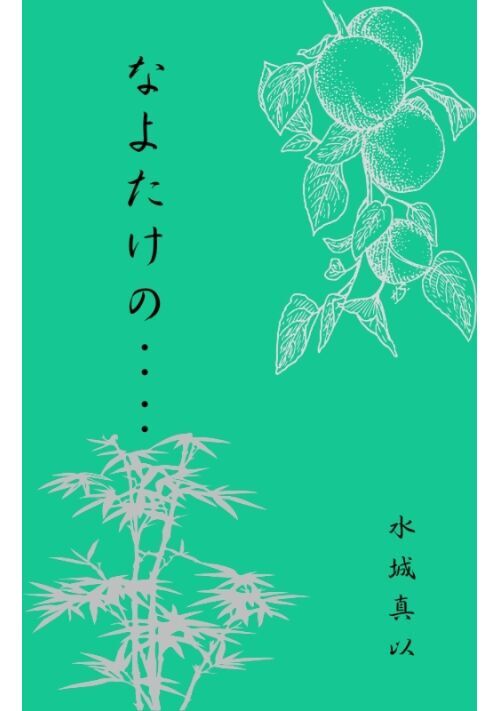


GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















