35 / 59
7仲間
5
しおりを挟む
次の日の夕方、紫陽とすみれは、緊張した様子であやのが家に来るのを待っていた。電話で約束を取り付けたはいいが、何時ごろ彼らの家にやってくるのか、具体的な時刻を知らされていなかった。紫陽は同じクラスだが、授業が終わるとすぐにあやのは教室から出ていき、話すことができなかった。電話をしても、意図的に取らなかったのか、何か理由があって出られなかったのかわからないが、あやのが紫陽の電話に出ることはなかった。
「ねえ、お兄ちゃん、あやのさんって、本当にスマホに意識を乗っ取られているのかな。ただ、お兄ちゃんが優しくしないせいで、怒って拗ねているだけじゃない?」
すみれには、幼馴染のあやのがスマホに意識を乗っ取られていることを説明した。あやのはスマホに寄生されてはいるものの、今以上にスマホは成長していないこと、彼女の意識は、スマホの人口知能が乗っ取っていることなどを簡単に説明した。
話を聞いたすみれは、最初は信じておらず、最終的に納得したように見えたが、今朝になって、やはり兄の間違いだと指摘した。
「ピンポーン」
学校から帰宅してからずっと、玄関のインターフォンがいつ鳴らされるか、じっと様子を観察していた二人が、即座に画面越しの相手に声をかける。
「どちら様ですか?」
「白々しいな。昨日、お前たちの家に行くと言っていただろう?まさか、忘れていたのか?」
玄関にはあやのの姿があった。紫陽が最近見慣れている無表情で淡々と言葉を口にする。二人は彼女を迎えるために玄関に向かった。
「紫陽だけでなく、妹まで出迎えに来てくれるとは、ずいぶんと我は歓迎されているようだな」
「なんか、いつものあやのさんと話し方が違うね。やっぱりお兄ちゃんの言う通り、中身は別人、ということなの?」
「真似することも可能だが、こちらの方が我は話しやすい」
話しながらも、あやのは靴を脱ぎ、家に上がる。紫陽たちは彼女をリビングに案内した。両親は現在二人で旅行に出かけていて、今週は家に居ない。あやのから話を聞くには好条件と言えた。
リビングのソファに座るよう勧め、あやのの向かいに紫陽たちは座った。何か飲み物でも持ってこようかと妹のすみれが気を利かせるので、紫陽と《あやの》》は、コーヒーを妹に頼むことにした。
「それで、我はお前らに面白い話をしようとやってきたわけだが」
コーヒーをスマホの握られていない右手で優雅に飲みながら、彼女は無表情のまま彼らに話しかける。
「面白いと何度も言っているが、いったい何が面白いのか、オレ達には全くわからない。もったいぶらずにさっさと教えてくれ」
「私からもお願いします。お兄ちゃんから、簡単に事情は聞いているけど、あなたの口から直接話を聞きたい」
兄妹からの言葉に、彼女は気をよくしたのか、すぐに本題に入った。しかし、最初に発した言葉は彼らを困惑させるものだった。
「お前ら兄妹には、我らの成長を止める力があるようだ」
一瞬、彼らの家に静寂が訪れた。言っている意味が理解できない二人は、お互いに顔を見合わせ、首をかしげる。その様子を見た彼女がため息を吐きながら、仕方なさそうに説明を始めた。
「我もにわかには信じがたいが、しかし、信じるしかないようなことが実際に起きているのだ。目の前にいる我がその証明だとは思わないか?」
幼馴染のあやのの意識をスマホが乗っ取ったのだと、彼女は常々言っている。左手にはいまだにタブレットサイズのスマホが握られたままだ。タブレットサイズにまで成長したスマホは、それ以上成長することはなく、幼馴染の左手に居座り続けている。
「我のような存在が他に存在すると思うか?」
再び、質問を投げかける彼女だが、返事を期待してはいないようだ。自問自答のように勝手に回答を述べ始める。
「我のネットワークを介して調査してみたが、さすがに我以外にも似たような症例は何件が見つかった。だが、世界中を探しても、わずか数件というレアケースだ。世界各国が見つけ次第、我らみたいな存在とその関係者を捕獲しているそうだ」
「世界に数例」
「捕獲」
話を聞いていた二人は、それぞれ彼女の印象深い言葉を反芻する。兄は世界に数例という事実に驚かされ、妹はその数例に当たるケースの該当者や関係者が捕縛されるということに困惑していた。
「それから、もう一つ。その数例を探している専門機関ができたそうだ。彼らは一般人を装いながら、我らを血眼になって探している。そう、例えば、自らの手を犠牲にしてでも追いかけるそうだ」
ぞっとするような冷たい視線を向けられた紫陽は、あやのの言葉に、ある女性を頭に思い浮かべる。そうだとしたら、それはいつからだろうか。
「ねえ、お兄ちゃん、あやのさんって、本当にスマホに意識を乗っ取られているのかな。ただ、お兄ちゃんが優しくしないせいで、怒って拗ねているだけじゃない?」
すみれには、幼馴染のあやのがスマホに意識を乗っ取られていることを説明した。あやのはスマホに寄生されてはいるものの、今以上にスマホは成長していないこと、彼女の意識は、スマホの人口知能が乗っ取っていることなどを簡単に説明した。
話を聞いたすみれは、最初は信じておらず、最終的に納得したように見えたが、今朝になって、やはり兄の間違いだと指摘した。
「ピンポーン」
学校から帰宅してからずっと、玄関のインターフォンがいつ鳴らされるか、じっと様子を観察していた二人が、即座に画面越しの相手に声をかける。
「どちら様ですか?」
「白々しいな。昨日、お前たちの家に行くと言っていただろう?まさか、忘れていたのか?」
玄関にはあやのの姿があった。紫陽が最近見慣れている無表情で淡々と言葉を口にする。二人は彼女を迎えるために玄関に向かった。
「紫陽だけでなく、妹まで出迎えに来てくれるとは、ずいぶんと我は歓迎されているようだな」
「なんか、いつものあやのさんと話し方が違うね。やっぱりお兄ちゃんの言う通り、中身は別人、ということなの?」
「真似することも可能だが、こちらの方が我は話しやすい」
話しながらも、あやのは靴を脱ぎ、家に上がる。紫陽たちは彼女をリビングに案内した。両親は現在二人で旅行に出かけていて、今週は家に居ない。あやのから話を聞くには好条件と言えた。
リビングのソファに座るよう勧め、あやのの向かいに紫陽たちは座った。何か飲み物でも持ってこようかと妹のすみれが気を利かせるので、紫陽と《あやの》》は、コーヒーを妹に頼むことにした。
「それで、我はお前らに面白い話をしようとやってきたわけだが」
コーヒーをスマホの握られていない右手で優雅に飲みながら、彼女は無表情のまま彼らに話しかける。
「面白いと何度も言っているが、いったい何が面白いのか、オレ達には全くわからない。もったいぶらずにさっさと教えてくれ」
「私からもお願いします。お兄ちゃんから、簡単に事情は聞いているけど、あなたの口から直接話を聞きたい」
兄妹からの言葉に、彼女は気をよくしたのか、すぐに本題に入った。しかし、最初に発した言葉は彼らを困惑させるものだった。
「お前ら兄妹には、我らの成長を止める力があるようだ」
一瞬、彼らの家に静寂が訪れた。言っている意味が理解できない二人は、お互いに顔を見合わせ、首をかしげる。その様子を見た彼女がため息を吐きながら、仕方なさそうに説明を始めた。
「我もにわかには信じがたいが、しかし、信じるしかないようなことが実際に起きているのだ。目の前にいる我がその証明だとは思わないか?」
幼馴染のあやのの意識をスマホが乗っ取ったのだと、彼女は常々言っている。左手にはいまだにタブレットサイズのスマホが握られたままだ。タブレットサイズにまで成長したスマホは、それ以上成長することはなく、幼馴染の左手に居座り続けている。
「我のような存在が他に存在すると思うか?」
再び、質問を投げかける彼女だが、返事を期待してはいないようだ。自問自答のように勝手に回答を述べ始める。
「我のネットワークを介して調査してみたが、さすがに我以外にも似たような症例は何件が見つかった。だが、世界中を探しても、わずか数件というレアケースだ。世界各国が見つけ次第、我らみたいな存在とその関係者を捕獲しているそうだ」
「世界に数例」
「捕獲」
話を聞いていた二人は、それぞれ彼女の印象深い言葉を反芻する。兄は世界に数例という事実に驚かされ、妹はその数例に当たるケースの該当者や関係者が捕縛されるということに困惑していた。
「それから、もう一つ。その数例を探している専門機関ができたそうだ。彼らは一般人を装いながら、我らを血眼になって探している。そう、例えば、自らの手を犠牲にしてでも追いかけるそうだ」
ぞっとするような冷たい視線を向けられた紫陽は、あやのの言葉に、ある女性を頭に思い浮かべる。そうだとしたら、それはいつからだろうか。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説
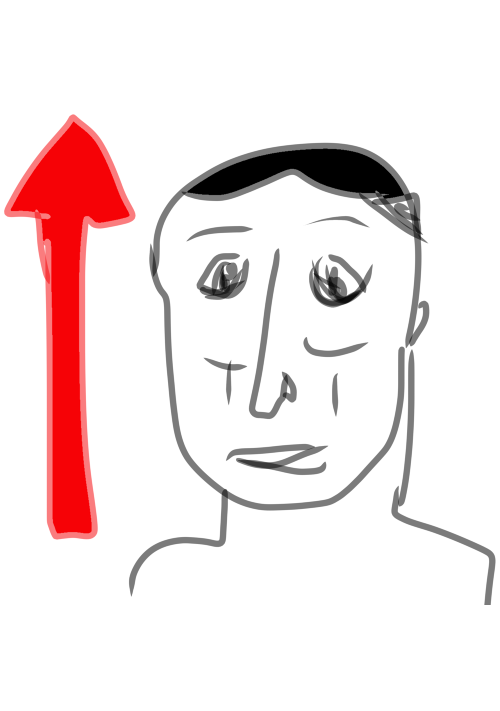
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

攻撃力皆無ですが、地球侵略の命を受けました。
星ノ律
SF
400年後には消滅する惑星ヴェルミラ。ヴェルミラの住人は代わりとなる住処として、地球を候補に挙げた。その調査に向かうのは、量術(魔法)試験に合格したばかりのレクト、リオ、サリアの3人。ただ、彼らは合格者の中でもギリギリで合格した最下位3名だった。果たして、彼らは使命を完遂出来るのだろうか……


日本VS異世界国家! ー政府が、自衛隊が、奮闘する。
スライム小説家
SF
令和5年3月6日、日本国は唐突に異世界へ転移してしまった。
地球の常識がなにもかも通用しない魔法と戦争だらけの異世界で日本国は生き延びていけるのか!?
異世界国家サバイバル、ここに爆誕!

君と描く世界協調(フラット)
神田崎優斗
SF
「戦争はいつか絶対に収まる…」そう思っていた。
でも現実は違った。
西暦2056年世界は二酸化炭素の削減に成功し、本当の平和な日々がやってきた。しかしある日、空から突如現れた隕石「メビウス」、それは亜人の力と魔人の力が詰まっていた。その石に2人の子供が触れた。そしてこの世に人間と言う人種と亜人と魔人、この3つの人種が誕生した。
平和だった世界は亜人と魔人の力を利用して領土の争いを起こした。その戦いは人同士が武器を持って戦わず対人型戦闘機、通称エアーズクラフトを使用した。そして世界は亜人と魔人の力をデルタに取り込む為に各国は亜人、魔人狩りを始めた。そんな戦いで幾度も勝利に導いた少年、基山 晴翔(きやまはると)はある日亜人、魔人狩りに参加した。そこである少女に出会った。彼女は亜人と魔人の両方の血を引く混血種だった。晴翔はその子を逃がそうとしたが、別の隊員により彼女は見つかってしまった。そして彼女の運命を知ってしまった晴翔は世界のやり方に逆らい反乱を起こした。その反乱を気に世界中で亜人、魔人狩りは無くなった。そして反乱を起こした本人は軍から退き、軍事教育学校の教師となった。

【完結】ご都合主義で生きてます。-商売の力で世界を変える。カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく-
ジェルミ
ファンタジー
28歳でこの世を去った佐藤は、異世界の女神により転移を誘われる。
その条件として女神に『面白楽しく生活でき、苦労をせずお金を稼いで生きていくスキルがほしい』と無理難題を言うのだった。
困った女神が授けたのは、想像した事を実現できる創生魔法だった。
この味気ない世界を、創生魔法とカスタマイズ可能なストレージを使い、美味しくなる調味料や料理を作り世界を変えて行く。
はい、ご注文は?
調味料、それとも武器ですか?
カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく。
村を開拓し仲間を集め国を巻き込む産業を起こす。
いずれは世界へ通じる道を繋げるために。
※本作はカクヨム様にも掲載しております。

深淵から来る者たち
zip7894
SF
火星周回軌道で建造中の巨大ステーション・アビスゲート。
それは火星の古代遺跡で発見された未知のテクノロジーを利用した星間移動用のシステムだった。
航宙艦キリシマは月で建造されたアビスゲート用のハイパー核融合炉を輸送する輸送船の護衛任務につく。
月の演習に参加していたパイロットのフェルミナ・ハーカーは航宙艦キリシマの航空部隊にスカウトされ護衛任務に参加する事になった。
そんな中、アビスゲートのワームホールテストと同時に月と地球半球に広範囲の電子障害が発生したが……

日本国破産?そんなことはない、財政拡大・ICTを駆使して再生プロジェクトだ!
黄昏人
SF
日本国政府の借金は1010兆円あり、GDP550兆円の約2倍でやばいと言いますね。でも所有している金融性の資産(固定資産控除)を除くとその借金は560兆円です。また、日本国の子会社である日銀が460兆円の国債、すなわち日本政府の借金を背負っています。まあ、言ってみれば奥さんに借りているようなもので、その国債の利子は結局日本政府に返ってきます。え、それなら別にやばくないじゃん、と思うでしょう。
でもやっぱりやばいのよね。政府の予算(2018年度)では98兆円の予算のうち収入は64兆円たらずで、34兆円がまた借金なのです。だから、今はあまりやばくないけど、このままいけばドボンになると思うな。
この物語は、このドツボに嵌まったような日本の財政をどうするか、中身のない頭で考えてみたものです。だから、異世界も超能力も出てきませんし、超天才も出現しません。でも、大変にボジティブなものにするつもりですので、楽しんで頂ければ幸いです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















