お気に入りに追加
15
あなたにおすすめの小説


火付け盗賊改め同心の娘は許婚に婚約解消され料理人を目指す。
克全
歴史・時代
「カクヨム」と「小説家になろう」にも投稿しています。
お先手組同心黒鉄家の長女・美幸は、許婚の大番組同心柴田家の真司郎から婚約解消を言われてしまった。理由を尋ねる美幸に真司郎は、札差への借財がかさみ同心株を売ることになった打ち明けてくれた。しかも長屋の大家株をもらう代わりに、金主の娘を嫁にもらわなければいけないというのだ。美幸は仕方なく真司郎を諦め自活の道を探すのだった。

白拍子、江戸の鍛冶屋と戯れる
橋本洋一
歴史・時代
「私のために――刀を打ってもらえませんか?」
時は元禄。江戸の町に突如現れた白拍子の少女、まつり。彼女は鍛冶屋の興江に刀を打ってもらおうとする。しかし興江は刀を打たない理由があった。一方、江戸の町を恐怖のどん底に陥れている人斬りがまつりと興江に関わるようになって――

高時が首
チゲン
歴史・時代
元弘三(1333)年五月、鎌倉幕府は滅亡した。そんな折り、鎌倉を目指して南下していた山伏の照隠は、首桶を抱えて鎌倉から北上してきた由茄という奇妙な娘と出会う。首桶のなかにあるのは、いったい誰の首なのか。疑問に思う照隠に対して由茄は告げる。首桶に収められているのは、鎌倉幕府の最重要人物だった北条高時の首だと。
2018年改稿。
小説投稿サイト『小説家になろう』にて同時掲載中。
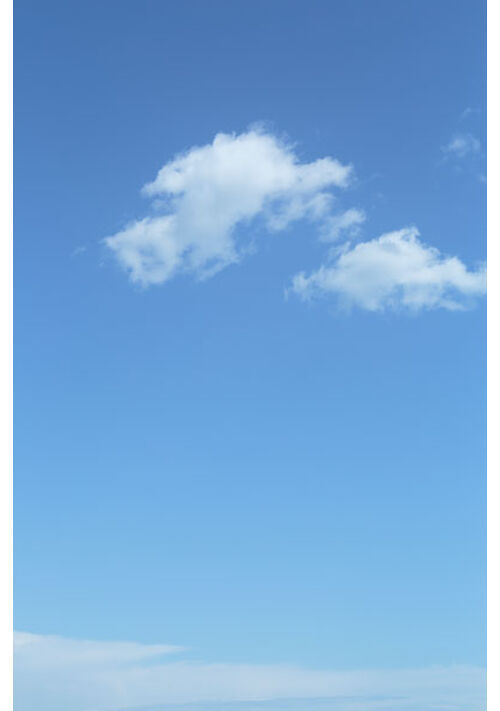

形だけの妻ですので
hana
恋愛
結婚半年で夫のワルツは堂々と不倫をした。
相手は伯爵令嬢のアリアナ。
栗色の長い髪が印象的な、しかし狡猾そうな女性だった。
形だけの妻である私は黙認を強制されるが……

KAKIDAMISHI -The Ultimate Karate Battle-
ジェド
歴史・時代
1894年、東洋の島国・琉球王国が沖縄県となった明治時代――
後の世で「空手」や「琉球古武術」と呼ばれることとなる武術は、琉球語で「ティー(手)」と呼ばれていた。
ティーの修業者たちにとって腕試しの場となるのは、自由組手形式の野試合「カキダミシ(掛け試し)」。
誇り高き武人たちは、時代に翻弄されながらも戦い続ける。
拳と思いが交錯する空手アクション歴史小説、ここに誕生!
・検索キーワード
空手道、琉球空手、沖縄空手、琉球古武道、剛柔流、上地流、小林流、少林寺流、少林流、松林流、和道流、松濤館流、糸東流、東恩流、劉衛流、極真会館、大山道場、芦原会館、正道会館、白蓮会館、国際FSA拳真館、大道塾空道

旧陸軍の天才?に転生したので大東亜戦争に勝ちます
竹本田重朗
ファンタジー
転生石原閣下による大東亜戦争必勝論
東亜連邦を志した同志達よ、ごきげんようである。どうやら、私は旧陸軍の石原莞爾に転生してしまったらしい。これは神の思し召しなのかもしれない。どうであれ、現代日本のような没落を回避するために粉骨砕身で働こうじゃないか。東亜の同志と手を取り合って真なる独立を掴み取るまで…
※超注意書き※
1.政治的な主張をする目的は一切ありません
2.そのため政治的な要素は「濁す」又は「省略」することがあります
3.あくまでもフィクションのファンタジーの非現実です
4.そこら中に無茶苦茶が含まれています
5.現実的に存在する如何なる国家や地域、団体、人物と関係ありません
6.カクヨムとマルチ投稿
以上をご理解の上でお読みください
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















