28 / 30
四章
沼の底から 3
しおりを挟む
そして、目を覚ました海斗は、再び自分があのいるだけで気分が悪くなる、そんな場所にいることに気が付いた。
ただ、見える光景そのものは、これまでと大きく違う。
以前までは、周囲を枯れ葉や枯れ枝が流れていただ、今は人の形をしたものが周囲を漂っている。
足元の、腐った泥と、そう感じていたものも同様で、骨が見えることもなく、ただどろどろと、ところどころに人の形を残した、そんなものが堆積してできていたらしい。
魂はいかに無事に送られようとも、こうして未練という重しを残した体は、沼の奥底に溜まっていくらしい。
だとすれば、周囲を流れる、まだ形の崩れていないあれらは、新しくここにやってきた、そんな者たちか、それともあえて地の底にと、体と共に沈んできた魂なのだろうか。
彼は、ぼんやりとそんなことを考えるが、目の前には探していた相手が、花家伊澄が、この前夢で見たように立っている。
だが、その表情は以前のものと違い、こちらを責める様な、そんな怒りを顔に浮かべていた。
彼からは、特に口を開くこともなく、さて、どんなことを言うのだろう、そうぼんやりと相手と目を合わせて、ただ待つ。
わざわざこんなところにまで引きずり込んだのだ、何か言いたいことの一つ二つ、いやもっとか、そういった物があるのだろうな、と。
「どうして、助けてくれなかったんですか。」
最初に彼女の口から出た言葉は、いつか聞いた言葉だった。
「無理を言うな。」
彼は癖で、ポケットを探れば、夢の中、まぁ今となってはこれが、訳の分からない所謂オカルトな状況だと、彼としてもそう認めつつはあるが、夢の中でも、煙草はいつものように持ち歩いていたらしい。
慣れに任せて、煙草を吸うための動作を行う、その途中、以前までのような重さが、この場所にないと、そんなことに今更気が付いた。
「虫の知らせ、なんてものは無かったし、そもそもなくなっていたことを知ったのだって、数日前だよ。
そんな人間が、どうして離れた場所で起きることに、どうこうできる。」
吐き出す煙に乗せて、そんな言葉を投げつける。
彼には、他に応えようもない。
知らなかった。だから何もできない。知った時には、とっくに手遅れだった。それで話は終わっているのだ。
「どうして、助けてくれたんですか。」
「まぁ、たまたま通りかかったからだな。
その日は偶然友人と駅前で遊んでいた、それでいつもと違う道で帰ることになった。
そして、現場に居合わせた。」
そういって、彼は少し考えて、言葉を付け足す。
「それだって、もう少し長く遊んだり、一人で何処かによったり。
まぁ、そういったもしがあれば、助け無かったさ。」
「ひどい人。何もそんないい方しなくてもいいじゃないですか。」
「他に、まぁ、うわべだけ取り繕った、そんな言葉が無いでもないがな。」
これでも、社会人だしな。
そう呟いて、彼は視線を外して少し考え、続く言葉を相手に伝える。
「で、それを聞いて、満足できるのか?」
彼は、そんなことをつぶやく。
「そういった、上辺だけで、そんなやり取りで終わってもいいなら、わざわざこんなところに、連れ来たりしてないだろ。」
こんなわけのわからない場所なら、煙草の煙も、その場にとどまるのかと、そう思えば、常と変わらず、広がり消えていく。
「だって、悲しいじゃないですか。
私が無事で、両親が殺されて。
もし私がその場にいれば、両親じゃなくて、私だけで済んだかもしれないのに。」
「まぁ、それももしもの話だよな。」
「それが、悪いんですか。」
「いや、いいさ。それこそ、そんな話でよければ、酒の席で何度も付き合ってるさ。」
そういって、彼は二本目の煙草に火をつける。
交わした言葉は少ないが、互いに考えて喋っているからだろうか、時間ばかりが立っている。
「それこそ、悪い方向に転ぶことだってあったしな。
被害者が3人じゃなくて、4人に、ひょっとすれば5人だったかもしれない。」
「本当にひどい人。」
「まぁ、自覚はあるよ。」
そういって彼は、ため息をつく。
こんな仕事を選ぶ、その程度にはひねくれている、その自覚は彼にもある。
「こっちに来てから。」
突然、話の内容を変えて、彼女は話し出す。
こっちに来て、というのは前職を止めて、それからという事だろう。
「その前からですね。両親が殺されて。それで会社でも騒ぎになって。
それで、周りの誰も彼もが、こそこそと、それでもこちらに聞こえるように言うんです。」
まぁ、そうだろうな、そんなことを考えて、彼はそれに頷きだけを返す。
言われた内容も、考えるまでもなく、察することができる。
彼だって、以前に散々そういう事があったのだ。
そして今回、それが無かったのは、全部忘れて、まったく関係のない場所にいたからだろう。
そもそも人と接することが、ほとんどない、そういった状態でもあったから。
そうでなければ、どうしても、周囲の雑音が苦しめただろう、彼女がそれに追い詰められたように。
「あの女、前に襲われたらしいぞ、とか。
隙があるから、誘ったから、痴情の縺れだったんじゃないかとか。
もう、本当に好きなように。」
そう語る彼女の表情には、どんな感情も浮かんでいない。
「それで、都合よく、自主退職者を求める話があったから、やめたんです。
なんだか、どうでもよくなってしまって。」
そう言うと、彼女も大きく息を吐き出す。
「こっちに戻ってきて、両親と一緒に住んでいた家で暮らし始めて。
でも、あんまり家にいると、どうしても落ち込んでしまうから、散歩に出て。」
その時に彼を見つけて、声をかけたのだと、彼女は語る。
そして、顔を合わせて、何を言うのかと思えば、彼はすっかり彼女の事を忘れていた。
「忘れられていて、悲しかった、そう思う反面、楽だな、そんなことも思ったんです。」
「まぁ、それについては、悪かった、そう思ってはいるさ。」
「いいえ、そこで両親の事を何か言われたら、今のようにはなっていなかったと思います。
だから、それでよかったんだと思います。
ええ、まぁそれから少ししてでしょうか。」
そういって、彼女は足元を見る。
そこには、やはり手があり、彼女の足をしっかりとつかんでいる。
「両親の姿を、見るようになったんです。」
彼女は、足元を見ながら、そんなことを言う。
それはつまり、依頼人と、まったく同じ状態だったと、そういう事だ。
「まぁ、死んでいる。それはわかっています。
葬式にも参加しました。両親の骨を、骨壺に入れたのも、覚えています。
お墓参りにだって行きましたし。」
それでもと、彼女は言葉を続ける。
「両親が、今も家で普通に暮らしている、そんな姿を見るんです。
それで、時折、ふとこちらを見て、言うんです。
私のせいだと。私のせいで死ぬことになったのだと。二人は私のせいで死んだのに、なんで私はまだ生きているのかと。」
それは、彼女の罪悪感、それそのものなのだろう。
かける言葉も見当たらず、ただ次の煙草を取り出して、火をつける。
そして、それから上る煙、その行く先をぼんやりと眺める。
「それじゃあと、そんなことを考えてこともあったんです。」
彼女の言葉は、徐々に疲れたものに変わってきていた。
まぁ、家にいる間、ずっとそんなものを見ながら、それも死んでいると理解していながら。
自分がおかしくなっているのだ、そんな事実を突きつけられる。そんな状態が長く続けば、ただただ疲れていくだろう。
彼にしても、ここ数日、随分と疲労を感じているのだから、彼女はその比ではないだろう。
「それで、気がついたら、こうして手が招き始めました。
両親も一緒にいるからと。ここで、みんなで、また過ごせばいいと。」
そういって振り返った彼女の後ろには、いつからそこにいたのか、足元に広がる泥をすくい、適当に人型に整えた、そういわんばかりの、あちこちが崩れ、体を作る泥が爛れたように流れ続ける、そんな不気味な人型があった。
そして、どろりと、人間であれば、口にあたる部分、そこが崩れ落ちたかと思えば、聞き覚えのある声が聞こえてくる。
どうして、助けてくれなかったのか。
どうして、娘を忘れていたのか。
どうして、あの時決着をつけてくれなかったのか。
そんな怨嗟の声と、そう呼んでいいものが、ただただ空いた穴から響いてくる。
「ね。両親もこういっているんです。
それで、私がここに来たら、喜んでくれて。
また三人で、仲良く暮らそう、そういってくれたんです。」
彼女にはその不細工な人型が、本当に両親に見えているのだろうか。
「まぁ、本当にそれでいいなら、そうすればいいんじゃないか。止めやしないさ。」
彼は次の煙草を取り出すでもなく、ただまっすぐ彼女を見ながら話す。
「流石に、人がどうしてもそうしたいと、そういうなら止められやしないさ。」
「ひどい人。じゃぁ、どうして、忘れずに、こんなところまで探しに来たんですか。」
「なんでだろうな。」
そういって、彼はどうしてこんなところまで来てしまったのか、それを考える。
仕事だから、最初はそうでも、あの依頼人に関してはそうでも、彼女については違う。
では、何故だろうか、そんなことを考えながら、思いつくことをそのままに話す。
「まぁ、忘れたくなかったからじゃないか。
もう過ぎたが、週末の約束もあったし、昔とは違って、まったく知らない相手でもない。
一緒に、まぁそういっていいものかは分からないが、まぁ、手伝ってもらって、事務所を整えてもらって。
そんなことを続けているうちに、知らない相手じゃ、なくなったからな。」
彼が、そんなことうぃえば、彼女はあきれたようにため息をつく。
「そんな理由で、こんなところまで。」
「最初に助けた時だって、そんな上等な理由はなかったさ。」
「私は、特別なんだと、そう思いましたよ。」
「勘違いまで責めないさ。まぁ、特別な思いで、いい意味でも、悪い意味でも、それには違いないだろうし。」
「本当に、ひどい人。」
そんなことを言い合って、お互いに苦笑いをする。
「そう言われてもな。他に、さっきも言ったが、上辺だけで、それでいいならそうするさ。」
「たまには、そういう言葉も期待しているんですよ。」
「それにしたって、こんなところでやるような事でもないだろう。」
「まぁ、そうですよね。」
そういって、彼女が泥の塊、それに振り向く。
流れる泥、それが勢いを増して流れ切ると、そこからは見覚えがある姿とは、少し違う、それでも年を取ったからだろう、そう分かる相手がそこにいた。
「ごめんなさい。やっぱり、私はまだここにはいたくありません。」
そういって彼女が頭を下げれば、穏やかにほほ笑む彼女の両親が、彼女の肩に手を置き、そのまま彼へと視線を向ける。
「まぁ、目に見える範囲であれば、手が届く範囲で、助けますよ。
それこそ、前と同じように。」
彼がそう言うと、一つ頷いて、二人の姿は、煙のように、薄れながら沼の上へと昇っていく。
「結局、それなんですね。」
彼のほうを振り向かず、彼女が震える声でそんなことを言う。
「それ以外に言えることもないさ。」
「少しくらい、いいじゃないですか。自分を助けてくれた相手、そんな相手から、言葉が欲しい。
それを、こんな時くらい叶えてくれたっていいじゃないですか。」
その言葉に、またポケットから煙草を取り出して、なんといったものか、そう考えながら、言葉を作る。
「そうだな。ただ、まぁ。」
彼は、何度かたばこの煙を吐き出す。
線香というには、かなり無理があるだろうが、それでも上る煙は、彼女の両親が昇って行った先へと向かい、同じように消えていく。
その様子を眺めながら、彼はようやく絞り出した言葉を彼女に伝える。
「ただ、まぁ。再開して、時間を過ごして。
そうしているうちに、一緒に食事に行こう、そう、誘いたくなるような、そういった物は生まれたさ。」
そう彼が言うと、彼女はゆっくりと頭を上げて、涙が後を作った顔のまま、彼と向かい合う。
「それは、お互いに生きていたから、そうなったわけだ。
だから、まぁ、これからもよろしくお願いします。今はそれくらい、だな。」
そう告げる彼の言葉に、彼女は涙を流しながら、ここ数日よく聞いた言葉を繰り返す。
「本当に、ひどい人。」
それでも、これまでとは違い、笑いながら、そんなことを言ってくる。
「まぁ、こっちも色々あってな。
そういった真っ当な事から、随分縁が遠かったんだよ。あの事件の後にな。」
「今度、聞かせてくださいね。」
「まぁ、そうだな。今度、またどこかで食事でもしながら、酒でも飲みながら、だな。」
「私、お酒苦手なんですよね。」
「ああ、それは知らなかった。なら、まぁ何か考えればいいさ。」
そうして、初めてこんなことを、軽い調子で話すなと、彼が考えていると、彼女は、彼から目をそらして、ある方向を見る。
そこには、依頼人と、泥の塊がいる。
依頼人は俯き既に体の半分ほどは、沼に沈んでいる。
あちらは、どうするんですか。
そう彼女は彼に尋ねた。
ただ、見える光景そのものは、これまでと大きく違う。
以前までは、周囲を枯れ葉や枯れ枝が流れていただ、今は人の形をしたものが周囲を漂っている。
足元の、腐った泥と、そう感じていたものも同様で、骨が見えることもなく、ただどろどろと、ところどころに人の形を残した、そんなものが堆積してできていたらしい。
魂はいかに無事に送られようとも、こうして未練という重しを残した体は、沼の奥底に溜まっていくらしい。
だとすれば、周囲を流れる、まだ形の崩れていないあれらは、新しくここにやってきた、そんな者たちか、それともあえて地の底にと、体と共に沈んできた魂なのだろうか。
彼は、ぼんやりとそんなことを考えるが、目の前には探していた相手が、花家伊澄が、この前夢で見たように立っている。
だが、その表情は以前のものと違い、こちらを責める様な、そんな怒りを顔に浮かべていた。
彼からは、特に口を開くこともなく、さて、どんなことを言うのだろう、そうぼんやりと相手と目を合わせて、ただ待つ。
わざわざこんなところにまで引きずり込んだのだ、何か言いたいことの一つ二つ、いやもっとか、そういった物があるのだろうな、と。
「どうして、助けてくれなかったんですか。」
最初に彼女の口から出た言葉は、いつか聞いた言葉だった。
「無理を言うな。」
彼は癖で、ポケットを探れば、夢の中、まぁ今となってはこれが、訳の分からない所謂オカルトな状況だと、彼としてもそう認めつつはあるが、夢の中でも、煙草はいつものように持ち歩いていたらしい。
慣れに任せて、煙草を吸うための動作を行う、その途中、以前までのような重さが、この場所にないと、そんなことに今更気が付いた。
「虫の知らせ、なんてものは無かったし、そもそもなくなっていたことを知ったのだって、数日前だよ。
そんな人間が、どうして離れた場所で起きることに、どうこうできる。」
吐き出す煙に乗せて、そんな言葉を投げつける。
彼には、他に応えようもない。
知らなかった。だから何もできない。知った時には、とっくに手遅れだった。それで話は終わっているのだ。
「どうして、助けてくれたんですか。」
「まぁ、たまたま通りかかったからだな。
その日は偶然友人と駅前で遊んでいた、それでいつもと違う道で帰ることになった。
そして、現場に居合わせた。」
そういって、彼は少し考えて、言葉を付け足す。
「それだって、もう少し長く遊んだり、一人で何処かによったり。
まぁ、そういったもしがあれば、助け無かったさ。」
「ひどい人。何もそんないい方しなくてもいいじゃないですか。」
「他に、まぁ、うわべだけ取り繕った、そんな言葉が無いでもないがな。」
これでも、社会人だしな。
そう呟いて、彼は視線を外して少し考え、続く言葉を相手に伝える。
「で、それを聞いて、満足できるのか?」
彼は、そんなことをつぶやく。
「そういった、上辺だけで、そんなやり取りで終わってもいいなら、わざわざこんなところに、連れ来たりしてないだろ。」
こんなわけのわからない場所なら、煙草の煙も、その場にとどまるのかと、そう思えば、常と変わらず、広がり消えていく。
「だって、悲しいじゃないですか。
私が無事で、両親が殺されて。
もし私がその場にいれば、両親じゃなくて、私だけで済んだかもしれないのに。」
「まぁ、それももしもの話だよな。」
「それが、悪いんですか。」
「いや、いいさ。それこそ、そんな話でよければ、酒の席で何度も付き合ってるさ。」
そういって、彼は二本目の煙草に火をつける。
交わした言葉は少ないが、互いに考えて喋っているからだろうか、時間ばかりが立っている。
「それこそ、悪い方向に転ぶことだってあったしな。
被害者が3人じゃなくて、4人に、ひょっとすれば5人だったかもしれない。」
「本当にひどい人。」
「まぁ、自覚はあるよ。」
そういって彼は、ため息をつく。
こんな仕事を選ぶ、その程度にはひねくれている、その自覚は彼にもある。
「こっちに来てから。」
突然、話の内容を変えて、彼女は話し出す。
こっちに来て、というのは前職を止めて、それからという事だろう。
「その前からですね。両親が殺されて。それで会社でも騒ぎになって。
それで、周りの誰も彼もが、こそこそと、それでもこちらに聞こえるように言うんです。」
まぁ、そうだろうな、そんなことを考えて、彼はそれに頷きだけを返す。
言われた内容も、考えるまでもなく、察することができる。
彼だって、以前に散々そういう事があったのだ。
そして今回、それが無かったのは、全部忘れて、まったく関係のない場所にいたからだろう。
そもそも人と接することが、ほとんどない、そういった状態でもあったから。
そうでなければ、どうしても、周囲の雑音が苦しめただろう、彼女がそれに追い詰められたように。
「あの女、前に襲われたらしいぞ、とか。
隙があるから、誘ったから、痴情の縺れだったんじゃないかとか。
もう、本当に好きなように。」
そう語る彼女の表情には、どんな感情も浮かんでいない。
「それで、都合よく、自主退職者を求める話があったから、やめたんです。
なんだか、どうでもよくなってしまって。」
そう言うと、彼女も大きく息を吐き出す。
「こっちに戻ってきて、両親と一緒に住んでいた家で暮らし始めて。
でも、あんまり家にいると、どうしても落ち込んでしまうから、散歩に出て。」
その時に彼を見つけて、声をかけたのだと、彼女は語る。
そして、顔を合わせて、何を言うのかと思えば、彼はすっかり彼女の事を忘れていた。
「忘れられていて、悲しかった、そう思う反面、楽だな、そんなことも思ったんです。」
「まぁ、それについては、悪かった、そう思ってはいるさ。」
「いいえ、そこで両親の事を何か言われたら、今のようにはなっていなかったと思います。
だから、それでよかったんだと思います。
ええ、まぁそれから少ししてでしょうか。」
そういって、彼女は足元を見る。
そこには、やはり手があり、彼女の足をしっかりとつかんでいる。
「両親の姿を、見るようになったんです。」
彼女は、足元を見ながら、そんなことを言う。
それはつまり、依頼人と、まったく同じ状態だったと、そういう事だ。
「まぁ、死んでいる。それはわかっています。
葬式にも参加しました。両親の骨を、骨壺に入れたのも、覚えています。
お墓参りにだって行きましたし。」
それでもと、彼女は言葉を続ける。
「両親が、今も家で普通に暮らしている、そんな姿を見るんです。
それで、時折、ふとこちらを見て、言うんです。
私のせいだと。私のせいで死ぬことになったのだと。二人は私のせいで死んだのに、なんで私はまだ生きているのかと。」
それは、彼女の罪悪感、それそのものなのだろう。
かける言葉も見当たらず、ただ次の煙草を取り出して、火をつける。
そして、それから上る煙、その行く先をぼんやりと眺める。
「それじゃあと、そんなことを考えてこともあったんです。」
彼女の言葉は、徐々に疲れたものに変わってきていた。
まぁ、家にいる間、ずっとそんなものを見ながら、それも死んでいると理解していながら。
自分がおかしくなっているのだ、そんな事実を突きつけられる。そんな状態が長く続けば、ただただ疲れていくだろう。
彼にしても、ここ数日、随分と疲労を感じているのだから、彼女はその比ではないだろう。
「それで、気がついたら、こうして手が招き始めました。
両親も一緒にいるからと。ここで、みんなで、また過ごせばいいと。」
そういって振り返った彼女の後ろには、いつからそこにいたのか、足元に広がる泥をすくい、適当に人型に整えた、そういわんばかりの、あちこちが崩れ、体を作る泥が爛れたように流れ続ける、そんな不気味な人型があった。
そして、どろりと、人間であれば、口にあたる部分、そこが崩れ落ちたかと思えば、聞き覚えのある声が聞こえてくる。
どうして、助けてくれなかったのか。
どうして、娘を忘れていたのか。
どうして、あの時決着をつけてくれなかったのか。
そんな怨嗟の声と、そう呼んでいいものが、ただただ空いた穴から響いてくる。
「ね。両親もこういっているんです。
それで、私がここに来たら、喜んでくれて。
また三人で、仲良く暮らそう、そういってくれたんです。」
彼女にはその不細工な人型が、本当に両親に見えているのだろうか。
「まぁ、本当にそれでいいなら、そうすればいいんじゃないか。止めやしないさ。」
彼は次の煙草を取り出すでもなく、ただまっすぐ彼女を見ながら話す。
「流石に、人がどうしてもそうしたいと、そういうなら止められやしないさ。」
「ひどい人。じゃぁ、どうして、忘れずに、こんなところまで探しに来たんですか。」
「なんでだろうな。」
そういって、彼はどうしてこんなところまで来てしまったのか、それを考える。
仕事だから、最初はそうでも、あの依頼人に関してはそうでも、彼女については違う。
では、何故だろうか、そんなことを考えながら、思いつくことをそのままに話す。
「まぁ、忘れたくなかったからじゃないか。
もう過ぎたが、週末の約束もあったし、昔とは違って、まったく知らない相手でもない。
一緒に、まぁそういっていいものかは分からないが、まぁ、手伝ってもらって、事務所を整えてもらって。
そんなことを続けているうちに、知らない相手じゃ、なくなったからな。」
彼が、そんなことうぃえば、彼女はあきれたようにため息をつく。
「そんな理由で、こんなところまで。」
「最初に助けた時だって、そんな上等な理由はなかったさ。」
「私は、特別なんだと、そう思いましたよ。」
「勘違いまで責めないさ。まぁ、特別な思いで、いい意味でも、悪い意味でも、それには違いないだろうし。」
「本当に、ひどい人。」
そんなことを言い合って、お互いに苦笑いをする。
「そう言われてもな。他に、さっきも言ったが、上辺だけで、それでいいならそうするさ。」
「たまには、そういう言葉も期待しているんですよ。」
「それにしたって、こんなところでやるような事でもないだろう。」
「まぁ、そうですよね。」
そういって、彼女が泥の塊、それに振り向く。
流れる泥、それが勢いを増して流れ切ると、そこからは見覚えがある姿とは、少し違う、それでも年を取ったからだろう、そう分かる相手がそこにいた。
「ごめんなさい。やっぱり、私はまだここにはいたくありません。」
そういって彼女が頭を下げれば、穏やかにほほ笑む彼女の両親が、彼女の肩に手を置き、そのまま彼へと視線を向ける。
「まぁ、目に見える範囲であれば、手が届く範囲で、助けますよ。
それこそ、前と同じように。」
彼がそう言うと、一つ頷いて、二人の姿は、煙のように、薄れながら沼の上へと昇っていく。
「結局、それなんですね。」
彼のほうを振り向かず、彼女が震える声でそんなことを言う。
「それ以外に言えることもないさ。」
「少しくらい、いいじゃないですか。自分を助けてくれた相手、そんな相手から、言葉が欲しい。
それを、こんな時くらい叶えてくれたっていいじゃないですか。」
その言葉に、またポケットから煙草を取り出して、なんといったものか、そう考えながら、言葉を作る。
「そうだな。ただ、まぁ。」
彼は、何度かたばこの煙を吐き出す。
線香というには、かなり無理があるだろうが、それでも上る煙は、彼女の両親が昇って行った先へと向かい、同じように消えていく。
その様子を眺めながら、彼はようやく絞り出した言葉を彼女に伝える。
「ただ、まぁ。再開して、時間を過ごして。
そうしているうちに、一緒に食事に行こう、そう、誘いたくなるような、そういった物は生まれたさ。」
そう彼が言うと、彼女はゆっくりと頭を上げて、涙が後を作った顔のまま、彼と向かい合う。
「それは、お互いに生きていたから、そうなったわけだ。
だから、まぁ、これからもよろしくお願いします。今はそれくらい、だな。」
そう告げる彼の言葉に、彼女は涙を流しながら、ここ数日よく聞いた言葉を繰り返す。
「本当に、ひどい人。」
それでも、これまでとは違い、笑いながら、そんなことを言ってくる。
「まぁ、こっちも色々あってな。
そういった真っ当な事から、随分縁が遠かったんだよ。あの事件の後にな。」
「今度、聞かせてくださいね。」
「まぁ、そうだな。今度、またどこかで食事でもしながら、酒でも飲みながら、だな。」
「私、お酒苦手なんですよね。」
「ああ、それは知らなかった。なら、まぁ何か考えればいいさ。」
そうして、初めてこんなことを、軽い調子で話すなと、彼が考えていると、彼女は、彼から目をそらして、ある方向を見る。
そこには、依頼人と、泥の塊がいる。
依頼人は俯き既に体の半分ほどは、沼に沈んでいる。
あちらは、どうするんですか。
そう彼女は彼に尋ねた。
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

心霊捜査官の事件簿 依頼者と怪異たちの狂騒曲
幽刻ネオン
ホラー
心理心霊課、通称【サイキック・ファンタズマ】。
様々な心霊絡みの事件や出来事を解決してくれる特殊公務員。
主人公、黄昏リリカは、今日も依頼者の【怪談・怪異譚】を代償に捜査に明け暮れていた。
サポートしてくれる、ヴァンパイアロードの男、リベリオン・ファントム。
彼女のライバルでビジネス仲間である【影の心霊捜査官】と呼ばれる青年、白夜亨(ビャクヤ・リョウ)。
現在は、三人で仕事を引き受けている。
果たして依頼者たちの問題を無事に解決することができるのか?
「聞かせてほしいの、あなたの【怪談】を」

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!


月影の約束
藤原遊
ホラー
――出会ったのは、呪いに囚われた美しい青年。救いたいと願った先に待つのは、愛か、別離か――
呪われた廃屋。そこは20年前、不気味な儀式が行われた末に、人々が姿を消したという場所。大学生の澪は、廃屋に隠された真実を探るため足を踏み入れる。そこで彼女が出会ったのは、儚げな美貌を持つ青年・陸。彼は、「ここから出て行け」と警告するが、澪はその悲しげな瞳に心を動かされる。
鏡の中に広がる異世界、繰り返される呪い、陸が抱える過去の傷……。澪は陸を救うため、呪いの核に立ち向かうことを決意する。しかし、呪いを解くためには大きな「代償」が必要だった。それは、澪自身の大切な記憶。
愛する人を救うために、自分との思い出を捨てる覚悟ができますか?

きらさぎ町
KZ
ホラー
ふと気がつくと知らないところにいて、近くにあった駅の名前は「きさらぎ駅」。
この駅のある「きさらぎ町」という不思議な場所では、繰り返すたびに何か大事なものが失くなっていく。自分が自分であるために必要なものが失われていく。
これは、そんな場所に迷い込んだ彼の物語だ……。

トゴウ様
真霜ナオ
ホラー
MyTube(マイチューブ)配信者として伸び悩んでいたユージは、配信仲間と共に都市伝説を試すこととなる。
「トゴウ様」と呼ばれるそれは、とある条件をクリアすれば、どんな願いも叶えてくれるというのだ。
「動画をバズらせたい」という願いを叶えるため、配信仲間と共に廃校を訪れた。
霊的なものは信じないユージだが、そこで仲間の一人が不審死を遂げてしまう。
トゴウ様の呪いを恐れて儀式を中断しようとするも、ルールを破れば全員が呪い殺されてしまうと知る。
誰も予想していなかった、逃れられない恐怖の始まりだった。
「第5回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!
他サイト様にも投稿しています。
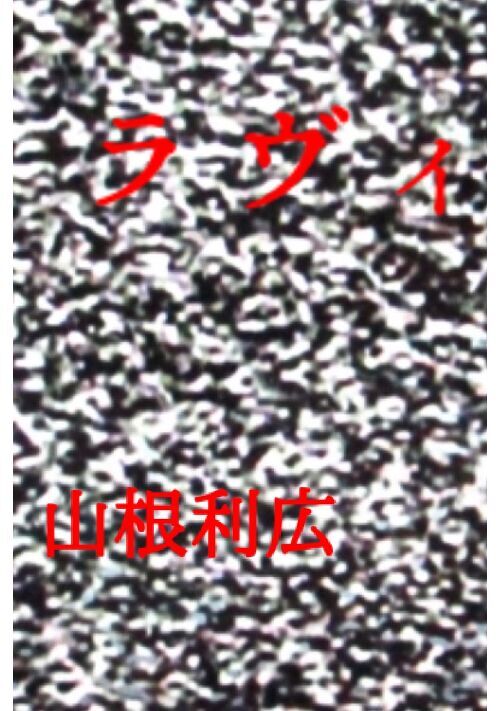
ラヴィ
山根利広
ホラー
男子高校生が不審死を遂げた。
現場から同じクラスの女子生徒のものと思しきペンが見つかる。
そして、解剖中の男子の遺体が突如消失してしまう。
捜査官の遠井マリナは、この事件の現場検証を行う中、奇妙な点に気づく。
「七年前にわたしが体験した出来事と酷似している——」
マリナは、まるで過去をなぞらえたような一連の展開に違和感を覚える。
そして、七年前同じように死んだクラスメイトの存在を思い出す。
だがそれは、連環する狂気の一端にすぎなかった……。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















