55 / 66
6-8
しおりを挟む
そうしていつものように夕方ごろまであちこちをふらふらと。良さげな物が目の端に止まればその場にしゃがみこんで。そうして拾い上げた石を手の中で転がしてみたり、日に掲げてみたり。
後は適当な草やそこらに落ちている枝で、良さげなものが有ればそれにも手を伸ばして。
いつものようにそんなことをしていれば、早いもので直ぐに日が傾き始める。
それこそ冬場に比べればかなりゆっくりとしたものなのだろうけれど、それでもいつもこうして気が付いた時にはいい時間になっている。
冬場、両親がついて来ている時は、たまに両親もこうしてうろつく僕について来たりもするけれど、二人は大体あの家に、僕も好きな縁側でのんびりとしている。
最初の頃は、面白い趣味だななんて言っていた父も、気が付けば祖父の隣で並んで鉢植えをつついていることも有るし、家には僕の物では無い鉢植えだってある。
手に持てるだけ、そんなに多くはないし、5つ程の石と、2本の枝、そんな物を拾って戻ってみれば、彼女は既に起き上がっていたようだ。
僕も良く座ってのんびりしている縁側で、お茶を飲みながら庭先をぼんやり見ていたようだ。
「おはよ。」
「えっと、こんばんは。外、行ってたんだ。」
「うん。石拾ってた。」
「えっと、そうなんだ。聞いてはいたけど。」
「僕、これ置いてくるから。」
もう少し話していてもいいかなとは思うけど、流石に地面に落ちているものをあれこれと触るから手は汚れているし、何か手に持ったままというのもあれだし。
「あ、うん。ごめんね呼び止めて。」
「いいよ。」
そういっていつものように鉢植えに直ぐには置かずに、石を集めている場所に置いておく。
並べて確かめるのは、明日の朝で良いのだから。
そして手を洗ったら玄関に回って、改めて家に入って、縁側でなんとなく彼女と並んで座る。
「あれが、君の言ってた鉢植え。」
「うん。」
夕日が少し不思議な彩を鉢に植えられた木々に加えている。
毎度悩んでしまうのだけど、どの時間に一番よく見えるようにするのが良いのだろうか。
何となく祖父はそれぞれ分けているようで、夕日、西から指す茜色、それが当たる場所にはそれが様になるような、朝日に映えるものはそちらの方にと、そう並べている気がする。
「僕も、並べ替えようかな。」
「え、何の話。」
「あ、ごめんちょっと考えてた。」
「あ、私の話、聞いてなかったんだ。」
どうやら僕が鉢植えに夢中になっている間に、彼女は何かを言っていたらしい。
「ごめん。全く。」
「もう。勉強、見てほしいって言ってたでしょ。」
「ああ、そういえば。でも、もう晩御飯になるよ。」
「え、早いんだね。」
確かに、時間はそろそろ6時になろうかというころだけど、いつもならその時間にはご飯に呼ばれるのだ。
僕も家ではだいたいその時間に食べてしまうし。
「えっと、普段もこれくらいに起きるの。」
「今日はちょっと寝過ごしちゃったけど、普段はもう少し早いよ。」
「じゃ、明日でいいや。一応課題も終わってるし。」
「なんだか間違えたままになってそうで、気になるけど。」
まぁ、そうだろう。僕は勉強はそこまで得意ではないし、好きでもない。
明日一日、それが最終日。明後日は、僕は昼前にはここを出るから、機会はそこだけとなってしまったけど。
彼女と会って、さて、何日たっただろうか。
こうしてここに来て、自分以外の、家族以外の誰かとこうして並んで縁側を眺めるなんて、想像もしたことが無かった。
「今夜も、山上るの。」
「うん。」
「へー。」
「キミも、来るんだよね。」
「うん。練習しに。でも、どうだろう。僕はゆっくり出るけど。」
「私も一緒でいいよ。これまでだったら、もう今頃山道を歩いてたけど、此処からなら近いから。」
祖父が荷物を取りに行くのに車で。勿論、僕らが歩くような山道を車で進んだ訳ではないだろうが、そうしなければならないほどに遠いのだろう。
何度聞いても、よくもまぁ、そんな事を思ってしまう。
「そっか。じゃ、少しくらいは荷物持つよ。」
「うん、ありがとう。それにしても、此処いいところだね。」
「うん。好きなんだ。」
「こうして家の中からもう星が見えるし。」
「綺麗だよ。冬とか。家の中からのんびり見ると。」
「ちょっとうらやましいかも。」
「また来ればいいんじゃない。」
僕は気軽にそんなことを口にする。
「いいのかな。」
「祖父母がいいって言うなら、良いんじゃないかな。」
「君は良いんだ。」
「良いから、そう言ってるからね。」
そう告げて彼女を改めて見る。
どうにも基本的に夜、月の下ばかりで見ていたけど、こうして改めて見るとなんというか大人っぽく見える。
短く切りそろえてる髪にしても、制服をきっちりと着込んでいる姿にしても。
「髪、短いのが似合うのは羨ましいかな。」
「なにそれ。」
「前、切った時に変だったから。もっと短くすれば似合いそうだったけど。」
「今の長いのも似合ってるよ。」
「邪魔なんだよね。」
「分かるかも。私もなんだかんだで山歩きに邪魔だから切っちゃってるし。」
「僕もそうしたいんだよね。」
そうして何でもないことを彼女と話す。
正直、人を羨ましい、そんな事を口にしたのは初めてかもしれない。
「えっと、括ったりしないの。」
「跡が付くから。それで変な癖がついても嫌だし。」
そうしてのんびりと、年頃らしい会話をしていればすぐに祖母に呼ばれる。
後は適当な草やそこらに落ちている枝で、良さげなものが有ればそれにも手を伸ばして。
いつものようにそんなことをしていれば、早いもので直ぐに日が傾き始める。
それこそ冬場に比べればかなりゆっくりとしたものなのだろうけれど、それでもいつもこうして気が付いた時にはいい時間になっている。
冬場、両親がついて来ている時は、たまに両親もこうしてうろつく僕について来たりもするけれど、二人は大体あの家に、僕も好きな縁側でのんびりとしている。
最初の頃は、面白い趣味だななんて言っていた父も、気が付けば祖父の隣で並んで鉢植えをつついていることも有るし、家には僕の物では無い鉢植えだってある。
手に持てるだけ、そんなに多くはないし、5つ程の石と、2本の枝、そんな物を拾って戻ってみれば、彼女は既に起き上がっていたようだ。
僕も良く座ってのんびりしている縁側で、お茶を飲みながら庭先をぼんやり見ていたようだ。
「おはよ。」
「えっと、こんばんは。外、行ってたんだ。」
「うん。石拾ってた。」
「えっと、そうなんだ。聞いてはいたけど。」
「僕、これ置いてくるから。」
もう少し話していてもいいかなとは思うけど、流石に地面に落ちているものをあれこれと触るから手は汚れているし、何か手に持ったままというのもあれだし。
「あ、うん。ごめんね呼び止めて。」
「いいよ。」
そういっていつものように鉢植えに直ぐには置かずに、石を集めている場所に置いておく。
並べて確かめるのは、明日の朝で良いのだから。
そして手を洗ったら玄関に回って、改めて家に入って、縁側でなんとなく彼女と並んで座る。
「あれが、君の言ってた鉢植え。」
「うん。」
夕日が少し不思議な彩を鉢に植えられた木々に加えている。
毎度悩んでしまうのだけど、どの時間に一番よく見えるようにするのが良いのだろうか。
何となく祖父はそれぞれ分けているようで、夕日、西から指す茜色、それが当たる場所にはそれが様になるような、朝日に映えるものはそちらの方にと、そう並べている気がする。
「僕も、並べ替えようかな。」
「え、何の話。」
「あ、ごめんちょっと考えてた。」
「あ、私の話、聞いてなかったんだ。」
どうやら僕が鉢植えに夢中になっている間に、彼女は何かを言っていたらしい。
「ごめん。全く。」
「もう。勉強、見てほしいって言ってたでしょ。」
「ああ、そういえば。でも、もう晩御飯になるよ。」
「え、早いんだね。」
確かに、時間はそろそろ6時になろうかというころだけど、いつもならその時間にはご飯に呼ばれるのだ。
僕も家ではだいたいその時間に食べてしまうし。
「えっと、普段もこれくらいに起きるの。」
「今日はちょっと寝過ごしちゃったけど、普段はもう少し早いよ。」
「じゃ、明日でいいや。一応課題も終わってるし。」
「なんだか間違えたままになってそうで、気になるけど。」
まぁ、そうだろう。僕は勉強はそこまで得意ではないし、好きでもない。
明日一日、それが最終日。明後日は、僕は昼前にはここを出るから、機会はそこだけとなってしまったけど。
彼女と会って、さて、何日たっただろうか。
こうしてここに来て、自分以外の、家族以外の誰かとこうして並んで縁側を眺めるなんて、想像もしたことが無かった。
「今夜も、山上るの。」
「うん。」
「へー。」
「キミも、来るんだよね。」
「うん。練習しに。でも、どうだろう。僕はゆっくり出るけど。」
「私も一緒でいいよ。これまでだったら、もう今頃山道を歩いてたけど、此処からなら近いから。」
祖父が荷物を取りに行くのに車で。勿論、僕らが歩くような山道を車で進んだ訳ではないだろうが、そうしなければならないほどに遠いのだろう。
何度聞いても、よくもまぁ、そんな事を思ってしまう。
「そっか。じゃ、少しくらいは荷物持つよ。」
「うん、ありがとう。それにしても、此処いいところだね。」
「うん。好きなんだ。」
「こうして家の中からもう星が見えるし。」
「綺麗だよ。冬とか。家の中からのんびり見ると。」
「ちょっとうらやましいかも。」
「また来ればいいんじゃない。」
僕は気軽にそんなことを口にする。
「いいのかな。」
「祖父母がいいって言うなら、良いんじゃないかな。」
「君は良いんだ。」
「良いから、そう言ってるからね。」
そう告げて彼女を改めて見る。
どうにも基本的に夜、月の下ばかりで見ていたけど、こうして改めて見るとなんというか大人っぽく見える。
短く切りそろえてる髪にしても、制服をきっちりと着込んでいる姿にしても。
「髪、短いのが似合うのは羨ましいかな。」
「なにそれ。」
「前、切った時に変だったから。もっと短くすれば似合いそうだったけど。」
「今の長いのも似合ってるよ。」
「邪魔なんだよね。」
「分かるかも。私もなんだかんだで山歩きに邪魔だから切っちゃってるし。」
「僕もそうしたいんだよね。」
そうして何でもないことを彼女と話す。
正直、人を羨ましい、そんな事を口にしたのは初めてかもしれない。
「えっと、括ったりしないの。」
「跡が付くから。それで変な癖がついても嫌だし。」
そうしてのんびりと、年頃らしい会話をしていればすぐに祖母に呼ばれる。
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

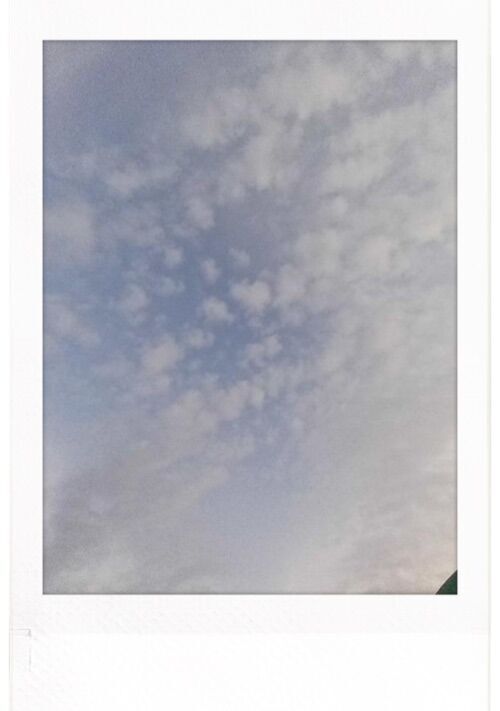
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。

Hand in Hand - 二人で進むフィギュアスケート青春小説
宮 都
青春
幼なじみへの気持ちの変化を自覚できずにいた中2の夏。ライバルとの出会いが、少年を未知のスポーツへと向わせた。
美少女と手に手をとって進むその競技の名は、アイスダンス!!
【2022/6/11完結】
その日僕たちの教室は、朝から転校生が来るという噂に落ち着きをなくしていた。帰国子女らしいという情報も入り、誰もがますます転校生への期待を募らせていた。
そんな中でただ一人、果歩(かほ)だけは違っていた。
「制覇、今日は五時からだから。来てね」
隣の席に座る彼女は大きな瞳を輝かせて、にっこりこちらを覗きこんだ。
担任が一人の生徒とともに教室に入ってきた。みんなの目が一斉にそちらに向かった。それでも果歩だけはずっと僕の方を見ていた。
◇
こんな二人の居場所に現れたアメリカ帰りの転校生。少年はアイスダンスをするという彼に強い焦りを感じ、彼と同じ道に飛び込んでいく……
――小説家になろう、カクヨム(別タイトル)にも掲載――

サンスポット【完結】
中畑 道
青春
校内一静で暗い場所に部室を構える竹ヶ鼻商店街歴史文化研究部。入学以来詳しい理由を聞かされることなく下校時刻まで部室で過ごすことを義務付けられた唯一の部員入間川息吹は、日課の筋トレ後ただ静かに時間が過ぎるのを待つ生活を一年以上続けていた。
そんな誰も寄り付かない部室を訪れた女生徒北条志摩子。彼女との出会いが切っ掛けで入間川は気付かされる。
この部の意義、自分が居る理由、そして、何をすべきかを。
※この物語は、全四章で構成されています。

放課後はネットで待ち合わせ
星名柚花(恋愛小説大賞参加中)
青春
【カクヨム×魔法のiらんどコンテスト特別賞受賞作】
高校入学を控えた前日、山科萌はいつものメンバーとオンラインゲームで遊んでいた。
何気なく「明日入学式だ」と言ったことから、ゲーム友達「ルビー」も同じ高校に通うことが判明。
翌日、萌はルビーと出会う。
女性アバターを使っていたルビーの正体は、ゲーム好きな美少年だった。
彼から女子避けのために「彼女のふりをしてほしい」と頼まれた萌。
初めはただのフリだったけれど、だんだん彼のことが気になるようになり…?

深海の星空
柴野日向
青春
「あなたが、少しでも笑っていてくれるなら、ぼくはもう、何もいらないんです」
ひねくれた孤高の少女と、真面目すぎる新聞配達の少年は、深い海の底で出会った。誰にも言えない秘密を抱え、塞がらない傷を見せ合い、ただ求めるのは、歩む深海に差し込む光。
少しずつ縮まる距離の中、明らかになるのは、少女の最も嫌う人間と、望まれなかった少年との残酷な繋がり。
やがて立ち塞がる絶望に、一縷の希望を見出す二人は、再び手を繋ぐことができるのか。
世界の片隅で、小さな幸福へと手を伸ばす、少年少女の物語。

冬の水葬
束原ミヤコ
青春
夕霧七瀬(ユウギリナナセ)は、一つ年上の幼なじみ、凪蓮水(ナギハスミ)が好き。
凪が高校生になってから疎遠になってしまっていたけれど、ずっと好きだった。
高校一年生になった夕霧は、凪と同じ高校に通えることを楽しみにしていた。
美術部の凪を追いかけて美術部に入り、気安い幼なじみの間柄に戻ることができたと思っていた――
けれど、そのときにはすでに、凪の心には消えない傷ができてしまっていた。
ある女性に捕らわれた凪と、それを追いかける夕霧の、繰り返す冬の話。

氷の蝶は死神の花の夢をみる
河津田 眞紀
青春
刈磨汰一(かるまたいち)は、生まれながらの不運体質だ。
幼い頃から数々の不運に見舞われ、二週間前にも交通事故に遭ったばかり。
久しぶりに高校へ登校するも、野球ボールが顔面に直撃し昏倒。生死の境を彷徨う。
そんな彼の前に「神」を名乗る怪しいチャラ男が現れ、命を助ける条件としてこんな依頼を突きつけてきた。
「その"厄"を引き寄せる体質を使って、神さまのたまごである"彩岐蝶梨"を護ってくれないか?」
彩岐蝶梨(さいきちより)。
それは、汰一が密かに想いを寄せる少女の名だった。
不運で目立たない汰一と、クール美少女で人気者な蝶梨。
まるで接点のない二人だったが、保健室でのやり取りを機に関係を持ち始める。
一緒に花壇の手入れをしたり、漫画を読んだり、勉強をしたり……
放課後の逢瀬を重ねる度に見えてくる、蝶梨の隙だらけな素顔。
その可愛さに悶えながら、汰一は想いをさらに強めるが……彼はまだ知らない。
完璧美少女な蝶梨に、本人も無自覚な"危険すぎる願望"があることを……
蝶梨に迫る、この世ならざる敵との戦い。
そして、次第に暴走し始める彼女の変態性。
その可愛すぎる変態フェイスを独占するため、汰一は神の力を駆使し、今日も闇を狩る。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















