20 / 23
第19話 変化の兆し?
しおりを挟む
「仕事、終了」
ううん、健康がやはり一番だ。身体が健やかならば、領主の仕事もはかどる。気持ちの方も晴々して、あらゆる事が気持ちよくなる。ずっと寝たきりでいるのは、かなりの苦痛が伴うからね。今までも病気にはいくらかかかったが、あの病気を通して、それが痛い程に分かってしまった。健康は、最大の財産である。自分の財産をどんなに蓄えても、自分が病気なら意味がない。健やかな身体と、穏やかな気持ちが保たれる事で、「人生」って言うのは何よりも輝くのだ。自分が生きてさえいれば、楽しい事はいくらでも味わえる。財産はそれを助ける、便利道具でしかない。道具は自分の背中に背負い、時には他者を生かして、みんなの幸せを満たすからこそ意味があるのだ。自分だけで財産を独り占めし、他人からもそれを奪うようでは、一定期間は幸せになれたとしても、やがては没落を生み、破滅を呼びこんで、自分も含めたあらゆるモノを損なってしまうのである。
俺がずっと前に見た社交界の光景も、その前兆をほのめかす壮大な序章だった。自分は、あんなふうになってはいけない。富と虚栄と保身に魅せられてはならない。人間の人生に必要な物は、「自分がこの世に生きている」と言う実感、「生まれてきてよかった」と思える幸福感なのだ。社交界の中で見たそれには、その幸福感を損なう地獄が流れていたばかりではない。それを否めるすべてが潜んでいた。人間が人間としての幸せを感じられなくなれば、その人はきっと誰よりも不幸になってしまう。自分は、そんな不幸には陥りたくなかった。
「生きている内は、幸せでありたい。幸せに生きて、周りの人達も幸せにしたい」
それを叶えるのは大変だろうが、それでも「やってやる」と言う気持ちは変わらなかった。俺が自分の趣味に打ちこむのも、それを「叶えたい」と思っているからである。一度きりの人生を、「俺」と言う存在を、魂の欠片まで大事にしたかった。俺が今日、封土の教会に行った理由もまた、その意識からきたモノだった。教会の中には墓が、両親の十字架が建っている。十字架の前には墓誌が刻まれ、そこには両親の名前と死亡日が彫られていた。墓誌の近くには……誰かが墓に添えてくれたのだろう、二つの小さな花が添えられていた。
俺は、その花に思わず泣いてしまった。花の色が美しかった事もあったが、それが風に動く姿からも、何とも言えない哀愁を覚えてしまったからである。俺は花の位置を少しずらし、風の当たらないところに置いて、それから両親の墓に十字を切ろうとした。だが、教会の司祭にそれを妨げられてしまった。司祭は俺の顔をまじまじと見たが、やがて来訪の意図を彼なりに察すると、俺の代わりに十字を切って、俺の両親に祈りを捧げはじめた。
「人間の魂は」
「うん?」
「決して滅びません。神のご加護がある限り、どんな魂もいずれ蘇る。今はただ、その時を待っているだけです」
俺はその言葉に胸を打たれたが、表情の方はあくまで冷静を装いつづけた。こう言う感情を悟られるのは、やはり恥ずかしい。
「異国の宗教では」
「はい?」
「そう言うのは、『輪廻転生』と言うらしい。『何かの姿で生まれた魂は、この世で生命が亡くなると、別の姿になって、この世界にまた戻ってくる』と言う考えだ。生前の行いに沿った姿や身分、種族や性別になってね。生命の環をいつまでも回りつづける」
「それは、面白い世界観ですね。私達の死生観では、魂はひたすらに昇っていくだけですが。そちらの世界では、同じところをぐるぐると回っているわけですね?」
「うん。だから、『死』と言う概念もない。死は、生の一部だからね。そこを通りすぎればまだ、新しい生命に生まれかわる。今の自分とは違う、まったく新しい自分に」
「貴方のご両親も、その新しい自分になっているかもしれませんね」
俺はまた、司祭の言葉に俯いてしまった。彼の言葉には、不思議な哀愁が漂っている。
「そうだといいな。もし、そうなっていれば……この世でまた、会えるからね。もう慣れてはいるけれど、やっぱり悲しいモノは悲しいよ」
司祭は、その言葉に押しだまった。その言葉がどうやら、司祭の心に刺さったらしい。彼は十字架の周りをしばらく歩き、頭上の空を時折見あげたが、俺の方にまた視線を戻すと、何処か寂しげな顔で、その場にゆっくりと立ちどまった。
「領主様にこれからも幸があらん事を」
意外な言葉だった。でも、うん、悪い気はしない。こう言う人に自分の幸せを祈られるのは、恥ずかしくもやはり嬉しかった。俺は自分の鼻先をポリポリと掻いて、目の前の司祭に「クスッ」と笑いかえした。
「ありがとう。俺も、貴方の幸せを祈らせてもらいます。この封土を治める者として。領民の幸せは、俺の幸せでもありますから。みんなが幸せになってくれたら、俺も」
「領主様」
司祭は俺の前に歩みよろうとしたが、その足をピタリと止めてしまった。彼がその場から歩きだそうとした瞬間、世話係の召使いがここに突然現れたからである。司祭は俺の顔をしばらく見て、それから世話係の顔に視線を移した。
「どうなされました?」
召使いは、その質問になかなか答えなかった。自分の息が上がっている事もあったが、その内側に何かを秘めているようで、司祭の質問にも上手く答えられなかったようである。俺が召使いの前に歩みより、彼にまた同じ質問を投げかけた時も、俺の目を何度か見わしたが、それ以上の反応はほとんど見せなかった。召使いは自分の息を整え、それがようやく落ちついたところで、俺の目をじっと見つめはじめた。
「決まりましたよ」
「え?」
何が?
「決まったんだ?」
「結婚の相手が、です。今まで様々な家を駆けまわりましたが、それをようやく見つけました。結婚の相手は、その家柄もよいお嬢様です」
俺は最初、彼が何を言っているのか分からなかった。「結婚」の意味は分かっても、そこからの思考がまったく働かない。まるで思考の時間が止まったようだった。あらゆる反論や反対意見が止まって、その場から一歩も動けなくなるように。頭の回転がすっかり止まってしまったのである。俺は回転の持ち手を何とか動かして、召使いの顔をじっと見かえした。
「どうして?」
「はい?」
「どうして、そんな事をしたんだ? どうして、そんな余計な事を?」
そうは言ったが、そんな事はずっと前から何となく察していた。察していたが、それが現実になるなんて思ってもいなかった。自分の結婚相手は、自分の手で見つけだす。領主の俺には叶わない夢かもしれないが、それでも一つくらい、身分の鎖を超えた願いは叶えたかった。そうでなければ、俺の存在意義がなくなる。俺が俺としての尊厳もなくなる。俺は自分では何もせず、どんな婚姻も叶うような貴族には、何があってもなりたくなかった。
「ふざけるな! 貴方の事は、家族のように思っていたけれど。今回ばかりは、許せない。貴方は、俺の大事な人生を勝手に決めてしまったんだ!」
召使いは、その言葉に怒らなかった。怒らなかったが、一種の不快感は覚えたらしい。俺が鋭い目で彼の顔を睨んだ時も、それに臆するどころか、俺の目を反対に睨みかえしてきた。
「貴方の人生は、貴方だけの物ではありません。貴方自身が、それをどう思っていようとも。貴方は、ここの領主です。領主には、領主の責任がある。『自分の血を繋げる』と言う責任が。私はただ、そのお手伝いをしただけです」
俺は、その言葉にふらついた。その言葉自体は、嬉しい。嬉しいが、それでもやはりふらついてしまった。自分の未来に影を感じて、その影が自分に迫ってくるような恐怖を覚えて。司祭が俺に「大丈夫ですか?」と訊いた時も、その質問に「ああうん、何とか」と答える事はできたが、それ以外の反応はできず、挙げ句は「ちょっと気持ちわるくなって」と苦笑いしてしまった。
俺は虚ろな視界にふらつきながらも、ある時は司祭の、またある時は両親の墓に目をやって、それに無言の救いを求めつづけた。自分はまだ、自分の自由を失いたくない。
「そのお嬢様は」
それに答えたのはもちろん、俺の目の前に立っている召使いだ。
「はい?」
「何歳くらい?」
「貴方と同い年ですよ。亜麻色の髪がとてもお綺麗な、見目麗しいお嬢様です。中身の方は、今どきの感じですが。話していて、とても気持ちいいお嬢様でした」
そうだとしても、やはり腑に落ちない。その子の事が嫌いなわけではないが、「強制」の二文字が俺をどうしても苛立たせてしまった。自分はこれから、会った事もない少女と結ばれなければならない。その少女と結ばれて、次の命を作らなければならない。女性の身体には(俺も男だからね)年相応な興味があった俺だが、今ばかりは「それ」が妙に腹立たしく、また一種の嫌悪感すらも覚えてしまった。
そいつは、俺の未来を阻む魔物。趣味の世界に攻めこもうとする破壊者だった。破壊者のやる事は、往々にしてろくでもない。今までの生活が、すっかり変わってしまう可能性もある。俺の大事な趣味が、壊されてしまうかもしれない可能性が。その可能性は、何としても防がなければならない。俺が俺として、これからも生きていくためにもね。その可能性だけは、絶対に壊したかった。
俺は鋭い目で、召使いの顔を睨んだ。それに怯まない召使いだったが、今はそんな事などどうでもいい。
「話は、どこまで進んでいるの?」
「詳しいところは、まだ。でも、だいたいの事は決まっています。式の打ち合わせが、来月の」
「ら、来月!」
「はい。相手に貴方の人柄をお話ししたら、相手がその気になってしまいましたね。本当は、明日にでも会いたいようです。打ち合わせが来月に延びた理由も、相手方にどうしても断れない約束があるからのようで」
「そ、そうか」
召使いは、その返事に押しだまった。その返事に苛立ったわけではなく、俺の態度にいらついてしまったらしい。彼の内心は推しはかれないが、「ゴホン」と咳払いした態度からは、その苛立ちが感じられた。召使いは真面目な顔で、俺の目を見かえした。
「相手方のお嬢様は」
「うん?」
「貴方の事をえらく気に入ったようです。『今までの男性とは、かなり違うようですね』と言って。彼女は……世俗な表現を使えば、とても好かれるようですから。それも同年代の男性にね。正に薔薇だらけの(※国のことわざで、「一人の女性が多くの男性に好かれている状態」を例えた言葉)状態です。彼女を嫁にしたい男性は、山ほどいる。貴方は、そんなご令嬢に好意を抱かれたのです」
「ふうん。それは、名誉な事だね。名誉な事だけど」
「はい?」
「それがどうして、こんなに嬉しくないんだろう?」
召使いは、その言葉に目を細めた、マズイ、これは相当に怒っている。
「領主様」
「な、なに?」
「子どもの時間は、終わりです」
俺は、その言葉にうつむいた。その言葉は、文字通りの死刑宣告に等しい。召使いは「今の生活を変える必要はない」と言ったが、それもただの誤魔化しにしか聞こえなかった。
「そ、そうか。なら、これからは?」
「ええ、大人の時間です。貴方も、女性の肌をしらなければなりません。いつまでも、清らかな身体でいるわけにはいかない。貴方にも、その時が訪れたのです」
そんな時は、いらない。そう言いかけたが、それを言うだけの気力が残っていなかった。召使いの言葉に言いかえす気力も。今の俺にできるのは、召使いに「気分が悪い」と言って、彼の前から歩きだす事だけだった。俺は真っ黒な気持ちで、地面の上を歩きつづけた。だが、奴はそれでも許さない。俺がどんなに離れようとしても、その背中に「待ってください」と話しかけてきた。「もう一つ、貴方に伝えなければならない事があります」
俺は、その言葉に振りかえった。これ以上、一体何を言うのだろう?
「なんだ?」
「貴方が前に『頼んだ』と言う道具……確か、『記録器』と言いましたか? それがさっき、貴方の館に届きました」
「カメラが館に届いた?」
「ええ、綺麗な箱に入れられてね。庭番の男が、その道具を預かっています。貴方が自分の館に戻られたら、すぐに渡せるように」
「そ、そうか。それは」
悪い時宜だね。あんなに楽しみにしていたのに……。
「今は」
「はい?」
「うんう、何でもない」
「そうですか。では、気をつけてお帰りください。私は、司祭と式の打ち合わせがありますので」
「分かった」
俺は憂鬱な顔で、自分の館に帰った。館の庭では召使いが言った通り、庭番が件の箱を持って、俺の帰りを待っていた。俺は彼の前に歩みより、彼に「悪かったね」と言って、彼から件の箱を受けとった。
「ありがとう」
「いえ」
返事は、それだけ。俺が館の中に入った時も、その様子をただ眺めていただけだった。彼は俺が玄関の戸を閉めると、あらゆる興味を忘れて、自分の仕事にまた戻りはじめた。
俺は、自分の部屋に戻った。そうする事以外、何の考えもなかったからだ。俺は部屋の中に入ると、ベッドの上に腰かけて、箱の中からカメラを取りだした。カメラの形は、格好良かった。詳しいところは分からないが、「レンズ」と呼ばれる部品はもちろん、その本体も見事な形に仕上がっていて、触れば触る程に愛着が、見れば見る程に興奮が湧きあがってしまった。
俺はその興奮にしばらく酔いしれたが、現実の事象にはやはり抗えないらしく、興奮の波が静まった頃には、その現実から逃れようとする意思、つまりは現実逃避を考えていた。
「明日は、コイツで遊ぼう」
コイツを使って、嫌な事を忘れよう。
「今の俺には、そうする事しかできないんだから」
俺は悲しげな顔で、手元のカメラを眺めつづけた。
ううん、健康がやはり一番だ。身体が健やかならば、領主の仕事もはかどる。気持ちの方も晴々して、あらゆる事が気持ちよくなる。ずっと寝たきりでいるのは、かなりの苦痛が伴うからね。今までも病気にはいくらかかかったが、あの病気を通して、それが痛い程に分かってしまった。健康は、最大の財産である。自分の財産をどんなに蓄えても、自分が病気なら意味がない。健やかな身体と、穏やかな気持ちが保たれる事で、「人生」って言うのは何よりも輝くのだ。自分が生きてさえいれば、楽しい事はいくらでも味わえる。財産はそれを助ける、便利道具でしかない。道具は自分の背中に背負い、時には他者を生かして、みんなの幸せを満たすからこそ意味があるのだ。自分だけで財産を独り占めし、他人からもそれを奪うようでは、一定期間は幸せになれたとしても、やがては没落を生み、破滅を呼びこんで、自分も含めたあらゆるモノを損なってしまうのである。
俺がずっと前に見た社交界の光景も、その前兆をほのめかす壮大な序章だった。自分は、あんなふうになってはいけない。富と虚栄と保身に魅せられてはならない。人間の人生に必要な物は、「自分がこの世に生きている」と言う実感、「生まれてきてよかった」と思える幸福感なのだ。社交界の中で見たそれには、その幸福感を損なう地獄が流れていたばかりではない。それを否めるすべてが潜んでいた。人間が人間としての幸せを感じられなくなれば、その人はきっと誰よりも不幸になってしまう。自分は、そんな不幸には陥りたくなかった。
「生きている内は、幸せでありたい。幸せに生きて、周りの人達も幸せにしたい」
それを叶えるのは大変だろうが、それでも「やってやる」と言う気持ちは変わらなかった。俺が自分の趣味に打ちこむのも、それを「叶えたい」と思っているからである。一度きりの人生を、「俺」と言う存在を、魂の欠片まで大事にしたかった。俺が今日、封土の教会に行った理由もまた、その意識からきたモノだった。教会の中には墓が、両親の十字架が建っている。十字架の前には墓誌が刻まれ、そこには両親の名前と死亡日が彫られていた。墓誌の近くには……誰かが墓に添えてくれたのだろう、二つの小さな花が添えられていた。
俺は、その花に思わず泣いてしまった。花の色が美しかった事もあったが、それが風に動く姿からも、何とも言えない哀愁を覚えてしまったからである。俺は花の位置を少しずらし、風の当たらないところに置いて、それから両親の墓に十字を切ろうとした。だが、教会の司祭にそれを妨げられてしまった。司祭は俺の顔をまじまじと見たが、やがて来訪の意図を彼なりに察すると、俺の代わりに十字を切って、俺の両親に祈りを捧げはじめた。
「人間の魂は」
「うん?」
「決して滅びません。神のご加護がある限り、どんな魂もいずれ蘇る。今はただ、その時を待っているだけです」
俺はその言葉に胸を打たれたが、表情の方はあくまで冷静を装いつづけた。こう言う感情を悟られるのは、やはり恥ずかしい。
「異国の宗教では」
「はい?」
「そう言うのは、『輪廻転生』と言うらしい。『何かの姿で生まれた魂は、この世で生命が亡くなると、別の姿になって、この世界にまた戻ってくる』と言う考えだ。生前の行いに沿った姿や身分、種族や性別になってね。生命の環をいつまでも回りつづける」
「それは、面白い世界観ですね。私達の死生観では、魂はひたすらに昇っていくだけですが。そちらの世界では、同じところをぐるぐると回っているわけですね?」
「うん。だから、『死』と言う概念もない。死は、生の一部だからね。そこを通りすぎればまだ、新しい生命に生まれかわる。今の自分とは違う、まったく新しい自分に」
「貴方のご両親も、その新しい自分になっているかもしれませんね」
俺はまた、司祭の言葉に俯いてしまった。彼の言葉には、不思議な哀愁が漂っている。
「そうだといいな。もし、そうなっていれば……この世でまた、会えるからね。もう慣れてはいるけれど、やっぱり悲しいモノは悲しいよ」
司祭は、その言葉に押しだまった。その言葉がどうやら、司祭の心に刺さったらしい。彼は十字架の周りをしばらく歩き、頭上の空を時折見あげたが、俺の方にまた視線を戻すと、何処か寂しげな顔で、その場にゆっくりと立ちどまった。
「領主様にこれからも幸があらん事を」
意外な言葉だった。でも、うん、悪い気はしない。こう言う人に自分の幸せを祈られるのは、恥ずかしくもやはり嬉しかった。俺は自分の鼻先をポリポリと掻いて、目の前の司祭に「クスッ」と笑いかえした。
「ありがとう。俺も、貴方の幸せを祈らせてもらいます。この封土を治める者として。領民の幸せは、俺の幸せでもありますから。みんなが幸せになってくれたら、俺も」
「領主様」
司祭は俺の前に歩みよろうとしたが、その足をピタリと止めてしまった。彼がその場から歩きだそうとした瞬間、世話係の召使いがここに突然現れたからである。司祭は俺の顔をしばらく見て、それから世話係の顔に視線を移した。
「どうなされました?」
召使いは、その質問になかなか答えなかった。自分の息が上がっている事もあったが、その内側に何かを秘めているようで、司祭の質問にも上手く答えられなかったようである。俺が召使いの前に歩みより、彼にまた同じ質問を投げかけた時も、俺の目を何度か見わしたが、それ以上の反応はほとんど見せなかった。召使いは自分の息を整え、それがようやく落ちついたところで、俺の目をじっと見つめはじめた。
「決まりましたよ」
「え?」
何が?
「決まったんだ?」
「結婚の相手が、です。今まで様々な家を駆けまわりましたが、それをようやく見つけました。結婚の相手は、その家柄もよいお嬢様です」
俺は最初、彼が何を言っているのか分からなかった。「結婚」の意味は分かっても、そこからの思考がまったく働かない。まるで思考の時間が止まったようだった。あらゆる反論や反対意見が止まって、その場から一歩も動けなくなるように。頭の回転がすっかり止まってしまったのである。俺は回転の持ち手を何とか動かして、召使いの顔をじっと見かえした。
「どうして?」
「はい?」
「どうして、そんな事をしたんだ? どうして、そんな余計な事を?」
そうは言ったが、そんな事はずっと前から何となく察していた。察していたが、それが現実になるなんて思ってもいなかった。自分の結婚相手は、自分の手で見つけだす。領主の俺には叶わない夢かもしれないが、それでも一つくらい、身分の鎖を超えた願いは叶えたかった。そうでなければ、俺の存在意義がなくなる。俺が俺としての尊厳もなくなる。俺は自分では何もせず、どんな婚姻も叶うような貴族には、何があってもなりたくなかった。
「ふざけるな! 貴方の事は、家族のように思っていたけれど。今回ばかりは、許せない。貴方は、俺の大事な人生を勝手に決めてしまったんだ!」
召使いは、その言葉に怒らなかった。怒らなかったが、一種の不快感は覚えたらしい。俺が鋭い目で彼の顔を睨んだ時も、それに臆するどころか、俺の目を反対に睨みかえしてきた。
「貴方の人生は、貴方だけの物ではありません。貴方自身が、それをどう思っていようとも。貴方は、ここの領主です。領主には、領主の責任がある。『自分の血を繋げる』と言う責任が。私はただ、そのお手伝いをしただけです」
俺は、その言葉にふらついた。その言葉自体は、嬉しい。嬉しいが、それでもやはりふらついてしまった。自分の未来に影を感じて、その影が自分に迫ってくるような恐怖を覚えて。司祭が俺に「大丈夫ですか?」と訊いた時も、その質問に「ああうん、何とか」と答える事はできたが、それ以外の反応はできず、挙げ句は「ちょっと気持ちわるくなって」と苦笑いしてしまった。
俺は虚ろな視界にふらつきながらも、ある時は司祭の、またある時は両親の墓に目をやって、それに無言の救いを求めつづけた。自分はまだ、自分の自由を失いたくない。
「そのお嬢様は」
それに答えたのはもちろん、俺の目の前に立っている召使いだ。
「はい?」
「何歳くらい?」
「貴方と同い年ですよ。亜麻色の髪がとてもお綺麗な、見目麗しいお嬢様です。中身の方は、今どきの感じですが。話していて、とても気持ちいいお嬢様でした」
そうだとしても、やはり腑に落ちない。その子の事が嫌いなわけではないが、「強制」の二文字が俺をどうしても苛立たせてしまった。自分はこれから、会った事もない少女と結ばれなければならない。その少女と結ばれて、次の命を作らなければならない。女性の身体には(俺も男だからね)年相応な興味があった俺だが、今ばかりは「それ」が妙に腹立たしく、また一種の嫌悪感すらも覚えてしまった。
そいつは、俺の未来を阻む魔物。趣味の世界に攻めこもうとする破壊者だった。破壊者のやる事は、往々にしてろくでもない。今までの生活が、すっかり変わってしまう可能性もある。俺の大事な趣味が、壊されてしまうかもしれない可能性が。その可能性は、何としても防がなければならない。俺が俺として、これからも生きていくためにもね。その可能性だけは、絶対に壊したかった。
俺は鋭い目で、召使いの顔を睨んだ。それに怯まない召使いだったが、今はそんな事などどうでもいい。
「話は、どこまで進んでいるの?」
「詳しいところは、まだ。でも、だいたいの事は決まっています。式の打ち合わせが、来月の」
「ら、来月!」
「はい。相手に貴方の人柄をお話ししたら、相手がその気になってしまいましたね。本当は、明日にでも会いたいようです。打ち合わせが来月に延びた理由も、相手方にどうしても断れない約束があるからのようで」
「そ、そうか」
召使いは、その返事に押しだまった。その返事に苛立ったわけではなく、俺の態度にいらついてしまったらしい。彼の内心は推しはかれないが、「ゴホン」と咳払いした態度からは、その苛立ちが感じられた。召使いは真面目な顔で、俺の目を見かえした。
「相手方のお嬢様は」
「うん?」
「貴方の事をえらく気に入ったようです。『今までの男性とは、かなり違うようですね』と言って。彼女は……世俗な表現を使えば、とても好かれるようですから。それも同年代の男性にね。正に薔薇だらけの(※国のことわざで、「一人の女性が多くの男性に好かれている状態」を例えた言葉)状態です。彼女を嫁にしたい男性は、山ほどいる。貴方は、そんなご令嬢に好意を抱かれたのです」
「ふうん。それは、名誉な事だね。名誉な事だけど」
「はい?」
「それがどうして、こんなに嬉しくないんだろう?」
召使いは、その言葉に目を細めた、マズイ、これは相当に怒っている。
「領主様」
「な、なに?」
「子どもの時間は、終わりです」
俺は、その言葉にうつむいた。その言葉は、文字通りの死刑宣告に等しい。召使いは「今の生活を変える必要はない」と言ったが、それもただの誤魔化しにしか聞こえなかった。
「そ、そうか。なら、これからは?」
「ええ、大人の時間です。貴方も、女性の肌をしらなければなりません。いつまでも、清らかな身体でいるわけにはいかない。貴方にも、その時が訪れたのです」
そんな時は、いらない。そう言いかけたが、それを言うだけの気力が残っていなかった。召使いの言葉に言いかえす気力も。今の俺にできるのは、召使いに「気分が悪い」と言って、彼の前から歩きだす事だけだった。俺は真っ黒な気持ちで、地面の上を歩きつづけた。だが、奴はそれでも許さない。俺がどんなに離れようとしても、その背中に「待ってください」と話しかけてきた。「もう一つ、貴方に伝えなければならない事があります」
俺は、その言葉に振りかえった。これ以上、一体何を言うのだろう?
「なんだ?」
「貴方が前に『頼んだ』と言う道具……確か、『記録器』と言いましたか? それがさっき、貴方の館に届きました」
「カメラが館に届いた?」
「ええ、綺麗な箱に入れられてね。庭番の男が、その道具を預かっています。貴方が自分の館に戻られたら、すぐに渡せるように」
「そ、そうか。それは」
悪い時宜だね。あんなに楽しみにしていたのに……。
「今は」
「はい?」
「うんう、何でもない」
「そうですか。では、気をつけてお帰りください。私は、司祭と式の打ち合わせがありますので」
「分かった」
俺は憂鬱な顔で、自分の館に帰った。館の庭では召使いが言った通り、庭番が件の箱を持って、俺の帰りを待っていた。俺は彼の前に歩みより、彼に「悪かったね」と言って、彼から件の箱を受けとった。
「ありがとう」
「いえ」
返事は、それだけ。俺が館の中に入った時も、その様子をただ眺めていただけだった。彼は俺が玄関の戸を閉めると、あらゆる興味を忘れて、自分の仕事にまた戻りはじめた。
俺は、自分の部屋に戻った。そうする事以外、何の考えもなかったからだ。俺は部屋の中に入ると、ベッドの上に腰かけて、箱の中からカメラを取りだした。カメラの形は、格好良かった。詳しいところは分からないが、「レンズ」と呼ばれる部品はもちろん、その本体も見事な形に仕上がっていて、触れば触る程に愛着が、見れば見る程に興奮が湧きあがってしまった。
俺はその興奮にしばらく酔いしれたが、現実の事象にはやはり抗えないらしく、興奮の波が静まった頃には、その現実から逃れようとする意思、つまりは現実逃避を考えていた。
「明日は、コイツで遊ぼう」
コイツを使って、嫌な事を忘れよう。
「今の俺には、そうする事しかできないんだから」
俺は悲しげな顔で、手元のカメラを眺めつづけた。
0
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

婚約破棄されたので森の奥でカフェを開いてスローライフ
あげは
ファンタジー
「私は、ユミエラとの婚約を破棄する!」
学院卒業記念パーティーで、婚約者である王太子アルフリードに突然婚約破棄された、ユミエラ・フォン・アマリリス公爵令嬢。
家族にも愛されていなかったユミエラは、王太子に婚約破棄されたことで利用価値がなくなったとされ家を勘当されてしまう。
しかし、ユミエラに特に気にした様子はなく、むしろ喜んでいた。
これまでの生活に嫌気が差していたユミエラは、元孤児で転生者の侍女ミシェルだけを連れ、その日のうちに家を出て人のいない森の奥に向かい、森の中でカフェを開くらしい。
「さあ、ミシェル! 念願のスローライフよ! 張り切っていきましょう!」
王都を出るとなぜか国を守護している神獣が待ち構えていた。
どうやら国を捨てユミエラについてくるらしい。
こうしてユミエラは、転生者と神獣という何とも不思議なお供を連れ、優雅なスローライフを楽しむのであった。
一方、ユミエラを追放し、神獣にも見捨てられた王国は、愚かな王太子のせいで混乱に陥るのだった――。
なろう・カクヨムにも投稿

少し冷めた村人少年の冒険記
mizuno sei
ファンタジー
辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。
トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。
優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。
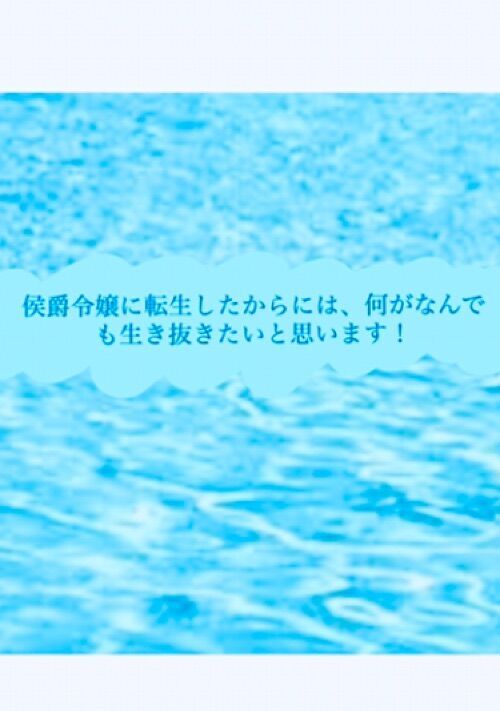
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

転生幼女の攻略法〜最強チートの異世界日記〜
みおな
ファンタジー
私の名前は、瀬尾あかり。
37歳、日本人。性別、女。職業は一般事務員。容姿は10人並み。趣味は、物語を書くこと。
そう!私は、今流行りのラノベをスマホで書くことを趣味にしている、ごくごく普通のOLである。
今日も、いつも通りに仕事を終え、いつも通りに帰りにスーパーで惣菜を買って、いつも通りに1人で食事をする予定だった。
それなのに、どうして私は道路に倒れているんだろう?後ろからぶつかってきた男に刺されたと気付いたのは、もう意識がなくなる寸前だった。
そして、目覚めた時ー

劣悪だと言われたハズレ加護の『空間魔法』を、便利だと思っているのは僕だけなのだろうか?
はらくろ
ファンタジー
海と交易で栄えた国を支える貴族家のひとつに、
強くて聡明な父と、優しくて活動的な母の間に生まれ育った少年がいた。
母親似に育った賢く可愛らしい少年は優秀で、将来が楽しみだと言われていたが、
その少年に、突然の困難が立ちはだかる。
理由は、貴族の跡取りとしては公言できないほどの、劣悪な加護を洗礼で授かってしまったから。
一生外へ出られないかもしれない幽閉のような生活を続けるよりも、少年は屋敷を出て行く選択をする。
それでも持ち前の強く非常識なほどの魔力の多さと、負けず嫌いな性格でその困難を乗り越えていく。
そんな少年の物語。

勇者パーティを追放された聖女ですが、やっと解放されてむしろ感謝します。なのにパーティの人たちが続々と私に助けを求めてくる件。
八木愛里
ファンタジー
聖女のロザリーは戦闘中でも回復魔法が使用できるが、勇者が見目麗しいソニアを新しい聖女として迎え入れた。ソニアからの入れ知恵で、勇者パーティから『役立たず』と侮辱されて、ついに追放されてしまう。
パーティの人間関係に疲れたロザリーは、ソロ冒険者になることを決意。
攻撃魔法の魔道具を求めて魔道具屋に行ったら、店主から才能を認められる。
ロザリーの実力を知らず愚かにも追放した勇者一行は、これまで攻略できたはずの中級のダンジョンでさえ失敗を繰り返し、仲間割れし破滅へ向かっていく。
一方ロザリーは上級の魔物討伐に成功したり、大魔法使いさまと協力して王女を襲ってきた魔獣を倒したり、国の英雄と呼ばれる存在になっていく。
これは真の実力者であるロザリーが、ソロ冒険者としての地位を確立していきながら、残念ながら追いかけてきた魔法使いや女剣士を「虫が良すぎるわ!」と追っ払い、入り浸っている魔道具屋の店主が実は憧れの大魔法使いさまだが、どうしても本人が気づかない話。
※11話以降から勇者パーティの没落シーンがあります。
※40話に鬱展開あり。苦手な方は読み飛ばし推奨します。
※表紙はAIイラストを使用。

魔法が使えない令嬢は住んでいた小屋が燃えたので家出します
怠惰るウェイブ
ファンタジー
グレイの世界は狭く暗く何よりも灰色だった。
本来なら領主令嬢となるはずの彼女は領主邸で住むことを許されず、ボロ小屋で暮らしていた。
彼女はある日、棚から落ちてきた一冊の本によって人生が変わることになる。
世界が色づき始めた頃、ある事件をきっかけに少女は旅をすることにした。
喋ることのできないグレイは旅を通して自身の世界を色付けていく。

偽物の侯爵子息は平民落ちのうえに国外追放を言い渡されたので自由に生きる。え?帰ってきてくれ?それは無理というもの
つくも茄子
ファンタジー
サビオ・パッツィーニは、魔術師の家系である名門侯爵家の次男に生まれながら魔力鑑定で『魔力無し』の判定を受けてしまう。魔力がない代わりにずば抜けて優れた頭脳を持つサビオに家族は温かく見守っていた。そんなある日、サビオが侯爵家の人間でない事が判明した。妖精の取り換えっ子だと神官は告げる。本物は家族によく似た天使のような美少年。こうしてサビオは「王家と侯爵家を謀った罪人」として国外追放されてしまった。
隣国でギルド登録したサビオは「黒曜」というギルド名で第二の人生を歩んでいく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















