16 / 23
第15話 瞑想に酔う
しおりを挟む
「仕事、終了」
ふう、今日も頑張りました。今日は早朝からの仕事だったので、「疲れ」よりも「眠気」の方が勝っていた。馬の上に乗っている時も、周りの景色をぼうっと眺める事はできたが、それがどう言う意味を表して、何を表しているのかは分からなかった。ただの流れる景色。時の流れに従った、景色の変容。自分の館に帰った時も、馬の上から降りる時は別として、館の食堂に入った時はもちろん、そこで今日の昼食を食べた時だって、「それが美味かった」と思う以外は何も感じなかったのである。
これには、俺自身も思わず笑ってしまった。朝が苦手な方ではなかったが、今日はどうも違うらしい。いつもはここで「これから何をしようかな?」と楽しくなるところだが、今日に限っては「それ」がまったく起こらなかった。不思議な安心感は覚えるが、それ以外は何も感じない状態。「虚無」と「安定」の間をふわふわしていたのである。そこには陰鬱な安らぎこそあったが、鮮やかな興奮はまったく見られなかった。
「本当、今日はどうしちゃったんだろう?」
別に疲れているわけでもないのに。あらゆる根気、やる気、集中力が削がれている。皿の上にナイフとフォークを置いた時も、何だか妙な気分に駆られてしまった。「自分は一体、どうしてしまったのだろう? 町の中に好奇心を置いてきてしまったのかな?」ってね。沈んだ気持ちになってしまったのだ。「こんな事は、滅多にない事なのに?」と、そう内心で思ってしまったのである。俺は椅子の背もたれに寄りかかって、食堂の天井をぼうっと見あげはじめた。
「はあ」
溜め息。
「はぁああ」
もう一発、溜め息。
「はぁ」
三発目の時には、流石の料理長も「どうしたのですか?」と訊いてきた。「そんなに溜め息ばかりついて。貴方の取り柄は、趣味への驚くべき回帰力でしょう?」
料理長は呆れ顔で、俺の横顔をじろじろ見た。
「それが、こんな?」
「う、うん」
俺は椅子の背もたれから背を離して、テーブルの上に両肘をつき、両手で自分の頭を支えた。そうしなければ、「今の体勢が保てない」と思ったからである。
「ああうん、ちょっとね? 気分がこう、優れないって言うか? 気持ちの方が、何だかモヤモヤするんだ」
「なるほど。それは、厄介ですね。私にも覚えがありますが、そう言う時は瞑想に限ります。自分の心を空にして、森羅万象の友人になる。疲れが眠気を制している時には、有効な手段ですよ?」
「瞑想、か。なるほど。それは、盲点だったね。何かに打ちこむ事、行動に示すだけが趣味じゃない。頭の空想に戯れるのもまた、一つの趣味だ。瞑想なら特別な道具も要らないからね」
料理長は複雑な顔で、その言葉に眉を寄せた。どうやら、その言葉に違和感を覚えたらしい。「う、ううん」と唸った声からも、その雰囲気が感じられた。料理長は世話係の召使いをチラッと見、俺の顔にまた視線を戻して、その目をじっと見つめた。
「いや、そうとも言えません。瞑想には、集中力が要りますからね。余計な雑念を抱いてはならない。雑念の中身を打ちはらう方法は、好い香りに鼻を休ませる事です」
「好い香りに鼻を休ませる?」
「そうです。例えば」
料理長はまた、世話係の召使いに視線を戻した。彼に何やら、言うつもりらしい。
「良い匂いのする蝋燭とか? そう言う蝋燭はもちろん、この館にもあるでしょう」
召使いの答えは、「ああうん」だった。
「領主様が以前……領主様は覚えていらっしゃらないかもしれませんが、怪しげな商人から買った蝋燭が数本。今は、館の倉庫に眠っているがね。『出せ』と言うのなら、すぐに出せる」
出すか? と、召使いは言った。
「お前さんのご要望通り。私には、普通の蝋燭にしか見えないがね。蝋燭の色も、至って普通だし。私としてはそんな物を使わなくても、『瞑想なんてすぐにできる』と思うが?」
「瞑想は、そんなに甘くない。アンタは分からないかもしれないが、『雑念』って言うのは本当に厄介なんだ。『それをどんなに払おう』と思っても、そいつの方からしつこく追いかけてくる。蝋燭は、そいつを巻くのにどうしても必要な道具なんだ」
「そ、そうか。そこまで言うのなら仕方ない。すぐに取ってくるから、待っていて下さい」
召使いは館の倉庫に走って、そこから何本かの蝋燭を取ってきた。それらの蝋燭が、今の話に出てきた物である。
「ほれ」
「ありがとう」
料理長は召使いから蝋燭を受けとって、俺の右手にそれらを渡した。
「蝋燭は、部屋の中を囲うように置いて下さい。間違っても、その近くに燃えやすい物は置かないように。貴方は蝋燭の中心に座って、自身の瞑想をはじめる。『胡座』の事は、ご存じですか?」
俺は、その質問にうなずいた。胡座の事は、異国の本から学んでいる。その本によると、胡座とは精神集中の方法であり、(上手く言い表せないが)両足を斜めに重ねながら座る事で、「仏」とか言う存在に近づく、あるいは、それ自体になる事を目的とした物らしかった。俺も実際に見たわけではないが、その本に書かれていた胡座は、こっちの文化ではほとんど見られない、神との対話とは違って、自然との会話、自分との対話のように思えた。まるで自分が自然と一つになっている……いや、「人間は、自然の一部である」と言う認識を思いださせるような感じだったのである。
そう言う感じは、こっちの文化ではあまり見られない。こっちの文化はあくまで自然と人間は別であり、人間が自然を認める事で、「その自然はそこにある」と言う感じだった。人間が目の前の自然を認めなければ、それがどんなにそびえ立っていても、「最初から無かった物」になってしまうのである。それが(俺にとっては)ある種の傲慢にも思えていたが、こちらの文化では「それ」が常識であり、また永久不変の真理でもあった。だから、人間は自然を配する。自然は、人間の所有物だから。いつでも使えて、いつでも費やせる、人類全体の財産だから。それ故に争いも起こる。「瞑想」と「座禅」は、それらの関係性を見なおす精神調整だった。
「もちろん、しっているよ。その意味も含めてね」
「そうですか。なら、話も早い。精神の眠気を払うにも、瞑想はいい方法です。なんたって、その眠気と友人になれますからね」
料理長は俺の顔から視線を逸らして、食堂の中から出ていった。「今のような時には、最高の方法です」
召使いは、その言葉に溜め息をついた。理由は分からないが、その言葉に呆れてしまったらしい。蝋燭の方に目をやった時も、何処か呆れ顔でそれを眺めていた。彼は蝋燭の表面をしばらく眺めたが、それも数分も経たぬうちに終わってしまった。
「領主様」
「ん? なんだ?」
「瞑想もいいですが、必要な注意も忘れないで下さい。館が火事になったなど、ご先祖の皆様に申し訳が立ちませんから」
「失礼な! それくらいの注意は、忘れないよ。俺も、自分の館を燃やしたくないからね」
「どうだか?」
俺は不機嫌な顔で、その言葉に溜め息をついた。その言葉に思わず苛立ってしまったからである。彼の心配も分かるが、そこはもう少し信じてもらいたかった。自分はここの主、その屋敷を燃やすわけがないだろう? 敵の襲撃で焼かれたなら仕方ないが、自分で焼くなどまずありえなかった。
「そんなに心配なら、部屋の外に控えていろよ」
俺は「ニヤリ」と笑って、食堂の中から出ていった。食堂の外は静かだったが、瞑想への期待が高まっていたせいで、自分の部屋に戻った時はもちろん、床の上に蝋燭を立てた時も、その静けさをすっかり忘れていた。それから蝋燭の先に火を点け、円の中心に自分が座った時も、蝋燭の火が作りだす妙な雰囲気に当てられてしまい、自分の呼吸に少し驚いた時以外は、不思議な気持ちで例の胡座をかきつづけていたのである。
「ふう」
俺は両目の瞼を閉じて、瞑想の世界に入りはじめた。瞑想の世界は穏やか、とは違うな。穏やかな雰囲気は漂っているが、それはあくまで雰囲気だけであり、その奥には神秘的な空気が漂っていた。まるで精神の一部が透けていくように、自分自身が透きとおっていくような感覚が渦巻いていたのである。これは、それを味わっている人にしか分からない。傍目からは眠っているようにしか見えないだろうが、自分としてはまったく起きているのだから。部屋の中に漂っている音はもちろん、窓の外から響いてくる音もしっかり聞こえている。が、それが意識に入ってこないのだ。音は「音」として分かっても、その間に遮る物があって、それ以外の諸々がすべて無くなっている。まるでこの世界から解きはなたれたかのようにね? あらゆる雑念がすっかり無くなっていた。
俺は「無我の境地」とも言える状態、その瞑想に精神を落としつづけた。精神の中には、だだっ広い空間が広がっている。空間の中には「宇宙」と呼ばれる真っ黒な場所があり、宇宙の中には恒星が、恒星の周りには惑星が、惑星の回りには衛星が飛んでいて、それらは俺のところにどんどん近づいていき、やがてはそれらの星々を形づくっている風景、風景の中にある生物界、生物界の中にある有と無、これらの根幹らしい原子までもがはっきりと見えはじめた。
原子は俺の細胞に訴えて、この世のすべてを語りはじめる。この世に生命が生まれて、それがどうして老いていくのか語りはじめる。「永遠の世界を作るためには、それ自体を永遠にできない」と言うふうにね。何だか分からない事を語ってくるのだ。「完全の正体が、不完全であるように」と言うふうに、今までの観念をすっかり覆してくるのである。これには、俺自身も思わず驚いてしまった。
「生きる事は」
すなわち、死ぬ事。
「生まれる事は」
すなわち、滅びる事。
「永遠を求める人の願望はすべて、終焉の現実に帰っていくんだ」
終焉の現実がなければ、誰も永遠を求めない。無限の生命を得ようともしない。俺達が「自分の命が惜しい」と思うのは、それが決して万能ではないからだ。万能の魂は、神の中にしかありえない。そして、俺達は決して神にはなりえない。神は無限の中を生き、俺達は有限の時を生きているからだ。有限の時間を生きている以上、その命にもまた限りがあるのである。そう思うと……。人の命は、儚いな。森の木々は、何百年も生きているのにね。人の命は、持っても百年ちょっとしかない。
こうして座禅を組んでいる俺もあと、何年生きられるのだろうか?
自分が自分として、この世に生きられるのだろうか? 今も減りつづけている、この命を……。
「はぁ」
俺は、瞑想の世界に溜め息をついた。瞑想の世界には、命の真実が潜んでいる。「命」と言うのは大きく、やがては「果てる」と言う真理を。そして、「その定めからは逃れられない」と言う宿命を。「座禅」を通して、俺に「それ」を伝えていた。「お前もいつかは、原子の世界に帰ってしまうのだ」と、そう静かに訴えていたのである。
「人間も、結局は原子の塊だからな。無数の原子が、結びついた集合体。瞑想は、それを気づかせる手段なんだ。あの夜空に広がっている宇宙も、そう言う類いの集まりでしかない。ようは、その大きさが違うだけなんだ。『集合体』と言う意味では、俺も宇宙と変わらない。俺の中にも、その宇宙が広がっている」
俺は自分の不思議さ、その神秘さにうなずきながらも、瞑想の世界に「クスッ」と笑って、明日の事をじっと考えはじめた。
「さて。明日は、何をしようかな?」
ふう、今日も頑張りました。今日は早朝からの仕事だったので、「疲れ」よりも「眠気」の方が勝っていた。馬の上に乗っている時も、周りの景色をぼうっと眺める事はできたが、それがどう言う意味を表して、何を表しているのかは分からなかった。ただの流れる景色。時の流れに従った、景色の変容。自分の館に帰った時も、馬の上から降りる時は別として、館の食堂に入った時はもちろん、そこで今日の昼食を食べた時だって、「それが美味かった」と思う以外は何も感じなかったのである。
これには、俺自身も思わず笑ってしまった。朝が苦手な方ではなかったが、今日はどうも違うらしい。いつもはここで「これから何をしようかな?」と楽しくなるところだが、今日に限っては「それ」がまったく起こらなかった。不思議な安心感は覚えるが、それ以外は何も感じない状態。「虚無」と「安定」の間をふわふわしていたのである。そこには陰鬱な安らぎこそあったが、鮮やかな興奮はまったく見られなかった。
「本当、今日はどうしちゃったんだろう?」
別に疲れているわけでもないのに。あらゆる根気、やる気、集中力が削がれている。皿の上にナイフとフォークを置いた時も、何だか妙な気分に駆られてしまった。「自分は一体、どうしてしまったのだろう? 町の中に好奇心を置いてきてしまったのかな?」ってね。沈んだ気持ちになってしまったのだ。「こんな事は、滅多にない事なのに?」と、そう内心で思ってしまったのである。俺は椅子の背もたれに寄りかかって、食堂の天井をぼうっと見あげはじめた。
「はあ」
溜め息。
「はぁああ」
もう一発、溜め息。
「はぁ」
三発目の時には、流石の料理長も「どうしたのですか?」と訊いてきた。「そんなに溜め息ばかりついて。貴方の取り柄は、趣味への驚くべき回帰力でしょう?」
料理長は呆れ顔で、俺の横顔をじろじろ見た。
「それが、こんな?」
「う、うん」
俺は椅子の背もたれから背を離して、テーブルの上に両肘をつき、両手で自分の頭を支えた。そうしなければ、「今の体勢が保てない」と思ったからである。
「ああうん、ちょっとね? 気分がこう、優れないって言うか? 気持ちの方が、何だかモヤモヤするんだ」
「なるほど。それは、厄介ですね。私にも覚えがありますが、そう言う時は瞑想に限ります。自分の心を空にして、森羅万象の友人になる。疲れが眠気を制している時には、有効な手段ですよ?」
「瞑想、か。なるほど。それは、盲点だったね。何かに打ちこむ事、行動に示すだけが趣味じゃない。頭の空想に戯れるのもまた、一つの趣味だ。瞑想なら特別な道具も要らないからね」
料理長は複雑な顔で、その言葉に眉を寄せた。どうやら、その言葉に違和感を覚えたらしい。「う、ううん」と唸った声からも、その雰囲気が感じられた。料理長は世話係の召使いをチラッと見、俺の顔にまた視線を戻して、その目をじっと見つめた。
「いや、そうとも言えません。瞑想には、集中力が要りますからね。余計な雑念を抱いてはならない。雑念の中身を打ちはらう方法は、好い香りに鼻を休ませる事です」
「好い香りに鼻を休ませる?」
「そうです。例えば」
料理長はまた、世話係の召使いに視線を戻した。彼に何やら、言うつもりらしい。
「良い匂いのする蝋燭とか? そう言う蝋燭はもちろん、この館にもあるでしょう」
召使いの答えは、「ああうん」だった。
「領主様が以前……領主様は覚えていらっしゃらないかもしれませんが、怪しげな商人から買った蝋燭が数本。今は、館の倉庫に眠っているがね。『出せ』と言うのなら、すぐに出せる」
出すか? と、召使いは言った。
「お前さんのご要望通り。私には、普通の蝋燭にしか見えないがね。蝋燭の色も、至って普通だし。私としてはそんな物を使わなくても、『瞑想なんてすぐにできる』と思うが?」
「瞑想は、そんなに甘くない。アンタは分からないかもしれないが、『雑念』って言うのは本当に厄介なんだ。『それをどんなに払おう』と思っても、そいつの方からしつこく追いかけてくる。蝋燭は、そいつを巻くのにどうしても必要な道具なんだ」
「そ、そうか。そこまで言うのなら仕方ない。すぐに取ってくるから、待っていて下さい」
召使いは館の倉庫に走って、そこから何本かの蝋燭を取ってきた。それらの蝋燭が、今の話に出てきた物である。
「ほれ」
「ありがとう」
料理長は召使いから蝋燭を受けとって、俺の右手にそれらを渡した。
「蝋燭は、部屋の中を囲うように置いて下さい。間違っても、その近くに燃えやすい物は置かないように。貴方は蝋燭の中心に座って、自身の瞑想をはじめる。『胡座』の事は、ご存じですか?」
俺は、その質問にうなずいた。胡座の事は、異国の本から学んでいる。その本によると、胡座とは精神集中の方法であり、(上手く言い表せないが)両足を斜めに重ねながら座る事で、「仏」とか言う存在に近づく、あるいは、それ自体になる事を目的とした物らしかった。俺も実際に見たわけではないが、その本に書かれていた胡座は、こっちの文化ではほとんど見られない、神との対話とは違って、自然との会話、自分との対話のように思えた。まるで自分が自然と一つになっている……いや、「人間は、自然の一部である」と言う認識を思いださせるような感じだったのである。
そう言う感じは、こっちの文化ではあまり見られない。こっちの文化はあくまで自然と人間は別であり、人間が自然を認める事で、「その自然はそこにある」と言う感じだった。人間が目の前の自然を認めなければ、それがどんなにそびえ立っていても、「最初から無かった物」になってしまうのである。それが(俺にとっては)ある種の傲慢にも思えていたが、こちらの文化では「それ」が常識であり、また永久不変の真理でもあった。だから、人間は自然を配する。自然は、人間の所有物だから。いつでも使えて、いつでも費やせる、人類全体の財産だから。それ故に争いも起こる。「瞑想」と「座禅」は、それらの関係性を見なおす精神調整だった。
「もちろん、しっているよ。その意味も含めてね」
「そうですか。なら、話も早い。精神の眠気を払うにも、瞑想はいい方法です。なんたって、その眠気と友人になれますからね」
料理長は俺の顔から視線を逸らして、食堂の中から出ていった。「今のような時には、最高の方法です」
召使いは、その言葉に溜め息をついた。理由は分からないが、その言葉に呆れてしまったらしい。蝋燭の方に目をやった時も、何処か呆れ顔でそれを眺めていた。彼は蝋燭の表面をしばらく眺めたが、それも数分も経たぬうちに終わってしまった。
「領主様」
「ん? なんだ?」
「瞑想もいいですが、必要な注意も忘れないで下さい。館が火事になったなど、ご先祖の皆様に申し訳が立ちませんから」
「失礼な! それくらいの注意は、忘れないよ。俺も、自分の館を燃やしたくないからね」
「どうだか?」
俺は不機嫌な顔で、その言葉に溜め息をついた。その言葉に思わず苛立ってしまったからである。彼の心配も分かるが、そこはもう少し信じてもらいたかった。自分はここの主、その屋敷を燃やすわけがないだろう? 敵の襲撃で焼かれたなら仕方ないが、自分で焼くなどまずありえなかった。
「そんなに心配なら、部屋の外に控えていろよ」
俺は「ニヤリ」と笑って、食堂の中から出ていった。食堂の外は静かだったが、瞑想への期待が高まっていたせいで、自分の部屋に戻った時はもちろん、床の上に蝋燭を立てた時も、その静けさをすっかり忘れていた。それから蝋燭の先に火を点け、円の中心に自分が座った時も、蝋燭の火が作りだす妙な雰囲気に当てられてしまい、自分の呼吸に少し驚いた時以外は、不思議な気持ちで例の胡座をかきつづけていたのである。
「ふう」
俺は両目の瞼を閉じて、瞑想の世界に入りはじめた。瞑想の世界は穏やか、とは違うな。穏やかな雰囲気は漂っているが、それはあくまで雰囲気だけであり、その奥には神秘的な空気が漂っていた。まるで精神の一部が透けていくように、自分自身が透きとおっていくような感覚が渦巻いていたのである。これは、それを味わっている人にしか分からない。傍目からは眠っているようにしか見えないだろうが、自分としてはまったく起きているのだから。部屋の中に漂っている音はもちろん、窓の外から響いてくる音もしっかり聞こえている。が、それが意識に入ってこないのだ。音は「音」として分かっても、その間に遮る物があって、それ以外の諸々がすべて無くなっている。まるでこの世界から解きはなたれたかのようにね? あらゆる雑念がすっかり無くなっていた。
俺は「無我の境地」とも言える状態、その瞑想に精神を落としつづけた。精神の中には、だだっ広い空間が広がっている。空間の中には「宇宙」と呼ばれる真っ黒な場所があり、宇宙の中には恒星が、恒星の周りには惑星が、惑星の回りには衛星が飛んでいて、それらは俺のところにどんどん近づいていき、やがてはそれらの星々を形づくっている風景、風景の中にある生物界、生物界の中にある有と無、これらの根幹らしい原子までもがはっきりと見えはじめた。
原子は俺の細胞に訴えて、この世のすべてを語りはじめる。この世に生命が生まれて、それがどうして老いていくのか語りはじめる。「永遠の世界を作るためには、それ自体を永遠にできない」と言うふうにね。何だか分からない事を語ってくるのだ。「完全の正体が、不完全であるように」と言うふうに、今までの観念をすっかり覆してくるのである。これには、俺自身も思わず驚いてしまった。
「生きる事は」
すなわち、死ぬ事。
「生まれる事は」
すなわち、滅びる事。
「永遠を求める人の願望はすべて、終焉の現実に帰っていくんだ」
終焉の現実がなければ、誰も永遠を求めない。無限の生命を得ようともしない。俺達が「自分の命が惜しい」と思うのは、それが決して万能ではないからだ。万能の魂は、神の中にしかありえない。そして、俺達は決して神にはなりえない。神は無限の中を生き、俺達は有限の時を生きているからだ。有限の時間を生きている以上、その命にもまた限りがあるのである。そう思うと……。人の命は、儚いな。森の木々は、何百年も生きているのにね。人の命は、持っても百年ちょっとしかない。
こうして座禅を組んでいる俺もあと、何年生きられるのだろうか?
自分が自分として、この世に生きられるのだろうか? 今も減りつづけている、この命を……。
「はぁ」
俺は、瞑想の世界に溜め息をついた。瞑想の世界には、命の真実が潜んでいる。「命」と言うのは大きく、やがては「果てる」と言う真理を。そして、「その定めからは逃れられない」と言う宿命を。「座禅」を通して、俺に「それ」を伝えていた。「お前もいつかは、原子の世界に帰ってしまうのだ」と、そう静かに訴えていたのである。
「人間も、結局は原子の塊だからな。無数の原子が、結びついた集合体。瞑想は、それを気づかせる手段なんだ。あの夜空に広がっている宇宙も、そう言う類いの集まりでしかない。ようは、その大きさが違うだけなんだ。『集合体』と言う意味では、俺も宇宙と変わらない。俺の中にも、その宇宙が広がっている」
俺は自分の不思議さ、その神秘さにうなずきながらも、瞑想の世界に「クスッ」と笑って、明日の事をじっと考えはじめた。
「さて。明日は、何をしようかな?」
0
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

婚約破棄されたので森の奥でカフェを開いてスローライフ
あげは
ファンタジー
「私は、ユミエラとの婚約を破棄する!」
学院卒業記念パーティーで、婚約者である王太子アルフリードに突然婚約破棄された、ユミエラ・フォン・アマリリス公爵令嬢。
家族にも愛されていなかったユミエラは、王太子に婚約破棄されたことで利用価値がなくなったとされ家を勘当されてしまう。
しかし、ユミエラに特に気にした様子はなく、むしろ喜んでいた。
これまでの生活に嫌気が差していたユミエラは、元孤児で転生者の侍女ミシェルだけを連れ、その日のうちに家を出て人のいない森の奥に向かい、森の中でカフェを開くらしい。
「さあ、ミシェル! 念願のスローライフよ! 張り切っていきましょう!」
王都を出るとなぜか国を守護している神獣が待ち構えていた。
どうやら国を捨てユミエラについてくるらしい。
こうしてユミエラは、転生者と神獣という何とも不思議なお供を連れ、優雅なスローライフを楽しむのであった。
一方、ユミエラを追放し、神獣にも見捨てられた王国は、愚かな王太子のせいで混乱に陥るのだった――。
なろう・カクヨムにも投稿

少し冷めた村人少年の冒険記
mizuno sei
ファンタジー
辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。
トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。
優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。
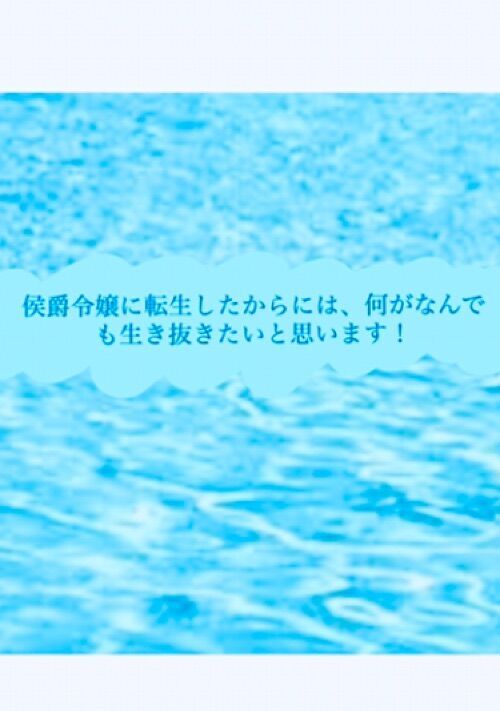
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

転生幼女の攻略法〜最強チートの異世界日記〜
みおな
ファンタジー
私の名前は、瀬尾あかり。
37歳、日本人。性別、女。職業は一般事務員。容姿は10人並み。趣味は、物語を書くこと。
そう!私は、今流行りのラノベをスマホで書くことを趣味にしている、ごくごく普通のOLである。
今日も、いつも通りに仕事を終え、いつも通りに帰りにスーパーで惣菜を買って、いつも通りに1人で食事をする予定だった。
それなのに、どうして私は道路に倒れているんだろう?後ろからぶつかってきた男に刺されたと気付いたのは、もう意識がなくなる寸前だった。
そして、目覚めた時ー

劣悪だと言われたハズレ加護の『空間魔法』を、便利だと思っているのは僕だけなのだろうか?
はらくろ
ファンタジー
海と交易で栄えた国を支える貴族家のひとつに、
強くて聡明な父と、優しくて活動的な母の間に生まれ育った少年がいた。
母親似に育った賢く可愛らしい少年は優秀で、将来が楽しみだと言われていたが、
その少年に、突然の困難が立ちはだかる。
理由は、貴族の跡取りとしては公言できないほどの、劣悪な加護を洗礼で授かってしまったから。
一生外へ出られないかもしれない幽閉のような生活を続けるよりも、少年は屋敷を出て行く選択をする。
それでも持ち前の強く非常識なほどの魔力の多さと、負けず嫌いな性格でその困難を乗り越えていく。
そんな少年の物語。

お兄様、冷血貴公子じゃなかったんですか?~7歳から始める第二の聖女人生~
みつまめ つぼみ
ファンタジー
17歳で偽りの聖女として処刑された記憶を持つ7歳の女の子が、今度こそ世界を救うためにエルメーテ公爵家に引き取られて人生をやり直します。
記憶では冷血貴公子と呼ばれていた公爵令息は、義妹である主人公一筋。
そんな義兄に戸惑いながらも甘える日々。
「お兄様? シスコンもほどほどにしてくださいね?」
恋愛ポンコツと冷血貴公子の、コミカルでシリアスな救世物語開幕!

偽物の侯爵子息は平民落ちのうえに国外追放を言い渡されたので自由に生きる。え?帰ってきてくれ?それは無理というもの
つくも茄子
ファンタジー
サビオ・パッツィーニは、魔術師の家系である名門侯爵家の次男に生まれながら魔力鑑定で『魔力無し』の判定を受けてしまう。魔力がない代わりにずば抜けて優れた頭脳を持つサビオに家族は温かく見守っていた。そんなある日、サビオが侯爵家の人間でない事が判明した。妖精の取り換えっ子だと神官は告げる。本物は家族によく似た天使のような美少年。こうしてサビオは「王家と侯爵家を謀った罪人」として国外追放されてしまった。
隣国でギルド登録したサビオは「黒曜」というギルド名で第二の人生を歩んでいく。

魔法が使えない令嬢は住んでいた小屋が燃えたので家出します
怠惰るウェイブ
ファンタジー
グレイの世界は狭く暗く何よりも灰色だった。
本来なら領主令嬢となるはずの彼女は領主邸で住むことを許されず、ボロ小屋で暮らしていた。
彼女はある日、棚から落ちてきた一冊の本によって人生が変わることになる。
世界が色づき始めた頃、ある事件をきっかけに少女は旅をすることにした。
喋ることのできないグレイは旅を通して自身の世界を色付けていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















