14 / 23
第13話 電子遊戯
しおりを挟む
「仕事、終了」
いやいや今日も、お疲れ様。今日の仕事を無事に終えて、これ以上に「ホッ」とする事はない。最近は、何かと忙しかったかな。自分の趣味自体はやれても、身体のどこかには見えない倦怠感を残っていた。今日の仕事も、「それ」との見事な戦いである。仕事の内容はそんなに難しくはなくても、一つ一つの細かい作業が、石積みのように重なって、それが終わった頃にはもう、不思議な倦怠感を覚えていた。倦怠感の裏には満足感も潜んでいたが、封土の現場から離れて、そこから自分の館に帰る間は、その満足感よりも倦怠感をより覚えてしまい、部屋の中に入った時だって、倦怠感の残滓に思わず潰されてしまった。
この感覚はたぶん、実際に味わってみないと分からない。頭の中では「仕事は既に終わっているのだ」と分かっているが、精神の方では「まだ終わっていない」と叫んでいる状態だったからだ。これには、流石に参ってしまう。身体と精神の疲れが離れている以上は、どんなに休んでも休んだ気がしないからだ。自分は、常に働いている。いや、ある意味では「働かされている」と言った方が正しいかもしれない。「お前の役割はこう、君の役割はコレ」と言う感じにね。「ホッ」としたくても、「ホッ」とできないのだ。「今日が終わった」と言う感覚の後ろでは、「明日もある」と言う感覚が控えている。
封土の領民達は「これ」をほとんど感じていないようだが、一応の休憩時間がある俺にとっては、ある意味で拷問のようにも思えていた。働いても、働いても終わらない拷問。拷問の先に待っている、ひとときの休み時間。その休み時間にできる事は少ないが、それも積みかさなれば……まあ、結構な時間になるからね。少なくても、部屋の中を見わたせる時間はできる。それができれば、今日の趣味も自ずと見えてくるだろう。「今日は、どれを楽しもうかな?」って、一種の余裕が出てくるわけさ。
「ううん」
俺は自分の顎をつまんで、「今日の趣味はどれにするか?」と考えた。その結果がこれ、映像器(別名「テレビジョン」とも呼ばれ、その画面に綺麗な映像を映す道具である)の前に置かれて電子遊戯(これの別名は「映像ゲーム」と言い、「画面器」と呼ばれる道具の画面に映像を映す事で、その内容を楽しめる仕組みになっている)である。電子遊戯は俺と同年代くらいの少年や少女達に人気な道具だが、俺よりも上の年齢層にも受けているらしく、それで日々の生活費を稼いでいる者や、貴族並みの生活を送っている平民すらもいた。
正に夢の道具。「仕事」も「娯楽」も与える、凄い道具なのである。かく言う俺も、数年前にこの電子遊戯を買ってしまった。最近はあまり遊んでいないが、こう言う機会の時には、電子遊戯の起動装置をポチッと押している。そして今日も、その起動装置をポチッと押していた。……うん、いい感じだ。画面の起動音も、いい音を奏でている。これは、気分が高まるね。画面の起動音は自然にはない音だが、それだけに人間の力が感じられて、画面の上に印が出てくる時は、いつ見てもワクワクしてしまった。
俺は「ニコッ」と笑って、電子遊具の操作器を握った。電子遊戯の操作器は握りやすい構造になっていて、自分の手が余程に大きくなければ、大抵はすぐに合うような感じだった。そこに付いている物(俺達は、「十次キー」とか「丸ボタン」とか呼んでいるが)も、使い手の使用感を重んじているようで、違和感はそんなに覚えられない。むしろ、爽快感すら覚えてしまった。不向きな人は「これ」に苦しめられるようだが、俺の場合は運が良かったらしく、取扱説明書を少し読んだだけで、すぐに「こんなモノかな?」と扱えてしまった。
今回楽しむ電子遊戯も、そんなふうに覚えた物である。少年貴族の間で流行っている格闘遊戯。自分の好きな疑似人間を戦わせて、その勝敗を決する遊戯だ。これが、かなり面白い。少年達の中には「経営系が好き」と言う者も多いが、経営は(俺の場合は)実際にやっているし、それはあくまでも経営風な遊びなので、現実の領地経営とはかなり掛けはなれていた。現実の料理経営は、遊戯のように甘くはない。電子遊戯の領地経営は「遊び手が飽きないように」、「遊び手の不満を促さないように」が主題になっているので、現実ではありえないところでいい事が起こったり、反対に悪い出来事が起こったりと、ありえない出来事がてんこ盛りになっていた。「すべては、遊び手の心を満たすために」と、あらゆるところに配慮がなされているのである。
それには、俺も思わず苦笑いしてしまった。これでは、領地経営の大変さが伝わらない。それがどんなに辛くて、苦しくても。電子遊戯の素晴らしいところは、そう言う部分は排せるところだが……。「辛い」も「苦しい」もない世界は、やはり何処か歪に感じられた。楽しさだけが搾りとられた世界。「娯楽」の意味では正しいのかもしれないが、それが変なふうに曲がって、「これが現実だ」と思うようになったら? おそらくは、怖い事になるだろう。それこそ、今の現実を壊すような出来事すら起きるかもしれない。「娯楽」を突きすすめた先には、そう言う罠が待っている。俺が今日、やろうとしている電子遊戯も……。
「ある意味じゃ、『それ』と同じかもしれないな」
現実の人間を殴る代わりに、虚構の存在を殴る。「現実の人間を傷つけなくて済む」と言う点では優れているかもしれないが、それも何かがおかしくなれば、本来の意義を失って、その部分がすっかり変わってしまう危険性もあった。例えば、「人を殴るのに抵抗がなくなる」と言った感じに。人間の道徳心がすっかり失われてしまう可能性もある。その意味では、この電子遊戯も「やりすぎてはいけないゲーム」、「程々が一番いいゲーム」だった。
「まあ、俺もそんなにやる方じゃないけどね? こう言う時以外は、さ」
俺は「ニコッ」と笑って、映像器の画面に目をやった。画面の上には、選択可能な疑似人間が移っている。彼等は細別や年齢の差こそあるものの、大体は何らかの武器を装っていて、大柄な男は大木を、小柄な少女は短剣などを握っていた。俺が選んだ疑似人間の騎士も、その右手に剣を携えている。初心者から上級者にも優しい武器、大体の男が大好きな聖剣を持っていた。
俺は画面の最初で選んだ物語編を進んで、そこに出てくる相手を「さて」と倒しはじめた。最初の敵は、魔術師の青年だった。魔術師の青年は中級者以上、特に上級者向けの疑似人間で、打撃技はそんなに強くないが、細かい魔法で繋げる連続攻撃が手ごわく、電子遊戯の難易度を「やさしい」にしないと、ほとんどの人間がすぐに殺されてしまう相手だった。これの覇を競う大会でも、この魔術師を使う人間は少なくない。またその容姿も優れているので、「絵師」と呼ばれる人々、特に女性絵師の間では、抜群の人気を誇っていた。そんな凄い疑似人間をこれから倒していくわけである。
俺は素人の技量を上手く使って、この相手を何とか戦いつづけた。騎士の剣術を巧みに使い、「ハメ技」と呼ばれる技術を生かして、相手の生命値をゴリゴリと削っていったのである。その途中で何度もやられ掛けても、その体勢をサッと戻し、相手の身体に攻撃をいくども当てつづけた。それがいい感じに溜まっていったおかげで、自分の生命値もかなり危なかったものの、制限時間内に魔術師の青年を何とか倒せたが、その興奮もすぐに収まってしまった。彼の次にもまだ、倒さなければならない敵は控えている。今度の敵は、男性支持者の中でも特に人気な修道女だった。
「コイツも、なかなか侮れない」
物理攻撃の類いはそんなに強くないが、「神の加護」と言う特殊技能を持っているおかげで、自分の生命値が半分になると、その防御力が二倍にまで上がってしまうのだ。これが、なかなかに厄介な技能である。他の疑似人間にも「それ」と似た特殊技能があるが、それらは魔力の回復速度が上がったり、自分の移動速度が上がったりで、疑似人間の防御力を上げる特殊機技能はこれしかなかった。俺が使っている騎士の特殊技能も、その攻撃力が一割二分五厘上がるだけである。だから、この特殊技能はほとんど卑怯技に近かった。相手の防御力が上がれば、倒すのがそれだけ難しくなるからね。男性支持者は、その特殊技能が好きなようだけど。騎士使いの俺としては、本当に困る相手だった。騎士と修道女の相性は、冗談抜きで最悪だったからである。「正直、かなり苦手な相手だけどね。もう、何回負けたか分からないくらいに」
俺は両手の操作器に力を入れて、画面の騎士をサッと動かした。騎士は、俺の操作に応えてくれた。俺の操作は単純な動きが多いので、「連続技」と呼ばれる物を除き、相手の生命値をそれなりにしか削れなかったが、「必殺技」と呼ばれる奥義のような技を出した時は、その生命値をゴリゴリと削られた。その効果もまた、宝石のように美しい。必殺技が決まる瞬間は、画面の絵が一瞬だけ止まって、そこから凄まじい攻撃の様子が描かれた。疑似人間が蝶のように舞い、剣が蜂のように舞う。現実の世界にも魔法は一応あったが、これは映像だからこそ見られる物、虚構の存在だからこそ味わえる光景に思えた。現実の世界をも越えた光景。虚構の中でしか描けない光景。それに魅せられた人々が、この電子遊戯にはまっていくのである。俺もそう言う趣向が強かったが、一日中これをやっているかもしれなかった。
俺は画面の騎士を動かして、敵の修道女を何とか倒す事ができた。
「よっしゃ!」
そう言って握った自分の拳は、自分が思った以上に汗ばんでいた。今の勝利がたぶん、自分の想像以上に嬉しかったらしい。修道女の次にも強い敵がまだまだ控えていたが、それすらも忘れてしまうくらいに喜んでしまった。「この調子で、どんどん勝っていこう」と、そう内心で思ってしまったのである。いつもの自分を忘れてしまうくらいにね。事実、それから先もずっと同じような感じだった。「呪い」を使う古代の蛇使いと戦った時も、「竜」になれる町の少女と戦った時も。両手の操作器を荒っぽく使ってしてしまったが、規則性のない動きが良い流れを作った事で、それらの敵を次々と倒す事ができた。彼等の最後に現れる敵も……そんな感じにいけばよかったが、こいつは流石にそうはいかなかった。強い技をいくども繰りだし、俺の騎士をどんどん追いつめる。俺も一応は「それ」に抗うが、流石は最後の敵であって、「再挑戦」と呼ばれる機能を何度も使ってしまった。
「くっ!」
俺は真面目な顔で、画面の敵と戦いつづけた。画面の敵が「ニヤリ」と笑った時はもちろん、俺の騎士を吹きとばした時も。あらゆる雑念を捨てて、そいつの生命値を削りつづけたのである。例のお世話係が「領主様、お食事の用意ができましたよ?」と現れた時も、その声だけを聞いて、目の前の敵にずっと挑みつづけた。その結果は、「やった!」の声からも分かるだろう? かなり危ないところだったが、相手の作った僅かな隙をついて、その強敵を何とか倒す事ができた。それも、騎士の必殺技で。美しい一撃を叩きこんだのである。
俺は「それ」に胸を高鳴らせたあまり、お世話係の存在をすっかり忘れて、子どものように「ヒャホォー!」と飛びあがってしまった。
「どんなもんだ! これで」
「確かに終わりです」
それで我に返った俺が、「ポカン」としたのは想像に難しくないだろう。俺は間抜けな顔で、自分の後ろを振りかえった。
「あう、そ、そうだな」
「まったく。電子遊戯もいいですが、程々して下さい」
「う、うん、分かった。ごめん」
俺は自分の頬を掻いて、部屋の中から歩きだした。今日の夕食を食べにいくためである。
「まあ、恥ずかしくはあったけどね。楽しかったから」
うん。
「さて。明日は、何をしようかな?」
いやいや今日も、お疲れ様。今日の仕事を無事に終えて、これ以上に「ホッ」とする事はない。最近は、何かと忙しかったかな。自分の趣味自体はやれても、身体のどこかには見えない倦怠感を残っていた。今日の仕事も、「それ」との見事な戦いである。仕事の内容はそんなに難しくはなくても、一つ一つの細かい作業が、石積みのように重なって、それが終わった頃にはもう、不思議な倦怠感を覚えていた。倦怠感の裏には満足感も潜んでいたが、封土の現場から離れて、そこから自分の館に帰る間は、その満足感よりも倦怠感をより覚えてしまい、部屋の中に入った時だって、倦怠感の残滓に思わず潰されてしまった。
この感覚はたぶん、実際に味わってみないと分からない。頭の中では「仕事は既に終わっているのだ」と分かっているが、精神の方では「まだ終わっていない」と叫んでいる状態だったからだ。これには、流石に参ってしまう。身体と精神の疲れが離れている以上は、どんなに休んでも休んだ気がしないからだ。自分は、常に働いている。いや、ある意味では「働かされている」と言った方が正しいかもしれない。「お前の役割はこう、君の役割はコレ」と言う感じにね。「ホッ」としたくても、「ホッ」とできないのだ。「今日が終わった」と言う感覚の後ろでは、「明日もある」と言う感覚が控えている。
封土の領民達は「これ」をほとんど感じていないようだが、一応の休憩時間がある俺にとっては、ある意味で拷問のようにも思えていた。働いても、働いても終わらない拷問。拷問の先に待っている、ひとときの休み時間。その休み時間にできる事は少ないが、それも積みかさなれば……まあ、結構な時間になるからね。少なくても、部屋の中を見わたせる時間はできる。それができれば、今日の趣味も自ずと見えてくるだろう。「今日は、どれを楽しもうかな?」って、一種の余裕が出てくるわけさ。
「ううん」
俺は自分の顎をつまんで、「今日の趣味はどれにするか?」と考えた。その結果がこれ、映像器(別名「テレビジョン」とも呼ばれ、その画面に綺麗な映像を映す道具である)の前に置かれて電子遊戯(これの別名は「映像ゲーム」と言い、「画面器」と呼ばれる道具の画面に映像を映す事で、その内容を楽しめる仕組みになっている)である。電子遊戯は俺と同年代くらいの少年や少女達に人気な道具だが、俺よりも上の年齢層にも受けているらしく、それで日々の生活費を稼いでいる者や、貴族並みの生活を送っている平民すらもいた。
正に夢の道具。「仕事」も「娯楽」も与える、凄い道具なのである。かく言う俺も、数年前にこの電子遊戯を買ってしまった。最近はあまり遊んでいないが、こう言う機会の時には、電子遊戯の起動装置をポチッと押している。そして今日も、その起動装置をポチッと押していた。……うん、いい感じだ。画面の起動音も、いい音を奏でている。これは、気分が高まるね。画面の起動音は自然にはない音だが、それだけに人間の力が感じられて、画面の上に印が出てくる時は、いつ見てもワクワクしてしまった。
俺は「ニコッ」と笑って、電子遊具の操作器を握った。電子遊戯の操作器は握りやすい構造になっていて、自分の手が余程に大きくなければ、大抵はすぐに合うような感じだった。そこに付いている物(俺達は、「十次キー」とか「丸ボタン」とか呼んでいるが)も、使い手の使用感を重んじているようで、違和感はそんなに覚えられない。むしろ、爽快感すら覚えてしまった。不向きな人は「これ」に苦しめられるようだが、俺の場合は運が良かったらしく、取扱説明書を少し読んだだけで、すぐに「こんなモノかな?」と扱えてしまった。
今回楽しむ電子遊戯も、そんなふうに覚えた物である。少年貴族の間で流行っている格闘遊戯。自分の好きな疑似人間を戦わせて、その勝敗を決する遊戯だ。これが、かなり面白い。少年達の中には「経営系が好き」と言う者も多いが、経営は(俺の場合は)実際にやっているし、それはあくまでも経営風な遊びなので、現実の領地経営とはかなり掛けはなれていた。現実の料理経営は、遊戯のように甘くはない。電子遊戯の領地経営は「遊び手が飽きないように」、「遊び手の不満を促さないように」が主題になっているので、現実ではありえないところでいい事が起こったり、反対に悪い出来事が起こったりと、ありえない出来事がてんこ盛りになっていた。「すべては、遊び手の心を満たすために」と、あらゆるところに配慮がなされているのである。
それには、俺も思わず苦笑いしてしまった。これでは、領地経営の大変さが伝わらない。それがどんなに辛くて、苦しくても。電子遊戯の素晴らしいところは、そう言う部分は排せるところだが……。「辛い」も「苦しい」もない世界は、やはり何処か歪に感じられた。楽しさだけが搾りとられた世界。「娯楽」の意味では正しいのかもしれないが、それが変なふうに曲がって、「これが現実だ」と思うようになったら? おそらくは、怖い事になるだろう。それこそ、今の現実を壊すような出来事すら起きるかもしれない。「娯楽」を突きすすめた先には、そう言う罠が待っている。俺が今日、やろうとしている電子遊戯も……。
「ある意味じゃ、『それ』と同じかもしれないな」
現実の人間を殴る代わりに、虚構の存在を殴る。「現実の人間を傷つけなくて済む」と言う点では優れているかもしれないが、それも何かがおかしくなれば、本来の意義を失って、その部分がすっかり変わってしまう危険性もあった。例えば、「人を殴るのに抵抗がなくなる」と言った感じに。人間の道徳心がすっかり失われてしまう可能性もある。その意味では、この電子遊戯も「やりすぎてはいけないゲーム」、「程々が一番いいゲーム」だった。
「まあ、俺もそんなにやる方じゃないけどね? こう言う時以外は、さ」
俺は「ニコッ」と笑って、映像器の画面に目をやった。画面の上には、選択可能な疑似人間が移っている。彼等は細別や年齢の差こそあるものの、大体は何らかの武器を装っていて、大柄な男は大木を、小柄な少女は短剣などを握っていた。俺が選んだ疑似人間の騎士も、その右手に剣を携えている。初心者から上級者にも優しい武器、大体の男が大好きな聖剣を持っていた。
俺は画面の最初で選んだ物語編を進んで、そこに出てくる相手を「さて」と倒しはじめた。最初の敵は、魔術師の青年だった。魔術師の青年は中級者以上、特に上級者向けの疑似人間で、打撃技はそんなに強くないが、細かい魔法で繋げる連続攻撃が手ごわく、電子遊戯の難易度を「やさしい」にしないと、ほとんどの人間がすぐに殺されてしまう相手だった。これの覇を競う大会でも、この魔術師を使う人間は少なくない。またその容姿も優れているので、「絵師」と呼ばれる人々、特に女性絵師の間では、抜群の人気を誇っていた。そんな凄い疑似人間をこれから倒していくわけである。
俺は素人の技量を上手く使って、この相手を何とか戦いつづけた。騎士の剣術を巧みに使い、「ハメ技」と呼ばれる技術を生かして、相手の生命値をゴリゴリと削っていったのである。その途中で何度もやられ掛けても、その体勢をサッと戻し、相手の身体に攻撃をいくども当てつづけた。それがいい感じに溜まっていったおかげで、自分の生命値もかなり危なかったものの、制限時間内に魔術師の青年を何とか倒せたが、その興奮もすぐに収まってしまった。彼の次にもまだ、倒さなければならない敵は控えている。今度の敵は、男性支持者の中でも特に人気な修道女だった。
「コイツも、なかなか侮れない」
物理攻撃の類いはそんなに強くないが、「神の加護」と言う特殊技能を持っているおかげで、自分の生命値が半分になると、その防御力が二倍にまで上がってしまうのだ。これが、なかなかに厄介な技能である。他の疑似人間にも「それ」と似た特殊技能があるが、それらは魔力の回復速度が上がったり、自分の移動速度が上がったりで、疑似人間の防御力を上げる特殊機技能はこれしかなかった。俺が使っている騎士の特殊技能も、その攻撃力が一割二分五厘上がるだけである。だから、この特殊技能はほとんど卑怯技に近かった。相手の防御力が上がれば、倒すのがそれだけ難しくなるからね。男性支持者は、その特殊技能が好きなようだけど。騎士使いの俺としては、本当に困る相手だった。騎士と修道女の相性は、冗談抜きで最悪だったからである。「正直、かなり苦手な相手だけどね。もう、何回負けたか分からないくらいに」
俺は両手の操作器に力を入れて、画面の騎士をサッと動かした。騎士は、俺の操作に応えてくれた。俺の操作は単純な動きが多いので、「連続技」と呼ばれる物を除き、相手の生命値をそれなりにしか削れなかったが、「必殺技」と呼ばれる奥義のような技を出した時は、その生命値をゴリゴリと削られた。その効果もまた、宝石のように美しい。必殺技が決まる瞬間は、画面の絵が一瞬だけ止まって、そこから凄まじい攻撃の様子が描かれた。疑似人間が蝶のように舞い、剣が蜂のように舞う。現実の世界にも魔法は一応あったが、これは映像だからこそ見られる物、虚構の存在だからこそ味わえる光景に思えた。現実の世界をも越えた光景。虚構の中でしか描けない光景。それに魅せられた人々が、この電子遊戯にはまっていくのである。俺もそう言う趣向が強かったが、一日中これをやっているかもしれなかった。
俺は画面の騎士を動かして、敵の修道女を何とか倒す事ができた。
「よっしゃ!」
そう言って握った自分の拳は、自分が思った以上に汗ばんでいた。今の勝利がたぶん、自分の想像以上に嬉しかったらしい。修道女の次にも強い敵がまだまだ控えていたが、それすらも忘れてしまうくらいに喜んでしまった。「この調子で、どんどん勝っていこう」と、そう内心で思ってしまったのである。いつもの自分を忘れてしまうくらいにね。事実、それから先もずっと同じような感じだった。「呪い」を使う古代の蛇使いと戦った時も、「竜」になれる町の少女と戦った時も。両手の操作器を荒っぽく使ってしてしまったが、規則性のない動きが良い流れを作った事で、それらの敵を次々と倒す事ができた。彼等の最後に現れる敵も……そんな感じにいけばよかったが、こいつは流石にそうはいかなかった。強い技をいくども繰りだし、俺の騎士をどんどん追いつめる。俺も一応は「それ」に抗うが、流石は最後の敵であって、「再挑戦」と呼ばれる機能を何度も使ってしまった。
「くっ!」
俺は真面目な顔で、画面の敵と戦いつづけた。画面の敵が「ニヤリ」と笑った時はもちろん、俺の騎士を吹きとばした時も。あらゆる雑念を捨てて、そいつの生命値を削りつづけたのである。例のお世話係が「領主様、お食事の用意ができましたよ?」と現れた時も、その声だけを聞いて、目の前の敵にずっと挑みつづけた。その結果は、「やった!」の声からも分かるだろう? かなり危ないところだったが、相手の作った僅かな隙をついて、その強敵を何とか倒す事ができた。それも、騎士の必殺技で。美しい一撃を叩きこんだのである。
俺は「それ」に胸を高鳴らせたあまり、お世話係の存在をすっかり忘れて、子どものように「ヒャホォー!」と飛びあがってしまった。
「どんなもんだ! これで」
「確かに終わりです」
それで我に返った俺が、「ポカン」としたのは想像に難しくないだろう。俺は間抜けな顔で、自分の後ろを振りかえった。
「あう、そ、そうだな」
「まったく。電子遊戯もいいですが、程々して下さい」
「う、うん、分かった。ごめん」
俺は自分の頬を掻いて、部屋の中から歩きだした。今日の夕食を食べにいくためである。
「まあ、恥ずかしくはあったけどね。楽しかったから」
うん。
「さて。明日は、何をしようかな?」
0
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

婚約破棄されたので森の奥でカフェを開いてスローライフ
あげは
ファンタジー
「私は、ユミエラとの婚約を破棄する!」
学院卒業記念パーティーで、婚約者である王太子アルフリードに突然婚約破棄された、ユミエラ・フォン・アマリリス公爵令嬢。
家族にも愛されていなかったユミエラは、王太子に婚約破棄されたことで利用価値がなくなったとされ家を勘当されてしまう。
しかし、ユミエラに特に気にした様子はなく、むしろ喜んでいた。
これまでの生活に嫌気が差していたユミエラは、元孤児で転生者の侍女ミシェルだけを連れ、その日のうちに家を出て人のいない森の奥に向かい、森の中でカフェを開くらしい。
「さあ、ミシェル! 念願のスローライフよ! 張り切っていきましょう!」
王都を出るとなぜか国を守護している神獣が待ち構えていた。
どうやら国を捨てユミエラについてくるらしい。
こうしてユミエラは、転生者と神獣という何とも不思議なお供を連れ、優雅なスローライフを楽しむのであった。
一方、ユミエラを追放し、神獣にも見捨てられた王国は、愚かな王太子のせいで混乱に陥るのだった――。
なろう・カクヨムにも投稿
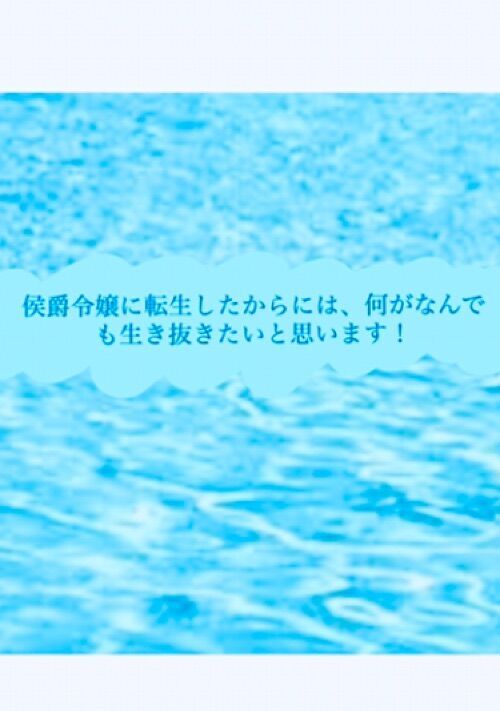
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

転生幼女の攻略法〜最強チートの異世界日記〜
みおな
ファンタジー
私の名前は、瀬尾あかり。
37歳、日本人。性別、女。職業は一般事務員。容姿は10人並み。趣味は、物語を書くこと。
そう!私は、今流行りのラノベをスマホで書くことを趣味にしている、ごくごく普通のOLである。
今日も、いつも通りに仕事を終え、いつも通りに帰りにスーパーで惣菜を買って、いつも通りに1人で食事をする予定だった。
それなのに、どうして私は道路に倒れているんだろう?後ろからぶつかってきた男に刺されたと気付いたのは、もう意識がなくなる寸前だった。
そして、目覚めた時ー

劣悪だと言われたハズレ加護の『空間魔法』を、便利だと思っているのは僕だけなのだろうか?
はらくろ
ファンタジー
海と交易で栄えた国を支える貴族家のひとつに、
強くて聡明な父と、優しくて活動的な母の間に生まれ育った少年がいた。
母親似に育った賢く可愛らしい少年は優秀で、将来が楽しみだと言われていたが、
その少年に、突然の困難が立ちはだかる。
理由は、貴族の跡取りとしては公言できないほどの、劣悪な加護を洗礼で授かってしまったから。
一生外へ出られないかもしれない幽閉のような生活を続けるよりも、少年は屋敷を出て行く選択をする。
それでも持ち前の強く非常識なほどの魔力の多さと、負けず嫌いな性格でその困難を乗り越えていく。
そんな少年の物語。

偽物の侯爵子息は平民落ちのうえに国外追放を言い渡されたので自由に生きる。え?帰ってきてくれ?それは無理というもの
つくも茄子
ファンタジー
サビオ・パッツィーニは、魔術師の家系である名門侯爵家の次男に生まれながら魔力鑑定で『魔力無し』の判定を受けてしまう。魔力がない代わりにずば抜けて優れた頭脳を持つサビオに家族は温かく見守っていた。そんなある日、サビオが侯爵家の人間でない事が判明した。妖精の取り換えっ子だと神官は告げる。本物は家族によく似た天使のような美少年。こうしてサビオは「王家と侯爵家を謀った罪人」として国外追放されてしまった。
隣国でギルド登録したサビオは「黒曜」というギルド名で第二の人生を歩んでいく。

魔法が使えない令嬢は住んでいた小屋が燃えたので家出します
怠惰るウェイブ
ファンタジー
グレイの世界は狭く暗く何よりも灰色だった。
本来なら領主令嬢となるはずの彼女は領主邸で住むことを許されず、ボロ小屋で暮らしていた。
彼女はある日、棚から落ちてきた一冊の本によって人生が変わることになる。
世界が色づき始めた頃、ある事件をきっかけに少女は旅をすることにした。
喋ることのできないグレイは旅を通して自身の世界を色付けていく。

幼馴染の勇者が一般人の僕をパーティーに入れようとするんですが
空色蜻蛉
ファンタジー
羊飼いの少年リヒトは、ある事件で勇者になってしまった幼馴染みに巻き込まれ、世界を救う旅へ……ではなく世界一周観光旅行に出発する。
「君達、僕は一般人だって何度言ったら分かるんだ?!
人間外の戦闘に巻き込まないでくれ。
魔王討伐の旅じゃなくて観光旅行なら別に良いけど……え? じゃあ観光旅行で良いって本気?」
どこまでもリヒト優先の幼馴染みと共に、人助けそっちのけで愉快な珍道中が始まる。一行のマスコット家畜メリーさんは巨大化するし、リヒト自身も秘密を抱えているがそれはそれとして。
人生は楽しまないと勿体ない!!
◇空色蜻蛉の作品一覧はhttps://kakuyomu.jp/users/25tonbo/news/1177354054882823862をご覧ください。

勇者パーティを追放された聖女ですが、やっと解放されてむしろ感謝します。なのにパーティの人たちが続々と私に助けを求めてくる件。
八木愛里
ファンタジー
聖女のロザリーは戦闘中でも回復魔法が使用できるが、勇者が見目麗しいソニアを新しい聖女として迎え入れた。ソニアからの入れ知恵で、勇者パーティから『役立たず』と侮辱されて、ついに追放されてしまう。
パーティの人間関係に疲れたロザリーは、ソロ冒険者になることを決意。
攻撃魔法の魔道具を求めて魔道具屋に行ったら、店主から才能を認められる。
ロザリーの実力を知らず愚かにも追放した勇者一行は、これまで攻略できたはずの中級のダンジョンでさえ失敗を繰り返し、仲間割れし破滅へ向かっていく。
一方ロザリーは上級の魔物討伐に成功したり、大魔法使いさまと協力して王女を襲ってきた魔獣を倒したり、国の英雄と呼ばれる存在になっていく。
これは真の実力者であるロザリーが、ソロ冒険者としての地位を確立していきながら、残念ながら追いかけてきた魔法使いや女剣士を「虫が良すぎるわ!」と追っ払い、入り浸っている魔道具屋の店主が実は憧れの大魔法使いさまだが、どうしても本人が気づかない話。
※11話以降から勇者パーティの没落シーンがあります。
※40話に鬱展開あり。苦手な方は読み飛ばし推奨します。
※表紙はAIイラストを使用。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















