お気に入りに追加
15
あなたにおすすめの小説

浅葱色の桜
初音
歴史・時代
新選組の局長、近藤勇がその剣術の腕を磨いた道場・試衛館。
近藤勇は、子宝にめぐまれなかった道場主・周助によって養子に迎えられる…というのが史実ですが、もしその周助に娘がいたら?というIfから始まる物語。
「女のくせに」そんな呪いのような言葉と向き合いながら、剣術の鍛錬に励む主人公・さくらの成長記です。
時代小説の雰囲気を味わっていただくため、縦書読みを推奨しています。縦書きで読みやすいよう、行間を詰めています。
小説家になろう、カクヨム、エブリスタでも載せてます。

降りしきる桜雨は、緋(あけ)の色
冴月希衣@商業BL販売中
歴史・時代
【原田左之助 異聞録】
時は幕末。ところは、江戸。掛川藩の中屋敷で中間(ちゅうげん)として働く十蔵(じゅうぞう)は、務めの傍ら、剣の稽古に励む日々を送っている。
「大切な者を護りたい。護れる者に、なりたい。今まで誰ひとりとして護れたことがない自分だからこそ、その為の“力”が欲しい!」
たったひとり残った家族、異母弟の宗次郎のため、鍛錬を続ける十蔵。その十蔵の前に、同じ後悔を持つ、ひとりの剣士が現れた。
息づく一挙一動に、鮮血の緋色を纏わせた男――。
◆本文、画像の無断転載禁止◆
No reproduction or republication without written permission.

幕末レクイエム―士魂の城よ、散らざる花よ―
馳月基矢
歴史・時代
徳川幕府をやり込めた勢いに乗じ、北進する新政府軍。
新撰組は会津藩と共に、牙を剥く新政府軍を迎え撃つ。
武士の時代、刀の時代は終わりを告げる。
ならば、刀を執る己はどこで滅ぶべきか。
否、ここで滅ぶわけにはいかない。
士魂は花と咲き、決して散らない。
冷徹な戦略眼で時流を見定める新撰組局長、土方歳三。
あやかし狩りの力を持ち、無敵の剣を謳われる斎藤一。
schedule
公開:2019.4.1
連載:2019.4.19-5.1 ( 6:30 & 18:30 )
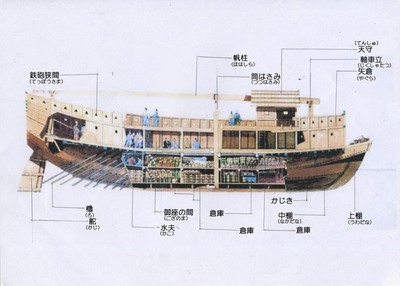

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

戦国を駆ける軍師・山本勘助の嫡男、山本雪之丞
沙羅双樹
歴史・時代
川中島の合戦で亡くなった軍師、山本勘助に嫡男がいた。その男は、山本雪之丞と言い、頭が良く、姿かたちも美しい若者であった。その日、信玄の館を訪れた雪之丞は、上洛の手段を考えている信玄に、「第二啄木鳥の戦法」を提案したのだった……。
この小説はカクヨムに連載中の「武田信玄上洛記」を大幅に加筆訂正したものです。より読みやすく面白く書き直しました。

淡々忠勇
香月しを
歴史・時代
新撰組副長である土方歳三には、斎藤一という部下がいた。
仕事を淡々とこなし、何事も素っ気ない男であるが、実際は土方を尊敬しているし、友情らしきものも感じている。そんな斎藤を、土方もまた信頼し、友情を感じていた。
完結まで、毎日更新いたします!
殺伐としたりほのぼのしたり、怪しげな雰囲気になったりしながら、二人の男が自分の道を歩いていくまでのお話。ほんのりコメディタッチ。
残酷な表現が時々ありますので(お侍さん達の話ですからね)R15をつけさせていただきます。
あッ、二人はあくまでも友情で結ばれておりますよ。友情ね。
★作品の無断転載や引用を禁じます。多言語に変えての転載や引用も許可しません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















