22 / 27
五 土方歳三之章:Blood
血華繚乱(三)
しおりを挟む
奥羽における一連の戦が終息したのは、九月二十四日のことだった。その日、最後まで抵抗の意志を見せていた庄内藩が倒幕派に降伏した。
会津藩の降伏はそれより二日前、九月二十二日だった。仙台藩はさらに四日前の二十日。
以前「容《かた》保《もり》公の首を差し出せ」との要求を突き付けたことのある倒幕派だが、戦後の講和では「相応の地位にある責任者に腹を切らせよ」との条件に落ち着いた。命を以て敗戦の責を負うのは、藩主やその家系に連なる者ではなくてもよい。
会津藩では家老の萱《かや》野《の》権《ごんの》兵《ひょう》衛《え》が腹を切るらしい。中野竹子に従軍を許した男だ。そのほかの年《とし》嵩《かさ》の家老は、すでに戦死したか自害したか追放されたかで、会津に残っていない。
斎藤は生き延びただろうか。盛《もり》之《の》輔《すけ》や健次郎は無事だろうか。鶴ヶ城に籠《こも》った者たちはこれからどうなるのか。
知己の安否もつかめないまま、俺たち新撰組は奥羽の地を離れる。
未練は捨てよう。迷いがあってはならない。吐き捨てるように俺は言う。
「奥羽の戦は、なるようになったというところだな。負けるべくして負けた。会津と奥羽諸藩の劣勢は引っ繰り返しようもなかった」
軍艦の船室で俺と差し向かいに座った男、幕府海軍の副総裁、榎《えの》本《もと》武《たけ》揚《あき》は大《おお》袈《げ》裟《さ》なほど深くうなずいた。
「奥羽諸藩の軍事力じゃあ、洋式の軍制と武器を取り入れた倒幕派には太刀打ちできなかった。一月近くも籠《ろう》城《じょう》した若松はよく耐えたと言いてぇところだが、しかしねえ、どうにもむなしさを覚えちまうな」
「榎本さんは鶴ヶ城にも手紙を送っていたんだろう? 海まで出てきてくれれば、軍を合して蝦《え》夷《ぞ》地《ち》に新しい国を造り、倒幕派を迎え撃てると」
「駄目でもともとの誘いじゃああったがね。会津の武士はいい。忠誠心あふれる、頑固で不屈な会津士魂こそ日本の侍のあるべき姿だ」
「そうだな。会津の武家は、女も子どもも見事な武士だ」
「とまあ、語りゃあ抜群に格好いい会津の武士だが、私じゃ務まらねぇな。どうもあの人たちゃあ難しかねぇかい? あの義理堅さ、嫌いじゃあないんだがねえ」
江戸っ子の榎本さんは、洋装の俺が言うのも何だが、見事なまでの西洋かぶれだ。洋装に短髪はもちろん、口髭まで西洋人のように整えている。着込んだ金ボタンの軍服も、西洋の海軍の士官服を忠実に真似たものらしい。
榎本さんと初めて会ったのは今年の一月、大坂でのことだ。俺より二つ三つ年下と聞いたが、巨大な船を何隻も引き連れた西洋帰りの小《こ》洒落《じゃれ》た男に、俺はひそかに圧倒された。軍艦、大砲、電信。俺が持たないものを、榎本さんはやすやすと使いこなしている。
俺は榎本さんの目を見据えた。
「これから冬が深まれば、蝦夷地は雪に閉ざされて、戦どころじゃなくなる。倒幕派が再び戦を仕掛けてくるのは、来年の夏になるだろう」
「来なくてもいいんだがなあ。宵《よい》越しの喧嘩を次の昼にまたおっ始めるような真似は野暮ってもんだぜ」
「残念ながら、薩摩や長州、土佐くんだりから繰り出してきた連中には、江戸の洒落っ気が通じねえ。俺たちも相手をしてやるしかねぇだろうよ」
「いいねえ、土方さん、その喧嘩っ早そうな顔付き。まあ、そういうこった。冬の間にじっくりと案を練っておこうじゃねぇか。蝦夷地は箱《はこ》館《だて》の五《ご》稜《りょう》郭《かく》が、私ら幕府軍の新たな城だ。来年の夏、西国の田舎侍どもを、ぱあっと盛大に歓待してやろう」
榎本さんは大口を開けて笑った。俺もつられて笑う。
「夏祭の話でもしているみてぇな口振りだ」
「祭でいいだろう。大砲と花火は親戚だ」
「違ぇねえ」
冬十月、榎本さん率いる幕府艦隊と合流した俺たち新撰組は、仙台から石《いしの》巻《まき》を経て、北へ向かう船上にある。
俺はたびたび榎本さんに呼ばれ、私室を訪れる。榎本さんの私室は操舵室に程近く、壁越しにも天井越しにも人の行き交う気配が感じられる。
洋上で過ごすこと数日、俺は船の独特な匂いに辟《へき》易《えき》している。潮の染み入った木と、木の腐敗を防ぐ塗料と、蒸気機関に差す油の混じった匂いだ。甲板の下にある狭苦しい船室は当然ながら窓もなく、船の匂いに人の体や汗の匂いまで混じっていて耐えがたい。
榎本さんの船団を幕府艦隊と呼ぶのは、おそらく正確ではない。榎本さんは、同志二千人ほどを連れて江戸湾の品川港を脱走してきた身の上だ。
脱走しなくては食い扶《ぶ》持《ち》がなかったのだと、榎本さんは言った。
ちょうど一年前の十月、幕府は政権を朝廷に返還した。今年に入って三月には江戸城を明け渡し、慶喜公は駿《すん》府《ぷ》に移り住むこととなった。
慶喜公の駿府移封を受けて困惑したのが、江戸城勤めの幕臣だ。江戸が倒幕派の根城になれば、働き口を失ってしまう。
榎本さんは江戸の幕臣連中に声を掛けた。路頭に迷うくらいなら、いっそ蝦夷地に移り住んで開拓し、新天地を築いてやろうじゃねぇか。
これに賛同した幕臣は二千人。俺たちのように仙台で榎本さんに合流した者を含めると、蝦夷地へ向かう艦隊にはおよそ三千人が乗り組んでいる。アメリカやオランダに発注して造られた軍艦と輸送船は、合わせて九隻。
「つくづく思うが、戦なんてのは綺麗事じゃねぇんだな」
「どうした、土方さん?」
「正義だ理想だ改革だとご大層な旗印を掲げたところで、そんなものは結局、地に足の付かねぇ格好つけに過ぎねぇよ。戦に身を投じる者の九割九分九厘は、戦わなけりゃ居場所や食い扶持がねえってだけさ」
「まったく以てそのとおり。しかし、賽《さい》は投げられた」
「賽? どういう意味だ?」
「大昔、ヨーロッパの戦でそう叫んだ軍人がいたのさ。もう賽は投げられたんだ。丁と出るか半と出るか、賭けに乗らにゃあ仕方がねえ」
「西洋の格言か。その軍人は賭けに勝ったのか?」
「さて、話の細けぇところは忘れちまった。しかしまあ、私らが賭けに負けた日にゃあ、武士なんぞ辞めっちまえばいいのさ。蝦夷地で畑を耕すなり本を読むなり、のんびりして生きりゃあいい。そうだろう?」
なるほどと相槌を打ってみせながら、俺は胸中を静かに凍らせた。悪いが、榎本さん、おまえさんの提案に乗るつもりは一切ない。
俺が武士を辞めるときは、生きることをやめるときだ。
「さて、俺はそろそろお暇《いとま》する」
「そうか。また折を見て、蝦夷地に到着した後のことを話してぇんだが」
「箱館に駐留する倒幕派を追い出すための作戦会議になら応じる。が、国の真似事をして役職を割り振ろうって話には呼ばないでくれ。柄じゃねえ」
「柄だと思うぜ? 土方さんには陸軍の総大将を頼みてぇんだよ。役者も真っ青の男前が肩で風切って陣頭に立ってくれるだけで、全軍の士気が上がるってもんだ」
俺は黙って微笑んで、榎本さんの船室を後にした。
冬の海風は高波の上に荒れ狂い、船はしぶきを蹴散らして進む。大揺れに揺れるぞと脅《おど》されていた割にさほどでもないと感じるのは、俺の肉体が獣じみて常軌を逸したせいだろうか。島田さんたちは船酔いで寝込んでいる。
甲板に立ち、見るともなしに灰色の空を見る。吹き付ける潮風はかすかに甘く、どこか血の味に似ている。
影のようにひっそりと、シジマが俺に寄り添った。
「小《こ》姓《しょう》が歳三を探しておったぞ」
「鉄之助のことか?」
「ああ、そのような名であった。仙台に先行したはよいものの、汝がなかなか連絡を寄越さぬから不安であったと、我をつかまえては同じ話ばかりする」
「鉄之助はまだ十五だ。戦場を連れ歩く気がしなかった。シジマ、おまえさんこそ、この船の上でやることもねぇだろう。鉄之助の暇潰しに付き合ってやってくれ」
「嫌じゃ。汝が構うてやればよい。髪を梳《す》かせるなり髭《ひげ》を剃《そ》らせるなり、あやつに命じれば、何でも喜んで引き受けようぞ」
「気が向いたらな」
俺は首筋に触れた。赤い環はシャツの襟からのぞく位置にくっきりと刻まれ、わずかに熱を帯びている。まるで激しく吸われた痕のように見えると、島田さんは苦笑し、鉄之助は頬を染めた。
環の下で脈が打っている。俺はまだ生きている。それが時折、不思議になる。
多くの人の死を見送ってきた。この手で創り出した死もまた、数え切れない。
「屍《しかばね》の列に俺が連なるのは、来年の春か夏だろう」
「予言か。何を根拠に」
「戦はいずれ終わる。終わっちまった後の手前の姿が一つも思い描けねえ。だから、俺は死ぬんだろう。死ぬしかねぇんだろう」
「汝は商いも得意だと、鉄之助が言うておったが」
「ずいぶん昔、江戸に住んでいたころの話だ。京都で鬼の副長なんぞと呼ばれている間に、愛想笑いもお世辞も口上も忘れちまったよ」
「また覚えればよい。人は、忘れることも覚えることも、捨てることも拾うことも、己の意志ひとつで決せるはず。山の獣にはそれができぬ。山から離れた獣には、捨てた山の暮らしを再び拾うことが叶わぬ」
シジマは金色の目を閉ざし、残影をまとう四本の尾をゆらゆらと振った。
寒空に舞う海鳥が濁った声で鳴き、風に乗って飛び去った。海鳥の行方を仰ぐ俺の目に、結ばず流した黒髪が掛かる。
唐突に、近藤さんの声が脳裏によみがえった。
トシの髪は女よりも綺麗だな。胸も背中もそんなに白いんじゃ、女のほうが恥じ入っちまっただろう。
近藤さんが呆れたような口調でそう言ったのは、いつだったか。正確には覚えていないが、十年近く昔、試衛館の近くの湯屋でのことだ。
まだ幼い顔をした斎藤一や沖田総司はきょとんとした後、もじもじと俺から目を逸《そ》らした。白いと誉められた俺の胸には、前夜に抱いた女に甘噛みされた痕が鮮やかに残っていた。
俺は髪に指を梳《す》き入れた。
「なあ、シジマよ。武士の髪は長いもんだと、俺はずっと思ってきた」
「何じゃ、薮《やぶ》から棒に?」
「髪だけじゃねぇな。武士は刀で戦うべきで鉄砲なんか持ち出さねえ、武士は朱子学を嗜《たしな》むべきで西洋にかぶれちゃならねえ、武士は幕府と朝廷に挺身して外国は打ち払わなけりゃならねえ。武士ってものの絵姿を妙な具合に思い描いて、それを目指してきた」
「我に人の種類だの身分だのはわからぬ」
「俺が思い込んでいた武士の絵姿は、きっと正しくなかった。俺が手に入れてぇと憧れてきたのは、格好や知識や思想なんていう外付けのもんじゃあねえ。ほしかったのは、武士の魂だ。そして武士の魂を抱いて生きるには、さほど多くのものは必要ねぇんだ」
脇差を抜き、左手で髪を括《くく》る。一息に断つ。
ざくり。手応えは意外に強かった。
頭を振ると、軽い。手の中の髪の束を少しだけ名残惜しく感じた。俺は手を開く。荒い潮風が髪をさらう。髪は、またたく間に吹き飛ばされていく。
「消え失せちまえ。未練も弱さも泣き言も全部、今ここで消え失せちまえばいい」
捨てて捨てて捨てて、いらないものは何もかも捨てて、削ぎ落とす。研ぎ澄ます。磨き上げる。ご立派な上っ面など不毛。体裁ばかりの綺麗事に唾《だ》棄《き》して、俺は唯一の覚悟のために生きることを誓う。
武士として戦い、武士として死ぬ。
髪を切って洋装をしても、刀を抜かずに鉄砲や大砲を使っても、禁忌の力の印章を身に刻んでも、体内に武家の血が一滴も流れていなくても、俺は武士の魂の何たるかを知っている。武士の魂をこの身に宿して生きている。
奥羽の陸《おか》の影をたどり、曇天に霞《かす》む南を振り返る。近藤さんの墓がある会津も、かつて住んだ江戸も、生まれ故郷の多摩も、二度と戻ることはないだろう。
今まで出会った人々の顔が、いちどきに脳裏に立ち現れる。一人ひとりの顔を、今は見つめてなどいられない。込み上げかけた情を断ち、熱っぽい息とともに吐き出して、俺は微笑んだ。
「さよなら」
俺は北に向き直った。黒々とした乱雲が行く手の空にある。ひときわ高い波が立て続けに船を襲う。まもなく氷混じりの嵐になるだろう。
船はしかし、まっすぐに進んでいく。
北へ。俺が命を賭《と》して戦うべき最後の地へ。
会津藩の降伏はそれより二日前、九月二十二日だった。仙台藩はさらに四日前の二十日。
以前「容《かた》保《もり》公の首を差し出せ」との要求を突き付けたことのある倒幕派だが、戦後の講和では「相応の地位にある責任者に腹を切らせよ」との条件に落ち着いた。命を以て敗戦の責を負うのは、藩主やその家系に連なる者ではなくてもよい。
会津藩では家老の萱《かや》野《の》権《ごんの》兵《ひょう》衛《え》が腹を切るらしい。中野竹子に従軍を許した男だ。そのほかの年《とし》嵩《かさ》の家老は、すでに戦死したか自害したか追放されたかで、会津に残っていない。
斎藤は生き延びただろうか。盛《もり》之《の》輔《すけ》や健次郎は無事だろうか。鶴ヶ城に籠《こも》った者たちはこれからどうなるのか。
知己の安否もつかめないまま、俺たち新撰組は奥羽の地を離れる。
未練は捨てよう。迷いがあってはならない。吐き捨てるように俺は言う。
「奥羽の戦は、なるようになったというところだな。負けるべくして負けた。会津と奥羽諸藩の劣勢は引っ繰り返しようもなかった」
軍艦の船室で俺と差し向かいに座った男、幕府海軍の副総裁、榎《えの》本《もと》武《たけ》揚《あき》は大《おお》袈《げ》裟《さ》なほど深くうなずいた。
「奥羽諸藩の軍事力じゃあ、洋式の軍制と武器を取り入れた倒幕派には太刀打ちできなかった。一月近くも籠《ろう》城《じょう》した若松はよく耐えたと言いてぇところだが、しかしねえ、どうにもむなしさを覚えちまうな」
「榎本さんは鶴ヶ城にも手紙を送っていたんだろう? 海まで出てきてくれれば、軍を合して蝦《え》夷《ぞ》地《ち》に新しい国を造り、倒幕派を迎え撃てると」
「駄目でもともとの誘いじゃああったがね。会津の武士はいい。忠誠心あふれる、頑固で不屈な会津士魂こそ日本の侍のあるべき姿だ」
「そうだな。会津の武家は、女も子どもも見事な武士だ」
「とまあ、語りゃあ抜群に格好いい会津の武士だが、私じゃ務まらねぇな。どうもあの人たちゃあ難しかねぇかい? あの義理堅さ、嫌いじゃあないんだがねえ」
江戸っ子の榎本さんは、洋装の俺が言うのも何だが、見事なまでの西洋かぶれだ。洋装に短髪はもちろん、口髭まで西洋人のように整えている。着込んだ金ボタンの軍服も、西洋の海軍の士官服を忠実に真似たものらしい。
榎本さんと初めて会ったのは今年の一月、大坂でのことだ。俺より二つ三つ年下と聞いたが、巨大な船を何隻も引き連れた西洋帰りの小《こ》洒落《じゃれ》た男に、俺はひそかに圧倒された。軍艦、大砲、電信。俺が持たないものを、榎本さんはやすやすと使いこなしている。
俺は榎本さんの目を見据えた。
「これから冬が深まれば、蝦夷地は雪に閉ざされて、戦どころじゃなくなる。倒幕派が再び戦を仕掛けてくるのは、来年の夏になるだろう」
「来なくてもいいんだがなあ。宵《よい》越しの喧嘩を次の昼にまたおっ始めるような真似は野暮ってもんだぜ」
「残念ながら、薩摩や長州、土佐くんだりから繰り出してきた連中には、江戸の洒落っ気が通じねえ。俺たちも相手をしてやるしかねぇだろうよ」
「いいねえ、土方さん、その喧嘩っ早そうな顔付き。まあ、そういうこった。冬の間にじっくりと案を練っておこうじゃねぇか。蝦夷地は箱《はこ》館《だて》の五《ご》稜《りょう》郭《かく》が、私ら幕府軍の新たな城だ。来年の夏、西国の田舎侍どもを、ぱあっと盛大に歓待してやろう」
榎本さんは大口を開けて笑った。俺もつられて笑う。
「夏祭の話でもしているみてぇな口振りだ」
「祭でいいだろう。大砲と花火は親戚だ」
「違ぇねえ」
冬十月、榎本さん率いる幕府艦隊と合流した俺たち新撰組は、仙台から石《いしの》巻《まき》を経て、北へ向かう船上にある。
俺はたびたび榎本さんに呼ばれ、私室を訪れる。榎本さんの私室は操舵室に程近く、壁越しにも天井越しにも人の行き交う気配が感じられる。
洋上で過ごすこと数日、俺は船の独特な匂いに辟《へき》易《えき》している。潮の染み入った木と、木の腐敗を防ぐ塗料と、蒸気機関に差す油の混じった匂いだ。甲板の下にある狭苦しい船室は当然ながら窓もなく、船の匂いに人の体や汗の匂いまで混じっていて耐えがたい。
榎本さんの船団を幕府艦隊と呼ぶのは、おそらく正確ではない。榎本さんは、同志二千人ほどを連れて江戸湾の品川港を脱走してきた身の上だ。
脱走しなくては食い扶《ぶ》持《ち》がなかったのだと、榎本さんは言った。
ちょうど一年前の十月、幕府は政権を朝廷に返還した。今年に入って三月には江戸城を明け渡し、慶喜公は駿《すん》府《ぷ》に移り住むこととなった。
慶喜公の駿府移封を受けて困惑したのが、江戸城勤めの幕臣だ。江戸が倒幕派の根城になれば、働き口を失ってしまう。
榎本さんは江戸の幕臣連中に声を掛けた。路頭に迷うくらいなら、いっそ蝦夷地に移り住んで開拓し、新天地を築いてやろうじゃねぇか。
これに賛同した幕臣は二千人。俺たちのように仙台で榎本さんに合流した者を含めると、蝦夷地へ向かう艦隊にはおよそ三千人が乗り組んでいる。アメリカやオランダに発注して造られた軍艦と輸送船は、合わせて九隻。
「つくづく思うが、戦なんてのは綺麗事じゃねぇんだな」
「どうした、土方さん?」
「正義だ理想だ改革だとご大層な旗印を掲げたところで、そんなものは結局、地に足の付かねぇ格好つけに過ぎねぇよ。戦に身を投じる者の九割九分九厘は、戦わなけりゃ居場所や食い扶持がねえってだけさ」
「まったく以てそのとおり。しかし、賽《さい》は投げられた」
「賽? どういう意味だ?」
「大昔、ヨーロッパの戦でそう叫んだ軍人がいたのさ。もう賽は投げられたんだ。丁と出るか半と出るか、賭けに乗らにゃあ仕方がねえ」
「西洋の格言か。その軍人は賭けに勝ったのか?」
「さて、話の細けぇところは忘れちまった。しかしまあ、私らが賭けに負けた日にゃあ、武士なんぞ辞めっちまえばいいのさ。蝦夷地で畑を耕すなり本を読むなり、のんびりして生きりゃあいい。そうだろう?」
なるほどと相槌を打ってみせながら、俺は胸中を静かに凍らせた。悪いが、榎本さん、おまえさんの提案に乗るつもりは一切ない。
俺が武士を辞めるときは、生きることをやめるときだ。
「さて、俺はそろそろお暇《いとま》する」
「そうか。また折を見て、蝦夷地に到着した後のことを話してぇんだが」
「箱館に駐留する倒幕派を追い出すための作戦会議になら応じる。が、国の真似事をして役職を割り振ろうって話には呼ばないでくれ。柄じゃねえ」
「柄だと思うぜ? 土方さんには陸軍の総大将を頼みてぇんだよ。役者も真っ青の男前が肩で風切って陣頭に立ってくれるだけで、全軍の士気が上がるってもんだ」
俺は黙って微笑んで、榎本さんの船室を後にした。
冬の海風は高波の上に荒れ狂い、船はしぶきを蹴散らして進む。大揺れに揺れるぞと脅《おど》されていた割にさほどでもないと感じるのは、俺の肉体が獣じみて常軌を逸したせいだろうか。島田さんたちは船酔いで寝込んでいる。
甲板に立ち、見るともなしに灰色の空を見る。吹き付ける潮風はかすかに甘く、どこか血の味に似ている。
影のようにひっそりと、シジマが俺に寄り添った。
「小《こ》姓《しょう》が歳三を探しておったぞ」
「鉄之助のことか?」
「ああ、そのような名であった。仙台に先行したはよいものの、汝がなかなか連絡を寄越さぬから不安であったと、我をつかまえては同じ話ばかりする」
「鉄之助はまだ十五だ。戦場を連れ歩く気がしなかった。シジマ、おまえさんこそ、この船の上でやることもねぇだろう。鉄之助の暇潰しに付き合ってやってくれ」
「嫌じゃ。汝が構うてやればよい。髪を梳《す》かせるなり髭《ひげ》を剃《そ》らせるなり、あやつに命じれば、何でも喜んで引き受けようぞ」
「気が向いたらな」
俺は首筋に触れた。赤い環はシャツの襟からのぞく位置にくっきりと刻まれ、わずかに熱を帯びている。まるで激しく吸われた痕のように見えると、島田さんは苦笑し、鉄之助は頬を染めた。
環の下で脈が打っている。俺はまだ生きている。それが時折、不思議になる。
多くの人の死を見送ってきた。この手で創り出した死もまた、数え切れない。
「屍《しかばね》の列に俺が連なるのは、来年の春か夏だろう」
「予言か。何を根拠に」
「戦はいずれ終わる。終わっちまった後の手前の姿が一つも思い描けねえ。だから、俺は死ぬんだろう。死ぬしかねぇんだろう」
「汝は商いも得意だと、鉄之助が言うておったが」
「ずいぶん昔、江戸に住んでいたころの話だ。京都で鬼の副長なんぞと呼ばれている間に、愛想笑いもお世辞も口上も忘れちまったよ」
「また覚えればよい。人は、忘れることも覚えることも、捨てることも拾うことも、己の意志ひとつで決せるはず。山の獣にはそれができぬ。山から離れた獣には、捨てた山の暮らしを再び拾うことが叶わぬ」
シジマは金色の目を閉ざし、残影をまとう四本の尾をゆらゆらと振った。
寒空に舞う海鳥が濁った声で鳴き、風に乗って飛び去った。海鳥の行方を仰ぐ俺の目に、結ばず流した黒髪が掛かる。
唐突に、近藤さんの声が脳裏によみがえった。
トシの髪は女よりも綺麗だな。胸も背中もそんなに白いんじゃ、女のほうが恥じ入っちまっただろう。
近藤さんが呆れたような口調でそう言ったのは、いつだったか。正確には覚えていないが、十年近く昔、試衛館の近くの湯屋でのことだ。
まだ幼い顔をした斎藤一や沖田総司はきょとんとした後、もじもじと俺から目を逸《そ》らした。白いと誉められた俺の胸には、前夜に抱いた女に甘噛みされた痕が鮮やかに残っていた。
俺は髪に指を梳《す》き入れた。
「なあ、シジマよ。武士の髪は長いもんだと、俺はずっと思ってきた」
「何じゃ、薮《やぶ》から棒に?」
「髪だけじゃねぇな。武士は刀で戦うべきで鉄砲なんか持ち出さねえ、武士は朱子学を嗜《たしな》むべきで西洋にかぶれちゃならねえ、武士は幕府と朝廷に挺身して外国は打ち払わなけりゃならねえ。武士ってものの絵姿を妙な具合に思い描いて、それを目指してきた」
「我に人の種類だの身分だのはわからぬ」
「俺が思い込んでいた武士の絵姿は、きっと正しくなかった。俺が手に入れてぇと憧れてきたのは、格好や知識や思想なんていう外付けのもんじゃあねえ。ほしかったのは、武士の魂だ。そして武士の魂を抱いて生きるには、さほど多くのものは必要ねぇんだ」
脇差を抜き、左手で髪を括《くく》る。一息に断つ。
ざくり。手応えは意外に強かった。
頭を振ると、軽い。手の中の髪の束を少しだけ名残惜しく感じた。俺は手を開く。荒い潮風が髪をさらう。髪は、またたく間に吹き飛ばされていく。
「消え失せちまえ。未練も弱さも泣き言も全部、今ここで消え失せちまえばいい」
捨てて捨てて捨てて、いらないものは何もかも捨てて、削ぎ落とす。研ぎ澄ます。磨き上げる。ご立派な上っ面など不毛。体裁ばかりの綺麗事に唾《だ》棄《き》して、俺は唯一の覚悟のために生きることを誓う。
武士として戦い、武士として死ぬ。
髪を切って洋装をしても、刀を抜かずに鉄砲や大砲を使っても、禁忌の力の印章を身に刻んでも、体内に武家の血が一滴も流れていなくても、俺は武士の魂の何たるかを知っている。武士の魂をこの身に宿して生きている。
奥羽の陸《おか》の影をたどり、曇天に霞《かす》む南を振り返る。近藤さんの墓がある会津も、かつて住んだ江戸も、生まれ故郷の多摩も、二度と戻ることはないだろう。
今まで出会った人々の顔が、いちどきに脳裏に立ち現れる。一人ひとりの顔を、今は見つめてなどいられない。込み上げかけた情を断ち、熱っぽい息とともに吐き出して、俺は微笑んだ。
「さよなら」
俺は北に向き直った。黒々とした乱雲が行く手の空にある。ひときわ高い波が立て続けに船を襲う。まもなく氷混じりの嵐になるだろう。
船はしかし、まっすぐに進んでいく。
北へ。俺が命を賭《と》して戦うべき最後の地へ。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

幕末レクイエム―誠心誠意、咲きて散れ―
馳月基矢
歴史・時代
幕末、動乱の京都の治安維持を担った新撰組。
華やかな活躍の時間は、決して長くなかった。
武士の世の終わりは刻々と迫る。
それでもなお刀を手にし続ける。
これは滅びの武士の生き様。
誠心誠意、ただまっすぐに。
結核を病み、あやかしの力を借りる天才剣士、沖田総司。
あやかし狩りの力を持ち、目的を秘めるスパイ、斎藤一。
同い年に生まれた二人の、別々の道。
仇花よ、あでやかに咲き、潔く散れ。
schedule
公開:2019.4.1
連載:2019.4.7-4.18 ( 6:30 & 18:30 )

柳鼓の塩小町 江戸深川のしょうけら退治
月芝
歴史・時代
花のお江戸は本所深川、その隅っこにある柳鼓長屋。
なんでも奥にある柳を蹴飛ばせばポンっと鳴くらしい。
そんな長屋の差配の孫娘お七。
なんの因果か、お七は産まれながらに怪異の類にめっぽう強かった。
徳を積んだお坊さまや、修験者らが加持祈祷をして追い払うようなモノどもを相手にし、
「えいや」と塩を投げるだけで悪霊退散。
ゆえについたあだ名が柳鼓の塩小町。
ひと癖もふた癖もある長屋の住人たちと塩小町が織りなす、ちょっと不思議で愉快なお江戸奇譚。

商い幼女と猫侍
和紗かをる
歴史・時代
黒船来航から少しの時代。動物狂いでお家断絶になった侍、渡会正嗣と伊勢屋の次女ふたみはあるきっかけから協力して犬、猫、鶏と一緒になって世を守る。世直しドタバタ活劇。綺羅星の様な偉人ひしめく幕末の日本で、二人がひっそりと織り成す物語です。

残影の艦隊~蝦夷共和国の理想と銀の道
谷鋭二
歴史・時代
この物語の舞台は主に幕末・維新の頃の日本です。物語の主人公榎本武揚は、幕末動乱のさなかにはるばるオランダに渡り、最高の技術、最高のスキル、最高の知識を手にいれ日本に戻ってきます。
しかし榎本がオランダにいる間に幕府の権威は完全に失墜し、やがて大政奉還、鳥羽・伏見の戦いをへて幕府は瓦解します。自然幕臣榎本武揚は行き場を失い、未来は絶望的となります。
榎本は新たな己の居場所を蝦夷(北海道)に見出し、同じく行き場を失った多くの幕臣とともに、蝦夷を開拓し新たなフロンティアを築くという壮大な夢を描きます。しかしやがてはその蝦夷にも薩長の魔の手がのびてくるわけです。
この物語では榎本武揚なる人物が最北に地にいかなる夢を見たか追いかけると同時に、世に言う箱館戦争の後、罪を許された榎本のその後の人生にも光を当ててみたいと思っている次第であります。

鎌倉最後の日
もず りょう
歴史・時代
かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

北武の寅 <幕末さいたま志士伝>
海野 次朗
歴史・時代
タイトルは『北武の寅』(ほくぶのとら)と読みます。
幕末の埼玉人にスポットをあてた作品です。主人公は熊谷北郊出身の吉田寅之助という青年です。他に渋沢栄一(尾高兄弟含む)、根岸友山、清水卯三郎、斎藤健次郎などが登場します。さらにベルギー系フランス人のモンブランやフランスお政、五代才助(友厚)、松木弘安(寺島宗則)、伊藤俊輔(博文)なども登場します。
根岸友山が出る関係から新選組や清河八郎の話もあります。また、渋沢栄一やモンブランが出る関係からパリ万博などパリを舞台とした場面が何回かあります。
前作の『伊藤とサトウ』と違って今作は史実重視というよりも、より「小説」に近い形になっているはずです。ただしキャラクターや時代背景はかなり重複しております。『伊藤とサトウ』でやれなかった事件を深掘りしているつもりですので、その点はご了承ください。
(※この作品は「NOVEL DAYS」「小説家になろう」「カクヨム」にも転載してます)
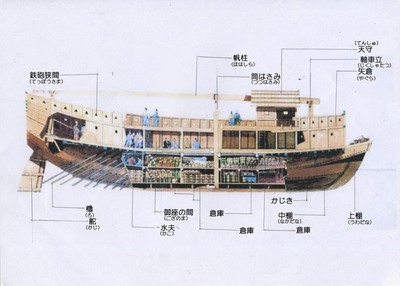

浅葱色の桜 ―堀川通花屋町下ル
初音
歴史・時代
新選組内外の諜報活動を行う諸士調役兼監察。その頭をつとめるのは、隊内唯一の女隊士だった。
義弟の近藤勇らと上洛して早2年。主人公・さくらの活躍はまだまだ続く……!
『浅葱色の桜』https://www.alphapolis.co.jp/novel/32482980/787215527
の続編となりますが、前作を読んでいなくても大丈夫な作りにはしています。前作未読の方もぜひ。
※時代小説の雰囲気を味わっていただくため、縦組みを推奨しています。行間を詰めてありますので横組みだと読みづらいかもしれませんが、ご了承ください。
※あくまでフィクションです。実際の人物、事件には関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















