17 / 27
四 斎藤一之章:My heart
誠義(三)
しおりを挟む
山川さんと彼岸獅子の大手柄に、鶴ヶ城は士気が高い。
前藩主の容《かた》保《もり》公と今の藩主の喜《のぶ》徳《のり》公が直々に、山川さんと小松村の獅子団を誉め称《たた》え、城に集う者たちをねぎらった。酒も振る舞われて、今夜は宴だ。暗い顔をしていたという皆が、楽しそうに笑っている。
オレは宴に加わらなかった。会津の武家は結束が固い。そこへ割り込むのは気が引ける。オレは当てもなく城内をぶらぶらした。
鶴ヶ城ほどの大きな城郭に足を踏み入れたのは、会津に来てからが初めてだった。四月の終わりだ。前回は、鉄《くろがね》門を入ってすぐの大広間で容保公に謁《えっ》見《けん》した。
堀と城壁と土塁、郭《くるわ》とそこに植えられた木々の内側には、上品な造りの建物が複雑な形で連なっている。藩主とその家族が暮らす屋敷だ。今は多くの場所が、籠《ろう》城《じょう》する者たちのために開放されている。
城内の人数、今日でおよそ三千人。藩境の戦から戻った藩士が毎日続々と、どうにかして入城を果たしている。これからさらに増えるだろう。
新撰組は、最も大きくなったときでも三百人に届かなかった。その十倍を超す人数が今、鶴ヶ城に籠っている。一体、一日に何斗の米が必要なんだろう? いや、何石《こく》かに上るんだろうか?
数の勘定は土方さんの十八番だった。オレも少しくらいは算盤《そろばん》の弾き方を教わっておけばよかったかもしれない。
秋の夜風を受けながら、土塁に登ってみる。土塁の上は要所に見張りが立って、堀の向こうの敵陣をうかがっている。
城を包囲する明かりの数は、やはり多い。敵に乗っ取られた屋敷や寺がある。焼け跡の上にも宿営が造られている。耳を澄ませば、かすかに聞こえる唄、野犬の遠吠え、秋の虫の音、堀で魚が跳ねる水音。
不意に、女の足音が夜の気配に交じる。オレは土塁の下を見やった。白河で会った女、弥《や》曽《そ》がいた。
「山口さま、お探ししました。やっと見付けたなし」
「何か用か?」
「はい。山口さまが今夜のうちにもお城を離れてしまわれるとうかがったので、何としてもお話ししてぇと思ったのです。山口さまが出陣なさっている間、ずっと、お会いしとうごぜぇました」
「あんたは無事だったんだな」
「わたくしはこのとおり、怪我ひとつごぜぇません。ご心配いただき、嬉しゅう存じます。そっつぁ行ってもよろしいかし?」
土塁にしつらえられた石段は、女が登るには急だろう。裾《すそ》が割れて脚がのぞくさまを思い描いて、オレは舌打ちした。今こんな場所で見たいものでもない。
オレは石段を跳び下りた。
「話なら、手短に済ませろ」
篝《かがり》火《び》が弥曽に光と影を投げ掛けている。夜陰の似合う女だ。深い色の襟元からのぞく肌が、ぞっとするほど白い。
「山口さまは男の中の男だと、お城のあちこちで耳にいたします。会津のために戻ってきてくださって、ありがとうごぜぇます。山口さまがお殿さまの前で、会津を思うお心を説いておられるのを聞いたときは、わたくし、胸がいっぱいになっつまいました」
「人に誉められる義のある男かどうか、わかったもんじゃない。新撰組の法《はっ》度《と》を犯しちまった。オレは、情を取って仲間を捨てた」
「そだにご自分を責めねぇでくなんしょ。悩んでしまわれるお気持ちもわかるけんじょ、時は巻き戻らねぇべし。どうぞ後悔などなさらぬよう」
「わかっている」
「差し出がましくて申し訳ありません。山口さま、少し、わたくしの身の上話を聞いていただけねぇかし?」
「身の上話?」
弥曽の濡れたような目が、じっとオレを見つめている。
「わたくしの父が先日、死にました。かねてから病み付いておりましたけんじょ、城下に敵が侵入するに至って、足手まといにはなりたくねぇと申しまして、わたくしに脇差を手渡しました。わたくしは、この手で、父の胸を突きました」
オレは息を呑んだ。弥曽は静かに微笑んでいる。いや、微笑んだように見えるだけで、本当はひどく虚《うつ》ろだ。
「それは、気の毒だった。自ら死を選んだ者が多かったようだな。その……申し訳ない」
「なぜ山口さまが謝られるのです? 敵を防げねかったからかし? おやめくなんしょ。山口さまたちが奮戦なさったことも、何《な》如《じょ》しようもねかったことも、わたくしはよくわかっております」
罵《ののし》られるほうが気楽だった。負けは負けだ。
オレは戦うことしか能がないのに、務めを果たせなかった。伏見の戦に始まって、勝沼、宇都宮、白河、棚倉、母成峠、十六橋、戸の口原。全部負けた。次こそ勝たねばと焦りながら勝てず、会津は戦火に呑まれた。
「戦に出る武士が死ぬなら仕方ない。覚悟の上だ。でも、若松では、戦う力のない者がたくさん死んだ。戦えないからと、死んでいった。それが苦しい」
「お優しいのですね」
「オレが?」
「ご自分ではおわかりになんねぇかし? 素っ気ねぇようで本当はお優しくて、お強くて見目も優れておられる。山口さまはきっと女《おな》子《ご》にお持てになんべし。罪なお人」
「は?」
「奥方さまはおられねぇとうかがいましたけんじょ、契《ちぎ》った仲の女子もいらっしゃらねぇのかし? ご自分の血を引く子《やや》を作らねばとお思いにはなりません?」
弥曽の話は唐突に過ぎた。オレが答えられずにいると、弥曽はひっそりとした声で笑った。湿った吐息が、耳を甘く引っ掻く。
「嫌《やん》だ、たまげたお顔などなさって。二十五にもおなりの立派な武士ですのに、可愛《めげ》ごどなあ。なんてずるい。山口さまのもっといろんなお顔を知りとうなります。笑ったお顔を見てみとうごぜぇます。この弥曽に笑い掛けてはいただけねぇかし?」
ずけずけと踏み入るな、と言いたかった。武家の女はもっと堅苦しい礼儀を叩き込まれているものじゃないのか? それがまるで岡場所の女のように、軽々しく男を誉めて懐《ふところ》に入り込もうとする。
いっそのこと品性がまるでないのなら、見下してしまえる。でも、オレの前に立つ女は楚々として、それがかえって色っぽい。怖いほどに。
息苦しさを覚えた。心臓の音が高く速い。オレは弥曽から顔を背けた。
「無駄話をしたいなら、よそを当たれ」
立ち去ろうと足を踏み出すと、思い掛けない素早さで袖をつかまれた。とっさに振りほどいて跳びのく。背中が古木の幹に触れた。
「よそには参れません。山口さまでねくては何の意味もねぇのです。お願ぇがごぜぇます。わたくしを山口さまと一緒にお連れくなんしょ。どこなりともお供いたします」
「馬鹿なことを。城を出れば戦場だ」
「お城に籠っていても、戦場であることに違いはねぇべし」
「城の外は桁違いに危険だと言っている」
「構いません。山口さまのおそばで死ねるのなら、弥曽は本望でごぜぇます」
「あんたを連れていって何の役に立つってんだ?」
「武芸も所詮は女《おな》子《ご》の腕、鉄砲も環の力も持たねぇ身には違ぇありません。けんじょも、山口さま、女子の体は山口さまにとって本当に何のお役にも立てねぇかし?」
ぞくりとした。体の奥で騒ぎ立てるものがある。
弥曽がオレに近付く。剣の間合いよりずっと近く、さらに一歩迫られて、柔術の間合いよりも近くなる。
古木の枝が垂れ込めて暗い。夜に慣れた目は、濡れてきらめく弥曽のまなざしに縫い止められた。酔い痴れそうだった。
弥曽の手がオレの胸に触れた。
「やめろ」
声が喉に絡んで震える。心臓のありかを探るように、弥曽の手がオレの胸を這う。
「女《おな》子《ご》はお嫌いですか?」
「違う」
「年増はお嫌い? わたくしは来年には三十の大年増ですもの」
「違う、そういうんじゃない」
「篠田の娘は年増盛りの売れ残り、手弱女《たおやめ》ぶった疫病神だと、わたくし、陰で笑われているのです。仕方ねぇべし。十年近くも前、父が嫁げと命じた相手は江戸の蘭学塾で抗争に巻き込まれて死に、次に縁談のあった相手は京都守護に赴《おもむ》いて撃ち殺されました」
「相手の男が死んだのは、あんたのせいってわけじゃないだろう」
譫《うわ》言《ごと》のようにつぶやく。頭の芯が痺れている。
弥曽が、香り立ちそうな笑声をこぼした。
「山口さまは、やはりお優しゅうごぜぇます。けんじょも、わたくし、もう何を言われても構わねぇのです。嫁ぐが武家の女の仕事でも、最早、嫁がずともいい。好いたお人に一度でも添うことができれば、この身など滅びっつまって構わね」
弥曽の手がオレの心臓の上にある。弥曽が刺客なら、オレはあっさり殺されている。
容《かた》保《もり》公の居所、この鶴ヶ城で場違いな真似は許されない。なけなしの矜《きょう》持《じ》がオレをつなぎ止めている。女を突き放せ、と頭は体に命じようとする。体は拒む。女に触れたら最後、きっと呑まれてしまう、と。
指一本動かせないまま、オレは、せめてもの賢《さか》しら口をひねり出した。
「馬鹿なことを言うのはよせ。家名に泥を塗るな」
「父は死にました。藩境の戦に出陣した兄弟の行方も知れません。女《おな》子《ご》のわたくしが一人残され、会津の命運とて明日をも知らねぇのです。この期《ご》に及んで篠田の家名など、何の価値もごぜぇません。ここにあるのは、ただ空っぽな女子の体だけ」
弥曽が、倒れ込むようにオレの胸に身を寄せた。着物越しに柔らかさを感じた。髪からも肌からも女の匂いがした。
喘《あえ》ぐように、弥曽は声を立てずに泣き出した。ひそやかな息遣いがオレの体を内側から引っ掻き回す。離れろと、オレはささやいた。嫌だと、弥曽は駄々をこねた。
「山口さま、弥曽をさらって、どこなりともお捨てくなんしょ。会津の武家であることが、弥曽のただ一つの誇りでした。戦にすべてを奪われました。誇りをなくした武家は魂をなくしたのも同じ。この体もまた、消えっつまえばいいのです」
「ならば、なぜ城に入った?」
「山口さまに、最後に一目お会いしとうごぜぇました。お会いできると信じておりました。山口さまに情けをかけていただきてぇのです。どうか弥曽をお救いくなんしょ。弥曽は、武家の生き方しか知らねぇ愚かな女《おな》子《ご》です。弥曽はこれから何《な》如《じょ》すんべし?」
殺せと言うのか。抱けと言うのか。両方望むのか。望まれて、オレが拒むとでも勘違いしているのか。
「オレを誰だと思ってる? あんたの目には何も見えてやしない」
女を殺したことはない。けれどきっとできる。女が死にたくなるほどの残酷な抱き方だってできる。京都で忌み嫌われた壬《み》生《ぶ》狼《ろ》の中で最も多く人を殺したのも欺《あざむ》いたのも、このオレ、斎藤一だ。
「ならば、本当のあなたさまを見てみとうごぜぇます。おっかねぇお姿になっつまってくなんしょ。おっかなければおっかねぇほど、きっとお美しくもなられるべし。弥曽は、見てみとうごぜぇます」
馬鹿言え。おっかないのは、より気味の悪い化け物は、あんたのほうだ。
その白い首筋を噛み裂いてしまいたい。生かすも殺すもオレ次第なら、本当に道具として扱ってやろうか。生きていることを後悔するまでめちゃくちゃにしてみようか。敵の陣中に投げ込んで囮《おとり》に使ってもいい。
欲に抗《あらが》えない。いっそここで食ってしまおうと思った。オレは弥曽の着物に手を掛けようと、腕を持ち上げる。
そのとき初めて、見られていることに気が付いた。聞かれていたことに気が付いた。そこにいるのが誰なのか気が付いた。
「時尾……」
弥曽が、びくりと顔を上げて振り向いた。
「嫌《やん》だ、時尾さん?」
時尾が踵《きびす》を返して駆け出した。
冷水を浴びせられた心地だった。オレは弥曽の体を押しのけた。頭が混乱している。今、オレは何をしようとしていた?
「待って、山口さま」
「悪い」
オレは弥曽を振り払って、時尾を追った。女の脚に追い付くのはすぐだった。肩をつかむと、時尾は身をよじって逃れた。
肩で息をする時尾は、苦しげに胸を押さえて眉をしかめた。
「やっぱり斎藤さまだった。お邪魔しっつまって申し訳ありません」
「邪魔も何も、勘違いだ」
「なぜわたしを追ってきたがよ? いつも笑っている弥曽さんがつれぇ思いをしているなんて誰《だっちぇ》もわかんねかった。弥曽さんは斎藤さまだけに胸の内を打ち明けたのです。戻ってあげてくなんしょ」
「勘違いだと言っているだろう。オレはあの女と言い交わしたわけじゃない」
「胸を貸していたべし? お似合いだと思いました。夫婦《めおと》のようなお姿だと」
「そんなんじゃない」
「嘘をつかねぇでくなんしょ! わたしは、人が強ぇ思いを抱けばわかるんだ。斎藤さまは弥曽さんに惚れっつまったんだべし。無理もねえ。弥曽さんみてぇに綺麗な人から慕われたら、可愛《めげ》ぇと思うのも当たり前だなし」
「違う……違うんだ、本当に」
時尾は泣き笑いの顔をした。
「斎藤さま、そだに泣きそうな目をされると、わたしは何《な》如《じょ》していいか、わかんねくなります」
「オレのほうがわからない。勝手なことを次々と言われて」
「勝手ですか? 斎藤さまはわたしに気が付かねぇくらい、弥曽さんに夢中だったではねぇですか」
返事に迷う。正直に告げるしかないと思った。
「惑わされたのは本当だ。気がどうにかなっちまいそうだった。馬鹿だな、オレは」
時尾から目を背けてしまいたかった。でも、オレは敢《あ》えて時尾を見つめ続けた。
胸が痛いような気がした。痛みが心地よかった。痛みの正体を探るのはやめた。心臓が穏やかに高鳴った。
時尾はゆっくりとまばたきをして、丁寧に頭を下げた。
「いろいろと失礼を申しました。お許しくなんしょ。弥曽さんにも後で謝ります」
「オレこそ、悪かった。嫌な思いをさせた」
「嫌な思いではねぇけんじょ、ただ……」
黙り込むと、城内の宴で男の声が唄を歌うのが聞こえた。京都で耳にした、他愛ない色恋の唄だ。一人の男と二人の女。ふらふらと揺れてばかりの男を想って、女は袖を噛む。
まるで唄に冷やかされるようで、かっと頬が熱を持った。時尾も同じことを思ったのか、口元を手で覆った。遠くの篝《かがり》火《び》の光がようやく届く暗がりでは、顔色はうかがえない。
知らぬふりを決め込むことにした。
「皆のところに戻らないのか?」
声がうわずってしまった。応える時尾も似たようなものだった。ぱたぱたと上前を整える仕草がぎこちない。
「んだなし。戻らねば、八重さんたちに心配させっつま。斎藤さま、わたし、これで失礼します」
お辞儀をして、時尾は足早に立ち去ろうとした。冷えた夜風が渡った。次はいつ会えるだろうかと、急に不安が胸に差した。
「時尾!」
声を上げた後で息を呑む。初めて名を呼んでしまった。せめて「時尾どの」と呼ぶべきだった。
振り返った時尾は目を見張っている。
「はい。何だべし?」
「その……鳩に手紙を持たせる。何でもいい、書くことは何でもいいから、知らせてほしい。城には、たぶんオレは、しばらく戻らないが……無事を、祈っている。だから、手紙を」
ちぐはぐで尻切れ蜻蛉《とんぼ》。伝えたいこともろくに伝えられず、不甲斐なさに舌打ちしたくなる。
時尾は微笑んだ。暗がりをも照らすような、ぱっと明るい笑顔だった。
「お手紙、書きます。斎藤さまも、どうぞお気を付けて」
前藩主の容《かた》保《もり》公と今の藩主の喜《のぶ》徳《のり》公が直々に、山川さんと小松村の獅子団を誉め称《たた》え、城に集う者たちをねぎらった。酒も振る舞われて、今夜は宴だ。暗い顔をしていたという皆が、楽しそうに笑っている。
オレは宴に加わらなかった。会津の武家は結束が固い。そこへ割り込むのは気が引ける。オレは当てもなく城内をぶらぶらした。
鶴ヶ城ほどの大きな城郭に足を踏み入れたのは、会津に来てからが初めてだった。四月の終わりだ。前回は、鉄《くろがね》門を入ってすぐの大広間で容保公に謁《えっ》見《けん》した。
堀と城壁と土塁、郭《くるわ》とそこに植えられた木々の内側には、上品な造りの建物が複雑な形で連なっている。藩主とその家族が暮らす屋敷だ。今は多くの場所が、籠《ろう》城《じょう》する者たちのために開放されている。
城内の人数、今日でおよそ三千人。藩境の戦から戻った藩士が毎日続々と、どうにかして入城を果たしている。これからさらに増えるだろう。
新撰組は、最も大きくなったときでも三百人に届かなかった。その十倍を超す人数が今、鶴ヶ城に籠っている。一体、一日に何斗の米が必要なんだろう? いや、何石《こく》かに上るんだろうか?
数の勘定は土方さんの十八番だった。オレも少しくらいは算盤《そろばん》の弾き方を教わっておけばよかったかもしれない。
秋の夜風を受けながら、土塁に登ってみる。土塁の上は要所に見張りが立って、堀の向こうの敵陣をうかがっている。
城を包囲する明かりの数は、やはり多い。敵に乗っ取られた屋敷や寺がある。焼け跡の上にも宿営が造られている。耳を澄ませば、かすかに聞こえる唄、野犬の遠吠え、秋の虫の音、堀で魚が跳ねる水音。
不意に、女の足音が夜の気配に交じる。オレは土塁の下を見やった。白河で会った女、弥《や》曽《そ》がいた。
「山口さま、お探ししました。やっと見付けたなし」
「何か用か?」
「はい。山口さまが今夜のうちにもお城を離れてしまわれるとうかがったので、何としてもお話ししてぇと思ったのです。山口さまが出陣なさっている間、ずっと、お会いしとうごぜぇました」
「あんたは無事だったんだな」
「わたくしはこのとおり、怪我ひとつごぜぇません。ご心配いただき、嬉しゅう存じます。そっつぁ行ってもよろしいかし?」
土塁にしつらえられた石段は、女が登るには急だろう。裾《すそ》が割れて脚がのぞくさまを思い描いて、オレは舌打ちした。今こんな場所で見たいものでもない。
オレは石段を跳び下りた。
「話なら、手短に済ませろ」
篝《かがり》火《び》が弥曽に光と影を投げ掛けている。夜陰の似合う女だ。深い色の襟元からのぞく肌が、ぞっとするほど白い。
「山口さまは男の中の男だと、お城のあちこちで耳にいたします。会津のために戻ってきてくださって、ありがとうごぜぇます。山口さまがお殿さまの前で、会津を思うお心を説いておられるのを聞いたときは、わたくし、胸がいっぱいになっつまいました」
「人に誉められる義のある男かどうか、わかったもんじゃない。新撰組の法《はっ》度《と》を犯しちまった。オレは、情を取って仲間を捨てた」
「そだにご自分を責めねぇでくなんしょ。悩んでしまわれるお気持ちもわかるけんじょ、時は巻き戻らねぇべし。どうぞ後悔などなさらぬよう」
「わかっている」
「差し出がましくて申し訳ありません。山口さま、少し、わたくしの身の上話を聞いていただけねぇかし?」
「身の上話?」
弥曽の濡れたような目が、じっとオレを見つめている。
「わたくしの父が先日、死にました。かねてから病み付いておりましたけんじょ、城下に敵が侵入するに至って、足手まといにはなりたくねぇと申しまして、わたくしに脇差を手渡しました。わたくしは、この手で、父の胸を突きました」
オレは息を呑んだ。弥曽は静かに微笑んでいる。いや、微笑んだように見えるだけで、本当はひどく虚《うつ》ろだ。
「それは、気の毒だった。自ら死を選んだ者が多かったようだな。その……申し訳ない」
「なぜ山口さまが謝られるのです? 敵を防げねかったからかし? おやめくなんしょ。山口さまたちが奮戦なさったことも、何《な》如《じょ》しようもねかったことも、わたくしはよくわかっております」
罵《ののし》られるほうが気楽だった。負けは負けだ。
オレは戦うことしか能がないのに、務めを果たせなかった。伏見の戦に始まって、勝沼、宇都宮、白河、棚倉、母成峠、十六橋、戸の口原。全部負けた。次こそ勝たねばと焦りながら勝てず、会津は戦火に呑まれた。
「戦に出る武士が死ぬなら仕方ない。覚悟の上だ。でも、若松では、戦う力のない者がたくさん死んだ。戦えないからと、死んでいった。それが苦しい」
「お優しいのですね」
「オレが?」
「ご自分ではおわかりになんねぇかし? 素っ気ねぇようで本当はお優しくて、お強くて見目も優れておられる。山口さまはきっと女《おな》子《ご》にお持てになんべし。罪なお人」
「は?」
「奥方さまはおられねぇとうかがいましたけんじょ、契《ちぎ》った仲の女子もいらっしゃらねぇのかし? ご自分の血を引く子《やや》を作らねばとお思いにはなりません?」
弥曽の話は唐突に過ぎた。オレが答えられずにいると、弥曽はひっそりとした声で笑った。湿った吐息が、耳を甘く引っ掻く。
「嫌《やん》だ、たまげたお顔などなさって。二十五にもおなりの立派な武士ですのに、可愛《めげ》ごどなあ。なんてずるい。山口さまのもっといろんなお顔を知りとうなります。笑ったお顔を見てみとうごぜぇます。この弥曽に笑い掛けてはいただけねぇかし?」
ずけずけと踏み入るな、と言いたかった。武家の女はもっと堅苦しい礼儀を叩き込まれているものじゃないのか? それがまるで岡場所の女のように、軽々しく男を誉めて懐《ふところ》に入り込もうとする。
いっそのこと品性がまるでないのなら、見下してしまえる。でも、オレの前に立つ女は楚々として、それがかえって色っぽい。怖いほどに。
息苦しさを覚えた。心臓の音が高く速い。オレは弥曽から顔を背けた。
「無駄話をしたいなら、よそを当たれ」
立ち去ろうと足を踏み出すと、思い掛けない素早さで袖をつかまれた。とっさに振りほどいて跳びのく。背中が古木の幹に触れた。
「よそには参れません。山口さまでねくては何の意味もねぇのです。お願ぇがごぜぇます。わたくしを山口さまと一緒にお連れくなんしょ。どこなりともお供いたします」
「馬鹿なことを。城を出れば戦場だ」
「お城に籠っていても、戦場であることに違いはねぇべし」
「城の外は桁違いに危険だと言っている」
「構いません。山口さまのおそばで死ねるのなら、弥曽は本望でごぜぇます」
「あんたを連れていって何の役に立つってんだ?」
「武芸も所詮は女《おな》子《ご》の腕、鉄砲も環の力も持たねぇ身には違ぇありません。けんじょも、山口さま、女子の体は山口さまにとって本当に何のお役にも立てねぇかし?」
ぞくりとした。体の奥で騒ぎ立てるものがある。
弥曽がオレに近付く。剣の間合いよりずっと近く、さらに一歩迫られて、柔術の間合いよりも近くなる。
古木の枝が垂れ込めて暗い。夜に慣れた目は、濡れてきらめく弥曽のまなざしに縫い止められた。酔い痴れそうだった。
弥曽の手がオレの胸に触れた。
「やめろ」
声が喉に絡んで震える。心臓のありかを探るように、弥曽の手がオレの胸を這う。
「女《おな》子《ご》はお嫌いですか?」
「違う」
「年増はお嫌い? わたくしは来年には三十の大年増ですもの」
「違う、そういうんじゃない」
「篠田の娘は年増盛りの売れ残り、手弱女《たおやめ》ぶった疫病神だと、わたくし、陰で笑われているのです。仕方ねぇべし。十年近くも前、父が嫁げと命じた相手は江戸の蘭学塾で抗争に巻き込まれて死に、次に縁談のあった相手は京都守護に赴《おもむ》いて撃ち殺されました」
「相手の男が死んだのは、あんたのせいってわけじゃないだろう」
譫《うわ》言《ごと》のようにつぶやく。頭の芯が痺れている。
弥曽が、香り立ちそうな笑声をこぼした。
「山口さまは、やはりお優しゅうごぜぇます。けんじょも、わたくし、もう何を言われても構わねぇのです。嫁ぐが武家の女の仕事でも、最早、嫁がずともいい。好いたお人に一度でも添うことができれば、この身など滅びっつまって構わね」
弥曽の手がオレの心臓の上にある。弥曽が刺客なら、オレはあっさり殺されている。
容《かた》保《もり》公の居所、この鶴ヶ城で場違いな真似は許されない。なけなしの矜《きょう》持《じ》がオレをつなぎ止めている。女を突き放せ、と頭は体に命じようとする。体は拒む。女に触れたら最後、きっと呑まれてしまう、と。
指一本動かせないまま、オレは、せめてもの賢《さか》しら口をひねり出した。
「馬鹿なことを言うのはよせ。家名に泥を塗るな」
「父は死にました。藩境の戦に出陣した兄弟の行方も知れません。女《おな》子《ご》のわたくしが一人残され、会津の命運とて明日をも知らねぇのです。この期《ご》に及んで篠田の家名など、何の価値もごぜぇません。ここにあるのは、ただ空っぽな女子の体だけ」
弥曽が、倒れ込むようにオレの胸に身を寄せた。着物越しに柔らかさを感じた。髪からも肌からも女の匂いがした。
喘《あえ》ぐように、弥曽は声を立てずに泣き出した。ひそやかな息遣いがオレの体を内側から引っ掻き回す。離れろと、オレはささやいた。嫌だと、弥曽は駄々をこねた。
「山口さま、弥曽をさらって、どこなりともお捨てくなんしょ。会津の武家であることが、弥曽のただ一つの誇りでした。戦にすべてを奪われました。誇りをなくした武家は魂をなくしたのも同じ。この体もまた、消えっつまえばいいのです」
「ならば、なぜ城に入った?」
「山口さまに、最後に一目お会いしとうごぜぇました。お会いできると信じておりました。山口さまに情けをかけていただきてぇのです。どうか弥曽をお救いくなんしょ。弥曽は、武家の生き方しか知らねぇ愚かな女《おな》子《ご》です。弥曽はこれから何《な》如《じょ》すんべし?」
殺せと言うのか。抱けと言うのか。両方望むのか。望まれて、オレが拒むとでも勘違いしているのか。
「オレを誰だと思ってる? あんたの目には何も見えてやしない」
女を殺したことはない。けれどきっとできる。女が死にたくなるほどの残酷な抱き方だってできる。京都で忌み嫌われた壬《み》生《ぶ》狼《ろ》の中で最も多く人を殺したのも欺《あざむ》いたのも、このオレ、斎藤一だ。
「ならば、本当のあなたさまを見てみとうごぜぇます。おっかねぇお姿になっつまってくなんしょ。おっかなければおっかねぇほど、きっとお美しくもなられるべし。弥曽は、見てみとうごぜぇます」
馬鹿言え。おっかないのは、より気味の悪い化け物は、あんたのほうだ。
その白い首筋を噛み裂いてしまいたい。生かすも殺すもオレ次第なら、本当に道具として扱ってやろうか。生きていることを後悔するまでめちゃくちゃにしてみようか。敵の陣中に投げ込んで囮《おとり》に使ってもいい。
欲に抗《あらが》えない。いっそここで食ってしまおうと思った。オレは弥曽の着物に手を掛けようと、腕を持ち上げる。
そのとき初めて、見られていることに気が付いた。聞かれていたことに気が付いた。そこにいるのが誰なのか気が付いた。
「時尾……」
弥曽が、びくりと顔を上げて振り向いた。
「嫌《やん》だ、時尾さん?」
時尾が踵《きびす》を返して駆け出した。
冷水を浴びせられた心地だった。オレは弥曽の体を押しのけた。頭が混乱している。今、オレは何をしようとしていた?
「待って、山口さま」
「悪い」
オレは弥曽を振り払って、時尾を追った。女の脚に追い付くのはすぐだった。肩をつかむと、時尾は身をよじって逃れた。
肩で息をする時尾は、苦しげに胸を押さえて眉をしかめた。
「やっぱり斎藤さまだった。お邪魔しっつまって申し訳ありません」
「邪魔も何も、勘違いだ」
「なぜわたしを追ってきたがよ? いつも笑っている弥曽さんがつれぇ思いをしているなんて誰《だっちぇ》もわかんねかった。弥曽さんは斎藤さまだけに胸の内を打ち明けたのです。戻ってあげてくなんしょ」
「勘違いだと言っているだろう。オレはあの女と言い交わしたわけじゃない」
「胸を貸していたべし? お似合いだと思いました。夫婦《めおと》のようなお姿だと」
「そんなんじゃない」
「嘘をつかねぇでくなんしょ! わたしは、人が強ぇ思いを抱けばわかるんだ。斎藤さまは弥曽さんに惚れっつまったんだべし。無理もねえ。弥曽さんみてぇに綺麗な人から慕われたら、可愛《めげ》ぇと思うのも当たり前だなし」
「違う……違うんだ、本当に」
時尾は泣き笑いの顔をした。
「斎藤さま、そだに泣きそうな目をされると、わたしは何《な》如《じょ》していいか、わかんねくなります」
「オレのほうがわからない。勝手なことを次々と言われて」
「勝手ですか? 斎藤さまはわたしに気が付かねぇくらい、弥曽さんに夢中だったではねぇですか」
返事に迷う。正直に告げるしかないと思った。
「惑わされたのは本当だ。気がどうにかなっちまいそうだった。馬鹿だな、オレは」
時尾から目を背けてしまいたかった。でも、オレは敢《あ》えて時尾を見つめ続けた。
胸が痛いような気がした。痛みが心地よかった。痛みの正体を探るのはやめた。心臓が穏やかに高鳴った。
時尾はゆっくりとまばたきをして、丁寧に頭を下げた。
「いろいろと失礼を申しました。お許しくなんしょ。弥曽さんにも後で謝ります」
「オレこそ、悪かった。嫌な思いをさせた」
「嫌な思いではねぇけんじょ、ただ……」
黙り込むと、城内の宴で男の声が唄を歌うのが聞こえた。京都で耳にした、他愛ない色恋の唄だ。一人の男と二人の女。ふらふらと揺れてばかりの男を想って、女は袖を噛む。
まるで唄に冷やかされるようで、かっと頬が熱を持った。時尾も同じことを思ったのか、口元を手で覆った。遠くの篝《かがり》火《び》の光がようやく届く暗がりでは、顔色はうかがえない。
知らぬふりを決め込むことにした。
「皆のところに戻らないのか?」
声がうわずってしまった。応える時尾も似たようなものだった。ぱたぱたと上前を整える仕草がぎこちない。
「んだなし。戻らねば、八重さんたちに心配させっつま。斎藤さま、わたし、これで失礼します」
お辞儀をして、時尾は足早に立ち去ろうとした。冷えた夜風が渡った。次はいつ会えるだろうかと、急に不安が胸に差した。
「時尾!」
声を上げた後で息を呑む。初めて名を呼んでしまった。せめて「時尾どの」と呼ぶべきだった。
振り返った時尾は目を見張っている。
「はい。何だべし?」
「その……鳩に手紙を持たせる。何でもいい、書くことは何でもいいから、知らせてほしい。城には、たぶんオレは、しばらく戻らないが……無事を、祈っている。だから、手紙を」
ちぐはぐで尻切れ蜻蛉《とんぼ》。伝えたいこともろくに伝えられず、不甲斐なさに舌打ちしたくなる。
時尾は微笑んだ。暗がりをも照らすような、ぱっと明るい笑顔だった。
「お手紙、書きます。斎藤さまも、どうぞお気を付けて」
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

幕末レクイエム―誠心誠意、咲きて散れ―
馳月基矢
歴史・時代
幕末、動乱の京都の治安維持を担った新撰組。
華やかな活躍の時間は、決して長くなかった。
武士の世の終わりは刻々と迫る。
それでもなお刀を手にし続ける。
これは滅びの武士の生き様。
誠心誠意、ただまっすぐに。
結核を病み、あやかしの力を借りる天才剣士、沖田総司。
あやかし狩りの力を持ち、目的を秘めるスパイ、斎藤一。
同い年に生まれた二人の、別々の道。
仇花よ、あでやかに咲き、潔く散れ。
schedule
公開:2019.4.1
連載:2019.4.7-4.18 ( 6:30 & 18:30 )

柳鼓の塩小町 江戸深川のしょうけら退治
月芝
歴史・時代
花のお江戸は本所深川、その隅っこにある柳鼓長屋。
なんでも奥にある柳を蹴飛ばせばポンっと鳴くらしい。
そんな長屋の差配の孫娘お七。
なんの因果か、お七は産まれながらに怪異の類にめっぽう強かった。
徳を積んだお坊さまや、修験者らが加持祈祷をして追い払うようなモノどもを相手にし、
「えいや」と塩を投げるだけで悪霊退散。
ゆえについたあだ名が柳鼓の塩小町。
ひと癖もふた癖もある長屋の住人たちと塩小町が織りなす、ちょっと不思議で愉快なお江戸奇譚。

商い幼女と猫侍
和紗かをる
歴史・時代
黒船来航から少しの時代。動物狂いでお家断絶になった侍、渡会正嗣と伊勢屋の次女ふたみはあるきっかけから協力して犬、猫、鶏と一緒になって世を守る。世直しドタバタ活劇。綺羅星の様な偉人ひしめく幕末の日本で、二人がひっそりと織り成す物語です。

残影の艦隊~蝦夷共和国の理想と銀の道
谷鋭二
歴史・時代
この物語の舞台は主に幕末・維新の頃の日本です。物語の主人公榎本武揚は、幕末動乱のさなかにはるばるオランダに渡り、最高の技術、最高のスキル、最高の知識を手にいれ日本に戻ってきます。
しかし榎本がオランダにいる間に幕府の権威は完全に失墜し、やがて大政奉還、鳥羽・伏見の戦いをへて幕府は瓦解します。自然幕臣榎本武揚は行き場を失い、未来は絶望的となります。
榎本は新たな己の居場所を蝦夷(北海道)に見出し、同じく行き場を失った多くの幕臣とともに、蝦夷を開拓し新たなフロンティアを築くという壮大な夢を描きます。しかしやがてはその蝦夷にも薩長の魔の手がのびてくるわけです。
この物語では榎本武揚なる人物が最北に地にいかなる夢を見たか追いかけると同時に、世に言う箱館戦争の後、罪を許された榎本のその後の人生にも光を当ててみたいと思っている次第であります。

鎌倉最後の日
もず りょう
歴史・時代
かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

北武の寅 <幕末さいたま志士伝>
海野 次朗
歴史・時代
タイトルは『北武の寅』(ほくぶのとら)と読みます。
幕末の埼玉人にスポットをあてた作品です。主人公は熊谷北郊出身の吉田寅之助という青年です。他に渋沢栄一(尾高兄弟含む)、根岸友山、清水卯三郎、斎藤健次郎などが登場します。さらにベルギー系フランス人のモンブランやフランスお政、五代才助(友厚)、松木弘安(寺島宗則)、伊藤俊輔(博文)なども登場します。
根岸友山が出る関係から新選組や清河八郎の話もあります。また、渋沢栄一やモンブランが出る関係からパリ万博などパリを舞台とした場面が何回かあります。
前作の『伊藤とサトウ』と違って今作は史実重視というよりも、より「小説」に近い形になっているはずです。ただしキャラクターや時代背景はかなり重複しております。『伊藤とサトウ』でやれなかった事件を深掘りしているつもりですので、その点はご了承ください。
(※この作品は「NOVEL DAYS」「小説家になろう」「カクヨム」にも転載してます)
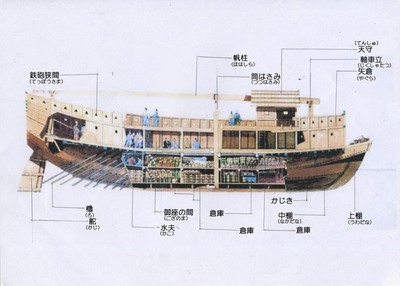

浅葱色の桜 ―堀川通花屋町下ル
初音
歴史・時代
新選組内外の諜報活動を行う諸士調役兼監察。その頭をつとめるのは、隊内唯一の女隊士だった。
義弟の近藤勇らと上洛して早2年。主人公・さくらの活躍はまだまだ続く……!
『浅葱色の桜』https://www.alphapolis.co.jp/novel/32482980/787215527
の続編となりますが、前作を読んでいなくても大丈夫な作りにはしています。前作未読の方もぜひ。
※時代小説の雰囲気を味わっていただくため、縦組みを推奨しています。行間を詰めてありますので横組みだと読みづらいかもしれませんが、ご了承ください。
※あくまでフィクションです。実際の人物、事件には関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















