4 / 17
第3章 懲戒解雇と妄想
しおりを挟む
1.
市ヶ谷へ向かう川島義則の足取りは重たかった。彼の目的地は、防衛省本庁の厚生棟だった。
川島は、OA機器の販売やメンテナンス管理を行う会社に勤めており、彼の担当の一つに防衛省厚生管理課があった。
厚生管理課は、コピー機や複合機を何台も納品している優良顧客である。パソコンも、彼の会社を通じて購入してくれていた。
会社にとっては良い取引先なのだが、川島にとっては最悪の取引先だった。
その原因は、厚生管理課長の井川にあった。
井川は、川島の高校時代の同級生だった。その当時から、井川は川島のことを敵対視していた。
理由は、成績と恋愛にあった。二人は、双方で争う関係だった。
成績に関しては、常に二人で学年トップの座を争っていたが、井川の成績が川島を上回ることはなかった。
加えて、井川が思いを寄せ続けていた同級生の女子生徒と川島が付き合うことになった。彼女のほうから告白しての結果であった。
これらのことは、人一倍強い井川のプライドをずたずたに引き裂いた。
高校を出て別の大学に進学した二人は、大学卒業後、井川が国家公務員となり、川島は民間企業に就職した。
そんな二人が再開したのが、一年前であった。
大学卒業後に就職した会社の業績が悪化しリストラの対象となった川島は、二年前に今の会社に転職し、入れ替わるように退職した前任者の後を引き継いで防衛省厚生管理課の担当となった。
川島は、責任者である井川のもとへ、新しく担当になることのあいさつに出向いた。
そのときは、相手が高校時代の同級生であることに気がつかなかったのだが、井川のほうは、すぐに気がついたようだった。
それからというもの、川島が厚生管理課を訪問するたびに、井川は陰湿な態度を取り続けた。何かにつけて難癖をつけ、川島の会社にクレームの電話を入れた。
相手が高校時代のライバルであったことに気づいた川島は、陰湿な態度を取られる理由を理解していた。しかし、相手は客であり、感情的な対応をするわけにはいかない。
加えて、川島には守るべきものがあった。妻と二人の子どもたちとの生活であった。
転職したことで、川島の年収は激減した。反面、子どもたちにかかる教育費も年々増え続けている。
老後のことを考えると安易に貯金を取り崩すわけにもいかず、専業主婦をしていた妻もパートとして働きに出ていた。それでも、生活はぎりぎりである。短気を起こして会社を辞めるわけにはいかない。
川島は、ぐっとこらえた。
そんな川島の事情を察したのか、井川の行動はエスカレートしていった。
部下の職員たちが見ている前で川島のことを罵倒し、サポート業務完了後の確認のための押印を理由もなく拒むなどのいじめを繰り返した。
確認印をもらえない限り、川島は次の行動へ移れない。その後に訪問を予定している顧客に対して迷惑をかける事態がたびたび発生した。そのことについて、会社から叱責を受けた。
川島は、ストレスで胃が痛むようになっていた。
それとともに、井川に対する憎悪が蓄積されていった。
2.
JR市ヶ谷駅の改札を出た川島は、靖国通りを直進した。左手に、防衛省の建物が見えてくる。
川島の胃が疼きだした。脳裏に、意地の悪い表情をした井川の顔が浮かんでくる。
自然と歩みが遅くなったが、気持ちを奮い立たせた。家族のためにも耐え忍ばなければならない。それが仕事というものだ。
厚生棟に到着した川島は、まっすぐに厚生管理課のあるフロアーへと向かった。
入り口のドアをノックし、ドアを開けて、大きな声で会社名を名乗る。
職員たちが顔を向けた。フロアー奥の課長席に座った井川も顔を向ける。よい獲物を見つけたとでも言いたげな薄ら笑いを浮かべていた。
川島は、いつも通りの作業に入った。川島の会社が納品したOA機器類の点検を行い、コピー機のカウントを数え、古くなった部品を交換する。
何人かの職員が、機器の使い方や使用中に発生したエラーに対する質問をしてきた。
川島は、一つ一つの質問に対して、懇切丁寧な説明を行った。
丁寧な対応をしたことで、すべての質問者がすっきりとした表情で席へと戻っていった。川島の対応は、職員たちからは評判が良かった。
大方の点検作業を終えたときだった。「○○さん。ちょっと、こっちに来てくれる」と、川島の会社名を口にした井川が席まで来るよう手招きをした。何事かを企んでいるかのような表情を浮かべていた。
川島は、点検作業の手を休め、井川の席へ向かった。
席の前に立ち、「いかがしましたか?」と声をかける。
「この間買い換えたパソコン、使いづらいんだよね」井川が、机の上のパソコンを指さした。
厚生管理課は、半月ほど前に、何台かのパソコンを新しいOSのものに買い替えた。井川が現在使用しているパソコンもそのうちの一台だった。パソコンを納品したのは、川島の会社である。
「どのような面が、使いづらいのでしょうか?」
「全部だよ。キー操作が、前のと全然違うじゃないか!」
(当たり前だろ! OSが新しくなったんだから)胸の中で毒ついた川島だったが、口では「使いづらいところを具体的におっしゃっていただけましたら、説明いたしますが」と返事をした。
「まず、ここ!」井川が、不機嫌そうな表情で、デスクトップのウィンドウに表示されたアイコンを指さした。使い慣れていた配列にできないという不満である。
パソコンを操作してもよいかと断った川島は、設定を変更し、井川の望むアイコン配列に近づけた。
しかし、完全に古いパソコンの時の配列にすることはできない。操作の問題ではなく、メーカー側の仕様の問題だからだ。
完全にできないことについて、井川が難癖をつけてきた。
川島は、物理的に不可能であることの理由を説明した。
しかし、井川は納得しない。理由は理解しているはずなのだが、川島をいじめるために難癖をつけ続けていることが見え見えであった。
アイコン配列に関してひとしきり難癖をつけた井川は、今度は文章ファイルの操作方法についての難癖をつけ始めた。機能がガラッと変わり、スムーズに作業できないという言い分であった。大事な文章を保存し損ねて業務に支障が出たことへの文句も口にする。
ほかに新しいパソコンに入れ替えた職員たちは、すぐに使いこなしている。使い方がわからなければ、マニュアル等で調べ、その後はひたすら慣れるべき問題であった。
その言葉を口にすることを堪えた川島は、丁寧な説明を繰り返した。
3.
文章ファイルの操作方法に関する説明を何とか終えた。
川島は、やり残した点検作業を再開するために、井川の席を離れようとした。
そのときだった。「ちょっと待て!」井川が、川島を呼び止めた。
(今度は、何だよ)内心うんざりしながら、川島は顔を向けた。
「あんたは、納品前に、こんなにも使いづらいパソコンだという説明をしなかったよな。それって、職務怠慢ではないのかね?」
川島の頭の中で、たくさんのクエッションマークが飛び交った。そもそも、川島が新しいパソコンを勧めたわけではない。セキュリティ能力をアップさせるためにバージョンを新しくする必要があるので、見積もりを作成してほしいという厚生管理課側の依頼に応えて納品したのである。
市場価格よりも安く納品できるように、メーカーサイドに交渉したのも川島である。文句を言われる筋合いなど、どこにもない。
「バージョンが変わると、どうしても最初は使いづらくなるのですよ。慣れるまでの辛抱ですから」川島は、当たり障りのない返事をした。
「なに? あんたは、慣れるのに手間取っているオレが悪いのだといいたいのかい?」
「そういうつもりで言ったのではありませんが」内心ではそういうつもりだよと舌を出しながらも、川島は、なだめるように口にした。
「いや。あんたは、そういうつもりで言っている。オレの質問に答える時も、馬鹿にしたような表情をしていたじゃないか! なめているのか?」
川島は、口をつぐんだ。どのような言葉を返しても建設的な会話にはならない。とりあえず、言いたいだけ言わせておこう。
井川が、かさにかかってきた。大声で、川島の態度が悪い、能力がないなどと喚き散らす。
部下の職員たちが、ちらちらと視線を向けてきた。川島に対して同情する空気が伝わってくる。
その空気を察したのか、井川の言動がエスカレートした。
「今回は、本当に我慢がならん。あんたの会社に電話してやる!」目の前の受話器に手を伸ばした。
川島は、黙ってやらせることにした。謝ったところで、振り上げたこぶしを収めるとは思えなかったからだ。上司に対して、昔の関係も含めたすべての事情を話したうえで事の顛末を説明すれば、理解してもらえるだろう。
厚生管理課の職員たちに聞いてもらえれば、川島に非がないことはわかってもらえるはずだ。
電話でひとしきり文句を言い、受話器を置いた井川が、川島と視線を合わせた。
「あんたの上司は、ひたすら謝っていたよ。あんたが戻ったら、厳重に注意すると言っていた。なんて言われるんだろうねぇ」口元をほころばせ、品のない笑みを浮かべる。
「優良顧客に対して不誠実な態度をとり、クレームにつながったんだからね。評価が下がるのは、間違いないよ。営業が評価を下げるっていうのは、収入減につながるっていうことだよな」
「……」
「あんた、あれだろう? 前の会社をリストラされてさ、今の会社に拾ってもらったんだろう? 前の会社が大企業で、そこそこの給料をもらっていたものだから、調子に乗ってガキをたくさん作って、セレブぶった生活をしちゃったみたいだけど、リストラくらって、年収ガタ落ちで、奥さんをパートに働きに出したって? 甲斐性ないねぇ、あんたは」
川島は、うつむいた。顔の表情を正常に保つことが難しくなっていた。握りしめたこぶしが、ぶるぶると震えている。
「あんたの会社に、言いたいことを全部言ったわけではないからね。あんたが会社に戻る間に、もう一度電話を入れておくよ。あんな営業、使えないって言っておくからさ。まぁ、給料とボーナスが下がるのは、間違いないでしょう。そうしたら、今よりももっと生活が苦しくなると思うよ。だからさあ、お子さんの進学をあきらめることを考えておいたほうがいいんじゃないのか? それとも、家庭の収入を増やすために、奥さんにもっと稼いでもらうか? 風俗に転職してもらったらどうかな? 無理か。しわくちゃ婆ちゃんを使ってくれる風俗店なんか、あるわけないか……」
川島の中で、何かがはじけた。
井川に、ゆっくりと視線を向ける。
井川の襟首をつかもうと、腕に力を込める。
しかし、襟首をつかむことはできなかった。腕を伸ばそうとするのを引き留める力が働いたからだ。
全身が、誰かに押さえつけられたように動かない。
そんな川島に向かって、誰かがささやた。
「公序良俗に反する行為にて、会社の信用を失墜させ、会社に甚大な損害を与えた者を、懲戒解雇に処する」
(懲戒解雇……)川島は、我に返った。
全身を押さえつけるような力も消えていた。
川島は、視線を前に向けた。井川が、自分に向って懸命にしゃべっている。
しかし、その声は聞こえてこなかった。
4.
「てめぇ、言いたい放題言いやがって! オレのことを馬鹿にするのは許せても、家族のことを馬鹿にするのは許せねぇ!」
座っていた井川の襟首をつかんだ川島は、渾身の力で、自分のほうへ引っ張った。
机の上のパソコンが、派手な音を立てながら床に落ちた。
襟首をつかまれた井川が、せき込みながら机の上で体を滑らせ、引きずられながら床に崩れ落ちる。
「立てよ!」川島は、井川を引きずり立たせた。
「今まで我慢を重ねた分な、爆発した時の怒りは止められねぇんだよ!」
髪の毛をつかみ、井川の顔面を机の上にたたきつけた。
ゴンという鈍い音が、厚生管理課のフロアー内に響き渡る。
職員たちは、驚いた表情で暴れる川島を見つめていた。しかし、制止しようとする者はいない。警備の人間や警察に連絡をしようとする者もいなかった。
職員たちは、川島に同情的だった。井川自身、部下から嫌われていたのだろう。
「もうそろそろ、止めといたほうがよいのでは」井川の顔面を机にたたきつけることを止めようとしない川島に向って、職員の一人が声をかけてきた。
川島は、井川の髪から手を離した。井川が、再び床に崩れ落ちる。
「川島さんのお気持ちは痛いほどわかります。でも、これ以上やると本当にヤバくなりますから、これくらいにしておきましょう」
「私たちがやりたかったことを川島さんが代わりにやってくれて、すっきりとしました」
「ボクたちみんな、今のことは見なかったことにしておきます。川島さんは点検作業を終えられて、そのまま帰ったことにしましょう。課長が何か言っても、ボクたち全員でそのようなことはなかったと証言しますから、安心してください」
やはり、職員たちは川島の味方であった。
井川が、髪の毛がぐちゃぐちゃに乱れた顔を部下たちに向ける。何事かを言いたげに口を開いたが、口をパクパクさせるだけで言葉を発することができずにいた。
職員たちは、何事もなかったかのように仕事を再開した。
一人の職員が、井川の机の引き出しから印鑑を出し、川島が持参した保守点検記録用紙に押印してくれた。
点検のための工具や書類をカバンの中にしまった川島は、職員たちに一礼し、厚生管理課を出た。厚生棟を出て、JRの市ヶ谷駅へ向かう道をゆっくりと歩く。
大それたことをしてしまったのだが、後悔はしていなかった。職員たちが見方をしてくれたからだ。
井川が何か申し立てても、職員たちがそのような事実はなかったと証言してくれれば問題はない。
それだけではなく、貯めに貯めていたものを発散できて、すっきりとした気分になっていた。
そんな川島の顔を、さわやかな風が吹きぬけた。
妄想から覚めた川島は、井川の顔を見つめた。気分が治まったのか、あるいは川島の反応のないことに張り合いがなくなったのか、井川が、もう用はないという言葉を口にした。
一部の点検が残っていたが、すでに保守点検記録用紙に井川の印が押されていた。
保守点検記録用紙をカバンにしまった川島は、残りの点検作業を終わらせ、厚生管理課を後にした。
厚生管理課の外は静まり返っていた。見学者たちの姿もない。
建物の入り口に向ってゆっくりと歩きながら、川島は、先ほどの出来事を思い浮かべた。
(かわいそうなやつなんだろうな…)川島は、井川のことをかわいそうな人間なのだと思えるようになっていた。
二十五年も前のことを根に持ち、当時の相手に仕返しをしようとしている。
同じように歳を取ったが、彼は、前に進むことができずにいるのだ。
それだけではない。部下たちが見ている前で、立場の弱い人間のことをいたぶる行為をやり続けた。
部下たちも、そんな井川のことを冷ややかな目で見ている。
そのことは、井川自身の評価にも影響するはずだ。
国家公務員の同期間での競争意識は激しいと聞いているが、彼は、誰よりも早く挫折を味わうことになるのだろう。
川島は、井川のことを哀れに思えるようになっていた。
それとともに、自分は救われたのだと感じていた。
あのまま手を出していたら、自分は、ただでは済まされなかった。ささやき声の通り、会社を首になっただろう。首になれば、愛する家族もろとも路頭に迷うことになる。
そんな川島の頭の中で、とある光景が浮かび上がった。
ある時、新宿歌舞伎町で妄想保険のモニターになることを勧められたときの光景であった。
市ヶ谷へ向かう川島義則の足取りは重たかった。彼の目的地は、防衛省本庁の厚生棟だった。
川島は、OA機器の販売やメンテナンス管理を行う会社に勤めており、彼の担当の一つに防衛省厚生管理課があった。
厚生管理課は、コピー機や複合機を何台も納品している優良顧客である。パソコンも、彼の会社を通じて購入してくれていた。
会社にとっては良い取引先なのだが、川島にとっては最悪の取引先だった。
その原因は、厚生管理課長の井川にあった。
井川は、川島の高校時代の同級生だった。その当時から、井川は川島のことを敵対視していた。
理由は、成績と恋愛にあった。二人は、双方で争う関係だった。
成績に関しては、常に二人で学年トップの座を争っていたが、井川の成績が川島を上回ることはなかった。
加えて、井川が思いを寄せ続けていた同級生の女子生徒と川島が付き合うことになった。彼女のほうから告白しての結果であった。
これらのことは、人一倍強い井川のプライドをずたずたに引き裂いた。
高校を出て別の大学に進学した二人は、大学卒業後、井川が国家公務員となり、川島は民間企業に就職した。
そんな二人が再開したのが、一年前であった。
大学卒業後に就職した会社の業績が悪化しリストラの対象となった川島は、二年前に今の会社に転職し、入れ替わるように退職した前任者の後を引き継いで防衛省厚生管理課の担当となった。
川島は、責任者である井川のもとへ、新しく担当になることのあいさつに出向いた。
そのときは、相手が高校時代の同級生であることに気がつかなかったのだが、井川のほうは、すぐに気がついたようだった。
それからというもの、川島が厚生管理課を訪問するたびに、井川は陰湿な態度を取り続けた。何かにつけて難癖をつけ、川島の会社にクレームの電話を入れた。
相手が高校時代のライバルであったことに気づいた川島は、陰湿な態度を取られる理由を理解していた。しかし、相手は客であり、感情的な対応をするわけにはいかない。
加えて、川島には守るべきものがあった。妻と二人の子どもたちとの生活であった。
転職したことで、川島の年収は激減した。反面、子どもたちにかかる教育費も年々増え続けている。
老後のことを考えると安易に貯金を取り崩すわけにもいかず、専業主婦をしていた妻もパートとして働きに出ていた。それでも、生活はぎりぎりである。短気を起こして会社を辞めるわけにはいかない。
川島は、ぐっとこらえた。
そんな川島の事情を察したのか、井川の行動はエスカレートしていった。
部下の職員たちが見ている前で川島のことを罵倒し、サポート業務完了後の確認のための押印を理由もなく拒むなどのいじめを繰り返した。
確認印をもらえない限り、川島は次の行動へ移れない。その後に訪問を予定している顧客に対して迷惑をかける事態がたびたび発生した。そのことについて、会社から叱責を受けた。
川島は、ストレスで胃が痛むようになっていた。
それとともに、井川に対する憎悪が蓄積されていった。
2.
JR市ヶ谷駅の改札を出た川島は、靖国通りを直進した。左手に、防衛省の建物が見えてくる。
川島の胃が疼きだした。脳裏に、意地の悪い表情をした井川の顔が浮かんでくる。
自然と歩みが遅くなったが、気持ちを奮い立たせた。家族のためにも耐え忍ばなければならない。それが仕事というものだ。
厚生棟に到着した川島は、まっすぐに厚生管理課のあるフロアーへと向かった。
入り口のドアをノックし、ドアを開けて、大きな声で会社名を名乗る。
職員たちが顔を向けた。フロアー奥の課長席に座った井川も顔を向ける。よい獲物を見つけたとでも言いたげな薄ら笑いを浮かべていた。
川島は、いつも通りの作業に入った。川島の会社が納品したOA機器類の点検を行い、コピー機のカウントを数え、古くなった部品を交換する。
何人かの職員が、機器の使い方や使用中に発生したエラーに対する質問をしてきた。
川島は、一つ一つの質問に対して、懇切丁寧な説明を行った。
丁寧な対応をしたことで、すべての質問者がすっきりとした表情で席へと戻っていった。川島の対応は、職員たちからは評判が良かった。
大方の点検作業を終えたときだった。「○○さん。ちょっと、こっちに来てくれる」と、川島の会社名を口にした井川が席まで来るよう手招きをした。何事かを企んでいるかのような表情を浮かべていた。
川島は、点検作業の手を休め、井川の席へ向かった。
席の前に立ち、「いかがしましたか?」と声をかける。
「この間買い換えたパソコン、使いづらいんだよね」井川が、机の上のパソコンを指さした。
厚生管理課は、半月ほど前に、何台かのパソコンを新しいOSのものに買い替えた。井川が現在使用しているパソコンもそのうちの一台だった。パソコンを納品したのは、川島の会社である。
「どのような面が、使いづらいのでしょうか?」
「全部だよ。キー操作が、前のと全然違うじゃないか!」
(当たり前だろ! OSが新しくなったんだから)胸の中で毒ついた川島だったが、口では「使いづらいところを具体的におっしゃっていただけましたら、説明いたしますが」と返事をした。
「まず、ここ!」井川が、不機嫌そうな表情で、デスクトップのウィンドウに表示されたアイコンを指さした。使い慣れていた配列にできないという不満である。
パソコンを操作してもよいかと断った川島は、設定を変更し、井川の望むアイコン配列に近づけた。
しかし、完全に古いパソコンの時の配列にすることはできない。操作の問題ではなく、メーカー側の仕様の問題だからだ。
完全にできないことについて、井川が難癖をつけてきた。
川島は、物理的に不可能であることの理由を説明した。
しかし、井川は納得しない。理由は理解しているはずなのだが、川島をいじめるために難癖をつけ続けていることが見え見えであった。
アイコン配列に関してひとしきり難癖をつけた井川は、今度は文章ファイルの操作方法についての難癖をつけ始めた。機能がガラッと変わり、スムーズに作業できないという言い分であった。大事な文章を保存し損ねて業務に支障が出たことへの文句も口にする。
ほかに新しいパソコンに入れ替えた職員たちは、すぐに使いこなしている。使い方がわからなければ、マニュアル等で調べ、その後はひたすら慣れるべき問題であった。
その言葉を口にすることを堪えた川島は、丁寧な説明を繰り返した。
3.
文章ファイルの操作方法に関する説明を何とか終えた。
川島は、やり残した点検作業を再開するために、井川の席を離れようとした。
そのときだった。「ちょっと待て!」井川が、川島を呼び止めた。
(今度は、何だよ)内心うんざりしながら、川島は顔を向けた。
「あんたは、納品前に、こんなにも使いづらいパソコンだという説明をしなかったよな。それって、職務怠慢ではないのかね?」
川島の頭の中で、たくさんのクエッションマークが飛び交った。そもそも、川島が新しいパソコンを勧めたわけではない。セキュリティ能力をアップさせるためにバージョンを新しくする必要があるので、見積もりを作成してほしいという厚生管理課側の依頼に応えて納品したのである。
市場価格よりも安く納品できるように、メーカーサイドに交渉したのも川島である。文句を言われる筋合いなど、どこにもない。
「バージョンが変わると、どうしても最初は使いづらくなるのですよ。慣れるまでの辛抱ですから」川島は、当たり障りのない返事をした。
「なに? あんたは、慣れるのに手間取っているオレが悪いのだといいたいのかい?」
「そういうつもりで言ったのではありませんが」内心ではそういうつもりだよと舌を出しながらも、川島は、なだめるように口にした。
「いや。あんたは、そういうつもりで言っている。オレの質問に答える時も、馬鹿にしたような表情をしていたじゃないか! なめているのか?」
川島は、口をつぐんだ。どのような言葉を返しても建設的な会話にはならない。とりあえず、言いたいだけ言わせておこう。
井川が、かさにかかってきた。大声で、川島の態度が悪い、能力がないなどと喚き散らす。
部下の職員たちが、ちらちらと視線を向けてきた。川島に対して同情する空気が伝わってくる。
その空気を察したのか、井川の言動がエスカレートした。
「今回は、本当に我慢がならん。あんたの会社に電話してやる!」目の前の受話器に手を伸ばした。
川島は、黙ってやらせることにした。謝ったところで、振り上げたこぶしを収めるとは思えなかったからだ。上司に対して、昔の関係も含めたすべての事情を話したうえで事の顛末を説明すれば、理解してもらえるだろう。
厚生管理課の職員たちに聞いてもらえれば、川島に非がないことはわかってもらえるはずだ。
電話でひとしきり文句を言い、受話器を置いた井川が、川島と視線を合わせた。
「あんたの上司は、ひたすら謝っていたよ。あんたが戻ったら、厳重に注意すると言っていた。なんて言われるんだろうねぇ」口元をほころばせ、品のない笑みを浮かべる。
「優良顧客に対して不誠実な態度をとり、クレームにつながったんだからね。評価が下がるのは、間違いないよ。営業が評価を下げるっていうのは、収入減につながるっていうことだよな」
「……」
「あんた、あれだろう? 前の会社をリストラされてさ、今の会社に拾ってもらったんだろう? 前の会社が大企業で、そこそこの給料をもらっていたものだから、調子に乗ってガキをたくさん作って、セレブぶった生活をしちゃったみたいだけど、リストラくらって、年収ガタ落ちで、奥さんをパートに働きに出したって? 甲斐性ないねぇ、あんたは」
川島は、うつむいた。顔の表情を正常に保つことが難しくなっていた。握りしめたこぶしが、ぶるぶると震えている。
「あんたの会社に、言いたいことを全部言ったわけではないからね。あんたが会社に戻る間に、もう一度電話を入れておくよ。あんな営業、使えないって言っておくからさ。まぁ、給料とボーナスが下がるのは、間違いないでしょう。そうしたら、今よりももっと生活が苦しくなると思うよ。だからさあ、お子さんの進学をあきらめることを考えておいたほうがいいんじゃないのか? それとも、家庭の収入を増やすために、奥さんにもっと稼いでもらうか? 風俗に転職してもらったらどうかな? 無理か。しわくちゃ婆ちゃんを使ってくれる風俗店なんか、あるわけないか……」
川島の中で、何かがはじけた。
井川に、ゆっくりと視線を向ける。
井川の襟首をつかもうと、腕に力を込める。
しかし、襟首をつかむことはできなかった。腕を伸ばそうとするのを引き留める力が働いたからだ。
全身が、誰かに押さえつけられたように動かない。
そんな川島に向かって、誰かがささやた。
「公序良俗に反する行為にて、会社の信用を失墜させ、会社に甚大な損害を与えた者を、懲戒解雇に処する」
(懲戒解雇……)川島は、我に返った。
全身を押さえつけるような力も消えていた。
川島は、視線を前に向けた。井川が、自分に向って懸命にしゃべっている。
しかし、その声は聞こえてこなかった。
4.
「てめぇ、言いたい放題言いやがって! オレのことを馬鹿にするのは許せても、家族のことを馬鹿にするのは許せねぇ!」
座っていた井川の襟首をつかんだ川島は、渾身の力で、自分のほうへ引っ張った。
机の上のパソコンが、派手な音を立てながら床に落ちた。
襟首をつかまれた井川が、せき込みながら机の上で体を滑らせ、引きずられながら床に崩れ落ちる。
「立てよ!」川島は、井川を引きずり立たせた。
「今まで我慢を重ねた分な、爆発した時の怒りは止められねぇんだよ!」
髪の毛をつかみ、井川の顔面を机の上にたたきつけた。
ゴンという鈍い音が、厚生管理課のフロアー内に響き渡る。
職員たちは、驚いた表情で暴れる川島を見つめていた。しかし、制止しようとする者はいない。警備の人間や警察に連絡をしようとする者もいなかった。
職員たちは、川島に同情的だった。井川自身、部下から嫌われていたのだろう。
「もうそろそろ、止めといたほうがよいのでは」井川の顔面を机にたたきつけることを止めようとしない川島に向って、職員の一人が声をかけてきた。
川島は、井川の髪から手を離した。井川が、再び床に崩れ落ちる。
「川島さんのお気持ちは痛いほどわかります。でも、これ以上やると本当にヤバくなりますから、これくらいにしておきましょう」
「私たちがやりたかったことを川島さんが代わりにやってくれて、すっきりとしました」
「ボクたちみんな、今のことは見なかったことにしておきます。川島さんは点検作業を終えられて、そのまま帰ったことにしましょう。課長が何か言っても、ボクたち全員でそのようなことはなかったと証言しますから、安心してください」
やはり、職員たちは川島の味方であった。
井川が、髪の毛がぐちゃぐちゃに乱れた顔を部下たちに向ける。何事かを言いたげに口を開いたが、口をパクパクさせるだけで言葉を発することができずにいた。
職員たちは、何事もなかったかのように仕事を再開した。
一人の職員が、井川の机の引き出しから印鑑を出し、川島が持参した保守点検記録用紙に押印してくれた。
点検のための工具や書類をカバンの中にしまった川島は、職員たちに一礼し、厚生管理課を出た。厚生棟を出て、JRの市ヶ谷駅へ向かう道をゆっくりと歩く。
大それたことをしてしまったのだが、後悔はしていなかった。職員たちが見方をしてくれたからだ。
井川が何か申し立てても、職員たちがそのような事実はなかったと証言してくれれば問題はない。
それだけではなく、貯めに貯めていたものを発散できて、すっきりとした気分になっていた。
そんな川島の顔を、さわやかな風が吹きぬけた。
妄想から覚めた川島は、井川の顔を見つめた。気分が治まったのか、あるいは川島の反応のないことに張り合いがなくなったのか、井川が、もう用はないという言葉を口にした。
一部の点検が残っていたが、すでに保守点検記録用紙に井川の印が押されていた。
保守点検記録用紙をカバンにしまった川島は、残りの点検作業を終わらせ、厚生管理課を後にした。
厚生管理課の外は静まり返っていた。見学者たちの姿もない。
建物の入り口に向ってゆっくりと歩きながら、川島は、先ほどの出来事を思い浮かべた。
(かわいそうなやつなんだろうな…)川島は、井川のことをかわいそうな人間なのだと思えるようになっていた。
二十五年も前のことを根に持ち、当時の相手に仕返しをしようとしている。
同じように歳を取ったが、彼は、前に進むことができずにいるのだ。
それだけではない。部下たちが見ている前で、立場の弱い人間のことをいたぶる行為をやり続けた。
部下たちも、そんな井川のことを冷ややかな目で見ている。
そのことは、井川自身の評価にも影響するはずだ。
国家公務員の同期間での競争意識は激しいと聞いているが、彼は、誰よりも早く挫折を味わうことになるのだろう。
川島は、井川のことを哀れに思えるようになっていた。
それとともに、自分は救われたのだと感じていた。
あのまま手を出していたら、自分は、ただでは済まされなかった。ささやき声の通り、会社を首になっただろう。首になれば、愛する家族もろとも路頭に迷うことになる。
そんな川島の頭の中で、とある光景が浮かび上がった。
ある時、新宿歌舞伎町で妄想保険のモニターになることを勧められたときの光景であった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


INNER NAUTS(インナーノーツ) 〜精神と異界の航海者〜
SunYoh
SF
ーー22世紀半ばーー
魂の源とされる精神世界「インナースペース」……その次元から無尽蔵のエネルギーを得ることを可能にした代償に、さまざまな災害や心身への未知の脅威が発生していた。
「インナーノーツ」は、時空を超越する船<アマテラス>を駆り、脅威の解消に「インナースペース」へ挑む。
<第一章 「誘い」>
粗筋
余剰次元活動艇<アマテラス>の最終試験となった有人起動試験は、原因不明のトラブルに見舞われ、中断を余儀なくされたが、同じ頃、「インナーノーツ」が所属する研究機関で保護していた少女「亜夢」にもまた異変が起こっていた……5年もの間、眠り続けていた彼女の深層無意識の中で何かが目覚めようとしている。
「インナースペース」のエネルギーを解放する特異な能力を秘めた亜夢の目覚めは、即ち、「インナースペース」のみならず、物質世界である「現象界(この世)」にも甚大な被害をもたらす可能性がある。
ーー亜夢が目覚める前に、この脅威を解消するーー
「インナーノーツ」は、この使命を胸に<アマテラス>を駆り、未知なる世界「インナースペース」へと旅立つ!
そこで彼らを待ち受けていたものとは……
※この物語はフィクションです。実際の国や団体などとは関係ありません。
※SFジャンルですが殆ど空想科学です。
※セルフレイティングに関して、若干抵触する可能性がある表現が含まれます。
※「小説家になろう」、「ノベルアップ+」でも連載中
※スピリチュアル系の内容を含みますが、特定の宗教団体等とは一切関係無く、布教、勧誘等を目的とした作品ではありません。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった
なるとし
ファンタジー
鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。
特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。
武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。
だけど、その母と娘二人は、
とおおおおんでもないヤンデレだった……
第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。


Condense Nation
鳳
SF
西暦XXXX年、突如としてこの国は天から舞い降りた勢力によって制圧され、
正体不明の蓋世に自衛隊の抵抗も及ばずに封鎖されてしまう。
海外逃亡すら叶わぬ中で資源、優秀な人材を巡り、内戦へ勃発。
軍事行動を中心とした攻防戦が繰り広げられていった。
生存のためならルールも手段も決していとわず。
凌ぎを削って各地方の者達は独自の術をもって命を繋いでゆくが、
決して平坦な道もなくそれぞれの明日を願いゆく。
五感の界隈すら全て内側の央へ。
サイバーとスチームの間を目指して
登場する人物・団体・名称等は架空であり、
実在のものとは関係ありません。

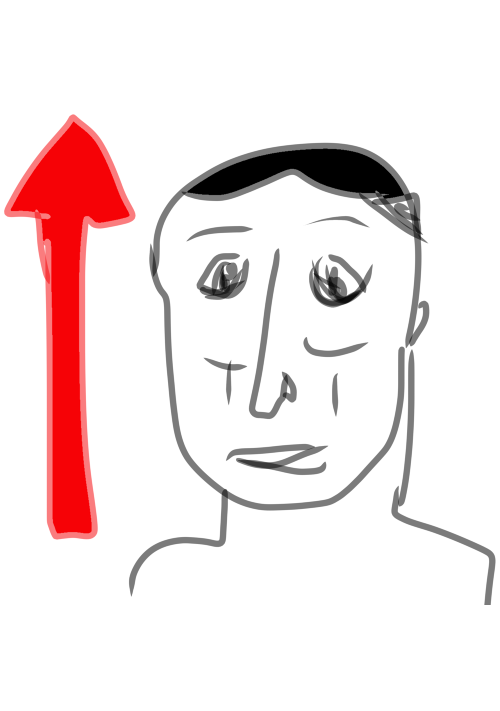
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















