9 / 19
⑨妹の婚約者
しおりを挟む
「よろしかったのですか?途中で抜け出したりして?」
「心配ない。もう、挨拶はすませたし、後は自由解散だ」
パーティー会場はお城からは少し離れたところに建っていて、お城までは豪華な薔薇が咲き誇る庭園が続いていた。
奥にいけば池があるらしく、時間があったらぜひ見てみたいとソフィアは眺めていた。
薔薇の回廊と言われる歩廊を二人で歩いていく。辺りは静かで虫の鳴き声が聞こえてくるだけだった。
「…先程は、取り乱してすまない。カルロスがソフィアに何かするとは思っていなかったが、どうしても気が立ってしまって……」
「他国へ行かれた使者からは、良いお返事が来ていないそうですね」
「ああ。カルロスから聞いたのか…、確かにその通りだ。それなんだが…実は…」
そう言ったまま、ランドールはまた考えるように黙りこんでしまった。なんとなく、気まずい沈黙が二人の間にながれた。
その時、何人かの話し声と楽しげに笑う声が聞こえてきた。
二人して急に聞こえてきた声に驚いて、回廊の端に逃れて隠れるように身を縮ませた。
「……あの、なぜ隠れる必要が…?普通に歩いているだけなので、堂々としていて問題ないのでは?」
「あっああ。そうだったな……」
ランドールの方を見上げると、思いのほか近い距離であったので、ソフィアの心臓はトクンと鳴った。
しかもその距離はゆっくりと近づいているように思えた。
「…ランドール様。どうして…そんなにこちらを…」
ランドールの目はソフィアを見つめて離さなかった。その視線の熱に気がついたとき、ソフィアは後戻りが出来ないところにいると感じた。
「…だめです。これ以上は…、戻れなくなります。私達は仮の…関係で…」
「ソフィア…」
続きの言葉を紡ぐ前に、ソフィアの唇はランドールの唇で塞がれた。
軽く触れるだけの優しいキス。
肩を押し返せばすぐに離れることができるだろう。
けれど、ランドールの唇は少し震えていて、ソフィアの強ばっていた体は自然と力が抜けていった。
わずかな時間重なってから、ランドールの唇はゆっくりと離れた。
結局目を閉じることもできずに、ソフィアはずっと目を開けたままだった。
近すぎてぼやけていた視界にランドールの瞳が見えて、そこに自分が映っているのが嘘みたいで不思議な光景だった。
「……すまない。ソフィア……俺は……」
苦しげに眉をひそめて、言葉を飲み込んだランドールは、ゆっくりとソフィアから離れて、先に戻ると言い残し、身を翻して足早に行ってしまった。
一人残されたソフィアは、呆然と立ち尽くしまい足が動かなかった。
月明かりの下、母が残してくれたという薄いピンクのドレスは白く光って見えた。
混じりけのない純粋な輝きは、自分の歩んできた過去を思うと眩しすぎて、しばらく目を開けることはできなかった。
□□
「たかがキス一つ。しかもちょっと触れただけよ。しっかりしなさい私!」
お城で開かれたパーティーの夜、不意にランドールとキスをしてしまった。
あの後は控え室に戻って着替えて、すぐ屋敷へ帰ってしまった。
帰りの馬車に乗っているときは、まるで夢から覚めたシンデレラのような気分だった。
思えばところどころ、ランドールの好意を感じるような視線を感じるときはあった。
それに気づかないふりをして、考えないようにしていた。
女性との交流が少なかったランドールが一緒に過ごすことで、ただ気持ちが引っ張られただけの一過性のものだろうと考えていた。
ここは多少の物事が分かっている立場として、冷静さを保ち正しい方向へ導いてあげるのが、自分があるべき姿だろうソフィアは思っている。
だがソフィアは、あの拙い子供のようなキスに動揺して、昨日からほとんど眠れていなかった。
激しくもなく、蕩けるようなものでもない、ただ触れただけの行為が、ソフィアの体に根をはってどこまでも伸びていくようだった。
休みは終わり、今日から学校であるのに、ソフィアのもやもやとした心は晴れない。
玄関で悶々としながら唸っていると、後ろからどうしたのと声をかけられた。
振り向くと、いつも仕事で早く出るはずの兄、ヘインズが立っていた。
「ソフィア、顔色が悪いよ。昨日はパーティーだったんだろう。無理はしていない?」
「……お兄様、大丈夫です。少し疲れているだけです」
「いや、しかし……」
ヘインズの話が終わらないうちに、迎えの馬車が来たと声がかけられた。
ヘインズも挨拶をするつもりなのだろう。ソフィアと一緒に玄関を出て馬車へ向かった。
「今日は仕事を遅らせてどうしても殿下にご挨拶したくて待っていたんだ」
「え…それは…そうですか」
またややこしいタイミングだとソフィアは軽く頭痛を覚えた。しかもヘインズは背中に手を回してきてベタベタとくっついてきたので、ソフィアは軽く睨み付けたが、ヘインズは逆に反応してくれて嬉しいみたいにニヤニヤと笑いだした。
「ちょっと!お兄様…、離して…」
「ソフィア、そちらは…?」
ヘインズと揉めていたら、なかなか来ないからかランドールが下りてきてしまった。
「これはこれは、わざわざありがとうございます殿下!私、ソフィアの兄のヘインズと申します!初めまして!」
「あっ…ああ」
ヘインズの場違いな明るさに、ランドールは若干引き気味に答えた。
「昨夜のパーティーには出席出来ず、申し訳ございませんでした。改めてお祝い申し上げます。うちの可愛い妹をどうぞよろしくお願いします」
「ああ、それなんだが……」
「ああ!!どうぞよろしくには色々な意味がありましてね。妹の将来を約束して頂いた殿下に私から一言よろしいでしょうか?」
異様なテンションとゴリ押しで、ランドールの言葉は封じられて、ヘインズが喋り続けている。まだ喋り足りないらしく、ランドールも驚きつつ、勢いに促されるように頷いた。
「妹は殿下の前では強がっているかもしれませんが、繊細で傷つきやすいです。もちろん、優しくて可愛い自慢の妹でありますが、そういう意味でまずよろしくという事と、うちは父が頼りにならないので、長男の私から言わせて頂きますが、中途半端に妹を弄ぶようなことをしたら、私は決して許さないです。と、いうことでどうぞよろしくお願いします」
今までヘラヘラとしていたくせに、急に真面目な顔になって、ヘインズは弾丸のようにランドールに向かって言葉を撃ち込んだ。
もちろん、ヘインズは仮の婚約者であることは知らない。昨日の今日で微妙な問題ではあるが、ランドールなら、この場を上手くごまかすように兄の言葉に了承してくれると思った。
しばらく考えるように下を向いて沈黙していたランドールだが、決意を込めたような目をしてヘインズに向き合った。
「……俺は今、申し訳ないがその約束に胸を張って分かったと言うことはできない」
ランドールのまさかの答えにソフィアは頭が真っ白になった。
自分の兄など適当にごまかしておけばいいものと思っていたが、ランドールもまた兄のように真剣な目をしていた。
「……まだ、ソフィアとの間にはお互いの考えの溝を埋めたり、俺のことを知ってもらったりソフィアのことをもっと知ったり、必要なことがたくさんあるんだ。今はまだ軽々しく言うことはできない。けれど、俺は……、ソフィアを……大切にしたい。傷つきやすくて強がりなソフィアを大切に包んであげたいと思っている」
ソフィアはランドールが言った言葉が信じられなかった。なぜそんな事を言うのだろう、これはごまかすための演技なのかと、どくどくと心臓がうるさく騒いでいた。
そして、ソフィアの胸に込み上げてきた震えるような喜び、それが何より信じられなかった。
「んー……。まぁ合格かな。一応兄として妹を守る騎士だったわけだから。その役目を簡単に譲るわけにはいかないしねー。まだ二人は足並みが揃っていないみたいだから、そこはしっかり話し合ってね」
「お兄様……」
いつもヘラヘラしていて頼りない兄だと思っていたが、ちゃんと見るところは見ていたし、ランドールの前でも怯むことなく挑んでいったその男らしさにソフィアは感動していた。
「あぁ!ソフィア…!たまらない!お兄ちゃんをそんな目で見てくれるなんて!」
「え…」
「あーもう!頬っぺたにキスしたい!ガブガブかぶりつきたい!さぁ兄と妹のスキンシップだよ。ソフィア!さぁおいで!」
「い……いやよ!行くわけないでしょう!」
ソフィアは兄の元から離れて、ランドールの方にかけよった。困惑するランドールに、さっさと行きましょうと声をかける。
「あ!そうだ、殿下!」
馬車まで走り出そうかというソフィアとランドールに向かって、ヘインズはしつこく声をかけてきた。仕方なく二人の足が止まった。
「いつか、妹を奪おうという男が出てきたら、これを言おうと決めていたんですよ。ソフィアのファーストキスの相手は俺なので!じゃよろしく!」
ぽかんとして思考が止まった二人に向かって、ヘインズはウィンクしながら手をヒラヒラと振って、屋敷に戻っていってしまった。
「……なんだあれは?本当にソフィアの兄か?」
「………のはずなんですけど」
強烈すぎる兄の勢いに押されながら、始終圧倒されてしまったが、そのおかげもあってか、二人の間にあったわだかまりはいつの間にか溶けているように感じた。
ソフィア行くぞと言って、ランドールが手を差し出してきた。
ソフィアはランドールの目を見つめ返して、その手に自分の手をゆっくり重ねたのだった。
□□□
「心配ない。もう、挨拶はすませたし、後は自由解散だ」
パーティー会場はお城からは少し離れたところに建っていて、お城までは豪華な薔薇が咲き誇る庭園が続いていた。
奥にいけば池があるらしく、時間があったらぜひ見てみたいとソフィアは眺めていた。
薔薇の回廊と言われる歩廊を二人で歩いていく。辺りは静かで虫の鳴き声が聞こえてくるだけだった。
「…先程は、取り乱してすまない。カルロスがソフィアに何かするとは思っていなかったが、どうしても気が立ってしまって……」
「他国へ行かれた使者からは、良いお返事が来ていないそうですね」
「ああ。カルロスから聞いたのか…、確かにその通りだ。それなんだが…実は…」
そう言ったまま、ランドールはまた考えるように黙りこんでしまった。なんとなく、気まずい沈黙が二人の間にながれた。
その時、何人かの話し声と楽しげに笑う声が聞こえてきた。
二人して急に聞こえてきた声に驚いて、回廊の端に逃れて隠れるように身を縮ませた。
「……あの、なぜ隠れる必要が…?普通に歩いているだけなので、堂々としていて問題ないのでは?」
「あっああ。そうだったな……」
ランドールの方を見上げると、思いのほか近い距離であったので、ソフィアの心臓はトクンと鳴った。
しかもその距離はゆっくりと近づいているように思えた。
「…ランドール様。どうして…そんなにこちらを…」
ランドールの目はソフィアを見つめて離さなかった。その視線の熱に気がついたとき、ソフィアは後戻りが出来ないところにいると感じた。
「…だめです。これ以上は…、戻れなくなります。私達は仮の…関係で…」
「ソフィア…」
続きの言葉を紡ぐ前に、ソフィアの唇はランドールの唇で塞がれた。
軽く触れるだけの優しいキス。
肩を押し返せばすぐに離れることができるだろう。
けれど、ランドールの唇は少し震えていて、ソフィアの強ばっていた体は自然と力が抜けていった。
わずかな時間重なってから、ランドールの唇はゆっくりと離れた。
結局目を閉じることもできずに、ソフィアはずっと目を開けたままだった。
近すぎてぼやけていた視界にランドールの瞳が見えて、そこに自分が映っているのが嘘みたいで不思議な光景だった。
「……すまない。ソフィア……俺は……」
苦しげに眉をひそめて、言葉を飲み込んだランドールは、ゆっくりとソフィアから離れて、先に戻ると言い残し、身を翻して足早に行ってしまった。
一人残されたソフィアは、呆然と立ち尽くしまい足が動かなかった。
月明かりの下、母が残してくれたという薄いピンクのドレスは白く光って見えた。
混じりけのない純粋な輝きは、自分の歩んできた過去を思うと眩しすぎて、しばらく目を開けることはできなかった。
□□
「たかがキス一つ。しかもちょっと触れただけよ。しっかりしなさい私!」
お城で開かれたパーティーの夜、不意にランドールとキスをしてしまった。
あの後は控え室に戻って着替えて、すぐ屋敷へ帰ってしまった。
帰りの馬車に乗っているときは、まるで夢から覚めたシンデレラのような気分だった。
思えばところどころ、ランドールの好意を感じるような視線を感じるときはあった。
それに気づかないふりをして、考えないようにしていた。
女性との交流が少なかったランドールが一緒に過ごすことで、ただ気持ちが引っ張られただけの一過性のものだろうと考えていた。
ここは多少の物事が分かっている立場として、冷静さを保ち正しい方向へ導いてあげるのが、自分があるべき姿だろうソフィアは思っている。
だがソフィアは、あの拙い子供のようなキスに動揺して、昨日からほとんど眠れていなかった。
激しくもなく、蕩けるようなものでもない、ただ触れただけの行為が、ソフィアの体に根をはってどこまでも伸びていくようだった。
休みは終わり、今日から学校であるのに、ソフィアのもやもやとした心は晴れない。
玄関で悶々としながら唸っていると、後ろからどうしたのと声をかけられた。
振り向くと、いつも仕事で早く出るはずの兄、ヘインズが立っていた。
「ソフィア、顔色が悪いよ。昨日はパーティーだったんだろう。無理はしていない?」
「……お兄様、大丈夫です。少し疲れているだけです」
「いや、しかし……」
ヘインズの話が終わらないうちに、迎えの馬車が来たと声がかけられた。
ヘインズも挨拶をするつもりなのだろう。ソフィアと一緒に玄関を出て馬車へ向かった。
「今日は仕事を遅らせてどうしても殿下にご挨拶したくて待っていたんだ」
「え…それは…そうですか」
またややこしいタイミングだとソフィアは軽く頭痛を覚えた。しかもヘインズは背中に手を回してきてベタベタとくっついてきたので、ソフィアは軽く睨み付けたが、ヘインズは逆に反応してくれて嬉しいみたいにニヤニヤと笑いだした。
「ちょっと!お兄様…、離して…」
「ソフィア、そちらは…?」
ヘインズと揉めていたら、なかなか来ないからかランドールが下りてきてしまった。
「これはこれは、わざわざありがとうございます殿下!私、ソフィアの兄のヘインズと申します!初めまして!」
「あっ…ああ」
ヘインズの場違いな明るさに、ランドールは若干引き気味に答えた。
「昨夜のパーティーには出席出来ず、申し訳ございませんでした。改めてお祝い申し上げます。うちの可愛い妹をどうぞよろしくお願いします」
「ああ、それなんだが……」
「ああ!!どうぞよろしくには色々な意味がありましてね。妹の将来を約束して頂いた殿下に私から一言よろしいでしょうか?」
異様なテンションとゴリ押しで、ランドールの言葉は封じられて、ヘインズが喋り続けている。まだ喋り足りないらしく、ランドールも驚きつつ、勢いに促されるように頷いた。
「妹は殿下の前では強がっているかもしれませんが、繊細で傷つきやすいです。もちろん、優しくて可愛い自慢の妹でありますが、そういう意味でまずよろしくという事と、うちは父が頼りにならないので、長男の私から言わせて頂きますが、中途半端に妹を弄ぶようなことをしたら、私は決して許さないです。と、いうことでどうぞよろしくお願いします」
今までヘラヘラとしていたくせに、急に真面目な顔になって、ヘインズは弾丸のようにランドールに向かって言葉を撃ち込んだ。
もちろん、ヘインズは仮の婚約者であることは知らない。昨日の今日で微妙な問題ではあるが、ランドールなら、この場を上手くごまかすように兄の言葉に了承してくれると思った。
しばらく考えるように下を向いて沈黙していたランドールだが、決意を込めたような目をしてヘインズに向き合った。
「……俺は今、申し訳ないがその約束に胸を張って分かったと言うことはできない」
ランドールのまさかの答えにソフィアは頭が真っ白になった。
自分の兄など適当にごまかしておけばいいものと思っていたが、ランドールもまた兄のように真剣な目をしていた。
「……まだ、ソフィアとの間にはお互いの考えの溝を埋めたり、俺のことを知ってもらったりソフィアのことをもっと知ったり、必要なことがたくさんあるんだ。今はまだ軽々しく言うことはできない。けれど、俺は……、ソフィアを……大切にしたい。傷つきやすくて強がりなソフィアを大切に包んであげたいと思っている」
ソフィアはランドールが言った言葉が信じられなかった。なぜそんな事を言うのだろう、これはごまかすための演技なのかと、どくどくと心臓がうるさく騒いでいた。
そして、ソフィアの胸に込み上げてきた震えるような喜び、それが何より信じられなかった。
「んー……。まぁ合格かな。一応兄として妹を守る騎士だったわけだから。その役目を簡単に譲るわけにはいかないしねー。まだ二人は足並みが揃っていないみたいだから、そこはしっかり話し合ってね」
「お兄様……」
いつもヘラヘラしていて頼りない兄だと思っていたが、ちゃんと見るところは見ていたし、ランドールの前でも怯むことなく挑んでいったその男らしさにソフィアは感動していた。
「あぁ!ソフィア…!たまらない!お兄ちゃんをそんな目で見てくれるなんて!」
「え…」
「あーもう!頬っぺたにキスしたい!ガブガブかぶりつきたい!さぁ兄と妹のスキンシップだよ。ソフィア!さぁおいで!」
「い……いやよ!行くわけないでしょう!」
ソフィアは兄の元から離れて、ランドールの方にかけよった。困惑するランドールに、さっさと行きましょうと声をかける。
「あ!そうだ、殿下!」
馬車まで走り出そうかというソフィアとランドールに向かって、ヘインズはしつこく声をかけてきた。仕方なく二人の足が止まった。
「いつか、妹を奪おうという男が出てきたら、これを言おうと決めていたんですよ。ソフィアのファーストキスの相手は俺なので!じゃよろしく!」
ぽかんとして思考が止まった二人に向かって、ヘインズはウィンクしながら手をヒラヒラと振って、屋敷に戻っていってしまった。
「……なんだあれは?本当にソフィアの兄か?」
「………のはずなんですけど」
強烈すぎる兄の勢いに押されながら、始終圧倒されてしまったが、そのおかげもあってか、二人の間にあったわだかまりはいつの間にか溶けているように感じた。
ソフィア行くぞと言って、ランドールが手を差し出してきた。
ソフィアはランドールの目を見つめ返して、その手に自分の手をゆっくり重ねたのだった。
□□□
1
お気に入りに追加
117
あなたにおすすめの小説

悪役令嬢は皇帝の溺愛を受けて宮入りする~夜も放さないなんて言わないで~
sweetheart
恋愛
公爵令嬢のリラ・スフィンクスは、婚約者である第一王子セトから婚約破棄を言い渡される。
ショックを受けたリラだったが、彼女はある夜会に出席した際、皇帝陛下である、に見初められてしまう。
そのまま後宮へと入ることになったリラは、皇帝の寵愛を受けるようになるが……。
「悪役令嬢は溺愛されて幸せになる」というテーマで描かれるラブロマンスです。
主人公は平民出身で、貴族社会に疎いヒロインが、皇帝陛下との恋愛を通じて成長していく姿を描きます。
また、悪役令嬢として成長した彼女が、婚約破棄された後にどのような運命を辿るのかも見どころのひとつです。
なお、後宮で繰り広げられる様々な事件や駆け引きが描かれていますので、シリアスな展開も楽しめます。
以上のようなストーリーになっていますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。


転生したらただの女子生徒Aでしたが、何故か攻略対象の王子様から溺愛されています
平山和人
恋愛
平凡なOLの私はある日、事故にあって死んでしまいました。目が覚めるとそこは知らない天井、どうやら私は転生したみたいです。
生前そういう小説を読みまくっていたので、悪役令嬢に転生したと思いましたが、実際はストーリーに関わらないただの女子生徒Aでした。
絶望した私は地味に生きることを決意しましたが、なぜか攻略対象の王子様や悪役令嬢、更にヒロインにまで溺愛される羽目に。
しかも、私が聖女であることも判明し、国を揺るがす一大事に。果たして、私はモブらしく地味に生きていけるのでしょうか!?

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

悪役令嬢はオッサンフェチ。
来栖もよもよ&来栖もよりーぬ
恋愛
侯爵令嬢であるクラリッサは、よく読んでいた小説で悪役令嬢であった前世を突然思い出す。
何故自分がクラリッサになったかどうかは今はどうでも良い。
ただ婚約者であるキース王子は、いわゆる細身の優男系美男子であり、万人受けするかも知れないが正直自分の好みではない。
ヒロイン的立場である伯爵令嬢アンナリリーが王子と結ばれるため、私がいじめて婚約破棄されるのは全く問題もないのだが、意地悪するのも気分が悪いし、家から追い出されるのは困るのだ。
だって私が好きなのは執事のヒューバートなのだから。
それならさっさと婚約破棄して貰おう、どうせ二人が結ばれるなら、揉め事もなく王子がバカを晒すこともなく、早い方が良いものね。私はヒューバートを落とすことに全力を尽くせるし。
……というところから始まるラブコメです。
悪役令嬢といいつつも小説の設定だけで、計算高いですが悪さもしませんしざまあもありません。単にオッサン好きな令嬢が、防御力高めなマッチョ系執事を落とすためにあれこれ頑張るというシンプルなお話です。

ある王国の王室の物語
朝山みどり
恋愛
平和が続くある王国の一室で婚約者破棄を宣言された少女がいた。カップを持ったまま下を向いて無言の彼女を国王夫妻、侯爵夫妻、王太子、異母妹がじっと見つめた。
顔をあげた彼女はカップを皿に置くと、レモンパイに手を伸ばすと皿に取った。
それから
「承知しました」とだけ言った。
ゆっくりレモンパイを食べるとお茶のおかわりを注ぐように侍女に合図をした。
それからバウンドケーキに手を伸ばした。
カクヨムで公開したものに手を入れたものです。
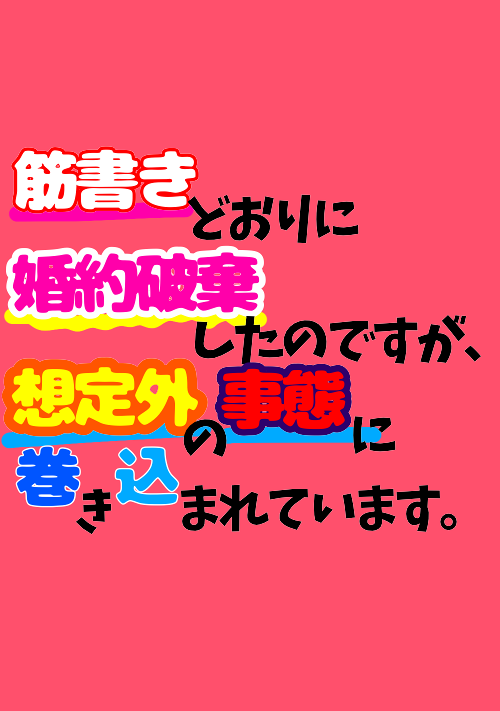
筋書きどおりに婚約破棄したのですが、想定外の事態に巻き込まれています。
一花カナウ
恋愛
第二王子のヨハネスと婚約が決まったとき、私はこの世界が前世で愛読していた物語の世界であることに気づく。
そして、この婚約がのちに解消されることも思い出していた。
ヨハネスは優しくていい人であるが、私にはもったいない人物。
慕ってはいても恋には至らなかった。
やがて、婚約破棄のシーンが訪れる。
私はヨハネスと別れを告げて、新たな人生を歩みだす
――はずだったのに、ちょっと待って、ここはどこですかっ⁉︎
しかも、ベッドに鎖で繋がれているんですけどっ⁉︎
困惑する私の前に現れたのは、意外な人物で……
えっと、あなたは助けにきたわけじゃなくて、犯人ってことですよね?
※ムーンライトノベルズで公開中の同名の作品に加筆修正(微調整?)したものをこちらで掲載しています。
※pixivにも掲載。
8/29 15時台HOTランキング 5位、恋愛カテゴリー3位ありがとうございます( ´ ▽ ` )ノノΞ❤︎{活力注入♪)

婚約破棄寸前の悪役令嬢に転生したはずなのに!?
もふきゅな
恋愛
現代日本の普通一般人だった主人公は、突然異世界の豪華なベッドで目を覚ます。鏡に映るのは見たこともない美しい少女、アリシア・フォン・ルーベンス。悪役令嬢として知られるアリシアは、王子レオンハルトとの婚約破棄寸前にあるという。彼女は、王子の恋人に嫌がらせをしたとされていた。
王子との初対面で冷たく婚約破棄を告げられるが、美咲はアリシアとして無実を訴える。彼女の誠実な態度に次第に心を開くレオンハルト
悪役令嬢としてのレッテルを払拭し、彼と共に幸せな日々を歩もうと試みるアリシア。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















