24 / 26
トラック2:学校の中の自分と家の中の自分は、性格が全く違うことがある
初めての拒絶
しおりを挟む
悩みを玲緒奈と香奈美に打ち明けてから数分、俺は近くのコンビニで辛子明太子おにぎりと温かいほうじ茶を買い、一息ついていた。
海苔と白米の素朴な味の中から、突如口の中に広がるパンチの効いた明太子の辛味。
明太子だけでご飯三杯は食える。
ほうじ茶をごくりと飲む。
おにぎりの軟らかい食感の中に流れるほうじ茶は、甘さと苦さを兼ね備え、相性は抜群。
勿論緑茶でも全然美味しく食べられるが、俺は断然ほうじ茶派だ。
と、そんな中ポケットの中に入れていた携帯が振動した。
見ると、お袋から一通のNINEが受信された。
『紗彩ちゃん、具合悪そうにしてる。早く帰ってあげて』
俺は、手に持っていた残りのおにぎりを急いで口に放り込んだ。
いきなりえづいてしまったものの、何とか凝縮された白米の塊を一噛み一噛み味わい、飲みこむことができた。
すぐさまサドルに跨り、重いペダルに全体重をかけるように漕ぐ。
だが一昨日の自分ほどではない。
あくまでも急がず焦らずの精神で帰宅した。
部屋に戻ると、紗彩は息苦しそうにしながら、俺の机にぐったりしていた。
机の上には、教科書と問題集がびっしり並んでいる。
「あぁ…、おかえりぃ」
蚊の鳴くような声で、ただひたすらに弱々しかった。
「おい紗彩、具合大丈夫なのか?」
若干自分も呼吸が荒かったが、紗彩の呼吸の荒さとは全く意味が違う。
「だ、大丈夫、平気だよ。だって、こんなにピンピンしてる」
そう言いながら紗彩は、どこかの筋肉エリートのように上腕二頭筋を見せつけてきた。だがその腕は細くてとても弱々しく、何だか見てるこっちが悲しい気分になってきてしまう。
「いやいや、どこもかしこも元気そうになんか見えないから」頭を振りながら、俺は言った。「熱はあるのか?」
「そういえば、何か熱いかも……」
その瞬間、紗彩の頭が前にふらつき始めたので、すかさず俺は、自分のおでこと紗彩のおでこを合わせた。「ひゃっ」と紗彩は、可愛い悲鳴を上げて驚いていたが、そんなのはお構いなしに、俺は彼女の熱を確かめた。
「…すごい熱じゃないか。何でこんなになるまで」
体感で38度はあるだろうか。中々の高温だった。
「何かくらくらしてきた。あれ、そういえば芳ちゃん、何でわたしを見てすぐ身体の具合聞いて……?」
そんな意識が朦朧としている紗彩の様子に俺は構わず、
「とにかく今日はもう寝るぞ」
と、紗彩の身体を持ち上げようとした。
だが、彼女はテーブルに接着剤でもつけたかのようにびったり離そうとしない。
それは初めての俺への拒絶だった。
「……やだ」
俺に顔を合わせることなく、頑なに寝ようとしてくれない。
「何言ってんだ紗彩。ひどい熱だぞ。そんなんで勉強しても身に着くわけなんかない」
英語に数学に日本史に物理。
古今東西の教科を一気に頭に入れるのなんて、無茶にもほどがある。俺だったら一瞬で頭がパンクする。
それに、ここ数日異様に寒い日が続いている。体調管理をするのも立派な勉強の一環だ。
自分にもブーメランのように突き刺さりながら、今一度心の中で反芻する。
「だめ…やめて」
相も変わらず紗彩は、机にひっついたばかりで動こうとしない。
そんな紗彩に俺は、
「いいから早く寝————」
と、再び彼女の小柄で華奢な身体を持ち上げようとしたが、途中で思い留まった。
精神が不安定な人に無理やり何かさせるのというのは、絶対にしてはいけないと本能が語ったからだ。
まるで自分の思い通りに生徒を操りたいだけの、一昔前の殴ることでストレスを解消する傲慢な先公のようで、思わず吐き気が出そうになる。
あくまでも彼女に寄り添ってあげて、想いを尊重すること。
今はそれが、一番必要だと直感した。
「何でそんな頑なに休もうとしないんだ?」
俺は、紗彩と目を合わせて聞く。
「だってわたしは……」紗彩がすっと息を吸い込む。「みんなより遅れてるから」
「みんなより遅れてる?」
俺は、紗彩の心意が分からず、語尾を疑問にして復唱し、彼女の心中を一言も余すことなく耳を傾けた。
「わたしは、芳ちゃんみたいに普通に学校に通うことができてないから。わたしには、半年以上通えていないブランクがある。だからこそ、遅れを取り戻さないといけない。でも高校での半年の遅れというのが、どれほど致命的かって考えれば考えるほど恐ろしくなってきて、いてもたってもいられない。高校の教科って中学の時と比べるとすごい多い。そんな中で全く進んでないのって、どう考えたってまずい。だからわたしは、普通の高校生に追いつけるように一分一秒も惜しんで勉強しないと……」
「そうだったのか」
紗彩が何故具合が悪くなってまで勉強を続けるのか、俺はようやく理解できた。
中学の不登校とはわけが違う。高校だと遅れの問題がすぐに浮上する。
目まぐるしい進みの速さ。授業を聞けば聞くほど全く違う内容を学習する。優秀な生徒は、授業を真面目に聞くだけでその範囲を習得できるというが、不器用な俺にはそんなのは到底出来るはずがなかった。今でも苦手な教科には遅れをとっている。
紗彩においては、その遅れが半年以上も続いているという計算になる。おびただしい程の教科数を数えると、自分も気が遠くなってきた。
結局俺は、当事者側に立って考えることができないままだった。
よく一人の女の子を救うなんて大言壮語を言ったものだ。自分が恥ずかしく思えて仕方なくなった。
そんな中でも、これだけは言えた。
俺は紗彩から顔を伏せる。
「でもさ、何も睡眠時間削ってまで取り組むのは逆効果だ。定期テストのように短期間の暗記なら良いかもしれないけど」
「そ、そうだね」
「受験勉強のような勉強尽くしなら規則正しく生活を送るべきだ。それに、現に紗彩は絶賛体調不良中だから、今だけは自分の体調に一番気を付けてほしい」
「……」
そして俺は最後にこう言った。
「大丈夫だ、紗彩なら。難関の公立高校にも受かった経験がある。お前の地頭の良さなら、あっという間に俺達通学勢に追いつけるさ」
「…わたしなら、できるかな?」
「ああ、できるさ! 俺が保証する!」
そう俺は、紗彩に向けて親指を立ててグッドサインした。
少し煮え切らない表情もあったものの、忽ち紗彩ははにかんだ様子で俺に顔を向けた。
「芳ちゃんがそこまで信じてくれるなら、悪い気がしないかも。言う通り、今日は早く寝るね」
机から離れ、着替える準備をするようになった。
「ありがとな。こんな素直になってくれるなんて、正直思っていなかった」
「もー。わたしがこうやって素直になる理由なんて、ひとつに決まってるじゃん」
紗彩が、子動物のような頬袋で、可愛く顔を膨らませてきた。
「え、何その理由って……?」
あまりにもその答えが分からず、きょとんとした表情を我慢して隠そうとしたが、それでも顔一面に出てしまった。
「勘の鈍い人には、教えられません」
そう言い残して、半ば上機嫌に寝間着の着替えを持って部屋を去っていった。
紗彩が素直になれる理由。
一晩中探っても、俺にはその答えが出てくることはなかった。
海苔と白米の素朴な味の中から、突如口の中に広がるパンチの効いた明太子の辛味。
明太子だけでご飯三杯は食える。
ほうじ茶をごくりと飲む。
おにぎりの軟らかい食感の中に流れるほうじ茶は、甘さと苦さを兼ね備え、相性は抜群。
勿論緑茶でも全然美味しく食べられるが、俺は断然ほうじ茶派だ。
と、そんな中ポケットの中に入れていた携帯が振動した。
見ると、お袋から一通のNINEが受信された。
『紗彩ちゃん、具合悪そうにしてる。早く帰ってあげて』
俺は、手に持っていた残りのおにぎりを急いで口に放り込んだ。
いきなりえづいてしまったものの、何とか凝縮された白米の塊を一噛み一噛み味わい、飲みこむことができた。
すぐさまサドルに跨り、重いペダルに全体重をかけるように漕ぐ。
だが一昨日の自分ほどではない。
あくまでも急がず焦らずの精神で帰宅した。
部屋に戻ると、紗彩は息苦しそうにしながら、俺の机にぐったりしていた。
机の上には、教科書と問題集がびっしり並んでいる。
「あぁ…、おかえりぃ」
蚊の鳴くような声で、ただひたすらに弱々しかった。
「おい紗彩、具合大丈夫なのか?」
若干自分も呼吸が荒かったが、紗彩の呼吸の荒さとは全く意味が違う。
「だ、大丈夫、平気だよ。だって、こんなにピンピンしてる」
そう言いながら紗彩は、どこかの筋肉エリートのように上腕二頭筋を見せつけてきた。だがその腕は細くてとても弱々しく、何だか見てるこっちが悲しい気分になってきてしまう。
「いやいや、どこもかしこも元気そうになんか見えないから」頭を振りながら、俺は言った。「熱はあるのか?」
「そういえば、何か熱いかも……」
その瞬間、紗彩の頭が前にふらつき始めたので、すかさず俺は、自分のおでこと紗彩のおでこを合わせた。「ひゃっ」と紗彩は、可愛い悲鳴を上げて驚いていたが、そんなのはお構いなしに、俺は彼女の熱を確かめた。
「…すごい熱じゃないか。何でこんなになるまで」
体感で38度はあるだろうか。中々の高温だった。
「何かくらくらしてきた。あれ、そういえば芳ちゃん、何でわたしを見てすぐ身体の具合聞いて……?」
そんな意識が朦朧としている紗彩の様子に俺は構わず、
「とにかく今日はもう寝るぞ」
と、紗彩の身体を持ち上げようとした。
だが、彼女はテーブルに接着剤でもつけたかのようにびったり離そうとしない。
それは初めての俺への拒絶だった。
「……やだ」
俺に顔を合わせることなく、頑なに寝ようとしてくれない。
「何言ってんだ紗彩。ひどい熱だぞ。そんなんで勉強しても身に着くわけなんかない」
英語に数学に日本史に物理。
古今東西の教科を一気に頭に入れるのなんて、無茶にもほどがある。俺だったら一瞬で頭がパンクする。
それに、ここ数日異様に寒い日が続いている。体調管理をするのも立派な勉強の一環だ。
自分にもブーメランのように突き刺さりながら、今一度心の中で反芻する。
「だめ…やめて」
相も変わらず紗彩は、机にひっついたばかりで動こうとしない。
そんな紗彩に俺は、
「いいから早く寝————」
と、再び彼女の小柄で華奢な身体を持ち上げようとしたが、途中で思い留まった。
精神が不安定な人に無理やり何かさせるのというのは、絶対にしてはいけないと本能が語ったからだ。
まるで自分の思い通りに生徒を操りたいだけの、一昔前の殴ることでストレスを解消する傲慢な先公のようで、思わず吐き気が出そうになる。
あくまでも彼女に寄り添ってあげて、想いを尊重すること。
今はそれが、一番必要だと直感した。
「何でそんな頑なに休もうとしないんだ?」
俺は、紗彩と目を合わせて聞く。
「だってわたしは……」紗彩がすっと息を吸い込む。「みんなより遅れてるから」
「みんなより遅れてる?」
俺は、紗彩の心意が分からず、語尾を疑問にして復唱し、彼女の心中を一言も余すことなく耳を傾けた。
「わたしは、芳ちゃんみたいに普通に学校に通うことができてないから。わたしには、半年以上通えていないブランクがある。だからこそ、遅れを取り戻さないといけない。でも高校での半年の遅れというのが、どれほど致命的かって考えれば考えるほど恐ろしくなってきて、いてもたってもいられない。高校の教科って中学の時と比べるとすごい多い。そんな中で全く進んでないのって、どう考えたってまずい。だからわたしは、普通の高校生に追いつけるように一分一秒も惜しんで勉強しないと……」
「そうだったのか」
紗彩が何故具合が悪くなってまで勉強を続けるのか、俺はようやく理解できた。
中学の不登校とはわけが違う。高校だと遅れの問題がすぐに浮上する。
目まぐるしい進みの速さ。授業を聞けば聞くほど全く違う内容を学習する。優秀な生徒は、授業を真面目に聞くだけでその範囲を習得できるというが、不器用な俺にはそんなのは到底出来るはずがなかった。今でも苦手な教科には遅れをとっている。
紗彩においては、その遅れが半年以上も続いているという計算になる。おびただしい程の教科数を数えると、自分も気が遠くなってきた。
結局俺は、当事者側に立って考えることができないままだった。
よく一人の女の子を救うなんて大言壮語を言ったものだ。自分が恥ずかしく思えて仕方なくなった。
そんな中でも、これだけは言えた。
俺は紗彩から顔を伏せる。
「でもさ、何も睡眠時間削ってまで取り組むのは逆効果だ。定期テストのように短期間の暗記なら良いかもしれないけど」
「そ、そうだね」
「受験勉強のような勉強尽くしなら規則正しく生活を送るべきだ。それに、現に紗彩は絶賛体調不良中だから、今だけは自分の体調に一番気を付けてほしい」
「……」
そして俺は最後にこう言った。
「大丈夫だ、紗彩なら。難関の公立高校にも受かった経験がある。お前の地頭の良さなら、あっという間に俺達通学勢に追いつけるさ」
「…わたしなら、できるかな?」
「ああ、できるさ! 俺が保証する!」
そう俺は、紗彩に向けて親指を立ててグッドサインした。
少し煮え切らない表情もあったものの、忽ち紗彩ははにかんだ様子で俺に顔を向けた。
「芳ちゃんがそこまで信じてくれるなら、悪い気がしないかも。言う通り、今日は早く寝るね」
机から離れ、着替える準備をするようになった。
「ありがとな。こんな素直になってくれるなんて、正直思っていなかった」
「もー。わたしがこうやって素直になる理由なんて、ひとつに決まってるじゃん」
紗彩が、子動物のような頬袋で、可愛く顔を膨らませてきた。
「え、何その理由って……?」
あまりにもその答えが分からず、きょとんとした表情を我慢して隠そうとしたが、それでも顔一面に出てしまった。
「勘の鈍い人には、教えられません」
そう言い残して、半ば上機嫌に寝間着の着替えを持って部屋を去っていった。
紗彩が素直になれる理由。
一晩中探っても、俺にはその答えが出てくることはなかった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説


M性に目覚めた若かりしころの思い出
kazu106
青春
わたし自身が生涯の性癖として持ち合わせるM性について、それをはじめて自覚した中学時代の体験になります。歳を重ねた者の、人生の回顧録のひとつとして、読んでいただけましたら幸いです。
一部、フィクションも交えながら、述べさせていただいてます。フィクション/ノンフィクションの境界は、読んでくださった方の想像におまかせいたします。

やくびょう神とおせっかい天使
倉希あさし
青春
一希児雄(はじめきじお)名義で執筆。疫病神と呼ばれた少女・神崎りこは、誰も不幸に見舞われないよう独り寂しく過ごしていた。ある日、同じクラスの少女・明星アイリがりこに話しかけてきた。アイリに不幸が訪れないよう避け続けるりこだったが…。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ただの黒歴史
鹿又杏奈\( ᐛ )/
青春
青春ジャンルではありますが、書き手の青春的な意味で高校時代に書いたポエムとかお話とかそういったものを成仏させようかと思ってます。
授業中に書いてたヤツなので紙媒体から打ち込むのに時間がかかるとは思いますが、暇であったら覗いて見て下さい。
偶に現在のも混ぜときます笑

燦歌を乗せて
河島アドミ
青春
「燦歌彩月第六作――」その先の言葉は夜に消える。
久慈家の名家である天才画家・久慈色助は大学にも通わず怠惰な毎日をダラダラと過ごす。ある日、久慈家を勘当されホームレス生活がスタートすると、心を奪われる被写体・田中ゆかりに出会う。
第六作を描く。そう心に誓った色助は、己の未熟とホームレス生活を満喫しながら作品へ向き合っていく。

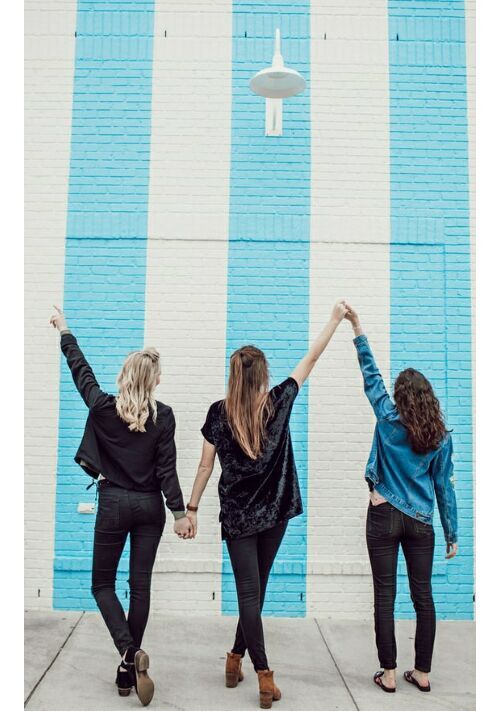
女子高生は小悪魔だ~教師のボクはこんな毎日送ってます
藤 ゆう
青春
ボクはある私立女子高の体育教師。大学をでて、初めての赴任だった。
「男子がいないからなぁ、ブリっ子もしないし、かなり地がでるぞ…おまえ食われるなよ(笑)」
先輩に聞いていたから少しは身構えていたけれど…
色んな(笑)事件がまきおこる。
どこもこんなものなのか?
新米のボクにはわからないけれど、ついにスタートした可愛い小悪魔たちとの毎日。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















