お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

クラス転移で無能判定されて追放されたけど、努力してSSランクのチートスキルに進化しました~【生命付与】スキルで異世界を自由に楽しみます~
いちまる
ファンタジー
ある日、クラスごと異世界に召喚されてしまった少年、天羽イオリ。
他のクラスメートが強力なスキルを発現させてゆく中、イオリだけが最低ランクのEランクスキル【生命付与】の持ち主だと鑑定される。
「無能は不要だ」と判断した他の生徒や、召喚した張本人である神官によって、イオリは追放され、川に突き落とされた。
しかしそこで、川底に沈んでいた謎の男の力でスキルを強化するチャンスを得た――。
1千年の努力とともに、イオリのスキルはSSランクへと進化!
自分を拾ってくれた田舎町のアイテムショップで、チートスキルをフル稼働!
「転移者が世界を良くする?」
「知らねえよ、俺は異世界を自由気ままに楽しむんだ!」
追放された少年の第2の人生が、始まる――!
※本作品は他サイト様でも掲載中です。

勇者召喚に巻き込まれ、異世界転移・貰えたスキルも鑑定だけ・・・・だけど、何かあるはず!
よっしぃ
ファンタジー
9月11日、12日、ファンタジー部門2位達成中です!
僕はもうすぐ25歳になる常山 順平 24歳。
つねやま じゅんぺいと読む。
何処にでもいる普通のサラリーマン。
仕事帰りの電車で、吊革に捕まりうつらうつらしていると・・・・
突然気分が悪くなり、倒れそうになる。
周りを見ると、周りの人々もどんどん倒れている。明らかな異常事態。
何が起こったか分からないまま、気を失う。
気が付けば電車ではなく、どこかの建物。
周りにも人が倒れている。
僕と同じようなリーマンから、数人の女子高生や男子学生、仕事帰りの若い女性や、定年近いおっさんとか。
気が付けば誰かがしゃべってる。
どうやらよくある勇者召喚とやらが行われ、たまたま僕は異世界転移に巻き込まれたようだ。
そして・・・・帰るには、魔王を倒してもらう必要がある・・・・と。
想定外の人数がやって来たらしく、渡すギフト・・・・スキルらしいけど、それも数が限られていて、勇者として召喚した人以外、つまり巻き込まれて転移したその他大勢は、1人1つのギフト?スキルを。あとは支度金と装備一式を渡されるらしい。
どうしても無理な人は、戻ってきたら面倒を見ると。
一方的だが、日本に戻るには、勇者が魔王を倒すしかなく、それを待つのもよし、自ら勇者に協力するもよし・・・・
ですが、ここで問題が。
スキルやギフトにはそれぞれランク、格、強さがバラバラで・・・・
より良いスキルは早い者勝ち。
我も我もと群がる人々。
そんな中突き飛ばされて倒れる1人の女性が。
僕はその女性を助け・・・同じように突き飛ばされ、またもや気を失う。
気が付けば2人だけになっていて・・・・
スキルも2つしか残っていない。
一つは鑑定。
もう一つは家事全般。
両方とも微妙だ・・・・
彼女の名は才村 友郁
さいむら ゆか。 23歳。
今年社会人になりたて。
取り残された2人が、すったもんだで生き残り、最終的には成り上がるお話。

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる
農民ヤズ―
ファンタジー
「ようこそおいでくださいました。勇者さま」
そんな言葉から始まった異世界召喚。
呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?
そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!
このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。
勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定
私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。
ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。
他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。
なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。
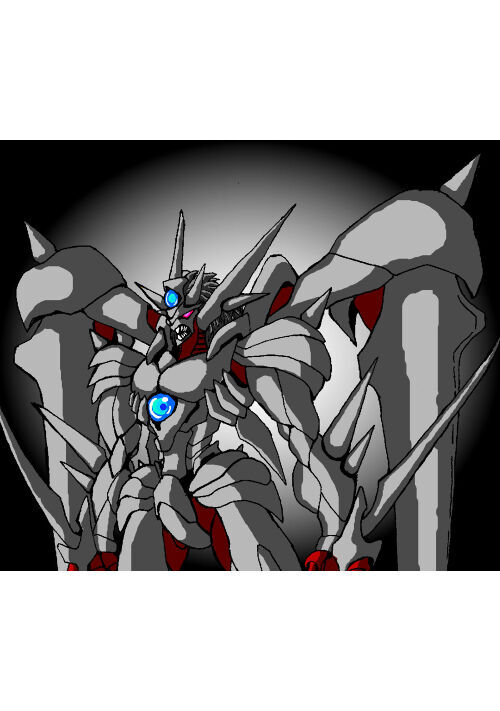
召喚魔王様がんばる
雑草弁士
ファンタジー
世界制覇を狙う悪の秘密結社の生み出した改造人間である主人公は、改造完了直後突然に異世界へと召喚されてしまう。しかもなんと『魔王』として!
そして彼は『勇者』の少女と出会ったり、敵対的な魔物たちを下して魔王軍を創ったり……。召喚された異世界で、彼はがんばって働き続ける。目標は世界征服!?
とりあえず、何も考えてない異世界ファンタジー物です。お楽しみいただければ、幸いです。

サモンブレイブ・クロニクル~無能扱いされた少年の異世界無双物語
イズミント(エセフォルネウス)
ファンタジー
高校2年の佐々木 暁斗は、クラスメイト達と共に異世界に召還される。
その目的は、魔王を倒す戦力として。
しかし、クラスメイトのみんなが勇者判定されるなかで、暁斗だけは勇者判定されず、無能とされる。
多くのクラスメイトにも見捨てられた暁斗は、唯一見捨てず助けてくれた女子生徒や、暁斗を介抱した魔女と共に異世界生活を送る。
その過程で、暁斗の潜在能力が発揮され、至るところで無双していくお話である。
*この作品はかつてノベルアップ+や小説家になろうに投稿したものの再々リメイクです。

目立ちたくない召喚勇者の、スローライフな(こっそり)恩返し
gari
ファンタジー
突然、異世界の村に転移したカズキは、村長父娘に保護された。
知らない間に脳内に寄生していた自称大魔法使いから、自分が召喚勇者であることを知るが、庶民の彼は勇者として生きるつもりはない。
正体がバレないようギルドには登録せず一般人としてひっそり生活を始めたら、固有スキル『蚊奪取』で得た規格外の能力と(この世界の)常識に疎い行動で逆に目立ったり、村長の娘と徐々に親しくなったり。
過疎化に悩む村の窮状を知り、恩返しのために温泉を開発すると見事大当たり! でも、その弊害で恩人父娘が窮地に陥ってしまう。
一方、とある国では、召喚した勇者(カズキ)の捜索が密かに行われていた。
父娘と村を守るため、武闘大会に出場しよう!
地域限定土産の開発や冒険者ギルドの誘致等々、召喚勇者の村おこしは、従魔や息子(?)や役人や騎士や冒険者も加わり順調に進んでいたが……
ついに、居場所が特定されて大ピンチ!!
どうする? どうなる? 召喚勇者。
※ 基本は主人公視点。時折、第三者視点が入ります。

何者でもない僕は異世界で冒険者をはじめる
月風レイ
ファンタジー
あらゆることを人より器用にこなす事ができても、何の長所にもなくただ日々を過ごす自分。
周りの友人は世界を羽ばたくスターになるのにも関わらず、自分はただのサラリーマン。
そんな平凡で退屈な日々に、革命が起こる。
それは突如現れた一枚の手紙だった。
その手紙の内容には、『異世界に行きますか?』と書かれていた。
どうせ、誰かの悪ふざけだろうと思い、適当に異世界にでもいけたら良いもんだよと、考えたところ。
突如、異世界の大草原に召喚される。
元の世界にも戻れ、無限の魔力と絶対不死身な体を手に入れた冒険が今始まる。

大工スキルを授かった貧乏貴族の養子の四男だけど、どうやら大工スキルは伝説の全能スキルだったようです
飼猫タマ
ファンタジー
田舎貴族の四男のヨナン・グラスホッパーは、貧乏貴族の養子。義理の兄弟達は、全員戦闘系のレアスキル持ちなのに、ヨナンだけ貴族では有り得ない生産スキルの大工スキル。まあ、養子だから仕方が無いんだけど。
だがしかし、タダの生産スキルだと思ってた大工スキルは、じつは超絶物凄いスキルだったのだ。その物凄スキルで、生産しまくって超絶金持ちに。そして、婚約者も出来て幸せ絶頂の時に嵌められて、人生ドン底に。だが、ヨナンは、有り得ない逆転の一手を持っていたのだ。しかも、その有り得ない一手を、本人が全く覚えてなかったのはお約束。
勿論、ヨナンを嵌めた奴らは、全員、ザマー百裂拳で100倍返し!
そんなお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















