1 / 4
第一話 須古銀次といふ者
しおりを挟むその者は、爺のように白髪らしい。
その者は、獣のように鋭い目をしているらしい。
その者は、鬼のように笑わないらしい。
その者は、拡声器を使っているように声が大きいらしい。
その者は、巨人のように背が高いらしい。
だから、その者は、白鬼と呼ばれている。
けふ、須古銀次に會ひました。
一九四四年。
戦争。
特別攻撃隊が現れる前のこと。
日中の暑さが残る深夜。雲に邪魔をされ、月の光が地に届かず、寂しそうに顔を覗かせる。その下で、様々な虫や鳥達が楽しそうに鳴いていた。
海軍の航空隊がある基地に、須古銀次という名の男が部屋にいた。
小さな部屋は殺風景で物が少なく、最低限の机と椅子、そして棚があるくらいだ。窓から覗けば、戦闘機が眠る掩体壕が見えた。
机に向かう須古の身なりは、汚れひとつない純白な軍服。詰め襟に、五つ釦、そして肩には桜が三つ並ぶ肩章。
彼は、小刀で綺麗に削った鉛筆を紙の上で走らせる。時折「くだらんな」と漏らしながら、書類にひたすら鉛筆を走らせていた。
耳を澄ませば、酒を飲み交わし、愉しそうに会話をする仲間の声が聴こえる。そんな中、騒がしい足音達が近づいてきた。
木の床がみしみしと鳴り、またかと思いながら、須古は溜息を吐く。金属がぶつかり合う音も聴こえ、片眉を上げた。
二人分の足音は、部屋のドアの前で消える。
律儀にノックをする相手に、須古は「はい」と返事をした。
ドアを開けた者は、カーキ色の軍服を着た二人組。きびきびとした動きで、脇を広げる陸軍式の敬礼をする。
「分隊長の一憲兵大尉だ。ここに〝二匹のネズミ〟が入ってきたはず。その二人を早々に引き渡してほしい」
詳しい理由を言わず、更にその言葉遣いは須古を見下している。
須古は片眉を寄せた。だが、彼は瞬き一つで不愉快な顔を消すと、一度立ち上がり、脇をしめた海軍式の敬礼を返した。
「〝ネズミ〟ですか。見ての通り、ここは古い基地ですから、ネズミなんて数え切れないくらいいますよ。それでは、まだ業務が残っているので失礼」
そう言って、座り直す。
二人組は白い布地に『憲兵』と書かれた赤字の憲兵腕章、腰元にはサーベルの軍刀を掲げている。
ああ、やはり憲兵だったかと思っていると、一は不愉快そうな表情を浮かべ、舌打ちをした。
「腑抜けたことを言う気か。ここにいるのはわかっている。さっさと引き渡せ!」
声を荒げたところで、須古は再び立ち上がる。木製の椅子をゆっくりと引きずる音が、妙に耳にまとわりついた。
「どこへ行っても、憲兵という者は、偉そうな言葉でものを言うのだな」
腰元にぶら下げた短刀に手を置き、ゆっくりと憲兵の前まで歩いた。
「突然やって来て引き渡せ? 一体、誰を?」
その問いに、一は間髪入れずに答えた。
「彼杵兵長と馬見上等兵だ! 我々に喧嘩をふっかけてきやがったのは軍法会議もの。ただちに引き渡せ!」
「引き渡せ引き渡せ煩いな。ったく」
面倒臭そうに頭を乱暴に掻いていると、一は「白髪か?」と呟いた。
今更かよと、須古は呆れながら思う。「俺は須古大尉だ」
「ああ、あの須古大尉殿か。ふん。なにが白鬼か。ただの爺——」
「それは」
ギラリと鋭利に輝く、須古の眼差し。それを見た一は畏怖するように、口が止まる。
「正義なのか」
薄い茶の瞳が金のように光っているように見え、更に一は動揺した。
「それだけを聞けば、彼杵と馬見が悪いことをしたように思えるが、その前にはなにがあった?」
じりじりと近寄る。
「まさか、先に手を出したのは憲兵さんじゃあ、ありませんよね」
「道端で! け、敬礼をしなかった奴らが悪い!」
「謝ったんじゃないのですか?」
「それは……」
言葉を濁す。答えられないということは、敬礼をしなかったことへの謝罪はきちんとしたのだ。それで済ませばよかったものの、血気盛んな軍人達は喧嘩をおっ始める。大体の流れが見えてきた。
須古はニヤリと不気味に笑う。
「土下座までして謝ったにもかかわらず、不当な暴力。そこに、正義はあったのか?」
刃のように鋭利な雰囲気に飲み込まれるように、一は最初の勢いが消失し、怖気づいた。『正義』という言葉が頭の中にひっそりと植え付けられ、少しずつその存在が大きくなっていく。だが、それを掻き消すように頭を大きく振った。
「ど、土下座をしたことを知っているのなら——」
吠える一に向かって、須古は威圧的に壁を叩く。
身長の高い須古は、自然に憲兵達を見下ろす形になった。
「ここにいたとしても引き渡さない。こちらで処理する」
ハッキリと耳の奥まで響く声。憲兵達は臆したように体を震わせた。ガチャリと軍刀が揺れる。
「お引き取り願おうか」
海軍としての短剣には武器の意味は小さい。
短剣には海軍としての誇りと栄誉が込められている。そして、彼にとっては、常に正しき道を選べと、上官から教えられた言葉が含まれている。
威嚇とも捉えられる須古の態度に、憲兵達は屈辱に塗れた表情を浮かべて、その場から離れた。
帰ってきた静寂に、須古は机に目をやる。そして、静かにドアを閉めて、机下を覗いた。
「あ! ——」
机下に隠れていた二人が大きく口を開くものだから、須古はすぐに唇に立てた人差し指を添える。
「そろそろ時間だから、俺は出る。貴様らはそこで大人しくしてろ。目を閉じ、耳を塞ぎ、決して口を開くな」
「爆弾が落ちるわけじゃないんですから」
彼杵と書かれた男が小声で言い、笑う。だが、須古は首を横に振った。
「貴様らだから言うんだ。命令だと思って、そうしてろ」
須古は黒い腕時計で時間を確認する。
そして、それ以上はなにも言わずに部屋を出て行った。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
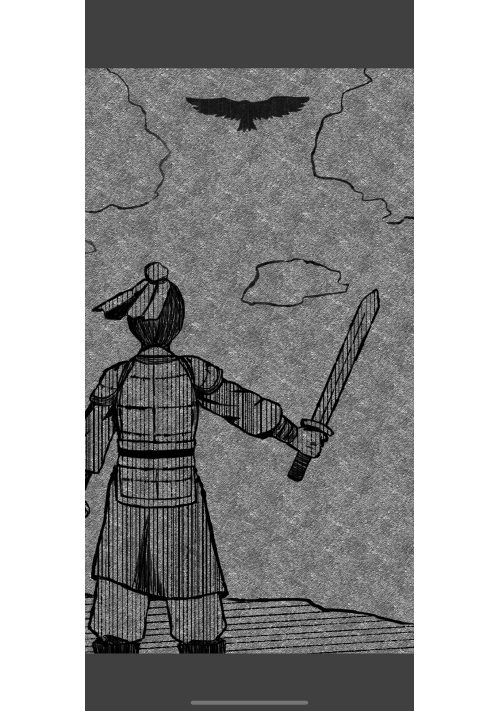
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

浮雲の譜
神尾 宥人
歴史・時代
時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。
峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……

空蝉
横山美香
歴史・時代
薩摩藩島津家の分家の娘として生まれながら、将軍家御台所となった天璋院篤姫。孝明天皇の妹という高貴な生まれから、第十四代将軍・徳川家定の妻となった和宮親子内親王。
二人の女性と二組の夫婦の恋と人生の物語です。

藤散華
水城真以
歴史・時代
――藤と梅の下に埋められた、禁忌と、恋と、呪い。
時は平安――左大臣の一の姫・彰子は、父・道長の命令で今上帝の女御となる。顔も知らない夫となった人に焦がれる彰子だが、既に帝には、定子という最愛の妃がいた。
やがて年月は過ぎ、定子の夭折により、帝と彰子の距離は必然的に近づいたように見えたが、彰子は新たな中宮となって数年が経っても懐妊の兆しはなかった。焦燥に駆られた左大臣に、妖しの影が忍び寄る。
非凡な運命に絡め取られた少女の命運は。

三國志 on 世説新語
ヘツポツ斎
歴史・時代
三國志のオリジンと言えば「三国志演義」? あるいは正史の「三國志」?
確かに、その辺りが重要です。けど、他の所にもネタが転がっています。
それが「世説新語」。三國志のちょっと後の時代に書かれた人物エピソード集です。当作はそこに載る1130エピソードの中から、三國志に関わる人物(西晋の統一まで)をピックアップ。それらを原文と、その超訳とでお送りします!
※当作はカクヨムさんの「世説新語 on the Web」を起点に、小説家になろうさん、ノベルアッププラスさん、エブリスタさんにも掲載しています。

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。


永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















