16 / 31
鬼ということ
しおりを挟む
夜――清涼殿の回廊を往く足音が一つ。御帳台(天蓋付きベッド)のある夜御殿の前まで来てピタリとやんだ。
扉の前には蛾王が虚空を見つめて屹立している。ゆっくり眼球を動かして来訪者を確認し、また虚空に戻った。
帝は御帳台のそばに燈明を持たせ、和歌の書などを読んでいる。
「父上――」
足音の主はシュウジンだった。帝は、入れ、と短く言った。
「随身も付けずに夜の散歩か」
「お話が」
「宗人よ。姫宮の一件、兵を使わなかったそうだな」
「はい。あくまで大学寮の授業……でしたので。しかし……」
「まあよい。仔細は戸勘解から聞いておる。学びの場となったであろう」
シュウジンは答えられなかった。帝は書物から目を離さない。
「のう、宗人。この世でわしの思い通りにならぬことが三つある。一つは賀茂川の水。一つは賽の目。そしてもう一つは――何かわかるか?」
「いえ……」
「燦々と陽が降り注ぐ中、一人気ままに散歩することだ。人は往々にして幸せに気づかぬもの。気付いた時、不幸となる。お前はまだ不幸を知らぬ」
帝はパタリと書物を閉じる。しかし振り返ることはなかった。
「明朝、わし自ら裁きを執り行う。鬼をよく見ておけ」
シュウジンはそれ以上何も言わず、深く一礼して夜御殿を去った。
鬼の裁きは翌朝早くに行われた。
場所は朱雀門と八省院の間にある広場だった。
八省院は、かつては臣下参列の中で行われる朝議(朝廷での儀式や政治)の場であった。しかし、永現の乱による戦災で多くの施設が焼失した。
そのため朝議は帝の住居である清涼殿そばの紫宸殿で行われている。
建設途中の大極院を背に、帝が座についた。その傍らには蛾王もいる。
左右に御堂晴隆、そしてシュウジンの姿もあり、ひと目でも鬼の王を見ようと時の左大臣、公卿などの雲上人や公家らが多数列席している。
南の応天門から、水野実真が捕縛した二人の鬼を連れて来た。
一人は片手を失った赤鬼。そして傷だらけでざんばら髪の鬼童丸である。赤鬼はこの場にいる誰より巨体を誇りながら、誰より怯えた様子だった。
鬼童丸はずっと俯いたままである。
「顔を上げよ」
赤鬼はサッと哀願の目を向けた。鬼童丸は下を向いたままだった。
「顔を上げよ」
帝はもう一度言った。しかし鬼童丸は微動だにしない。左右に列席する八省の長官、通称『八卿』たちがざわざわと顔を見合わせる。帝の命に従わないのであればその怒りは当然である。怒りは死につながる。
しかし帝は、ふうむ、と声を発して、その禿頭に青筋を浮かべなかった。
「晴隆よ、この者たちの罪はなんだ?」
「鬼ということ――でございます」
「そうか。では赤鬼よ、お前はどうして鬼になった?」
赤鬼は膝を擦って帝に少し近づいた。実真が鎖を引く。
「ど、どうかお許しください! 俺は、いや私は、帝に刃向おうなどとつゆにも思っていません。私ははるか北方のアイヌモシリ……つまりエミシから流れてまいりました。それゆえここでの生き方を知らなかっただけでございます!」
「ほう、蝦夷か! どのようなところじゃ!?」
帝は目を丸くして身を乗り出す。帝が自分に関心を示したと思った赤鬼は少し安堵した様子である。
「エミシの地はとても雪深く、とても広大でございます。強大な力を持つ何人もの首長のもとで、それぞれが助け合って暮らしているのです。彼らは弓を巧みに操り、一撃でヒグマをも射止めてしまいます。しかし彼らが戦うのは獣たちではありません。獣は糧であり、友なのです。過酷な大地で生きることこそが戦いであり、それゆえとても、とても誇り高く強うございます」
「嬉しそうに話すのう。しかしお前はここにおる。何故だ?」
「それは……首長の座をめぐって敗れ……それで」
「流れ着いたというわけか」
「どうか、どうか御慈悲を賜りたい! 私めをエミシに帰して頂いたあかつきには晴れて首長となり、帝に多くの珍品宝物を献上しとうございます」
「ふむ……エミシの宝物か……面白そうじゃのう」
赤鬼は顔をパッと輝かせ、また膝を擦って前に進み出る。
「そ、その通りでございます! なにとぞ私めにお慈悲を」
「ぬぁらぬわぁぁぁ!!」
帝の怒声が八省院の広場に鳴り響いた。腹底まで震わす大怒号だった。
赤鬼は子供のように怯え、八卿たちも唖然とした。シュウジンはそっと目を背けた。
「わしは鬼を知りたくて問うた。それをお前は無視して故郷の話を長々と……決闘に敗れ故郷を失い、異国に来て腕まで失った男に今さら何が出来る!? 我が民を傷つけたうえ、さらにわしまで愚弄するとは言語道断ッ! 皮を剥ぎ、肉を削ぎ、お前を犬に食わせてやるわ!」
場は凍りついた。聴衆はみな息を止め、衣擦れの音すらしないよう目立たないように存在を殺す。それほど冷たい静寂が支配していた。
すると、一つの笑い声が空気を震わした。鬼童丸である。
「くっくっく……とんだ茶番だなぁ、おい。鬼という罪だと? 鬼を知りたいだと? 笑わせる。なーんにもわかっちゃいないな、お前は。なあ、帝よ」
あまりにも不遜。あまりにも大胆。そしてあまりにも前代未聞。
帝を挑発する不敵な言葉は誰の耳にも入り込み、そして思考を掻き乱した。
一体、この男は何を言っているのか――?
帝は音もなく立ち上がり、まるい目玉をさらに広げる。
実真が鎖を引いて挑発を止めようとするが、鬼童丸は俯いたまま続けた。
「お前たちは、いつから自分が鬼ではないと思った? どうして俺たちが鬼だと? こうは考えたことはないか? 自分こそ鬼かもしれない――と」
裁きの場に衝撃が走った――はずだが、それがあまりに大きすぎて、みな理解が追いつかない。
鬼童丸は再びくつくつ笑う。
「俺たちは……いや、少なくとも俺は善良な人間だ。この場にいる誰よりもまっとうで、か弱い人間だと言っているんだ。なぜだかわかるか? それはテメェらこそが冥府魔道に堕ちた鬼だからだ!」
鬼童丸はざんばら髪を振り上げて、顔を正面に向けた。
その顔を見て、帝の目はまたさらに大きく円を描く。
「ら、来世か……!」
「この顔は忘れられねえか、クソハゲ」
その時、八卿の一人が腰を上げた。
「ぶ、無礼者ぞ! 口を慎め!」
鬼童丸はその方向を見てニヤリと笑う。
「俺は鬼なんだろ? 礼儀なんてあると思うか?」
帝は唇をわなわなと震わせ、ひじ掛け付きの椅子に腰を下ろす。怒気も萎え、意気も消沈したと見た御堂晴隆は帝に耳打ちした。
「ここは私にお任せを」
「……」
「よろしいですな」
帝は頷く。晴隆は前に進み出た。
「これより裁きを行う。罪状は朝廷の威光に従わぬという蛮行。双方、斬首とすべきである――しかし、この者たちは化外の地に生きる者ゆえ、日ノ本の法による裁きは分不相応。よって、彼らの道理に基づくものとする」
晴隆は側近に耳打ちして指示を出す。側近は複数の部下と共に鬼童丸と赤鬼のもとに走った。赤鬼の手枷足枷を解き、太刀を持たせる。一方の鬼童丸にはさらなる鉄の手枷をはめた。
何が行われるのか。聴衆はざわつく。晴隆が声を上げた。
「朝廷が手を下すまでもない。勝手に殺し合うがいい」
「はっはは! 内裏にも物わかりのいいヤツがいたのか」
鬼童丸は晴隆に向かって言い放った。そして手枷を掲げる。
「だが、これの根拠はなんだ?」
「赤鬼は帝に慈悲を乞うた。そして黒鬼、キサマは帝を愚弄し嘲笑した。それらが根拠である。何か不服でも?」
鬼童丸と晴隆は冷たい視線をぶつけ合った。
「は……文句はねえよ。で、勝ったら助けてくれるってか?」
「思い上がるな。迷い込んだ犬を逃すだけだ」
「だ、そうだぜ?」
鬼童丸は手枷を見せて赤鬼に向かって言った。赤鬼は太刀を握る手に力をこめる。活路を見出し、鼻息が荒くなる。
「待つんだ、御堂晴隆」
そこで言葉を発したのはシュウジンだった。
「この結果は火を見るより明らかだ。それにどうしてキミが裁きを進める? 父は――帝は何も言っていないというのに」
シュウジンはただうろたえるばかりの帝を一瞥する。
「帝は私に一任された。それ以上、何がございます?」
重苦しい沈黙が流れた。鬼童丸が首を鳴らしながら言った。
「おい、どうでもいいよ。さっさと始めようぜ」
鬼童丸は赤鬼に向かって挑発の微笑を向ける。
「う、うおおお!」
赤鬼は蛮声を上げて鬼童丸に斬りかかる。上段から豪速で振り降ろした。
鬼童丸は怪しい笑みを見せた、と思うと、手枷の鎖でその斬撃を正面から受け止めた。次の瞬間には鎖で太刀を絡め取り、瞬時に縛りを狭めて太刀を破壊してしまう。そうとわかった時にはもう、鬼童丸は赤鬼の背後を取り、背中を蹴って駆け上がり、首に鎖を回していた。ギリギリと締め付ける。
あっという間の出来事だった。みな、呆然としていた。
「ぐ、ぐぐぐ……」
赤鬼は泡を吹き、白目を剥いた。今にも縊り殺されそうである。
が、鬼童丸は首の鎖を解いた。赤鬼は倒れて咳込んだ。
「決着だ。さあ、俺を殺せ」
御堂晴隆は眉間に深い皺を刻む。この男はこの期に及んで何を言う――。
「いいか、お前ら。帝の慈悲とやらのせいで、この赤鬼サンは強気になって考えなしに突っ込んできた。そして俺は罪のおかげで、こいつの隙を衝いて背後を取ることが出来た。この意味がわかるか? わかんねえよな」
それでだ、と鬼童丸は続ける。
「お前たちは赤鬼を殺したい。だから俺は殺さねえ。そして、いま俺は、俺を殺せとお前らに命令した。もちろん、従ってくれるんだよな?」
何が言いたい! とまた別の八卿が怒声を上げる。
「お前らの望みは叶わねえが、俺の望みは叶うということだ。つまり、この場を支配しているのは――俺だ!」
時が止まった。みな息を止めた。何か途轍もなく恐ろしい怪物を相手にしているのでは――。そのような予感が聴衆から震えとなって湧き上がる。
晴隆は瞳の奥を鈍く輝かせた。
が、その晴隆の肩を帝が掴む。よろめきながら椅子から立ち上っていた。
「それこそが鬼か……来世……」
鬼童丸は氷のような瞳で帝を見据えた。
「来世……わしも鬼になれるか。鬼のように自由に……」
「いいや、なれねえな、お前は」
「な、なぜだ」
「お前は浮世を殺した。畜生にも劣る虫けらだ」
帝は崩れ落ち、両手と両膝を突く。あまりに衝撃的な光景に八卿や聴衆は腰を浮かせるが、それ以上は動くことができない。
日ノ本の日輪たる帝が、まるで頭を垂れているようではないか――!
「浮世……許しておくれ……わしはただ……」
帝は震える声で言い、ゆっくりと顔を上げる。帝の満月のような目玉か落雷のような涙が流れていた。その視界に、歪んだ鬼童丸の像が浮かぶ。
鬼童丸はまったくの無の表情で言い捨てた。
「詫びるぐらいなら死ね」
扉の前には蛾王が虚空を見つめて屹立している。ゆっくり眼球を動かして来訪者を確認し、また虚空に戻った。
帝は御帳台のそばに燈明を持たせ、和歌の書などを読んでいる。
「父上――」
足音の主はシュウジンだった。帝は、入れ、と短く言った。
「随身も付けずに夜の散歩か」
「お話が」
「宗人よ。姫宮の一件、兵を使わなかったそうだな」
「はい。あくまで大学寮の授業……でしたので。しかし……」
「まあよい。仔細は戸勘解から聞いておる。学びの場となったであろう」
シュウジンは答えられなかった。帝は書物から目を離さない。
「のう、宗人。この世でわしの思い通りにならぬことが三つある。一つは賀茂川の水。一つは賽の目。そしてもう一つは――何かわかるか?」
「いえ……」
「燦々と陽が降り注ぐ中、一人気ままに散歩することだ。人は往々にして幸せに気づかぬもの。気付いた時、不幸となる。お前はまだ不幸を知らぬ」
帝はパタリと書物を閉じる。しかし振り返ることはなかった。
「明朝、わし自ら裁きを執り行う。鬼をよく見ておけ」
シュウジンはそれ以上何も言わず、深く一礼して夜御殿を去った。
鬼の裁きは翌朝早くに行われた。
場所は朱雀門と八省院の間にある広場だった。
八省院は、かつては臣下参列の中で行われる朝議(朝廷での儀式や政治)の場であった。しかし、永現の乱による戦災で多くの施設が焼失した。
そのため朝議は帝の住居である清涼殿そばの紫宸殿で行われている。
建設途中の大極院を背に、帝が座についた。その傍らには蛾王もいる。
左右に御堂晴隆、そしてシュウジンの姿もあり、ひと目でも鬼の王を見ようと時の左大臣、公卿などの雲上人や公家らが多数列席している。
南の応天門から、水野実真が捕縛した二人の鬼を連れて来た。
一人は片手を失った赤鬼。そして傷だらけでざんばら髪の鬼童丸である。赤鬼はこの場にいる誰より巨体を誇りながら、誰より怯えた様子だった。
鬼童丸はずっと俯いたままである。
「顔を上げよ」
赤鬼はサッと哀願の目を向けた。鬼童丸は下を向いたままだった。
「顔を上げよ」
帝はもう一度言った。しかし鬼童丸は微動だにしない。左右に列席する八省の長官、通称『八卿』たちがざわざわと顔を見合わせる。帝の命に従わないのであればその怒りは当然である。怒りは死につながる。
しかし帝は、ふうむ、と声を発して、その禿頭に青筋を浮かべなかった。
「晴隆よ、この者たちの罪はなんだ?」
「鬼ということ――でございます」
「そうか。では赤鬼よ、お前はどうして鬼になった?」
赤鬼は膝を擦って帝に少し近づいた。実真が鎖を引く。
「ど、どうかお許しください! 俺は、いや私は、帝に刃向おうなどとつゆにも思っていません。私ははるか北方のアイヌモシリ……つまりエミシから流れてまいりました。それゆえここでの生き方を知らなかっただけでございます!」
「ほう、蝦夷か! どのようなところじゃ!?」
帝は目を丸くして身を乗り出す。帝が自分に関心を示したと思った赤鬼は少し安堵した様子である。
「エミシの地はとても雪深く、とても広大でございます。強大な力を持つ何人もの首長のもとで、それぞれが助け合って暮らしているのです。彼らは弓を巧みに操り、一撃でヒグマをも射止めてしまいます。しかし彼らが戦うのは獣たちではありません。獣は糧であり、友なのです。過酷な大地で生きることこそが戦いであり、それゆえとても、とても誇り高く強うございます」
「嬉しそうに話すのう。しかしお前はここにおる。何故だ?」
「それは……首長の座をめぐって敗れ……それで」
「流れ着いたというわけか」
「どうか、どうか御慈悲を賜りたい! 私めをエミシに帰して頂いたあかつきには晴れて首長となり、帝に多くの珍品宝物を献上しとうございます」
「ふむ……エミシの宝物か……面白そうじゃのう」
赤鬼は顔をパッと輝かせ、また膝を擦って前に進み出る。
「そ、その通りでございます! なにとぞ私めにお慈悲を」
「ぬぁらぬわぁぁぁ!!」
帝の怒声が八省院の広場に鳴り響いた。腹底まで震わす大怒号だった。
赤鬼は子供のように怯え、八卿たちも唖然とした。シュウジンはそっと目を背けた。
「わしは鬼を知りたくて問うた。それをお前は無視して故郷の話を長々と……決闘に敗れ故郷を失い、異国に来て腕まで失った男に今さら何が出来る!? 我が民を傷つけたうえ、さらにわしまで愚弄するとは言語道断ッ! 皮を剥ぎ、肉を削ぎ、お前を犬に食わせてやるわ!」
場は凍りついた。聴衆はみな息を止め、衣擦れの音すらしないよう目立たないように存在を殺す。それほど冷たい静寂が支配していた。
すると、一つの笑い声が空気を震わした。鬼童丸である。
「くっくっく……とんだ茶番だなぁ、おい。鬼という罪だと? 鬼を知りたいだと? 笑わせる。なーんにもわかっちゃいないな、お前は。なあ、帝よ」
あまりにも不遜。あまりにも大胆。そしてあまりにも前代未聞。
帝を挑発する不敵な言葉は誰の耳にも入り込み、そして思考を掻き乱した。
一体、この男は何を言っているのか――?
帝は音もなく立ち上がり、まるい目玉をさらに広げる。
実真が鎖を引いて挑発を止めようとするが、鬼童丸は俯いたまま続けた。
「お前たちは、いつから自分が鬼ではないと思った? どうして俺たちが鬼だと? こうは考えたことはないか? 自分こそ鬼かもしれない――と」
裁きの場に衝撃が走った――はずだが、それがあまりに大きすぎて、みな理解が追いつかない。
鬼童丸は再びくつくつ笑う。
「俺たちは……いや、少なくとも俺は善良な人間だ。この場にいる誰よりもまっとうで、か弱い人間だと言っているんだ。なぜだかわかるか? それはテメェらこそが冥府魔道に堕ちた鬼だからだ!」
鬼童丸はざんばら髪を振り上げて、顔を正面に向けた。
その顔を見て、帝の目はまたさらに大きく円を描く。
「ら、来世か……!」
「この顔は忘れられねえか、クソハゲ」
その時、八卿の一人が腰を上げた。
「ぶ、無礼者ぞ! 口を慎め!」
鬼童丸はその方向を見てニヤリと笑う。
「俺は鬼なんだろ? 礼儀なんてあると思うか?」
帝は唇をわなわなと震わせ、ひじ掛け付きの椅子に腰を下ろす。怒気も萎え、意気も消沈したと見た御堂晴隆は帝に耳打ちした。
「ここは私にお任せを」
「……」
「よろしいですな」
帝は頷く。晴隆は前に進み出た。
「これより裁きを行う。罪状は朝廷の威光に従わぬという蛮行。双方、斬首とすべきである――しかし、この者たちは化外の地に生きる者ゆえ、日ノ本の法による裁きは分不相応。よって、彼らの道理に基づくものとする」
晴隆は側近に耳打ちして指示を出す。側近は複数の部下と共に鬼童丸と赤鬼のもとに走った。赤鬼の手枷足枷を解き、太刀を持たせる。一方の鬼童丸にはさらなる鉄の手枷をはめた。
何が行われるのか。聴衆はざわつく。晴隆が声を上げた。
「朝廷が手を下すまでもない。勝手に殺し合うがいい」
「はっはは! 内裏にも物わかりのいいヤツがいたのか」
鬼童丸は晴隆に向かって言い放った。そして手枷を掲げる。
「だが、これの根拠はなんだ?」
「赤鬼は帝に慈悲を乞うた。そして黒鬼、キサマは帝を愚弄し嘲笑した。それらが根拠である。何か不服でも?」
鬼童丸と晴隆は冷たい視線をぶつけ合った。
「は……文句はねえよ。で、勝ったら助けてくれるってか?」
「思い上がるな。迷い込んだ犬を逃すだけだ」
「だ、そうだぜ?」
鬼童丸は手枷を見せて赤鬼に向かって言った。赤鬼は太刀を握る手に力をこめる。活路を見出し、鼻息が荒くなる。
「待つんだ、御堂晴隆」
そこで言葉を発したのはシュウジンだった。
「この結果は火を見るより明らかだ。それにどうしてキミが裁きを進める? 父は――帝は何も言っていないというのに」
シュウジンはただうろたえるばかりの帝を一瞥する。
「帝は私に一任された。それ以上、何がございます?」
重苦しい沈黙が流れた。鬼童丸が首を鳴らしながら言った。
「おい、どうでもいいよ。さっさと始めようぜ」
鬼童丸は赤鬼に向かって挑発の微笑を向ける。
「う、うおおお!」
赤鬼は蛮声を上げて鬼童丸に斬りかかる。上段から豪速で振り降ろした。
鬼童丸は怪しい笑みを見せた、と思うと、手枷の鎖でその斬撃を正面から受け止めた。次の瞬間には鎖で太刀を絡め取り、瞬時に縛りを狭めて太刀を破壊してしまう。そうとわかった時にはもう、鬼童丸は赤鬼の背後を取り、背中を蹴って駆け上がり、首に鎖を回していた。ギリギリと締め付ける。
あっという間の出来事だった。みな、呆然としていた。
「ぐ、ぐぐぐ……」
赤鬼は泡を吹き、白目を剥いた。今にも縊り殺されそうである。
が、鬼童丸は首の鎖を解いた。赤鬼は倒れて咳込んだ。
「決着だ。さあ、俺を殺せ」
御堂晴隆は眉間に深い皺を刻む。この男はこの期に及んで何を言う――。
「いいか、お前ら。帝の慈悲とやらのせいで、この赤鬼サンは強気になって考えなしに突っ込んできた。そして俺は罪のおかげで、こいつの隙を衝いて背後を取ることが出来た。この意味がわかるか? わかんねえよな」
それでだ、と鬼童丸は続ける。
「お前たちは赤鬼を殺したい。だから俺は殺さねえ。そして、いま俺は、俺を殺せとお前らに命令した。もちろん、従ってくれるんだよな?」
何が言いたい! とまた別の八卿が怒声を上げる。
「お前らの望みは叶わねえが、俺の望みは叶うということだ。つまり、この場を支配しているのは――俺だ!」
時が止まった。みな息を止めた。何か途轍もなく恐ろしい怪物を相手にしているのでは――。そのような予感が聴衆から震えとなって湧き上がる。
晴隆は瞳の奥を鈍く輝かせた。
が、その晴隆の肩を帝が掴む。よろめきながら椅子から立ち上っていた。
「それこそが鬼か……来世……」
鬼童丸は氷のような瞳で帝を見据えた。
「来世……わしも鬼になれるか。鬼のように自由に……」
「いいや、なれねえな、お前は」
「な、なぜだ」
「お前は浮世を殺した。畜生にも劣る虫けらだ」
帝は崩れ落ち、両手と両膝を突く。あまりに衝撃的な光景に八卿や聴衆は腰を浮かせるが、それ以上は動くことができない。
日ノ本の日輪たる帝が、まるで頭を垂れているようではないか――!
「浮世……許しておくれ……わしはただ……」
帝は震える声で言い、ゆっくりと顔を上げる。帝の満月のような目玉か落雷のような涙が流れていた。その視界に、歪んだ鬼童丸の像が浮かぶ。
鬼童丸はまったくの無の表情で言い捨てた。
「詫びるぐらいなら死ね」
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

妖刀 益荒男
地辻夜行
歴史・時代
東西南北老若男女
お集まりいただきました皆様に
本日お聞きいただきますのは
一人の男の人生を狂わせた妖刀の話か
はたまた一本の妖刀の剣生を狂わせた男の話か
蓋をあけて見なけりゃわからない
妖気に魅入られた少女にのっぺらぼう
からかい上手の女に皮肉な忍び
個性豊かな面子に振り回され
妖刀は己の求める鞘に会えるのか
男は己の尊厳を取り戻せるのか
一人と一刀の冒険活劇
いまここに開幕、か~い~ま~く~

黄昏の芙蓉
翔子
歴史・時代
本作のあらすじ:
平安の昔、六条町にある呉服問屋の女主として切り盛りしていた・有子は、四人の子供と共に、何不自由なく暮らしていた。
ある日、織物の生地を御所へ献上した折に、時の帝・冷徳天皇に誘拐されてしまい、愛しい子供たちと離れ離れになってしまった。幾度となく抗議をするも聞き届けられず、朝廷側から、店と子供たちを御所が保護する事を条件に出され、有子は泣く泣く後宮に入り帝の妻・更衣となる事を決意した。
御所では、信頼出来る御付きの女官・勾当内侍、帝の中宮・藤壺の宮と出会い、次第に、女性だらけの後宮生活に慣れて行った。ところがそのうち、中宮付きの乳母・藤小路から様々な嫌がらせを受けるなど、徐々に波乱な後宮生活を迎える事になって行く。
※ずいぶん前に書いた小説です。稚拙な文章で申し訳ございませんが、初心の頃を忘れないために修正を加えるつもりも無いことをご了承ください。

【完結】風天の虎 ――車丹波、北の関ヶ原
糸冬
歴史・時代
車丹波守斯忠。「猛虎」の諱で知られる戦国武将である。
慶長五年(一六〇〇年)二月、徳川家康が上杉征伐に向けて策動する中、斯忠は反徳川派の急先鋒として、主君・佐竹義宣から追放の憂き目に遭う。
しかし一念発起した斯忠は、異母弟にして養子の車善七郎と共に数百の手勢を集めて会津に乗り込み、上杉家の筆頭家老・直江兼続が指揮する「組外衆」に加わり働くことになる。
目指すは徳川家康の首級ただ一つ。
しかし、その思いとは裏腹に、最初に与えられた役目は神指城の普請場での土運びであった……。
その名と生き様から、「国民的映画の主人公のモデル」とも噂される男が身を投じた、「もう一つの関ヶ原」の物語。

葉桜よ、もう一度 【完結】
五月雨輝
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。
謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

ふたりの旅路
三矢由巳
歴史・時代
第三章開始しました。以下は第一章のあらすじです。
志緒(しお)のいいなずけ駒井幸之助は文武両道に秀でた明るく心優しい青年だった。祝言を三カ月後に控え幸之助が急死した。幸せの絶頂から奈落の底に突き落とされた志緒と駒井家の人々。一周忌の後、家の存続のため駒井家は遠縁の山中家から源治郎を養子に迎えることに。志緒は源治郎と幸之助の妹佐江が結婚すると思っていたが、駒井家の人々は志緒に嫁に来て欲しいと言う。
無口で何を考えているかわからない源治郎との結婚に不安を感じる志緒。果たしてふたりの運命は……。

【完結】女神は推考する
仲 奈華 (nakanaka)
歴史・時代
父や夫、兄弟を相次いで失った太后は途方にくれた。
直系の男子が相次いて死亡し、残っているのは幼い皇子か血筋が遠いものしかいない。
強欲な叔父から持ち掛けられたのは、女である私が即位するというものだった。
まだ幼い息子を想い決心する。子孫の為、夫の為、家の為私の役目を果たさなければならない。
今までは子供を産む事が役割だった。だけど、これからは亡き夫に変わり、残された私が守る必要がある。
これは、大王となる私の守る為の物語。
額田部姫(ヌカタベヒメ)
主人公。母が蘇我一族。皇女。
穴穂部皇子(アナホベノミコ)
主人公の従弟。
他田皇子(オサダノオオジ)
皇太子。主人公より16歳年上。後の大王。
広姫(ヒロヒメ)
他田皇子の正妻。他田皇子との間に3人の子供がいる。
彦人皇子(ヒコヒトノミコ)
他田大王と広姫の嫡子。
大兄皇子(オオエノミコ)
主人公の同母兄。
厩戸皇子(ウマヤドノミコ)
大兄皇子の嫡子。主人公の甥。
※飛鳥時代、推古天皇が主人公の小説です。
※歴史的に年齢が分かっていない人物については、推定年齢を記載しています。※異母兄弟についての明記をさけ、母方の親類表記にしています。
※名前については、できるだけ本名を記載するようにしています。(馴染みが無い呼び方かもしれません。)
※史実や事実と異なる表現があります。
※主人公が大王になった後の話を、第2部として追加する可能性があります。その時は完結→連載へ設定変更いたします。

加藤虎之助(後の清正、15歳)、姉さん女房をもらいました!
野松 彦秋
歴史・時代
加藤虎之助15歳、山崎シノ17歳
一族の出世頭、又従弟秀吉に翻弄(祝福?)されながら、
二人は夫婦としてやっていけるのか、身分が違う二人が真の夫婦になるまでの物語。
若い虎之助とシノの新婚生活を温かく包む羽柴家の人々。しかし身分違いの二人の祝言が、織田信長の耳に入り、まさかの展開に。少年加藤虎之助が加藤清正になるまでのモノカタリである。
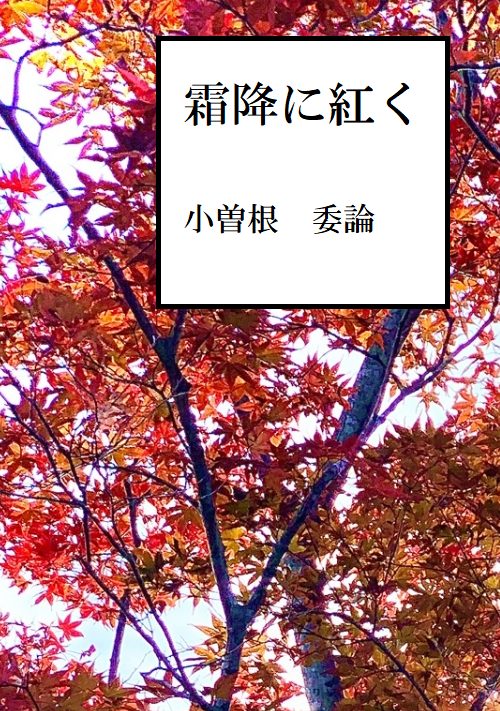
霜降に紅く
小曽根 委論(おぞね いろん)
歴史・時代
常陸国に仕える仲田家の次男坊宗兵衛は、殺された父親の仇を探す放浪の旅に出ていた。ある日宗兵衛は、仇討ちを恐れる者が多数逃げ込むと言われている、その名も『仇討山』の存在を知り、足を運ぶ。そこで出会った虚無僧・宮浦から情報を聞き出そうとする宗兵衛。果たして彼は宿敵を討ち果たすことが出来るのか。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















