141 / 185
139話
しおりを挟む
「《滅炎》」
靄を出るなりそう唱えると、生み出された炎はビームのように一直線にラースへと向かって行く。
「随分な挨拶だな」
そうラースに正面から体で受け止められた。元から赤黒い肌というのもあってか火傷すらしていないように見える。
実際、火傷すらしていないだろう。それほどラースの体は強靭だ。
人のような直立二足歩行に決して貧弱ではない下半身を持ちながらも逆三角形に見える肩幅に胸筋、それでいて体中に獣の毛が生えていて手足に鋭い爪を備えオオカミの顔をしている。所謂、狼人間だ。
「何で面倒くせぇ巻き込み方をした?」
「お前の侍女たちのことか。それ程、あの女たちを気に入っているのだな」
「侍女じゃねぇがそこはいい。もっと楽な消し方があっただろ。何でわざわざあんな真似をした?」
俺たちが負けた後、ララたちが消されるのは仕方のないことだ。今はそういう戦いをしている。
だが、あんな人間同士の争いに巻き込まなくてもこいつ等なら一瞬で苦痛を味合う間もなく消せる。それをこの戦いが終わった後にやればよかった。
それをわざわざ苦痛の多い殺し方を選んだ。メナたちの前では取り繕っていたが、1人になった今、そこに対する苛立ちが抑えられない。
「争いに綺麗事は不要だろう?現にお前を乱せている。その事実以上に必要なことがあるか?」
「そんな性格じゃねぇだろ。本性を現せ」
「これ程、怒っているゼギウスを見るのはいつ振りだろうな」
本性を現す気はないようだ。それならそれでいい。さっさと終わらせる。
「《怠惰の砂時計》《100分の1》」
時の流れを遅くして一気に距離を詰める。そこから無抵抗のラースの心臓を貫こうと手刀を伸ばすと、ラースは動いた。
「対策をしていない訳がないだろう。庭全域で怠惰の砂時計は使えないぞ」
そう余裕のある言葉と共に爪によるカウンターがくるが、これはある程度、読めていた。腕でラースの手首の辺りを上に弾き、その勢いで上体を浮かせた。
「そうか。《1分の1》《滅雷》」
時の流れを戻してから即座に追加でスキルを唱える。時の流れが戻ろうとも詰めた距離は変わらない。
《滅雷》がラースの腹部目掛けて閃光を走らせる。それをラースは浮かされた上体の勢いを利用して後方宙返りをして宙に居る間に閃光を躱そうとした。
それでも完璧に躱し切ることは不可能で体を浮かせる最中の右の太腿を貫き大きな穴を空ける。が、先に時の流れを戻した分、狙った場所を貫くには至らなかった。
だが、ラースはそのまま後方宙返りから後方転回に切り替え手を先に地面に着いて勢いを殺し左足で地面を蹴って四足で走り反撃に出ようとする。が、これも読めていた。
向かってくるラースに《滅氷》で地面を凍らせる。《滅雷》の傷を庇った走り方とそこへ意識を割かれて反応も遅れたのかラースの手足は地面に着いたまま凍った。
「怒らせ過ぎたな。《絶滅》」
この一撃でラースだけでなくこの空間ごと消滅させた。
空間が消滅したことで元の庭に戻る。奥には屋敷があり手前には靄が6つあるままだ。
「出て来いよ。居るんだろ?」
そう呼び掛けるとラースが姿を現す。その姿に傷はなくさっきの体とは違うのが見て取れる。
この程度で終わるような奴ではないと思っていたが狙いが分からない。今更、俺の力量を測った訳でもないだろうに。
「こうしてここで向き合うと思い出す。スロウスのことを」
怒ってるのは俺だけじゃねぇってことか。俺とスロウスが戦い、スロウスが死んだこの場所でその怒りをぶつけるつもりのようだ。ラースらしいと言えばラースらしい。
「だからってあんな真似をしたのは解せねぇな」
「そうか、なら互いの怒りをぶつけ合うしかないな。《ラース・オブ・スロウス》」
そうラースが唱えると雰囲気が変わる。体内にある魔力量は数倍に増幅して沸騰しているように荒々しい。それは俺に対する怒りを表していた。
まだあの時の怒りをとってたのか…
ラースはその時に覚えた怒りを保存でき、その時に覚えた怒りの大きさや深さによって魔力量や魔力系統が変わる。
そういった意味で今のラースは過去最強だ。あの時の怒りに上回るものはない。
ゴリラのような上体の浮いた姿勢から四足で距離を詰めてくる。さっきの戦いと比べると動きが数段速い。
それでも対応できないような速さではなく迎え撃つように掌底を構える。それをラースが上体を浮かせて攻撃に出ようとした完璧なタイミングで撃ったつもりだったが、潜るように下に躱された。
だが、それも読めていた。ラースが低い姿勢になったところに掌底の打ち上げと体を捻じった勢いを利用して跳び、回転しながらラースの頭に蹴りを入れる。
しかし、それを狙っていたようにラースに足を掴まれて地面に叩きつけられる。そこへ追撃をするようにラースは爪を構えた。
「《風炎爪》」
左右の手に炎と風、別々の属性を纏って腕をクロスするように引っ掻いてくる。それを《絶》で打ち消し、腕がクロスしたところで手と手の間に蹴りを入れて止めた。更にその反動を利用して起き上がり距離を取って仕切り直す。
「我の相手がゼギウスであることに感謝するぞ、スロウス。そうでなければこの怒り、晴らすことはできなかった」
そうラースは天を仰ぐ。別にこれが理由という訳ではないが、こっちに選択権がある時点でラースの相手をするのは俺だと決まっていた。
ラースの相手をできるのは俺だけだ。
「そりゃよかったな。そんなもの抱えられたまま怨霊になられても面倒くせぇ」
「怨霊か。そのスロウスの怨念が今、お前に向かっている」
「それはスロウスのじゃねぇ、お前のだろ」
確かに俺がスロウスを手にかけた。だが、それは真剣勝負の結果であって互いに怨み合って戦った訳ではない。
だから俺はスロウスから《怠惰》を託された。
ラースの方がスロウスと長い時を共にしたとはいえ、スロウスの死からラースが抱いた怒りをスロウスの怨念にされるのは解せない。
「そうなのかもしれないな。だが、この怒りはお前へのものだ」
ラースの魔力が更に増幅し体内だけに抑えられなくなる。体から溢れた魔力はラースの体から天に向かって伸びていた。
今の言葉で迷いが消えたようだ。これが本来のスロウスへの想いで俺への怒り。
その怒りは荒々しく触れただけで致命傷になりそうだが、ラースの制御化を離れ無造作にただ俺へと向かってきているだけだ。無造作とあって躱すのは容易いが、その怒りが尽きる気配はない。
「躱したところでこの怒りが尽きることはない。寧ろ、増すばかりだ」
その宣言通り更に怒りは膨れ上がる。それは無造作だったはずが、躱す場所が無くなるほど広域に広がっていた。
流石にこの魔力量は《絶》で消せる範囲を超えている。だが、躱す場所も見当たらない。
さて、どうしたものか。アルとゲンにかなりの魔力量を渡した手前、無駄に使えるような余裕はない。アルやゲンと違って今この時も魔力は生成されているが、ラースの怒りを前にそれは微々たるものに過ぎない。
「我の怒りに向き合え。これはお前の業だ」
そう言われると避けるのが逃げているように聞こえる。
だが、どの道もう逃げ場はない。やるしかねぇか。
体の重要な部分と右手だけを魔力で覆いラースの怒りへと突っ込んで行く。
怒りに触れた瞬間、魔力で覆っていない場所は溶けるように消える。魔力で覆っている部分も長くはもたない。
それでも、そのままラースの元まで近寄り、右手をラースへの心臓へと突き刺し残っている魔力の全てを使う。
「《絶滅》」
それは再びラースの体を消滅させた。
靄を出るなりそう唱えると、生み出された炎はビームのように一直線にラースへと向かって行く。
「随分な挨拶だな」
そうラースに正面から体で受け止められた。元から赤黒い肌というのもあってか火傷すらしていないように見える。
実際、火傷すらしていないだろう。それほどラースの体は強靭だ。
人のような直立二足歩行に決して貧弱ではない下半身を持ちながらも逆三角形に見える肩幅に胸筋、それでいて体中に獣の毛が生えていて手足に鋭い爪を備えオオカミの顔をしている。所謂、狼人間だ。
「何で面倒くせぇ巻き込み方をした?」
「お前の侍女たちのことか。それ程、あの女たちを気に入っているのだな」
「侍女じゃねぇがそこはいい。もっと楽な消し方があっただろ。何でわざわざあんな真似をした?」
俺たちが負けた後、ララたちが消されるのは仕方のないことだ。今はそういう戦いをしている。
だが、あんな人間同士の争いに巻き込まなくてもこいつ等なら一瞬で苦痛を味合う間もなく消せる。それをこの戦いが終わった後にやればよかった。
それをわざわざ苦痛の多い殺し方を選んだ。メナたちの前では取り繕っていたが、1人になった今、そこに対する苛立ちが抑えられない。
「争いに綺麗事は不要だろう?現にお前を乱せている。その事実以上に必要なことがあるか?」
「そんな性格じゃねぇだろ。本性を現せ」
「これ程、怒っているゼギウスを見るのはいつ振りだろうな」
本性を現す気はないようだ。それならそれでいい。さっさと終わらせる。
「《怠惰の砂時計》《100分の1》」
時の流れを遅くして一気に距離を詰める。そこから無抵抗のラースの心臓を貫こうと手刀を伸ばすと、ラースは動いた。
「対策をしていない訳がないだろう。庭全域で怠惰の砂時計は使えないぞ」
そう余裕のある言葉と共に爪によるカウンターがくるが、これはある程度、読めていた。腕でラースの手首の辺りを上に弾き、その勢いで上体を浮かせた。
「そうか。《1分の1》《滅雷》」
時の流れを戻してから即座に追加でスキルを唱える。時の流れが戻ろうとも詰めた距離は変わらない。
《滅雷》がラースの腹部目掛けて閃光を走らせる。それをラースは浮かされた上体の勢いを利用して後方宙返りをして宙に居る間に閃光を躱そうとした。
それでも完璧に躱し切ることは不可能で体を浮かせる最中の右の太腿を貫き大きな穴を空ける。が、先に時の流れを戻した分、狙った場所を貫くには至らなかった。
だが、ラースはそのまま後方宙返りから後方転回に切り替え手を先に地面に着いて勢いを殺し左足で地面を蹴って四足で走り反撃に出ようとする。が、これも読めていた。
向かってくるラースに《滅氷》で地面を凍らせる。《滅雷》の傷を庇った走り方とそこへ意識を割かれて反応も遅れたのかラースの手足は地面に着いたまま凍った。
「怒らせ過ぎたな。《絶滅》」
この一撃でラースだけでなくこの空間ごと消滅させた。
空間が消滅したことで元の庭に戻る。奥には屋敷があり手前には靄が6つあるままだ。
「出て来いよ。居るんだろ?」
そう呼び掛けるとラースが姿を現す。その姿に傷はなくさっきの体とは違うのが見て取れる。
この程度で終わるような奴ではないと思っていたが狙いが分からない。今更、俺の力量を測った訳でもないだろうに。
「こうしてここで向き合うと思い出す。スロウスのことを」
怒ってるのは俺だけじゃねぇってことか。俺とスロウスが戦い、スロウスが死んだこの場所でその怒りをぶつけるつもりのようだ。ラースらしいと言えばラースらしい。
「だからってあんな真似をしたのは解せねぇな」
「そうか、なら互いの怒りをぶつけ合うしかないな。《ラース・オブ・スロウス》」
そうラースが唱えると雰囲気が変わる。体内にある魔力量は数倍に増幅して沸騰しているように荒々しい。それは俺に対する怒りを表していた。
まだあの時の怒りをとってたのか…
ラースはその時に覚えた怒りを保存でき、その時に覚えた怒りの大きさや深さによって魔力量や魔力系統が変わる。
そういった意味で今のラースは過去最強だ。あの時の怒りに上回るものはない。
ゴリラのような上体の浮いた姿勢から四足で距離を詰めてくる。さっきの戦いと比べると動きが数段速い。
それでも対応できないような速さではなく迎え撃つように掌底を構える。それをラースが上体を浮かせて攻撃に出ようとした完璧なタイミングで撃ったつもりだったが、潜るように下に躱された。
だが、それも読めていた。ラースが低い姿勢になったところに掌底の打ち上げと体を捻じった勢いを利用して跳び、回転しながらラースの頭に蹴りを入れる。
しかし、それを狙っていたようにラースに足を掴まれて地面に叩きつけられる。そこへ追撃をするようにラースは爪を構えた。
「《風炎爪》」
左右の手に炎と風、別々の属性を纏って腕をクロスするように引っ掻いてくる。それを《絶》で打ち消し、腕がクロスしたところで手と手の間に蹴りを入れて止めた。更にその反動を利用して起き上がり距離を取って仕切り直す。
「我の相手がゼギウスであることに感謝するぞ、スロウス。そうでなければこの怒り、晴らすことはできなかった」
そうラースは天を仰ぐ。別にこれが理由という訳ではないが、こっちに選択権がある時点でラースの相手をするのは俺だと決まっていた。
ラースの相手をできるのは俺だけだ。
「そりゃよかったな。そんなもの抱えられたまま怨霊になられても面倒くせぇ」
「怨霊か。そのスロウスの怨念が今、お前に向かっている」
「それはスロウスのじゃねぇ、お前のだろ」
確かに俺がスロウスを手にかけた。だが、それは真剣勝負の結果であって互いに怨み合って戦った訳ではない。
だから俺はスロウスから《怠惰》を託された。
ラースの方がスロウスと長い時を共にしたとはいえ、スロウスの死からラースが抱いた怒りをスロウスの怨念にされるのは解せない。
「そうなのかもしれないな。だが、この怒りはお前へのものだ」
ラースの魔力が更に増幅し体内だけに抑えられなくなる。体から溢れた魔力はラースの体から天に向かって伸びていた。
今の言葉で迷いが消えたようだ。これが本来のスロウスへの想いで俺への怒り。
その怒りは荒々しく触れただけで致命傷になりそうだが、ラースの制御化を離れ無造作にただ俺へと向かってきているだけだ。無造作とあって躱すのは容易いが、その怒りが尽きる気配はない。
「躱したところでこの怒りが尽きることはない。寧ろ、増すばかりだ」
その宣言通り更に怒りは膨れ上がる。それは無造作だったはずが、躱す場所が無くなるほど広域に広がっていた。
流石にこの魔力量は《絶》で消せる範囲を超えている。だが、躱す場所も見当たらない。
さて、どうしたものか。アルとゲンにかなりの魔力量を渡した手前、無駄に使えるような余裕はない。アルやゲンと違って今この時も魔力は生成されているが、ラースの怒りを前にそれは微々たるものに過ぎない。
「我の怒りに向き合え。これはお前の業だ」
そう言われると避けるのが逃げているように聞こえる。
だが、どの道もう逃げ場はない。やるしかねぇか。
体の重要な部分と右手だけを魔力で覆いラースの怒りへと突っ込んで行く。
怒りに触れた瞬間、魔力で覆っていない場所は溶けるように消える。魔力で覆っている部分も長くはもたない。
それでも、そのままラースの元まで近寄り、右手をラースへの心臓へと突き刺し残っている魔力の全てを使う。
「《絶滅》」
それは再びラースの体を消滅させた。
0
お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説

王宮で汚職を告発したら逆に指名手配されて殺されかけたけど、たまたま出会ったメイドロボに転生者の技術力を借りて反撃します
有賀冬馬
ファンタジー
王国貴族ヘンリー・レンは大臣と宰相の汚職を告発したが、逆に濡れ衣を着せられてしまい、追われる身になってしまう。
妻は宰相側に寝返り、ヘンリーは女性不信になってしまう。
さらに差し向けられた追手によって左腕切断、毒、呪い状態という満身創痍で、命からがら雪山に逃げ込む。
そこで力尽き、倒れたヘンリーを助けたのは、奇妙なメイド型アンドロイドだった。
そのアンドロイドは、かつて大賢者と呼ばれた転生者の技術で作られたメイドロボだったのだ。
現代知識チートと魔法の融合技術で作られた義手を与えられたヘンリーが、独立勢力となって王国の悪を蹴散らしていく!

大切”だった”仲間に裏切られたので、皆殺しにしようと思います
騙道みりあ
ファンタジー
魔王を討伐し、世界に平和をもたらした”勇者パーティー”。
その一員であり、”人類最強”と呼ばれる少年ユウキは、何故か仲間たちに裏切られてしまう。
仲間への信頼、恋人への愛。それら全てが作られたものだと知り、ユウキは怒りを覚えた。
なので、全員殺すことにした。
1話完結ですが、続編も考えています。

幼なじみ三人が勇者に魅了されちゃって寝盗られるんだけど数年後勇者が死んで正気に戻った幼なじみ達がめちゃくちゃ後悔する話
妄想屋さん
ファンタジー
『元彼?冗談でしょ?僕はもうあんなのもうどうでもいいよ!』
『ええ、アタシはあなたに愛して欲しい。あんなゴミもう知らないわ!』
『ええ!そうですとも!だから早く私にも――』
大切な三人の仲間を勇者に〈魅了〉で奪い取られて絶望した主人公と、〈魅了〉から解放されて今までの自分たちの行いに絶望するヒロイン達の話。
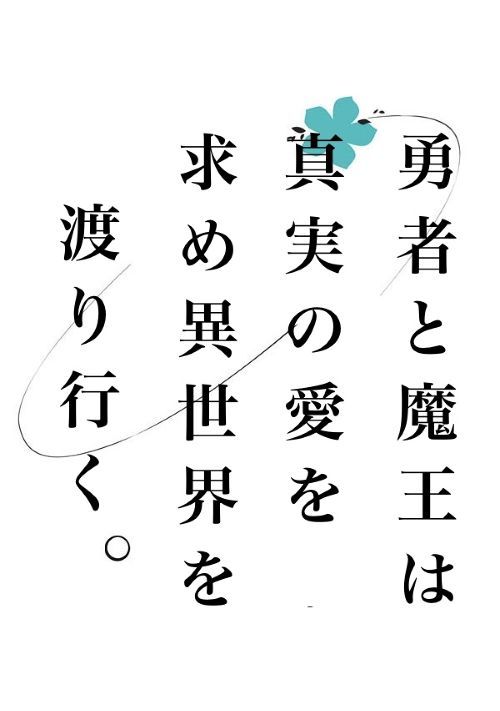
勇者と魔王は真実の愛を求めて異世界を渡り行く
usiroka
ファンタジー
何千年と終わることなく続く人間と魔族の戦争
そんな長い戦争を終わらせるため一人の勇者と魔王は身を挺して殺し合いを始める
しかしそこに現れた神さまと名乗る男は突然とその殺し合いに水を差す
神さまがわざわざ勇者と魔王の戦いに水を差した理由に勇者と魔王は大きく戸惑いを見せるがその理由とは…!?
※第零章はオマケのようなものなので読みたい方だけ読んでください
※この物語はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。

母親に家を追い出されたので、勝手に生きる!!(泣きついて来ても、助けてやらない)
いくみ
ファンタジー
実母に家を追い出された。
全く親父の奴!勝手に消えやがって!
親父が帰ってこなくなったから、実母が再婚したが……。その再婚相手は働きもせずに好き勝手する男だった。
俺は消えた親父から母と頼むと、言われて。
母を守ったつもりだったが……出て行けと言われた……。
なんだこれ!俺よりもその男とできた子供の味方なんだな?
なら、出ていくよ!
俺が居なくても食って行けるなら勝手にしろよ!
これは、のんびり気ままに冒険をする男の話です。
カクヨム様にて先行掲載中です。
不定期更新です。

オリュンポス
ハーメルンのホラ吹き
ファンタジー
悠久の時を生き続ける種族たちの星。
別名:神々の世界【オリュンポス】では、いつ始まったのかも分からない神域を広める領土戦争が何億世紀にも渡り続いていた。戦の時代に産み落とされた主人公も【常世の終焉】と呼ばれた神界戦争に参加し、自領を広げ【禍威の混沌狐】と畏怖の対象にされるまで登りつめた。しかし、複数の神によって封印された過去の神となった主人公。
幾億の時を経て封印から逃れることに成功した主人公は...

異世界帰りの元勇者、日本に突然ダンジョンが出現したので「俺、バイト辞めますっ!」
シオヤマ琴@『最強最速』発売中
ファンタジー
俺、結城ミサオは異世界帰りの元勇者。
異世界では強大な力を持った魔王を倒しもてはやされていたのに、こっちの世界に戻ったら平凡なコンビニバイト。
せっかく強くなったっていうのにこれじゃ宝の持ち腐れだ。
そう思っていたら突然目の前にダンジョンが現れた。
これは天啓か。
俺は一も二もなくダンジョンへと向かっていくのだった。

拾った子犬がケルベロスでした~実は古代魔法の使い手だった少年、本気出すとコワい(?)愛犬と楽しく暮らします~
荒井竜馬
ファンタジー
旧題: ケルベロスを拾った少年、パーティ追放されたけど実は絶滅した古代魔法の使い手だったので、愛犬と共に成り上がります。
=========================
<<<<第4回次世代ファンタジーカップ参加中>>>>
参加時325位 → 現在5位!
応援よろしくお願いします!(´▽`)
=========================
S級パーティに所属していたソータは、ある日依頼最中に仲間に崖から突き落とされる。
ソータは基礎的な魔法しか使えないことを理由に、仲間に裏切られたのだった。
崖から落とされたソータが死を覚悟したとき、ソータは地獄を追放されたというケルベロスに偶然命を助けられる。
そして、どう見ても可愛らしい子犬しか見えない自称ケルベロスは、ソータの従魔になりたいと言い出すだけでなく、ソータが使っている魔法が古代魔であることに気づく。
今まで自分が規格外の古代魔法でパーティを守っていたことを知ったソータは、古代魔法を扱って冒険者として成長していく。
そして、ソータを崖から突き落とした本当の理由も徐々に判明していくのだった。
それと同時に、ソータを追放したパーティは、本当の力が明るみになっていってしまう。
ソータの支援魔法に頼り切っていたパーティは、C級ダンジョンにも苦戦するのだった……。
他サイトでも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















