お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
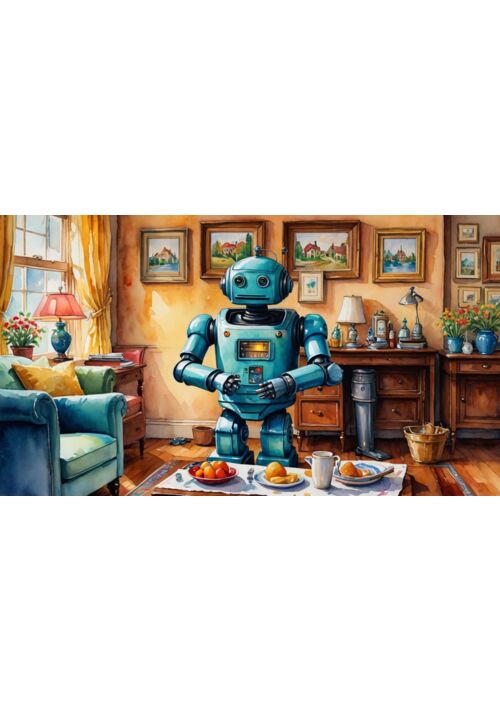
AI執事、今日もやらかす ~ポンコツだけど憎めない人工知能との奇妙な共同生活~
鷹栖 透
SF
AI執事アルフレッドは完璧なプレゼン資料を用意するが、主人公の花子は資料を捨て、自らの言葉でプレゼンに挑む。完璧を求めるAIと、不完全さの中にこそ真の創造性を見出す人間の対比を通して、人間の可能性とAIとの関係性を問う感動の物語。崖っぷちのデザイナー花子と、人間を理解しようと奮闘するAI執事アルフレッドの成長は、あなたに温かい涙と、未来への希望をもたらすだろう。

ふたつの足跡
Anthony-Blue
SF
ある日起こった災いによって、本来の当たり前だった世界が当たり前ではなくなった。
今の『当たり前』の世界に、『当たり前』ではない自分を隠して生きている。
そんな自分を憂い、怯え、それでも逃げられない現実を受け止められるのか・・・。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した
若き日の滝川一益と滝川義太夫、
尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として
天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が
からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

DEADNIGHT
CrazyLight Novels
SF
総合 850 PV 達成!ありがとうございます!
Season 2 Ground 執筆中 全章執筆終了次第順次公開予定
1396年、5歳の主人公は村で「自由のために戦う」という言葉を耳にする。当時は意味を理解できなかった、16年後、その言葉の重みを知ることになる。
21歳で帝国軍事組織CTIQAに入隊した主人公は、すぐさまDeadNight(DN)という反乱組織との戦いに巻き込まれた。戦場で自身がDN支配地域の出身だと知り、衝撃を受けた。激しい戦闘の中で意識を失った主人公は、目覚めると2063年の未来世界にいた。
そこで主人公は、CTIQAが敗北し、新たな組織CREWが立ち上がったことを知る。DNはさらに強大化しており、CREWの隊長は主人公に協力を求めた。主人公は躊躇しながらも同意し、10年間新しい戦闘技術を学ぶ。
2073年、第21回DVC戦争が勃発。主人公は過去の経験と新しい技術を駆使して戦い、敵陣に単身で乗り込み、敵軍大将軍の代理者を倒した。この勝利により、両軍に退避命令が出された。主人公がCREW本部の総括官に呼び出され、主人公は自分の役割や、この終わりなき戦いの行方について考えを巡らせながら、総括官室へ向かう。それがはじまりだった。

恋するジャガーノート
まふゆとら
SF
【全話挿絵つき!巨大怪獣バトル×怪獣擬人化ラブコメ!】
遊園地のヒーローショーでスーツアクターをしている主人公・ハヤトが拾ったのは、小さな怪獣・クロだった。
クロは自分を助けてくれたハヤトと心を通わせるが、ふとしたきっかけで力を暴走させ、巨大怪獣・ヴァニラスへと変貌してしまう。
対怪獣防衛組織JAGD(ヤクト)から攻撃を受けるヴァニラス=クロを救うため、奔走するハヤト。
道中で事故に遭って死にかけた彼を、母の形見のペンダントから現れた自称・妖精のシルフィが救う。
『ハヤト、力が欲しい? クロを救える、力が』
シルフィの言葉に頷いたハヤトは、彼女の協力を得てクロを救う事に成功するが、
光となって解けた怪獣の体は、なぜか美少女の姿に変わってしまい……?
ヒーローに憧れる記憶のない怪獣・クロ、超古代から蘇った不良怪獣・カノン、地球へ逃れてきた伝説の不死蝶・ティータ──
三人(体)の怪獣娘とハヤトによる、ドタバタな日常と手に汗握る戦いの日々が幕を開ける!
「pixivFANBOX」(https://mafuyutora.fanbox.cc/)と「Fantia」(fantia.jp/mafuyu_tora)では、会員登録不要で電子書籍のように読めるスタイル(縦書き)で公開しています!有料コースでは怪獣紹介ミニコーナーも!ぜひご覧ください!
※登場する怪獣・キャラクターは全てオリジナルです。
※全編挿絵付き。画像・文章の無断転載は禁止です。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















