32 / 84
第32話 特別
しおりを挟む
誰かの特別になりたかった。
俺の周りには昔から特別な人たちがいっぱいいた。
不思議だったり、才能があったり、或いはその両方を持っていたり、病的だったり、脅迫的であったり、あるいは何も考えていなかったり。
そういう特別を俺は目指していた。
桜庭しづるという少年は――俺という凡庸な少年は。
生まれ持って他にはないもの、そういうものがきっと自分にはあると信じていた。
例えば――誰よりとまで言わなくても人の考えていることがわかったり、ほんの少し未来を見通す頭脳があったり、或いは器用な指先で自分の作りたいものを何でも作れてしまったり、一番と行かなくても賢かったり、何かの才能に多少恵まれていたり――
けれど今になって思えば、それはそう思い込んでいただけに過ぎなかった。
それは――隣にずっと、ずっと。特別なアイツが居やがったからだ。
悠里。非凡な才を持つ人間。
俺とは生きる世界が違う癖に――俺とは違う非凡な癖に。
ずるいという言葉は決してかけてはいけないのをわかっている。
アイツが誰よりも弱いことを俺は知っている。
アイツが誰よりも一人では生きられなかったことを知っている。
アイツが誰よりも時間をかけて生きる術を身につけようとしてきたことを知っている。
それでも、どうしてもアイツには敵わない――どこかで負けている。
俺が食らいついたと思う度にアイツはひらりとすり抜けて、何食わぬ顔で一歩先にいる。
遠い――凡庸には、余りにも遠い一歩先に。
何一つ人と違わない――ただ特別さを知ってしまっただけの自分では決して届かないとさえ思うその先に。
陽炎のようなアイツがずっと立っている。
知らず手を伸ばす。欲しいんだ。なんでもいい、特別さが……。
俺がアイツの隣に立って何も気負わなくていい、たったそれだけの特別さが――。
「――ここは」
俺は何度も夢に現れる道に立っていた。
通り慣れた実家前の新しい道路。
その道は平坦で、優しく太陽が照りつけている。
風は穏やかで、どこまでも緩やかに歩きやすい道が広がっている。
無限に分岐する道の先はどれも断ち切れている、手前の道のどこも踏み跡は途切れて消えていた。
俺はまっすぐに歩いて行く。
どこまでも行くと、夜に差し掛かり始めた。
俺はなんとなくの気分で隣の道に逸れた。
それは暗い山の中に繋がっていた――星の零れて見える空があった。
「兄ちゃん、どこに行くんだい」
ふいに隣から誰かが俺に話しかけた。
道の脇に、古ぼけた年寄りがいた。
真っ赤な日に焼けた顔で、真っ青な眼をしていた。
ボロの布だけを身に纏い、大きな石の上に腰掛けている。
俺には一瞥くれないのに、言葉だけは正面を向いていた。
「星を見に行くんだ。そっちに星が綺麗に見えそうな山があったから」
老人はぼろぼろの歯を見せて、象の嘶きの様な声でにまりんと嗤った。
「やめとけ、まだここは工事中なんだ。また来なよ。そしたら開けといてやる」
「なんの工事をしてるんだ?」
「もう少ししたらわかる。それよりいいのか、早く戻らないと戻れなくなるぜ」
「戻る? 俺が一体どこに戻るっていうんだよ」
「どこへでも。お前、そもそも呼ばれてただろ。思い出せよ」
「呼ばれてた――俺が?」
「ああ。そのまま270度ターンして-90度したらそのまま踏み出せよ。そしたら思い出すだろ」
「なんだそれ180度って素直に言えよ……じゃあまた来る」
「おう。達者でな」
「あ、そうだ。ここ、何ができるんだ?」
「そうさな。別になんてこったないんだがぁね。『小さな思い出』ができる」
「『小さな思い出』――自然公園みたいなもんか?」
「それはできてのお楽しみだ。行った行った」
俺は会釈だけして踵を返すと、平坦な道を歩き始めた。
暑くもなく寒くもなく、ほんの少しの雨が時折降った。
どこまでも進む内に、月が高く上り始めた。
俺はだんだん眠くなってきて、道路の脇の柔らかい芝生の上で眠り始めた。
次の朝も迎えられると信じて――。
「――」
胸と首が熱い。
なのに体中がいうことがを聞かない。
耳元にはガソリンエンジンの音と、人工皮革の嫌いな匂いが漂っている。
俺は――仰向けになっていた。胸の上に重力の重みを感じる。何かが乗っているのだろうか。
天井は曲がって見える。
首が動かない。いや、動けないのか。
何かで押さえつけている。
これは暖かさがあって、柔らかくて――しっとりと濡れている。
……息苦しい。なんだこれは。
暫く身じろぎもできないままなされるがままにされていると、ゆっくりと視界の揺れと歪曲は収まってきた。
意識もようやく自分の現状に思いを馳せるくらいの余裕が生まれてきて、俺は“寒い”と感じ始めていた。
「ん……」
辺りは暗い。
目の前には丸いフレームと、更にその30センチほど向こう側に大きな四角いフレーム。
天井は低い――ここは……。
「はっ――礼香ッ!」
跳ね起きようと腹筋に力を入れた瞬間、背中に恐ろしい寒気が駆け上がった。
「――うッ――ぐ」
内臓から響くような痛みと、筋肉を無理やり牽いたような激しい疼痛に声も出ない。
「……しづるさん。起きたんですか」
「――」
首元から暖かいものが離れて、礼香の声は目の前から聞こえた。
「大丈夫、じゃないですよね。ごめんなさい」
「礼香――無事だったか、よかった」
俺は痛みよりも、礼香が無事なことに安堵していた。
「怪我はないか、目立つところに傷とかは――」
「大丈夫……大丈夫ですよ。私はいい……本当にバカな人――あなたの方が死にそうだったのに」
左手の方をそっと見やると、不格好ながらきつくタオルが巻かれていた。止血はできているようだった。
「手当してくれてたのか……それに車まで運んでくれてる」
「……先にごめんなさい。その……暖めるために車まで連れてこなきゃって思ったけど力も知恵も足りなくって。地面に水を蒔いて泥濘ませてから引きずってきたんです。だからシートもお洋服もどろんこになっちゃった……」
「……いや、驚いた。十分機転が利いてる。むしろその足でよく俺を車まで連れてこられたな。シートと服はいいよ。シートはともかく……服はどうせ替えもあるんだ」
暗い中、二人の声と息だけが車を満たしていた。
呼吸する度に俺の胸の上で小さく礼香とその長い髪が揺れた。礼香は首筋から汗を光らせて、それでも俺をきつく抱いて体温を伝えてくれていた。
……間違いなく礼香の体温がなければ目覚めることはできなかっただろう。
「とにかく暖めなきゃって思って。……ごめんなさい」
礼香の声は上擦っていた。俺はかける言葉もなかった。
「おかげで助かった……間違いなくこうしてくれなかったら死んでたと思う。むしろ――指先も動く。うまくやってくれた」
幸運なことにあれだけ氷点下の水に浸かりっぱなしだったというのに、末端もちゃんと感触が戻っている。
あれからどれだけの時間が経っているのかはわからないが、ここまでやれたのは賞賛に値する。
「俺の気が付いてる内に出発しよう……そういや、“お祈り”はできてたのか?」
「どうやらできてるみたいです……。知らない間にどうしてだろう……」
「さっきのこと、覚えてはいるか?」
「ぼんやりだけですけど……理由は――どうなんだろう、ごめんなさい」
礼香は歯切れ悪そうにそう言った。
「今はいい。出よう。帰ろう、急いで」
車のライトを点灯させると、思ったよりも車内の状態は酷かった。
当然、俺も礼香もなのだがそれについてはわざわざ言及する必要はなかった。
礼香はそっと助手席に座ると、俺の方をおずおずと見つめた。
「大丈夫。怒ってない」
「ほんと、ですか……」
「怒る元気もないしな。行くぞ」
ハンドルをゆっくりと握る。
「ぐっ……」
硬直していた筋肉がゆっくりとほぐれていく。
指先は少し滑りがあるが、十分誰も居ない夜道程度なら運転も不可能ではないだろう。
アクセルを踏んで、引き返す。
「それにしても本当にちゃんと動くな……礼香、どうやって指とか暖めてくれたんだ?」
「へぇっ!? こ、こう。こんな感じですよ」
礼香は慌てたように手と手を合わせてすりすりともみ合わせる。しかし噛み合いの悪い歯車のように指先は外れている。
「……器用だな」
「い、いいじゃないですか。今は。それより運転に集中しないとあ、危ないですよ」
「それもそうだな――あ、俺がふらっとしたら構わずに殴ってくれ。そっちのが却って危険だからな」
「は、はい! 礼香がんばりましゅ!」
「顎はやめてくれよ」
「気をつけます……」
妙に背筋を伸ばした礼香を助手席に乗せて、車は闇の中を滑って街頭に向けて漕いでいた。
星は相変わらず綺麗に映えていたが、それどころではなかった。
また奇怪な一件に遭遇している。
運良く今は意識があるが、きっと着く頃にはもう限界だろう。思考を整えるなら今しかない。
「礼香、湖でお祈りをしてる時、急に湖に向かって歩いて行ったのは覚えてるか……? その時、礼香の足下の水は凍ってた」
「……はい。覚えてます。でもそこからなんだか意識がぼうっとしてて、自分が何を考えていたとかっていうのがはっきりしてないんです。なんて言うんでしょう……」
「言い表しにくい、か。そりゃあそうだよな。あんな経験、普通に生きててポンポンあったらそっちの方が問題だ」
「う~ん、ごめんなさい……なんだかこう、脳に直接幽霊が入ってきたみたいな感覚っていうか……白昼夢っていうか明晰夢っていうか……そんな感じだったんです」
「いや、いい。そこ自体は重要じゃないんだ。問題はそれが初めてかってことなんだけど……今の回答を見るに初めてなんだよな?」
「はい、初めてだったし正気に戻ってびっくりしたくらいでした――あんなに冷たいところにいたはずなのに私は全然怪我もないですし」
「そうか……そのお父さんにも聞いたことはないよな、いや殆ど覚えてないんだったか。ごめん、頭が回ってないみたいだ。悪いことを聞いた」
「……いえ」
礼香は通り過ぎていく路灯を見上げながら、考えるように黙りこくった。
「もう一つ疑問がある。その石なんだけど、やっぱり妙な力――こういうより他に言い様がないもの……があるみたいだ。礼香に自覚がないとするなら、やっぱりさっき起こったことの原因はその石か礼香、或いはどちらも揃っている状況に起因にしているって考えるのが妥当だ。その石について何か聞いたことはないか?」
「ん……この石はお父さんがお母さんに貰ったものみたい……っていうのは聞いた気がします。それもはっきり覚えているわけではないんですけど」
「そうか、まあ昔のことだ、そんなもんだよな――」
「はい……力になれなくてすみません」
「気にしないよ」
エンジン音だけが聞こえる車内で俺は黙々と運転を続け、礼香も随分疲労しているからかうつらうつらと船を漕ぎ始めていた。
湖で起こったあの極端な冷却現象――あんな事例は世界中探し立ってないだろう。終わり際に流れていった雪星、ひょっとして何か関係があるのだろうか。
俺は疲労と肉体の負荷でもう既に限界に近かったがなんとか思考を止めないことで意識を現実に結びつけていた。
久遠にも感じる時間の中、街路の立ち並ぶ街の中に戻ってきたのは既に星空が大きく回ってからのことだった。
「礼香、ようやっと着いたぜ」
「ふぁっはい!」
想像以上の疲労だ――。正直もう動きたくないのだが、ここで寝入ってしまったら本気で明日に目覚められなくなりそうだ。
「あっ」
「どうした? 礼香、何かあるか?」
「あ、あの、どうしましょう、お風呂」
「どうしよって、どういう」
「二人とも酷い有様ですけど、どっちかが入ってる間ここで待ちます……?」
「あー……それな」
それについては全く考えてなかった。
けど俺ももう既に正直死に体に近いことを自覚している。
おまけに正直寒気が酷い、完全に回復しているわけではないから当たり前なのだけれど。
「礼香、先に行くなら行ってもいいぜ」
「あ、あの……でもしづるさんの体の方が酷い状態ですし……」
「いや、構わない――いいよ」
完全に強がりであることは俺が一番理解していた。
こんなのは自殺行為だ。だがもう既に礼香と入浴の順番や仔細についての相談をするにあたっての体力がないことも事実だった。
どうとでもなってしまえ、意識を投げかけたその時だった。
「ダメです。しづるさん。一緒に入りましょう」
「は――? え?」
呆気にとられる俺をよそに、礼香は杖を器用についてドアを開けると、俺の肩に潜り込んだ。
「いいです。何も言わないでください。いいんです。だから私に甘えてください」
「……」
無言で脱衣所に叩き込まれた。
「準備しますから先に入っててください」
「お、おう……」
礼香は脱衣所からひょこりと出ると、靴下だけを脱いでどこかへ向かった。
それを確認して俺はいそいそと服を脱ぐと、タオルを巻いて風呂場に入った。
もう既に十分に暖まっている洗い場につま先が触れた瞬間、妙に涙が出た。生きている実感が、そこにあったからだった。
慎重にしゃがみ込むと流し湯をして泥を落とし、止血用の包帯で患部を圧迫する。
「……」
本来これほど傷が広いとかなり痛い作業なのだが、アドレナリンがまだ続いているのか、なんとか悶絶するだけで済んだ。
「ぐっ……」
流れるぬるま湯程度の温度でも末端は灼けたように痛む。重度の凍傷にならなかっただけでもかなりの幸運だとは分かっていても、末端の細胞組織が壊れていくのが如実に感じられる痛みというのは流石に堪える。
ようやくシャワーの温度に慣れた肌を流し、曇った鏡を左手で磨くと後ろでノックの音が響いた。
「入りますよ――」
「あ、ああ」
酷く緊張したような声で入ってきた礼香を直視しないように俺は正面を向いた。
「あ――」
「あ――」
磨いた鏡の中の礼香と目が合った。
俺の首元には身に覚えのない赤い斑点が大きくあざになっていた。
そしてタオルを巻いた礼香はその首元を見て、瞳を真っ赤に乱反射させながら指の隙間でこちらを見ていた。
白く湯気に揺蕩う中、俺と礼香の視線は交錯して交わらなかった。
この二人きりの狭い密室の中、俺の目の前には鏡があった。
鏡には顔を下手に隠す礼香と、俺自身の首に付いた真っ赤な痣が点々と浮き出ていた。
「れ、礼香……? これなんなんだ?」
「……」
礼香は顔を赤らめたまま微動だにせず暫く経って後ずさると、足を庇いながら静かに座り込み、体を流した。何度かその水音が響いた後、すっくと立ち上がった礼香は手の平を首元に添えた。
「あったかい、ですか?」
手の温度は温かかった。人肌の馴染む温度は俺の首筋を通って、末端の痛みを和らげてくれていた。それは間違いなく、人肌の魔力であった。吸い付くようなきめやかな手の平が直に俺の体を触れていた。
「……ああ。あたたかい。安まる感じがするよ」
「じゃあ、今度はこっち」
礼香はそのまま流れる水のような絹の髪を耳にかけると、しなだれかかって俺の背中の影に隠れた。
「っはぁ、む……」
背中を濡れた穂先が小さく撫ぜた。背中の影の中で礼香は淑やかに注意深く動いていた。背中に広がるじわりとした熱を感じながら、俺はようやく指先が無事だった理由に得心がいっていた。
やがて柔らかく包み込むような感覚が離れていく去り際、ほんの少しの水音だけが残り、礼香の声が聞こえた。
「どっちが温かかったですか?」
「後の方、だな」
「なら、これ以上は聞かないで下さい。あの、その、この。えと、やっぱり恥ずかしいですから」
「ああ……ありがとう。おかげで助かった」
俺の首元の痣は、礼香が俺の体温を必死に保とうとしてくれていた名残だった。血液の温度を少しでもあげようと礼香なりに必死に行動したのだ。頸静脈を狙って温めてくれていたなら、直接生存に関係ある行動だった。
「礼香。本当に頑張ったな。多分礼香が居なきゃ本当に死んでた」
「えへ……まあ私が居なきゃこんなに怪我することもなかったでしょうけどね……」
背中に体を預けて嬉しそうに笑む礼香の表情は、今までの緊張が解けたように頬は緩んでいた。
「大胆に出たな、それにしたって」
「私もそう思います。だって、きっと普段の私じゃ思いつかない」
「俺もだ。だから見た瞬間驚かされた」
ただの窮地の閃きなのだろうか。いや、俺は少し違う予感を持っていた。これはきっと成長だ。礼香が持っていたものが伸びつつある。そうなら俺の怪我も浮かばれるというものだ。
「さ、肩、貸しますから浸かって下さい」
「悪い、迷惑を掛ける」
湯に触れた足先がビリビリとしびれる。
「っつーー……」
「ゆっくり慣らしてから入って下さいね。ぬるい温度にしてありますけど」
「早めに老人になった気分だ……」
「無理しないで下さいねおじいさま」
「だ~れがおじいさまだ……っ、ふう」
足先が通過した辺りで湯の温度はようやく体に馴染んだ。生きている――心地だ。
「……苦しくないですか?」
「大丈夫、ちょっと情けなさにこころ打ちひしがれてるけどな……」
入り始めに激痛を発していた末端も、長い時間を掛けてこの温度になれ始めていた――というよりも、低温によってシャットダウンされていた肉体の機能がゆっくりと解放され始めたような実感が表現としてはしっくりと来る。視界の揺れの正常化、思考機能の回復、常に酸欠状態だった呼吸の復元……。これはこれで仕事の役に立つ経験かもな……勿論、俺が精神の方が専門だってことを加味した上での評価ではあるけれど。
「……」
礼香は汚れてしまった体や髪をゆっくりと時間を掛けて洗い上げていった。こちらを見る瞳は何度も揺れて恥じらっているのがわかったが、何も言えなかった。きっと本人が一番驚いているのだろう。首元の赤痣も然り、今のこの状況然り、きっと礼香本人も理由が分からない内から動いているのだろう。正にそれを表現するなら“衝動”という言葉が正しいように。
幸いだったのは、俺がこの短期間でものを考えられるまで回復していたことだった。俺の頭の中にある悩みは自分の生死――つまり明日の朝に呼吸して目覚められるかという極めて生物的な問いから、ある伝えなければならないことに変わり、それに思考の比重は大きく割かれていた。
「しづるさん、のぼせてませんか?」
頬に手の平が触れる。目と目が合い、礼香が静かに微笑んだ。
「大丈夫、考え事をしてたぐらいなんだ」
「そうですか。なにかあったら私にすぐ言って下さいね」
「ああ……」
礼香にとっての俺は今、どんな位置にいるのだろう。その答えは、この張り切りようから“弟”に近いものになっていると考えるのが妥当だった。
そう、伝えるべきことがあるだろう。
「礼香」
蛇口を捻る音と共に、礼香の視線だけがこちらを向いた。長い髪が多くの水気を含んでしっとりと嫋やかに流れている。元々目元の隠れた重めのヘアスタイルだからわかりにくいが、はっきりとした目鼻立ちにあどけなさ残る頬紅は未来に彼女が美しい女性になることを予見させていた。
「後で話しておきたいことがあるって言ったよな。お風呂を上がったらでいいから、少し話そう」
少し俯いた礼香は、こちらをもう一度向き直った。
「……蕾のことですか?」
「……!」
「わかります。なんとなく。しづるさんが時間を取って話してくれることはきっとそのことですから」
「……悪いね。切り出し方が上手じゃなくて」
「いえ。全然気にしません。失礼しますね」
タオルで髪を巻き上げた礼香はそっと湯船に足先から浸かってきた。
俺の足の間に礼香はちょこんと器用に座って、俺たちは対面していた。
「雷くんの靴が見つかった。そして君に宛てての手紙もあった。車のトランクに置いてあるんだ……。内容は、君に向けてのものがほとんどだ。目を通してない。見つかったのは廃教会の丘の地下室で、理由は不明だ。靴は半分だけしか見つからなかった。それ以外のものもなかった。けど雷くんはこの世界に存在したんだ。確かに。そこにいた形跡があった」
「そう、ですか。よかった」
よかった――。そんな言葉が壁にやけに反射して波紋になって鼓膜に響いた。
無言で礼香の腕が俺の胴に添えられた。俯いた唇の端は結ばれて少しも動くことはなかった。
「居ないって覚悟してたから、雷が居たってだけで一歩前進です。ね、そうですよね」
縋るような目に、俺はただ頷くことしかできなかった。誰にもこの思いはわからないだろう。分かった気になるのは余りにも傲慢で、不誠実だろう。
「君の思うままに」
「はい、これはきっと前進なんです。悲しい行進でも、進み続ける限りは意味がありますから。そこに答えを得ることにきっと意味がある――それがいい報せだろうと悪い報せだろうと」
「――ああ。そうだな。進み続けよう」
悲しい行進でも、進み続ける限りは意味がある――それの意味するところは死への巡礼だ。
人間という生に縛られた生き物は進み続ける限りその先に必ず死が存在する。生とは道程でしかなく、最後は死に帰着する。
悲しみ、怒り、喜び、笑い――成長、孤独、融和、社会、あらゆる経験は死のために積み上げられるとさえ言い換えられるだろう。
そして、その始まりの場所に礼香は居る。代わってやることもなかったことにすることもできない――。これが、きっと彼女を形作る世界の雛だから。
「……さ、あがりましょう。のぼせちゃいますよ」
礼香は顔を湯船に浸けて犬のように水を払うと、俺の背中に腕を回して胸に飛び込んできた。
「しづるさん」
細い肩周りが少し震えていた。
「……」
「会えたのがしづるさんでよかった」
「……そうか」
礼香を促すように一つ頭を撫でてやると、真っ直ぐとガーネットの瞳がこちらを見た。
「立てますか」
「ああ、だいぶん回復したからもう大丈夫」
――その後、風呂を上がった俺は玄関に彼の靴を置き、ベッドを借りて眠り始めた。今できることはもう既にやりきった。これ以上は高望みというものだ。
そしてこれからの時間は、礼香の為の時間だ。俺にできることなんて何もない。
せいぜいゆっくりと眠ること。もう何日マトモに寝入ってないだろう。普通な俺にしては頑張りすぎたくらいだ。
「悠里……」
だというのに、胸騒ぎがしていた。天井を見上げる眠い目が閉じないのが良い証拠だった。
アイツは無事だろうか。
「大丈夫だ、しづる。アイツは俺の知ってる一番の特別製だろ」
言い聞かせるように天井に言い放つと、俺は意識をどこかにぶん投げた。
俺の周りには昔から特別な人たちがいっぱいいた。
不思議だったり、才能があったり、或いはその両方を持っていたり、病的だったり、脅迫的であったり、あるいは何も考えていなかったり。
そういう特別を俺は目指していた。
桜庭しづるという少年は――俺という凡庸な少年は。
生まれ持って他にはないもの、そういうものがきっと自分にはあると信じていた。
例えば――誰よりとまで言わなくても人の考えていることがわかったり、ほんの少し未来を見通す頭脳があったり、或いは器用な指先で自分の作りたいものを何でも作れてしまったり、一番と行かなくても賢かったり、何かの才能に多少恵まれていたり――
けれど今になって思えば、それはそう思い込んでいただけに過ぎなかった。
それは――隣にずっと、ずっと。特別なアイツが居やがったからだ。
悠里。非凡な才を持つ人間。
俺とは生きる世界が違う癖に――俺とは違う非凡な癖に。
ずるいという言葉は決してかけてはいけないのをわかっている。
アイツが誰よりも弱いことを俺は知っている。
アイツが誰よりも一人では生きられなかったことを知っている。
アイツが誰よりも時間をかけて生きる術を身につけようとしてきたことを知っている。
それでも、どうしてもアイツには敵わない――どこかで負けている。
俺が食らいついたと思う度にアイツはひらりとすり抜けて、何食わぬ顔で一歩先にいる。
遠い――凡庸には、余りにも遠い一歩先に。
何一つ人と違わない――ただ特別さを知ってしまっただけの自分では決して届かないとさえ思うその先に。
陽炎のようなアイツがずっと立っている。
知らず手を伸ばす。欲しいんだ。なんでもいい、特別さが……。
俺がアイツの隣に立って何も気負わなくていい、たったそれだけの特別さが――。
「――ここは」
俺は何度も夢に現れる道に立っていた。
通り慣れた実家前の新しい道路。
その道は平坦で、優しく太陽が照りつけている。
風は穏やかで、どこまでも緩やかに歩きやすい道が広がっている。
無限に分岐する道の先はどれも断ち切れている、手前の道のどこも踏み跡は途切れて消えていた。
俺はまっすぐに歩いて行く。
どこまでも行くと、夜に差し掛かり始めた。
俺はなんとなくの気分で隣の道に逸れた。
それは暗い山の中に繋がっていた――星の零れて見える空があった。
「兄ちゃん、どこに行くんだい」
ふいに隣から誰かが俺に話しかけた。
道の脇に、古ぼけた年寄りがいた。
真っ赤な日に焼けた顔で、真っ青な眼をしていた。
ボロの布だけを身に纏い、大きな石の上に腰掛けている。
俺には一瞥くれないのに、言葉だけは正面を向いていた。
「星を見に行くんだ。そっちに星が綺麗に見えそうな山があったから」
老人はぼろぼろの歯を見せて、象の嘶きの様な声でにまりんと嗤った。
「やめとけ、まだここは工事中なんだ。また来なよ。そしたら開けといてやる」
「なんの工事をしてるんだ?」
「もう少ししたらわかる。それよりいいのか、早く戻らないと戻れなくなるぜ」
「戻る? 俺が一体どこに戻るっていうんだよ」
「どこへでも。お前、そもそも呼ばれてただろ。思い出せよ」
「呼ばれてた――俺が?」
「ああ。そのまま270度ターンして-90度したらそのまま踏み出せよ。そしたら思い出すだろ」
「なんだそれ180度って素直に言えよ……じゃあまた来る」
「おう。達者でな」
「あ、そうだ。ここ、何ができるんだ?」
「そうさな。別になんてこったないんだがぁね。『小さな思い出』ができる」
「『小さな思い出』――自然公園みたいなもんか?」
「それはできてのお楽しみだ。行った行った」
俺は会釈だけして踵を返すと、平坦な道を歩き始めた。
暑くもなく寒くもなく、ほんの少しの雨が時折降った。
どこまでも進む内に、月が高く上り始めた。
俺はだんだん眠くなってきて、道路の脇の柔らかい芝生の上で眠り始めた。
次の朝も迎えられると信じて――。
「――」
胸と首が熱い。
なのに体中がいうことがを聞かない。
耳元にはガソリンエンジンの音と、人工皮革の嫌いな匂いが漂っている。
俺は――仰向けになっていた。胸の上に重力の重みを感じる。何かが乗っているのだろうか。
天井は曲がって見える。
首が動かない。いや、動けないのか。
何かで押さえつけている。
これは暖かさがあって、柔らかくて――しっとりと濡れている。
……息苦しい。なんだこれは。
暫く身じろぎもできないままなされるがままにされていると、ゆっくりと視界の揺れと歪曲は収まってきた。
意識もようやく自分の現状に思いを馳せるくらいの余裕が生まれてきて、俺は“寒い”と感じ始めていた。
「ん……」
辺りは暗い。
目の前には丸いフレームと、更にその30センチほど向こう側に大きな四角いフレーム。
天井は低い――ここは……。
「はっ――礼香ッ!」
跳ね起きようと腹筋に力を入れた瞬間、背中に恐ろしい寒気が駆け上がった。
「――うッ――ぐ」
内臓から響くような痛みと、筋肉を無理やり牽いたような激しい疼痛に声も出ない。
「……しづるさん。起きたんですか」
「――」
首元から暖かいものが離れて、礼香の声は目の前から聞こえた。
「大丈夫、じゃないですよね。ごめんなさい」
「礼香――無事だったか、よかった」
俺は痛みよりも、礼香が無事なことに安堵していた。
「怪我はないか、目立つところに傷とかは――」
「大丈夫……大丈夫ですよ。私はいい……本当にバカな人――あなたの方が死にそうだったのに」
左手の方をそっと見やると、不格好ながらきつくタオルが巻かれていた。止血はできているようだった。
「手当してくれてたのか……それに車まで運んでくれてる」
「……先にごめんなさい。その……暖めるために車まで連れてこなきゃって思ったけど力も知恵も足りなくって。地面に水を蒔いて泥濘ませてから引きずってきたんです。だからシートもお洋服もどろんこになっちゃった……」
「……いや、驚いた。十分機転が利いてる。むしろその足でよく俺を車まで連れてこられたな。シートと服はいいよ。シートはともかく……服はどうせ替えもあるんだ」
暗い中、二人の声と息だけが車を満たしていた。
呼吸する度に俺の胸の上で小さく礼香とその長い髪が揺れた。礼香は首筋から汗を光らせて、それでも俺をきつく抱いて体温を伝えてくれていた。
……間違いなく礼香の体温がなければ目覚めることはできなかっただろう。
「とにかく暖めなきゃって思って。……ごめんなさい」
礼香の声は上擦っていた。俺はかける言葉もなかった。
「おかげで助かった……間違いなくこうしてくれなかったら死んでたと思う。むしろ――指先も動く。うまくやってくれた」
幸運なことにあれだけ氷点下の水に浸かりっぱなしだったというのに、末端もちゃんと感触が戻っている。
あれからどれだけの時間が経っているのかはわからないが、ここまでやれたのは賞賛に値する。
「俺の気が付いてる内に出発しよう……そういや、“お祈り”はできてたのか?」
「どうやらできてるみたいです……。知らない間にどうしてだろう……」
「さっきのこと、覚えてはいるか?」
「ぼんやりだけですけど……理由は――どうなんだろう、ごめんなさい」
礼香は歯切れ悪そうにそう言った。
「今はいい。出よう。帰ろう、急いで」
車のライトを点灯させると、思ったよりも車内の状態は酷かった。
当然、俺も礼香もなのだがそれについてはわざわざ言及する必要はなかった。
礼香はそっと助手席に座ると、俺の方をおずおずと見つめた。
「大丈夫。怒ってない」
「ほんと、ですか……」
「怒る元気もないしな。行くぞ」
ハンドルをゆっくりと握る。
「ぐっ……」
硬直していた筋肉がゆっくりとほぐれていく。
指先は少し滑りがあるが、十分誰も居ない夜道程度なら運転も不可能ではないだろう。
アクセルを踏んで、引き返す。
「それにしても本当にちゃんと動くな……礼香、どうやって指とか暖めてくれたんだ?」
「へぇっ!? こ、こう。こんな感じですよ」
礼香は慌てたように手と手を合わせてすりすりともみ合わせる。しかし噛み合いの悪い歯車のように指先は外れている。
「……器用だな」
「い、いいじゃないですか。今は。それより運転に集中しないとあ、危ないですよ」
「それもそうだな――あ、俺がふらっとしたら構わずに殴ってくれ。そっちのが却って危険だからな」
「は、はい! 礼香がんばりましゅ!」
「顎はやめてくれよ」
「気をつけます……」
妙に背筋を伸ばした礼香を助手席に乗せて、車は闇の中を滑って街頭に向けて漕いでいた。
星は相変わらず綺麗に映えていたが、それどころではなかった。
また奇怪な一件に遭遇している。
運良く今は意識があるが、きっと着く頃にはもう限界だろう。思考を整えるなら今しかない。
「礼香、湖でお祈りをしてる時、急に湖に向かって歩いて行ったのは覚えてるか……? その時、礼香の足下の水は凍ってた」
「……はい。覚えてます。でもそこからなんだか意識がぼうっとしてて、自分が何を考えていたとかっていうのがはっきりしてないんです。なんて言うんでしょう……」
「言い表しにくい、か。そりゃあそうだよな。あんな経験、普通に生きててポンポンあったらそっちの方が問題だ」
「う~ん、ごめんなさい……なんだかこう、脳に直接幽霊が入ってきたみたいな感覚っていうか……白昼夢っていうか明晰夢っていうか……そんな感じだったんです」
「いや、いい。そこ自体は重要じゃないんだ。問題はそれが初めてかってことなんだけど……今の回答を見るに初めてなんだよな?」
「はい、初めてだったし正気に戻ってびっくりしたくらいでした――あんなに冷たいところにいたはずなのに私は全然怪我もないですし」
「そうか……そのお父さんにも聞いたことはないよな、いや殆ど覚えてないんだったか。ごめん、頭が回ってないみたいだ。悪いことを聞いた」
「……いえ」
礼香は通り過ぎていく路灯を見上げながら、考えるように黙りこくった。
「もう一つ疑問がある。その石なんだけど、やっぱり妙な力――こういうより他に言い様がないもの……があるみたいだ。礼香に自覚がないとするなら、やっぱりさっき起こったことの原因はその石か礼香、或いはどちらも揃っている状況に起因にしているって考えるのが妥当だ。その石について何か聞いたことはないか?」
「ん……この石はお父さんがお母さんに貰ったものみたい……っていうのは聞いた気がします。それもはっきり覚えているわけではないんですけど」
「そうか、まあ昔のことだ、そんなもんだよな――」
「はい……力になれなくてすみません」
「気にしないよ」
エンジン音だけが聞こえる車内で俺は黙々と運転を続け、礼香も随分疲労しているからかうつらうつらと船を漕ぎ始めていた。
湖で起こったあの極端な冷却現象――あんな事例は世界中探し立ってないだろう。終わり際に流れていった雪星、ひょっとして何か関係があるのだろうか。
俺は疲労と肉体の負荷でもう既に限界に近かったがなんとか思考を止めないことで意識を現実に結びつけていた。
久遠にも感じる時間の中、街路の立ち並ぶ街の中に戻ってきたのは既に星空が大きく回ってからのことだった。
「礼香、ようやっと着いたぜ」
「ふぁっはい!」
想像以上の疲労だ――。正直もう動きたくないのだが、ここで寝入ってしまったら本気で明日に目覚められなくなりそうだ。
「あっ」
「どうした? 礼香、何かあるか?」
「あ、あの、どうしましょう、お風呂」
「どうしよって、どういう」
「二人とも酷い有様ですけど、どっちかが入ってる間ここで待ちます……?」
「あー……それな」
それについては全く考えてなかった。
けど俺ももう既に正直死に体に近いことを自覚している。
おまけに正直寒気が酷い、完全に回復しているわけではないから当たり前なのだけれど。
「礼香、先に行くなら行ってもいいぜ」
「あ、あの……でもしづるさんの体の方が酷い状態ですし……」
「いや、構わない――いいよ」
完全に強がりであることは俺が一番理解していた。
こんなのは自殺行為だ。だがもう既に礼香と入浴の順番や仔細についての相談をするにあたっての体力がないことも事実だった。
どうとでもなってしまえ、意識を投げかけたその時だった。
「ダメです。しづるさん。一緒に入りましょう」
「は――? え?」
呆気にとられる俺をよそに、礼香は杖を器用についてドアを開けると、俺の肩に潜り込んだ。
「いいです。何も言わないでください。いいんです。だから私に甘えてください」
「……」
無言で脱衣所に叩き込まれた。
「準備しますから先に入っててください」
「お、おう……」
礼香は脱衣所からひょこりと出ると、靴下だけを脱いでどこかへ向かった。
それを確認して俺はいそいそと服を脱ぐと、タオルを巻いて風呂場に入った。
もう既に十分に暖まっている洗い場につま先が触れた瞬間、妙に涙が出た。生きている実感が、そこにあったからだった。
慎重にしゃがみ込むと流し湯をして泥を落とし、止血用の包帯で患部を圧迫する。
「……」
本来これほど傷が広いとかなり痛い作業なのだが、アドレナリンがまだ続いているのか、なんとか悶絶するだけで済んだ。
「ぐっ……」
流れるぬるま湯程度の温度でも末端は灼けたように痛む。重度の凍傷にならなかっただけでもかなりの幸運だとは分かっていても、末端の細胞組織が壊れていくのが如実に感じられる痛みというのは流石に堪える。
ようやくシャワーの温度に慣れた肌を流し、曇った鏡を左手で磨くと後ろでノックの音が響いた。
「入りますよ――」
「あ、ああ」
酷く緊張したような声で入ってきた礼香を直視しないように俺は正面を向いた。
「あ――」
「あ――」
磨いた鏡の中の礼香と目が合った。
俺の首元には身に覚えのない赤い斑点が大きくあざになっていた。
そしてタオルを巻いた礼香はその首元を見て、瞳を真っ赤に乱反射させながら指の隙間でこちらを見ていた。
白く湯気に揺蕩う中、俺と礼香の視線は交錯して交わらなかった。
この二人きりの狭い密室の中、俺の目の前には鏡があった。
鏡には顔を下手に隠す礼香と、俺自身の首に付いた真っ赤な痣が点々と浮き出ていた。
「れ、礼香……? これなんなんだ?」
「……」
礼香は顔を赤らめたまま微動だにせず暫く経って後ずさると、足を庇いながら静かに座り込み、体を流した。何度かその水音が響いた後、すっくと立ち上がった礼香は手の平を首元に添えた。
「あったかい、ですか?」
手の温度は温かかった。人肌の馴染む温度は俺の首筋を通って、末端の痛みを和らげてくれていた。それは間違いなく、人肌の魔力であった。吸い付くようなきめやかな手の平が直に俺の体を触れていた。
「……ああ。あたたかい。安まる感じがするよ」
「じゃあ、今度はこっち」
礼香はそのまま流れる水のような絹の髪を耳にかけると、しなだれかかって俺の背中の影に隠れた。
「っはぁ、む……」
背中を濡れた穂先が小さく撫ぜた。背中の影の中で礼香は淑やかに注意深く動いていた。背中に広がるじわりとした熱を感じながら、俺はようやく指先が無事だった理由に得心がいっていた。
やがて柔らかく包み込むような感覚が離れていく去り際、ほんの少しの水音だけが残り、礼香の声が聞こえた。
「どっちが温かかったですか?」
「後の方、だな」
「なら、これ以上は聞かないで下さい。あの、その、この。えと、やっぱり恥ずかしいですから」
「ああ……ありがとう。おかげで助かった」
俺の首元の痣は、礼香が俺の体温を必死に保とうとしてくれていた名残だった。血液の温度を少しでもあげようと礼香なりに必死に行動したのだ。頸静脈を狙って温めてくれていたなら、直接生存に関係ある行動だった。
「礼香。本当に頑張ったな。多分礼香が居なきゃ本当に死んでた」
「えへ……まあ私が居なきゃこんなに怪我することもなかったでしょうけどね……」
背中に体を預けて嬉しそうに笑む礼香の表情は、今までの緊張が解けたように頬は緩んでいた。
「大胆に出たな、それにしたって」
「私もそう思います。だって、きっと普段の私じゃ思いつかない」
「俺もだ。だから見た瞬間驚かされた」
ただの窮地の閃きなのだろうか。いや、俺は少し違う予感を持っていた。これはきっと成長だ。礼香が持っていたものが伸びつつある。そうなら俺の怪我も浮かばれるというものだ。
「さ、肩、貸しますから浸かって下さい」
「悪い、迷惑を掛ける」
湯に触れた足先がビリビリとしびれる。
「っつーー……」
「ゆっくり慣らしてから入って下さいね。ぬるい温度にしてありますけど」
「早めに老人になった気分だ……」
「無理しないで下さいねおじいさま」
「だ~れがおじいさまだ……っ、ふう」
足先が通過した辺りで湯の温度はようやく体に馴染んだ。生きている――心地だ。
「……苦しくないですか?」
「大丈夫、ちょっと情けなさにこころ打ちひしがれてるけどな……」
入り始めに激痛を発していた末端も、長い時間を掛けてこの温度になれ始めていた――というよりも、低温によってシャットダウンされていた肉体の機能がゆっくりと解放され始めたような実感が表現としてはしっくりと来る。視界の揺れの正常化、思考機能の回復、常に酸欠状態だった呼吸の復元……。これはこれで仕事の役に立つ経験かもな……勿論、俺が精神の方が専門だってことを加味した上での評価ではあるけれど。
「……」
礼香は汚れてしまった体や髪をゆっくりと時間を掛けて洗い上げていった。こちらを見る瞳は何度も揺れて恥じらっているのがわかったが、何も言えなかった。きっと本人が一番驚いているのだろう。首元の赤痣も然り、今のこの状況然り、きっと礼香本人も理由が分からない内から動いているのだろう。正にそれを表現するなら“衝動”という言葉が正しいように。
幸いだったのは、俺がこの短期間でものを考えられるまで回復していたことだった。俺の頭の中にある悩みは自分の生死――つまり明日の朝に呼吸して目覚められるかという極めて生物的な問いから、ある伝えなければならないことに変わり、それに思考の比重は大きく割かれていた。
「しづるさん、のぼせてませんか?」
頬に手の平が触れる。目と目が合い、礼香が静かに微笑んだ。
「大丈夫、考え事をしてたぐらいなんだ」
「そうですか。なにかあったら私にすぐ言って下さいね」
「ああ……」
礼香にとっての俺は今、どんな位置にいるのだろう。その答えは、この張り切りようから“弟”に近いものになっていると考えるのが妥当だった。
そう、伝えるべきことがあるだろう。
「礼香」
蛇口を捻る音と共に、礼香の視線だけがこちらを向いた。長い髪が多くの水気を含んでしっとりと嫋やかに流れている。元々目元の隠れた重めのヘアスタイルだからわかりにくいが、はっきりとした目鼻立ちにあどけなさ残る頬紅は未来に彼女が美しい女性になることを予見させていた。
「後で話しておきたいことがあるって言ったよな。お風呂を上がったらでいいから、少し話そう」
少し俯いた礼香は、こちらをもう一度向き直った。
「……蕾のことですか?」
「……!」
「わかります。なんとなく。しづるさんが時間を取って話してくれることはきっとそのことですから」
「……悪いね。切り出し方が上手じゃなくて」
「いえ。全然気にしません。失礼しますね」
タオルで髪を巻き上げた礼香はそっと湯船に足先から浸かってきた。
俺の足の間に礼香はちょこんと器用に座って、俺たちは対面していた。
「雷くんの靴が見つかった。そして君に宛てての手紙もあった。車のトランクに置いてあるんだ……。内容は、君に向けてのものがほとんどだ。目を通してない。見つかったのは廃教会の丘の地下室で、理由は不明だ。靴は半分だけしか見つからなかった。それ以外のものもなかった。けど雷くんはこの世界に存在したんだ。確かに。そこにいた形跡があった」
「そう、ですか。よかった」
よかった――。そんな言葉が壁にやけに反射して波紋になって鼓膜に響いた。
無言で礼香の腕が俺の胴に添えられた。俯いた唇の端は結ばれて少しも動くことはなかった。
「居ないって覚悟してたから、雷が居たってだけで一歩前進です。ね、そうですよね」
縋るような目に、俺はただ頷くことしかできなかった。誰にもこの思いはわからないだろう。分かった気になるのは余りにも傲慢で、不誠実だろう。
「君の思うままに」
「はい、これはきっと前進なんです。悲しい行進でも、進み続ける限りは意味がありますから。そこに答えを得ることにきっと意味がある――それがいい報せだろうと悪い報せだろうと」
「――ああ。そうだな。進み続けよう」
悲しい行進でも、進み続ける限りは意味がある――それの意味するところは死への巡礼だ。
人間という生に縛られた生き物は進み続ける限りその先に必ず死が存在する。生とは道程でしかなく、最後は死に帰着する。
悲しみ、怒り、喜び、笑い――成長、孤独、融和、社会、あらゆる経験は死のために積み上げられるとさえ言い換えられるだろう。
そして、その始まりの場所に礼香は居る。代わってやることもなかったことにすることもできない――。これが、きっと彼女を形作る世界の雛だから。
「……さ、あがりましょう。のぼせちゃいますよ」
礼香は顔を湯船に浸けて犬のように水を払うと、俺の背中に腕を回して胸に飛び込んできた。
「しづるさん」
細い肩周りが少し震えていた。
「……」
「会えたのがしづるさんでよかった」
「……そうか」
礼香を促すように一つ頭を撫でてやると、真っ直ぐとガーネットの瞳がこちらを見た。
「立てますか」
「ああ、だいぶん回復したからもう大丈夫」
――その後、風呂を上がった俺は玄関に彼の靴を置き、ベッドを借りて眠り始めた。今できることはもう既にやりきった。これ以上は高望みというものだ。
そしてこれからの時間は、礼香の為の時間だ。俺にできることなんて何もない。
せいぜいゆっくりと眠ること。もう何日マトモに寝入ってないだろう。普通な俺にしては頑張りすぎたくらいだ。
「悠里……」
だというのに、胸騒ぎがしていた。天井を見上げる眠い目が閉じないのが良い証拠だった。
アイツは無事だろうか。
「大丈夫だ、しづる。アイツは俺の知ってる一番の特別製だろ」
言い聞かせるように天井に言い放つと、俺は意識をどこかにぶん投げた。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

ステルスセンス
竜の字
ミステリー
出版社に入社した羽津宮
一年後に退職を考えるまで追い詰められてしまう。
そんな時、1人のホームレスと出会う。
そのホームレスが持つ「ステルスセンス」
と書かれたノート、そこに書かれて居る事を
実戦して行く事で人生が好転し始める羽津宮
その「ステルスセンス」と書かれたノートの
意味とは?

夫の書斎から渡されなかった恋文を見つけた話
束原ミヤコ
恋愛
フリージアはある日、夫であるエルバ公爵クライヴの書斎の机から、渡されなかった恋文を見つけた。
クライヴには想い人がいるという噂があった。
それは、隣国に嫁いだ姫サフィアである。
晩餐会で親し気に話す二人の様子を見たフリージアは、妻でいることが耐えられなくなり離縁してもらうことを決めるが――。

(ほぼ)1分で読める怖い話
涼宮さん
ホラー
ほぼ1分で読める怖い話!
【ホラー・ミステリーでTOP10入りありがとうございます!】
1分で読めないのもあるけどね
主人公はそれぞれ別という設定です
フィクションの話やノンフィクションの話も…。
サクサク読めて楽しい!(矛盾してる)
⚠︎この物語で出てくる場所は実在する場所とは全く関係御座いません
⚠︎他の人の作品と酷似している場合はお知らせください
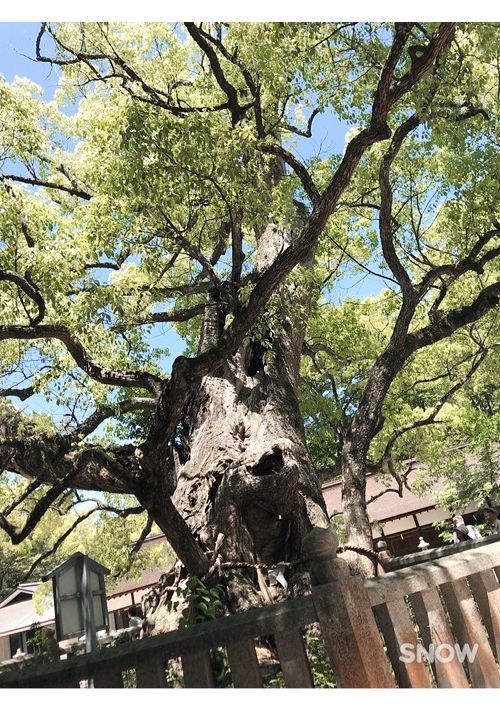


最強総長は闇姫の首筋に牙を立てる~紅い月の真実~
星空永遠
恋愛
裏社会で『闇姫』と恐れられている金髪に赤い瞳が特徴的なクール美少女の闇華。そんな闇華は紅い月を摂取した壱流を助けたあと姿を消し闇姫を卒業。
「惚れてる女の前でカッコつけてなにが悪い?」かつての弱々しい面影が消え男らしくなった壱流と高校で再会を果たす闇姫。吸血鬼になった最強総長からの溺愛吸血ラブ!
*野いちご、魔法のiらんどにて同作品掲載中(完結済)

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















