3 / 6
武士の一分
しおりを挟む
中村一氏という男がいた。早くから秀吉に仕え、重臣として大名にまで出世した武将である。しかし、関ヶ原合戦が起る前に病没してしまう。一氏は、豊臣家の家臣ではあったが、秀吉が亡くなると、早くから家康に接近し、合戦が起こる前に、すでに家康に味方する事を約束していたのだった。
一氏には息子があった。中村一忠という。一氏は、家康に息子を託していた。関ヶ原合戦には、この息子が参戦し、戦後の功により、伯耆国(鳥取県)十七万五千石の大名へ加増された。家康は、約束を果たしたのだった。
一忠は、伯耆国に移り、施政を開始した。しかし、まだ十代の若武者で政治の事など分からない。そこで、一族で重臣でもある横田村(むら)詮(あき)が家老として、施政を担う事となった。
村詮は、検地を行い、城下町を整備し、運河を広げ、国を豊かにしようと、その辣腕を大いに奮った。実際に国営は上手く行っていたらしい。しかし、いつの世にも一人だけ出世を果たすと、それを妬む者や、阻む者たちが現れるのが、世の常であっただろうか。そして、滝川三九郎の元に、ある書状が届いたのもちょうどその頃の事であった。
慶長八年(1603)二月十二日、徳川家康は、晴れて征夷大将軍の宣下を請けて、将軍となり、ここに江戸幕府が誕生した。これより、三百年近くに及ぶ、江戸時代が始まるのである。
「江戸が将軍の街になった」
と町衆たちが騒ぎ、何やら祭りがずっと続いていくかのような賑わいを見せていた。
「これで、再建が進むだろう」
と大人衆が歓び、そのまま言葉通りに江戸の町造りは、進んでいるかのようであった。そして、立て直された長屋の一室に、再び居を構えた滝川家では、主たる三九郎は無為の刻を過ごしているのだった。
「お前さま、一体どうなさるので?」
三九郎は、寝転がって三日前に届いた書状を眺めている。その横で女房のお菊は、飽きる事なく、家計の助けの為に針仕事に精を出していた。
「う~ん」
この三日間、ずっと気の無い返事を返してくるだけで、寝転がってばかりいる旦那と、それには何も言わずに健気に内職をする妻と、慎ましいが小さな幸せが、この時の二人の間にはあったのかもしれない。
「三九郎様!」
外から元気よく三九郎を呼ぶ声が聞こえる。才蔵に違いなかった。
「おう才蔵、向こうの様子はどうだ?」
「はい、変わりありません」
才蔵は、三九郎とお菊が長屋に戻った後も、真田屋敷に残り、そこから長屋へと毎日通って来ているのだった。
「今日は、三九郎様に、御客人をお連れ致しました」
才蔵の後ろに立っていた武士が笠を外して顔を見せると、途端に三九郎の顔が破顔した。
「これは、五郎右衛門殿では御座らぬか?お懐かしゅう」
「御免仕る」
男が中に入るとお菊と目が合い、互いに会釈を交わす。
「お菊、この方は、柳生五郎右衛門宗章(むねあき)殿と言うてな、わしの剣術の師で、当代切っての剣豪じゃ」
「まぁ三九郎の妻、菊と申します。このような所で申し訳ござりませぬが、どうぞお上り下さりませ」
狭い長屋の一室にて、お菊が炊事場で湯を沸かし、お茶を入れ、その湯を沸かす火の番を才蔵が受け持つ。三九郎は、客をもてなす為に、先程まで自分が寝転がっていた布団をどけるのだった。
「それで、何用で?」
「ふむ。わしは今、伯耆国中村家の家老、横田殿の剣術指南を務めておる」
五郎右衛門は、三九郎からの問いにそれだけを言うと、再び茶を飲み続けている。
「ははぁ、この書状は、どうやら先生の仕業らしい」
三九郎は、そう言うと、件の文を五郎右衛門の前に差し出した。
「さすが我が弟子、気づかれたか」
五郎右衛門は、差し出された茶の加減を確かめるように、呑むのだった。
その書状は、織田有楽斎から、中村一忠への仕官推挙の書状であったのだ。三九郎は、この書状が届いてから、その意図を計りかねて、無為の刻を過ごしていたのであった。
「今、中村家では、若殿が若年なのをよい事に、一家の功労者である横田殿を失脚させようとする動きがある。しかし、横田殿には、わしが就いておる。迂闊には手出し出来ん。しかし…」
「その若殿を警護する者がいない」
「ご明察!」
三九郎の答えに満足した五郎右衛門は、湯呑みを置き、三九郎と対するように座り直した。
「わしは、諸国を巡り、剣術修行に明け暮れた。その旅先で不意に寄っただけの一浪人に横田内膳正殿は、わしを食客として遇しただけでなく、剣術指南として、我が腕を認めてくれた。わしは恩義に報いねばならぬ」
「それで、私に若殿の警護をしろと?」
「この通りじゃ、頼む」
五郎右衛門は、深々と頭を下げた。
「どうか頭をお上げ下され」
「三九郎殿、そなたは、腕も立ち、武士として誇りある男。主を望まぬは知ってはいるが、織田有楽斎様よりの推薦状を持参すれば、中村家の剣術指南役として、召し抱える手筈になっておる」
「どうか、どうか、この柳生宗章との誼を思うて、否とは言うて下さるな」
五郎右衛門は、言葉を尽くすと、再び頭を下げ続けていた。
「承知仕った。他でも無い、わが師からの頼みです。お引き受け致しましょう」
三九郎は、五郎右衛門の両手を取ると、身体を起こしてやった。
「忝い、忝い」
三九郎は、柳生宗章という男が好きであった。この男は、柳生石舟齋の四男で、秀忠に仕える柳生宗矩の実の兄にあたる。弟である宗矩は、徳川家へ仕官したが、宗章はそれを潔しとせずに、諸国を巡り剣術の研鑽を続けたとされる。
権力欲も無く、出世欲も無い。ただただ剣の道を究める事にしか興味が無い、生粋の剣術使いと言えた。だからこそ、三九郎は、この男の事が好きな事に違いなかった。
「お菊、どうやら花のお江戸は、暫く見納めらしいぞ」
夫の唐突な宣言に、ただただ戸惑う新妻であった。
この時代、江戸から伯耆国へ陸路で行くには、中山道か東海道を通って、一度京の都へ向かい、そこから山陰道を通るルートが規定であった。三九郎たちも東海道を通って、山陰道へ向かったに違いない。途中、京の都で都見物をを楽しんだかもしれない。何せ、三九郎にとっては、久方ぶりの上方であっただろうからだ。
「お前様、西国も寒うございますなぁ」
「いま少し南に降れば、冬場でも暖かいと言うが、伯耆国は、北国と同じじゃそうな」
三九郎の後ろを歩くお菊は、長旅にも根を上げずに健気に歩を進める。
「あの柳生宗章殿とは、どういった御仁で?」
これも当然の如く、三九郎らに同行する才蔵は、いきなり現れた剣士の事が気になって仕方ない。
「あの仁は、わしの命の恩人で、剣の師匠筋にあたるお人よ。わしは、あの方に到底返し切れぬ人生の借りがあるわ」
三九郎が、まだ十代の頃に諸国を巡る旅に出ていた時の事であった。三九郎は、大和国から東国へ向かおうとする山道で、盗賊に襲われ、深傷を負ってしまった。万事休すかと思われた、その時に現れたのが宗章であった。一命を救われた三九郎は、傷を癒す為に柳生の里へ逗留し、その間に新陰流の極意を学んだのであった。
「わしも無鉄砲な若衆じゃったからのう」
「無鉄砲さは、今もお変わりありませぬが」
「こ奴!」
三人は笑う。その道中は、とても楽しそうであった。夫婦揃っての初めての旅であったし、才蔵としても、初めての長旅であった。三人とも何せまだ若いのだ。
「そら、あの山を越えれば伯耆国ぞ」
三九郎が指さす山の上には、分厚く暗い色の雲が拡がって見える。それが、領内では、すでに冬が始まっている事を感じさせていたのだった。
伯耆国と言えば、出雲の文化圏内の国であり、古くから鉄の産地として盛んであった所だ。この時の国主は、すでに述べたが、中村一氏の遺児一忠であり、米子藩十七万五千石の大名であった。
国に入った三九郎らは、旅の垢を落すと、先に戻っていた宗章と再会を果たした。宗章は、すぐに目通りの手筈を整えてくれた。
「そなたが滝川三九郎か。五郎右衛門殿から委細承知しておる」
「はっ」
謁見の席上で、先に声を掛けてきたのが、藩の執政である横田内膳村詮である。
村詮は、前主一氏の妹を妻としており、一忠にとっては、叔父にあたる。そして、家康の推薦を受けて、施政を司る立場であった。
「滝川家と我が中村家とは、縁続きと聞いたが誠か?」
上座より、まだあどけなさが残る、主の一忠がその曇りない眼で語りかける。
「左様聞いておりまする。三九郎殿の滝川家と中村家とは、甲賀より出ずる氏にて、元は同族であると」
それは、三九郎も亡父より聞いたことがある程度の事であった。
「三九郎とやら、今後は、そなたを我が一族と思おうぞ」
「ははっ」
思いがけない言葉に、三九郎は少し困惑する。
「滝川殿は、我が流派である新陰流の達人に御座います」
三九郎の困惑を見て取ってか、宗章が横より助け舟を出してくれた。
「そうであるか。村詮!」
「ははっ両名とも、我が殿に新陰流の極意とやらをお見せ頂きたい。この儀如何に?」
「承り候」
初の謁見は上々であった。二人は、並んで退席するのだった。
そして、その日の夜は、宗章宅で三九郎らを囲んだ、ささやかな宴が開かれていた。
「ささっ一杯」
宗章は、自ら三九郎やお菊に酌をし、膳を運ぶなどの気遣いをしてくれていたのだった。
「わしは、所帯持ちでないのでな。不作法はこらえてくれ。料理も酒も用意しておるゆえ、心ゆくまで楽しんでいけ」
宗章は、一人でいそいそと用意を進める。家人の数名が続いて料理を運んで来ると、さっさと退室していく。後は、三九郎らが残るばかりであった。
「そっちの若いのは、名は何と言ったか?お主も来い」
奥に一人控えている才蔵も宗章は、手招きで部屋へ誘う。
「いえ、私はここで」
「才蔵、構う事はない。こっちに来よ」
「そうだぞ才蔵とやら、若いのに遠慮はいかん」
「いえ、私はそう言う事では…」
「今宵ぐらいは、忍びとて酔ってもよかろう」
その宗章の言葉に才蔵は、敏感に反応していた。もうちょっとで胸に秘めている手裏剣に手を差し入れる所であったのだ。
「気づいておられたか?」
「そう気にする事はない。このわし以外は、気づいておらぬ」
宗章は、そう言いながら悠然と杯を干していた。これだけで、才蔵はこの仁には敵わない事を悟り、降参とばかりに両手をあげて、宗章の前にドッカリと座るのだった。
「そうだ。それでよい」
宗章は、自分が飲み干した杯を切ると、それを才蔵の前にズイっと差し出す。才蔵も何も言わずにそれを受け取ると、宗章が並々と注いだ酒を一気に飲み干して見せるのだった。
「おっ若いのにイケル口か?」
これがきっかけで、小宴は一気に盛り上がりを見せるのだった。
話しの内容は、三九郎の柳生の里での修業時代を酒の肴にして進んでいるようであった。
「それで、主人はその時どのように?」
お菊も才蔵も知らぬ十代の三九郎の姿を知る宗章の話しは、二人には新鮮そのものだった。
「三九郎殿もな、最初はカラキシで御座ったよ。しかしな、決して諦めぬ。何度叩きのめされてもな。いずれ、余りのしつこさに教える師範代たちが根を挙げ始め、結局最後には、わししか教える者もおらんなったわ」
酔いのせいか、いつもより数倍も饒舌に話す宗章とは対照的に、三九郎は、笑い続ける三人の中で、苦笑いするしかないのであった。
「ところで、殿様の御前での事どうされる?」
「うむ、わしと三九郎殿とで演武仕るとするか?」
「それは良いとして、ただ太刀の型を見せても芸はあるまい」
「ならば、どうするぞ?」
「アレで行くか?」
「アレか。よし決まりだ!」
三九郎と宗章の間でしか分からない会話が続いていた。お菊がアレとは何かを聞いても、楽しみにしていろとしか言わず、三九郎も口を割らない。むくれるお菊を才蔵が宥めていた。
「ところで、我が殿をどう見た?」
飲み続けている宗章は、さっきまでの酔っていた饒舌家の顔とはうって変り、三九郎が気づくと、その表情は鋭い剣術家としての顔を覗かせているようだった。
「やはり何かありましたか?」
それに気付いた三九郎は、宗章に問い返す。
「中村の殿は、御年十三歳と若年である。であるからして、横田殿が執政として藩を動かしておる。ここまではよいな」
宗章の荒い語気に三人は、コクンと頷く。
「最近の事だが、若殿と横田殿との間が上手く行っていない気がしてな。いや、何かあったとかではないのだが…」
「二人は、叔父甥の間柄では?」
「如何にも。しかし、時に血縁者同士は、骨肉の争いと化す場合があるでな」
ありえそうな話ではあった。年若く未熟な領主と、先主と義兄弟の間柄である百戦錬磨の主席家老とであった。何が生じても不思議ではない。
「殿がどう思っておるのかは、今一つ分からぬ。特に気性も激しく殿より御手打ちにあった者も出ていると聞く。何より、側近共が若殿を取り込もうとしておるのではないかと…」
若年より、模範となるべき父親を欠いて、それに代わる者として、横田村詮は務めていたのかもしれない。しかし、元来激しい気性を持つ若武者には、時に苦言を呈する叔父を疎ましく思っても不思議ではなかった。
「わしはな、流浪の兵法者に過ぎぬ身でありながら、こんな立派な屋敷をつけ、分不相応に扱ってくれる方に、恩を感じておるのだ」
その遠くを見つめながら話す宗章の言葉に偽りはないと、忍びであり、疑う事が職業である筈の才蔵さえもそう思えるほど、宗章の言葉は胸に染みた。
場が和み、酒と話しが尽きない。心が通じ合った相手と呑める酒は格別であっただろう。この日、二人は遅くまで飲み明かした。様々な事を語り合い、共に学んだ新陰流の今後の事も語り合っていた。宗章は、弟である柳生宗矩が、江戸将軍家の剣術指南役となっている事を歓びながらも、剣を極めるよりも、政治を追求する姿勢を嘆いている様子であった。
「苦労が絶えませぬな」
「全くだ!」
三九郎と宗章は、笑い合っていた。しかし、この時すでに何かが起こる事を二人はすでに予感していたのかもしれなかった。
新陰流ご披露の場は、後日の吉日を選び、比較的晴れた空が高い日に行われた。
そもそも、新陰流と言えば、陰流の流れを汲み、上泉伊勢守信綱によって創始された剣術の流派である。それが柳生石舟齋に伝承された。従って、柳生新陰流というのは、俗称である。
正式には、ただの新陰流である。他の新陰流を名乗る支流派や、他派との区別の為に後年呼ばれた為に過ぎない。あくまで、新陰流の正統を継いだのは、二代目石舟齋の柳生であるという自負があるのであろう。
「両名とも、存分に披露致すが宜しい」
横田村詮が声をあげた。白洲にて、大勢の見物客と、宗章の弟子となった藩士たち、そして、上座には、若殿一忠の顔が見える。太鼓のドンと言う合図と共に、一礼の後の向かい合った宗章と三九郎の二人は、佩刀を鞘から抜いて構えた。
「真剣で行うのか…」
場内より声が漏れる。しかし、二人は気にする風もなく、始めて行く。両者ともに一刀両断の構えを取り、エイッと掛け声を発すると共に、型を次々に披露していく。宗章は、斬釘截鉄の型をとり、三九郎は、燕飛をする。また宗章が村雲とすれば、三九郎は月影をすると言うように、両者が黙々とその技を披露していく。それは、とてもゆっくりと誰からも見えるように、確実に一つ一つの業を相手の寸止めで行っていく。
「何じゃ、案外に退屈なものじゃな…」
場内に溜息が、そして若殿が欠伸を漏らしてきたその時に、一連の型が終わりを告げる太鼓が一つなった。宗章は、若殿に向かって一礼する。
それが終わりの合図であると、場内に居た多勢がそう思っていたに違いなかった。しかし、宗章は、再び三九郎に対して、構えを取ると、三九郎も応じるように、再び構えて見せた。
「来い!」
宗章の大喝が合図となり、三九郎は宗章へ、猛然と剣を繰り出し始めた。今度は、先程の型とは違い、鋭い突きを見せる。そして、先程行った型の順番通りに、それを行っていく。二人は、それを寸前で見切る動作を見せつけていった。
しかも、その二人の一連のスピードは、速さを増していくばかりなのだ。三九郎が突き、宗章が鼻先で避ける。または、宗章が斬りつけ、その白刃の残像に三九郎が寸前で身体を晒していく。一見すると、すでに何度か斬られているように見える程の斬撃が、両者の間で何十合と繰り広げられていた。
先程とは違う、神業とも言うべき、技と業とのぶつかり合いに、場内で、歓声が鳴り始めていた。新陰流は、活人剣と云われる。その所以は、人を動かして勝つと言う事であり、相手の先を読む事に重きを置いた剣術であるという。
そして、その業一つ一つを見れば、わざと隙を作り、相手を誘い、その動きに反応するかのように、繰り出す業が多いように思われる。新陰流の業を知らなければ、対峙した相手は、隙があると思い、罠に嵌る事になる。
その空いている頭や、腕等を狙って、剣を繰り出した時には、すでに相手の身体はそこに無く、気が付けば、自分がやられているのである。そのような神業が繰り出せるように成るには、日々の修練を怠りなく続ける、強い意志が必要であった。
三九郎が跳び、宗章が舞う。その度に場内よりおおっとも、ううっとも、いう歓声が上がった。そして、披露がすべて終わる頃には、鳴り止まない程の喝采が起きるという現象が、巻き起こっているのであった。
両者は、終わりを告げる太鼓の音と共に、若殿に向かい一礼をする。そして、宗章と三九郎は、目だけで語りあい、お互いの研鑽してきた修練の業を讃え合っていた。剣を交えた者だけが、分かり合える独特な物の存在を確認しあったのだろう。
「お主ら…」
「両名とも、みごと、お見事であったぞ。殿、両名に労いのお言葉を」
一忠の言葉を遮るように、横田内膳が場内に大声をあげる。そして、そんな家老を睨みつける、若殿の側近たちの姿が見えた。
「… 両名とも大儀であった。仔細は、内膳に任せる」
「ははっ」
しかし、誰もその事に気づかず、こうして、披露の儀は無事に終わる。三九郎も宗章も無事に大役を果たした高揚感で胸がいっぱいになっていた。三九郎は、これを機に正式に中村家へ仕える身分となる。しかしそれは、新たな悲劇の始まりでもあった。
その報せを三九郎が聞いたのは、伯耆国での生活が少し落ち着いてきた頃の事であった。
「何と!それはどういう事か?」
「何か企みて候」
才蔵が珍しく、息を切らしながら、三九郎に報せを持ってきたのは、伯耆国内で、ある人物を見たからに他ならなかった。
「本当に佐助だったのか?」
「間違いございませぬ」
才蔵が佐助の顔を見誤る筈は無かった。どんなに変装や、擬態を工夫していたとしても、才蔵の嗅覚と本能とが、佐助を見つけるであろう。
「その忍は何者ぞ?」
「親の仇にて、我らが敵也!」
三九郎の元へ来ていた宗章に問われて、才蔵は短く答えた。詳細は分からねど、才蔵の眼に宿る復讐の炎を見て、宗章は得心するのだった。
「とにかくも、用心にしくは無し。上田の義兄上にも書状を認めよう」
「私が届けましょうや?」
「いや、才蔵は奴から目を離すな。何かあれば報せよ」
才蔵は頷くと、すぐ様に部屋を飛び出していった。三九郎は、腕組みをしながら思案する。ただ今度こそは、必ず企まれる筈の陰謀を阻止し、佐助を斬るという一念を持つだけであった。
その頃、伯耆国内のとある寺内にて、一人の男が一室にて静かに座していた。名を安井清一郎という。領主中村一忠の側近で、まだ若武者ながら、家中で将来を嘱望された人物である。清一郎は、この一刻近くをある人物が来るのをただひたすら待っていた。そこにスーッと微かな障子を開ける音と共に、一人の老人が入って来た。
「お若いの、薬は要らんかね?」
「ほう、爺様は薬売りか?どんな薬がある」
「何でもござれよ。打ち身、切り傷、風邪薬に、虫殺しまで…」
「国の害虫を始末する薬はあるかい?」
「毎度あり。それでは、早速商談を始めましょうぞ」
その薬売りの老人は、どっかりと清一郎の前に座り、懐よりある書状を出して広げて見せた。それを食い入るように見る清一郎。
「これは、誠であろうな?」
「もちろんじゃ。この通りに行えば、奸賊は死に、そなたは国を救った名誉の武士となる」
老人は、そう言うとニヤリと笑う。とても下衆な笑いだと清一郎は感じていた。だが、この老人の申し状は、とても魅力的であった。というよりも、清一郎が望む未来そのものであったと言える。
「ならば、この証をお示し頂きたい」
ただで、大事を決めてしまう程、俺は甘くは無いと、清一郎の目がそう語っていた。
「よかろう」
老人がそう言うと、いつの間にかに、清一郎の前に、短刀が置かれている。清一郎は、それを恐る恐る手に取る。そして、その短刀を鞘から抜くと、そこに葵の御紋が確かにある事を確認するのだった。
「委細承知!」
「ならば、カラクリをご論じろう」
清十郎がそう言うと、老人は、清一郎の側で耳打ちし始めた。二人の密談は、ほんの半刻に満たない時間であった。
「ならば、わしは立ち戻って主にお伝え申す。ゆめゆめご油断なさらぬよう」
そう言い残すと、老人は、葵の御紋を見つめ続ける清一郎が気づかぬ内に、いつの間にかに姿を消しているのだった。そして、その胸に迫る高揚感を隠しきれない様子の清一郎は、すぐにその部屋を出ると、足早に決意をした顔で、去って行くのだった。
「どうやら、上手く運びそうじゃ」
清一郎が去った事を確認した佐助は、薬売りの旗を放り捨てると、素早くその場から飛び去り、また暗闇の中へ消えた。しかし佐助は、己の姿を視界に捉えている影の存在に、気づいていないのであった。
その日は、しっとりと、静かに雨が降っていた。冬の雨は、何とも冷たく、また重たく感じるものだ。とても気持ちを暗くさせる。或いは、そのような感傷など、必要ないかのように、物事は進むものなのかもしれないが。
或いは、後になってから、あの時こうだったのは、それが原因だったかもしれないなどと、人々が後付のように噂する事象としての雨が、この日の静かなる雨という事なのかもしれなかった。
米子城内では、只今、大賑わいの大忙しといった様子で、城内がバタバタとしていた。外に振り続ける雨に、少しみぞれがかってきた事に気づいている者も皆無である程の忙しさであった。
今日は、領主一忠の正室であり、家康の養女でもある、於さめの方の額治しの儀が執り行われ、城内は宴席場と化していたのだった。於さめの方は、家康の家臣である松平康元の娘であった。康元は、家康の異父弟である。つまりは、政略結婚であったが、家康の養女とはいえ、娘を貰い受けられるのは、中村家の忠義が認められた証拠でもあった。
正室はこの時、まだ十二歳であった。儀式は、男の元服に相当する物だが、これでようやく、若殿様と、御正室様とが枕を共に出来るという証でもあり、とても重要な儀式である。日中の儀式は滞りなく進み、そこには、中村家の家臣一同が参列していた。三九郎も宗章ももちろんその中にいただろう。そして、夜になり、城内では宴席が設けられていたのだった。
「どうじゃ三九郎殿、呑んでおられるか?」
酒宴が進む中、宗章が三九郎を見つけて、酌を勧める。三九郎は、慇懃に空になった杯を差出し、並々と注がれた酒を、一気に胃袋に流し込んだ。
「私は、この後も勤めがございますゆえ」
返杯に酒を注ぎながら、やんわりとこれ以上の酒を断る。それを聞いて、宗章は笑う。
「お勤めは大事なれど、御苦労な事だ」
三九郎は、本当はこの日は非番であった。一忠の剣術指南役の一人としての任に、殿の護衛役としての役目も兼務している。それが、若い同僚より、どうしてもと請われて、警護の任を替わったのだった。いずれ交代の時間がくれば、配置に付かねばならない。
「お勤めは、もう慣れたか?」
「まぁ何とか…」
それが三九郎の正直な気持ちであった。実際、勤め日の一日は、午前中は、御殿様の剣の稽古の相手、午後からは、選ばれた側近と、子弟たちへの稽古であった。それが、日によっては警護の任が入る。世の中の野で、好きなように暮らしてきた三九郎にとっては、給金は良くても、いささか退屈な日々を過ごしていたのだった。
「これも給金分の内ですかね?」
そう言って笑う。
「おぉ雪じゃ。初雪じゃ!」
盛り上がる城内を更に盛り上げるように、外を見ると、先程から降り続いていた雨が、いつの間にかに、更に雪へと変わって、幻想的な白い世界へと変貌させ始めていたのだった。
「あの重たい雨は、雪の振る前兆でしたかな?」
三九郎と宗章は、雪見酒と化した酒宴を楽しんでいたのだった。
「滝川殿、そろそろお時間では?」
二人が話している間に、そう言って、声を掛けてきたのは、安井清一郎であった。
「はい。存じ上げております」
三九郎は、そう言って頭を下げる。清一郎は、殿様の警護役の責任者であった。
「ご両者は御存じかな?この国では、初雪が降る日は、変事の兆候ありと、古くからの言い伝えがあるそうな。事にこのような暗い夜は…」
清一郎が何故、急にそのような事を、この目出度い宴席で言い始めたのか、その時二人には、分からなかった。
「では、そろそろ」
「うむ、また達者で呑もうぞ」
三九郎と宗章は、そう言って、お互いの杯を同時に干した。二人にとって、それが酌み交わされた最後の酒であり、この時話した会話が、最後の会話となる事を、まだ知り得ないでいたのだった。
その後、酒宴も程良い時間でお開きとなり、各々が城より帰っていく。宗章も自宅へと戻ったが、三九郎は宿直の警護番としての勤めがあるため、城内に詰めていた。
「殿の命により、暫くこちらで控えているように」
そう清一郎に言われて、三九郎ら警護の者達は、控えの間と呼ばれる一室で待機を命じられていた。御殿様が居る謁見の間では、若殿と横田村詮とが居て、二人だけで何やら話している様子であった。その様子を確認出来るのは、清一郎唯一人だけであった。この異例の処置に、三九郎ら警護の番は、いささか戸惑っていた。
「何か不遜の事があれば、対処出来ないぞ」
村詮が何かするとは思われないが、時代はまだ戦国の気風を多分に遺したる時期である。何者が、例え殿の身内であれ、重臣が謁見し、殿様が人払いを命じても、すぐの次の間で控えるのが常識とされている。この控えの間では、近いとはいえ、咄嗟の行動が取りづらいだろう。三九郎らは、ただ待つだけしか出来ないでいた。
この日の晩、宴もお開きとなった頃、ほろ酔い気分で帰路に着こうとしていた家老の横田村詮は、殿の小姓に呼び止められて、帰宅するのを後にしていた。
「殿が火急お越し下さいと…」
いささか困惑気味に、一口水を飲み、酔いを紛らわせてから、殿の御前に参上すべく、城内を小姓に続いていく。
「何か変事が起ったか?」
「お急ぎ下さいませ」
小姓の様子で、それと確信した村詮は、歩を速めた。程なくして、殿がいる謁見の間に到着する。
「内膳、江戸より急使じゃ」
一忠より差し出された書状を手に取るため、挨拶もそこそこに、村詮は、何事か?と若殿直々に書状を受け取ろうと、前のめりに、跪く体勢となった。
その時であった。村詮が書状を両手で受けて、それに目を落した瞬間、ピューッという異様な音と共に、首の辺りに違和感を生じたのだ。村詮は、感じた首の右側を手で自然と押さえて、また広げて確認すると、そこに赤い血が着いており、自分が血を流している事に始めて気づいたのだった。
やーっという、その甲高い掛け声と共に、一忠が自分の短刀を振り上げて、向って来るのを、スローモーションで体感した時、村詮はこれが、自分を殺す為の謀議であった事を理解した。
村詮は、咄嗟に空いている左手で、腰の柄に手を掛けるが、相手が自分の主である事を思って、抜けないでいた。この間にも、一忠は、所構わずに、一振り、二振り、一突き、二突きと、刀を繰り出してくる。しかし、所詮、歴戦の猛者である村詮と、年若い実戦経験の無い一忠との違いである。村詮は、その攻撃を寸前で、すべて躱していた。
村詮は、仕方なく、次の間へと逃げ、距離を置こうとしていた。
「奸賊覚悟!」
いきなり、後ろから背中を斬りつけられる。村詮が振り返ると、そこに居たのは、安井清一郎であった。
「安井、謀ったな!」
村詮の怒号に、清一郎は一瞬怯んだ。斬りつけられた、背中も致命傷とはなっていない様子で、村詮は、まだ逃げ延びようとしていた。
「各々方、賊が侵入したぞ!出会い候え!」
清一郎の大声が城内に響き渡っていた。
一方その頃、控えの間で待機していた三九郎は、何やら只事ではない様子を聞きつけ、命令が無いので動けないと言う同僚をよそに、勝手に次の間の出口付近にきて、中の様子を伺おうとしていた。その時であった。清一郎の賊侵入との声に三九郎の顔は、一瞬にして、剣士の顔に変貌していた。
謁見の間では、戦う男達の声と、剣を交える音が聞こえる。三九郎は、素早く抜刀すると、次の間へ、踊るように入り込んだ。そして、三九郎の出現により、退路を断たれた格好となった賊は、三九郎目掛けて、鬼の形相で向かってきた。三九郎は、中段に構えると、その賊の突進を利用するかのように、サッと身を躱し、躱しざまに、横一線の一撃を相手に喰らわせるのだった。
「ぎゃーっ」
断末魔を挙げたかのように、一声あげると、賊はバッタリとその場に、前のめりに倒れ込んだ。
「滝川殿か?お見事也!」
清一郎が走りより、賊を足蹴に仰向けに転がす。そこで初めて、三九郎は、その賊が家老の横田村詮である事を知るのだった。
「これは、どういう事か?横田殿、横田殿!」
三九郎は、村詮を抱きかかえて、揺さぶってみるが、すでにこと切れた後であった。享年五十二歳と伝わる。
「安井、貴様!」
三九郎は、怒りと共に清一郎の胸倉と掴む。しかし、清一郎は臆する事なく、三九郎の手を振り払うと、後ろで放心したかのように、座り込んでいる少年に話し掛けた。
「殿、狼藉者は、この清一郎が斬りまして候」
「た、大儀である」
少しの間をおいて、やっと絞り出した言葉に呼応するかのように、清一郎の笑い声が、不気味に城内に響いていた。上気した息を吐きながら、叔父の血まみれの死体を見続ける若殿と、それを見て笑い続ける家臣。その異様な光景を後悔と共に、呆然とするしかない三九郎であった。
藩内は、騒然としていた。無理もない。若い殿様が、執政である筆頭家老を誅殺してのである。皆一様に、何が何だか分からなくなっており、噂だけがオヒレをつけて、一人歩きし始めていた。先刻までの目出度い宴席が、幻であるかのようであった。
三九郎は、暗い雪道を進んでいる。今晩から降り始めた雪は、藩内すべてを白く染め上げているようだった。まるで、何かを覆い隠してしまいたいかのように。三九郎が誰も通っていない道の歩を進める度に、力強い足跡が後ろに付いていくのだった。
「お前様、一体何事が?」
一度自宅に戻った三九郎は、一人、心配顔をして待っていたお菊に、事の次第を話しながら、身支度を整える。自分の愛刀を鞘から抜き放つと、その刀が発する不気味な光を白刃の具合とを確かめて、また鞘に納める。そして、素早く具足に着替え始める。
「才蔵は?」
「いえ、まだ戻って参りませぬ」
短い問いに短い答え。それだけで分かり合える夫婦である。三九郎の表情を見ただけで、事態が切迫している事に、お菊は気づいていたのだった。
自宅に戻る途中に、三九郎は、宗章の屋敷を訪れたのだが、すでに誰も居ない様子であった。聞けば、横田家の家臣たちは、主の急死を知り、すでに内膳丸と呼ばれる横田家の邸宅もある、砦に集まり始めていたのだった。ここに才蔵がおれば、内膳丸に忍び込み、宗章と連絡も可能であっただろう。
「致し方なし…」
小さく呟いた三九郎であったが、心に残るわだかまりまでは、消せそうになかった。三九郎は、宗章に弁明したい分けではなかった。何を言った所で、自分が村詮を殺した事実が消せる分けではない。恐らく、いや間違いなく、宗章の人柄からして、激しい争いになる事は必定であった。
であるのならば、宗章との戦いが避けられないのであればこそ、三九郎は、師であり、友でもある宗章に対して、互いの胸中をさらけ出したかったに違いなかったのだ。
「心配するな。大丈夫だ」
愛妻の哀願するような表情に、そっと頬を撫ぜてやる。それが例え、気休めの言葉や態度であっても、それだけでも、お菊は救われる気持ちになれたのだった。
「お前様、お気張りなさいまし」
お菊は、三つ指をついて、夫を送り出す。武家の妻たる者、いつ如何なる時でも、戦いに臨む男の後ろ髪を引いてはならないのだ。
「行って参る」
お菊は、精いっぱいの笑顔をして、三九郎は、それを振り返らずに受けながら、力強く邸宅を飛び出していくのだった。
さて宗章であるが、自宅に戻ると程なく、村詮急死の報を受けた。事の次第を確かめるため、すぐに邸宅を飛び出し、内膳丸へと駆けつけていた。
「内膳殿は?」
泣き崩れる村詮の奥方と、それを気丈にも励ます村詮の嫡男主馬助の姿を認めた時、宗章の心は、すでに決まっていた。
「許すまじ、許すまじ!」
宗章以下、内膳丸に駆けつけた横田派の家臣は、総勢二百名を超えていた。これらが決死の覚悟で、村詮の嫡男主馬助を大将に、藩を二分する戦を引き起こすつもりであった。
この事態に一忠以下、清一郎らの城内派は、浮足だっていた。事を起こせば、このような事態になる事など、分かりきっていた筈であるのにも関わらずである。
「どうする?どうする?」
泣きそうな顔で、室内をウロウロする殿様と、腕組みしたままで、座り込んで微動だにせず、事態の解決を図ろうとしない側近の滑稽な姿に、城に戻っていた三九郎は、冷ややかな顔で見ている。
「一度、使者を送ってみるべきでは?」
あたり前過ぎる解決策を、先刻より提示されていたのだが、肝心の使者になりたがる者が見つからず、決行されないでいた。
「やはり、拙者が参りましょうや?」
見かねた三九郎が声を挙げたが、村詮を斬った張本人が乗り込んだとあっては、只で済む筈もなく、却下されていた。しかし、この三九郎の申し出に、清一郎一人だけが賛成し、余計三九郎を苛立たせていたのだった。
「仕方なし。ここは、我が家臣より、使者を立てよう」
状況を見て、溜息交じりに、そう切り出したのは、米子藩の隣国で、出雲国の領主である堀尾吉晴であった。
吉晴は、一忠の父親である一氏とは、長年の僚友であり、豊臣三中老の一人として、秀吉古参の家臣でもあった男である。仏の茂助と呼ばれ、その誠実な人柄は信望を集めていた。
しかし、一度戦となると、誰よりも果敢に攻めかかる、勇猛の武将でもあった。その吉晴が、友の忘れ形見である一忠に請われて、隣国から事態の収拾に軍勢を引き連れて、駆けつけたのだった。
「全く、大事を仕出かしてくれたものよ」
家臣に差配しながら、親友の早すぎる死に、思いを馳せずにはいられない吉晴であった。
吉晴よりの仲裁の使者は、数度に渡って放たれたが、内膳丸の横田派は、いっこうに投降する様子は無かった。
「殿様と刺し違えても、無念を晴らす」
という過激な者もあれば、
「殿がここに来て頭を垂れるならば、考えなくもない」
という者もいたが、要するに横田派の誰一人として、このまま泣き寝入りをしようとする者はいなかったのであった。
「堀尾吉晴の名を持って、こちらに居る者すべてに恩賞を授ける。また横田内膳が子、主馬助には、家督相続を安堵する」
出来るだけの状況打開の案が提示されたが、
「為らば、安井清一郎の首を持って参れ!」
この一言によって、両派の決裂は決定的となってしまった。
「ここに至っては、一戦致しかたなし!」
合議上での吉晴の発言により、米子藩を二分する戦いは、必然となってしまう。三九郎も忸怩たる思いはあったが、心は決していた。その時、外はまだ暗闇の中であった。
これから、行われるであろう戦いの舞台とされる場所が飯山城である。この城に横田主馬助と、柳生宗章以下二百名が、米子城の二の丸に位置する内膳丸より、飯山城へと移り、徹底抗戦の構えを見せたためであった。
この飯山城は、米子城の三の丸に位置し、元々が、今から約五百年前に山名氏の出城として築かれた砦であった。この城は、出雲国と伯耆国との国境沿いに位置する重要な場所に築かれており、山名氏、毛利氏、尼子氏と言った戦国大名たちが、覇を競った場所でもある。現在も、山城後の石垣が残されており、当時の姿を偲ぶことが出来る。
その飯山城に、中村・堀尾連合軍が攻め込んだ時には、昨晩より降り始めた雪も止み、辺りは、まだ溶けきらぬ残雪が、山々を白く染め抜いていたのだった。
「老公には、どうか後詰めをお願い申す。先陣は、我らにお任せ願いたし」
軍議の場にて、諸将の前でそう堀尾吉晴に啖呵を切っていたのは、中村一忠の側近の一人である天野宗杷であった。この男は、安井清一郎と共に、今回の横田騒動を引き起こした首謀者の一人と目される人物でもあった。
「何を言うか。わざわざ出張ってきた我らが、後詰めとは片腹痛し」
吉晴は、六十を過ぎる齢であったが、老いぼれ呼ばわりされて、歴戦の勇士が黙っている筈もない。軍議の場で、私が俺がと互いに譲らず、他の者も先陣を主張し始める等、混乱が生じ始めていた。
「三九郎は、どう思うか?」
今まで一言も発せずにいた、首座に居る一忠が、初めて口を開き、軍議の末席に座る三九郎へ意見を求める。すると先程まで、騒いでいた諸将は皆、一様に口を閉ざし、三九郎へ視線が集まる。
「つまりは、表門を我ら米子藩にて、裏門を松江藩にお願いしては如何に?」
三九郎は、殊更に大声で、しかもはっきりと主張した。
「それは、名案なり!」
三九郎の案に一忠は、膝を打つ。横で座る吉晴も大きく頷いた。これで軍議の方針は決した。後は行動を起こすのみであった。場は、俄然活気づいていたが、三九郎の気持ちは晴れやかではなかった。出来れば、こんな戦には、関わり合いなど持ちたくないと考えていたからだ。
しかし、状況は変わる。人間は思い通りには、いかないものだ。例えそれが、天下を制した家康であっても。三九郎は、条件反射とはいえ、横田村詮を殺した張本人であり、その事実が、中村軍内における彼の評価を一時的にでも、高める効果を発揮しているようであった。
三九郎からしてみれば、武器を持って、襲い掛かってきた曲者を成敗した、つまりは剣士としての性質であっただろうし、一忠の警護役の任からしても妥当な事でもあっただろうと思うのだ。
しかし、三九郎は思う。
(俺が引き金を引いてしまったこの戦の、決着を見届けねばならないだろう)
その思いから、三九郎は不本意ながらも、中村軍の一員として、戦う事を決意したのだった。それは、武士の一分であった。
後の世に、横田騒動、米子城騒動と呼ばれる戦いは、横田村詮殺害後の翌日、未明に行われた。この戦いの最初の砲火をどちらの陣営が放ったのかは、判別としない。
しかし、この戦いの特筆すべき点として挙げるとするならば、両陣営とも消極的な戦いとして、始まってという所であっただろう。何せ前日までは、味方であった同僚、知人、などが、敵味方に別れているのである。中には、縁戚関係で別れた者もあったかもしれない。
であるならば、人間の心理として、遠巻きに銃弾と弓矢を持って、それに当るように考えるのが、自然の流れであっただろう。特にこの際、守る横田方よりも、攻める中村方の士気の低下が、著しく顕著であった事も拍車をかけていた。つまりは、この戦闘に参加した大多数の人間は、余り乗る気ではなかったのである。
そして、そんな状態が二刻程続いてきた時に、ようやく表門の突破に成功するのであった。このまま形勢が決まってしまうかと思われたその時に、中村方に立ち塞がった一人の侍がいた。柳生五郎右衛門宗章である。
宗章は、長槍を奮うと、城の庭園の池の一角に侵入する敵を突き殺し、薙倒し始めた。宗章は、丁度、敵が進行する場所のポイントとなる場所を選び、大勢で攻めかかれない場所を見つけると、そこを自らの拠点としていた。
そして、この柳生家の剣豪が一人居るだけで、表門を攻める中村方に遅れが生じ、裏門を攻める堀尾方との連携にも乱れが生じでしまい、挟み撃ちで一挙に城を落とすという三九郎が立てた作戦が、無に帰する所まで、事態を深刻にしてしまっていたのだった。
この状況に、名乗りを上げた一人の中村方の武将が居た。矢野助之進という剛力で知られた男であった。
「この助之進にお任せあれ」
「頼んだぞ」
一忠は、助之進に盃を取らせると、流石に剛の者らしく、助之進はそれを一気に飲み干し、盃を地面に叩きつけて割り、大声で自らを鼓舞すると、勇ましく戦場へ向かうのであった。
しかし、そんな矢野助之進戦死の報せは、それから半刻もしない内にもたらされた。
「助之進程の男が…」
一忠はそう嘆き、
「誰かおらぬのか?」
焦りから、他の者に怒号を浴びせる清一郎に、幕内は、静まり帰っていた。これで、中村方の突撃が跳ね返されたのは、すでに三度目であった。
「もう中村家に勇者、忠臣は無きや?」
天野が味方を鼓舞しようとするが、戦況は厳しくなる一方であった。宗章は、この戦において、すでに三十人程を討ち取っていたという。
(新陰流とは、これ程までに凄まじい物であったか…)
宗章の獅子奮迅の働きに、小勢の横田方は、大いに士気を高め、その勢いを増しているようであった。そして、このような戦況の成り行きを、幕内の隅で座して、静かに見守っていた三九郎が動いたのは、そんな時であった。
三九郎は、一言も発せず、狼狽えるばかりの一忠らに一礼だけをすると、幕内から出て、宗章の待つ戦場へ向かうのであった。そして、その決意に満ちた、一人の剣士の生き様に気づく者など、居なかったのであった。
風が吹いていた。その風は、戦場に放たれた火を炎へと変え、疾風となりて、人々を飲み込もうとしているかのようであった。
三九郎は、針がねを額に巻くと、自らの両頬を一回だけパンッと叩いた。その瞬間、先程まで幕内で、目を細めて、まるで眠りこけているかのようであった男の顔つきが一変していた。三九郎は、新陰流の剣士として、戦場へ向かう事を決意したようであった。
荒い息遣いがしている。その場所で一人の男が立っていた。男は、額の汗を拭うと、荒くなった息を落ち着かせようと、フゥーっと深く息を一つ吐いた。山城の庭園、池の畔りにてと記せば、どんなに長閑な情景が浮かぶだろうか。
しかし、今その男、柳生宗章が立っているその場は、地獄の血の池、その物であっただろう。池には、多数の味方の屍と、そして、それを遥かに上回る敵の死体とが浮かんでいるのだった。宗章は、どれぐらい敵を倒したのか、味方が傷つき倒れて行ったのか、把握出来なくなる程、槍を突く事をまたは、払う事に集中しているようであった。
いつの間にかに、敵の何回目かの突撃を食い止め、気が付けば、敵は一時退却している様子だった。
「宗章殿…」
不意に名前を呼ばれて、宗章は一瞬気づくのに遅れた。呼ばれた方向を見ると、そこに立っていたのは、間違いなく友であった。
「三九郎殿…」
友であり、弟子であり、同じ新陰流剣士であり、今は敵である滝川三九郎一積である。三九郎は、宗章の姿を認めると、静かに、腰の佩刀を鞘から抜き放ち、正眼の構えを取る。それを見た宗章は、持っていた長槍を鋭く投げた。投げた槍は、建物の柱に見事に突き刺さった。
「わしは嬉しいぞ」
「お互い、悲しい性ですな」
宗章も抜刀し、上段に構えを取る。剣士同士の、強者を見ると戦いたくなる悲しい性との思いと、剣士としての誇りと歓びが入り混じる不思議に高揚した感覚に、二人はこの時陥っていた。二人の剣士から、笑みが零れていた。
金属の反発する音が辺りに響く。二人は間合いを取り、読み合い、相手の出方に瞬時に対応する為、一瞬たりとも、気を抜けない状況であった。
「宗章殿、息が乱れている。他日を期しても良いぞ」
「何を申すか。今、この時でなければならぬ」
そう言い切るより早く、宗章が動いた。その斬撃は凄まじく、三九郎は受けるので精一杯の様子だ。
(流石は、わが師…)
三九郎は、戦いながらも、心の中で、感嘆せずにはおられない。
二人は、気づいていないが、実はこの時、再度の突撃が、中村方より行われ始めた所であった。三九郎と宗章の周りを、敵味方が通り過ぎようと、試みるのだが、二人の凄まじい戦いに巻き込まれて、死ぬ者が数人出た所で、他の者たちは、この場所よりの突撃を諦めて、場所を移動し始めていた。
そして、残った者たちは、いつしか争いを忘れて、二人の新陰流の剣士同士による、稀代の名勝負の成り行きを追い始めていたのだった。
斬釘截鉄、燕飛、山陰、月影、浮舟など、新陰流の技と業とのぶつかり合いが続いていた。二人の戦いは、いつまでも続のではないかと、錯覚する者達までいる程に、二人の戦いは拮抗していた。
「三九郎、決着をつけるぞ」
「おおっ望む所!」
二人は、息を整え、構えを改める。宗章は思う。今この時でなければ、滝川三九郎という優しすぎる男が、師である自分に向かって、本気の勝負に出る事はないだろう。他日を期せば、自分が勝つ可能性が高い。
しかし、そんな事の為に、自分は生きて来たのだろうか?否、柳生宗章は、剣の道を究める為に、生きて来たのだ。強者と戦い、剣とは何かを知る為にこそ、自分は生きている。いや、滝川三九郎という剣豪と戦う、この一戦の為に自分は生きてきたのではないのだろうか?とすら、思えてくるのだった。
宗章は、再び上段の構えを取った。
三九郎は思う。わが師であり、友でもある宗章と争う事は、不幸であろうかと。しかし、同時にこうも思う。柳生宗章ほどの稀代の剣豪と、真剣勝負が出来るのは、同じ新陰流の剣士として、これ以上の誉れは無いのではないのかと。
三九郎は、相反する二つの気持ちを確かに持ちながらも、剣士としての誇りの為に、また宗章に対して、真剣で応える事こそが、この時代の侍の矜持でもあると思っていたのだろう。
三九郎は、宗章に対して、刀を横にする構えを取った。そして、それが何を狙っての事なのか、宗章には分かっていた。宗章は、上段に構えて、正眼に三九郎と対峙していた。
これは、新陰流でいう所の、一刀両断の法であった。対して、三九郎は、宗章を横に見るようにしている。丁度、左肩を宗章に見せつけるように。これは、合撃という技である。
宗章が上段より、刀を振りおろし、三九郎の肩を狙うと、すかさず身を翻して、その振り下ろされる刀の上より、刀を打ち落とす神業である。
これを宗章ほどの強者に対して、行うのは、正に至難の業である。まして、宗章には、その業がどういう物か、熟知しているのだ。
(勝てる…)
そのシンプルだが、強い気持ちに、宗章の心は支配され始めていた。
新陰流において、正眼の構えをとる相手に、合撃の技を仕掛けるのは、言わばセオリーではあったが、三九郎の知らない、その合撃の返し技を宗章は知っていたのだ。それは、柳生本家の人間にしか、受け継がれない秘伝の業である。
まず、合撃の技に合わせるように、刀を相手の肩口を狙って振り下ろす。そして、敵が振り下ろした、自分の刀を打ち落としに来た所で、力を込めて、刀を上に返すのである。そうすれば、相手の振り下ろされた刀を跳ね返し、そのまま敵の喉元を突けるのである。
かなり難度の妙技であり、実戦でこれを試みた者など、今まで一人としていなかった。しかし、宗章には、自信があった。この勝負の時に、自らに一番の大技を課して、三九郎に勝つのである。剣士として、その誘惑には勝てなかった。
(満足だ。わしは、満足だ…)
宗章は、剣士として、こんなにも充足感を得る勝負が出来た事に、心が満ちる歓びを得ていた。しかし、この勝負が着く前に、満ちてしまった心が、その行方を左右したのかもしれない。
「行くぞ!」
「おおっ!」
二人の大喝が辺りに響いた。
宗章は、上段から、一刀両断の法を繰り出し、三九郎の左肩を狙って、刀を振り下ろす。対する三九郎は、その肩に降ろされる刀を寸前で躱すと、振り下ろされた宗章の刀に向かって、自らの帯刀を力いっぱい振り下ろした。
次の瞬間だった。宗章は、刀を返すと、三九郎の振り下ろされる刀目掛けて、刀を払った。
三九郎の刀は、鈍い金属音と共に、舞い上がると、二人の間に落ち、地面に突き刺さる。勝負あった!とその戦いを見守る大勢の敵味方の誰もが、思ったその時であった。
「ぐっ…」
片膝を地面に付き、衣に血を付けているのは、宗章であった。対する三九郎は、その手に、宗章の血をつけた自らの脇差を、しっかりと握り締めているのだった。
「みごと、見事だ…」
宗章は、それだけを言った。三九郎は、刀を弾かれると見た瞬間に、自分の大刀を捨てると、脇差を瞬時に抜き出し、がら空きになった宗章の左胸へ、突き刺したのだった。
「宗章殿…宗章!」
崩れ落ちる友を助け起こそうとする三九郎であったが、宗章はすでに事切れた後であった。その顔は、とても安らかな表情をしていると、三九郎は思った。
(勝負の瞬間、お菊の顔がよぎった…)
二人の新陰流の剣士による壮絶な戦いは幕を閉じた。
二人の勝負を分けたのは、宗章は、勝負の前に戦いの充足感を得たのに対し、三九郎は、自分を待つ妻の為にも、死ぬわけにはいかないとの思いがあり、それが両者の生と死とを分けたのかもしれなかった。
宗章の安らかな横顔に、いつの間にか再び振り始めた雪が、舞い降り始めていたのだった。
「天も泣いておるわ…」
三九郎の独白が、辺りに染み渡るかのようであった。
とにかくも、一つの戦いが終わりを告げた。その後、宗章を失った横田方は、徐々に当初の勢いを無くしていき、表門、裏門共に突破されると、総崩れとなった。主将の横田主馬助ら、横田村詮の家族郎党は、自刃して果てるという、壮絶な最後で戦は幕を閉じた。何とも後味と悪い戦いがここに終結した。
しかし、誰にも知られない一つの戦いがまだ終わってはいなかった。それは、忍びの戦いであった。
戦が起って、ほぼ人の居ない、米子城の奥の院である。そこに一人の男が忍びこんでいた。佐助であった。佐助は、必死にある物を手に入れるべく、探っていたのだ。
(おかしいぞ、どこにも無い…)
佐助の焦りを現すかのように、その部屋中が、佐助によって荒らされていた。
「やはり、現れたな」
佐助が驚いて振り向くと、そこに立っていたのは、才蔵であった。才蔵は、ある物を右手に持っていた。
「それは、もしや…」
佐助が認めて、その才蔵が持っている物を欲しがるように、手を伸ばす仕草をすると、才蔵は、挑発するように、それをズイッと前に押し出すような恰好をした。
「この葵の御紋の入った短刀を、取りに来ると思っておったぞ」
その短刀は、安井清一郎に宛て、柳生宗矩が謀略の支援を認めた書状の入った短刀であった。もちろん、その書状の最後には、徳川秀忠の花押が押されていたのだ。
勝ち誇ったように物的証拠を示す才蔵に対して、佐助は、じっと凝視していくる。その表情は、冷酷そのものであった。
「貴様、才蔵とかいう若造か?あの三郎の息子であったな。親に似て、間抜けなものだな。わしを殺す、唯一の機会を逃したぞ」
「ベラベラと喋る奴だ。すぐにその舌を引っこ抜いてくれるが、殺す前に尋ねたい事がある。何故、中村家で内紛を謀議したか」
才蔵の目は、怒りに満ちていた。当たり前である。目の前に、親や仲間の仇が、すぐ手の届く所に居るのである。
「けっけっけ。何もここに限った事でもない。大名家の力を削ぐ為に事を成すが、我が仕事でな」
佐助は、その下品な笑いと共に、何とも下衆な内容をしゃべる。才蔵の怒りは更に増した。
「成程、各大名家の力を削がねば、あの次期将軍では、徳川も終わりと言う訳か?」
「ほざけ!」
佐助は、自分の忍刀を抜くと、才蔵目掛けて突っ込んできた。才蔵は、それを見計らっていたっていたかのように、自分も忍刀で対抗する。狭い部屋、暗闇の中で、忍びによる死闘が開始されたのだった。
金属音だけが不気味に木霊する。名乗りも無し、気勢も上げず、掛け声もない。出来るだけ音を出さない、無音での戦いが忍びである。そして、その戦いは、あっけない程の短時間で決着の時を迎えていた。
転機は、才蔵の懐から、件の書状が滑り落ちた時におきた。佐助は、それをすかさず拾い上げた。しかし、そこに一瞬の隙が生まれたのだった。才蔵は、佐助が書状に気を取られている隙に、手裏剣を二本佐助に放つ。すると、書状を取ろうと、伸ばした佐助の右手に見事ひとつが命中したのだった。
(グッ)
一瞬苦悶に顔をしかめた佐助であったが、さすがに声を一言もあげず、書状も傷ついた右手で、しっかりと持っていた。
(ここまでだな…)
才蔵は心で呟くと、後ろ背に、勢いよく襖を開け放つ。
「曲者じゃ、出会え候え」
才蔵は、大声で呼ばわると、辺りから灯りを持って、警護の者たちが迫る音が聞こえてきていた。
「きさま…」
負傷した右手を抑えながら、佐助はある事に気づいていた。才蔵は、忍刀を使っているが、微かな灯りで、照らし出されたその恰好は、侍のそれであったのだ。
これでは、どうしても、賊とそれを阻もうとした城の者である。佐助は、瞬時に自らの不利を悟ると、才蔵の居る反対側の障子に、忍刀を投げつけ、ぶち破る。そして、身を乗り出すと、下を確認する。すぐに堀があり、下が水である事を理解すると、躊躇なく、そこから飛び降りるのだった。
(しまった…)
才蔵が思った時には、佐助の身体は、障子の外に消えていた。才蔵は、駆けつけてきた城の護衛たちと共に、佐助の行方を探すが、佐助の姿はどこにもなかった。才蔵は、またしても佐助を取り逃がしてしまったのだった。
横田騒動と言われる戦いは、これで終わった。城では、戦勝の宴が行われていた。しかし、その場に滝川三九郎の姿は無い。三九郎は、自邸に戻っていた。
「宗章殿に…」
三九郎は、お菊と帰ってきた才蔵と共に、亡き友に盃を捧げる。
「宗章殿は、俺が斬った」
盃を一気に飲み干すと、三九郎はお菊に事の顛末を語る。
「それは、宗章殿も本望でありましょう」
お菊はそれだけを言うと、空になった盃を再び満たしてやる。三九郎は、その並々となった盃に視線を落とすと、またそれを一気に飲み干していた。
「そうか、佐助は取り逃がしてか…」
「はい、しかし奴が手傷を負った箇所には、毒を塗ってありました」
才蔵の正確な報告で、三九郎は、この騒動の事態の顛末を知り得ていたのだった。
「ならば、佐助もこれでお終いじゃな。少なくとも、忍びとしては」
「そうだと、良いのですが…」
三九郎は、何も答えずに、ゴロンと転がる。そして、寝転がったままで、再び盃を口に持っていく。一口飲もうとして、一瞬躊躇し、杯を天に掲げる。そして、再び杯を口に運んだ。それが、三九郎なりの、死者への手向けであった。
「三九郎、思い留まっては呉れぬか?」
騒動より、数日後の事であった。一忠に呼び出された三九郎は、横田村詮の死によって空席となっていた家老職を提示されたのだが、これを瞬時に断っていた。
そして、
「お暇を頂きまする」
三九郎は、中村家を去るという。その決意は固かった。一忠は、何とか三九郎を止めようとしたのだが、友を殺して、その屍の上に出世するなど、滝川三九郎の名折れだと断固として断ったのであった。
「すまぬ、また浪々暮らしじゃ」
「はい」
城から戻って、お菊に詫びた三九郎であったが、帰ると、お菊はもう支度を始めてしまっていた。三九郎の性分であれば、そうするだろう事をお菊には、分かっていたのだ。
「お菊様、これはどうします?」
「才蔵、これはこっちでお願い」
「はい」
二人は、見事な連携で、さっさと荷物を纏めてしまった。不要な家具などは、世話になった者達へ、餞別としてあげればいいし、身軽に越して来たのだ。また身一つで行けばいいだけだ。滝川三九郎という男は、人が屍の上に、自らの権力を据えるなど到底出来ない男であった。
この戦国の世を生き抜く侍としては、少々欲の無さすぎる武士(もののふ)の生き様が、お菊には、何とも言えず好ましく感じていた。
「また、江戸で長屋暮らしじゃ」
「あら、嬉しいこと」
頭を掻く夫に、本当に嬉しそうに笑う妻、この二人の為に自分は生きるのだと、この瞬間を、何とも好ましく思う才蔵であった。
そして、中村家のその後であるが、この横田騒動は、当然幕府の知る所となっていた。当然の事ながら、将軍家康の耳にも届く。
家康は激怒した。自分が認めて、一忠の後見役とした横田村詮をいきなり誅殺したのだ。自分の顔に泥を塗られたのも当然であった。家康は、即刻、この度に騒動を主導した者達を罰した。つまり、一忠の側近である安井清一郎は切腹とし、天野宗杷は、斬首となった。天野はキリシタンであり、自決出来ない為の処置と言われている。その他、謀議に加担した主だった者が吟味なくして、すぐに処刑された事が、家康の激怒を物語っている。
これに驚いた一忠は、謝罪の為に江戸に向かうが、江戸入府を拒否され謹慎とされた。が後に許されている。一忠の父一氏の功績に報いる為と、幕府が開かれて間もない時期であった事が、幸いしたと言えた。今、中村家を取り潰して、政治的な動揺を、全国に飛び火させない処置でもあった。
しかし、罪を許された一忠であるが、それから六年後の慶長十四(1609)年五月に急死した。享年二十歳の若さであった。狩りの最中に食した、梅に当たったと言われているが、まずもって、毒殺である可能性が高い。誰がそれを行ったかは、明らかであった。
そして、届け出てない庶子の男児は居たらしいが、幕府は中村家の断絶、一家の取潰しを決定した。横田村詮が存命であったならば、その庶子を持って、中村家を継がしめる事が出来たかもしれない。ここに米子藩中村家は、歴史の彼方に消えるのであった。
一氏には息子があった。中村一忠という。一氏は、家康に息子を託していた。関ヶ原合戦には、この息子が参戦し、戦後の功により、伯耆国(鳥取県)十七万五千石の大名へ加増された。家康は、約束を果たしたのだった。
一忠は、伯耆国に移り、施政を開始した。しかし、まだ十代の若武者で政治の事など分からない。そこで、一族で重臣でもある横田村(むら)詮(あき)が家老として、施政を担う事となった。
村詮は、検地を行い、城下町を整備し、運河を広げ、国を豊かにしようと、その辣腕を大いに奮った。実際に国営は上手く行っていたらしい。しかし、いつの世にも一人だけ出世を果たすと、それを妬む者や、阻む者たちが現れるのが、世の常であっただろうか。そして、滝川三九郎の元に、ある書状が届いたのもちょうどその頃の事であった。
慶長八年(1603)二月十二日、徳川家康は、晴れて征夷大将軍の宣下を請けて、将軍となり、ここに江戸幕府が誕生した。これより、三百年近くに及ぶ、江戸時代が始まるのである。
「江戸が将軍の街になった」
と町衆たちが騒ぎ、何やら祭りがずっと続いていくかのような賑わいを見せていた。
「これで、再建が進むだろう」
と大人衆が歓び、そのまま言葉通りに江戸の町造りは、進んでいるかのようであった。そして、立て直された長屋の一室に、再び居を構えた滝川家では、主たる三九郎は無為の刻を過ごしているのだった。
「お前さま、一体どうなさるので?」
三九郎は、寝転がって三日前に届いた書状を眺めている。その横で女房のお菊は、飽きる事なく、家計の助けの為に針仕事に精を出していた。
「う~ん」
この三日間、ずっと気の無い返事を返してくるだけで、寝転がってばかりいる旦那と、それには何も言わずに健気に内職をする妻と、慎ましいが小さな幸せが、この時の二人の間にはあったのかもしれない。
「三九郎様!」
外から元気よく三九郎を呼ぶ声が聞こえる。才蔵に違いなかった。
「おう才蔵、向こうの様子はどうだ?」
「はい、変わりありません」
才蔵は、三九郎とお菊が長屋に戻った後も、真田屋敷に残り、そこから長屋へと毎日通って来ているのだった。
「今日は、三九郎様に、御客人をお連れ致しました」
才蔵の後ろに立っていた武士が笠を外して顔を見せると、途端に三九郎の顔が破顔した。
「これは、五郎右衛門殿では御座らぬか?お懐かしゅう」
「御免仕る」
男が中に入るとお菊と目が合い、互いに会釈を交わす。
「お菊、この方は、柳生五郎右衛門宗章(むねあき)殿と言うてな、わしの剣術の師で、当代切っての剣豪じゃ」
「まぁ三九郎の妻、菊と申します。このような所で申し訳ござりませぬが、どうぞお上り下さりませ」
狭い長屋の一室にて、お菊が炊事場で湯を沸かし、お茶を入れ、その湯を沸かす火の番を才蔵が受け持つ。三九郎は、客をもてなす為に、先程まで自分が寝転がっていた布団をどけるのだった。
「それで、何用で?」
「ふむ。わしは今、伯耆国中村家の家老、横田殿の剣術指南を務めておる」
五郎右衛門は、三九郎からの問いにそれだけを言うと、再び茶を飲み続けている。
「ははぁ、この書状は、どうやら先生の仕業らしい」
三九郎は、そう言うと、件の文を五郎右衛門の前に差し出した。
「さすが我が弟子、気づかれたか」
五郎右衛門は、差し出された茶の加減を確かめるように、呑むのだった。
その書状は、織田有楽斎から、中村一忠への仕官推挙の書状であったのだ。三九郎は、この書状が届いてから、その意図を計りかねて、無為の刻を過ごしていたのであった。
「今、中村家では、若殿が若年なのをよい事に、一家の功労者である横田殿を失脚させようとする動きがある。しかし、横田殿には、わしが就いておる。迂闊には手出し出来ん。しかし…」
「その若殿を警護する者がいない」
「ご明察!」
三九郎の答えに満足した五郎右衛門は、湯呑みを置き、三九郎と対するように座り直した。
「わしは、諸国を巡り、剣術修行に明け暮れた。その旅先で不意に寄っただけの一浪人に横田内膳正殿は、わしを食客として遇しただけでなく、剣術指南として、我が腕を認めてくれた。わしは恩義に報いねばならぬ」
「それで、私に若殿の警護をしろと?」
「この通りじゃ、頼む」
五郎右衛門は、深々と頭を下げた。
「どうか頭をお上げ下され」
「三九郎殿、そなたは、腕も立ち、武士として誇りある男。主を望まぬは知ってはいるが、織田有楽斎様よりの推薦状を持参すれば、中村家の剣術指南役として、召し抱える手筈になっておる」
「どうか、どうか、この柳生宗章との誼を思うて、否とは言うて下さるな」
五郎右衛門は、言葉を尽くすと、再び頭を下げ続けていた。
「承知仕った。他でも無い、わが師からの頼みです。お引き受け致しましょう」
三九郎は、五郎右衛門の両手を取ると、身体を起こしてやった。
「忝い、忝い」
三九郎は、柳生宗章という男が好きであった。この男は、柳生石舟齋の四男で、秀忠に仕える柳生宗矩の実の兄にあたる。弟である宗矩は、徳川家へ仕官したが、宗章はそれを潔しとせずに、諸国を巡り剣術の研鑽を続けたとされる。
権力欲も無く、出世欲も無い。ただただ剣の道を究める事にしか興味が無い、生粋の剣術使いと言えた。だからこそ、三九郎は、この男の事が好きな事に違いなかった。
「お菊、どうやら花のお江戸は、暫く見納めらしいぞ」
夫の唐突な宣言に、ただただ戸惑う新妻であった。
この時代、江戸から伯耆国へ陸路で行くには、中山道か東海道を通って、一度京の都へ向かい、そこから山陰道を通るルートが規定であった。三九郎たちも東海道を通って、山陰道へ向かったに違いない。途中、京の都で都見物をを楽しんだかもしれない。何せ、三九郎にとっては、久方ぶりの上方であっただろうからだ。
「お前様、西国も寒うございますなぁ」
「いま少し南に降れば、冬場でも暖かいと言うが、伯耆国は、北国と同じじゃそうな」
三九郎の後ろを歩くお菊は、長旅にも根を上げずに健気に歩を進める。
「あの柳生宗章殿とは、どういった御仁で?」
これも当然の如く、三九郎らに同行する才蔵は、いきなり現れた剣士の事が気になって仕方ない。
「あの仁は、わしの命の恩人で、剣の師匠筋にあたるお人よ。わしは、あの方に到底返し切れぬ人生の借りがあるわ」
三九郎が、まだ十代の頃に諸国を巡る旅に出ていた時の事であった。三九郎は、大和国から東国へ向かおうとする山道で、盗賊に襲われ、深傷を負ってしまった。万事休すかと思われた、その時に現れたのが宗章であった。一命を救われた三九郎は、傷を癒す為に柳生の里へ逗留し、その間に新陰流の極意を学んだのであった。
「わしも無鉄砲な若衆じゃったからのう」
「無鉄砲さは、今もお変わりありませぬが」
「こ奴!」
三人は笑う。その道中は、とても楽しそうであった。夫婦揃っての初めての旅であったし、才蔵としても、初めての長旅であった。三人とも何せまだ若いのだ。
「そら、あの山を越えれば伯耆国ぞ」
三九郎が指さす山の上には、分厚く暗い色の雲が拡がって見える。それが、領内では、すでに冬が始まっている事を感じさせていたのだった。
伯耆国と言えば、出雲の文化圏内の国であり、古くから鉄の産地として盛んであった所だ。この時の国主は、すでに述べたが、中村一氏の遺児一忠であり、米子藩十七万五千石の大名であった。
国に入った三九郎らは、旅の垢を落すと、先に戻っていた宗章と再会を果たした。宗章は、すぐに目通りの手筈を整えてくれた。
「そなたが滝川三九郎か。五郎右衛門殿から委細承知しておる」
「はっ」
謁見の席上で、先に声を掛けてきたのが、藩の執政である横田内膳村詮である。
村詮は、前主一氏の妹を妻としており、一忠にとっては、叔父にあたる。そして、家康の推薦を受けて、施政を司る立場であった。
「滝川家と我が中村家とは、縁続きと聞いたが誠か?」
上座より、まだあどけなさが残る、主の一忠がその曇りない眼で語りかける。
「左様聞いておりまする。三九郎殿の滝川家と中村家とは、甲賀より出ずる氏にて、元は同族であると」
それは、三九郎も亡父より聞いたことがある程度の事であった。
「三九郎とやら、今後は、そなたを我が一族と思おうぞ」
「ははっ」
思いがけない言葉に、三九郎は少し困惑する。
「滝川殿は、我が流派である新陰流の達人に御座います」
三九郎の困惑を見て取ってか、宗章が横より助け舟を出してくれた。
「そうであるか。村詮!」
「ははっ両名とも、我が殿に新陰流の極意とやらをお見せ頂きたい。この儀如何に?」
「承り候」
初の謁見は上々であった。二人は、並んで退席するのだった。
そして、その日の夜は、宗章宅で三九郎らを囲んだ、ささやかな宴が開かれていた。
「ささっ一杯」
宗章は、自ら三九郎やお菊に酌をし、膳を運ぶなどの気遣いをしてくれていたのだった。
「わしは、所帯持ちでないのでな。不作法はこらえてくれ。料理も酒も用意しておるゆえ、心ゆくまで楽しんでいけ」
宗章は、一人でいそいそと用意を進める。家人の数名が続いて料理を運んで来ると、さっさと退室していく。後は、三九郎らが残るばかりであった。
「そっちの若いのは、名は何と言ったか?お主も来い」
奥に一人控えている才蔵も宗章は、手招きで部屋へ誘う。
「いえ、私はここで」
「才蔵、構う事はない。こっちに来よ」
「そうだぞ才蔵とやら、若いのに遠慮はいかん」
「いえ、私はそう言う事では…」
「今宵ぐらいは、忍びとて酔ってもよかろう」
その宗章の言葉に才蔵は、敏感に反応していた。もうちょっとで胸に秘めている手裏剣に手を差し入れる所であったのだ。
「気づいておられたか?」
「そう気にする事はない。このわし以外は、気づいておらぬ」
宗章は、そう言いながら悠然と杯を干していた。これだけで、才蔵はこの仁には敵わない事を悟り、降参とばかりに両手をあげて、宗章の前にドッカリと座るのだった。
「そうだ。それでよい」
宗章は、自分が飲み干した杯を切ると、それを才蔵の前にズイっと差し出す。才蔵も何も言わずにそれを受け取ると、宗章が並々と注いだ酒を一気に飲み干して見せるのだった。
「おっ若いのにイケル口か?」
これがきっかけで、小宴は一気に盛り上がりを見せるのだった。
話しの内容は、三九郎の柳生の里での修業時代を酒の肴にして進んでいるようであった。
「それで、主人はその時どのように?」
お菊も才蔵も知らぬ十代の三九郎の姿を知る宗章の話しは、二人には新鮮そのものだった。
「三九郎殿もな、最初はカラキシで御座ったよ。しかしな、決して諦めぬ。何度叩きのめされてもな。いずれ、余りのしつこさに教える師範代たちが根を挙げ始め、結局最後には、わししか教える者もおらんなったわ」
酔いのせいか、いつもより数倍も饒舌に話す宗章とは対照的に、三九郎は、笑い続ける三人の中で、苦笑いするしかないのであった。
「ところで、殿様の御前での事どうされる?」
「うむ、わしと三九郎殿とで演武仕るとするか?」
「それは良いとして、ただ太刀の型を見せても芸はあるまい」
「ならば、どうするぞ?」
「アレで行くか?」
「アレか。よし決まりだ!」
三九郎と宗章の間でしか分からない会話が続いていた。お菊がアレとは何かを聞いても、楽しみにしていろとしか言わず、三九郎も口を割らない。むくれるお菊を才蔵が宥めていた。
「ところで、我が殿をどう見た?」
飲み続けている宗章は、さっきまでの酔っていた饒舌家の顔とはうって変り、三九郎が気づくと、その表情は鋭い剣術家としての顔を覗かせているようだった。
「やはり何かありましたか?」
それに気付いた三九郎は、宗章に問い返す。
「中村の殿は、御年十三歳と若年である。であるからして、横田殿が執政として藩を動かしておる。ここまではよいな」
宗章の荒い語気に三人は、コクンと頷く。
「最近の事だが、若殿と横田殿との間が上手く行っていない気がしてな。いや、何かあったとかではないのだが…」
「二人は、叔父甥の間柄では?」
「如何にも。しかし、時に血縁者同士は、骨肉の争いと化す場合があるでな」
ありえそうな話ではあった。年若く未熟な領主と、先主と義兄弟の間柄である百戦錬磨の主席家老とであった。何が生じても不思議ではない。
「殿がどう思っておるのかは、今一つ分からぬ。特に気性も激しく殿より御手打ちにあった者も出ていると聞く。何より、側近共が若殿を取り込もうとしておるのではないかと…」
若年より、模範となるべき父親を欠いて、それに代わる者として、横田村詮は務めていたのかもしれない。しかし、元来激しい気性を持つ若武者には、時に苦言を呈する叔父を疎ましく思っても不思議ではなかった。
「わしはな、流浪の兵法者に過ぎぬ身でありながら、こんな立派な屋敷をつけ、分不相応に扱ってくれる方に、恩を感じておるのだ」
その遠くを見つめながら話す宗章の言葉に偽りはないと、忍びであり、疑う事が職業である筈の才蔵さえもそう思えるほど、宗章の言葉は胸に染みた。
場が和み、酒と話しが尽きない。心が通じ合った相手と呑める酒は格別であっただろう。この日、二人は遅くまで飲み明かした。様々な事を語り合い、共に学んだ新陰流の今後の事も語り合っていた。宗章は、弟である柳生宗矩が、江戸将軍家の剣術指南役となっている事を歓びながらも、剣を極めるよりも、政治を追求する姿勢を嘆いている様子であった。
「苦労が絶えませぬな」
「全くだ!」
三九郎と宗章は、笑い合っていた。しかし、この時すでに何かが起こる事を二人はすでに予感していたのかもしれなかった。
新陰流ご披露の場は、後日の吉日を選び、比較的晴れた空が高い日に行われた。
そもそも、新陰流と言えば、陰流の流れを汲み、上泉伊勢守信綱によって創始された剣術の流派である。それが柳生石舟齋に伝承された。従って、柳生新陰流というのは、俗称である。
正式には、ただの新陰流である。他の新陰流を名乗る支流派や、他派との区別の為に後年呼ばれた為に過ぎない。あくまで、新陰流の正統を継いだのは、二代目石舟齋の柳生であるという自負があるのであろう。
「両名とも、存分に披露致すが宜しい」
横田村詮が声をあげた。白洲にて、大勢の見物客と、宗章の弟子となった藩士たち、そして、上座には、若殿一忠の顔が見える。太鼓のドンと言う合図と共に、一礼の後の向かい合った宗章と三九郎の二人は、佩刀を鞘から抜いて構えた。
「真剣で行うのか…」
場内より声が漏れる。しかし、二人は気にする風もなく、始めて行く。両者ともに一刀両断の構えを取り、エイッと掛け声を発すると共に、型を次々に披露していく。宗章は、斬釘截鉄の型をとり、三九郎は、燕飛をする。また宗章が村雲とすれば、三九郎は月影をすると言うように、両者が黙々とその技を披露していく。それは、とてもゆっくりと誰からも見えるように、確実に一つ一つの業を相手の寸止めで行っていく。
「何じゃ、案外に退屈なものじゃな…」
場内に溜息が、そして若殿が欠伸を漏らしてきたその時に、一連の型が終わりを告げる太鼓が一つなった。宗章は、若殿に向かって一礼する。
それが終わりの合図であると、場内に居た多勢がそう思っていたに違いなかった。しかし、宗章は、再び三九郎に対して、構えを取ると、三九郎も応じるように、再び構えて見せた。
「来い!」
宗章の大喝が合図となり、三九郎は宗章へ、猛然と剣を繰り出し始めた。今度は、先程の型とは違い、鋭い突きを見せる。そして、先程行った型の順番通りに、それを行っていく。二人は、それを寸前で見切る動作を見せつけていった。
しかも、その二人の一連のスピードは、速さを増していくばかりなのだ。三九郎が突き、宗章が鼻先で避ける。または、宗章が斬りつけ、その白刃の残像に三九郎が寸前で身体を晒していく。一見すると、すでに何度か斬られているように見える程の斬撃が、両者の間で何十合と繰り広げられていた。
先程とは違う、神業とも言うべき、技と業とのぶつかり合いに、場内で、歓声が鳴り始めていた。新陰流は、活人剣と云われる。その所以は、人を動かして勝つと言う事であり、相手の先を読む事に重きを置いた剣術であるという。
そして、その業一つ一つを見れば、わざと隙を作り、相手を誘い、その動きに反応するかのように、繰り出す業が多いように思われる。新陰流の業を知らなければ、対峙した相手は、隙があると思い、罠に嵌る事になる。
その空いている頭や、腕等を狙って、剣を繰り出した時には、すでに相手の身体はそこに無く、気が付けば、自分がやられているのである。そのような神業が繰り出せるように成るには、日々の修練を怠りなく続ける、強い意志が必要であった。
三九郎が跳び、宗章が舞う。その度に場内よりおおっとも、ううっとも、いう歓声が上がった。そして、披露がすべて終わる頃には、鳴り止まない程の喝采が起きるという現象が、巻き起こっているのであった。
両者は、終わりを告げる太鼓の音と共に、若殿に向かい一礼をする。そして、宗章と三九郎は、目だけで語りあい、お互いの研鑽してきた修練の業を讃え合っていた。剣を交えた者だけが、分かり合える独特な物の存在を確認しあったのだろう。
「お主ら…」
「両名とも、みごと、お見事であったぞ。殿、両名に労いのお言葉を」
一忠の言葉を遮るように、横田内膳が場内に大声をあげる。そして、そんな家老を睨みつける、若殿の側近たちの姿が見えた。
「… 両名とも大儀であった。仔細は、内膳に任せる」
「ははっ」
しかし、誰もその事に気づかず、こうして、披露の儀は無事に終わる。三九郎も宗章も無事に大役を果たした高揚感で胸がいっぱいになっていた。三九郎は、これを機に正式に中村家へ仕える身分となる。しかしそれは、新たな悲劇の始まりでもあった。
その報せを三九郎が聞いたのは、伯耆国での生活が少し落ち着いてきた頃の事であった。
「何と!それはどういう事か?」
「何か企みて候」
才蔵が珍しく、息を切らしながら、三九郎に報せを持ってきたのは、伯耆国内で、ある人物を見たからに他ならなかった。
「本当に佐助だったのか?」
「間違いございませぬ」
才蔵が佐助の顔を見誤る筈は無かった。どんなに変装や、擬態を工夫していたとしても、才蔵の嗅覚と本能とが、佐助を見つけるであろう。
「その忍は何者ぞ?」
「親の仇にて、我らが敵也!」
三九郎の元へ来ていた宗章に問われて、才蔵は短く答えた。詳細は分からねど、才蔵の眼に宿る復讐の炎を見て、宗章は得心するのだった。
「とにかくも、用心にしくは無し。上田の義兄上にも書状を認めよう」
「私が届けましょうや?」
「いや、才蔵は奴から目を離すな。何かあれば報せよ」
才蔵は頷くと、すぐ様に部屋を飛び出していった。三九郎は、腕組みをしながら思案する。ただ今度こそは、必ず企まれる筈の陰謀を阻止し、佐助を斬るという一念を持つだけであった。
その頃、伯耆国内のとある寺内にて、一人の男が一室にて静かに座していた。名を安井清一郎という。領主中村一忠の側近で、まだ若武者ながら、家中で将来を嘱望された人物である。清一郎は、この一刻近くをある人物が来るのをただひたすら待っていた。そこにスーッと微かな障子を開ける音と共に、一人の老人が入って来た。
「お若いの、薬は要らんかね?」
「ほう、爺様は薬売りか?どんな薬がある」
「何でもござれよ。打ち身、切り傷、風邪薬に、虫殺しまで…」
「国の害虫を始末する薬はあるかい?」
「毎度あり。それでは、早速商談を始めましょうぞ」
その薬売りの老人は、どっかりと清一郎の前に座り、懐よりある書状を出して広げて見せた。それを食い入るように見る清一郎。
「これは、誠であろうな?」
「もちろんじゃ。この通りに行えば、奸賊は死に、そなたは国を救った名誉の武士となる」
老人は、そう言うとニヤリと笑う。とても下衆な笑いだと清一郎は感じていた。だが、この老人の申し状は、とても魅力的であった。というよりも、清一郎が望む未来そのものであったと言える。
「ならば、この証をお示し頂きたい」
ただで、大事を決めてしまう程、俺は甘くは無いと、清一郎の目がそう語っていた。
「よかろう」
老人がそう言うと、いつの間にかに、清一郎の前に、短刀が置かれている。清一郎は、それを恐る恐る手に取る。そして、その短刀を鞘から抜くと、そこに葵の御紋が確かにある事を確認するのだった。
「委細承知!」
「ならば、カラクリをご論じろう」
清十郎がそう言うと、老人は、清一郎の側で耳打ちし始めた。二人の密談は、ほんの半刻に満たない時間であった。
「ならば、わしは立ち戻って主にお伝え申す。ゆめゆめご油断なさらぬよう」
そう言い残すと、老人は、葵の御紋を見つめ続ける清一郎が気づかぬ内に、いつの間にかに姿を消しているのだった。そして、その胸に迫る高揚感を隠しきれない様子の清一郎は、すぐにその部屋を出ると、足早に決意をした顔で、去って行くのだった。
「どうやら、上手く運びそうじゃ」
清一郎が去った事を確認した佐助は、薬売りの旗を放り捨てると、素早くその場から飛び去り、また暗闇の中へ消えた。しかし佐助は、己の姿を視界に捉えている影の存在に、気づいていないのであった。
その日は、しっとりと、静かに雨が降っていた。冬の雨は、何とも冷たく、また重たく感じるものだ。とても気持ちを暗くさせる。或いは、そのような感傷など、必要ないかのように、物事は進むものなのかもしれないが。
或いは、後になってから、あの時こうだったのは、それが原因だったかもしれないなどと、人々が後付のように噂する事象としての雨が、この日の静かなる雨という事なのかもしれなかった。
米子城内では、只今、大賑わいの大忙しといった様子で、城内がバタバタとしていた。外に振り続ける雨に、少しみぞれがかってきた事に気づいている者も皆無である程の忙しさであった。
今日は、領主一忠の正室であり、家康の養女でもある、於さめの方の額治しの儀が執り行われ、城内は宴席場と化していたのだった。於さめの方は、家康の家臣である松平康元の娘であった。康元は、家康の異父弟である。つまりは、政略結婚であったが、家康の養女とはいえ、娘を貰い受けられるのは、中村家の忠義が認められた証拠でもあった。
正室はこの時、まだ十二歳であった。儀式は、男の元服に相当する物だが、これでようやく、若殿様と、御正室様とが枕を共に出来るという証でもあり、とても重要な儀式である。日中の儀式は滞りなく進み、そこには、中村家の家臣一同が参列していた。三九郎も宗章ももちろんその中にいただろう。そして、夜になり、城内では宴席が設けられていたのだった。
「どうじゃ三九郎殿、呑んでおられるか?」
酒宴が進む中、宗章が三九郎を見つけて、酌を勧める。三九郎は、慇懃に空になった杯を差出し、並々と注がれた酒を、一気に胃袋に流し込んだ。
「私は、この後も勤めがございますゆえ」
返杯に酒を注ぎながら、やんわりとこれ以上の酒を断る。それを聞いて、宗章は笑う。
「お勤めは大事なれど、御苦労な事だ」
三九郎は、本当はこの日は非番であった。一忠の剣術指南役の一人としての任に、殿の護衛役としての役目も兼務している。それが、若い同僚より、どうしてもと請われて、警護の任を替わったのだった。いずれ交代の時間がくれば、配置に付かねばならない。
「お勤めは、もう慣れたか?」
「まぁ何とか…」
それが三九郎の正直な気持ちであった。実際、勤め日の一日は、午前中は、御殿様の剣の稽古の相手、午後からは、選ばれた側近と、子弟たちへの稽古であった。それが、日によっては警護の任が入る。世の中の野で、好きなように暮らしてきた三九郎にとっては、給金は良くても、いささか退屈な日々を過ごしていたのだった。
「これも給金分の内ですかね?」
そう言って笑う。
「おぉ雪じゃ。初雪じゃ!」
盛り上がる城内を更に盛り上げるように、外を見ると、先程から降り続いていた雨が、いつの間にかに、更に雪へと変わって、幻想的な白い世界へと変貌させ始めていたのだった。
「あの重たい雨は、雪の振る前兆でしたかな?」
三九郎と宗章は、雪見酒と化した酒宴を楽しんでいたのだった。
「滝川殿、そろそろお時間では?」
二人が話している間に、そう言って、声を掛けてきたのは、安井清一郎であった。
「はい。存じ上げております」
三九郎は、そう言って頭を下げる。清一郎は、殿様の警護役の責任者であった。
「ご両者は御存じかな?この国では、初雪が降る日は、変事の兆候ありと、古くからの言い伝えがあるそうな。事にこのような暗い夜は…」
清一郎が何故、急にそのような事を、この目出度い宴席で言い始めたのか、その時二人には、分からなかった。
「では、そろそろ」
「うむ、また達者で呑もうぞ」
三九郎と宗章は、そう言って、お互いの杯を同時に干した。二人にとって、それが酌み交わされた最後の酒であり、この時話した会話が、最後の会話となる事を、まだ知り得ないでいたのだった。
その後、酒宴も程良い時間でお開きとなり、各々が城より帰っていく。宗章も自宅へと戻ったが、三九郎は宿直の警護番としての勤めがあるため、城内に詰めていた。
「殿の命により、暫くこちらで控えているように」
そう清一郎に言われて、三九郎ら警護の者達は、控えの間と呼ばれる一室で待機を命じられていた。御殿様が居る謁見の間では、若殿と横田村詮とが居て、二人だけで何やら話している様子であった。その様子を確認出来るのは、清一郎唯一人だけであった。この異例の処置に、三九郎ら警護の番は、いささか戸惑っていた。
「何か不遜の事があれば、対処出来ないぞ」
村詮が何かするとは思われないが、時代はまだ戦国の気風を多分に遺したる時期である。何者が、例え殿の身内であれ、重臣が謁見し、殿様が人払いを命じても、すぐの次の間で控えるのが常識とされている。この控えの間では、近いとはいえ、咄嗟の行動が取りづらいだろう。三九郎らは、ただ待つだけしか出来ないでいた。
この日の晩、宴もお開きとなった頃、ほろ酔い気分で帰路に着こうとしていた家老の横田村詮は、殿の小姓に呼び止められて、帰宅するのを後にしていた。
「殿が火急お越し下さいと…」
いささか困惑気味に、一口水を飲み、酔いを紛らわせてから、殿の御前に参上すべく、城内を小姓に続いていく。
「何か変事が起ったか?」
「お急ぎ下さいませ」
小姓の様子で、それと確信した村詮は、歩を速めた。程なくして、殿がいる謁見の間に到着する。
「内膳、江戸より急使じゃ」
一忠より差し出された書状を手に取るため、挨拶もそこそこに、村詮は、何事か?と若殿直々に書状を受け取ろうと、前のめりに、跪く体勢となった。
その時であった。村詮が書状を両手で受けて、それに目を落した瞬間、ピューッという異様な音と共に、首の辺りに違和感を生じたのだ。村詮は、感じた首の右側を手で自然と押さえて、また広げて確認すると、そこに赤い血が着いており、自分が血を流している事に始めて気づいたのだった。
やーっという、その甲高い掛け声と共に、一忠が自分の短刀を振り上げて、向って来るのを、スローモーションで体感した時、村詮はこれが、自分を殺す為の謀議であった事を理解した。
村詮は、咄嗟に空いている左手で、腰の柄に手を掛けるが、相手が自分の主である事を思って、抜けないでいた。この間にも、一忠は、所構わずに、一振り、二振り、一突き、二突きと、刀を繰り出してくる。しかし、所詮、歴戦の猛者である村詮と、年若い実戦経験の無い一忠との違いである。村詮は、その攻撃を寸前で、すべて躱していた。
村詮は、仕方なく、次の間へと逃げ、距離を置こうとしていた。
「奸賊覚悟!」
いきなり、後ろから背中を斬りつけられる。村詮が振り返ると、そこに居たのは、安井清一郎であった。
「安井、謀ったな!」
村詮の怒号に、清一郎は一瞬怯んだ。斬りつけられた、背中も致命傷とはなっていない様子で、村詮は、まだ逃げ延びようとしていた。
「各々方、賊が侵入したぞ!出会い候え!」
清一郎の大声が城内に響き渡っていた。
一方その頃、控えの間で待機していた三九郎は、何やら只事ではない様子を聞きつけ、命令が無いので動けないと言う同僚をよそに、勝手に次の間の出口付近にきて、中の様子を伺おうとしていた。その時であった。清一郎の賊侵入との声に三九郎の顔は、一瞬にして、剣士の顔に変貌していた。
謁見の間では、戦う男達の声と、剣を交える音が聞こえる。三九郎は、素早く抜刀すると、次の間へ、踊るように入り込んだ。そして、三九郎の出現により、退路を断たれた格好となった賊は、三九郎目掛けて、鬼の形相で向かってきた。三九郎は、中段に構えると、その賊の突進を利用するかのように、サッと身を躱し、躱しざまに、横一線の一撃を相手に喰らわせるのだった。
「ぎゃーっ」
断末魔を挙げたかのように、一声あげると、賊はバッタリとその場に、前のめりに倒れ込んだ。
「滝川殿か?お見事也!」
清一郎が走りより、賊を足蹴に仰向けに転がす。そこで初めて、三九郎は、その賊が家老の横田村詮である事を知るのだった。
「これは、どういう事か?横田殿、横田殿!」
三九郎は、村詮を抱きかかえて、揺さぶってみるが、すでにこと切れた後であった。享年五十二歳と伝わる。
「安井、貴様!」
三九郎は、怒りと共に清一郎の胸倉と掴む。しかし、清一郎は臆する事なく、三九郎の手を振り払うと、後ろで放心したかのように、座り込んでいる少年に話し掛けた。
「殿、狼藉者は、この清一郎が斬りまして候」
「た、大儀である」
少しの間をおいて、やっと絞り出した言葉に呼応するかのように、清一郎の笑い声が、不気味に城内に響いていた。上気した息を吐きながら、叔父の血まみれの死体を見続ける若殿と、それを見て笑い続ける家臣。その異様な光景を後悔と共に、呆然とするしかない三九郎であった。
藩内は、騒然としていた。無理もない。若い殿様が、執政である筆頭家老を誅殺してのである。皆一様に、何が何だか分からなくなっており、噂だけがオヒレをつけて、一人歩きし始めていた。先刻までの目出度い宴席が、幻であるかのようであった。
三九郎は、暗い雪道を進んでいる。今晩から降り始めた雪は、藩内すべてを白く染め上げているようだった。まるで、何かを覆い隠してしまいたいかのように。三九郎が誰も通っていない道の歩を進める度に、力強い足跡が後ろに付いていくのだった。
「お前様、一体何事が?」
一度自宅に戻った三九郎は、一人、心配顔をして待っていたお菊に、事の次第を話しながら、身支度を整える。自分の愛刀を鞘から抜き放つと、その刀が発する不気味な光を白刃の具合とを確かめて、また鞘に納める。そして、素早く具足に着替え始める。
「才蔵は?」
「いえ、まだ戻って参りませぬ」
短い問いに短い答え。それだけで分かり合える夫婦である。三九郎の表情を見ただけで、事態が切迫している事に、お菊は気づいていたのだった。
自宅に戻る途中に、三九郎は、宗章の屋敷を訪れたのだが、すでに誰も居ない様子であった。聞けば、横田家の家臣たちは、主の急死を知り、すでに内膳丸と呼ばれる横田家の邸宅もある、砦に集まり始めていたのだった。ここに才蔵がおれば、内膳丸に忍び込み、宗章と連絡も可能であっただろう。
「致し方なし…」
小さく呟いた三九郎であったが、心に残るわだかまりまでは、消せそうになかった。三九郎は、宗章に弁明したい分けではなかった。何を言った所で、自分が村詮を殺した事実が消せる分けではない。恐らく、いや間違いなく、宗章の人柄からして、激しい争いになる事は必定であった。
であるのならば、宗章との戦いが避けられないのであればこそ、三九郎は、師であり、友でもある宗章に対して、互いの胸中をさらけ出したかったに違いなかったのだ。
「心配するな。大丈夫だ」
愛妻の哀願するような表情に、そっと頬を撫ぜてやる。それが例え、気休めの言葉や態度であっても、それだけでも、お菊は救われる気持ちになれたのだった。
「お前様、お気張りなさいまし」
お菊は、三つ指をついて、夫を送り出す。武家の妻たる者、いつ如何なる時でも、戦いに臨む男の後ろ髪を引いてはならないのだ。
「行って参る」
お菊は、精いっぱいの笑顔をして、三九郎は、それを振り返らずに受けながら、力強く邸宅を飛び出していくのだった。
さて宗章であるが、自宅に戻ると程なく、村詮急死の報を受けた。事の次第を確かめるため、すぐに邸宅を飛び出し、内膳丸へと駆けつけていた。
「内膳殿は?」
泣き崩れる村詮の奥方と、それを気丈にも励ます村詮の嫡男主馬助の姿を認めた時、宗章の心は、すでに決まっていた。
「許すまじ、許すまじ!」
宗章以下、内膳丸に駆けつけた横田派の家臣は、総勢二百名を超えていた。これらが決死の覚悟で、村詮の嫡男主馬助を大将に、藩を二分する戦を引き起こすつもりであった。
この事態に一忠以下、清一郎らの城内派は、浮足だっていた。事を起こせば、このような事態になる事など、分かりきっていた筈であるのにも関わらずである。
「どうする?どうする?」
泣きそうな顔で、室内をウロウロする殿様と、腕組みしたままで、座り込んで微動だにせず、事態の解決を図ろうとしない側近の滑稽な姿に、城に戻っていた三九郎は、冷ややかな顔で見ている。
「一度、使者を送ってみるべきでは?」
あたり前過ぎる解決策を、先刻より提示されていたのだが、肝心の使者になりたがる者が見つからず、決行されないでいた。
「やはり、拙者が参りましょうや?」
見かねた三九郎が声を挙げたが、村詮を斬った張本人が乗り込んだとあっては、只で済む筈もなく、却下されていた。しかし、この三九郎の申し出に、清一郎一人だけが賛成し、余計三九郎を苛立たせていたのだった。
「仕方なし。ここは、我が家臣より、使者を立てよう」
状況を見て、溜息交じりに、そう切り出したのは、米子藩の隣国で、出雲国の領主である堀尾吉晴であった。
吉晴は、一忠の父親である一氏とは、長年の僚友であり、豊臣三中老の一人として、秀吉古参の家臣でもあった男である。仏の茂助と呼ばれ、その誠実な人柄は信望を集めていた。
しかし、一度戦となると、誰よりも果敢に攻めかかる、勇猛の武将でもあった。その吉晴が、友の忘れ形見である一忠に請われて、隣国から事態の収拾に軍勢を引き連れて、駆けつけたのだった。
「全く、大事を仕出かしてくれたものよ」
家臣に差配しながら、親友の早すぎる死に、思いを馳せずにはいられない吉晴であった。
吉晴よりの仲裁の使者は、数度に渡って放たれたが、内膳丸の横田派は、いっこうに投降する様子は無かった。
「殿様と刺し違えても、無念を晴らす」
という過激な者もあれば、
「殿がここに来て頭を垂れるならば、考えなくもない」
という者もいたが、要するに横田派の誰一人として、このまま泣き寝入りをしようとする者はいなかったのであった。
「堀尾吉晴の名を持って、こちらに居る者すべてに恩賞を授ける。また横田内膳が子、主馬助には、家督相続を安堵する」
出来るだけの状況打開の案が提示されたが、
「為らば、安井清一郎の首を持って参れ!」
この一言によって、両派の決裂は決定的となってしまった。
「ここに至っては、一戦致しかたなし!」
合議上での吉晴の発言により、米子藩を二分する戦いは、必然となってしまう。三九郎も忸怩たる思いはあったが、心は決していた。その時、外はまだ暗闇の中であった。
これから、行われるであろう戦いの舞台とされる場所が飯山城である。この城に横田主馬助と、柳生宗章以下二百名が、米子城の二の丸に位置する内膳丸より、飯山城へと移り、徹底抗戦の構えを見せたためであった。
この飯山城は、米子城の三の丸に位置し、元々が、今から約五百年前に山名氏の出城として築かれた砦であった。この城は、出雲国と伯耆国との国境沿いに位置する重要な場所に築かれており、山名氏、毛利氏、尼子氏と言った戦国大名たちが、覇を競った場所でもある。現在も、山城後の石垣が残されており、当時の姿を偲ぶことが出来る。
その飯山城に、中村・堀尾連合軍が攻め込んだ時には、昨晩より降り始めた雪も止み、辺りは、まだ溶けきらぬ残雪が、山々を白く染め抜いていたのだった。
「老公には、どうか後詰めをお願い申す。先陣は、我らにお任せ願いたし」
軍議の場にて、諸将の前でそう堀尾吉晴に啖呵を切っていたのは、中村一忠の側近の一人である天野宗杷であった。この男は、安井清一郎と共に、今回の横田騒動を引き起こした首謀者の一人と目される人物でもあった。
「何を言うか。わざわざ出張ってきた我らが、後詰めとは片腹痛し」
吉晴は、六十を過ぎる齢であったが、老いぼれ呼ばわりされて、歴戦の勇士が黙っている筈もない。軍議の場で、私が俺がと互いに譲らず、他の者も先陣を主張し始める等、混乱が生じ始めていた。
「三九郎は、どう思うか?」
今まで一言も発せずにいた、首座に居る一忠が、初めて口を開き、軍議の末席に座る三九郎へ意見を求める。すると先程まで、騒いでいた諸将は皆、一様に口を閉ざし、三九郎へ視線が集まる。
「つまりは、表門を我ら米子藩にて、裏門を松江藩にお願いしては如何に?」
三九郎は、殊更に大声で、しかもはっきりと主張した。
「それは、名案なり!」
三九郎の案に一忠は、膝を打つ。横で座る吉晴も大きく頷いた。これで軍議の方針は決した。後は行動を起こすのみであった。場は、俄然活気づいていたが、三九郎の気持ちは晴れやかではなかった。出来れば、こんな戦には、関わり合いなど持ちたくないと考えていたからだ。
しかし、状況は変わる。人間は思い通りには、いかないものだ。例えそれが、天下を制した家康であっても。三九郎は、条件反射とはいえ、横田村詮を殺した張本人であり、その事実が、中村軍内における彼の評価を一時的にでも、高める効果を発揮しているようであった。
三九郎からしてみれば、武器を持って、襲い掛かってきた曲者を成敗した、つまりは剣士としての性質であっただろうし、一忠の警護役の任からしても妥当な事でもあっただろうと思うのだ。
しかし、三九郎は思う。
(俺が引き金を引いてしまったこの戦の、決着を見届けねばならないだろう)
その思いから、三九郎は不本意ながらも、中村軍の一員として、戦う事を決意したのだった。それは、武士の一分であった。
後の世に、横田騒動、米子城騒動と呼ばれる戦いは、横田村詮殺害後の翌日、未明に行われた。この戦いの最初の砲火をどちらの陣営が放ったのかは、判別としない。
しかし、この戦いの特筆すべき点として挙げるとするならば、両陣営とも消極的な戦いとして、始まってという所であっただろう。何せ前日までは、味方であった同僚、知人、などが、敵味方に別れているのである。中には、縁戚関係で別れた者もあったかもしれない。
であるならば、人間の心理として、遠巻きに銃弾と弓矢を持って、それに当るように考えるのが、自然の流れであっただろう。特にこの際、守る横田方よりも、攻める中村方の士気の低下が、著しく顕著であった事も拍車をかけていた。つまりは、この戦闘に参加した大多数の人間は、余り乗る気ではなかったのである。
そして、そんな状態が二刻程続いてきた時に、ようやく表門の突破に成功するのであった。このまま形勢が決まってしまうかと思われたその時に、中村方に立ち塞がった一人の侍がいた。柳生五郎右衛門宗章である。
宗章は、長槍を奮うと、城の庭園の池の一角に侵入する敵を突き殺し、薙倒し始めた。宗章は、丁度、敵が進行する場所のポイントとなる場所を選び、大勢で攻めかかれない場所を見つけると、そこを自らの拠点としていた。
そして、この柳生家の剣豪が一人居るだけで、表門を攻める中村方に遅れが生じ、裏門を攻める堀尾方との連携にも乱れが生じでしまい、挟み撃ちで一挙に城を落とすという三九郎が立てた作戦が、無に帰する所まで、事態を深刻にしてしまっていたのだった。
この状況に、名乗りを上げた一人の中村方の武将が居た。矢野助之進という剛力で知られた男であった。
「この助之進にお任せあれ」
「頼んだぞ」
一忠は、助之進に盃を取らせると、流石に剛の者らしく、助之進はそれを一気に飲み干し、盃を地面に叩きつけて割り、大声で自らを鼓舞すると、勇ましく戦場へ向かうのであった。
しかし、そんな矢野助之進戦死の報せは、それから半刻もしない内にもたらされた。
「助之進程の男が…」
一忠はそう嘆き、
「誰かおらぬのか?」
焦りから、他の者に怒号を浴びせる清一郎に、幕内は、静まり帰っていた。これで、中村方の突撃が跳ね返されたのは、すでに三度目であった。
「もう中村家に勇者、忠臣は無きや?」
天野が味方を鼓舞しようとするが、戦況は厳しくなる一方であった。宗章は、この戦において、すでに三十人程を討ち取っていたという。
(新陰流とは、これ程までに凄まじい物であったか…)
宗章の獅子奮迅の働きに、小勢の横田方は、大いに士気を高め、その勢いを増しているようであった。そして、このような戦況の成り行きを、幕内の隅で座して、静かに見守っていた三九郎が動いたのは、そんな時であった。
三九郎は、一言も発せず、狼狽えるばかりの一忠らに一礼だけをすると、幕内から出て、宗章の待つ戦場へ向かうのであった。そして、その決意に満ちた、一人の剣士の生き様に気づく者など、居なかったのであった。
風が吹いていた。その風は、戦場に放たれた火を炎へと変え、疾風となりて、人々を飲み込もうとしているかのようであった。
三九郎は、針がねを額に巻くと、自らの両頬を一回だけパンッと叩いた。その瞬間、先程まで幕内で、目を細めて、まるで眠りこけているかのようであった男の顔つきが一変していた。三九郎は、新陰流の剣士として、戦場へ向かう事を決意したようであった。
荒い息遣いがしている。その場所で一人の男が立っていた。男は、額の汗を拭うと、荒くなった息を落ち着かせようと、フゥーっと深く息を一つ吐いた。山城の庭園、池の畔りにてと記せば、どんなに長閑な情景が浮かぶだろうか。
しかし、今その男、柳生宗章が立っているその場は、地獄の血の池、その物であっただろう。池には、多数の味方の屍と、そして、それを遥かに上回る敵の死体とが浮かんでいるのだった。宗章は、どれぐらい敵を倒したのか、味方が傷つき倒れて行ったのか、把握出来なくなる程、槍を突く事をまたは、払う事に集中しているようであった。
いつの間にかに、敵の何回目かの突撃を食い止め、気が付けば、敵は一時退却している様子だった。
「宗章殿…」
不意に名前を呼ばれて、宗章は一瞬気づくのに遅れた。呼ばれた方向を見ると、そこに立っていたのは、間違いなく友であった。
「三九郎殿…」
友であり、弟子であり、同じ新陰流剣士であり、今は敵である滝川三九郎一積である。三九郎は、宗章の姿を認めると、静かに、腰の佩刀を鞘から抜き放ち、正眼の構えを取る。それを見た宗章は、持っていた長槍を鋭く投げた。投げた槍は、建物の柱に見事に突き刺さった。
「わしは嬉しいぞ」
「お互い、悲しい性ですな」
宗章も抜刀し、上段に構えを取る。剣士同士の、強者を見ると戦いたくなる悲しい性との思いと、剣士としての誇りと歓びが入り混じる不思議に高揚した感覚に、二人はこの時陥っていた。二人の剣士から、笑みが零れていた。
金属の反発する音が辺りに響く。二人は間合いを取り、読み合い、相手の出方に瞬時に対応する為、一瞬たりとも、気を抜けない状況であった。
「宗章殿、息が乱れている。他日を期しても良いぞ」
「何を申すか。今、この時でなければならぬ」
そう言い切るより早く、宗章が動いた。その斬撃は凄まじく、三九郎は受けるので精一杯の様子だ。
(流石は、わが師…)
三九郎は、戦いながらも、心の中で、感嘆せずにはおられない。
二人は、気づいていないが、実はこの時、再度の突撃が、中村方より行われ始めた所であった。三九郎と宗章の周りを、敵味方が通り過ぎようと、試みるのだが、二人の凄まじい戦いに巻き込まれて、死ぬ者が数人出た所で、他の者たちは、この場所よりの突撃を諦めて、場所を移動し始めていた。
そして、残った者たちは、いつしか争いを忘れて、二人の新陰流の剣士同士による、稀代の名勝負の成り行きを追い始めていたのだった。
斬釘截鉄、燕飛、山陰、月影、浮舟など、新陰流の技と業とのぶつかり合いが続いていた。二人の戦いは、いつまでも続のではないかと、錯覚する者達までいる程に、二人の戦いは拮抗していた。
「三九郎、決着をつけるぞ」
「おおっ望む所!」
二人は、息を整え、構えを改める。宗章は思う。今この時でなければ、滝川三九郎という優しすぎる男が、師である自分に向かって、本気の勝負に出る事はないだろう。他日を期せば、自分が勝つ可能性が高い。
しかし、そんな事の為に、自分は生きて来たのだろうか?否、柳生宗章は、剣の道を究める為に、生きて来たのだ。強者と戦い、剣とは何かを知る為にこそ、自分は生きている。いや、滝川三九郎という剣豪と戦う、この一戦の為に自分は生きてきたのではないのだろうか?とすら、思えてくるのだった。
宗章は、再び上段の構えを取った。
三九郎は思う。わが師であり、友でもある宗章と争う事は、不幸であろうかと。しかし、同時にこうも思う。柳生宗章ほどの稀代の剣豪と、真剣勝負が出来るのは、同じ新陰流の剣士として、これ以上の誉れは無いのではないのかと。
三九郎は、相反する二つの気持ちを確かに持ちながらも、剣士としての誇りの為に、また宗章に対して、真剣で応える事こそが、この時代の侍の矜持でもあると思っていたのだろう。
三九郎は、宗章に対して、刀を横にする構えを取った。そして、それが何を狙っての事なのか、宗章には分かっていた。宗章は、上段に構えて、正眼に三九郎と対峙していた。
これは、新陰流でいう所の、一刀両断の法であった。対して、三九郎は、宗章を横に見るようにしている。丁度、左肩を宗章に見せつけるように。これは、合撃という技である。
宗章が上段より、刀を振りおろし、三九郎の肩を狙うと、すかさず身を翻して、その振り下ろされる刀の上より、刀を打ち落とす神業である。
これを宗章ほどの強者に対して、行うのは、正に至難の業である。まして、宗章には、その業がどういう物か、熟知しているのだ。
(勝てる…)
そのシンプルだが、強い気持ちに、宗章の心は支配され始めていた。
新陰流において、正眼の構えをとる相手に、合撃の技を仕掛けるのは、言わばセオリーではあったが、三九郎の知らない、その合撃の返し技を宗章は知っていたのだ。それは、柳生本家の人間にしか、受け継がれない秘伝の業である。
まず、合撃の技に合わせるように、刀を相手の肩口を狙って振り下ろす。そして、敵が振り下ろした、自分の刀を打ち落としに来た所で、力を込めて、刀を上に返すのである。そうすれば、相手の振り下ろされた刀を跳ね返し、そのまま敵の喉元を突けるのである。
かなり難度の妙技であり、実戦でこれを試みた者など、今まで一人としていなかった。しかし、宗章には、自信があった。この勝負の時に、自らに一番の大技を課して、三九郎に勝つのである。剣士として、その誘惑には勝てなかった。
(満足だ。わしは、満足だ…)
宗章は、剣士として、こんなにも充足感を得る勝負が出来た事に、心が満ちる歓びを得ていた。しかし、この勝負が着く前に、満ちてしまった心が、その行方を左右したのかもしれない。
「行くぞ!」
「おおっ!」
二人の大喝が辺りに響いた。
宗章は、上段から、一刀両断の法を繰り出し、三九郎の左肩を狙って、刀を振り下ろす。対する三九郎は、その肩に降ろされる刀を寸前で躱すと、振り下ろされた宗章の刀に向かって、自らの帯刀を力いっぱい振り下ろした。
次の瞬間だった。宗章は、刀を返すと、三九郎の振り下ろされる刀目掛けて、刀を払った。
三九郎の刀は、鈍い金属音と共に、舞い上がると、二人の間に落ち、地面に突き刺さる。勝負あった!とその戦いを見守る大勢の敵味方の誰もが、思ったその時であった。
「ぐっ…」
片膝を地面に付き、衣に血を付けているのは、宗章であった。対する三九郎は、その手に、宗章の血をつけた自らの脇差を、しっかりと握り締めているのだった。
「みごと、見事だ…」
宗章は、それだけを言った。三九郎は、刀を弾かれると見た瞬間に、自分の大刀を捨てると、脇差を瞬時に抜き出し、がら空きになった宗章の左胸へ、突き刺したのだった。
「宗章殿…宗章!」
崩れ落ちる友を助け起こそうとする三九郎であったが、宗章はすでに事切れた後であった。その顔は、とても安らかな表情をしていると、三九郎は思った。
(勝負の瞬間、お菊の顔がよぎった…)
二人の新陰流の剣士による壮絶な戦いは幕を閉じた。
二人の勝負を分けたのは、宗章は、勝負の前に戦いの充足感を得たのに対し、三九郎は、自分を待つ妻の為にも、死ぬわけにはいかないとの思いがあり、それが両者の生と死とを分けたのかもしれなかった。
宗章の安らかな横顔に、いつの間にか再び振り始めた雪が、舞い降り始めていたのだった。
「天も泣いておるわ…」
三九郎の独白が、辺りに染み渡るかのようであった。
とにかくも、一つの戦いが終わりを告げた。その後、宗章を失った横田方は、徐々に当初の勢いを無くしていき、表門、裏門共に突破されると、総崩れとなった。主将の横田主馬助ら、横田村詮の家族郎党は、自刃して果てるという、壮絶な最後で戦は幕を閉じた。何とも後味と悪い戦いがここに終結した。
しかし、誰にも知られない一つの戦いがまだ終わってはいなかった。それは、忍びの戦いであった。
戦が起って、ほぼ人の居ない、米子城の奥の院である。そこに一人の男が忍びこんでいた。佐助であった。佐助は、必死にある物を手に入れるべく、探っていたのだ。
(おかしいぞ、どこにも無い…)
佐助の焦りを現すかのように、その部屋中が、佐助によって荒らされていた。
「やはり、現れたな」
佐助が驚いて振り向くと、そこに立っていたのは、才蔵であった。才蔵は、ある物を右手に持っていた。
「それは、もしや…」
佐助が認めて、その才蔵が持っている物を欲しがるように、手を伸ばす仕草をすると、才蔵は、挑発するように、それをズイッと前に押し出すような恰好をした。
「この葵の御紋の入った短刀を、取りに来ると思っておったぞ」
その短刀は、安井清一郎に宛て、柳生宗矩が謀略の支援を認めた書状の入った短刀であった。もちろん、その書状の最後には、徳川秀忠の花押が押されていたのだ。
勝ち誇ったように物的証拠を示す才蔵に対して、佐助は、じっと凝視していくる。その表情は、冷酷そのものであった。
「貴様、才蔵とかいう若造か?あの三郎の息子であったな。親に似て、間抜けなものだな。わしを殺す、唯一の機会を逃したぞ」
「ベラベラと喋る奴だ。すぐにその舌を引っこ抜いてくれるが、殺す前に尋ねたい事がある。何故、中村家で内紛を謀議したか」
才蔵の目は、怒りに満ちていた。当たり前である。目の前に、親や仲間の仇が、すぐ手の届く所に居るのである。
「けっけっけ。何もここに限った事でもない。大名家の力を削ぐ為に事を成すが、我が仕事でな」
佐助は、その下品な笑いと共に、何とも下衆な内容をしゃべる。才蔵の怒りは更に増した。
「成程、各大名家の力を削がねば、あの次期将軍では、徳川も終わりと言う訳か?」
「ほざけ!」
佐助は、自分の忍刀を抜くと、才蔵目掛けて突っ込んできた。才蔵は、それを見計らっていたっていたかのように、自分も忍刀で対抗する。狭い部屋、暗闇の中で、忍びによる死闘が開始されたのだった。
金属音だけが不気味に木霊する。名乗りも無し、気勢も上げず、掛け声もない。出来るだけ音を出さない、無音での戦いが忍びである。そして、その戦いは、あっけない程の短時間で決着の時を迎えていた。
転機は、才蔵の懐から、件の書状が滑り落ちた時におきた。佐助は、それをすかさず拾い上げた。しかし、そこに一瞬の隙が生まれたのだった。才蔵は、佐助が書状に気を取られている隙に、手裏剣を二本佐助に放つ。すると、書状を取ろうと、伸ばした佐助の右手に見事ひとつが命中したのだった。
(グッ)
一瞬苦悶に顔をしかめた佐助であったが、さすがに声を一言もあげず、書状も傷ついた右手で、しっかりと持っていた。
(ここまでだな…)
才蔵は心で呟くと、後ろ背に、勢いよく襖を開け放つ。
「曲者じゃ、出会え候え」
才蔵は、大声で呼ばわると、辺りから灯りを持って、警護の者たちが迫る音が聞こえてきていた。
「きさま…」
負傷した右手を抑えながら、佐助はある事に気づいていた。才蔵は、忍刀を使っているが、微かな灯りで、照らし出されたその恰好は、侍のそれであったのだ。
これでは、どうしても、賊とそれを阻もうとした城の者である。佐助は、瞬時に自らの不利を悟ると、才蔵の居る反対側の障子に、忍刀を投げつけ、ぶち破る。そして、身を乗り出すと、下を確認する。すぐに堀があり、下が水である事を理解すると、躊躇なく、そこから飛び降りるのだった。
(しまった…)
才蔵が思った時には、佐助の身体は、障子の外に消えていた。才蔵は、駆けつけてきた城の護衛たちと共に、佐助の行方を探すが、佐助の姿はどこにもなかった。才蔵は、またしても佐助を取り逃がしてしまったのだった。
横田騒動と言われる戦いは、これで終わった。城では、戦勝の宴が行われていた。しかし、その場に滝川三九郎の姿は無い。三九郎は、自邸に戻っていた。
「宗章殿に…」
三九郎は、お菊と帰ってきた才蔵と共に、亡き友に盃を捧げる。
「宗章殿は、俺が斬った」
盃を一気に飲み干すと、三九郎はお菊に事の顛末を語る。
「それは、宗章殿も本望でありましょう」
お菊はそれだけを言うと、空になった盃を再び満たしてやる。三九郎は、その並々となった盃に視線を落とすと、またそれを一気に飲み干していた。
「そうか、佐助は取り逃がしてか…」
「はい、しかし奴が手傷を負った箇所には、毒を塗ってありました」
才蔵の正確な報告で、三九郎は、この騒動の事態の顛末を知り得ていたのだった。
「ならば、佐助もこれでお終いじゃな。少なくとも、忍びとしては」
「そうだと、良いのですが…」
三九郎は、何も答えずに、ゴロンと転がる。そして、寝転がったままで、再び盃を口に持っていく。一口飲もうとして、一瞬躊躇し、杯を天に掲げる。そして、再び杯を口に運んだ。それが、三九郎なりの、死者への手向けであった。
「三九郎、思い留まっては呉れぬか?」
騒動より、数日後の事であった。一忠に呼び出された三九郎は、横田村詮の死によって空席となっていた家老職を提示されたのだが、これを瞬時に断っていた。
そして、
「お暇を頂きまする」
三九郎は、中村家を去るという。その決意は固かった。一忠は、何とか三九郎を止めようとしたのだが、友を殺して、その屍の上に出世するなど、滝川三九郎の名折れだと断固として断ったのであった。
「すまぬ、また浪々暮らしじゃ」
「はい」
城から戻って、お菊に詫びた三九郎であったが、帰ると、お菊はもう支度を始めてしまっていた。三九郎の性分であれば、そうするだろう事をお菊には、分かっていたのだ。
「お菊様、これはどうします?」
「才蔵、これはこっちでお願い」
「はい」
二人は、見事な連携で、さっさと荷物を纏めてしまった。不要な家具などは、世話になった者達へ、餞別としてあげればいいし、身軽に越して来たのだ。また身一つで行けばいいだけだ。滝川三九郎という男は、人が屍の上に、自らの権力を据えるなど到底出来ない男であった。
この戦国の世を生き抜く侍としては、少々欲の無さすぎる武士(もののふ)の生き様が、お菊には、何とも言えず好ましく感じていた。
「また、江戸で長屋暮らしじゃ」
「あら、嬉しいこと」
頭を掻く夫に、本当に嬉しそうに笑う妻、この二人の為に自分は生きるのだと、この瞬間を、何とも好ましく思う才蔵であった。
そして、中村家のその後であるが、この横田騒動は、当然幕府の知る所となっていた。当然の事ながら、将軍家康の耳にも届く。
家康は激怒した。自分が認めて、一忠の後見役とした横田村詮をいきなり誅殺したのだ。自分の顔に泥を塗られたのも当然であった。家康は、即刻、この度に騒動を主導した者達を罰した。つまり、一忠の側近である安井清一郎は切腹とし、天野宗杷は、斬首となった。天野はキリシタンであり、自決出来ない為の処置と言われている。その他、謀議に加担した主だった者が吟味なくして、すぐに処刑された事が、家康の激怒を物語っている。
これに驚いた一忠は、謝罪の為に江戸に向かうが、江戸入府を拒否され謹慎とされた。が後に許されている。一忠の父一氏の功績に報いる為と、幕府が開かれて間もない時期であった事が、幸いしたと言えた。今、中村家を取り潰して、政治的な動揺を、全国に飛び火させない処置でもあった。
しかし、罪を許された一忠であるが、それから六年後の慶長十四(1609)年五月に急死した。享年二十歳の若さであった。狩りの最中に食した、梅に当たったと言われているが、まずもって、毒殺である可能性が高い。誰がそれを行ったかは、明らかであった。
そして、届け出てない庶子の男児は居たらしいが、幕府は中村家の断絶、一家の取潰しを決定した。横田村詮が存命であったならば、その庶子を持って、中村家を継がしめる事が出来たかもしれない。ここに米子藩中村家は、歴史の彼方に消えるのであった。
0
お気に入りに追加
16
あなたにおすすめの小説


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
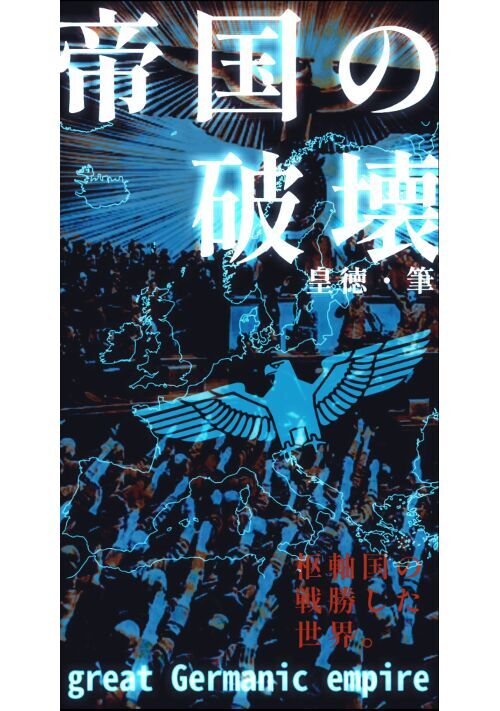
『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−
皇徳❀twitter
歴史・時代
この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。
二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

天竜川で逢いましょう 起きたら関ヶ原の戦い直前の石田三成になっていた 。そもそも現代人が生首とか無理なので平和な世の中を作ろうと思います。
岩 大志
歴史・時代
ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。
けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。
髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。
戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!?

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す。
独裁国家が民主国家を数で上回っている現代だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 純粋に国を、民を憂う思いが、粛清の嵐を巻き起こす
【第弐章 川中島合戦】 甲斐の虎と越後の龍、激突す
【第参章 戦争の黒幕】 京の都が、二人の英雄を不倶戴天の敵と成す
【第四章 織田信長の愛娘】 清廉潔白な人々が、武器商人への憎悪を燃やす
【最終章 西上作戦】 武田家を滅ぼす策略に抗うべく、信長と家康打倒を決断す
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です))

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した
若き日の滝川一益と滝川義太夫、
尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として
天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が
からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記
颯野秋乃
歴史・時代
1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。
ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。
また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。
その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。
この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。
またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。
この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…
大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。
【重要】
不定期更新。超絶不定期更新です。

本能のままに
揚羽
歴史・時代
1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった
もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!
※更新は不定期になると思います。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















