13 / 15
第十二幕 ~秀吉の躍進~
しおりを挟む
秀吉が本能寺の変を知ったのは、翌日の六月三日の事であった。運命の分かれ道であったのだろうか?光秀が毛利軍へ発した間者が、毛利軍と見誤って、羽柴軍の陣所へ飛び込んでしまったと言われている。
しかし、これによりも先に、秀吉は、京都で急変が起きる事を知っていた可能性がある。
「何という事だ…京の間者からの報せて、もしや!と思うていたが…」
信長の死を知った秀吉は狼狽の余り、幕下において暫く、誰にも会わないで、一人いた。
「これでは、毛利と秘密裏に和睦を結んでいたのが、仇となるでは無いか?」
秀吉は、一人愚痴を零し続けていた。
「それにしても、恐ろしいのは明智光秀よ。あの織田信長を本当に殺したのだ…わしは、あの男には、届かないのか…」
秀吉は、そう呟いてから、一人視線を下に落として動かなくなってしまった。
(わしの夢が…天下が遠のいていく…)
秀吉は、数年前の事を思い出していた。安土城にて、信長を囲んで酒宴を開いていた時の事であった。
「謙信も信玄もすでに亡く、上様の天下取りを妨げる者など、すでに在りませぬなあ」
酒宴も進み、皆が程よく酔った所で、話しの話題は何時しか、天下論へと傾いて行った。
「余がまだ尾張を総べる前は、斎藤道三が居り、三好長慶がいた。毛利元就が健在で、本願寺や六角、浅井・朝倉などが跋扈しておった。しかし、今となっては、誰が余を止められるだろうか?」
皆は口ぐちに、その時の戦話しで盛り上がり、各々が自分の手柄話しを始めていた。
「ここで皆に問いたい!余が死ねば、天下は誰の物となろうか?」
「されば、そこに居わす若殿にござ候」
「たわけ!これは座興じゃ。余の血縁は外せ」
秀吉の言葉にすかさず信長が答え、場は笑いに包まれた。それを契機として、皆は口ぐちに、自分の思う天下論に興じ始めていた。
「北条はどうか?早雲より、その治政は、優れておると聞く」
「いや、武田、今川も弱体した今となっては、北条も天下を取るまではいかぬ」
「なれば、土佐をまとめた長宗我部はどうか?いや、まだ小さい。ならば…」
議論は、紛糾していたが、結論は出そうにはない様子であった。
この酒宴に参加していた者は、羽柴秀吉に柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、若殿こと、織田信忠と信雄・信孝兄弟、堀秀政、村井貞勝、細川藤孝などであった。重臣でも滝川一益は居らず、明智光秀も丹波にて任務に当っており、不在であった。
「大殿は如何にお考えか?」
柴田勝家が信長に問う。それまで話し声で賑わっていた酒宴場は、いつの間にか静かになり、一人もしゃべる者が居なくなっていた。皆が信長の言葉に耳を傾けていた。
「余の見立てでは、我が家臣に居るやも知れぬ。それもこの場に居らぬ誰かじゃ」
この信長の発言により、場は更に熱を帯び始めていた。
「滝川殿か?いや、徳川殿では?」
一人の者が発言した所で、口ぐちに(そうだ!)という声が上がり始めた。
「三河殿か?確かに家康は力を持った。三河に加えて、駿河・遠江を加えて、徳川は大国と言える。三河武士は結束が強く、一人一人も武功者が多いと聞く。家康も思慮深く、家臣思いで、関係も良好じゃ。しかし、余から見れば、まだ若いなぁ。三方ヶ原のように血気に逸る所もまだある。天下は遠かろう」
これが、この時点でも信長による家康評であった。
「しからば、何者が大殿の天下を継げましょうや?拙者には、何者にもそれは成し得ぬ事と存じ候」
丹羽長秀が、前に進み出て大声を張り上げる。その言葉に喝采の声が所々で上がる。
「一人だけ居るわ」
信長は、そう言うと、呑めない酒を杯に注ぎ、一気に飲み干した。
「明智日向守也!」
万座の席で一つの声が上がった。秀吉が声のした方を見ると、細川藤孝であった。それを聞いた皆は、藤孝の顔を見た後、すぐに信長を見た。
信長は、否定も肯定もしなかった。その態度が、信長が考える唯一人の人物を指し示していた。
(明智だと言うのか…)
秀吉は、内心でこれ以上にない落胆と、嫉妬の渦の中に居た。秀吉は、再度、藤孝を見た。藤孝も自分と同じ顔をしていると、秀吉は思った。藤孝も秀吉を見た。お互いに見合わせた顔が、二人の真実を告げていた。
(俺は、光秀に劣ると言うのか…)
この思いこそが、秀吉が心の奥底にしまっていた筈の「天下人」という野心に、火をつけるきっかけとなった事を、秀吉以外は、誰も知らなかったのである。
秀吉は、信長の死を知り、幕舎内に一人、引き籠ったままであった。
「殿、御免仕る」
その時、幕舎内に秀吉の参謀である黒田官兵衛が不用意に入って来ていた。
「殿、御武運が開け申したぞ!」
官兵衛は、そう言うと秀吉に近寄り、自分の右手でその左膝をさすった。その時、見上げた秀吉の眼を官兵衛は見た。見てしまった。これまで見たことも無い、何とも卑しい眼をしていた。
(見られた…殺すしかない!)
秀吉は、とっさに官兵衛に殺意を覚えた。他の誰にも見せたことの無い、自分の心底を、心の奥底に潜む、自分という人間の、最も卑しい部分を見られた気がしていた。秀吉の内に秘めた殺意を感じ取った官兵衛は、膝に置いた手をとっさに放した。そして、目を伏せて、その場に平伏した。他に自分の命が助かる術を思いつかなかったからであった。
「信長公無き後は、貴方様が天下人に…。この官兵衛微力を尽くし申す所存…」
額を地面に擦りつけながら、そう心の底から哀願する官兵衛を見た秀吉は、こう思った。
(この男はいつか、殺さねばなぬかもしれぬ…)
秀吉は、平伏する官兵衛の後頭部を見ながら、心の内から湧き出る殺意を抑えようと努力していた。
「恵瓊を呼べ!」
秀吉は、幕舎から出るのにそれだけを言った。その言葉だけで、官兵衛には、それが何を意味するのかが理解出来た。秀吉が去った幕舎の中で、官兵衛は一人、戦慄が身体を駆け巡り、先程秀吉の膝を触っていた震えている自分の右腕を、必死に反対の手で押さえていた。
安国寺恵瓊。毛利家の家臣で、主に外交僧として活躍した人物である。彼を語る時に必ず語られるのが、信長の横死を予見し、秀吉の台頭を見抜いた、次の言葉であろう。
(信長公の代、五年程は持たるべき候。栄達の後、高転び仰向けに転がりし候。藤吉郎さりとては者にて候)
この予言を彼は、天正元年(1573)に記している。この年は、信長が浅井・朝倉を滅ぼした年であったが、まだ政権を確立するまでは、力が及んでいない時期である。恵瓊の眼力の確かさが伺える。恵瓊が秀吉を賞賛している事から分かるように、恵瓊は、早い段階で、毛利と織田との間の外交折衝を務めていた。
それは、両雄が友好関係から一転して、敵対関係になってからも続いており、この秀吉との関係は、不思議としか言いようがない。普通、敵対関係になってしまった陣営の一軍の大将と外交官とが、関係を続けられるであろうか?ここに両者の何らかの策謀が働いていたとしても、全くおかしくはない。
恵瓊は、後年に秀吉の直臣に取り立てられて、大名となっている。
「安国寺殿、参られました」
恵瓊が秀吉の元を訪れたのは、その日の夜半に入った時間であった。その幕舎内には、秀吉の他には、参謀の黒田官兵衛、秀吉の弟で副将でもある羽柴秀長、秀吉の重臣である蜂須賀小六正勝、秀吉の側近の石田佐吉が居た。
「火急のお召し、何事にござろうや?」
恵瓊は、天幕内の空気が張付いているのを感じて、困惑していた。
(いつもの空気ではない…)
そこは、いつの時でも敵陣に赴いて、外交折衝をしてきた嗅覚とでも言うのだろうか?それが働いていたのだろう。
「信長公は、お主が予見した通りに死んだ…」
そう語った秀吉の目は、恵瓊の方を見ては居なかった。
「六月二日の未明に、宿泊していた本能寺にて、惟任日向の軍に襲われて、非業の死を遂げられた由」
秀吉の横から官兵衛が、詳細を話してくれた。
「兄上!敵方の武将に漏らすなど…」
「構わぬ。恵瓊は最早、身内に候」
弟の秀長は、懸念を表したが、秀吉はそう言って、意に介そうとはしなかった。
「これから、どうなさるおつもりで…」
恵瓊は、自分の背中に冷や汗が流れるのを感じていた。喉は一瞬にして渇き、声を絞り出すように何とか口を動かしていた。その横で蜂須賀小六は、憮然とした表情で、自分の顎髭を触っている。
「恵瓊よ、良く聞くがいい。わしとそなたと、ここに居る皆の未来のために、一つの首を獲って来て貰いたい」
その秀吉の頼みが、何を指しているのかを、恵瓊は瞬時に判断していた。最早、サイは投げらているのだ。やるしかなかった。
「殿、本当に大丈夫なのでしょうか?」
恵瓊が去った後に、小六が秀吉に問いかける。
「賭けじゃ、賭け!あの安国寺恵瓊は、元は毛利に滅ぼされた安芸武田氏の出だ。今は毛利に仕えるとも、心底でどう思っておるかは、別儀であろう?」
そう言って微かに笑う秀吉を、小六は不気味に思うのだった。
秀吉が備中高松城を水攻めにし、その包囲を完成させて、城の周りに湖を出現させたのは、天正十年(1582)五月十二日の事であった。この水攻めをする前に、三万の大軍にて、二度に渡る総攻撃を仕掛けるも、城主、清水宗治と共に籠城する敵に、手酷い痛手を被り、城を落とす事は出来ないでいた。
秀吉は、官兵衛の献策を聞き入れて、水攻めの奇策を実行に移す事を決意した。長堤の堤防を設置し、その建設にあたっては、土塁を運んできた近隣の民百姓に、金や米を渡して、驚異的な速さで堤を完成させたのは、有名な話しである。
これに危機感を募らせた毛利軍は、三万とも四万とも言われる毛利本軍を、援軍として派遣する事に決定した。それに対抗して、秀吉は、信長に援軍を要請し、それを受けた信長は、自らの出兵と光秀にも援軍として、出馬命令を下した。
そして、光秀が本能寺の変を起こして、信長を殺害する。秀吉は、一転して窮地に立たされる事となってしまった。
ここで、ある疑念が湧いてくる。果たして、高松城の水攻めと、信長への援軍要請は、必要な事案であったのだろうか?という事である。秀吉は、毛利氏相手に優勢に戦を展開していた。いくら、毛利本軍が控えているとはいえ、援軍を要請して、信長が出兵するまでは、まだ戦は進んでいないのである。
思い出してもらいたい。信長が仇敵武田氏を滅ぼした時は、先に嫡男信忠を大将に軍を派遣して、ほとんど戦局が決まってから、信長は動いている。これを毛利との戦線に置き換えると、まだ時期が早すぎるように感じるのだ。秀吉は、苦戦のために援軍を要請したとなっている。しかし、本当は優勢であったのだ。
これを秀吉による信長への点数稼ぎと考える節もあるが、信長は、過去に自力で敵を破れなかった、本願寺攻めの大将であった佐久間信盛を、戦後に高野山に追放している。信長は、働かない大将を許さない。
先年に秀吉は、備前の大名である宇喜多直家を独断で降して味方にした事があった。秀吉は賞賛されると思っていたが、信長は烈火の如く怒り、秀吉は恐縮するしかなかったという事実がある。秀吉は何としてでも、毛利氏を独力で落とさねば、立場が無かった筈なのである。
また、城を水攻めにするのは、自軍の力を示す効果は期待出来るが、持久戦となり、落城するまでに時間が掛かり過ぎるという欠点がある。また、敵の救援が到着する時間を与える結果となっており、短期決戦を望んでいた筈の秀吉の意志とは違う。
実は、この時すでに毛利側からは、内々に織田との講和を望む条件提示が出されており、秘密裏に和睦へと向けた話し合いが秀吉と恵瓊との間で持たれていた。この事実は、秀吉が後年に記した歴史書の中で認めている。
変である。すでに講和の条件を詰めている段階で、信長が来れば、講和自体が無くなる可能性が高い。これは、信長も知っていたのだろうか?いや、そうであれば、信長は救援には来ないであっただろう。
信長自身は、光秀を使って家康を討とうと暗躍していた。それを逆手に取って、光秀に討たれた。そして、秀吉も毛利を使って信長を討とうと画策していたとしたら、荒唐無稽な考えであろうか?この事に思い至った時に、恵瓊の予見が現実の物として、甦ってくるのである。
(信長公、高転びに転がり申し候、藤吉郎さりとてはの者にて候…)
本能寺の変の策謀は、実に二重三重にも入り重なった、様々な人々による思惑の渦の中で、複雑になった糸が解けぬ状態のまま、新たな火種を残して、戦の火中に押し進んでいくのであった。
安国寺恵瓊は、今や湖水に浮かんでいる備中高松城に来ていた。
「これは、これは恵瓊殿。何ぞ吉報がござりましたかな?」
城主の清水宗治は、小船に乗って城に入った恵瓊を迎え入れていた。
「なぜ、吉報と思いなさる?宗治殿」
「使者である恵瓊殿が単身で城に来られたと言う事は、和議が整ったからに、他なりませぬ」
恵瓊は、その宗治の明るく務める態度に胸が痛んでいた。清水宗治は、元々は、毛利家ではなく、三村氏の重臣であった。
それが、時勢により、毛利氏に仕えるようになった。言わば、外様の自治領主であった。宗治は、毛利元就の三男で、毛利家重臣の小早川隆景付きの家臣として、毛利氏に仕えており、忠誠心も厚く、毛利家首脳陣からの信頼も篤い男であった。
「うむ、実はその件で来たのです。貴殿のお心次第で、この城の家臣一同と、如いては毛利家全体が救われる…」
そこまで、恵瓊が言った時に宗治は、恵瓊の前に右手を広げて、それを制止した。
「恵瓊殿のお心遣い感謝に堪えませぬ。喜んで、この首を差し出しましょう」
宗治は、そう言って深々と頭を下げた。恵瓊は、内心で感動を覚えていた。これ程までに見事な勇者を見たのは始めてであった。
(毛利宗家が、宗治の命を惜しむ分けだ…)
実は、これより以前に出されていた、毛利家と秀吉との講和の条件は、毛利側から五ヶ国の割譲と、備中高松城の開城。そして、城主の清水宗治の首を差し出すという内容であったのだ。毛利家惣領たる毛利輝元と、毛利家の両川こと、吉川元春と小早川隆景は、協議を重ねた結果、城の明け渡しと国の割譲は受け入れたが、宗治の命だけは頑として拒否していた。そして、和睦は一時、破談になりかけていた経緯があったのだ。
「これは、拙僧の一存なのです。毛利のお館様は、宗治殿の命を助けようと…」
ここまで言った時に、恵瓊の目から涙が溢れ、それ以上言葉にはならなかった。これには、恵瓊自身が一番驚いていた。
「分かっており申す。よく分かって御座る」
宗治は、終始笑顔であった。交渉の細部の打ち合わせの為に、再び秀吉の元へ赴く為に城を出で、湖上の人となった恵瓊を宗治は、いつまでも見送っていた。
(惜しい男だが…)
恵瓊が見た高松城内の様子は、兵糧が底を尽き、援軍はこの水のために近寄る事さえ出来ない状況で、弾薬や矢も尽きかけている。城兵は皆、生気を失った顔をしており、中には、空腹の余り、味方の死体を貪る者も居たという。
宗治が即座に、自分の命を差し出す事を了承したのは、この城兵たちの命と、微かに残った希望の灯火とを護るためであったのだろうと、恵瓊はその時、理解したのだった。
六月四日、一艘の小舟が城を取り巻く、湖の中を進んでいた。その舟には、船頭が一人と、白装束姿の武士が四名と、襷を掛けて太刀を携えた、二人の武者が見えていた。
皆、神妙な顔をしており、一言も言葉を発する者は居ない。その舟が進む様子を、高松城の城方の敗残兵約五千名と毛利本隊の四万、羽柴軍約三万が固唾を飲んで、見守っていた。小舟はやがて、秀吉の陣が良く見える前まで来ると、そこで止まった。
「これなるは、高松城城主、清水宗治にて候、羽柴筑前守殿におかれましては、ゆめゆめ約定の儀、取り違え無きよう、お願い申しあげまする」
宗治は、大声で口上を述べると、深々と一礼した。その所作、言動の一つ一つが形を成しており、これから死に立ち向かう者としての、恐れや不安といった要素は、少しも見られなかった。
「黒田官兵衛にございまする。約定の儀、必ず果たし候、御心配なさるべからず」
官兵衛は、思わず大声を上げていた。官兵衛と宗治は、その瞬間、確かに目線が合わさっていた。宗治は、官兵衛の言葉に安堵したのか、大きく頷いて見せた。
宗治は、ここで曲舞の一節を謡い、舞ったという。その後、静かに着座すると、辞世の句を認めた。
「浮世をば、今こそ渡れ武士(もののふ)の、名を高松の苔に残して」
辞世を認め終わった宗治は、一つ大きく深呼吸した。そして、衣服の前をはだけさせ、脇差を構えると、一気に自らの腹に突き立てた。宗治が横一線に脇差を引き終えた瞬間に、その背後にいた介錯人の男が太刀を一閃する。
そして、宗治の首と胴が離れた。宗治の横に控えていた兄の月清入道と、家老の二人は、遅れてはならじと、次々に自らの腹に刀を突き立てた。その都度、介錯人の二人は、太刀を一閃していた。
「お見事なり!真に武士であった」
一部始終を見ていた秀吉は、思わず自分の片膝を叩いて、宗治達の死に様を讃えた。この時の宗治が行った切腹の方法が、その後の武士社会においての「名誉ある切腹の死」という、一つの概念までに、後世育っていくのであった。
これにより、毛利氏と秀吉による和議は成立した。秀吉は、毛利本隊の退却を見届けると、高松城の土塁を破壊するように命令し、六月六日の午後には、城を取り囲んでいた軍勢に撤退命令を下した。
これに遡る事、六月四日、毛利氏との緊急和議が整った直後の事である。
「佐吉、頼んだぞ」
「御意!」
秀吉の陣より、一人の若者が主命を帯びて、飛び出していった。石田佐吉は、まだ若く、一手の大将が務まる武人ではなかったが、補給や兵理の道に明るく、諸事万端を任せるのに耐えうる人材であったので、秀吉は何かと重宝していた。
秀吉は、すでに撤退準備の指令を出していた。佐吉には、その撤退にあたっての準備の為に、先に送り出していたのであった。これが、後世に奇跡の業と言わしめた「中国大返し」の始まりであった。
秀吉は、毛利氏側とのギリギリの中で、駆け引きを進めながらも、一方では即時退却に向けて、すぐに動き出していた。秀吉は、先に兵を少しずつ、敵に悟られないように返していきながらも、自分は最後まで残っていたという。
「名将清水宗治の死を見届けるまでは、一歩も動かぬ」
秀吉は、家臣にそう言っていたという。見事な敵に対する敬意を表する気持ちと、軍勢の一部がすでに退却を始めているのを悟られない、秀吉なりの策であった。
もちろん、看破されていたら、手薄の本陣を突かれて、万事休すであっただろう。秀吉の豪胆さを示す逸話である。
秀吉は、味方が全軍引き上げるのを見届けると、自分の馬に跨り、とてつもない速さで駆け始めていた。最早、信長の死を知った時の動揺する禿げ鼠の姿はそこには無く、天下に全身全霊を賭けて挑む、一人の武人の姿がそこにはあった。
一方、本隊を撤退し、羽柴軍を見送った毛利軍では、ようやく信長の死を知り、秀吉に一杯喰わされていた事が発覚して、陣中で騒ぎとなっていた。
「今からでも遅くはなし。追撃に如かず!」
毛利元就の次男で、毛利家筆頭家老の吉川元春は、強硬に追撃を主張していた。
「和議の約定は約定也。ここで追撃しては、当家は天下より謗りを受ける。それに、羽柴筑前ほどの者、すでに手は打っておよう」
そう兄を諭したのは、もう一人の筆頭家老である、毛利元就の三男である小早川隆景であった。隆景の推察通りに、秀吉は高松城を囲んでいた土塁を破壊し、濁流で辺りを水浸しとし、敵の追撃を凌いでいた。そして、万一に備えて、味方となった岡山城主の宇喜多直家の遺児、秀家の軍勢を温存して、毛利の追撃に備えていたのだった。
この時に追撃しなかった事で、後日、毛利家は秀吉より厚遇をもって、処される事になるのである。
秀吉は、馬上の人となった。備中高松城を四日に出立していた先発隊に沼(岡山)で追い付き、六日夜には姫路城に達している。秀吉は、五日の日に中川清秀に書状を出しており、そこにも沼まで軍勢を引き上げていると記してある。
「上様及び殿様は、別儀無く候、まずはお喜び申し候…」
秀吉は、強行軍の合間にも、情報操作で敵を攪乱し、味方を増やす作戦に出ている。この書状の中で秀吉は、信長と信忠が光秀の謀叛を回避して、無事に京都を脱出したと書いている。中川清秀は、高山右近と並んで、近畿地方における光秀組下の有力武将であった。秀吉は、光秀勢力の切り崩しに掛かっていたのである。
この策が効果を発揮したのか、清秀は秀吉と誓紙を交わし、義兄弟の契りを交わすまでに、急速にその仲を深めている。また秀吉は、光秀組下武将の中でも、その両翼とも言える細川幽斎と、筒井順慶にもその策謀の手を伸ばしている。
まず、細川家であるが、本能寺の変より数年前から、細川家の家老である、松井康之と昵懇の仲となっていた。秀吉と康之は、播磨攻略戦や、鳥取城攻略の際に共に戦った仲であった。秀吉は、敵軍の安国寺恵瓊を、その「人たらし」の才で籠絡したように、松井康之を籠絡して、内通者に仕立て上げていたのである。
秀吉は、この康之より、光秀や信長及び、京周辺の内情を、逐一報せを貰い、遠く中国の戦線にありながら、手に取るように光秀の行動を読んでいた。これが、両者の明暗を分ける結果となったのである。
また、康之を介して、細川幽斎・忠興親子を懐柔し、光秀に組みしないように、目を光らせていた。後年、松井康之は、秀吉より直臣に取り立て、石見半国十八万国の大名にすると約束されたが、康之はこれを辞退している。
筒井順慶である。日和見の代名詞のように、後年批判を浴びた彼であるが、秀吉による情報操作に踊らされた被害者でもあった。
まず、順慶は、本能寺の変当日に上洛の途中で、信長が中国への出陣の為に安土に帰ったとの情報を得て、仕方なく領国へと帰還している。これがすでに秀吉側から発せられた虚報である可能性があった。ここで、順慶が約束通りに光秀と合流していたならば、結果はどうなっていたかは分からない。
順慶は、光秀が派遣した軍使の藤田伝吾を一度は追い返すも、翻意してもう一度引き返させ、羽柴軍至るの決定的な報が届いた時に、光秀への加担を泣く泣く諦めている。
秀吉は、「光秀と津田信澄による謀反」などの偽情報を流し、潜在的な敵を除く事もやっており、これらは軍師の黒田官兵衛の策謀かもしれなかった。
秀吉は、姫路に到着後は、迫る台風をやり過ごす為と、軍勢に休息を与える為に一日の休息を姫路城で与えていた。
「良くない兆しが見えまする。明日出立なされば、二度と姫路城には、帰って来れますまい。明日のご出陣は、お控えさなれ」
秀吉は、真言宗の護摩堂の僧に、吉兆を占わせていた。
「そは、吉報なり!城に二度と帰らぬとは、明智を討ち果たし、主君の仇を討つ兆しと見た」
秀吉は、僧からの忠告も意に介さずに、家臣たちが待つ大広間へと急ぎ足で向かった。
「皆聞け!護摩堂は大吉と出た。何者も恐れるに足らずじゃ。主君信長公の仇を報じ、逆賊日向守を討つ為に、皆の力をどうか、この秀吉に御貸し頂きたい」
秀吉は、そう言うとその場に座り、深々と家臣一同に向かって、頭を下げた。それを見た家臣達は、皆がこの殿の為ならばと、深く心に刻み、大いに士気を挙げるのだった。
かつて、織田信長は、桶狭間の戦いに向かうに際し、熱田神社において、戦勝祈願を行い、その際に建物の奥で音がした(或いはさせた)のを吉兆と捉えて、味方の士気を多いに鼓舞した。秀吉は、その時の信長を間近で見ていた。秀吉は、その故事に倣ったのかもしれない。
「エイエイオーッ!エイエイオーッツ!」
誰からともなく、勝鬨の声が上がる。その場は、興奮の坩堝と化していた。その様子を黒田官兵衛は、ただ静かにじっと見つめているのだった。
(何と見事に兵をまとめらるるかな…)
官兵衛は、秀吉の人心掌握の見事さに、呆れ果てる思いがしていた。このような危急存亡の秋では、皆が不安に思っており、その心の渦が、いつ暴発するとも限らない。それを逆手に取って、秀吉は、護摩堂の占いという形を借りて、士気をあげるのに利用したのであった。占いの結果など、どちらでも良かった。ただ、明智と戦う為に勝てると皆が思いこむための、きっかけが必要だっただけなのであった。
(この殿ならば、信長公亡き後の天下を安んじ給うやもしれない…)
官兵衛は、その思いをきっかけに、自分も狂乱と化したその群衆の渦の中に身を預けるのだった。
翌九日に軍を発した秀吉は、明石、尼崎を通り抜けて、京都に向かい、六月十二日には、摂津富田へ着陣を果たした。こうして、長年謎とされてきた、秀吉による中国大返しは完遂したのだった。
秀吉が後世に残した惟任退治記による、六月六日より、高松城からの退却を発したのは嘘ではない。
しかし、より正確を記するのなら、六月四日の時点で、退却軍を開始していたのである。秀吉がなぜ?六日からに拘ったかは、議論が待たれる所であるが、この二日間の間に何があったのか?秀吉は、一体何を隠そうとしていたのだろうか?自らの陰謀の証拠であろうか?それとも…
しかし、これによりも先に、秀吉は、京都で急変が起きる事を知っていた可能性がある。
「何という事だ…京の間者からの報せて、もしや!と思うていたが…」
信長の死を知った秀吉は狼狽の余り、幕下において暫く、誰にも会わないで、一人いた。
「これでは、毛利と秘密裏に和睦を結んでいたのが、仇となるでは無いか?」
秀吉は、一人愚痴を零し続けていた。
「それにしても、恐ろしいのは明智光秀よ。あの織田信長を本当に殺したのだ…わしは、あの男には、届かないのか…」
秀吉は、そう呟いてから、一人視線を下に落として動かなくなってしまった。
(わしの夢が…天下が遠のいていく…)
秀吉は、数年前の事を思い出していた。安土城にて、信長を囲んで酒宴を開いていた時の事であった。
「謙信も信玄もすでに亡く、上様の天下取りを妨げる者など、すでに在りませぬなあ」
酒宴も進み、皆が程よく酔った所で、話しの話題は何時しか、天下論へと傾いて行った。
「余がまだ尾張を総べる前は、斎藤道三が居り、三好長慶がいた。毛利元就が健在で、本願寺や六角、浅井・朝倉などが跋扈しておった。しかし、今となっては、誰が余を止められるだろうか?」
皆は口ぐちに、その時の戦話しで盛り上がり、各々が自分の手柄話しを始めていた。
「ここで皆に問いたい!余が死ねば、天下は誰の物となろうか?」
「されば、そこに居わす若殿にござ候」
「たわけ!これは座興じゃ。余の血縁は外せ」
秀吉の言葉にすかさず信長が答え、場は笑いに包まれた。それを契機として、皆は口ぐちに、自分の思う天下論に興じ始めていた。
「北条はどうか?早雲より、その治政は、優れておると聞く」
「いや、武田、今川も弱体した今となっては、北条も天下を取るまではいかぬ」
「なれば、土佐をまとめた長宗我部はどうか?いや、まだ小さい。ならば…」
議論は、紛糾していたが、結論は出そうにはない様子であった。
この酒宴に参加していた者は、羽柴秀吉に柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、若殿こと、織田信忠と信雄・信孝兄弟、堀秀政、村井貞勝、細川藤孝などであった。重臣でも滝川一益は居らず、明智光秀も丹波にて任務に当っており、不在であった。
「大殿は如何にお考えか?」
柴田勝家が信長に問う。それまで話し声で賑わっていた酒宴場は、いつの間にか静かになり、一人もしゃべる者が居なくなっていた。皆が信長の言葉に耳を傾けていた。
「余の見立てでは、我が家臣に居るやも知れぬ。それもこの場に居らぬ誰かじゃ」
この信長の発言により、場は更に熱を帯び始めていた。
「滝川殿か?いや、徳川殿では?」
一人の者が発言した所で、口ぐちに(そうだ!)という声が上がり始めた。
「三河殿か?確かに家康は力を持った。三河に加えて、駿河・遠江を加えて、徳川は大国と言える。三河武士は結束が強く、一人一人も武功者が多いと聞く。家康も思慮深く、家臣思いで、関係も良好じゃ。しかし、余から見れば、まだ若いなぁ。三方ヶ原のように血気に逸る所もまだある。天下は遠かろう」
これが、この時点でも信長による家康評であった。
「しからば、何者が大殿の天下を継げましょうや?拙者には、何者にもそれは成し得ぬ事と存じ候」
丹羽長秀が、前に進み出て大声を張り上げる。その言葉に喝采の声が所々で上がる。
「一人だけ居るわ」
信長は、そう言うと、呑めない酒を杯に注ぎ、一気に飲み干した。
「明智日向守也!」
万座の席で一つの声が上がった。秀吉が声のした方を見ると、細川藤孝であった。それを聞いた皆は、藤孝の顔を見た後、すぐに信長を見た。
信長は、否定も肯定もしなかった。その態度が、信長が考える唯一人の人物を指し示していた。
(明智だと言うのか…)
秀吉は、内心でこれ以上にない落胆と、嫉妬の渦の中に居た。秀吉は、再度、藤孝を見た。藤孝も自分と同じ顔をしていると、秀吉は思った。藤孝も秀吉を見た。お互いに見合わせた顔が、二人の真実を告げていた。
(俺は、光秀に劣ると言うのか…)
この思いこそが、秀吉が心の奥底にしまっていた筈の「天下人」という野心に、火をつけるきっかけとなった事を、秀吉以外は、誰も知らなかったのである。
秀吉は、信長の死を知り、幕舎内に一人、引き籠ったままであった。
「殿、御免仕る」
その時、幕舎内に秀吉の参謀である黒田官兵衛が不用意に入って来ていた。
「殿、御武運が開け申したぞ!」
官兵衛は、そう言うと秀吉に近寄り、自分の右手でその左膝をさすった。その時、見上げた秀吉の眼を官兵衛は見た。見てしまった。これまで見たことも無い、何とも卑しい眼をしていた。
(見られた…殺すしかない!)
秀吉は、とっさに官兵衛に殺意を覚えた。他の誰にも見せたことの無い、自分の心底を、心の奥底に潜む、自分という人間の、最も卑しい部分を見られた気がしていた。秀吉の内に秘めた殺意を感じ取った官兵衛は、膝に置いた手をとっさに放した。そして、目を伏せて、その場に平伏した。他に自分の命が助かる術を思いつかなかったからであった。
「信長公無き後は、貴方様が天下人に…。この官兵衛微力を尽くし申す所存…」
額を地面に擦りつけながら、そう心の底から哀願する官兵衛を見た秀吉は、こう思った。
(この男はいつか、殺さねばなぬかもしれぬ…)
秀吉は、平伏する官兵衛の後頭部を見ながら、心の内から湧き出る殺意を抑えようと努力していた。
「恵瓊を呼べ!」
秀吉は、幕舎から出るのにそれだけを言った。その言葉だけで、官兵衛には、それが何を意味するのかが理解出来た。秀吉が去った幕舎の中で、官兵衛は一人、戦慄が身体を駆け巡り、先程秀吉の膝を触っていた震えている自分の右腕を、必死に反対の手で押さえていた。
安国寺恵瓊。毛利家の家臣で、主に外交僧として活躍した人物である。彼を語る時に必ず語られるのが、信長の横死を予見し、秀吉の台頭を見抜いた、次の言葉であろう。
(信長公の代、五年程は持たるべき候。栄達の後、高転び仰向けに転がりし候。藤吉郎さりとては者にて候)
この予言を彼は、天正元年(1573)に記している。この年は、信長が浅井・朝倉を滅ぼした年であったが、まだ政権を確立するまでは、力が及んでいない時期である。恵瓊の眼力の確かさが伺える。恵瓊が秀吉を賞賛している事から分かるように、恵瓊は、早い段階で、毛利と織田との間の外交折衝を務めていた。
それは、両雄が友好関係から一転して、敵対関係になってからも続いており、この秀吉との関係は、不思議としか言いようがない。普通、敵対関係になってしまった陣営の一軍の大将と外交官とが、関係を続けられるであろうか?ここに両者の何らかの策謀が働いていたとしても、全くおかしくはない。
恵瓊は、後年に秀吉の直臣に取り立てられて、大名となっている。
「安国寺殿、参られました」
恵瓊が秀吉の元を訪れたのは、その日の夜半に入った時間であった。その幕舎内には、秀吉の他には、参謀の黒田官兵衛、秀吉の弟で副将でもある羽柴秀長、秀吉の重臣である蜂須賀小六正勝、秀吉の側近の石田佐吉が居た。
「火急のお召し、何事にござろうや?」
恵瓊は、天幕内の空気が張付いているのを感じて、困惑していた。
(いつもの空気ではない…)
そこは、いつの時でも敵陣に赴いて、外交折衝をしてきた嗅覚とでも言うのだろうか?それが働いていたのだろう。
「信長公は、お主が予見した通りに死んだ…」
そう語った秀吉の目は、恵瓊の方を見ては居なかった。
「六月二日の未明に、宿泊していた本能寺にて、惟任日向の軍に襲われて、非業の死を遂げられた由」
秀吉の横から官兵衛が、詳細を話してくれた。
「兄上!敵方の武将に漏らすなど…」
「構わぬ。恵瓊は最早、身内に候」
弟の秀長は、懸念を表したが、秀吉はそう言って、意に介そうとはしなかった。
「これから、どうなさるおつもりで…」
恵瓊は、自分の背中に冷や汗が流れるのを感じていた。喉は一瞬にして渇き、声を絞り出すように何とか口を動かしていた。その横で蜂須賀小六は、憮然とした表情で、自分の顎髭を触っている。
「恵瓊よ、良く聞くがいい。わしとそなたと、ここに居る皆の未来のために、一つの首を獲って来て貰いたい」
その秀吉の頼みが、何を指しているのかを、恵瓊は瞬時に判断していた。最早、サイは投げらているのだ。やるしかなかった。
「殿、本当に大丈夫なのでしょうか?」
恵瓊が去った後に、小六が秀吉に問いかける。
「賭けじゃ、賭け!あの安国寺恵瓊は、元は毛利に滅ぼされた安芸武田氏の出だ。今は毛利に仕えるとも、心底でどう思っておるかは、別儀であろう?」
そう言って微かに笑う秀吉を、小六は不気味に思うのだった。
秀吉が備中高松城を水攻めにし、その包囲を完成させて、城の周りに湖を出現させたのは、天正十年(1582)五月十二日の事であった。この水攻めをする前に、三万の大軍にて、二度に渡る総攻撃を仕掛けるも、城主、清水宗治と共に籠城する敵に、手酷い痛手を被り、城を落とす事は出来ないでいた。
秀吉は、官兵衛の献策を聞き入れて、水攻めの奇策を実行に移す事を決意した。長堤の堤防を設置し、その建設にあたっては、土塁を運んできた近隣の民百姓に、金や米を渡して、驚異的な速さで堤を完成させたのは、有名な話しである。
これに危機感を募らせた毛利軍は、三万とも四万とも言われる毛利本軍を、援軍として派遣する事に決定した。それに対抗して、秀吉は、信長に援軍を要請し、それを受けた信長は、自らの出兵と光秀にも援軍として、出馬命令を下した。
そして、光秀が本能寺の変を起こして、信長を殺害する。秀吉は、一転して窮地に立たされる事となってしまった。
ここで、ある疑念が湧いてくる。果たして、高松城の水攻めと、信長への援軍要請は、必要な事案であったのだろうか?という事である。秀吉は、毛利氏相手に優勢に戦を展開していた。いくら、毛利本軍が控えているとはいえ、援軍を要請して、信長が出兵するまでは、まだ戦は進んでいないのである。
思い出してもらいたい。信長が仇敵武田氏を滅ぼした時は、先に嫡男信忠を大将に軍を派遣して、ほとんど戦局が決まってから、信長は動いている。これを毛利との戦線に置き換えると、まだ時期が早すぎるように感じるのだ。秀吉は、苦戦のために援軍を要請したとなっている。しかし、本当は優勢であったのだ。
これを秀吉による信長への点数稼ぎと考える節もあるが、信長は、過去に自力で敵を破れなかった、本願寺攻めの大将であった佐久間信盛を、戦後に高野山に追放している。信長は、働かない大将を許さない。
先年に秀吉は、備前の大名である宇喜多直家を独断で降して味方にした事があった。秀吉は賞賛されると思っていたが、信長は烈火の如く怒り、秀吉は恐縮するしかなかったという事実がある。秀吉は何としてでも、毛利氏を独力で落とさねば、立場が無かった筈なのである。
また、城を水攻めにするのは、自軍の力を示す効果は期待出来るが、持久戦となり、落城するまでに時間が掛かり過ぎるという欠点がある。また、敵の救援が到着する時間を与える結果となっており、短期決戦を望んでいた筈の秀吉の意志とは違う。
実は、この時すでに毛利側からは、内々に織田との講和を望む条件提示が出されており、秘密裏に和睦へと向けた話し合いが秀吉と恵瓊との間で持たれていた。この事実は、秀吉が後年に記した歴史書の中で認めている。
変である。すでに講和の条件を詰めている段階で、信長が来れば、講和自体が無くなる可能性が高い。これは、信長も知っていたのだろうか?いや、そうであれば、信長は救援には来ないであっただろう。
信長自身は、光秀を使って家康を討とうと暗躍していた。それを逆手に取って、光秀に討たれた。そして、秀吉も毛利を使って信長を討とうと画策していたとしたら、荒唐無稽な考えであろうか?この事に思い至った時に、恵瓊の予見が現実の物として、甦ってくるのである。
(信長公、高転びに転がり申し候、藤吉郎さりとてはの者にて候…)
本能寺の変の策謀は、実に二重三重にも入り重なった、様々な人々による思惑の渦の中で、複雑になった糸が解けぬ状態のまま、新たな火種を残して、戦の火中に押し進んでいくのであった。
安国寺恵瓊は、今や湖水に浮かんでいる備中高松城に来ていた。
「これは、これは恵瓊殿。何ぞ吉報がござりましたかな?」
城主の清水宗治は、小船に乗って城に入った恵瓊を迎え入れていた。
「なぜ、吉報と思いなさる?宗治殿」
「使者である恵瓊殿が単身で城に来られたと言う事は、和議が整ったからに、他なりませぬ」
恵瓊は、その宗治の明るく務める態度に胸が痛んでいた。清水宗治は、元々は、毛利家ではなく、三村氏の重臣であった。
それが、時勢により、毛利氏に仕えるようになった。言わば、外様の自治領主であった。宗治は、毛利元就の三男で、毛利家重臣の小早川隆景付きの家臣として、毛利氏に仕えており、忠誠心も厚く、毛利家首脳陣からの信頼も篤い男であった。
「うむ、実はその件で来たのです。貴殿のお心次第で、この城の家臣一同と、如いては毛利家全体が救われる…」
そこまで、恵瓊が言った時に宗治は、恵瓊の前に右手を広げて、それを制止した。
「恵瓊殿のお心遣い感謝に堪えませぬ。喜んで、この首を差し出しましょう」
宗治は、そう言って深々と頭を下げた。恵瓊は、内心で感動を覚えていた。これ程までに見事な勇者を見たのは始めてであった。
(毛利宗家が、宗治の命を惜しむ分けだ…)
実は、これより以前に出されていた、毛利家と秀吉との講和の条件は、毛利側から五ヶ国の割譲と、備中高松城の開城。そして、城主の清水宗治の首を差し出すという内容であったのだ。毛利家惣領たる毛利輝元と、毛利家の両川こと、吉川元春と小早川隆景は、協議を重ねた結果、城の明け渡しと国の割譲は受け入れたが、宗治の命だけは頑として拒否していた。そして、和睦は一時、破談になりかけていた経緯があったのだ。
「これは、拙僧の一存なのです。毛利のお館様は、宗治殿の命を助けようと…」
ここまで言った時に、恵瓊の目から涙が溢れ、それ以上言葉にはならなかった。これには、恵瓊自身が一番驚いていた。
「分かっており申す。よく分かって御座る」
宗治は、終始笑顔であった。交渉の細部の打ち合わせの為に、再び秀吉の元へ赴く為に城を出で、湖上の人となった恵瓊を宗治は、いつまでも見送っていた。
(惜しい男だが…)
恵瓊が見た高松城内の様子は、兵糧が底を尽き、援軍はこの水のために近寄る事さえ出来ない状況で、弾薬や矢も尽きかけている。城兵は皆、生気を失った顔をしており、中には、空腹の余り、味方の死体を貪る者も居たという。
宗治が即座に、自分の命を差し出す事を了承したのは、この城兵たちの命と、微かに残った希望の灯火とを護るためであったのだろうと、恵瓊はその時、理解したのだった。
六月四日、一艘の小舟が城を取り巻く、湖の中を進んでいた。その舟には、船頭が一人と、白装束姿の武士が四名と、襷を掛けて太刀を携えた、二人の武者が見えていた。
皆、神妙な顔をしており、一言も言葉を発する者は居ない。その舟が進む様子を、高松城の城方の敗残兵約五千名と毛利本隊の四万、羽柴軍約三万が固唾を飲んで、見守っていた。小舟はやがて、秀吉の陣が良く見える前まで来ると、そこで止まった。
「これなるは、高松城城主、清水宗治にて候、羽柴筑前守殿におかれましては、ゆめゆめ約定の儀、取り違え無きよう、お願い申しあげまする」
宗治は、大声で口上を述べると、深々と一礼した。その所作、言動の一つ一つが形を成しており、これから死に立ち向かう者としての、恐れや不安といった要素は、少しも見られなかった。
「黒田官兵衛にございまする。約定の儀、必ず果たし候、御心配なさるべからず」
官兵衛は、思わず大声を上げていた。官兵衛と宗治は、その瞬間、確かに目線が合わさっていた。宗治は、官兵衛の言葉に安堵したのか、大きく頷いて見せた。
宗治は、ここで曲舞の一節を謡い、舞ったという。その後、静かに着座すると、辞世の句を認めた。
「浮世をば、今こそ渡れ武士(もののふ)の、名を高松の苔に残して」
辞世を認め終わった宗治は、一つ大きく深呼吸した。そして、衣服の前をはだけさせ、脇差を構えると、一気に自らの腹に突き立てた。宗治が横一線に脇差を引き終えた瞬間に、その背後にいた介錯人の男が太刀を一閃する。
そして、宗治の首と胴が離れた。宗治の横に控えていた兄の月清入道と、家老の二人は、遅れてはならじと、次々に自らの腹に刀を突き立てた。その都度、介錯人の二人は、太刀を一閃していた。
「お見事なり!真に武士であった」
一部始終を見ていた秀吉は、思わず自分の片膝を叩いて、宗治達の死に様を讃えた。この時の宗治が行った切腹の方法が、その後の武士社会においての「名誉ある切腹の死」という、一つの概念までに、後世育っていくのであった。
これにより、毛利氏と秀吉による和議は成立した。秀吉は、毛利本隊の退却を見届けると、高松城の土塁を破壊するように命令し、六月六日の午後には、城を取り囲んでいた軍勢に撤退命令を下した。
これに遡る事、六月四日、毛利氏との緊急和議が整った直後の事である。
「佐吉、頼んだぞ」
「御意!」
秀吉の陣より、一人の若者が主命を帯びて、飛び出していった。石田佐吉は、まだ若く、一手の大将が務まる武人ではなかったが、補給や兵理の道に明るく、諸事万端を任せるのに耐えうる人材であったので、秀吉は何かと重宝していた。
秀吉は、すでに撤退準備の指令を出していた。佐吉には、その撤退にあたっての準備の為に、先に送り出していたのであった。これが、後世に奇跡の業と言わしめた「中国大返し」の始まりであった。
秀吉は、毛利氏側とのギリギリの中で、駆け引きを進めながらも、一方では即時退却に向けて、すぐに動き出していた。秀吉は、先に兵を少しずつ、敵に悟られないように返していきながらも、自分は最後まで残っていたという。
「名将清水宗治の死を見届けるまでは、一歩も動かぬ」
秀吉は、家臣にそう言っていたという。見事な敵に対する敬意を表する気持ちと、軍勢の一部がすでに退却を始めているのを悟られない、秀吉なりの策であった。
もちろん、看破されていたら、手薄の本陣を突かれて、万事休すであっただろう。秀吉の豪胆さを示す逸話である。
秀吉は、味方が全軍引き上げるのを見届けると、自分の馬に跨り、とてつもない速さで駆け始めていた。最早、信長の死を知った時の動揺する禿げ鼠の姿はそこには無く、天下に全身全霊を賭けて挑む、一人の武人の姿がそこにはあった。
一方、本隊を撤退し、羽柴軍を見送った毛利軍では、ようやく信長の死を知り、秀吉に一杯喰わされていた事が発覚して、陣中で騒ぎとなっていた。
「今からでも遅くはなし。追撃に如かず!」
毛利元就の次男で、毛利家筆頭家老の吉川元春は、強硬に追撃を主張していた。
「和議の約定は約定也。ここで追撃しては、当家は天下より謗りを受ける。それに、羽柴筑前ほどの者、すでに手は打っておよう」
そう兄を諭したのは、もう一人の筆頭家老である、毛利元就の三男である小早川隆景であった。隆景の推察通りに、秀吉は高松城を囲んでいた土塁を破壊し、濁流で辺りを水浸しとし、敵の追撃を凌いでいた。そして、万一に備えて、味方となった岡山城主の宇喜多直家の遺児、秀家の軍勢を温存して、毛利の追撃に備えていたのだった。
この時に追撃しなかった事で、後日、毛利家は秀吉より厚遇をもって、処される事になるのである。
秀吉は、馬上の人となった。備中高松城を四日に出立していた先発隊に沼(岡山)で追い付き、六日夜には姫路城に達している。秀吉は、五日の日に中川清秀に書状を出しており、そこにも沼まで軍勢を引き上げていると記してある。
「上様及び殿様は、別儀無く候、まずはお喜び申し候…」
秀吉は、強行軍の合間にも、情報操作で敵を攪乱し、味方を増やす作戦に出ている。この書状の中で秀吉は、信長と信忠が光秀の謀叛を回避して、無事に京都を脱出したと書いている。中川清秀は、高山右近と並んで、近畿地方における光秀組下の有力武将であった。秀吉は、光秀勢力の切り崩しに掛かっていたのである。
この策が効果を発揮したのか、清秀は秀吉と誓紙を交わし、義兄弟の契りを交わすまでに、急速にその仲を深めている。また秀吉は、光秀組下武将の中でも、その両翼とも言える細川幽斎と、筒井順慶にもその策謀の手を伸ばしている。
まず、細川家であるが、本能寺の変より数年前から、細川家の家老である、松井康之と昵懇の仲となっていた。秀吉と康之は、播磨攻略戦や、鳥取城攻略の際に共に戦った仲であった。秀吉は、敵軍の安国寺恵瓊を、その「人たらし」の才で籠絡したように、松井康之を籠絡して、内通者に仕立て上げていたのである。
秀吉は、この康之より、光秀や信長及び、京周辺の内情を、逐一報せを貰い、遠く中国の戦線にありながら、手に取るように光秀の行動を読んでいた。これが、両者の明暗を分ける結果となったのである。
また、康之を介して、細川幽斎・忠興親子を懐柔し、光秀に組みしないように、目を光らせていた。後年、松井康之は、秀吉より直臣に取り立て、石見半国十八万国の大名にすると約束されたが、康之はこれを辞退している。
筒井順慶である。日和見の代名詞のように、後年批判を浴びた彼であるが、秀吉による情報操作に踊らされた被害者でもあった。
まず、順慶は、本能寺の変当日に上洛の途中で、信長が中国への出陣の為に安土に帰ったとの情報を得て、仕方なく領国へと帰還している。これがすでに秀吉側から発せられた虚報である可能性があった。ここで、順慶が約束通りに光秀と合流していたならば、結果はどうなっていたかは分からない。
順慶は、光秀が派遣した軍使の藤田伝吾を一度は追い返すも、翻意してもう一度引き返させ、羽柴軍至るの決定的な報が届いた時に、光秀への加担を泣く泣く諦めている。
秀吉は、「光秀と津田信澄による謀反」などの偽情報を流し、潜在的な敵を除く事もやっており、これらは軍師の黒田官兵衛の策謀かもしれなかった。
秀吉は、姫路に到着後は、迫る台風をやり過ごす為と、軍勢に休息を与える為に一日の休息を姫路城で与えていた。
「良くない兆しが見えまする。明日出立なされば、二度と姫路城には、帰って来れますまい。明日のご出陣は、お控えさなれ」
秀吉は、真言宗の護摩堂の僧に、吉兆を占わせていた。
「そは、吉報なり!城に二度と帰らぬとは、明智を討ち果たし、主君の仇を討つ兆しと見た」
秀吉は、僧からの忠告も意に介さずに、家臣たちが待つ大広間へと急ぎ足で向かった。
「皆聞け!護摩堂は大吉と出た。何者も恐れるに足らずじゃ。主君信長公の仇を報じ、逆賊日向守を討つ為に、皆の力をどうか、この秀吉に御貸し頂きたい」
秀吉は、そう言うとその場に座り、深々と家臣一同に向かって、頭を下げた。それを見た家臣達は、皆がこの殿の為ならばと、深く心に刻み、大いに士気を挙げるのだった。
かつて、織田信長は、桶狭間の戦いに向かうに際し、熱田神社において、戦勝祈願を行い、その際に建物の奥で音がした(或いはさせた)のを吉兆と捉えて、味方の士気を多いに鼓舞した。秀吉は、その時の信長を間近で見ていた。秀吉は、その故事に倣ったのかもしれない。
「エイエイオーッ!エイエイオーッツ!」
誰からともなく、勝鬨の声が上がる。その場は、興奮の坩堝と化していた。その様子を黒田官兵衛は、ただ静かにじっと見つめているのだった。
(何と見事に兵をまとめらるるかな…)
官兵衛は、秀吉の人心掌握の見事さに、呆れ果てる思いがしていた。このような危急存亡の秋では、皆が不安に思っており、その心の渦が、いつ暴発するとも限らない。それを逆手に取って、秀吉は、護摩堂の占いという形を借りて、士気をあげるのに利用したのであった。占いの結果など、どちらでも良かった。ただ、明智と戦う為に勝てると皆が思いこむための、きっかけが必要だっただけなのであった。
(この殿ならば、信長公亡き後の天下を安んじ給うやもしれない…)
官兵衛は、その思いをきっかけに、自分も狂乱と化したその群衆の渦の中に身を預けるのだった。
翌九日に軍を発した秀吉は、明石、尼崎を通り抜けて、京都に向かい、六月十二日には、摂津富田へ着陣を果たした。こうして、長年謎とされてきた、秀吉による中国大返しは完遂したのだった。
秀吉が後世に残した惟任退治記による、六月六日より、高松城からの退却を発したのは嘘ではない。
しかし、より正確を記するのなら、六月四日の時点で、退却軍を開始していたのである。秀吉がなぜ?六日からに拘ったかは、議論が待たれる所であるが、この二日間の間に何があったのか?秀吉は、一体何を隠そうとしていたのだろうか?自らの陰謀の証拠であろうか?それとも…
0
お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

陸のくじら侍 -元禄の竜-
陸 理明
歴史・時代
元禄時代、江戸に「くじら侍」と呼ばれた男がいた。かつて武士であるにも関わらず鯨漁に没頭し、そして誰も知らない理由で江戸に流れてきた赤銅色の大男――権藤伊佐馬という。海の巨獣との命を削る凄絶な戦いの果てに会得した正確無比な投げ銛術と、苛烈なまでの剛剣の使い手でもある伊佐馬は、南町奉行所の戦闘狂の美貌の同心・青碕伯之進とともに江戸の悪を討ちつつ、日がな一日ずっと釣りをして生きていくだけの暮らしを続けていた……

浪漫的女英雄三国志
はぎわら歓
歴史・時代
女性の身でありながら天下泰平を志す劉備玄徳は、関羽、張飛、趙雲、諸葛亮を得て、宿敵の女王、曹操孟徳と戦う。
184年黄巾の乱がおこり、義勇軍として劉備玄徳は立ち上がる。宦官の孫である曹操孟徳も挙兵し、名を上げる。
二人の英雄は火花を散らしながら、それぞれの国を建国していく。その二国の均衡を保つのが孫権の呉である。
222年に三国が鼎立し、曹操孟徳、劉備玄徳がなくなった後、呉の孫権仲謀の妹、孫仁尚香が三国の行く末を見守る。
玄徳と曹操は女性です。
他は三国志演義と性別は一緒の予定です。
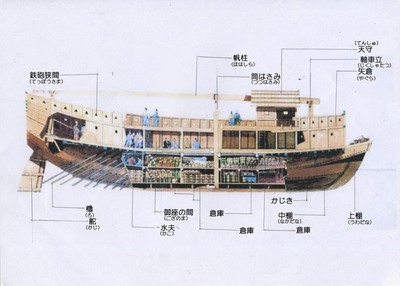

世界大戦は終わらない
Ittoh
歴史・時代
歴史上、人類が経験した、初めての世界大戦、元老井上馨が、「天祐」といったのは、大日本帝国の国際的な地位確立を図る好機であった。世界中の人々を巻き込んだ世界大戦は、世界の歴史そのものを変えたのである。そして大陸には、国際連盟の委任統治領として、「特区」が生まれるのである。

豊家軽業夜話
黒坂 わかな
歴史・時代
猿楽小屋や市で賑わう京の寺院にて、軽業師の竹早は日の本一の技を見せる。そこに、参詣に訪れていた豊臣秀吉の側室・松の丸殿が通りがかり、竹早は伏見城へ行くことに。やがて竹早は秀頼と出会い…。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――
黒鯛の刺身♪
歴史・時代
戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。
一般には武田勝頼と記されることが多い。
……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。
信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。
つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。
一介の後見人の立場でしかない。
織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。
……これは、そんな悲運の名将のお話である。
【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵
【注意】……武田贔屓のお話です。
所説あります。
あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

枢軸国
よもぎもちぱん
歴史・時代
時は1919年
第一次世界大戦の敗戦によりドイツ帝国は滅亡した。皇帝陛下 ヴィルヘルム二世の退位により、ドイツは共和制へと移行する。ヴェルサイユ条約により1320億金マルク 日本円で200兆円もの賠償金を課される。これに激怒したのは偉大なる我らが総統閣下"アドルフ ヒトラー"である。結果的に敗戦こそしたものの彼の及ぼした影響は非常に大きかった。
主人公はソフィア シュナイダー
彼女もまた、ドイツに転生してきた人物である。前世である2010年頃の記憶を全て保持しており、映像を写真として記憶することが出来る。
生き残る為に、彼女は持てる知識を総動員して戦う
偉大なる第三帝国に栄光あれ!
Sieg Heil(勝利万歳!)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















