お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

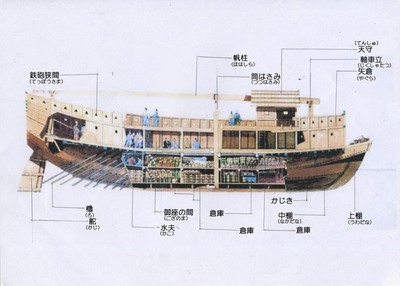

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――
黒鯛の刺身♪
歴史・時代
戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。
一般には武田勝頼と記されることが多い。
……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。
信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。
つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。
一介の後見人の立場でしかない。
織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。
……これは、そんな悲運の名将のお話である。
【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵
【注意】……武田贔屓のお話です。
所説あります。
あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

帰る旅
七瀬京
歴史・時代
宣教師に「見世物」として飼われていた私は、この国の人たちにとって珍奇な姿をして居る。
それを織田信長という男が気に入り、私は、信長の側で飼われることになった・・・。
荘厳な安土城から世界を見下ろす信長は、その傲岸な態度とは裏腹に、深い孤独を抱えた人物だった・・。
『本能寺』へ至るまでの信長の孤独を、側に仕えた『私』の視点で浮き彫りにする。

人生を共にしてほしい、そう言った最愛の人は不倫をしました。
松茸
恋愛
どうか僕と人生を共にしてほしい。
そう言われてのぼせ上った私は、侯爵令息の彼との結婚に踏み切る。
しかし結婚して一年、彼は私を愛さず、別の女性と不倫をした。

狂乱の桜(表紙イラスト・挿絵あり)
東郷しのぶ
歴史・時代
戦国の世。十六歳の少女、万は築山御前の侍女となる。
御前は、三河の太守である徳川家康の正妻。万は、気高い貴婦人の御前を一心に慕うようになるのだが……?
※表紙イラスト・挿絵7枚を、ますこ様より頂きました! ありがとうございます!(各ページに掲載しています)
他サイトにも投稿中。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

戦国を駆ける軍師・山本勘助の嫡男、山本雪之丞
沙羅双樹
歴史・時代
川中島の合戦で亡くなった軍師、山本勘助に嫡男がいた。その男は、山本雪之丞と言い、頭が良く、姿かたちも美しい若者であった。その日、信玄の館を訪れた雪之丞は、上洛の手段を考えている信玄に、「第二啄木鳥の戦法」を提案したのだった……。
この小説はカクヨムに連載中の「武田信玄上洛記」を大幅に加筆訂正したものです。より読みやすく面白く書き直しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















