43 / 86
Eighth Chapter...7/26
『G』の機関
しおりを挟む
「体、冷えてないかい? 温かいお茶でも出そうか」
「いやいや、そんなお気遣いなく。無理して来ちゃったのは私なんですから」
「無理して、か。今日はどんな用事で?」
「はい……ちょっとした相談というか」
察しの良い八木さんは、すぐにどんな用件かと促してくれたので、私は永射さんと土砂崩れ、二つの事件について自分の考えを簡潔に語った。但し、玄人が話してくれた靴跡の問題だけは秘密にして。
八木さんは聞き上手でもあるので、私のまとまらない言葉も辛抱強く聞いてくれ、相槌も打ってくれ、話しながら自分の考えも整理できるような時間になったのはありがたかった。
「まあ、皆不安だろうとは思っていたよ。そうか……大変だったね」
結局温かいお茶を用意してくれた八木さんは、話をすべて聞き終えると、まずは慰めの言葉をかけてくれた。私がはいと頷くと、
「私も昨日、牛牧さんから簡単な事情は教えてもらったんだ。しかし、土砂崩れの程度までは聞いていなかった。多分……牛牧さんも詳しく把握できていなかったんだろう」
「まあ、確認したのは私と双太さんですし、牛牧さんまで具体的に伝わってなかったのかもですね」
牛牧さんも院長として病院にはいるのだが、診察のみならず事務的な面でも、ほとんどの仕事は貴獅さんが行っているはずだ。八木さんに連絡してきた時点では、詳しい内容を知らなかったとしてもおかしくはないか。
蚊帳の外、というわけでは流石にないだろう。
「龍美さんは、私のことも心配してくれたわけだ。どうもありがとう」
「や、それは当然ですよ。こんな山の中にいるわけですし……」
こんな山の中というのは失言だったかと、口に出してしまってから焦ったが、八木さんは笑って流してくれた。
「実のところ、不安が無いと言えば嘘になる。元々地盤があまり強くないことは認識していたからね。ちなみに、これは初めて話すことだけれど、地盤に関係して私も電波塔の設置に協力しているんだ」
「え? そうだったんですか」
「ええ。電波塔は極力高い位置に設置しなければならなくて、そのためにはあの場所が最適だった。そこで周囲の地質調査に私が駆り出されたわけだ」
つまり、八木さんは私に言われるまでもなく、電波塔計画が進められていく中で、自ら付近の地質を調べて把握していたのか。まあ、私と違って八木さんは専門家なのだし、先んじて知っていてもおかしくない。知らなければ教えてあげなきゃ、などと思っていた自分が恥ずかしくなってしまった。
「勿論、電波塔だけでなくこの観測所についても、しっかりと地盤補強はしているのだけど、土砂崩れが起きる可能性はゼロではないね。私も研究が一段落したら、この街から出ていくことになっているし、それまでの辛抱だ」
「ああ……ですよね」
今まであまり意識してはこなかったが、八木さんは外部から調査のためにここへ来ている。具体的な調査内容までは知るところではないけれど、成果が得られたら帰っていくのは当然のことだ。
私はすっかり、八木さんを街の住民として認識していたけれど。説明会での自分の役割をオブザーバーと言っていたように、彼は街のオブザーバーなのだなあと思わされた。
「工事業者は貴獅さんが手配するということだったけれど、龍美さんが見た感じでは、復旧にどれくらいかかりそうだったかな」
「うーん、除去作業には一週間かそれ以上かかるんじゃないかと。ここって、やたら高い堤防があるじゃないですか。津波を防ぐ分にはいいんですが、土砂をせき止める形になっちゃってて、被害が大きくなってた感じです」
「なるほど。地震が多いということで、堤防も大げさなくらい頑丈に造られたのだけど……そこは誤算だったね」
津波から街を守るという観点からすれば、あれくらい高い堤防でもやり過ぎではないはずだ。ただ、海ばかりに目が行き過ぎて、陸の方を見れていなかったということか。
ただ、どちらも解決させるのは難しいのだろうが。
「一週間。まあ、そこまで深刻な事態にはならないだろう。……比べて永射さんの事件の方は、明らかに深刻だ」
「ええ。どうして永射さん、あんなことになっちゃったんでしょう……」
鬼封じの池で、水死体となって発見された永射さん。
状況的に、電波塔の説明会が終わった後、山の中へ入っていき、川から転落したことになる。
誰かに呼び出されたのか、或いは誰かを呼び出したのか。
少なくとも、人のいる場所から離れたくてふらりと、なんて理由ではないはずだ。
「あの人がなぜ、説明会の後山へ入ったのかはさっぱり分からない。事件の詳細については私もお手上げだ。私が危惧しているのは、彼亡き後に満生台がどうなっていくのか、だね……」
八木さんは口元に手を当てながら呟く。彼とて純粋な住民ではないが、一人の協力者として満生台の行く末を気にかけてくれている。
リーダーを失ったこの街が、これから誰を中心に、どう展開していくのか。それは確かに重要な部分だ。
「私の考えでは、しばらくは貴獅さんが計画を引き継ぐと思うけれど……また新しい人が街へやって来そうだ。永射さんとある程度似通った人が」
「まあ、永射さんも外から来た人ですもんね。次の人が来るだけ、か」
そう考えると、何だか物悲しくなってしまう。社会の仕組みと言われればそれまでだが、人の代わりはいくらでもいるという典型だ。
「ねえ、八木さん。永射さんがどういう伝手でこの街にやって来たかっていうのはご存知だったりしますか?」
「伝手……私もそういった事情には詳しくないけどね。確か牛牧さんがどこかの機関と提携して資金援助を受け、その代わりに永射さんが派遣されてきた……というような流れだったはずだよ」
「資金援助? そんなことがあったんですね」
「公言はされていないけど、一度牛牧さんから聞いたことがあるんだ。その機関というのも満生台に関心を持っていたらしくて、協力は惜しまなかったとか。資金援助と永射さんの派遣があったのが今から四年前の二〇〇八年。そこから一気に満生台のニュータウン化計画が進行していったんだ。病院の増築に、電波塔の設置といったようにね」
ある意味では、永射さんを呼びこんだのは牛牧さんということになるのか。ただ、その『機関』というのも資金援助の代わりに街の開発に協力させてほしい、というような交換条件を提示したのだろうし、円満な協力関係なのかどうかは不明だ。
しかし、機関か。正式な名称が出てこないのが何となく怪しいな。
「八木さんは、資金援助をしてくれた機関がどこなのかって聞いてたり?」
「そこまでは。ただ、永射さんがスーツに付けていたバッジは、所属する機関のものだと聞いたことはある。龍美さんは憶えているかな?」
「あー……『G』に見える形のバッジですか」
「そう。『G』が機関の頭文字とか、象徴なんじゃないかな。ハッキリしたことは私も言えないけれど」
Gが付く法人なんていくらでもあるだろうし、八木さんの情報だけでは特定できないか。
となれば、牛牧さんが教えてくれるのが一番ありがたいのだが……流石に大人の話だ、おいそれと話してくれるとは思えなかった。
一応、聞けたら聞いておくことにしよう。
「あと、盈虧園も永射さんが設備の増設をしてくれたんですよね。そのときに盈虧園って名前を決めたって聞きましたけど」
「そのようだ。街の公共施設は、永射さん主導で変えられていったし、これからもその予定だっただろう」
「……これは私の個人的な疑問なんですけど。永射さん、どうして盈虧園なんて名前にしたんでしょう」
「うん?」
質問の意図が掴めなかったようで、八木さんは首を傾げる。まあ、それも当然だ。そのままの意味で受け取っても、それは彼にしか分からないだろうと言うしかない質問なのだから。
「八木さんは、盈虧院って施設をご存知ですか?」
「……なるほど、そういうことか」
そこで八木さんは、私の言いたいことを理解してくれる。名前を出しただけで分かったなら、施設のことは知っているということだ。
何だかんだ、全国各所に点在していた施設だから、名が知れているのもおかしくはない。
「とある理由で、私もその名前を知ってまして。盈虧なんて言葉が珍しいものだから、何か関係があるんじゃないかと思ったんですよ。たとえば、永射さんは昔その施設の関係者だったとか、今所属している機関がその運営法人なんじゃないかとか……」
「残念ながら、私もその関連性は分からないね。それに、盈虧院は少し前に廃止されたはずだよ」
「――え?」
盈虧院が、廃止された?
それは初耳だった。私が仁科家に引き取られてから、盈虧院のことを調べることがなかったからか。
自分はもう孤児ではない。だからあの施設のことはもう関係ないと思おう。そういう意識でいたから、検索すればいつでも分かる情報も知らなかったのだ。
「そっか……無くなっちゃったんだ、盈虧院」
「……ええ。龍美さんの事情は聞かないけれど、決して悪い意味での閉鎖ではなかったようだよ。突然ではなく、全ての孤児を送り出してから役割を終えて、という」
全ての孤児を送り出して。
ああ、それなら私のように苦しんでいた子どもたちもみんな。
普通と呼べるような日常へ、歩んでいけるようになったのかな。
何もかもが円滑に、というわけには流石にいかなかっただろうけど。
その終わりが辛いものじゃなかったのなら、良かったと思う。
盈虧院で育った、一人の子どもとして。
「いやいや、そんなお気遣いなく。無理して来ちゃったのは私なんですから」
「無理して、か。今日はどんな用事で?」
「はい……ちょっとした相談というか」
察しの良い八木さんは、すぐにどんな用件かと促してくれたので、私は永射さんと土砂崩れ、二つの事件について自分の考えを簡潔に語った。但し、玄人が話してくれた靴跡の問題だけは秘密にして。
八木さんは聞き上手でもあるので、私のまとまらない言葉も辛抱強く聞いてくれ、相槌も打ってくれ、話しながら自分の考えも整理できるような時間になったのはありがたかった。
「まあ、皆不安だろうとは思っていたよ。そうか……大変だったね」
結局温かいお茶を用意してくれた八木さんは、話をすべて聞き終えると、まずは慰めの言葉をかけてくれた。私がはいと頷くと、
「私も昨日、牛牧さんから簡単な事情は教えてもらったんだ。しかし、土砂崩れの程度までは聞いていなかった。多分……牛牧さんも詳しく把握できていなかったんだろう」
「まあ、確認したのは私と双太さんですし、牛牧さんまで具体的に伝わってなかったのかもですね」
牛牧さんも院長として病院にはいるのだが、診察のみならず事務的な面でも、ほとんどの仕事は貴獅さんが行っているはずだ。八木さんに連絡してきた時点では、詳しい内容を知らなかったとしてもおかしくはないか。
蚊帳の外、というわけでは流石にないだろう。
「龍美さんは、私のことも心配してくれたわけだ。どうもありがとう」
「や、それは当然ですよ。こんな山の中にいるわけですし……」
こんな山の中というのは失言だったかと、口に出してしまってから焦ったが、八木さんは笑って流してくれた。
「実のところ、不安が無いと言えば嘘になる。元々地盤があまり強くないことは認識していたからね。ちなみに、これは初めて話すことだけれど、地盤に関係して私も電波塔の設置に協力しているんだ」
「え? そうだったんですか」
「ええ。電波塔は極力高い位置に設置しなければならなくて、そのためにはあの場所が最適だった。そこで周囲の地質調査に私が駆り出されたわけだ」
つまり、八木さんは私に言われるまでもなく、電波塔計画が進められていく中で、自ら付近の地質を調べて把握していたのか。まあ、私と違って八木さんは専門家なのだし、先んじて知っていてもおかしくない。知らなければ教えてあげなきゃ、などと思っていた自分が恥ずかしくなってしまった。
「勿論、電波塔だけでなくこの観測所についても、しっかりと地盤補強はしているのだけど、土砂崩れが起きる可能性はゼロではないね。私も研究が一段落したら、この街から出ていくことになっているし、それまでの辛抱だ」
「ああ……ですよね」
今まであまり意識してはこなかったが、八木さんは外部から調査のためにここへ来ている。具体的な調査内容までは知るところではないけれど、成果が得られたら帰っていくのは当然のことだ。
私はすっかり、八木さんを街の住民として認識していたけれど。説明会での自分の役割をオブザーバーと言っていたように、彼は街のオブザーバーなのだなあと思わされた。
「工事業者は貴獅さんが手配するということだったけれど、龍美さんが見た感じでは、復旧にどれくらいかかりそうだったかな」
「うーん、除去作業には一週間かそれ以上かかるんじゃないかと。ここって、やたら高い堤防があるじゃないですか。津波を防ぐ分にはいいんですが、土砂をせき止める形になっちゃってて、被害が大きくなってた感じです」
「なるほど。地震が多いということで、堤防も大げさなくらい頑丈に造られたのだけど……そこは誤算だったね」
津波から街を守るという観点からすれば、あれくらい高い堤防でもやり過ぎではないはずだ。ただ、海ばかりに目が行き過ぎて、陸の方を見れていなかったということか。
ただ、どちらも解決させるのは難しいのだろうが。
「一週間。まあ、そこまで深刻な事態にはならないだろう。……比べて永射さんの事件の方は、明らかに深刻だ」
「ええ。どうして永射さん、あんなことになっちゃったんでしょう……」
鬼封じの池で、水死体となって発見された永射さん。
状況的に、電波塔の説明会が終わった後、山の中へ入っていき、川から転落したことになる。
誰かに呼び出されたのか、或いは誰かを呼び出したのか。
少なくとも、人のいる場所から離れたくてふらりと、なんて理由ではないはずだ。
「あの人がなぜ、説明会の後山へ入ったのかはさっぱり分からない。事件の詳細については私もお手上げだ。私が危惧しているのは、彼亡き後に満生台がどうなっていくのか、だね……」
八木さんは口元に手を当てながら呟く。彼とて純粋な住民ではないが、一人の協力者として満生台の行く末を気にかけてくれている。
リーダーを失ったこの街が、これから誰を中心に、どう展開していくのか。それは確かに重要な部分だ。
「私の考えでは、しばらくは貴獅さんが計画を引き継ぐと思うけれど……また新しい人が街へやって来そうだ。永射さんとある程度似通った人が」
「まあ、永射さんも外から来た人ですもんね。次の人が来るだけ、か」
そう考えると、何だか物悲しくなってしまう。社会の仕組みと言われればそれまでだが、人の代わりはいくらでもいるという典型だ。
「ねえ、八木さん。永射さんがどういう伝手でこの街にやって来たかっていうのはご存知だったりしますか?」
「伝手……私もそういった事情には詳しくないけどね。確か牛牧さんがどこかの機関と提携して資金援助を受け、その代わりに永射さんが派遣されてきた……というような流れだったはずだよ」
「資金援助? そんなことがあったんですね」
「公言はされていないけど、一度牛牧さんから聞いたことがあるんだ。その機関というのも満生台に関心を持っていたらしくて、協力は惜しまなかったとか。資金援助と永射さんの派遣があったのが今から四年前の二〇〇八年。そこから一気に満生台のニュータウン化計画が進行していったんだ。病院の増築に、電波塔の設置といったようにね」
ある意味では、永射さんを呼びこんだのは牛牧さんということになるのか。ただ、その『機関』というのも資金援助の代わりに街の開発に協力させてほしい、というような交換条件を提示したのだろうし、円満な協力関係なのかどうかは不明だ。
しかし、機関か。正式な名称が出てこないのが何となく怪しいな。
「八木さんは、資金援助をしてくれた機関がどこなのかって聞いてたり?」
「そこまでは。ただ、永射さんがスーツに付けていたバッジは、所属する機関のものだと聞いたことはある。龍美さんは憶えているかな?」
「あー……『G』に見える形のバッジですか」
「そう。『G』が機関の頭文字とか、象徴なんじゃないかな。ハッキリしたことは私も言えないけれど」
Gが付く法人なんていくらでもあるだろうし、八木さんの情報だけでは特定できないか。
となれば、牛牧さんが教えてくれるのが一番ありがたいのだが……流石に大人の話だ、おいそれと話してくれるとは思えなかった。
一応、聞けたら聞いておくことにしよう。
「あと、盈虧園も永射さんが設備の増設をしてくれたんですよね。そのときに盈虧園って名前を決めたって聞きましたけど」
「そのようだ。街の公共施設は、永射さん主導で変えられていったし、これからもその予定だっただろう」
「……これは私の個人的な疑問なんですけど。永射さん、どうして盈虧園なんて名前にしたんでしょう」
「うん?」
質問の意図が掴めなかったようで、八木さんは首を傾げる。まあ、それも当然だ。そのままの意味で受け取っても、それは彼にしか分からないだろうと言うしかない質問なのだから。
「八木さんは、盈虧院って施設をご存知ですか?」
「……なるほど、そういうことか」
そこで八木さんは、私の言いたいことを理解してくれる。名前を出しただけで分かったなら、施設のことは知っているということだ。
何だかんだ、全国各所に点在していた施設だから、名が知れているのもおかしくはない。
「とある理由で、私もその名前を知ってまして。盈虧なんて言葉が珍しいものだから、何か関係があるんじゃないかと思ったんですよ。たとえば、永射さんは昔その施設の関係者だったとか、今所属している機関がその運営法人なんじゃないかとか……」
「残念ながら、私もその関連性は分からないね。それに、盈虧院は少し前に廃止されたはずだよ」
「――え?」
盈虧院が、廃止された?
それは初耳だった。私が仁科家に引き取られてから、盈虧院のことを調べることがなかったからか。
自分はもう孤児ではない。だからあの施設のことはもう関係ないと思おう。そういう意識でいたから、検索すればいつでも分かる情報も知らなかったのだ。
「そっか……無くなっちゃったんだ、盈虧院」
「……ええ。龍美さんの事情は聞かないけれど、決して悪い意味での閉鎖ではなかったようだよ。突然ではなく、全ての孤児を送り出してから役割を終えて、という」
全ての孤児を送り出して。
ああ、それなら私のように苦しんでいた子どもたちもみんな。
普通と呼べるような日常へ、歩んでいけるようになったのかな。
何もかもが円滑に、というわけには流石にいかなかっただろうけど。
その終わりが辛いものじゃなかったのなら、良かったと思う。
盈虧院で育った、一人の子どもとして。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

暗闇の中の囁き
葉羽
ミステリー
名門の作家、黒崎一郎が自らの死を予感し、最後の作品『囁く影』を執筆する。その作品には、彼の過去や周囲の人間関係が暗号のように隠されている。彼の死後、古びた洋館で起きた不可解な殺人事件。被害者は、彼の作品の熱心なファンであり、館の中で自殺したかのように見せかけられていた。しかし、その背後には、作家の遺作に仕込まれた恐ろしいトリックと、館に潜む恐怖が待ち受けていた。探偵の名探偵、青木は、暗号を解読しながら事件の真相に迫っていくが、次第に彼自身も館の恐怖に飲み込まれていく。果たして、彼は真実を見つけ出し、恐怖から逃れることができるのか?

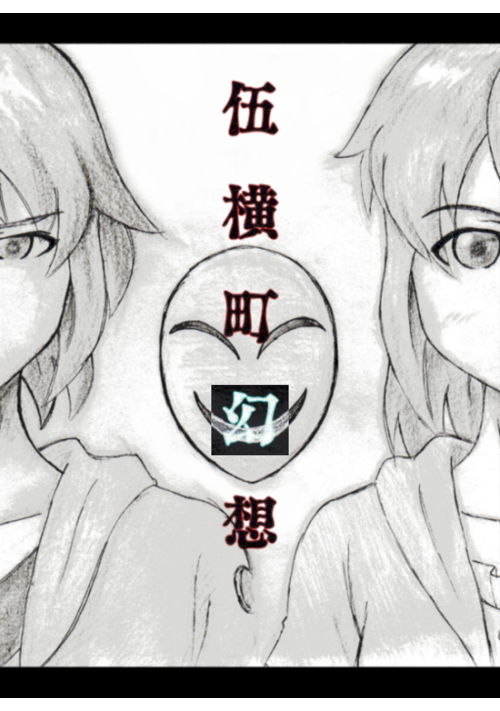
【連作ホラー】伍横町幻想 —Until the day we meet again—
至堂文斗
ホラー
――その幻想から、逃れられるか。
降霊術。それは死者を呼び出す禁忌の術式。
歴史を遡れば幾つも逸話はあれど、現実に死者を呼ぶことが出来たかは定かでない。
だがあるとき、長い実験の果てに、一人の男がその術式を生み出した。
降霊術は決して公に出ることはなかったものの、書物として世に残り続けた。
伍横町。そこは古くから気の流れが集まる場所と言われている小さな町。
そして、全ての始まりの町。
男が生み出した術式は、この町で幾つもの悲劇をもたらしていく。
運命を狂わされた者たちは、生と死の狭間で幾つもの涙を零す。
これは、四つの悲劇。
【魂】を巡る物語の始まりを飾る、四つの幻想曲――。
【霧夏邸幻想 ―Primal prayer-】
「――霧夏邸って知ってる?」
事故により最愛の娘を喪い、 降霊術に狂った男が住んでいた邸宅。
霊に会ってみたいと、邸内に忍び込んだ少年少女たちを待ち受けるものとは。
【三神院幻想 ―Dawn comes to the girl―】
「どうか、目を覚ましてはくれないだろうか」
眠りについたままの少女のために、 少年はただ祈り続ける。
その呼び声に呼応するかのように、 少女は記憶の世界に覚醒する。
【流刻園幻想 ―Omnia fert aetas―】
「……だから、違っていたんだ。沢山のことが」
七不思議の噂で有名な流刻園。夕暮れ時、教室には二人の少年少女がいた。
少年は、一通の便箋で呼び出され、少女と別れて屋上へと向かう。それが、悲劇の始まりであるとも知らずに。
【伍横町幻想 ―Until the day we meet again―】
「……ようやく、時が来た」
伍横町で降霊術の実験を繰り返してきた仮面の男。 最愛の女性のため、彼は最後の計画を始動する。
その計画を食い止めるべく、悲劇に巻き込まれた少年少女たちは苛酷な戦いに挑む。
伍横町の命運は、子どもたちの手に委ねられた。

リモート刑事 笹本翔
雨垂 一滴
ミステリー
『リモート刑事 笹本翔』は、過去のトラウマと戦う一人の刑事が、リモート捜査で事件を解決していく、刑事ドラマです。
主人公の笹本翔は、かつて警察組織の中でトップクラスの捜査官でしたが、ある事件で仲間を失い、自身も重傷を負ったことで、外出恐怖症(アゴラフォビア)に陥り、現場に出ることができなくなってしまいます。
それでも、彼の卓越した分析力と冷静な判断力は衰えず、リモートで捜査指示を出しながら、次々と難事件を解決していきます。
物語の鍵を握るのは、翔の若き相棒・竹内優斗。熱血漢で行動力に満ちた優斗と、過去の傷を抱えながらも冷静に捜査を指揮する翔。二人の対照的なキャラクターが織りなすバディストーリーです。
翔は果たして過去のトラウマを克服し、再び現場に立つことができるのか?
翔と優斗が数々の難事件に挑戦します!
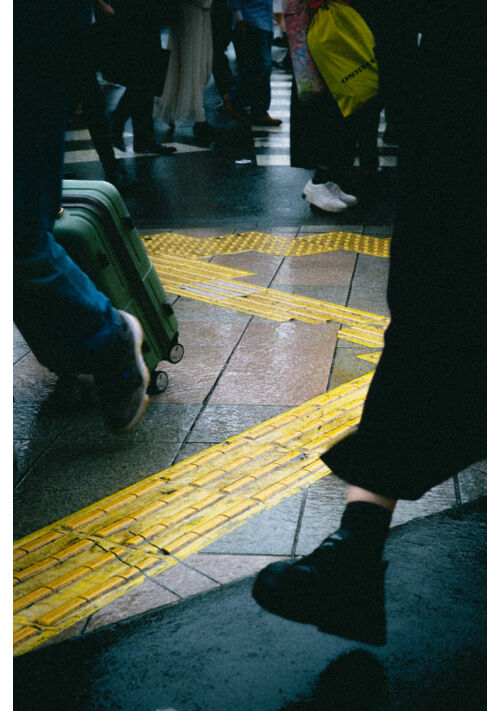
秋月真夜は泣くことにしたー東の京のエグレゴア
鹿村杞憂
ミステリー
カメラマン志望の大学生・百鳥圭介は、ある日、不気味な影をまとった写真を撮影する。その影について謎めいた霊媒師・秋月真夜から「エグレゴア」と呼ばれる集合的な感情や欲望の具現化だと聞かされる。圭介は真夜の助手としてエグレゴアの討伐を手伝うことになり、人々、そして社会の深淵を覗き込む「人の心」を巡る物語に巻き込まれていくことになる。

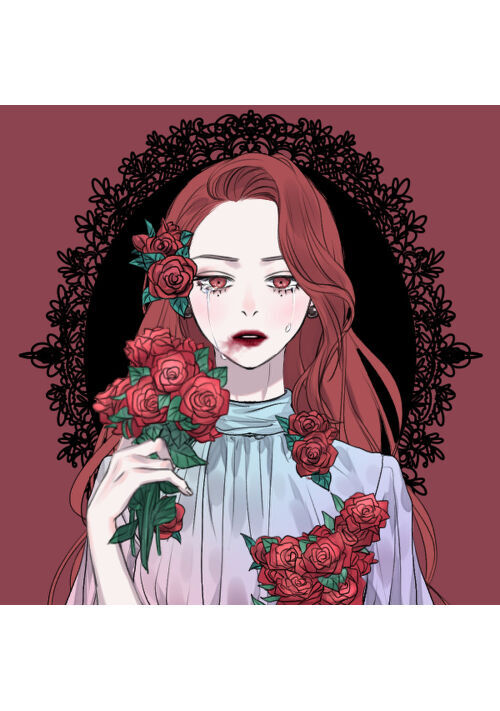
Mary Magdalene~天使と悪魔~
DAO
ミステリー
『私は血の様に赤い髪と赤い目が大嫌いだった。』『私は真っ赤に染まる姉さんが大好きだった』
正反対の性格の双子の姉妹。 赤い髪のマリアは大人しく真面目。 青い目のメアリは社交的なシスコン。
ある日、双子の乗船した豪華客船で残虐非道な殺人事件が起きるのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















