87 / 150
第四部 第三章 鋼灰色(スティールグレイ)の戯れ
第四部 鋼灰色(スティールグレイ)の嘲り 第三章 1
しおりを挟む
第三章 鋼灰色(スティールグレイ)の戯れ
* 1 *
門を入ってすぐの小さな広場の向こうは、迷路だった。
「いきなりこれか……」
昔、貴族が住む屋敷の庭園なんかにあったという生け垣を使った迷路なんてものじゃない。
外壁よりも少し低いくらいの白いコンクリートの壁が僕たちの行く手を阻み、乗り越えようにもそれを防ぐように鋭い金属製の針が上部に取りつけられている。
「本気で遊ぶつもりだぜ、あのジジイ……」
手で顔を覆ってため息を吐き脱力している猛臣に、僕も同意したい気持ちだ。この時点でもう帰りたくなってる。
『おにぃちゃん、……ここ、おかしいよ!』
「どうした? リーリエ」
スマートギアのスピーカーを通して、リーリエが緊張した声を発する。
スマートギアによって映像と音声は送信されているが、リーリエの本体である人工個性のシステムは僕の自宅だ。見回す限りいきなり迷路なんて頭おかしい状況はともかく、不自然なところは見当たらない。
『なんていうか、フェアリーリングの中にいるときに似てるの』
「フェアリーリングの中?」
どうしてそんなことがリーリエにわかるのかはわからない。
バトルのときに張ることがあるフェアリーリングは、その内側でやっているバトルを、側を通る人にすら気づかせなくする魔法のような効果がある。
出入りはとくに制限されてるわけではなく、バトルの参加者だろうと無関係な人だろうと入ることも出ることも可能。バトルの参加者であっても外にいると中の様子を見ることはできず、一度中に入った後だと何故か中の様子を認識できるようになるという、不思議な効果がある。
レーダーを監視してもらうためにリーリエはすでにアリシアとリンクしてるから、それで感知できてるのかも知れない、と思うけど、夏姫たちを見てもよくわからないらしいことを、リーリエが感知できてる理由はやっぱり理解できない。
「あ! まずい!」
そう叫んだ近藤が門に向かって走り出す。
振り向いてみると、開くときには音がしていた門が、いままさに閉まるところだった。
扉に取りついた瞬間完全に閉じてしまった扉は、近藤が動かそうとしてもビクともしない。外壁の上にも侵入防止なのか逃走防止なのか、びっしりと針が据えられていて、乗り越えるのは壁登りの道具でもないと厳しい。
「……先に進むしかないようですね、克樹さん」
「うん、そうみたい。行こ、天堂さんのところに」
真っ先に現実を受け入れた女子ふたり、夏姫と灯理の声に、僕はため息を漏らした。
「それだけじゃねぇよ。クソッ。そういう空間かよ」
悪態を吐いた猛臣が指さす方向。
屋敷が見えていたはずのそっちには、山の稜線と空しか見えなかった。
門ところまで下がって見ても同じ。この角度なら屋敷の屋根くらい見えてもおかしくないのに、欠片も見えない。それどころか、レーダーで距離が確認できていた天堂翔機のエリキシルスフィアの反応が消えている。
「空間が広がってる?」
『うん、たぶんそうだと思うよ。すごいね! おにぃちゃんっ』
リーリエははしゃいでいるが、こっちはそうもいかない。
ただでさえ直線距離で百メートルはあったんだ、どれくらい空間が拡張されたか次第で、迷路の脱出までの時間も変わる。
ルールに時間制限はないわけだけど、ホテルで持たされた簡単な弁当と、非常用の食料というかお菓子くらいしか食料の手持ちはない。脱出に二日以上かかるとなると、空腹が問題になるのは確実だ。
それより僕が思うこと。
――やっぱり、天堂翔機はモルガーナに近い人物なんだ。
僕たちが使うフェアリーリングには空間を拡張する機能なんてない。
リーリエが似ているだけと言ってたけど、フェアリーリングも魔法だとしたら、ここの空間も魔法による効果だろう。
天堂翔機はモルガーナの力なのか、彼女から教えられたものなのかわからないけど、魔法が使える。魔女の僕(しもべ)か、それに近い存在なんだ。
「壁の厚さはどれくらい?」
「ちょっと待ってろ」
近藤にそう声をかけると、たぶん今日のために用意してきたんだろう、クッション材が入ってそうな、金属が表面を覆ってる手袋を填め、コンクリートの壁を殴りつける。
「五センチ、ってところかな。鉄板なんかは入ってないと思う。厚くはないが、オレが崩して進むのは無理だろう。どうする? 克樹。どれくらい広さがあるのかわからないんじゃ、一日で脱出できるとも限らないぞ」
「あのジジイの目的だろうな、これが。俺様たちにアライズを使わせるための」
「そうだろうね」
迷路自体はむやみに進まず、広くてもルールに沿って進めばいつかは脱出できる。
ただやっぱり広さがネックだし、魔法で拡張された空間なんだったら、いつまでも同じ構造とも限らない。
「どうするの? 克樹。進まないとどうしようもないけど」
さすがに不安と困惑の表情を浮かべる夏姫。
他のみんなも似たような表情だ。
「近藤、僕の荷物を」
「何かあるのか?」
「これを想定して持ってきたわけじゃないんだけどね」
近藤に持たせていたスポーツバッグから、僕はひとつのケースを取り出す。
中に入っていたのは四つのローターを持つ小型のヘリコプター。ドローンという奴だ。
「リーリエ、頼む」
『うんっ』
ドローンの電源を入れてやると、早速リンクしたリーリエが空に飛ばした。
リーリエがリンクして動かせるのは、何もスフィアドールに限らない。いまでこそ改造してドールから動かせるようにしてるけど、ピクシードール用の機動ユニットであるスレイプニルも、最初は外部機器としてではなく、アリシアと同時にリーリエがリンクして動かしていたんだ。
ドローンを遠隔操作することくらい、リーリエには朝飯前のことだ。
スマートギアにドローンから送られてくる映像を表示しつつ、リーリエが測定した情報も重ねる。
「これであればそう時間はかからず脱出できますね、克樹さん」
「いや、念には念を入れよう。みんな、スマートギアの外部音声をミュートにして、耳を塞いでくれ」
「何するつもり? 克樹」
「口で説明するよりやった方が早い」
言いながら僕は、自分が背負ってきたデイパックからケースをひとつ引っ張りだし、中からピクシードールを一体取り出す。
アリシアではなく、シンシアを。
「リーリエ、やることはわかってるな?」
『うん、大丈夫だよ』
シンシアとのリンクを確認して、土が剥き出しの地面に立たせた僕は、できるだけ壁まで下がって、ヘッドホンの上からさらに手を当てて耳を塞いだ。
みんなも同じようにたった二〇センチしかないシンシアから離れて、耳を塞ぐ。
緑色の三つ編みを背中に垂らし、眼鏡型視覚センサーをかけたドレスのような鎧のようなハードアーマーのシンシアは、目を閉じて大きく口を開けた。
「きゃっ!!」
「んんんっ!」
演出に過ぎないシンシアの動きの直後、耳には聞こえない音が僕の鼓膜を強く刺激した。
夏姫と灯理が悲鳴を上げ、近藤が膝を着き、猛臣が強く目をつむっていた。
「……な、に、しやがった、てめぇ!」
「待って、槙島さん」
つかみかかってきそうな猛臣を抑えてくれたのは夏姫。
「リーリエ、どこまで走査できた?」
『んー。全体はさすがに無理だねぇ。シンシアをアライズさせてればもっと広い範囲まで見えると思うけど、これ以上はおにぃちゃんたちの近くで音量上げるわけにはいかないもんね。ちょっと待ってね、もうすぐ処理終わるから』
リーリエの方で処理した情報が徐々に送られてきて、スマートギアの視界に新たに開いたウィンドウにそれを表示する。
概ね終わった処理済みデータと、ドローンの方から送られてきてる映像を解析したものを、ここにいる全員に共有するよう設定した。
「こいつは……、ドローンの映像だけじゃなく、三次元データ? もしかして――」
「そっ。シンシアはパワー型のバトルドールだけど、いろんなセンサーも積んでるからね、パッシブも、アクティブも。超音波ソナー使って映像との誤差がないか確認したんだ」
「さすがだね、リーリエ。アリシアにもそんなのあったよね? シンシアはそれの凄い奴なんだ」
『へっへーっ。凄いでしょーっ。でも本当に凄いのは、こういうことできるようにしてたおにぃちゃんなんだけどね!』
以前、夏姫が近藤と戦うとき、彼女の元に急いで駆けつけるのにアリシアにアクティブソナーつきのヘルメットを被せていたけど、シンシアに内蔵してるのはそれの強化版だ。
たった二〇センチしかないピクシードールにできる限り高出力のアクティブソナーを搭載してるから、複雑な構造な迷路でも数百メートルの範囲までは把握することができる。超音波の反響で得られたデータをリーリエの方で処理すれば、迷路の立体的な構造を得ることもできる。
さすがにあんまり遠くなると詳細の把握は難しくなるけど、近距離であれば待ち伏せだろうと障害物だろうと、もしあれば出くわす前に丸見えだった。
出力が大きい分、バッテリの消耗が飛んでもないけど、本当かどうかはともかく、ひとり一回しか使えないアライズを使って壁を崩して進むより効率的だ。
やっと状況がわかったらしい猛臣は、黒いヘルメット型のスマートギアを被り、顎をさすりながら構造を確認してるようだった。
夏姫は得意げに胸を反らしてる、リーリエが操るシンシアの前に屈んで笑っている。
「マップデータは手に入ったと思っていいのか? 克樹」
「どうだろうね。ここから屋敷までは直線距離で一キロ近くあるみたいだし、理屈はともかく空間が拡張されたのは確かだ。迷路の構造も変わらないとも限らない。たまにドローンとシンシアで確認しながら進む必要があるね」
そんなに長時間飛び続けていられるわけじゃないドローンを着地させ、ケースごと荷物と一緒に近藤に押しつける。
シンシアが夏姫の伸ばした手の上に座っているのを見た僕は、微笑みを向けてくる灯理と、不満そうな表情を浮かべながらも顎で先を促す猛臣に頷きを返した。
「天堂翔機はたぶん、ここで誰かひとりアライズを使わせるつもりだったんだと思う。仕掛けがいくつあるかわからないし、できるだけアライズを使わずに進もう。簡単には進ませてくれないだろうけどね」
「うん、わかった」
「ちっ、わかったよ」
「はい」
「あぁ」
『うんっ』
全員の返事を聞いて、僕はリーリエに解析してもらった順路を進み始める。
――この先は、アライズを使わずに、ってのは難しいと思うけどね。
最初から迷路なんていう時間のかかる、そして面倒臭い障害を用意していた天堂翔機。
詳しい性格はわからないけど、こういうことを楽しむ性格なことだけは確かだ。
そういう人がこの先もアライズを使わずに進ませてくれるとは、僕には思えなかった。
*
「まさかあんな装備を用意してるとはな。人数が多いというのは、いつもとは違う趣向が楽しめるものだな」
ベッドに横になる老人は、スマートギアの視界に映し出された克樹たちの様子を見、クツクツと笑う。
「しかしお前の言う通りだ、音山克樹。この先はそう簡単にはいかないぞ」
薄い掛け布団から腕を出したのを見、控えていたメイド服のエルフドールが察して身体を起こすのを助ける。
「今回はワシのところまでたどり着く者がいるやも知れないな。あれを準備しておこう」
老人は言いながら、メイドドールにスマートギアで詳しい指示を与える。
「期待を裏切ってくれるなよ」
老人の低い笑い声が、ベッドとサイドテーブルくらいしかなく、メイドドールも指示を受けて出て行き、ひとりになった殺風景な部屋に響いていた。
* 1 *
門を入ってすぐの小さな広場の向こうは、迷路だった。
「いきなりこれか……」
昔、貴族が住む屋敷の庭園なんかにあったという生け垣を使った迷路なんてものじゃない。
外壁よりも少し低いくらいの白いコンクリートの壁が僕たちの行く手を阻み、乗り越えようにもそれを防ぐように鋭い金属製の針が上部に取りつけられている。
「本気で遊ぶつもりだぜ、あのジジイ……」
手で顔を覆ってため息を吐き脱力している猛臣に、僕も同意したい気持ちだ。この時点でもう帰りたくなってる。
『おにぃちゃん、……ここ、おかしいよ!』
「どうした? リーリエ」
スマートギアのスピーカーを通して、リーリエが緊張した声を発する。
スマートギアによって映像と音声は送信されているが、リーリエの本体である人工個性のシステムは僕の自宅だ。見回す限りいきなり迷路なんて頭おかしい状況はともかく、不自然なところは見当たらない。
『なんていうか、フェアリーリングの中にいるときに似てるの』
「フェアリーリングの中?」
どうしてそんなことがリーリエにわかるのかはわからない。
バトルのときに張ることがあるフェアリーリングは、その内側でやっているバトルを、側を通る人にすら気づかせなくする魔法のような効果がある。
出入りはとくに制限されてるわけではなく、バトルの参加者だろうと無関係な人だろうと入ることも出ることも可能。バトルの参加者であっても外にいると中の様子を見ることはできず、一度中に入った後だと何故か中の様子を認識できるようになるという、不思議な効果がある。
レーダーを監視してもらうためにリーリエはすでにアリシアとリンクしてるから、それで感知できてるのかも知れない、と思うけど、夏姫たちを見てもよくわからないらしいことを、リーリエが感知できてる理由はやっぱり理解できない。
「あ! まずい!」
そう叫んだ近藤が門に向かって走り出す。
振り向いてみると、開くときには音がしていた門が、いままさに閉まるところだった。
扉に取りついた瞬間完全に閉じてしまった扉は、近藤が動かそうとしてもビクともしない。外壁の上にも侵入防止なのか逃走防止なのか、びっしりと針が据えられていて、乗り越えるのは壁登りの道具でもないと厳しい。
「……先に進むしかないようですね、克樹さん」
「うん、そうみたい。行こ、天堂さんのところに」
真っ先に現実を受け入れた女子ふたり、夏姫と灯理の声に、僕はため息を漏らした。
「それだけじゃねぇよ。クソッ。そういう空間かよ」
悪態を吐いた猛臣が指さす方向。
屋敷が見えていたはずのそっちには、山の稜線と空しか見えなかった。
門ところまで下がって見ても同じ。この角度なら屋敷の屋根くらい見えてもおかしくないのに、欠片も見えない。それどころか、レーダーで距離が確認できていた天堂翔機のエリキシルスフィアの反応が消えている。
「空間が広がってる?」
『うん、たぶんそうだと思うよ。すごいね! おにぃちゃんっ』
リーリエははしゃいでいるが、こっちはそうもいかない。
ただでさえ直線距離で百メートルはあったんだ、どれくらい空間が拡張されたか次第で、迷路の脱出までの時間も変わる。
ルールに時間制限はないわけだけど、ホテルで持たされた簡単な弁当と、非常用の食料というかお菓子くらいしか食料の手持ちはない。脱出に二日以上かかるとなると、空腹が問題になるのは確実だ。
それより僕が思うこと。
――やっぱり、天堂翔機はモルガーナに近い人物なんだ。
僕たちが使うフェアリーリングには空間を拡張する機能なんてない。
リーリエが似ているだけと言ってたけど、フェアリーリングも魔法だとしたら、ここの空間も魔法による効果だろう。
天堂翔機はモルガーナの力なのか、彼女から教えられたものなのかわからないけど、魔法が使える。魔女の僕(しもべ)か、それに近い存在なんだ。
「壁の厚さはどれくらい?」
「ちょっと待ってろ」
近藤にそう声をかけると、たぶん今日のために用意してきたんだろう、クッション材が入ってそうな、金属が表面を覆ってる手袋を填め、コンクリートの壁を殴りつける。
「五センチ、ってところかな。鉄板なんかは入ってないと思う。厚くはないが、オレが崩して進むのは無理だろう。どうする? 克樹。どれくらい広さがあるのかわからないんじゃ、一日で脱出できるとも限らないぞ」
「あのジジイの目的だろうな、これが。俺様たちにアライズを使わせるための」
「そうだろうね」
迷路自体はむやみに進まず、広くてもルールに沿って進めばいつかは脱出できる。
ただやっぱり広さがネックだし、魔法で拡張された空間なんだったら、いつまでも同じ構造とも限らない。
「どうするの? 克樹。進まないとどうしようもないけど」
さすがに不安と困惑の表情を浮かべる夏姫。
他のみんなも似たような表情だ。
「近藤、僕の荷物を」
「何かあるのか?」
「これを想定して持ってきたわけじゃないんだけどね」
近藤に持たせていたスポーツバッグから、僕はひとつのケースを取り出す。
中に入っていたのは四つのローターを持つ小型のヘリコプター。ドローンという奴だ。
「リーリエ、頼む」
『うんっ』
ドローンの電源を入れてやると、早速リンクしたリーリエが空に飛ばした。
リーリエがリンクして動かせるのは、何もスフィアドールに限らない。いまでこそ改造してドールから動かせるようにしてるけど、ピクシードール用の機動ユニットであるスレイプニルも、最初は外部機器としてではなく、アリシアと同時にリーリエがリンクして動かしていたんだ。
ドローンを遠隔操作することくらい、リーリエには朝飯前のことだ。
スマートギアにドローンから送られてくる映像を表示しつつ、リーリエが測定した情報も重ねる。
「これであればそう時間はかからず脱出できますね、克樹さん」
「いや、念には念を入れよう。みんな、スマートギアの外部音声をミュートにして、耳を塞いでくれ」
「何するつもり? 克樹」
「口で説明するよりやった方が早い」
言いながら僕は、自分が背負ってきたデイパックからケースをひとつ引っ張りだし、中からピクシードールを一体取り出す。
アリシアではなく、シンシアを。
「リーリエ、やることはわかってるな?」
『うん、大丈夫だよ』
シンシアとのリンクを確認して、土が剥き出しの地面に立たせた僕は、できるだけ壁まで下がって、ヘッドホンの上からさらに手を当てて耳を塞いだ。
みんなも同じようにたった二〇センチしかないシンシアから離れて、耳を塞ぐ。
緑色の三つ編みを背中に垂らし、眼鏡型視覚センサーをかけたドレスのような鎧のようなハードアーマーのシンシアは、目を閉じて大きく口を開けた。
「きゃっ!!」
「んんんっ!」
演出に過ぎないシンシアの動きの直後、耳には聞こえない音が僕の鼓膜を強く刺激した。
夏姫と灯理が悲鳴を上げ、近藤が膝を着き、猛臣が強く目をつむっていた。
「……な、に、しやがった、てめぇ!」
「待って、槙島さん」
つかみかかってきそうな猛臣を抑えてくれたのは夏姫。
「リーリエ、どこまで走査できた?」
『んー。全体はさすがに無理だねぇ。シンシアをアライズさせてればもっと広い範囲まで見えると思うけど、これ以上はおにぃちゃんたちの近くで音量上げるわけにはいかないもんね。ちょっと待ってね、もうすぐ処理終わるから』
リーリエの方で処理した情報が徐々に送られてきて、スマートギアの視界に新たに開いたウィンドウにそれを表示する。
概ね終わった処理済みデータと、ドローンの方から送られてきてる映像を解析したものを、ここにいる全員に共有するよう設定した。
「こいつは……、ドローンの映像だけじゃなく、三次元データ? もしかして――」
「そっ。シンシアはパワー型のバトルドールだけど、いろんなセンサーも積んでるからね、パッシブも、アクティブも。超音波ソナー使って映像との誤差がないか確認したんだ」
「さすがだね、リーリエ。アリシアにもそんなのあったよね? シンシアはそれの凄い奴なんだ」
『へっへーっ。凄いでしょーっ。でも本当に凄いのは、こういうことできるようにしてたおにぃちゃんなんだけどね!』
以前、夏姫が近藤と戦うとき、彼女の元に急いで駆けつけるのにアリシアにアクティブソナーつきのヘルメットを被せていたけど、シンシアに内蔵してるのはそれの強化版だ。
たった二〇センチしかないピクシードールにできる限り高出力のアクティブソナーを搭載してるから、複雑な構造な迷路でも数百メートルの範囲までは把握することができる。超音波の反響で得られたデータをリーリエの方で処理すれば、迷路の立体的な構造を得ることもできる。
さすがにあんまり遠くなると詳細の把握は難しくなるけど、近距離であれば待ち伏せだろうと障害物だろうと、もしあれば出くわす前に丸見えだった。
出力が大きい分、バッテリの消耗が飛んでもないけど、本当かどうかはともかく、ひとり一回しか使えないアライズを使って壁を崩して進むより効率的だ。
やっと状況がわかったらしい猛臣は、黒いヘルメット型のスマートギアを被り、顎をさすりながら構造を確認してるようだった。
夏姫は得意げに胸を反らしてる、リーリエが操るシンシアの前に屈んで笑っている。
「マップデータは手に入ったと思っていいのか? 克樹」
「どうだろうね。ここから屋敷までは直線距離で一キロ近くあるみたいだし、理屈はともかく空間が拡張されたのは確かだ。迷路の構造も変わらないとも限らない。たまにドローンとシンシアで確認しながら進む必要があるね」
そんなに長時間飛び続けていられるわけじゃないドローンを着地させ、ケースごと荷物と一緒に近藤に押しつける。
シンシアが夏姫の伸ばした手の上に座っているのを見た僕は、微笑みを向けてくる灯理と、不満そうな表情を浮かべながらも顎で先を促す猛臣に頷きを返した。
「天堂翔機はたぶん、ここで誰かひとりアライズを使わせるつもりだったんだと思う。仕掛けがいくつあるかわからないし、できるだけアライズを使わずに進もう。簡単には進ませてくれないだろうけどね」
「うん、わかった」
「ちっ、わかったよ」
「はい」
「あぁ」
『うんっ』
全員の返事を聞いて、僕はリーリエに解析してもらった順路を進み始める。
――この先は、アライズを使わずに、ってのは難しいと思うけどね。
最初から迷路なんていう時間のかかる、そして面倒臭い障害を用意していた天堂翔機。
詳しい性格はわからないけど、こういうことを楽しむ性格なことだけは確かだ。
そういう人がこの先もアライズを使わずに進ませてくれるとは、僕には思えなかった。
*
「まさかあんな装備を用意してるとはな。人数が多いというのは、いつもとは違う趣向が楽しめるものだな」
ベッドに横になる老人は、スマートギアの視界に映し出された克樹たちの様子を見、クツクツと笑う。
「しかしお前の言う通りだ、音山克樹。この先はそう簡単にはいかないぞ」
薄い掛け布団から腕を出したのを見、控えていたメイド服のエルフドールが察して身体を起こすのを助ける。
「今回はワシのところまでたどり着く者がいるやも知れないな。あれを準備しておこう」
老人は言いながら、メイドドールにスマートギアで詳しい指示を与える。
「期待を裏切ってくれるなよ」
老人の低い笑い声が、ベッドとサイドテーブルくらいしかなく、メイドドールも指示を受けて出て行き、ひとりになった殺風景な部屋に響いていた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

鋼殻牙龍ドラグリヲ
南蛮蜥蜴
ファンタジー
歪なる怪物「害獣」の侵攻によって緩やかに滅びゆく世界にて、「アーマメントビースト」と呼ばれる兵器を操り、相棒のアンドロイド「カルマ」と共に戦いに明け暮れる主人公「真継雪兎」
ある日、彼はとある任務中に害獣に寄生され、身体を根本から造り替えられてしまう。 乗っ取られる危険を意識しつつも生きることを選んだ雪兎だったが、それが苦難の道のりの始まりだった。
次々と出現する凶悪な害獣達相手に、無双の機械龍「ドラグリヲ」が咆哮と共に牙を剥く。
延々と繰り返される殺戮と喪失の果てに、勇敢で臆病な青年を待ち受けるのは絶対的な破滅か、それともささやかな希望か。
※小説になろう、カクヨム、ノベプラでも掲載中です。
※挿絵は雨川真優(アメカワマユ)様@zgmf_x11dより頂きました。利用許可済です。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

関西訛りな人工生命体の少女がお母さんを探して旅するお話。
虎柄トラ
SF
あるところに誰もがうらやむ才能を持った科学者がいた。
科学者は天賦の才を得た代償なのか、天涯孤独の身で愛する家族も頼れる友人もいなかった。
愛情に飢えた科学者は存在しないのであれば、創造すればいいじゃないかという発想に至る。
そして試行錯誤の末、科学者はありとあらゆる癖を詰め込んだ最高傑作を完成させた。
科学者は人工生命体にリアムと名付け、それはもうドン引きするぐらい溺愛した。
そして月日は経ち、可憐な少女に成長したリアムは二度目の誕生日を迎えようとしていた。
誕生日プレゼントを手に入れるため科学者は、リアムに留守番をお願いすると家を出て行った。
それからいくつも季節が通り過ぎたが、科学者が家に帰ってくることはなかった。
科学者が帰宅しないのは迷子になっているからだと、推察をしたリアムはある行動を起こした。
「お母さん待っててな、リアムがいま迎えに行くから!」
一度も外に出たことがない関西訛りな箱入り娘による壮大な母親探しの旅がいまはじまる。
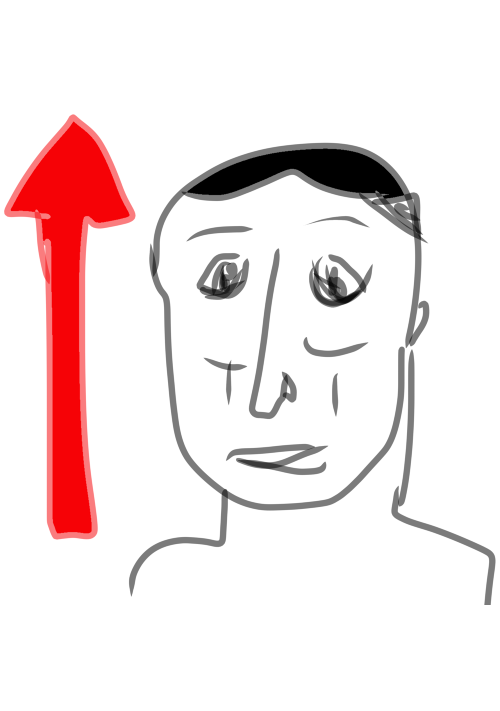
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)


決戦の夜が明ける ~第3堡塁の側壁~
独立国家の作り方
SF
ドグミス国連軍陣地に立て籠もり、全滅の危機にある島民と共に戦おうと、再上陸を果たした陸上自衛隊警備中隊は、条約軍との激戦を戦い抜き、遂には玉砕してしまいます。
今より少し先の未来、第3次世界大戦が終戦しても、世界は統一政府を樹立出来ていません。
南太平洋の小国をめぐり、新世界秩序は、新国連軍とS条約同盟軍との拮抗状態により、4度目の世界大戦を待逃れています。
そんな最中、ドグミス島で警備中隊を率いて戦った、旧陸上自衛隊1等陸尉 三枝啓一の弟、三枝龍二は、兄の志を継ぐべく「国防大学校」と名称が変更されたばかりの旧防衛大学校へと進みます。
しかし、その弟で三枝家三男、陸軍工科学校1学年の三枝昭三は、駆け落ち騒動の中で、共に協力してくれた同期生たちと、駐屯地の一部を占拠し、反乱を起こして徹底抗戦を宣言してしまいます。
龍二達防大学生たちは、そんな状況を打破すべく、駆け落ちの相手の父親、東京第1師団長 上条中将との交渉に挑みますが、関係者全員の軍籍剥奪を賭けた、訓練による決戦を申し出られるのです。
力を持たない学生や生徒達が、大人に対し、一歩に引くことなく戦いを挑んで行きますが、彼らの選択は、正しかったと世論が認めるでしょうか?
是非、ご一読ください。

惑星保護区
ラムダムランプ
SF
この物語について
旧人類と別宇宙から来た種族との出来事にまつわる話です。
概要
かつて地球に住んでいた旧人類と別宇宙から来た種族がトラブルを引き起こし、その事が発端となり、地球が宇宙の中で【保護区】(地球で言う自然保護区)に制定され
制定後は、他の星の種族は勿論、あらゆる別宇宙の種族は地球や現人類に対し、安易に接触、交流、知能や技術供与する事を固く禁じられた。
現人類に対して、未だ地球以外の種族が接触して来ないのは、この為である。
初めて書きますので読みにくいと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















